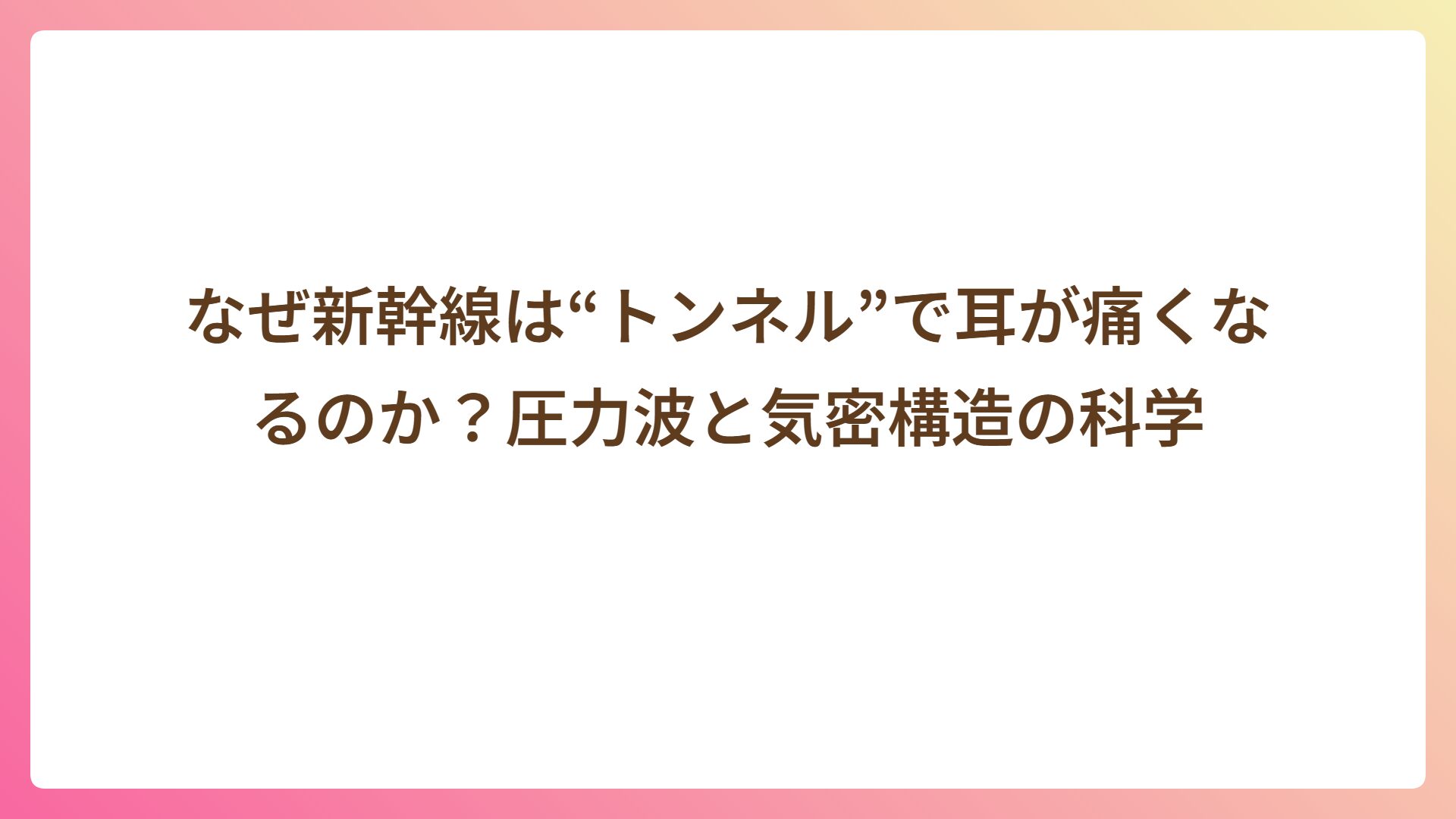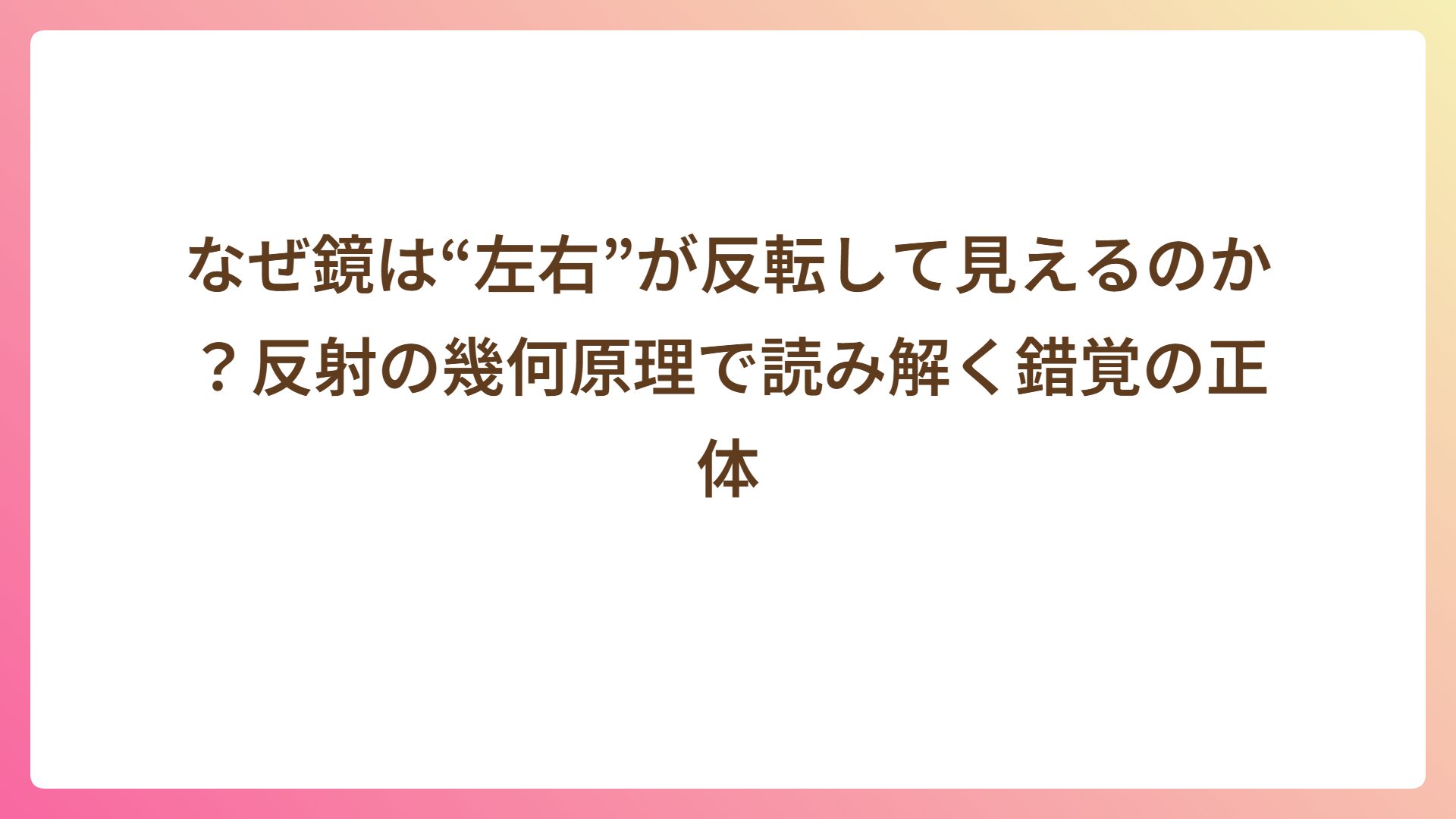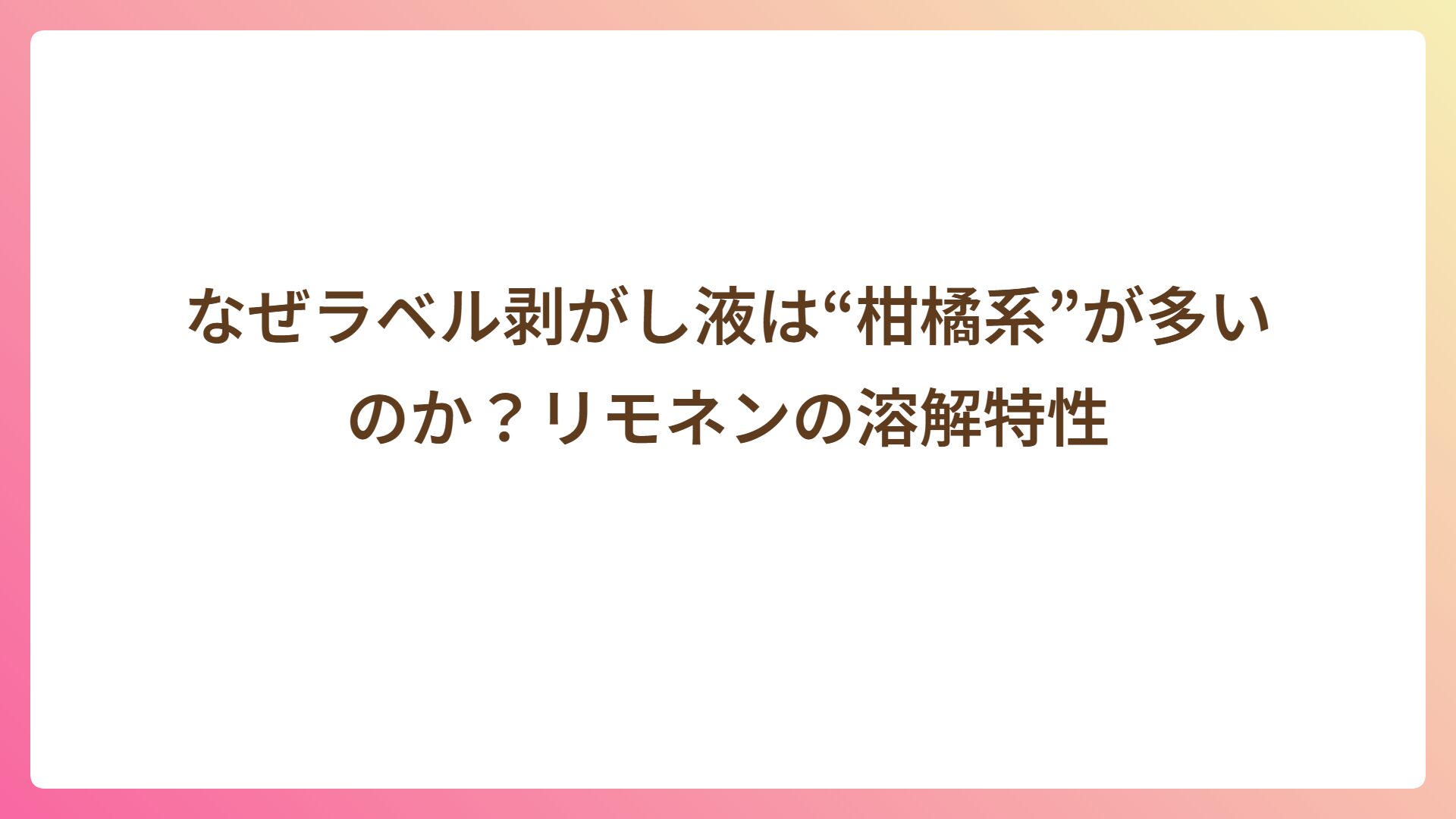なぜ信号の“青”は地域で色味が違うのか?規格と視認環境の違いを解説
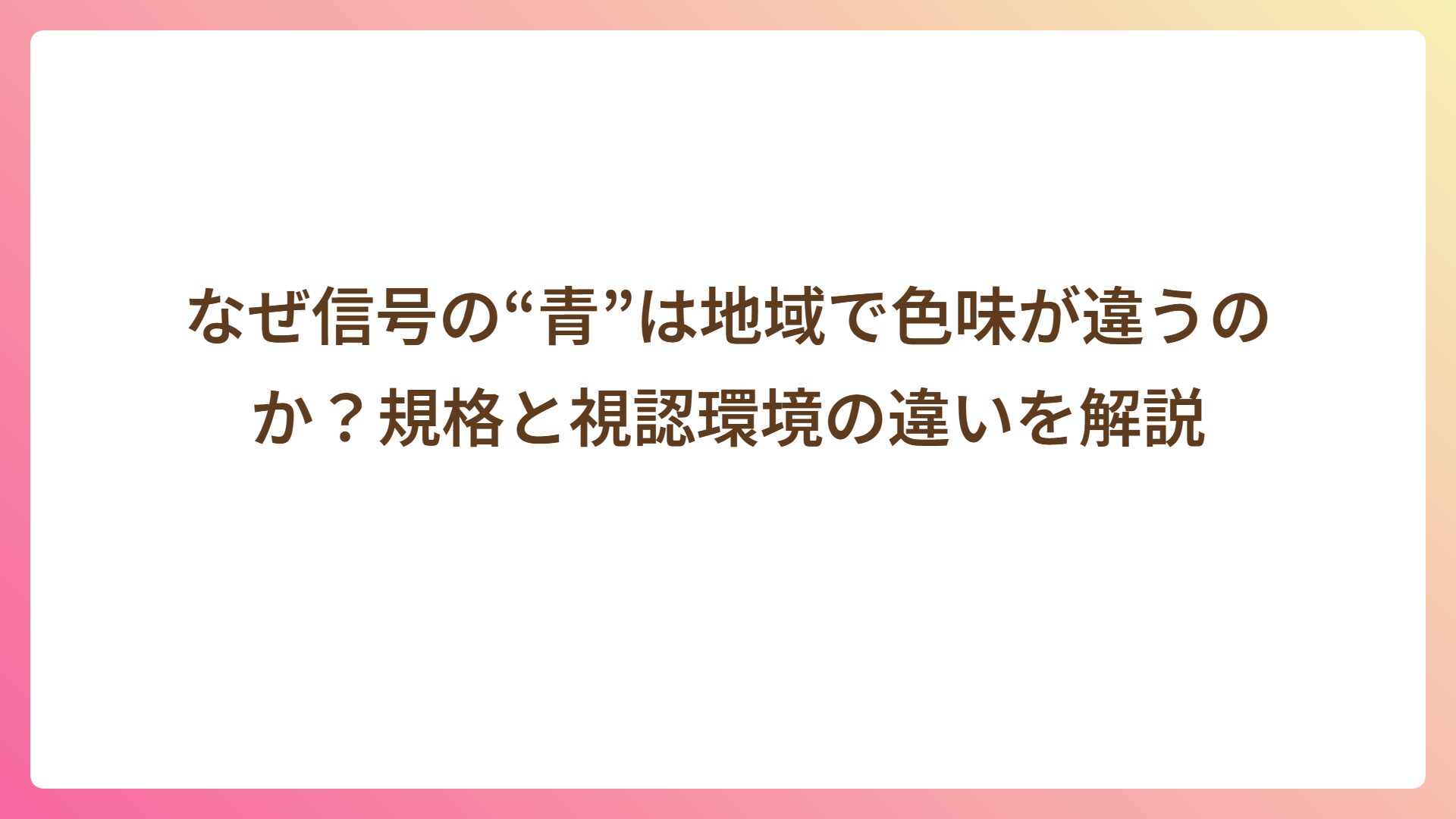
旅行先で信号を見たとき、「いつもより緑っぽい」「やけに青く見える」と感じたことはありませんか?
実は、日本国内でも信号の“青”の色味には微妙な地域差があります。
これは単なる製造誤差ではなく、光源・気候・道路環境といった条件に合わせて最適化されているためです。
今回は、信号の「青」が地域で異なって見える理由を、規格・照明・視認性の3つの視点から解説します。
日本の信号は“青”ではなく“青緑色”が正式な規格
まず前提として、日本の道路信号機の「青」は、法的には青緑色(Blue-Green)と定められています。
これは「道路交通信号の色度規格(JIS Z 9103)」によって定義されており、
青の範囲に加えて緑寄りの色域も許容されています。
つまり、信号の“青”は本来「緑を少し含んだ青緑色」であり、
製造メーカーや照明方式の違いによって、青寄り/緑寄りのばらつきが生まれるのです。
なぜ「青なのに緑っぽい」?歴史的な言葉の由来
日本語では、古くから「青」が“青と緑”の両方を指す色名でした。
「青葉」「青りんご」「青信号」などがその名残です。
そのため、信号の緑色を導入した当初も「青信号」と呼ばれるようになり、
結果的に呼び名と実際の色がずれたという経緯があります。
この“言葉と実物のズレ”が、現代でも「青なのに緑っぽい」と感じる原因のひとつです。
地域で色味が違う理由①:光源の種類(電球・LED)
信号の色味を最も左右するのが光源の違いです。
- 古い信号機(白熱電球+色フィルター)
→ フィルター越しの光がやや緑寄りに見える。 - 新型信号機(LED方式)
→ LEDのスペクトル特性により、鮮やかな“青み”が強く出る。
そのため、旧型が残る地域では緑が強く、LED化が進んだ地域では青が鮮明に見えます。
特に都市部ではLED更新が早いため、「都会の信号は青っぽい」と感じる傾向があります。
地域で色味が違う理由②:日照条件と視認環境
日本は南北に長く、地域によって太陽光の角度や天候の傾向が異なります。
- 雪国や北国(北海道・東北):白い背景が多いため、コントラストを高めるために緑寄りの濃い青を採用。
- 南西地域(九州・沖縄など):強い日差し下で視認しやすいよう、明るい青寄りの色味が選ばれる。
また、道路の植栽・ビル反射・街灯の色なども背景に影響し、
同じ規格でも実際の見え方が地域環境で変化します。
地域で色味が違う理由③:メーカーや自治体ごとの調達仕様
信号機は警察庁管轄ですが、設置や調達は都道府県単位で行われています。
このため、採用するメーカーや仕様書の細部に違いがあり、
結果的に地域ごとで微妙な色味差が生じます。
たとえば、A県では「冬季の視認性重視で濃い青」、
B県では「夜間のまぶしさ軽減で淡い青」など、
環境最適化を目的とした“ローカルチューニング”が行われているのです。
人間の目の特性も“青の感じ方”に影響
人の視覚は、明るい場所では「緑」に敏感、暗い場所では「青」に敏感になるという特徴があります。
そのため、昼間と夜間で信号の青が違って見えるのは、照明だけでなく生理的な要因も関係しています。
夜の信号がより青く感じられるのは、暗所視(ロドプシン優位)による青系感度の上昇が原因です。
まとめ:信号の“青の違い”は環境と技術の調和
信号の青が地域で違って見えるのは、
- JIS規格上の「青緑」範囲の許容幅
- 光源方式(電球型・LED型)の違い
- 日照・背景・気候など地域ごとの視認環境
- 人間の目の特性による見え方の差
といった複数の要因が重なっているためです。
つまり、「青信号」は単なる色ではなく、“安全に見える色”として最適化された設計なのです。