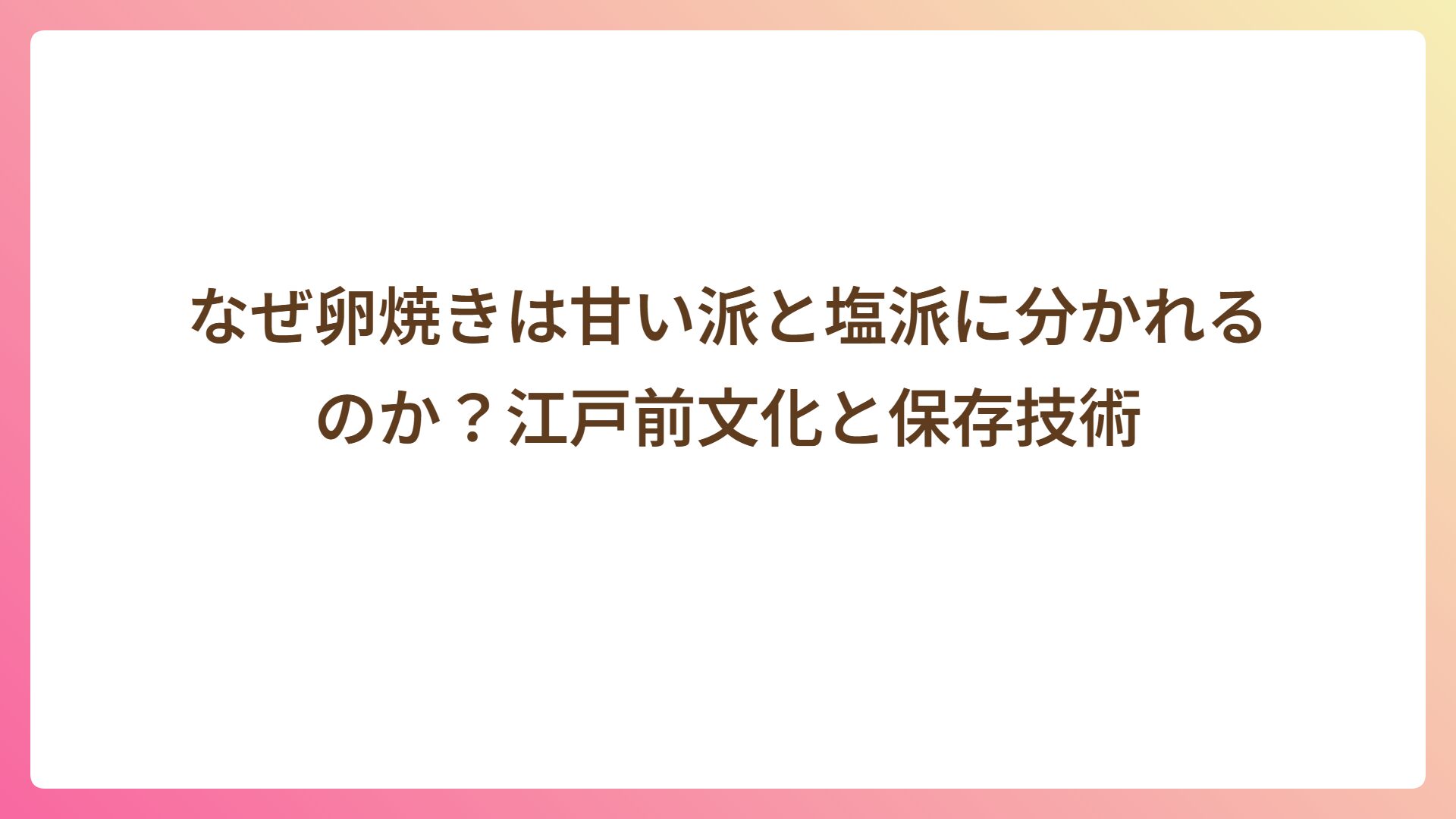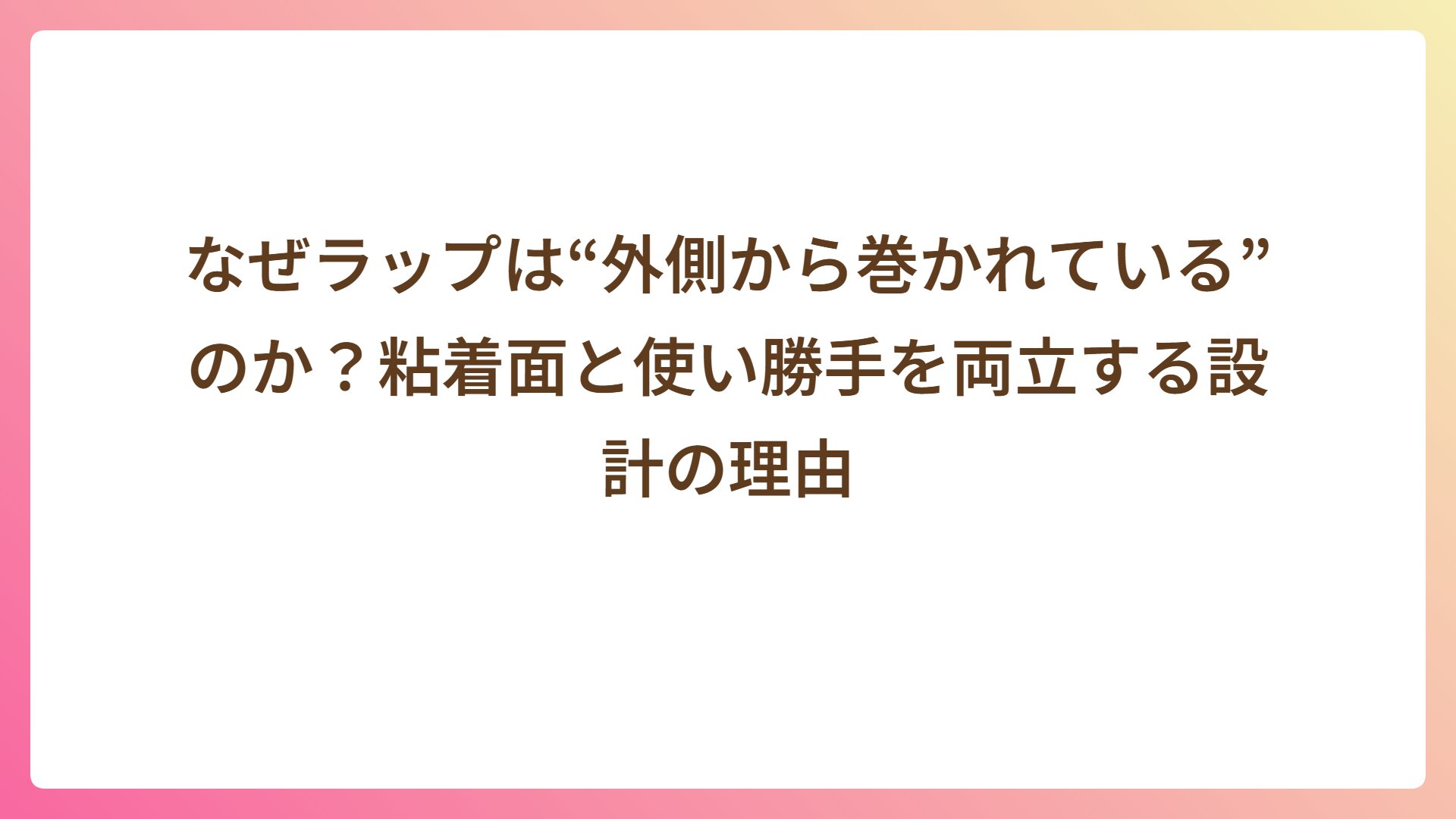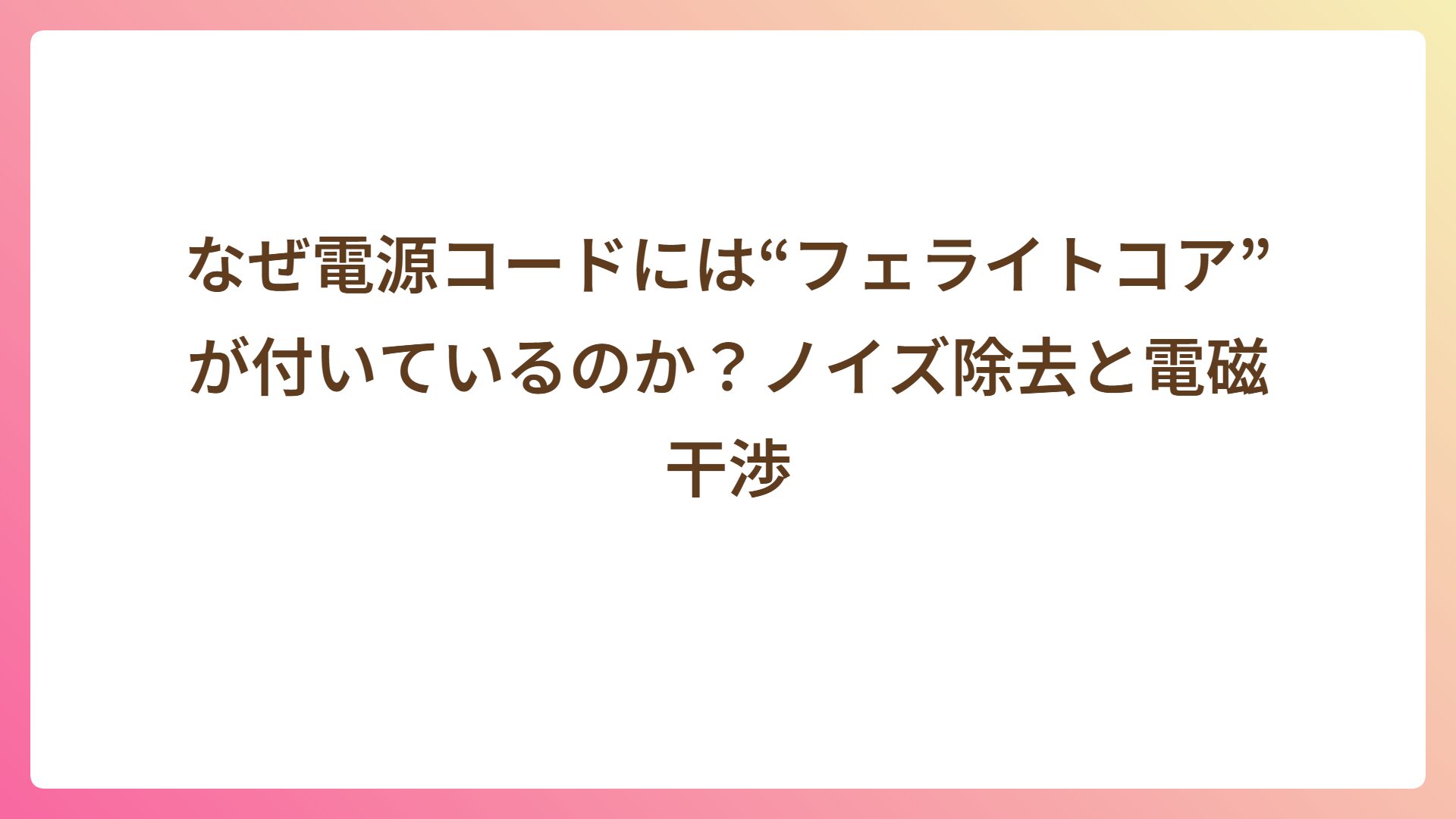なぜ1日は24時間?誰が決めた?10や20じゃダメだった理由とは

みなさんは「どうして1日は24時間なんだろう?」と不思議に思ったことはありませんか?
私たちの生活はこの「24時間」にがっちり縛られていますが、10時間や20時間でもよかったような気もしますよね。
今回は、1日24時間制の起源や、それがどうやって世界に広まったのかについて解説します。
1日が24時間になった理由
結論から言うと、「1日=24時間」という概念は古代エジプトに由来します。
とはいえ、古代エジプト人は最初から1日を24分割しようとしたわけではありません。
彼らはまず、昼間と夜をそれぞれ12時間に分けたのです。
昼は日時計、夜は星で測る
- 昼間の12分割:太陽の動きを測る日時計を用いて、太陽が出ている時間を12に分けた。
- 夜の12分割:太陽が使えない夜は、星の動きや配置を見て、同じく12に分けた。
つまり、昼12時間+夜12時間=24時間という仕組みが自然と出来上がったというわけです。
ただし当時は、夏は昼が長く、冬は夜が長いため、1時間の長さは季節によって変化する不定時法が使われていました。
なぜ「12」なのか?なぜ10や20ではないのか?
ここで気になるのが、「なぜ10でも20でもなく、12という中途半端な数にしたのか?」という疑問です。
有力な説:指の関節で数えられるから
古代の人々は、親指を使って他の4本の指の関節(1本につき3関節)を数えることで「12」という数を使いこなしていました。
- 3関節 × 4本指 = 12
- その12を左手の指を折ってカウントすることで、12×5=60まで数えられる(=60進法の原型)
この方法は直感的かつ数え間違いが少ないため、古代文明では広く使われていたと考えられています。
「24時間制」を広めたのは誰?
このような「昼12・夜12」の文化を踏まえ、紀元前2世紀にはギリシャの天文学者ヒッパルコスが「1日=24等分」という考え方を提唱しました。
さらに時代が進み、14世紀ヨーロッパで機械式時計が発明されたことで、「一定の長さを持つ1時間」が定着し、現代の24時間制が普及していきました。
おわりに
当たり前のように使っている「1日=24時間」という仕組みも、古代エジプトの天文観察と、人間の指の関節が生んだ自然な数え方が元だったとは驚きですね。
ちなみに、分(60分)や秒(60秒)といった時間単位も、この「12」や「60」という数字の文化に深く関係しています。
数字の起源をたどると、私たちの日常がどれほど古代の知恵に支えられているかがよく分かります。
身の回りの「当たり前」も、たまには立ち止まって調べてみると、面白い発見があるかもしれませんよ。