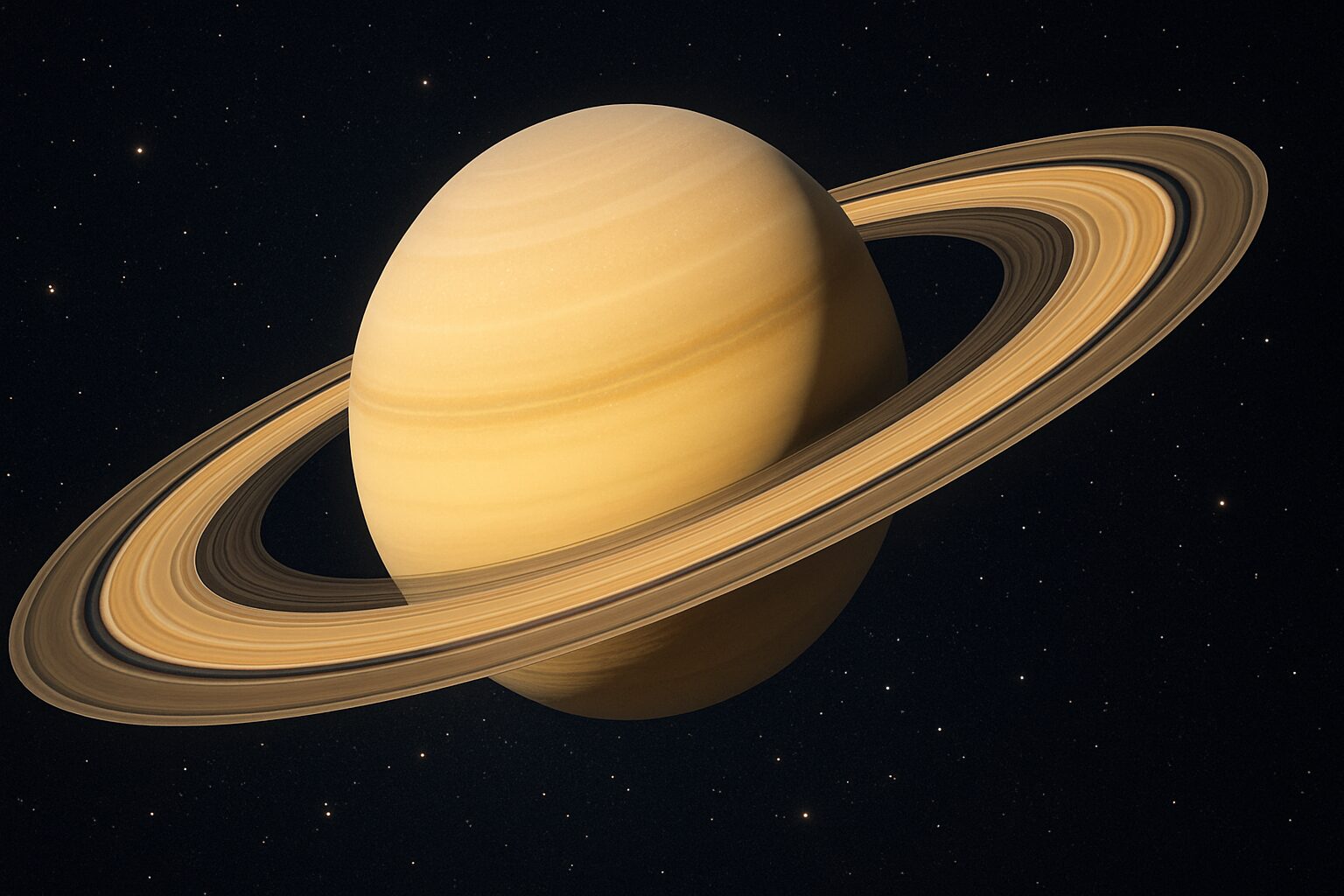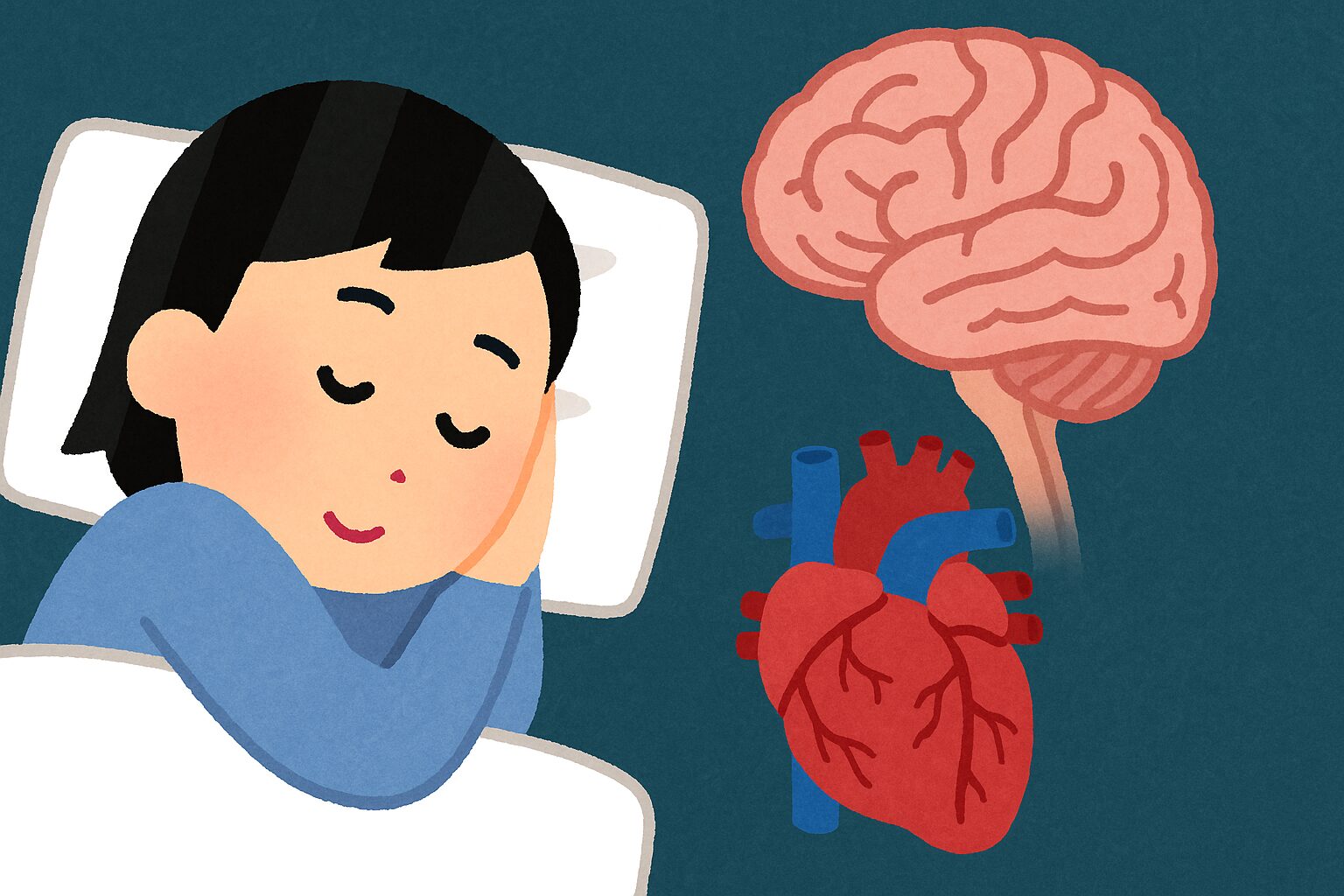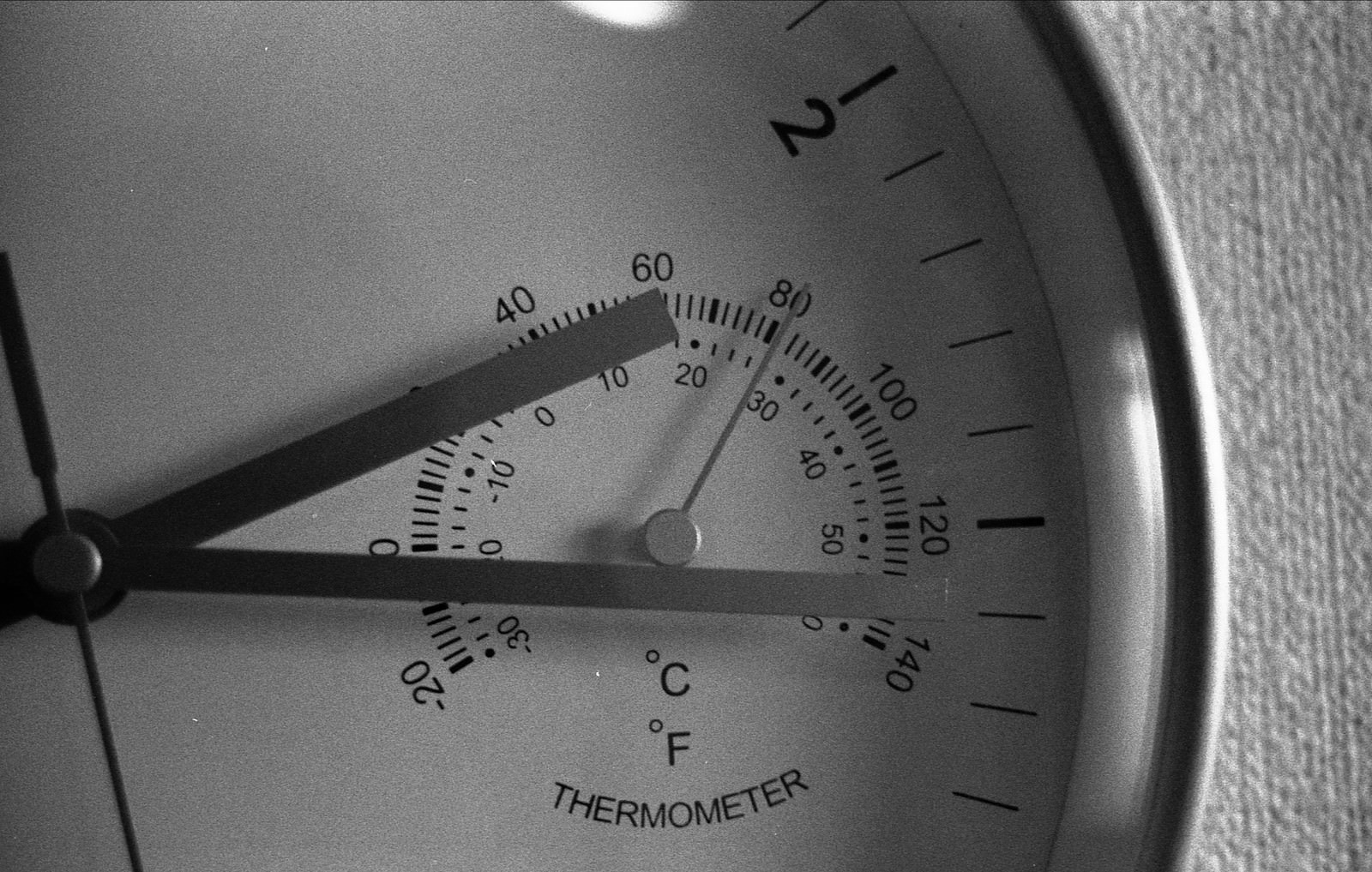なぜ小銭は“5円玉”だけ穴が空いているのか?製造コストと識別性が生んだ独自デザイン
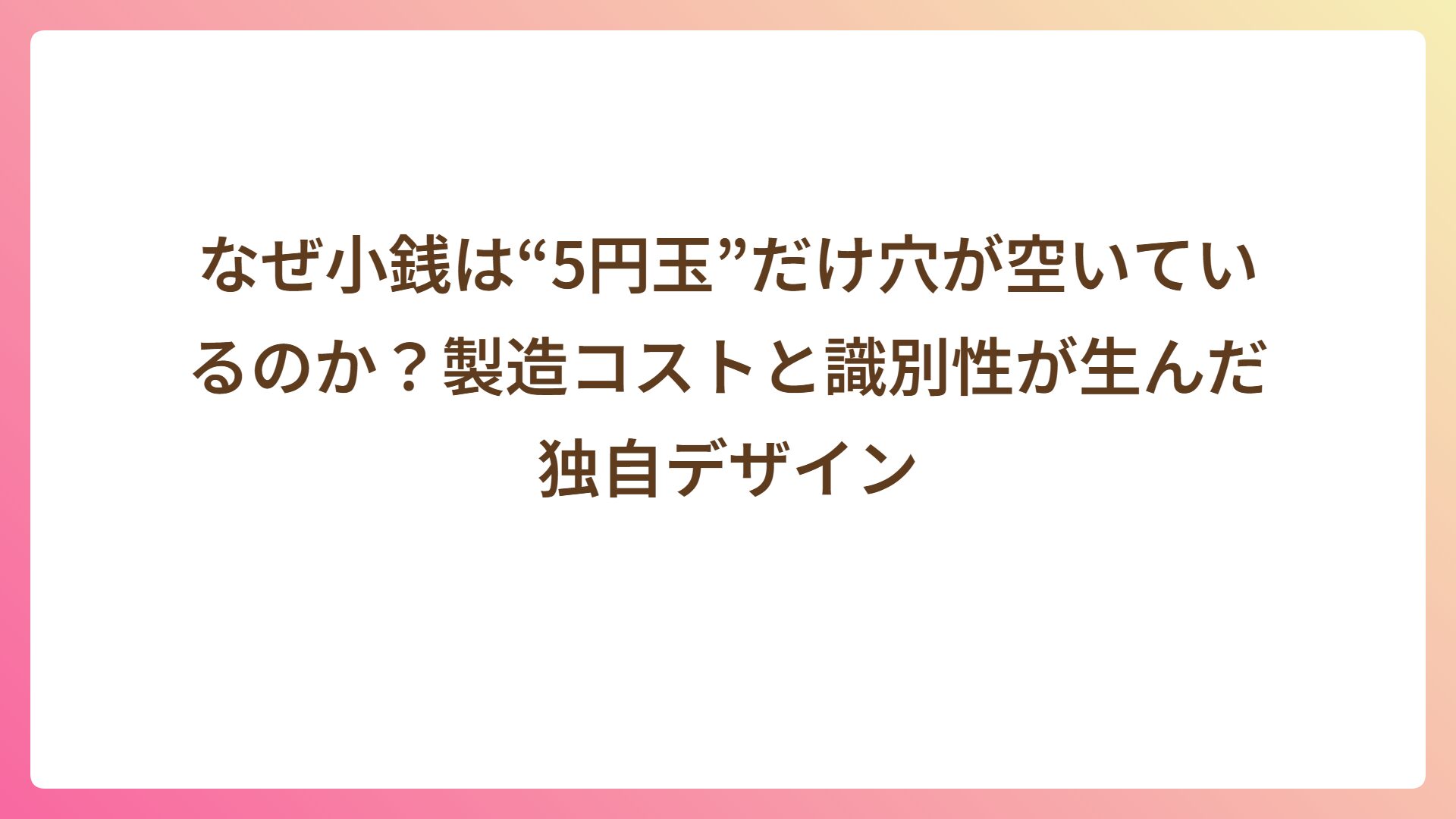
1円・10円・50円・100円・500円──
日本の硬貨の中で、真ん中に穴が空いているのは5円と50円の2種類。
しかし、その中でも**長い歴史を持つ「穴あき硬貨」**は5円玉です。
なぜ小銭の中で5円玉だけに穴が空けられたのでしょうか?
そこには、製造技術・識別性・歴史的事情が深く関係しています。
戦後の金属不足が「穴あき硬貨」を生んだ
現在の5円玉が誕生したのは、昭和23年(1948年)。
終戦直後の日本は深刻な金属不足にあり、
貨幣製造のための銅や亜鉛も貴重な資源でした。
そこで、当時の大蔵省(現在の財務省)は
「できるだけ金属を節約しながらも使いやすい硬貨を」
という方針で新しい5円硬貨を設計。
その結果、中央に穴を開けることで材料を減らすという、
コスト削減と軽量化を両立する形になったのです。
穴を開けることで「識別しやすく」なった
5円玉には、もう一つの重要な理由があります。
それは、誰でも簡単に識別できること。
当時は視覚障がい者向けの配慮がほとんどなかった時代ですが、
偶然にも穴のあるデザインが
「触ってすぐに5円玉だと分かる」という利点を生みました。
実際、現代の硬貨設計基準でも
- 直径・厚み・重さ・素材
- 表面のギザギザ(ミゾ)
- 穴の有無
が「識別のための要素」として規定されています。
つまり5円玉の穴は、デザインというより“識別装置”なのです。
デザイン面でも「農業と産業」を象徴
現在の5円玉には、
稲穂・歯車・水の波紋という3つのモチーフが刻まれています。
- 稲穂 … 農業
- 歯車 … 工業
- 波紋 … 水運・貿易
これらは戦後日本の再建と産業発展を象徴しており、
中央の穴は「すべてを結ぶ輪」「発展の中心」を意味するとも言われます。
つまり、穴は経済的理由と象徴的デザインの融合なのです。
50円玉にも穴があるのは“識別バランス”のため
5円玉だけでなく、1959年に登場した50円玉にも穴があります。
これは、100円玉と大きさ・形状が似ていたため、
「見分けやすいように穴を追加しよう」
という意図で設計されました。
ただし、1円・10円・100円・500円はすでに大きさ・色・縁のギザなどで区別可能だったため、
新たに穴を開ける必要がなかったのです。
つまり、穴のある硬貨が2種類にとどまっているのは、
「必要な区別ができる範囲で設計されている」からです。
穴のサイズにも“物理的な最適値”がある
5円玉の穴径は5mm。
これは製造効率・機械精度・使用感のバランスを取った結果です。
穴が小さすぎると汚れが詰まりやすく、
大きすぎると強度が下がって折れやすくなるため、
硬貨としての耐久性と識別性を両立する黄金比として採用されています。
現代でも“穴あき硬貨”が続く理由
現在では金属資源の不足は解消されていますが、
5円玉は依然として日本文化を象徴するデザインとして愛されています。
さらに、
- 自動販売機や硬貨計数機でも認識しやすい
- 偽造防止効果がある(穴あけ加工が難しい)
といった技術的な利点もあるため、
改鋳(かいちゅう)後も穴あき仕様は維持されています。
まとめ:5円玉の穴は“節約”と“識別”の結晶
5円玉に穴が空いているのは、
- 戦後の金属不足で材料を節約するため
- 触覚・視覚で識別しやすくするため
- 経済復興を象徴するデザインの一部として採用されたため
という機能と歴史の両立によるものです。
つまり、あの小さな穴には、
日本の戦後復興・技術合理性・デザイン文化のすべてが詰まっているのです。