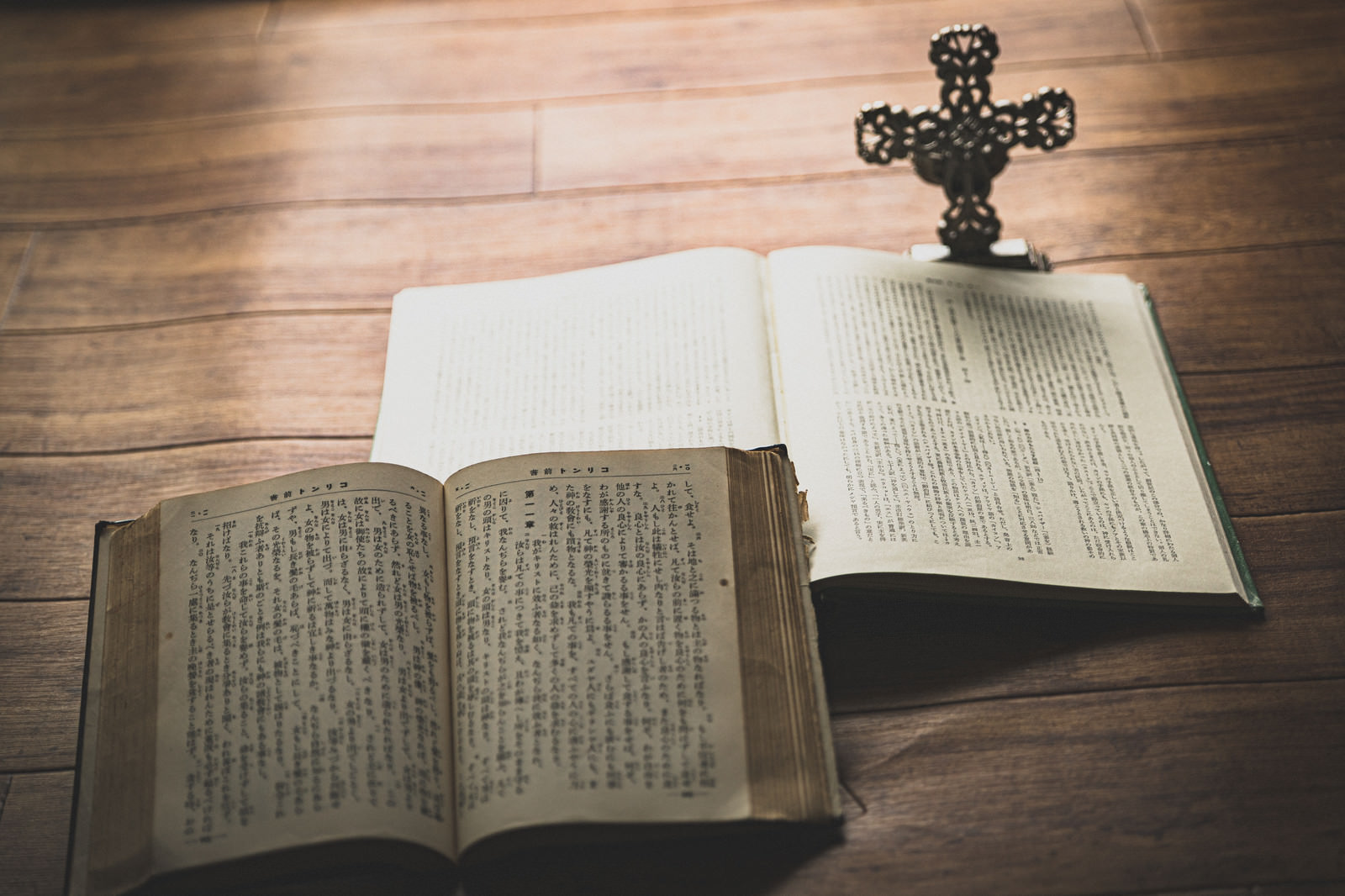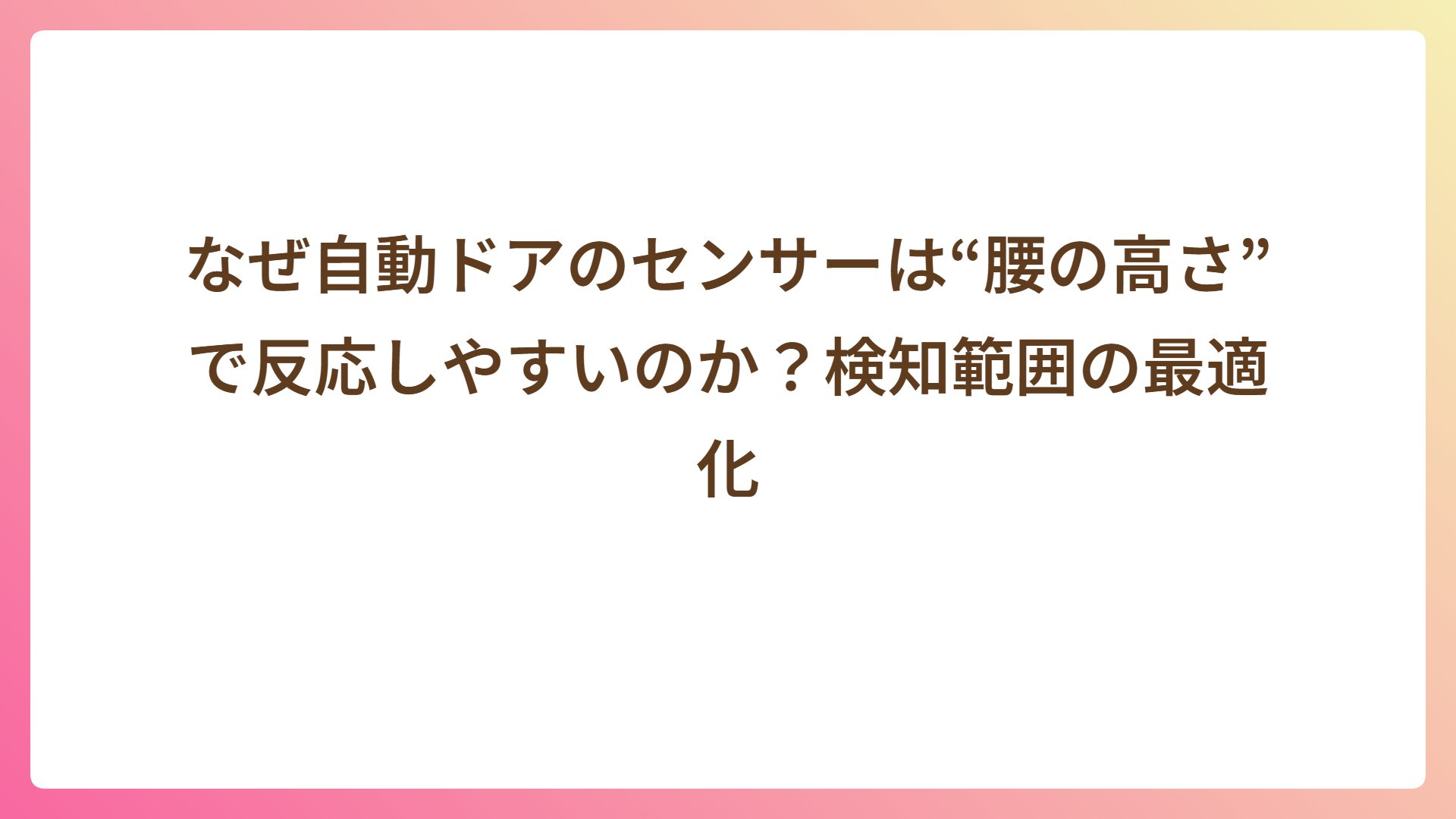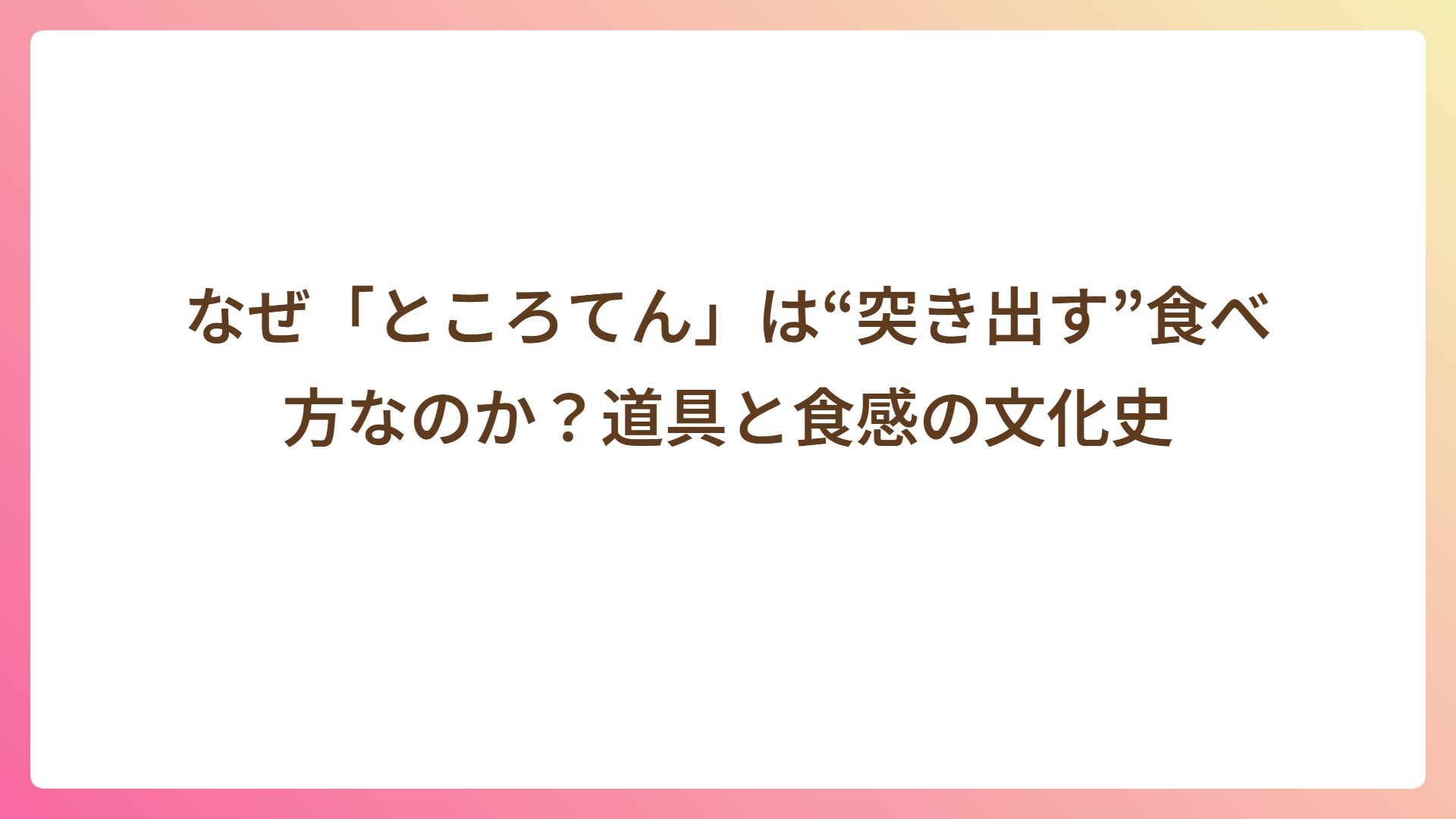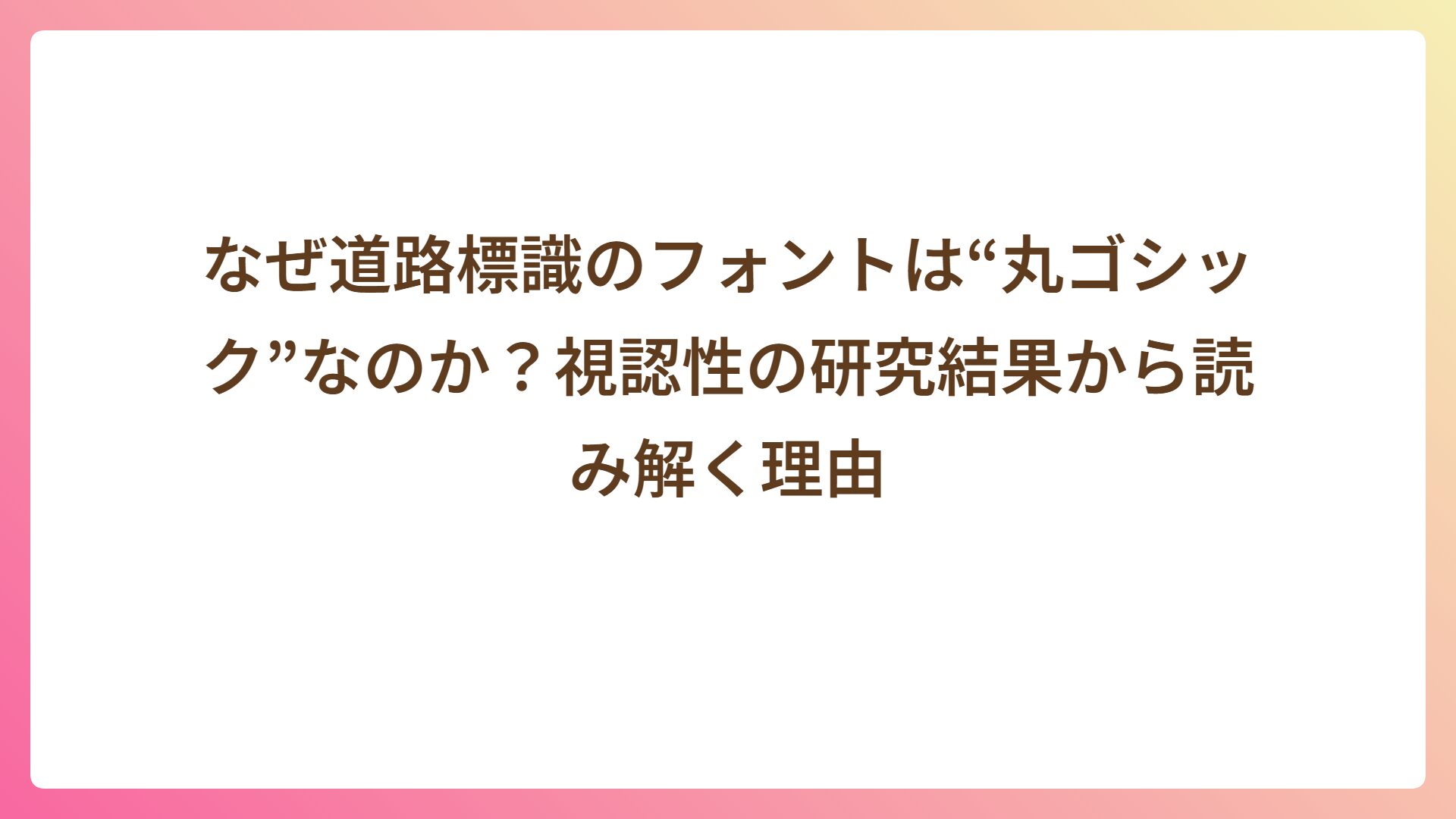運転免許証の番号の意味とは?再発行回数や取得年がバレるって本当?

皆さんの運転免許証には、氏名や住所と並んで「番号」と書かれた12桁の数字が記載されていますよね。
実はこの番号、ただの通し番号ではなく、それぞれにしっかり意味があるんです。
中には「再発行した回数がバレる」というちょっと恥ずかしい情報まで含まれていたりします。
今回は、運転免許証の番号に隠された意味をひとつずつ解説していきます。
1〜2桁目:最初に取得した都道府県がわかる
番号の先頭2桁は、初めて運転免許を取得した都道府県の番号を表しています。
たとえば「10」は北海道、「12」は千葉県、「30」は和歌山県、「97」は沖縄県といった具合に、都道府県ごとに番号が割り振られています。
これは引っ越して免許証の住所変更をしても変わることはありません。
3〜4桁目:免許取得の西暦下2桁を示す
続く3桁目と4桁目には、最初に免許を取得した年の西暦の下2桁が記載されています。
たとえば「05」であれば2005年、「23」であれば2023年に免許を取得したということになります。
5〜10桁目:識別用の個別番号
5桁目から10桁目までは、個人を識別するための任意の数字です。
都道府県ごとの公安委員会が独自に付番しており、特に意味はありません。完全に人によって異なる番号になります。
11桁目:チェックディジット
11桁目は「チェックディジット」と呼ばれ、番号の入力ミスや偽造を防ぐための検証用の数字です。
他の数字をもとに算出された値で、適当に番号を作ってもここが合わなければ無効となる仕組みです。
12桁目:再発行回数がバレる
12桁目の数字は、これまでに運転免許証を再発行した回数を表しています。
- 0:再発行なし
- 1:1回再発行
- 2:2回再発行
- …
- 9:9回再発行
10回を超えるとまた「0」や「1」に戻るため、累計回数までは分からないものの、少なくとも一度でも再発行していればわかってしまいます。
番号の他にもチェックされる「照会番号」
番号とは別に、交付年月日のすぐ右横に6桁の数字が記載されています。これは「照会番号」と呼ばれ、各都道府県の内部データベースでの検索に使われる番号です。
一般の人が使う機会はありませんが、免許センターや警察ではよく使われています。
おわりに
運転免許証の番号には、都道府県・取得年・再発行回数など、意外と多くの情報が詰まっていることがわかりました。
普段何気なく見ている12桁の数字にも、意味を知ると少し見え方が変わってきますね。
身分証明の場面で使うことも多い運転免許証ですが、個人情報の宝庫でもあるので、取り扱いにはくれぐれも注意しましょう。