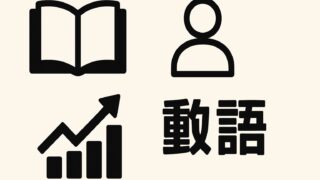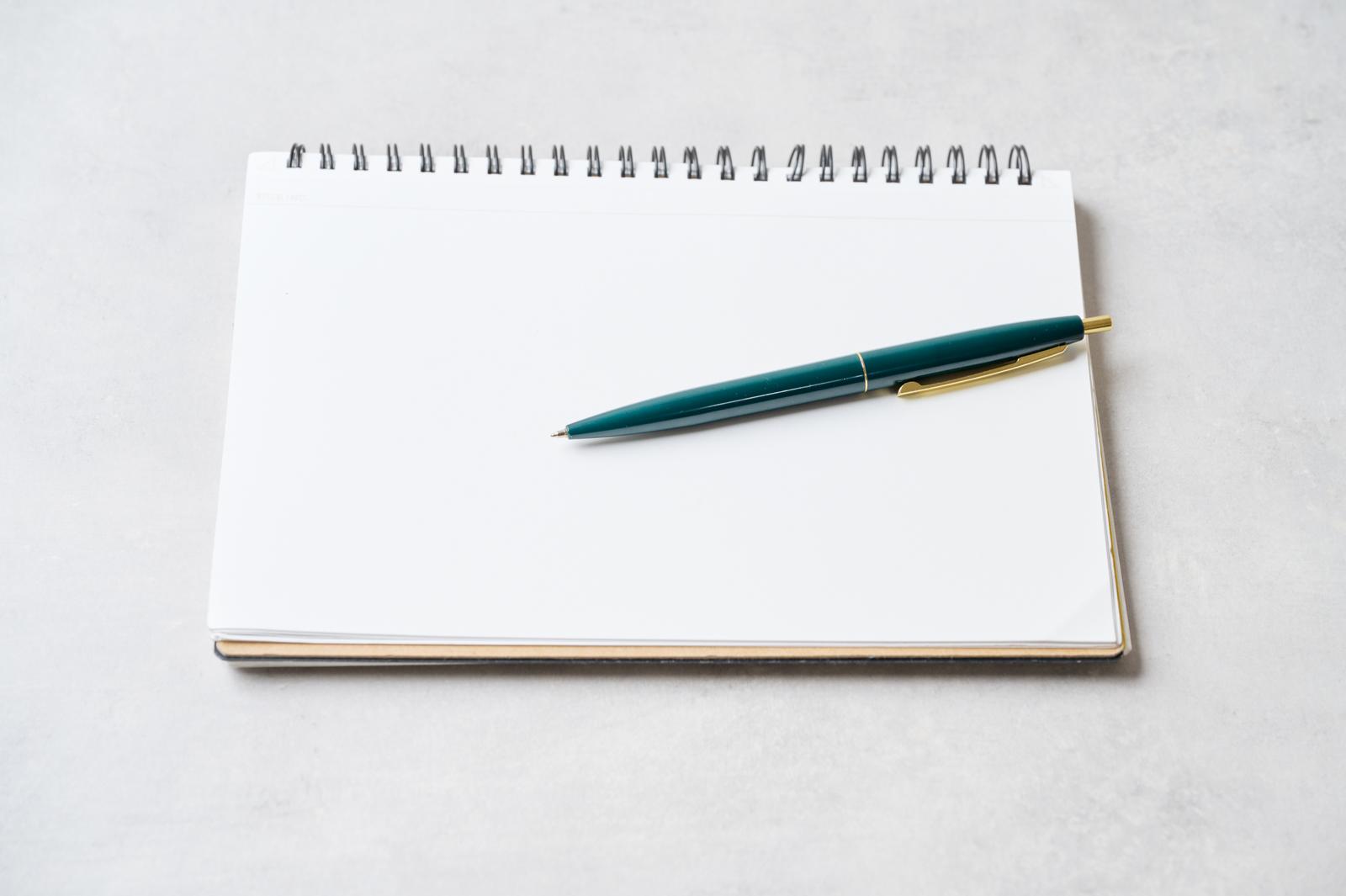雑魚ってなんで「ざこ」って読むの?ざつぎょじゃダメなの?

突然ですが、「雑魚」という漢字、正しく読めますか?
正解は「ざこ」ですが、「雑(ざつ)」はともかく、「魚(ぎょ)」を「こ」と読むのは少し不自然に感じる人も多いのではないでしょうか。
「ざつぎょ」ならまだ納得できそうなのに、なぜ「ざこ」と読むようになったのでしょうか?
今回は、このちょっと不思議な読み方のルーツについて解説していきます。
雑魚とは「さまざまな小魚の総称」
まず、「雑魚(ざこ)」という言葉は、釣りや漁などで意図せずとれてしまう、小さくてあまり価値のない魚たちの総称です。
たとえば大きな魚を狙って仕掛けた網や釣り針に、小ぶりな魚が一緒に引っかかってしまうことがあります。これらの小魚たちは、売り物としての価値が低かったため、漁師たちはひとまとめにして「雑魚」と呼んでいました。
つまり、「雑魚」とは特定の魚種を指すのではなく、「いろいろ混じった小魚たち」をひとまとめにした言葉だったんですね。
語源は「雑喉(ざっこう)」にあり
それでは本題の「ざこ」という読み方について見ていきましょう。
この読みは、もともと「雑喉(ざっこう)」という言葉が語源になっているといわれています。
ここで注目したいのが、「喉」という字。
実はこの「喉(こう)」は、古くは女房言葉などで「魚」を指す隠語的な使われ方をしていたのです。
つまり、「雑喉」は「いろんな小魚」という意味で、「雑魚」とほぼ同じ意味の言葉だったわけです。
それがやがて、「ざっこう」→「ざこ」と発音が変化し、
あわせて表記も「喉」からより意味が伝わりやすい「魚」に置き換わって、
「雑喉(ざっこう)」 → 「雑喉(ざこ)」 → 「雑魚(ざこ)」
という流れで今の形になったとされています。
つまり、「魚(こ)」という読み方は辞書に載るような一般的な訓読みではなく、言葉の変遷によって偶然生まれた特殊なケースなんです。
おわりに
「雑魚(ざこ)」という言葉の読みが、実は「雑喉(ざっこう)」という古い言葉からきていたというのは意外だったのではないでしょうか?
漢字の読みには、他にもこのように歴史や言葉の変化に起因する例が数多くあります。
ふと「なんでこんな読み方なんだろう?」と思ったときには、ぜひその由来を調べてみてください。身近な日本語の面白さに気づけるかもしれませんよ。