なぜ鏡餅は“重ねる”のか?円と歳の象徴
mixtrivia_com
MixTrivia
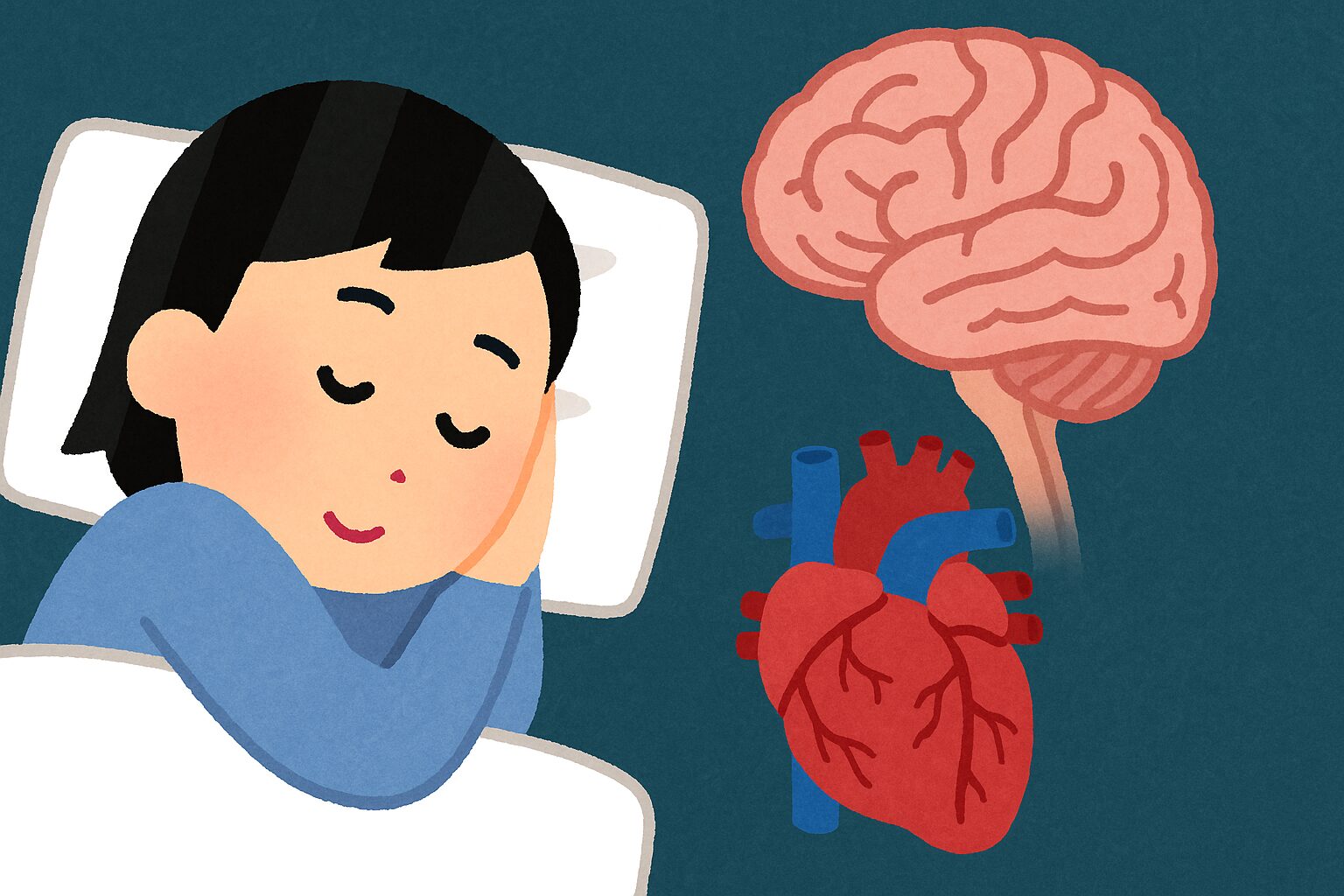
子どもの頃、「眠っている間に心臓や呼吸が止まらないのはなぜ?」と不思議に思ったことはありませんか?実はそこには、人間の体を守る巧妙な仕組みがあります。本記事では、睡眠中でも体が生き続けられる理由を解説します。
人間の体を管理しているのは脳です。大きく分けると以下の3つの部位があります。
脳幹は心臓を動かす心臓中枢や呼吸中枢を含み、生命維持に不可欠な役割を果たしています。
私たちが眠っている間も、脳幹は休むことなく働き続けています。脳幹からの命令は自律神経を通じて全身に伝わり、血液循環や呼吸などを自動的にコントロールしています。
つまり、眠っている間に命の維持に必要な機能が止まることはありません。
心臓には「刺激伝導系」と呼ばれる仕組みがあり、外部の命令がなくても自動的に拍動を続けます。ただし、拍動の速さや強さは脳幹からの命令を受けて調節されています。
そのため、睡眠中でも状況に応じて心拍数を上げたり下げたりできるのです。
呼吸もまた延髄にある呼吸中枢の支配を受けています。
自動運転と手動操作の両方が可能な、効率的な仕組みになっているのです。
もし脳幹が重大な損傷を受けると、生命維持が難しくなってしまいます。逆にいえば、私たちが眠って安心していられるのは、脳幹が黙々と働き続けてくれているからなのです。