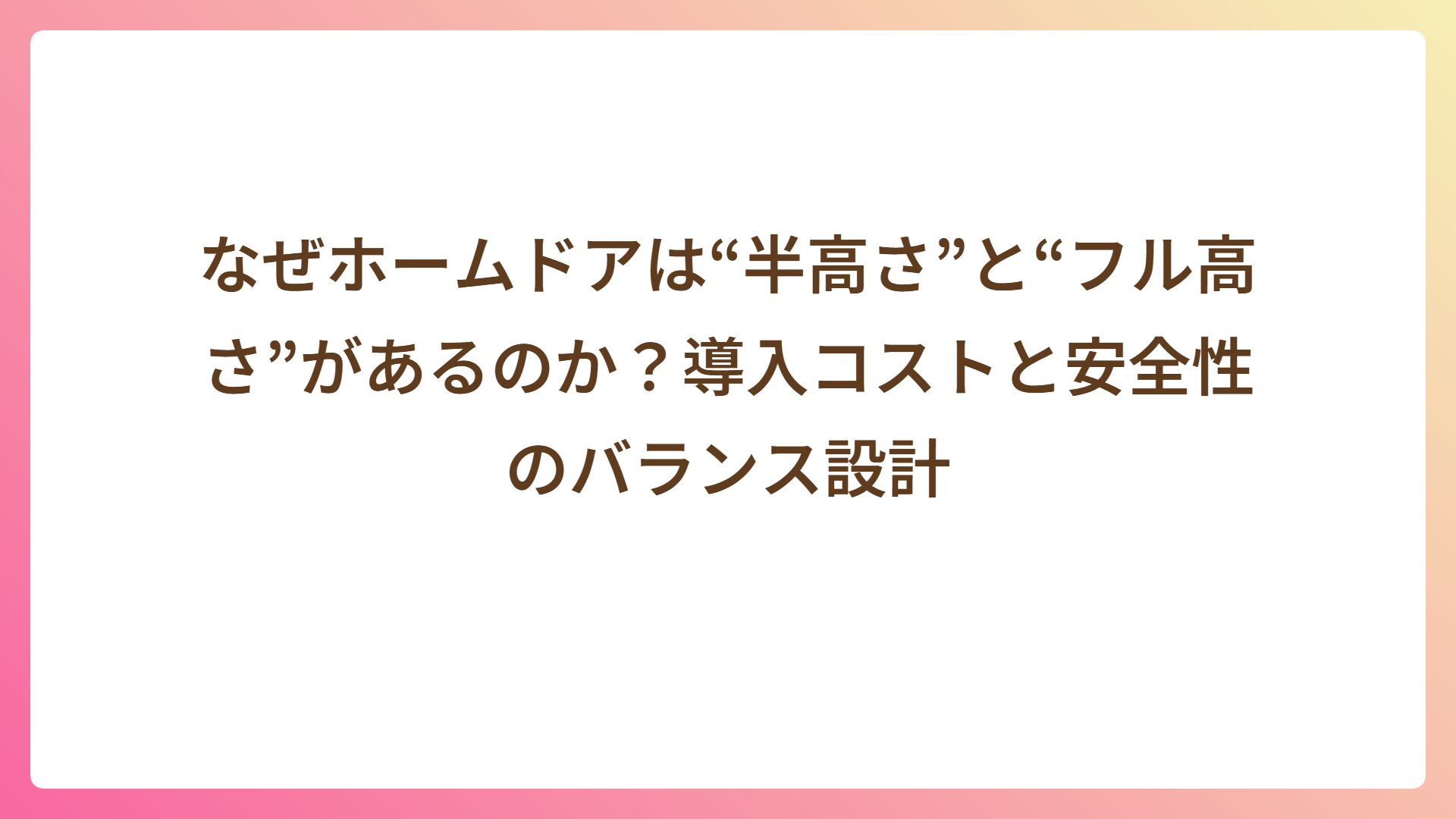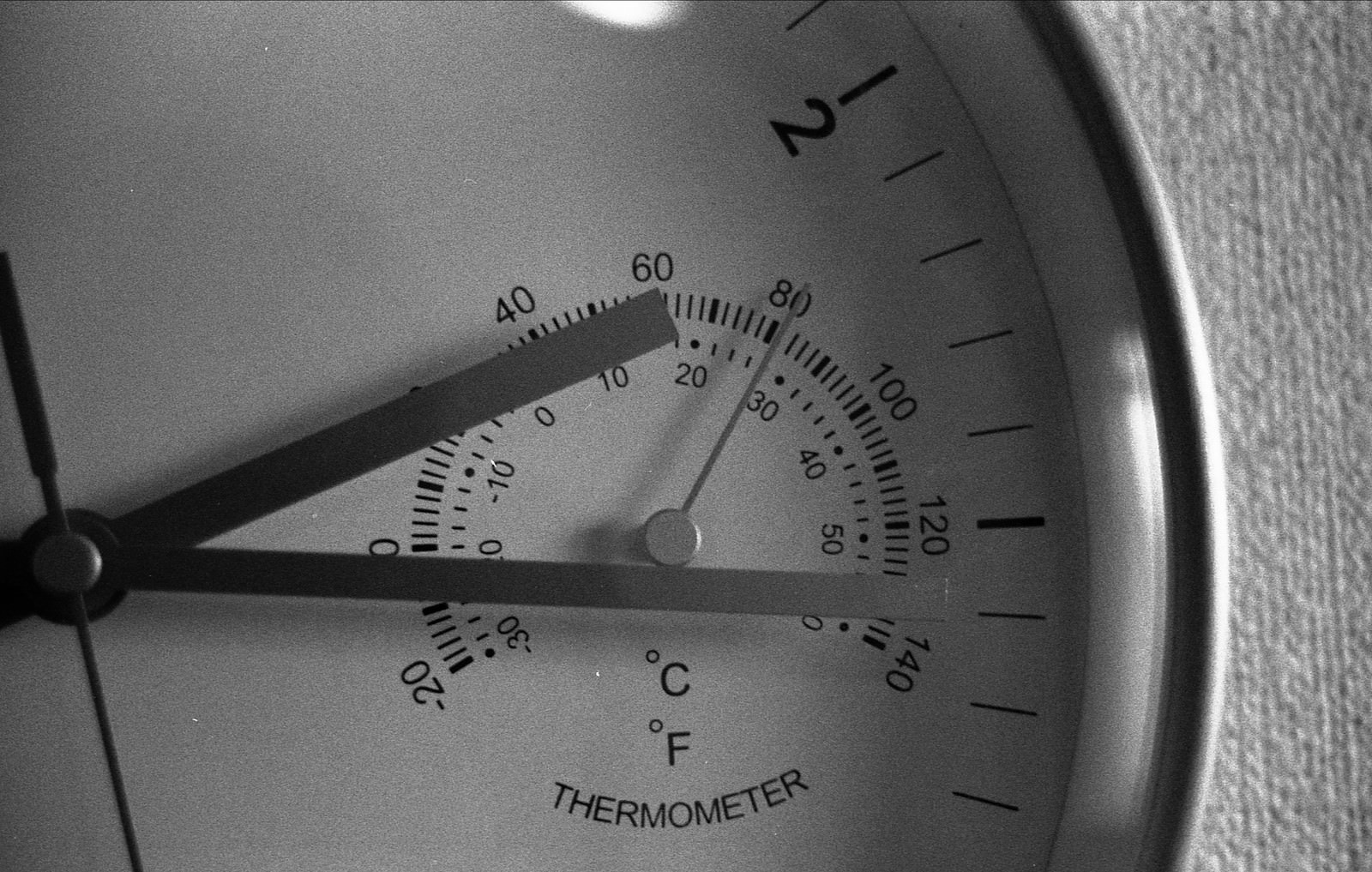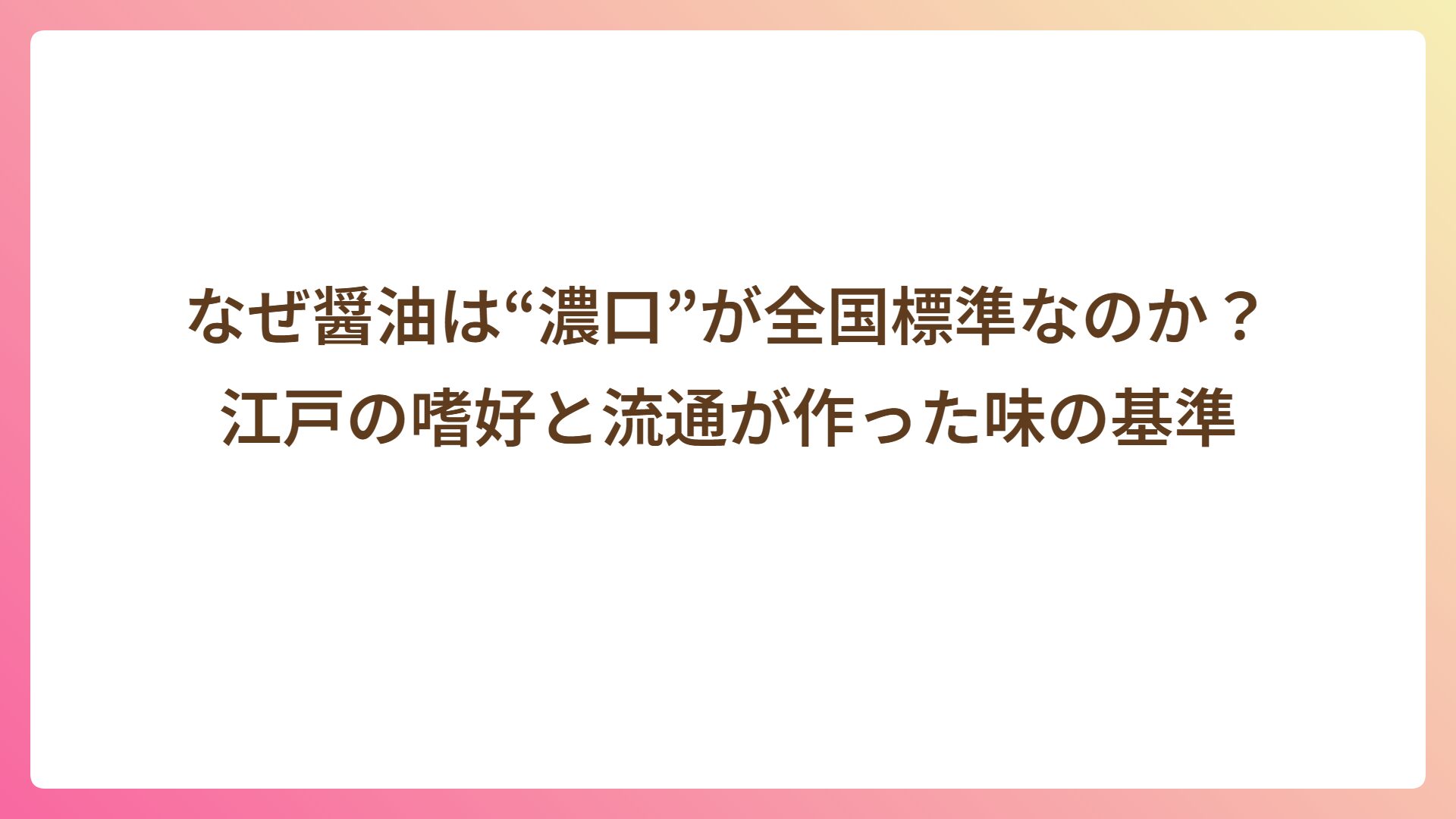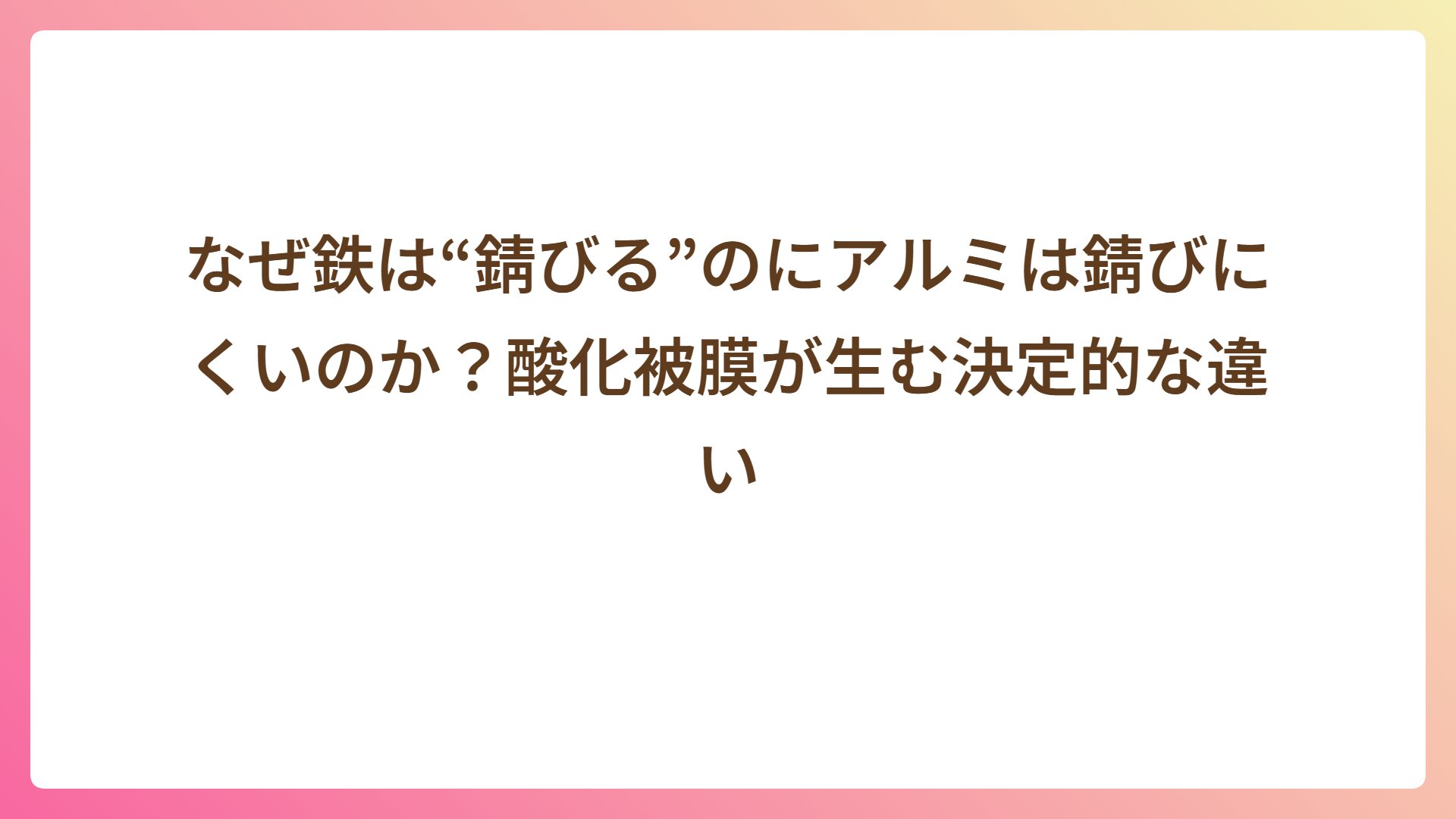桜餅の葉っぱは食べる?柏餅や柿の葉寿司との違いと見分け方を消費者庁ルールで解説

桜餅の葉っぱを食べる派・食べない派、毎年のように話題になりますよね。
ではなぜ、柏餅や柿の葉寿司では葉っぱを食べないのに、桜餅だけは“食べてもいい雰囲気”があるのでしょうか?
その答えは意外にも、パッケージの原材料表示に隠れています。
今回は、消費者庁の食品表示ルールをもとに、「葉っぱを食べられる和菓子と食べられない和菓子の見分け方」をわかりやすく解説します。
桜餅・柏餅・柿の葉寿司で違いが出る理由
桜餅や柏餅、柿の葉寿司など、“葉っぱで包む食べ物”は見た目が似ていても、葉の扱い方はまったく違います。
| 食べ物 | 包む葉 | 食べる? | 理由 |
|---|---|---|---|
| 桜餅 | 桜の葉(塩漬け) | 食べてもOK派あり | 食用加工済みで香りづけ目的 |
| 柏餅 | 柏の葉 | 食べない | 硬くて消化しにくく、食用加工されていない |
| 柿の葉寿司 | 柿の葉 | 食べない | 包装・保存目的で渋みが強い |
この違いを生むのが、“葉が食品の一部として扱われているかどうか” です。
その見分け方こそ、次に紹介する「原材料表示」にあります。
原材料表示に「葉っぱ」が書いてあるかどうかをチェック
消費者庁が定める「食品表示法」と「食品表示基準」では、加工食品の原材料名を正しく表示する義務があります。
つまり、製造者が「この葉も食品の一部」として扱う場合は、原材料名欄にその葉っぱの名称を記載しなければなりません。
✅ 原材料名に「桜葉」などが書かれている場合
→ 食材として扱われている可能性が高い。
→ 食べても問題ない設計になっていることが多い。
❌ 原材料名に「葉」が書かれていない場合
→ 包装材・装飾目的として使われている可能性が高い。
→ 食べずに取り除くのが前提。
実際に桜餅のパッケージでは「もち米、砂糖、小豆、桜葉(塩漬)」などと明記されている商品があります。
一方で、柿の葉寿司や柏餅では「柿葉」「柏葉」といった表記は通常ありません。
この違いこそが、「食べられる葉/食べない葉」を見分ける最大のポイントなのです。
消費者庁ルールの根拠:食品表示法と食品表示基準
消費者庁が定める食品表示法(平成25年法律第70号)および食品表示基準では、以下のように定められています。
食品表示法 第1条(目的)
食品の表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保および合理的な食品選択の機会の確保を目的とする。
(出典:消費者庁「食品表示法」公式サイト)
食品表示基準 第4条(原材料名の表示)
加工食品に使用した原材料は、重量の多い順にその名称を表示しなければならない。
(出典:食品表示基準(内閣府令)PDF)
つまり、もし葉っぱが食用目的で使用されているなら、製造者はその名称を表示しなければならないということです。
このルールに基づけば、「原材料表示に葉がある=食べてもOKの設計」 と考えるのが合理的です。
表示だけで判断できない例外もある
もちろん、表示だけで100%判断できるわけではありません。
次のような例外が存在します。
- 店舗販売や手作り和菓子では、簡易表示しか行われないことがある
- 葉っぱが香りづけ目的で微量使用され、省略される場合がある
- 食感や嗜好の問題で、表示があっても「食べない派」が多い地域もある
特に桜餅は地域性が強く、関東の「長命寺(焼き皮タイプ)」では葉を外す派が多く、関西の「道明寺」では葉ごと食べる派が多い傾向にあります。
葉っぱを食べるときの注意点
- クマリン成分:桜葉に含まれる香り成分。通常量では問題なし。
- アレルギー:口腔アレルギー体質の人は注意。
- 繊維の硬さ:特に子どもや高齢者は誤嚥のリスクがあるため控えるのが安心。
まとめ:迷ったら「原材料名」に注目しよう
葉っぱが食べられるかどうかは、「感覚」ではなくラベル表示で見分けるのが確実です。
| チェック項目 | 判断の目安 |
|---|---|
| 原材料名に葉の名前がある | 食べられる可能性が高い |
| 原材料名に葉が書かれていない | 食べないのが安全 |
| 包装や見た目でしか葉が確認できない | 装飾・保湿目的の可能性大 |