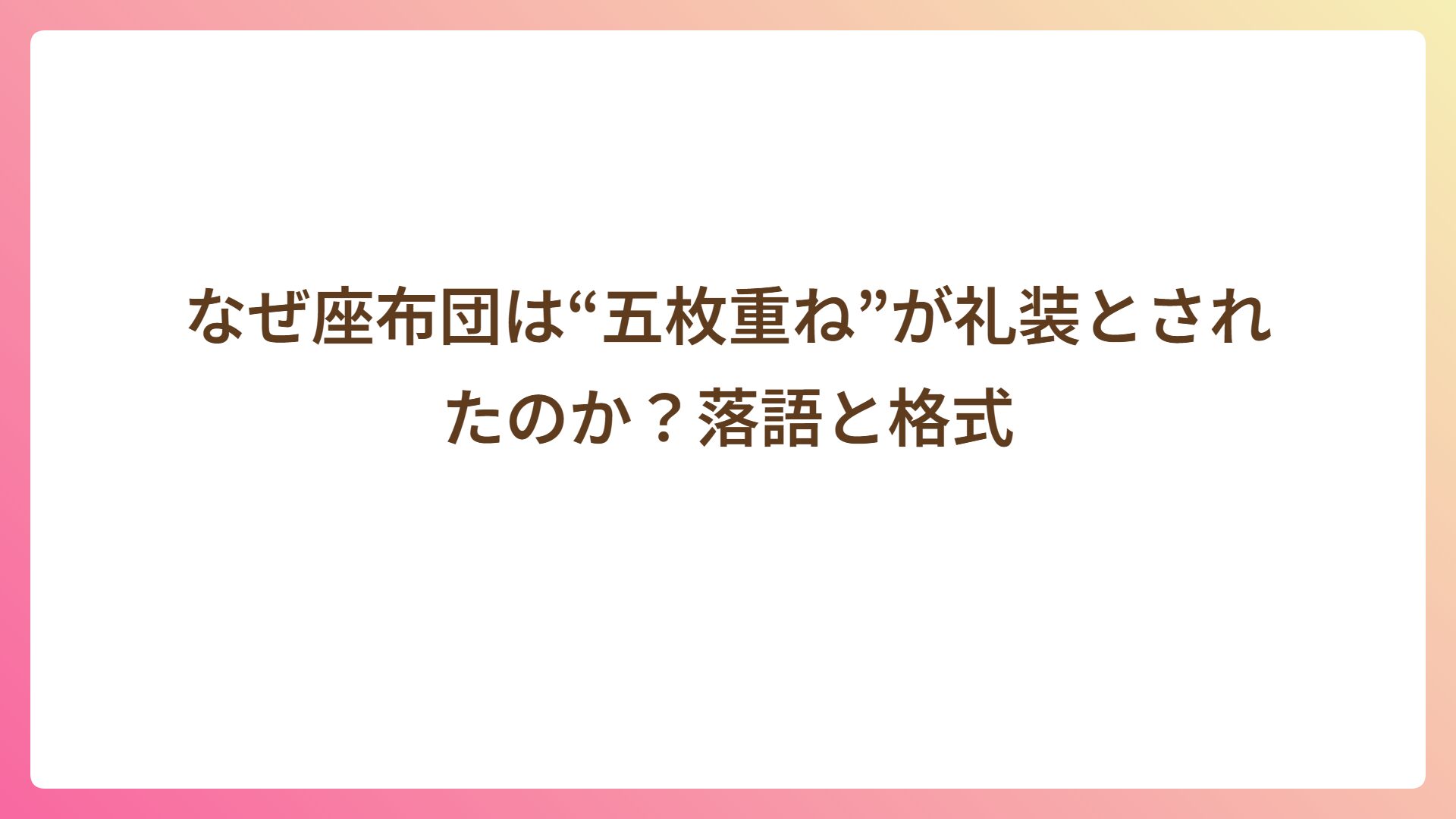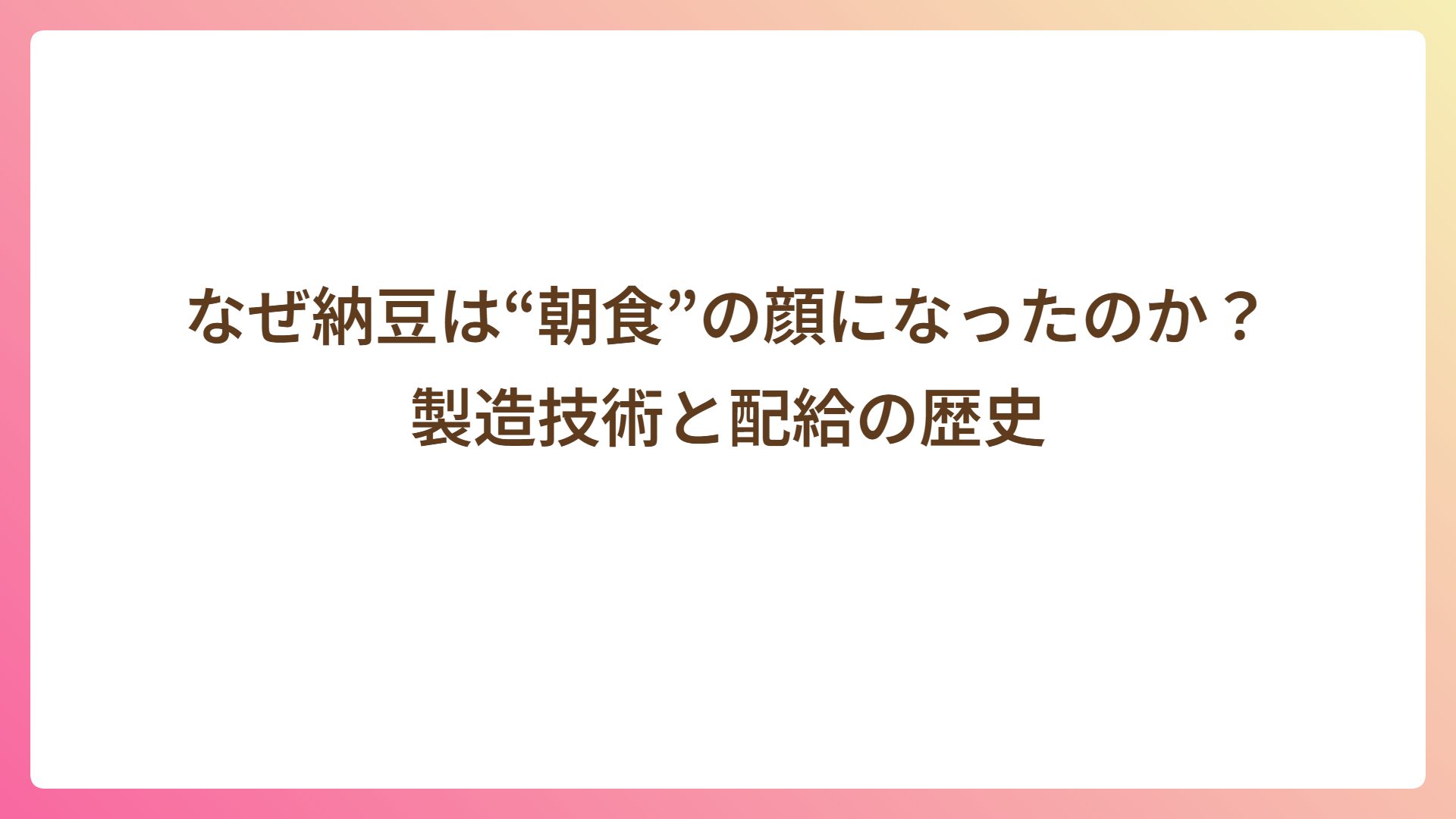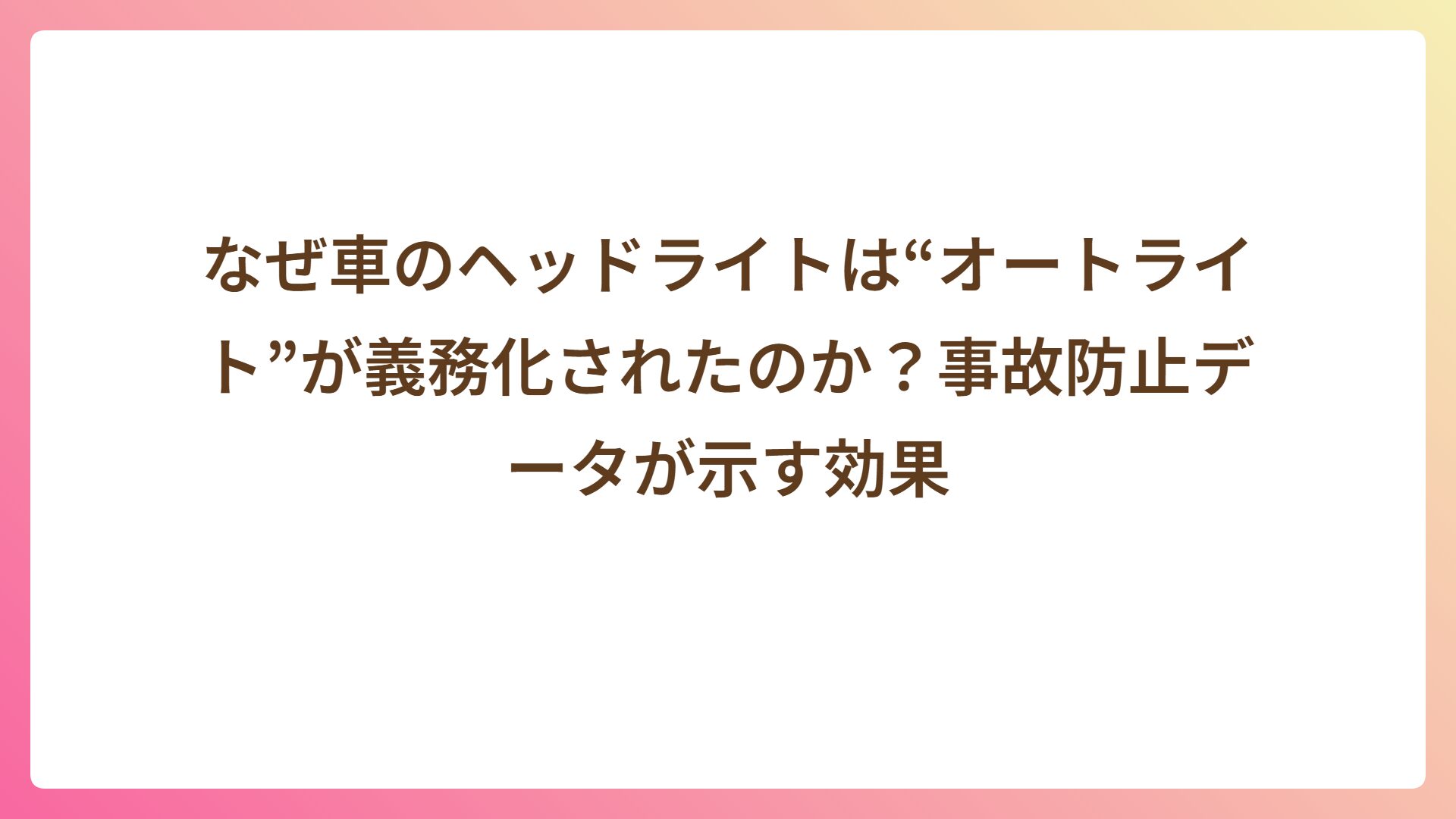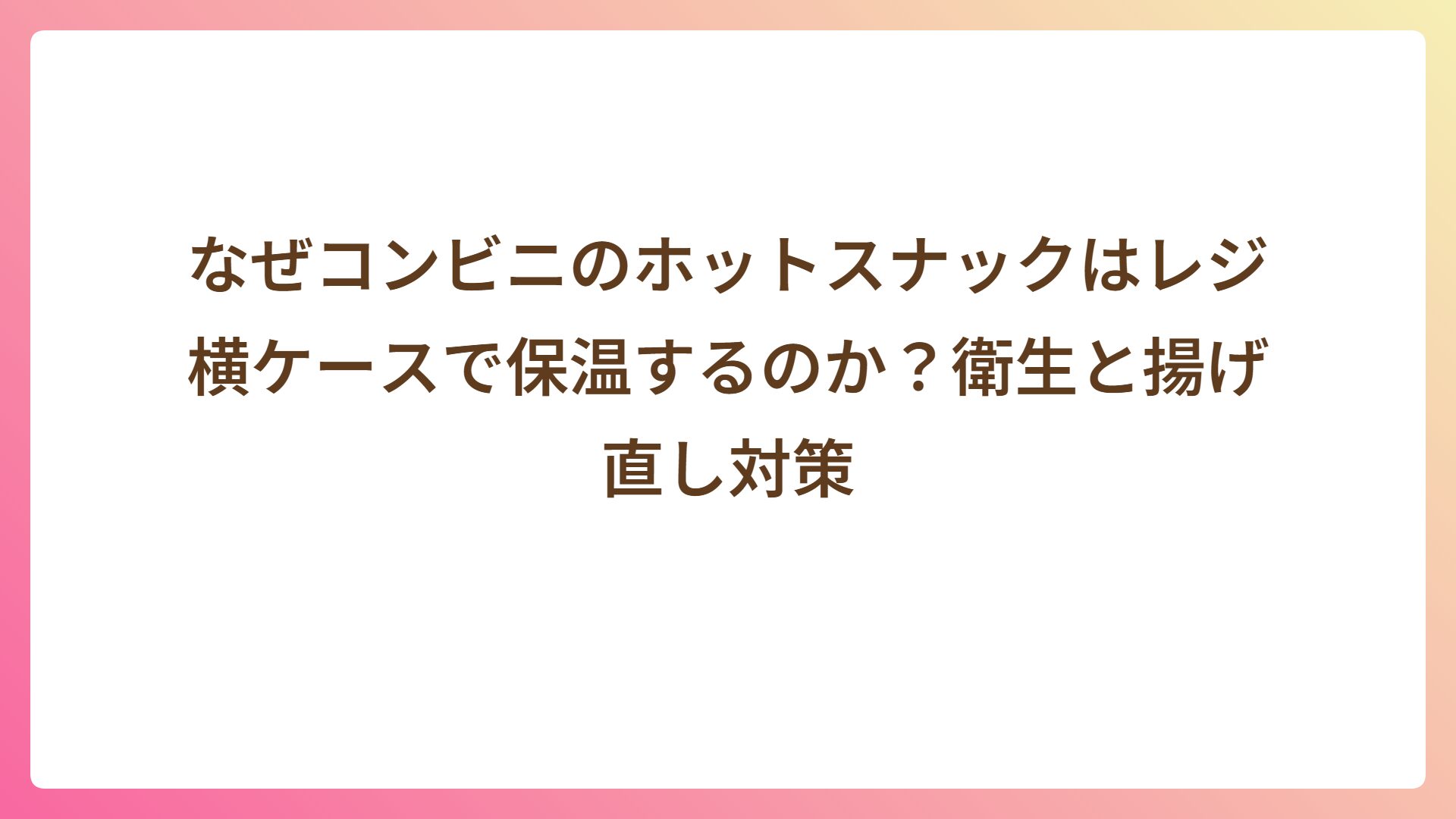なぜ猫は夜に目が光るのか?瞳孔の構造と“タペタム”の不思議な反射機能

夜道で猫と目が合うと、ギラッと光るその瞳にドキッとすることがありますよね。
実はあの光、単なる“ホラー演出”ではなく、暗闇でもよく見えるための進化的な仕組みなのです。
この記事では、猫の目が光る理由を「瞳孔」と「タペタム」という2つの構造からわかりやすく解説します。
猫の目が光るのは「タペタム・ルシダム」のおかげ
猫の目が光るのは、タペタム・ルシダム(Tapetum lucidum)という特殊な反射膜の存在によるものです。
このタペタムは、網膜の裏側にある薄い層で、光を反射して再び網膜へ送り返す働きを持っています。
人間の目では、光は網膜に当たった時点で吸収されて終わります。
しかし猫の目では、タペタムによって光が“もう一度リサイクル”されるため、暗闇でも微弱な光を有効に使えるのです。
その結果、猫の暗闇での視力は人間の約6倍も高いと言われています。
「光っている」のではなく「反射している」
多くの人は「猫の目が自ら光っている」と思いがちですが、正確には外からの光を反射しているだけです。
懐中電灯や車のヘッドライトなど、わずかな光が瞳の奥でタペタムに反射し、それが外に漏れて見える――これが“光る目”の正体です。
タペタムが反射する光は、猫の種類や光の角度によって黄緑色・青色・金色などに見えることがあります。
暗闇でも見える理由 ― 瞳孔が大きく開く構造
タペタムだけでなく、猫の瞳孔(どうこう)の構造も夜目の良さに大きく関係しています。
猫の瞳孔は「縦に細長いスリット型」で、
- 明るい場所では細く閉じて光の量を制限
- 暗い場所では大きく開いて光を最大限取り込む
という調整を瞬時に行います。
この瞳孔の開閉幅は非常に広く、明るい昼間から真っ暗な夜まで、あらゆる光量に対応できるのです。
猫の目の構造は“夜行性”への進化の結果
猫はもともと夜行性(正確には薄明薄暮性=夕方・早朝に活動)です。
暗闇でも獲物を見つけられるよう、目の構造が進化してきました。
その特徴をまとめると👇
| 構造 | 役割 | 効果 |
|---|---|---|
| タペタム・ルシダム | 光を反射して再利用 | 暗所での視力向上 |
| 縦長の瞳孔 | 光の量を自在に調整 | 明暗差の大きい環境に対応 |
| 高感度な視細胞(杆体) | 光を感知する細胞が多い | 薄暗い環境で動きを察知 |
これらが組み合わさることで、猫は暗闇でも物体の輪郭や動きを正確に捉えることができるのです。
猫以外にも「目が光る動物」は多い
タペタム・ルシダムを持つのは猫だけではありません。
夜行性や薄明性の動物には、同様の構造を持つものが多く存在します。
- イヌ・キツネ:猫と同様に黄緑~青に反射
- シカ・ウシ:金色に輝くタペタム
- イルカ・サメ:海中でも光を有効利用するため発達
一方で、人間やブタ、鳥類などにはタペタムがなく、暗闇ではほとんど見えません。
つまり、「目が光るかどうか」は生態と生活環境に合わせた進化の違いなのです。
まとめ:猫の“光る目”は夜のハンターの証
猫の目が夜に光るのは、
- 網膜の裏にあるタペタム・ルシダムが光を反射しているから
- 縦長の瞳孔で光量を自在にコントロールしているから
- これらが夜行性としての生存戦略になっているから
という理由によるものです。
つまり、あのミステリアスな光は――
猫が夜の世界を生き抜くために手に入れた、“闇を味方につける瞳”の証なのです。