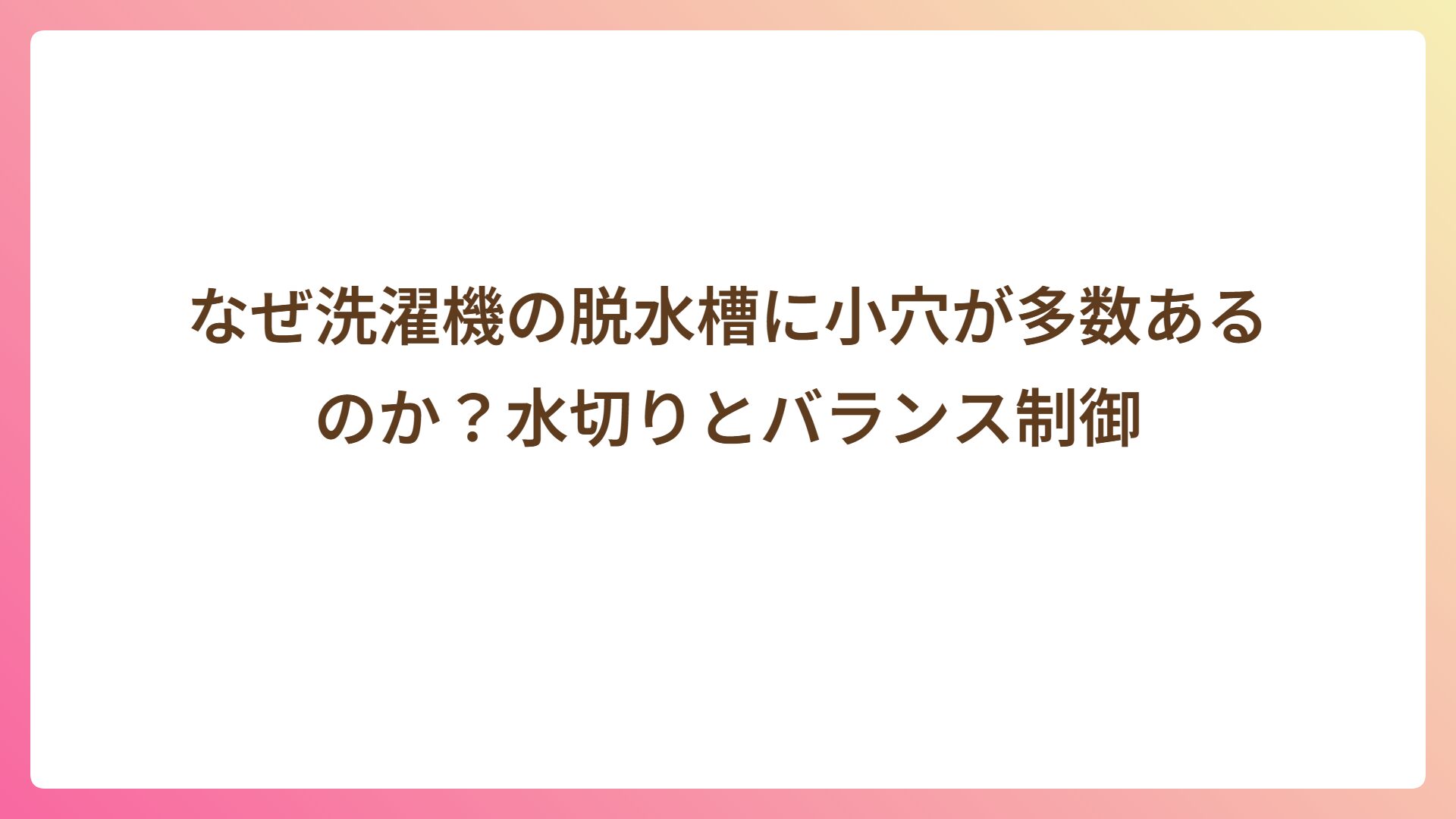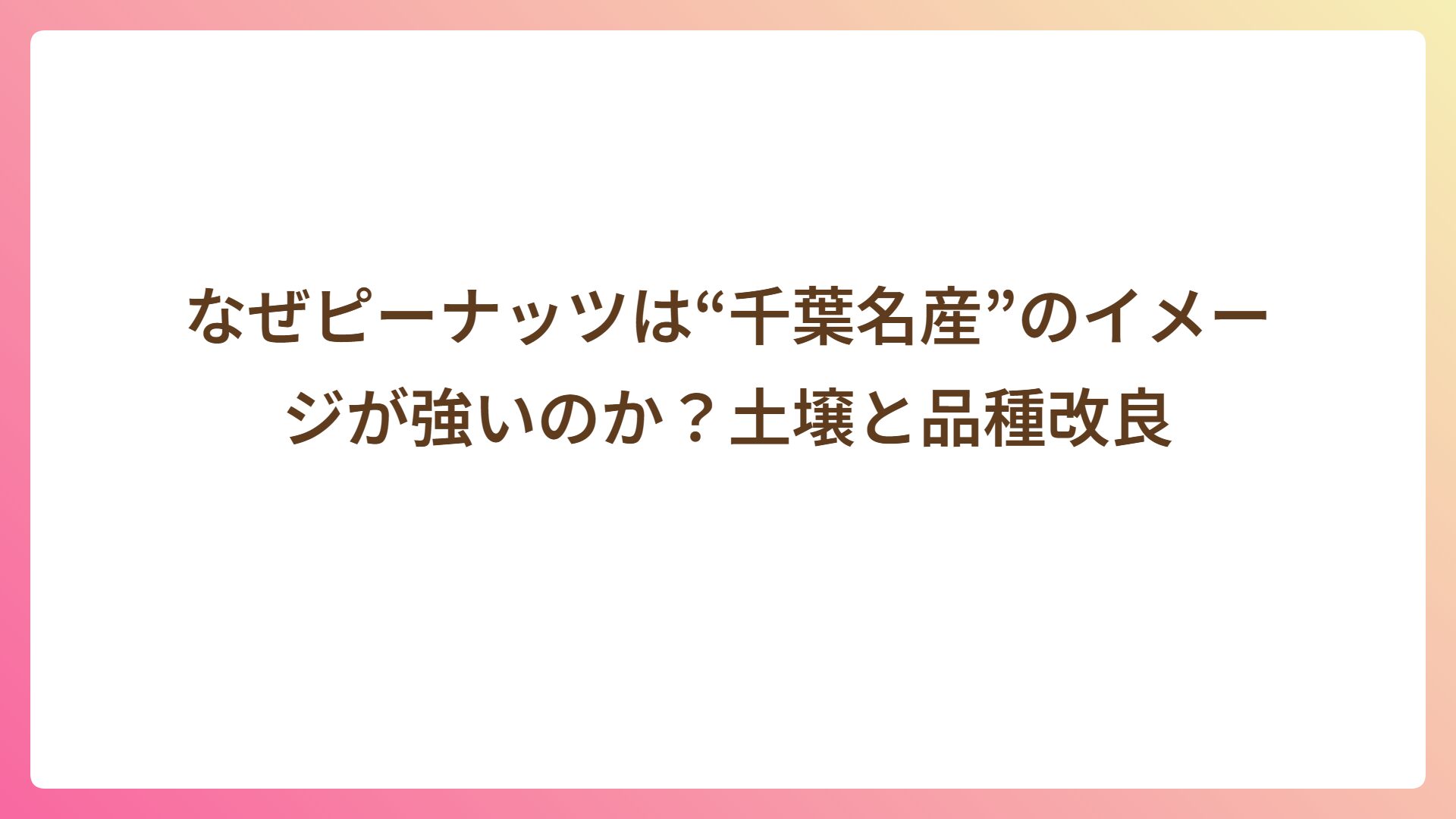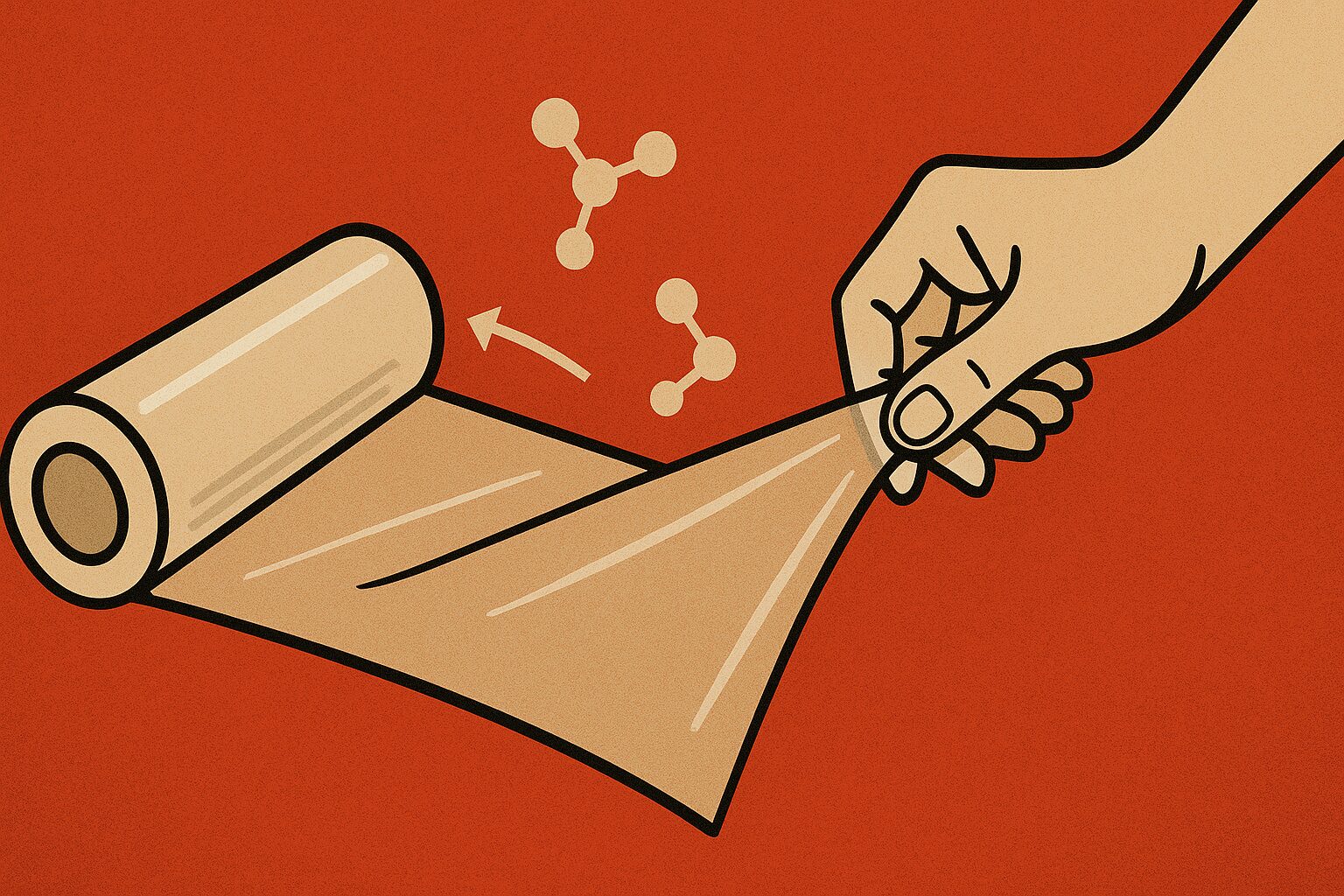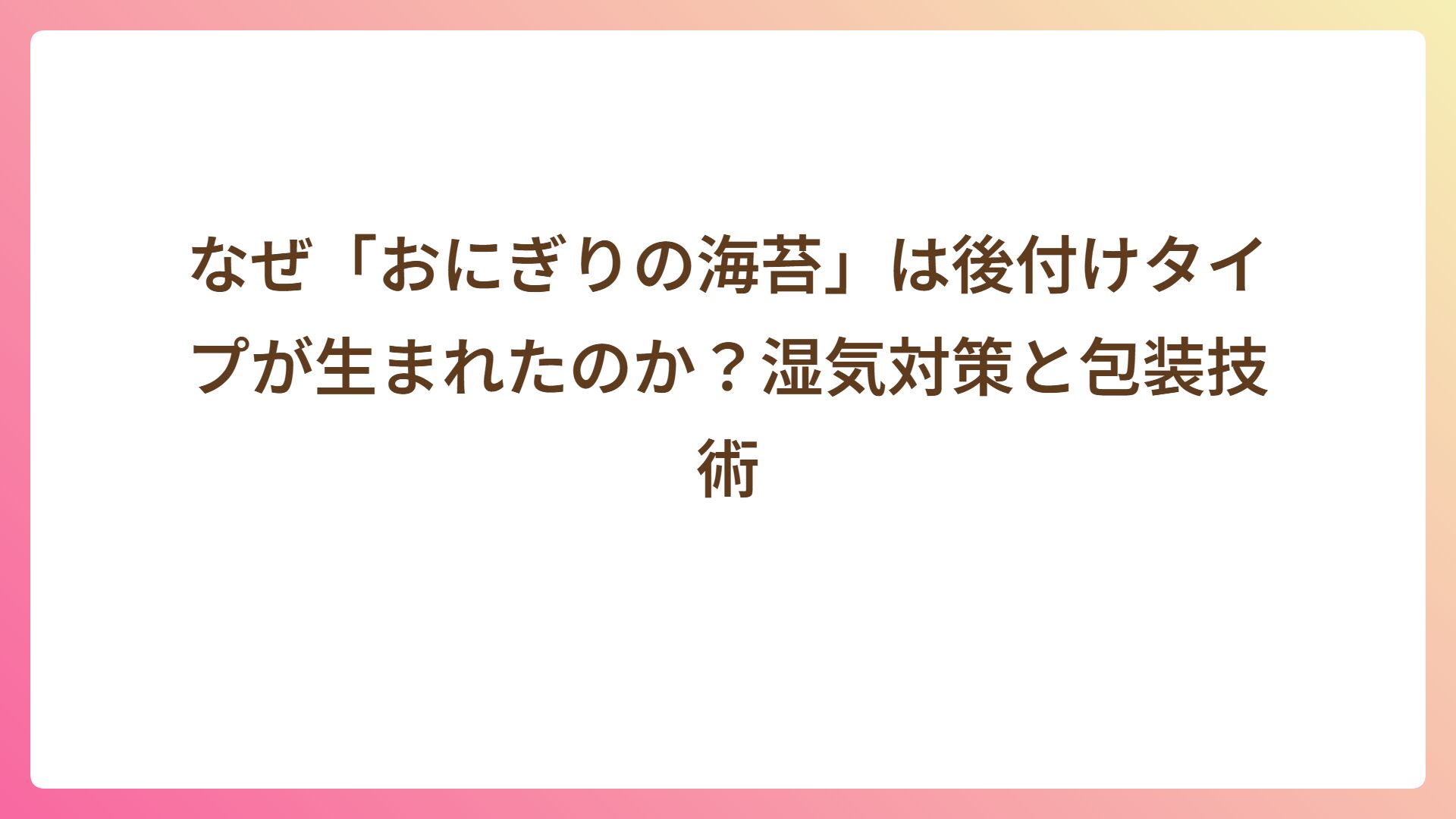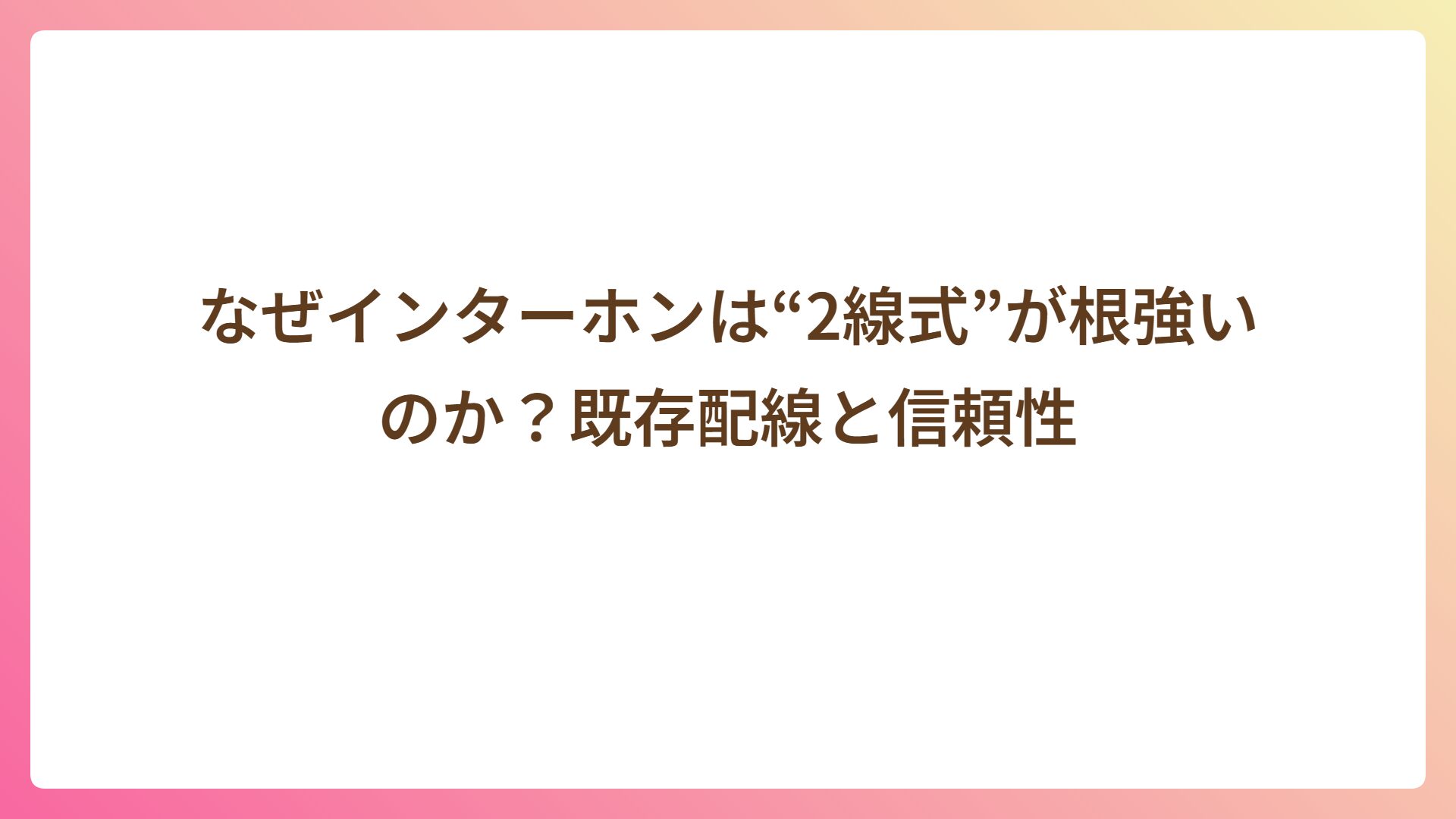なぜ信号機は縦型と横型があるのか?積雪・風・道路条件で変わる設置理由
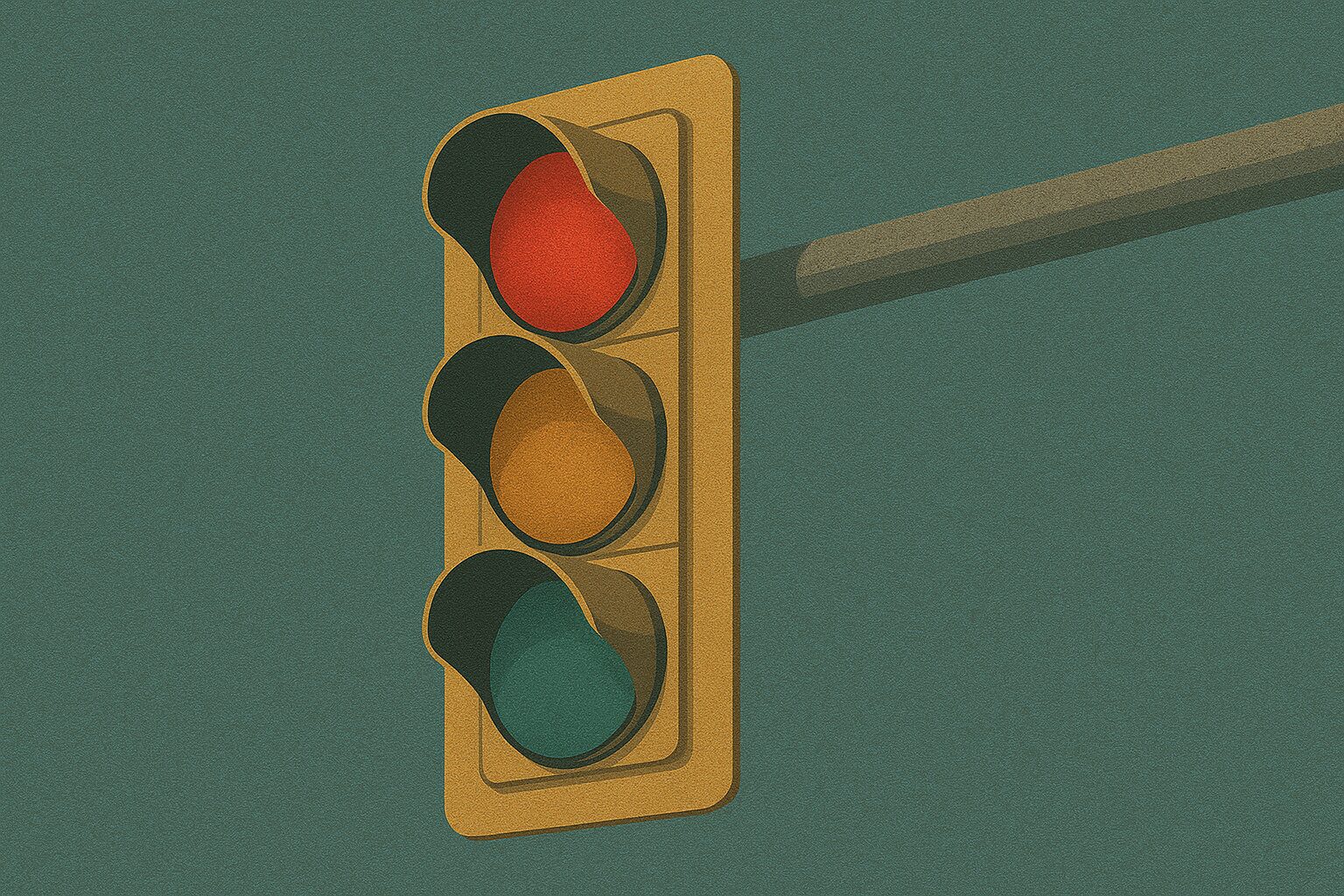
道路を走っていると、地域によって「縦に並んだ信号」と「横に並んだ信号」があることに気づく人も多いでしょう。
北海道では縦型が多く、東京や大阪などでは横型が主流です。
この違いは、単なるデザインではなく、その土地の気候や道路事情に合わせた合理的な理由によるものです。
積雪対策:雪が積もらないように「縦型」が採用される
最も分かりやすい理由が、積雪への対応です。
北海道や東北地方など、冬に大雪が降る地域では、
信号機の上に雪が積もるとランプが見えにくくなるという問題が発生します。
横型だとランプの上に雪が乗りやすいため、
除雪しなければ信号の光が遮られてしまうことも。
そこで、雪が滑り落ちやすい縦型信号が採用されているのです。
縦型なら、雪が自然に下に落ちてくれるため、
視認性を保ちつつメンテナンスの手間も減らせます。
強風・台風地域では「風の抵抗」を考慮
一方、海沿いや台風の通り道にあたる地域では、風への強さが重要になります。
信号機は高い位置に設置されるため、強風を受けやすい構造です。
横型は面積が広く、風を正面から受けやすい一方で、
縦型は側面積が小さいため風の抵抗を減らせるという利点があります。
特に日本海側や台風常襲地帯では、耐風性を考慮して縦型を採用するケースが多いのです。
都市部では「横型」が主流──見やすさと設置スペースの問題
逆に、関東・関西の都市部では横型信号が一般的です。
これは、都市部の交差点では建物や標識、看板が多く、
縦型だと背景に埋もれて見づらくなるためです。
また、道路の上に設置するアーム部分(門型支柱)の強度上、
複数車線の上に横長で配置した方が見やすく、均等に視界に入るという利点もあります。
さらに、狭い歩道や電柱に取り付ける場合、
縦型では高さが出すぎてしまうこともあるため、
都市部ではスペース効率を優先した横型設計が適しているのです。
見やすさの工夫:縦でも横でも「上が赤・下が青」は共通
縦型と横型でランプの並び方は違いますが、色の順番は全国共通です。
- 縦型:上から赤 → 黄 → 青
- 横型:右から赤 → 黄 → 青
どちらも運転者が「赤=進入禁止」「青=進行可」をすぐ判断できるよう、
視線の流れに合わせた配置になっています。
一見バラバラに見えても、認知心理に基づいた統一ルールがあるのです。
その他の要因:設置コストや自治体の慣習
信号機の設置には、支柱の構造・風圧計算・配線工事など多くの要素が関係します。
そのため、同じ県内でも自治体によって縦型・横型が混在することもあります。
たとえば、
- 雪国でも市街地では横型(デザインや電線配置の都合)
- 都市でも坂道や強風地域では縦型(安全優先)
といったように、環境+地形+運用コストのバランスで決まるのです。
まとめ:信号機の形は“地域の気候を映すデザイン”
信号機が縦型か横型かは、
- 雪が積もる地域では「縦型」
- 都市部や広い交差点では「横型」
- 強風地域では「風に強い縦型」
というように、土地の特性に最適化された設計です。
つまり、信号機の形を見れば、その地域の気候・地形・安全思想までも垣間見えるのです。