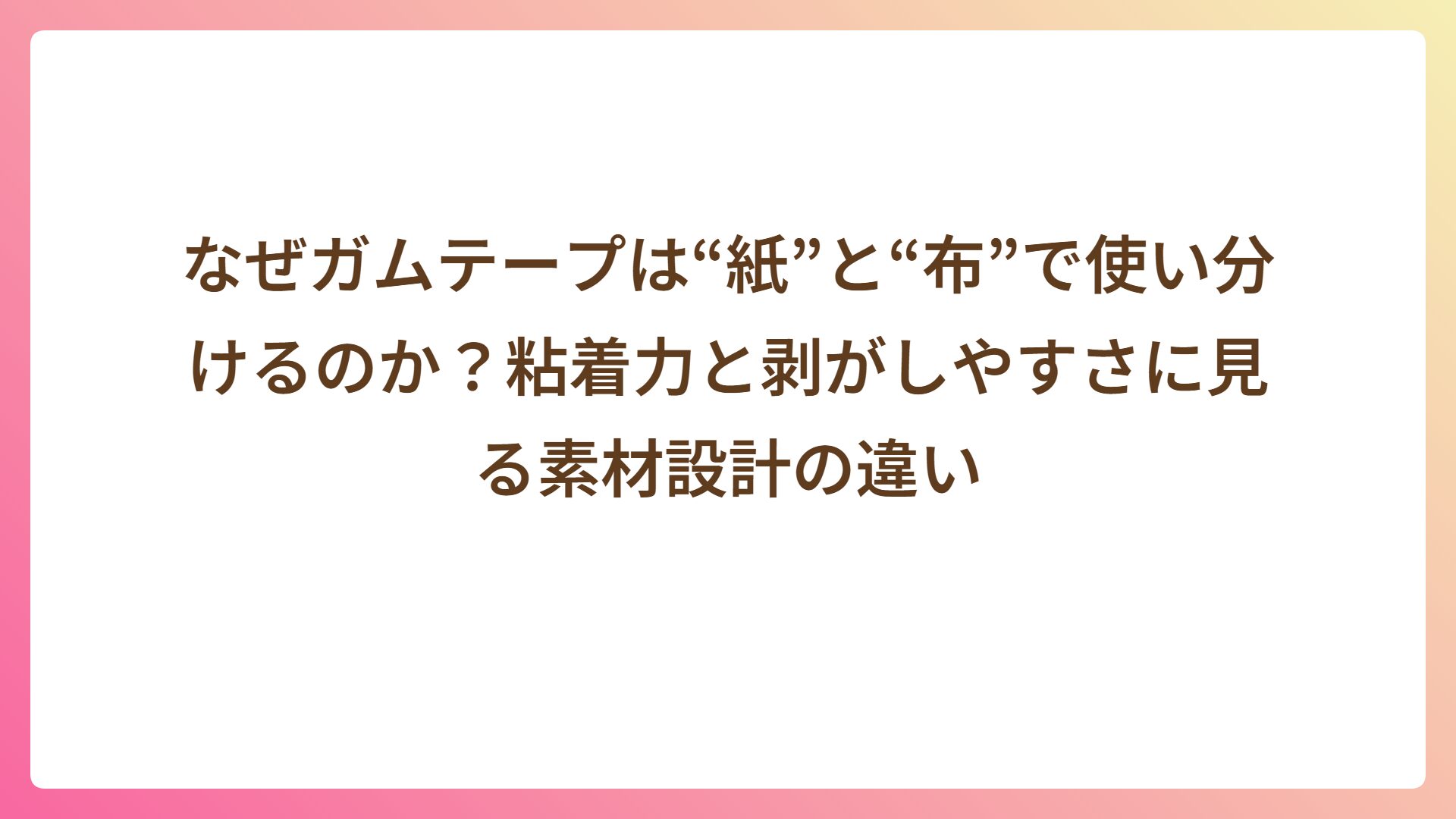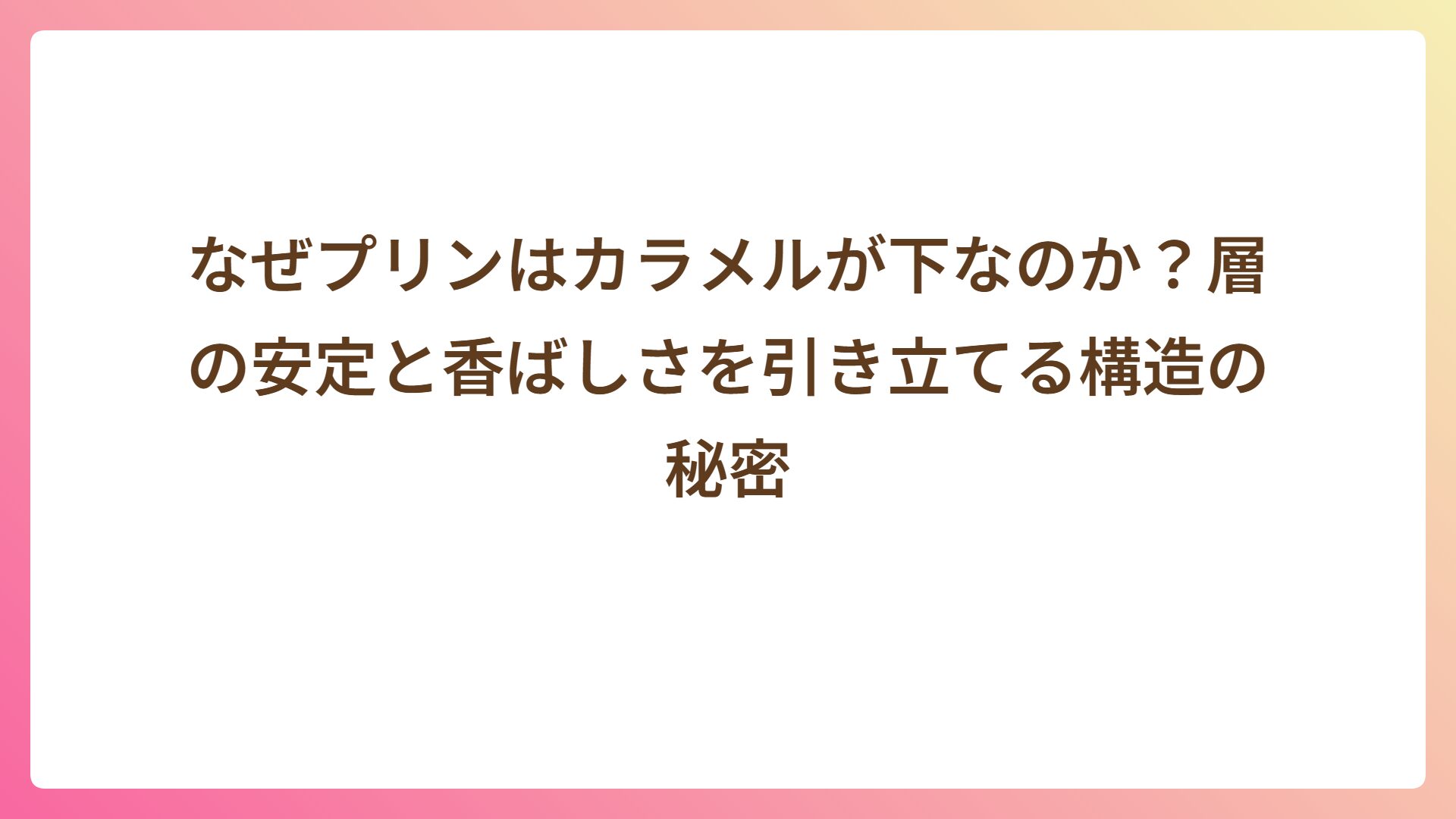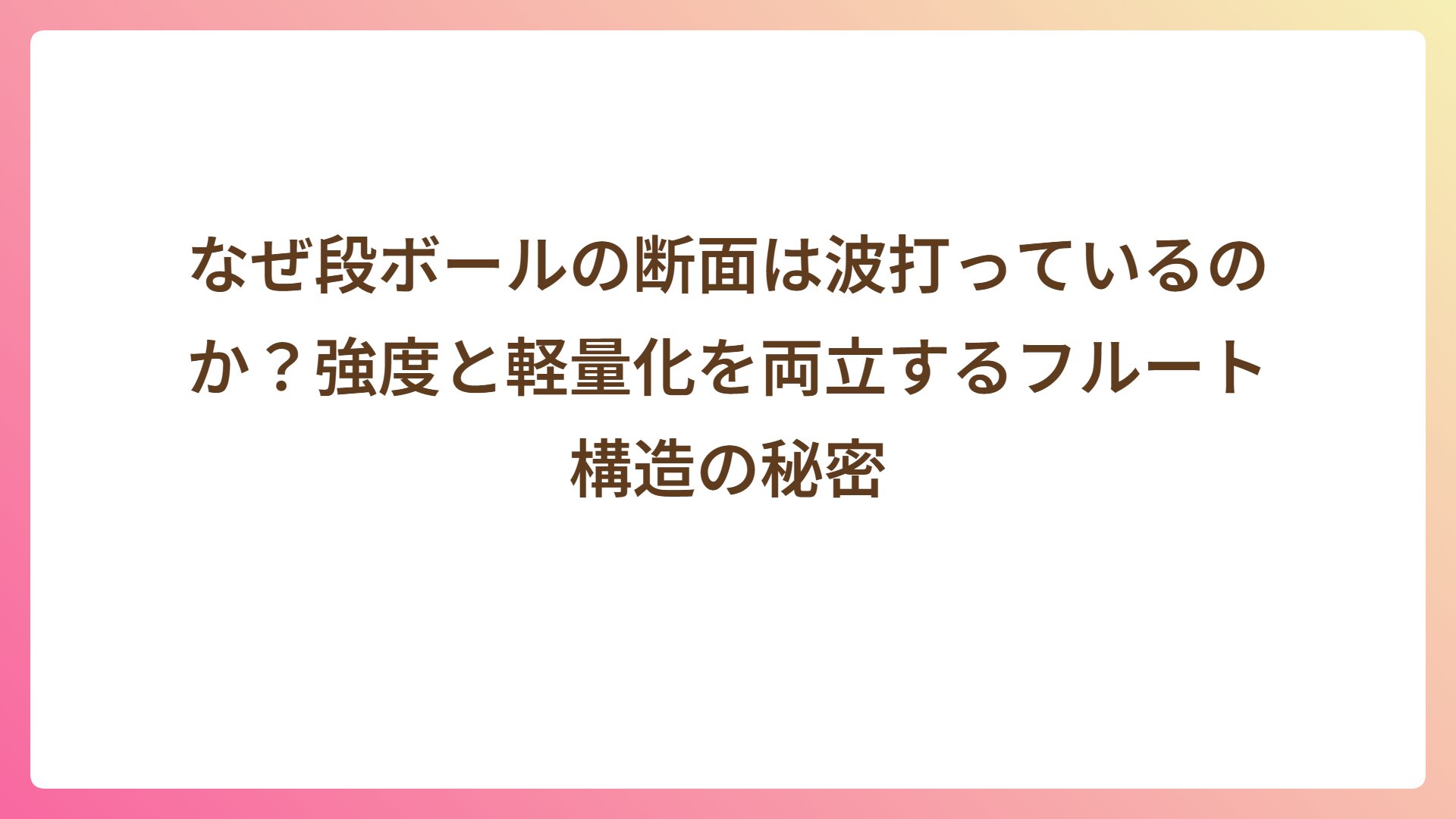なぜ紙の本は“右開き”と“左開き”があるのか?言語と組版が決めたページ方向の違い
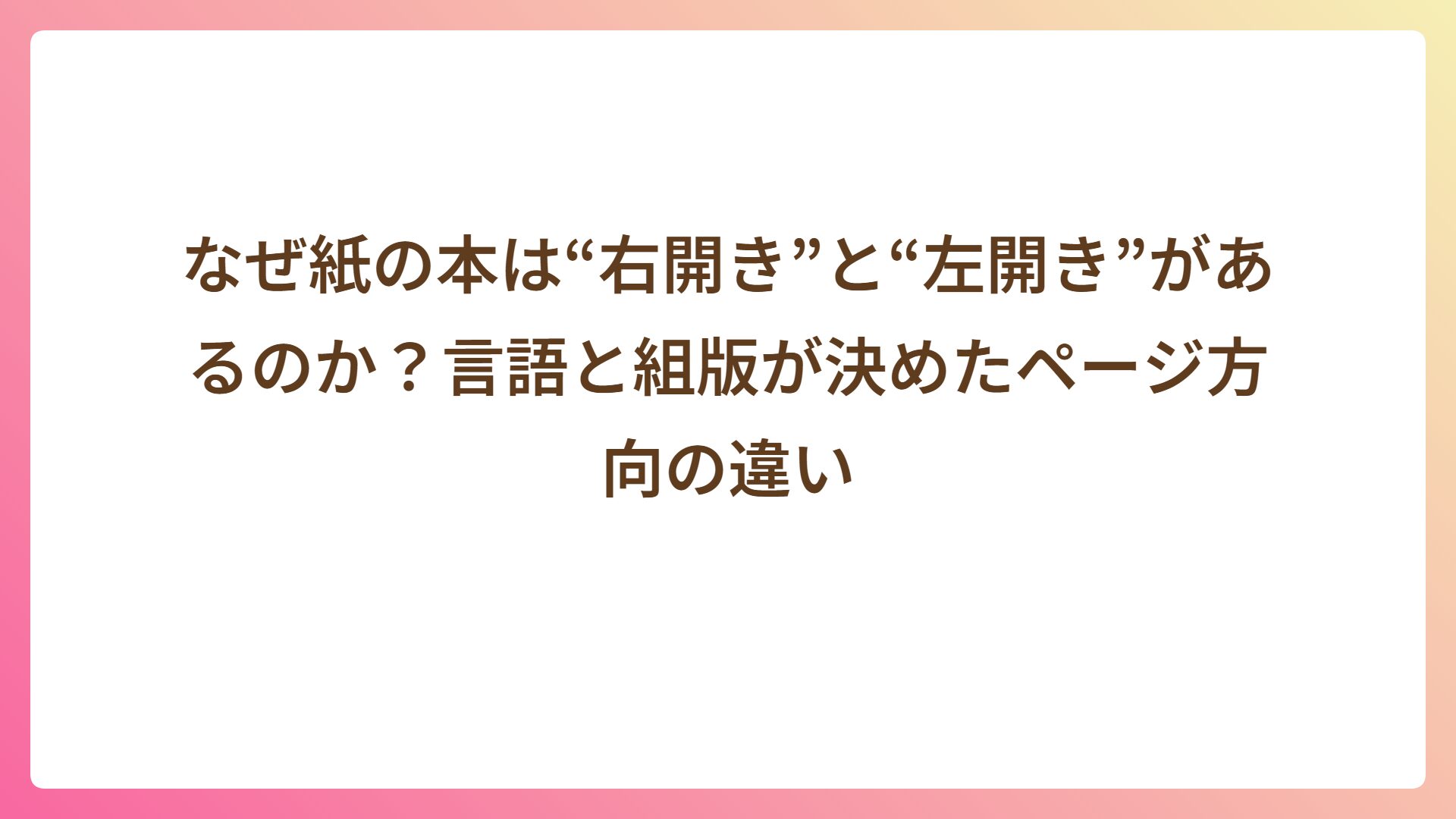
書店で本を手に取ると、
日本の小説や漫画は「右開き」、
英語の洋書や理系の教科書は「左開き」。
同じ「本」なのに、なぜ開く向きが違うのでしょうか?
その理由は、言語の書き方と印刷の歴史にあります。
「右開き」「左開き」は書字方向によって決まる
本の開く向きは、文字を読む方向によって決まります。
| 書字方向 | 主な言語 | 開く向き |
|---|---|---|
| 右から左へ(縦書き) | 日本語(文芸・新聞など) | 右開き |
| 左から右へ(横書き) | 英語・フランス語など欧文 | 左開き |
日本語の縦書きは「右から左」へ進むため、
1ページ目を右側に配置するのが自然です。
逆に横書き(左→右)では、左側から読む方が視線の流れに合います。
つまり、“どちら向きに読むか”が“どちら側から開くか”を決めているのです。
日本語には「縦書き」と「横書き」が共存している
日本語は世界でも珍しく、縦書きと横書きの両方が定着している言語です。
そのため、本や雑誌のジャンルによって開き方が異なります。
| 用途・ジャンル | 組版方向 | 開く向き |
|---|---|---|
| 文学・新聞・漫画 | 縦書き(右→左) | 右開き |
| 教科書・技術書・洋書 | 横書き(左→右) | 左開き |
| 雑誌・カタログ | 横書きが増加傾向 | 左開きが主流に |
たとえば漫画単行本は右開き、
理系参考書は左開き。
同じ出版社でも内容によってページ構成を切り替えるのが一般的です。
歴史的には「右開き」が先──巻物からの流れ
日本の書物文化の原点は、古代の巻物や和本(和綴じ本)。
これらは右から左へ読む構造で、当然「右開き」でした。
奈良・平安時代の経典や物語も縦書きで、
書写方向はすでに右→左。
その伝統が江戸時代の木版印刷や和綴じに受け継がれ、
「日本語=右開き」の形式が定着しました。
一方、西洋ではギリシャ語・ラテン語・英語など、
すべて左→右で書く言語が主流だったため、
本は左開きで作るのが自然だったのです。
印刷技術の輸入で「左開き」も並行して普及
明治時代以降、西洋の印刷技術や活版組版が導入されると、
横書きや左開きの書物も登場しました。
特に理工系分野や語学書では、
欧文との併記が必要なため、横書きが主流に。
結果、戦後には「縦書き=右開き」「横書き=左開き」という
二系統の文化が共存することになりました。
デジタル時代でも「右開き文化」は残る
電子書籍やスマートフォンのリーダーアプリでも、
漫画や文芸作品は右からスワイプしてページをめくる仕様になっています。
これは紙の文化の名残であり、
読者の“めくる感覚”を再現するための設計です。
逆に、英語の電子書籍や学術PDFは左めくりが標準。
つまり、デジタルでもなお「書字方向=ページ方向」の原則は維持されているのです。
海外にも“右開き”の文化はある?
右開きの書物文化は日本だけではありません。
アラビア語、ヘブライ語、ペルシア語など、
右から左へ書く言語圏でも同様に右開きが採用されています。
つまり、これは“東洋的”というよりも、
書字方向に応じた自然なデザインの結果なのです。
まとめ:右開きと左開きは“読み方の文化の違い”
紙の本の開く向きが違うのは、
- 言語の書字方向(右→左 or 左→右)
- 印刷・製本の歴史的経緯
- 日本語の縦書き文化と横書き文化の共存
といった要素が重なった結果です。
つまり、右開き・左開きはどちらが正しいという話ではなく、
「読む方向」と「文化の流れ」が作った自然なルール」なのです。