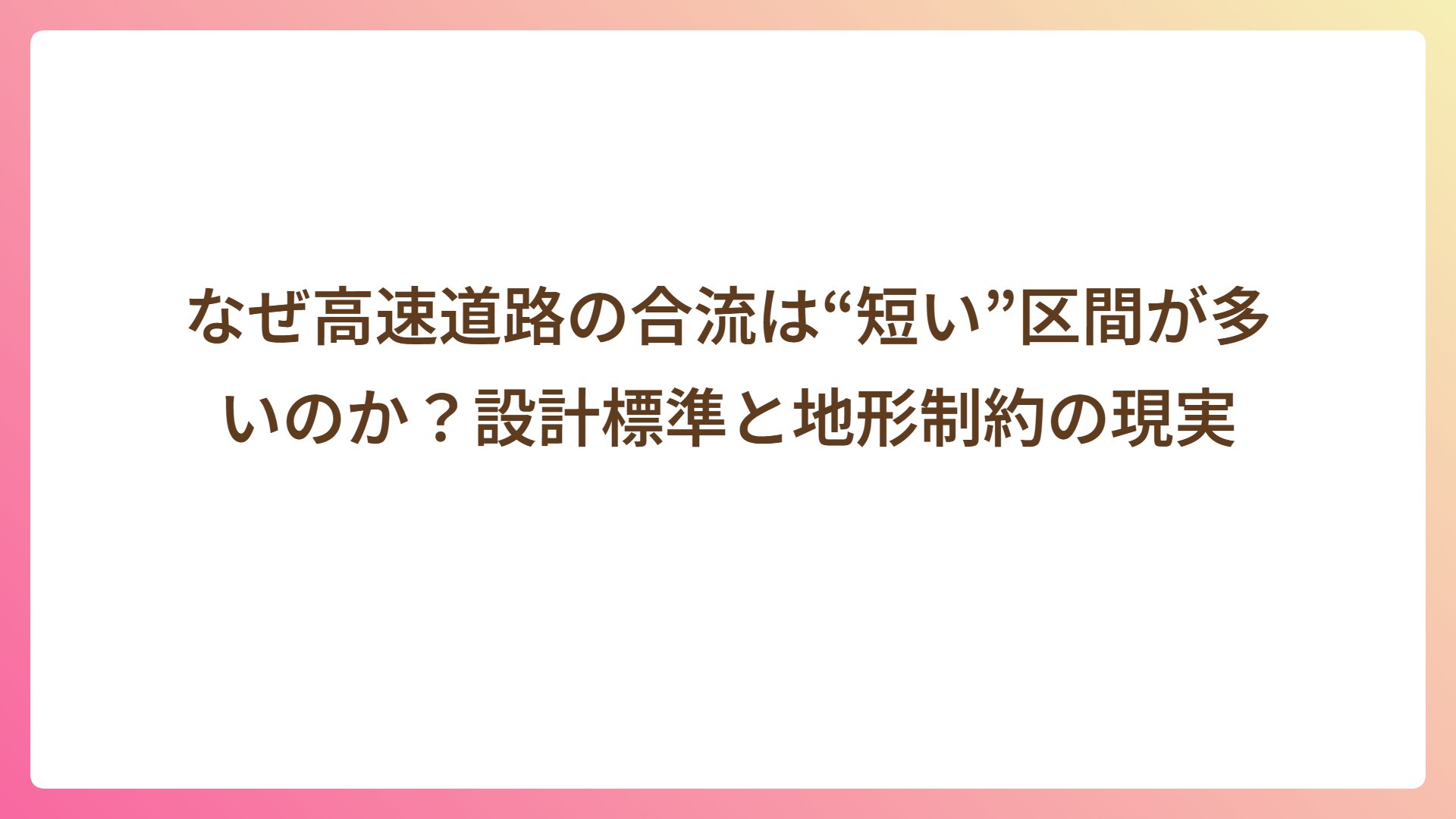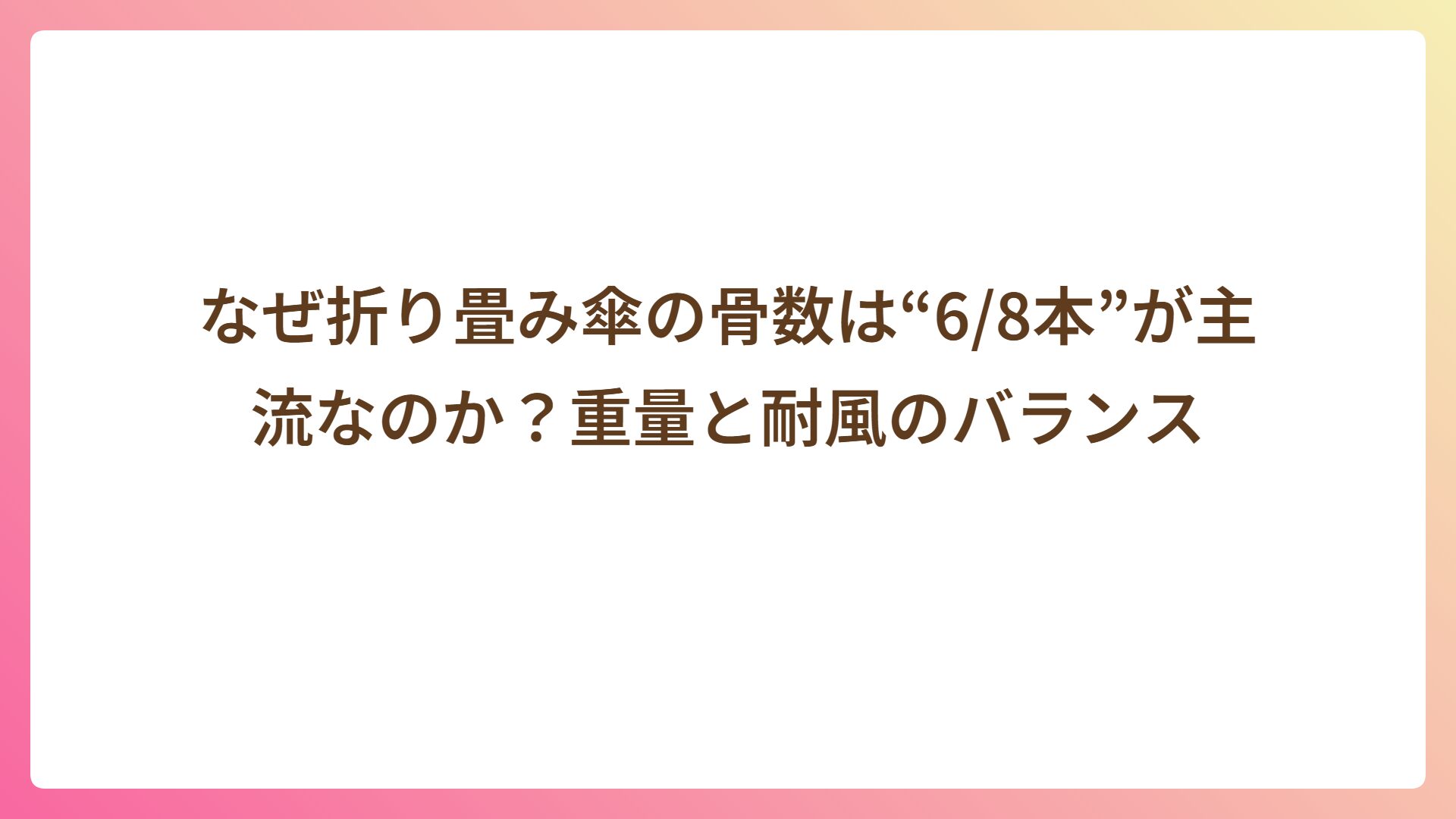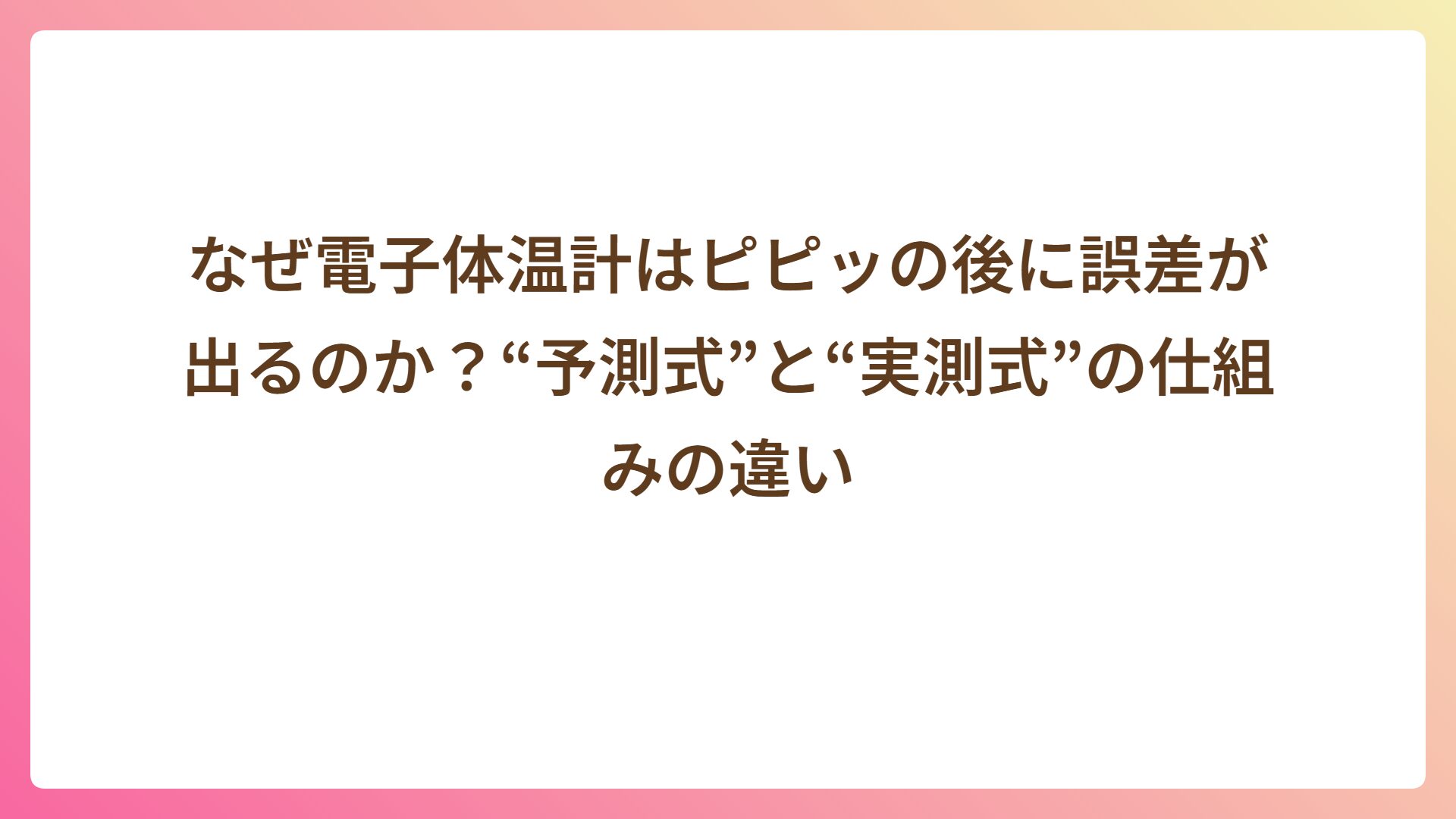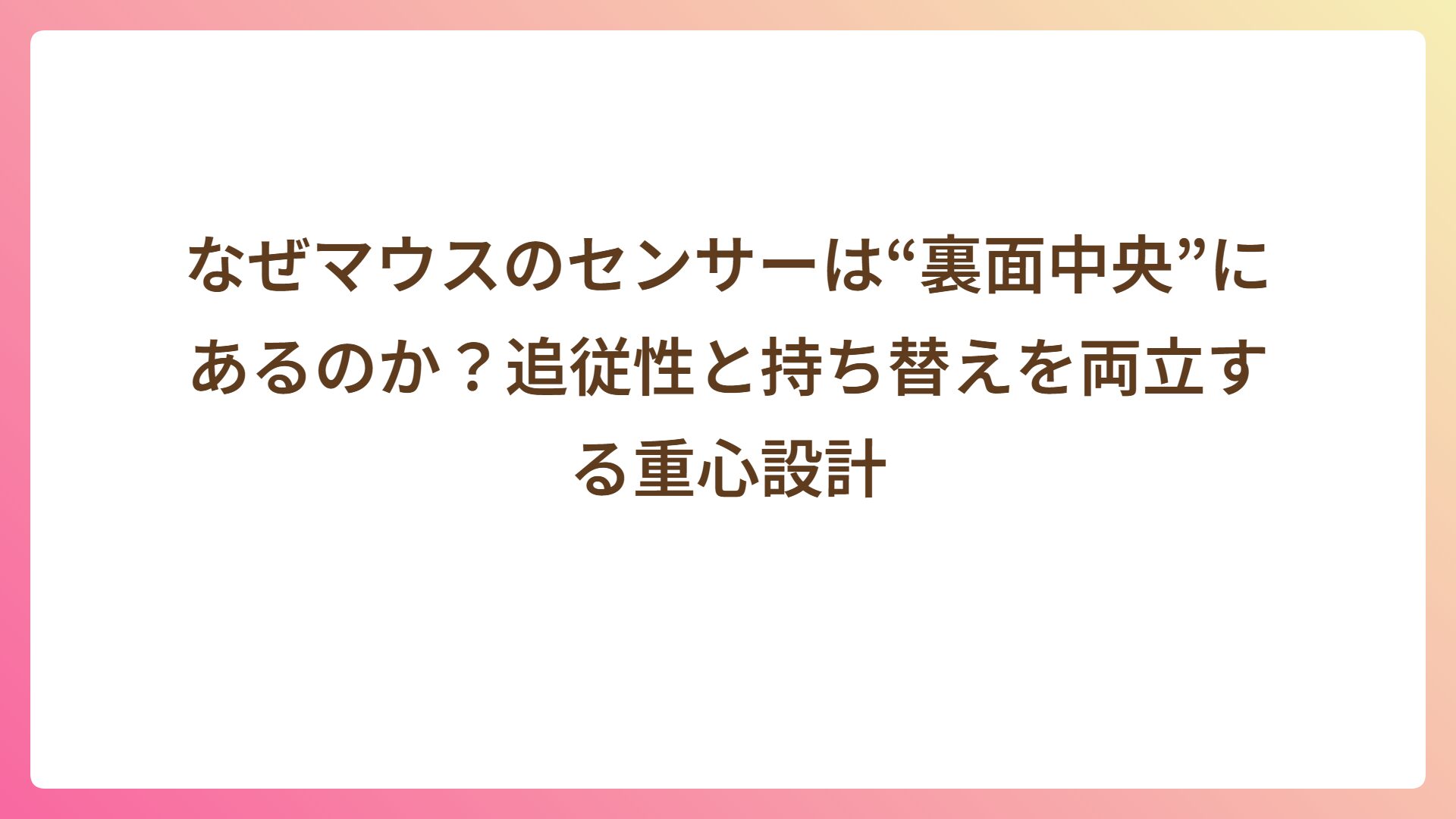なぜATMは一定額でしか硬貨を出せないのか?構造と機構に潜む制約の理由
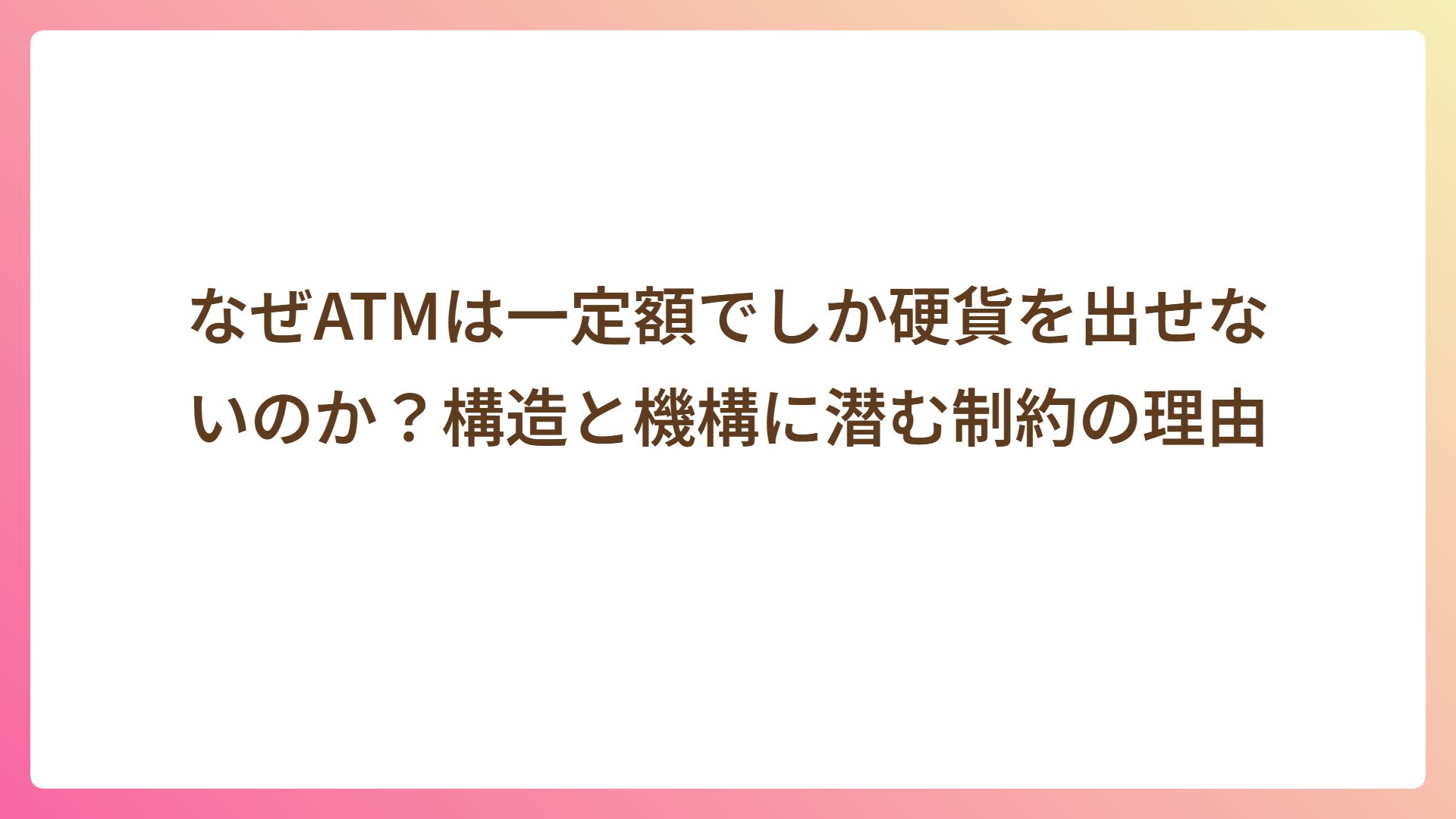
ATMでお金を引き出すとき、「千円単位」ではなく「硬貨で○○円も出せたらいいのに」と思ったことはありませんか?
実は、多くのATMは硬貨を一定単位でしか出せないか、そもそも硬貨を扱わないように設計されています。
その背景には、機械構造の制約と運用コストの問題があるのです。
紙幣と硬貨では“扱い方”がまったく違う
紙幣は薄く軽いため、ATM内部では吸引・搬送ローラーで1枚ずつ取り出すことができます。
一方で硬貨は金属製で重く、形も硬さも異なるため、紙幣とは全く別のメカニズムが必要になります。
硬貨を扱うATMには「硬貨ユニット」と呼ばれる専用の機構があり、
1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉のそれぞれを**別のホッパー(貯蔵部)**に保管します。
このユニットが
- 正しい枚数を検知
- 枚数分を一定速度で排出
- 残量をカウントし再補充
といった処理を行うため、構造が複雑で壊れやすいのです。
硬貨は“詰まりやすく”“摩耗しやすい”
硬貨ユニットの最大の弱点は、詰まりやすさと摩耗です。
特に、長年使われた硬貨は汚れや傷で厚さや縁の摩耗にばらつきがあり、
搬送レーンで引っかかることがあります。
また、複数の種類を同時に扱うとセンサーの誤検知が起きやすく、
たとえば「100円玉のはずが10円が混ざる」といったトラブルが発生します。
そのため、金融機関の多くは
「硬貨を扱うと機械の保守コストが急増する」
という理由で、硬貨対応ATMを最小限に限定しているのです。
“一定額単位”しか出せないのは構造上の都合
硬貨対応ATMが「100円単位」「500円単位」などの制限を設けているのは、
排出単位を固定しないと誤動作しやすいためです。
例えば、
- 100円×7枚
- 10円×3枚+50円×2枚 など
毎回異なる組み合わせを出すには、
複数のホッパーがミリ秒単位で連携して動作する必要があります。
これを正確に行うには高度な制御が必要で、
少しでもタイミングがずれると硬貨が重なったり弾かれたりして排出エラーが起きてしまいます。
結果として、ATMメーカーは
「確実に取り出せる固定単位(例:100円刻み)」
を採用しているのです。
“入金”はできても“出金”は難しい理由
多くのATMでは、硬貨の入金は可能ですが、出金は制限付きです。
これは入金が「まとめて回収してカウントするだけ」なのに対し、
出金では「枚数を数え、指定通りに1枚ずつ出す」必要があるため。
入金は多少誤差があっても機械内で集計できる一方、
出金は1枚でも間違うとトラブルになるため、
精密な仕分けと搬送精度が求められるのです。
メンテナンスコストが高すぎる
硬貨ユニットは紙幣ユニットに比べて
- 重量があり、機械全体が大型化する
- 定期清掃・潤滑・補充の手間が多い
- 故障時に出張修理が必要になる
といった課題を抱えています。
実際、ATMを製造するメーカー(富士通・日立・OKIなど)では、
「硬貨対応モデルはメンテナンスコストが約2倍」と言われることもあります。
そのため、銀行では支店内専用や両替機能付き機種など、用途を限定して設置しているのです。
キャッシュレス化の影響も
近年は電子マネーやQR決済の普及により、
硬貨の流通量自体が減少傾向にあります。
このため、金融機関は硬貨対応ATMを減らす方向へ舵を切っており、
硬貨入出金を行いたい場合は「窓口」または「店舗限定機」へ誘導する形になっています。
まとめ:硬貨を自由に出せないのは“機械的に難しいから”
ATMが一定額でしか硬貨を出せないのは、
- 各硬貨を仕分け・搬送する構造が複雑
- 詰まりや摩耗などのトラブルが多い
- 複数ホッパーを同時制御するのが困難
- メンテナンスコストが高い
という機構的・運用的な制約によるものです。
つまり、硬貨出金が制限されているのは「銀行の都合」ではなく、
現状の機械技術と運用コストのバランスの結果なのです。