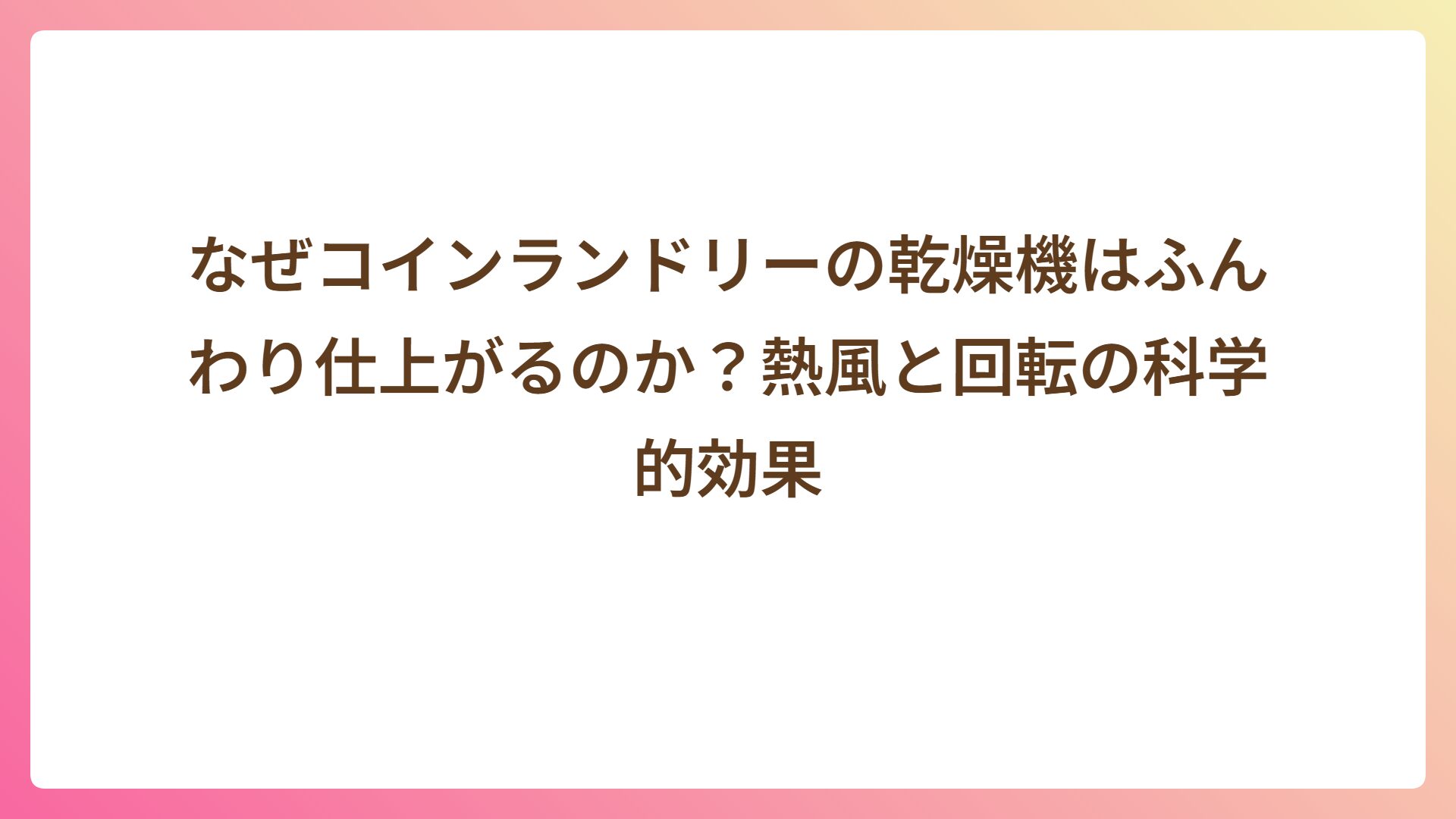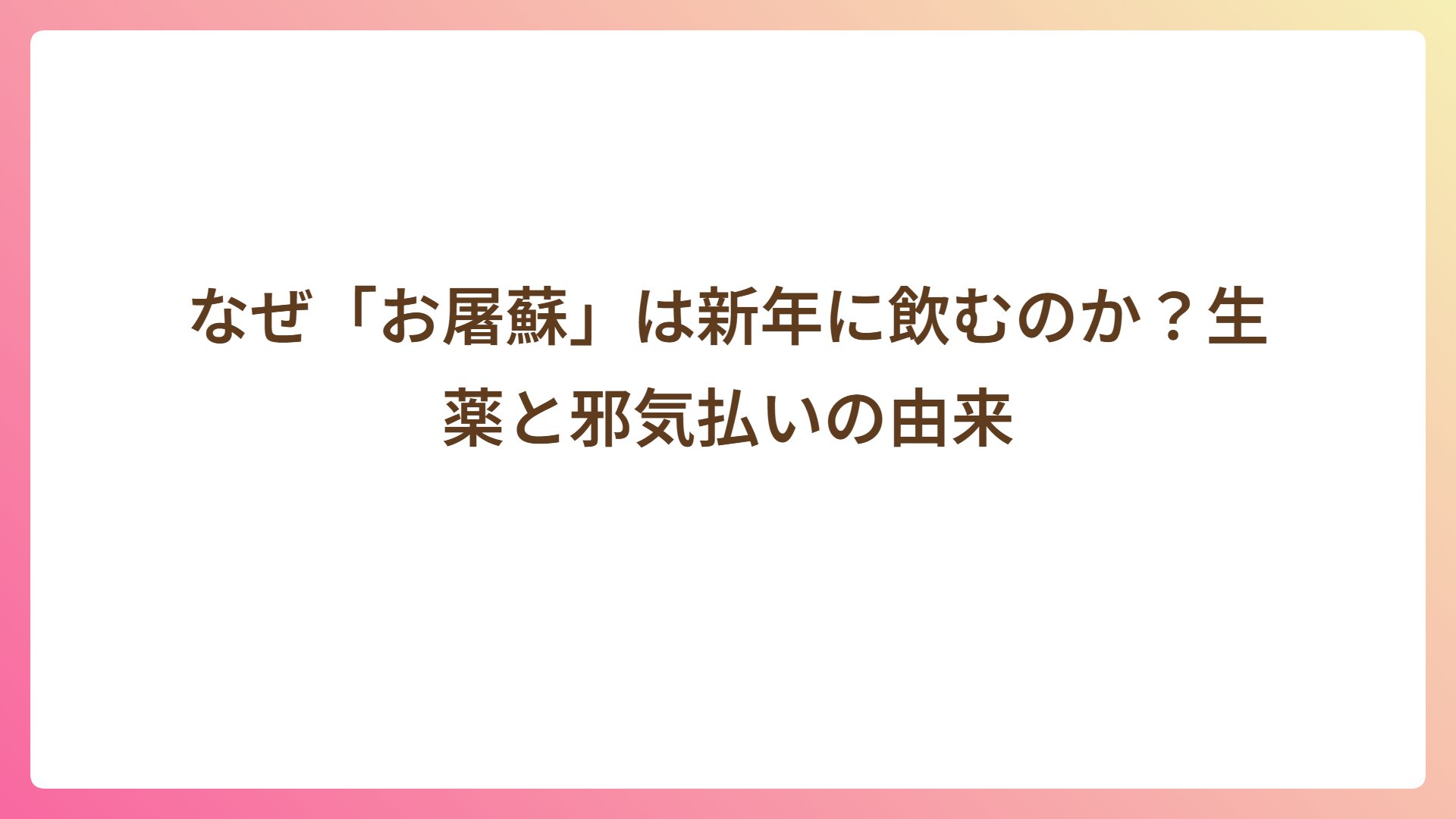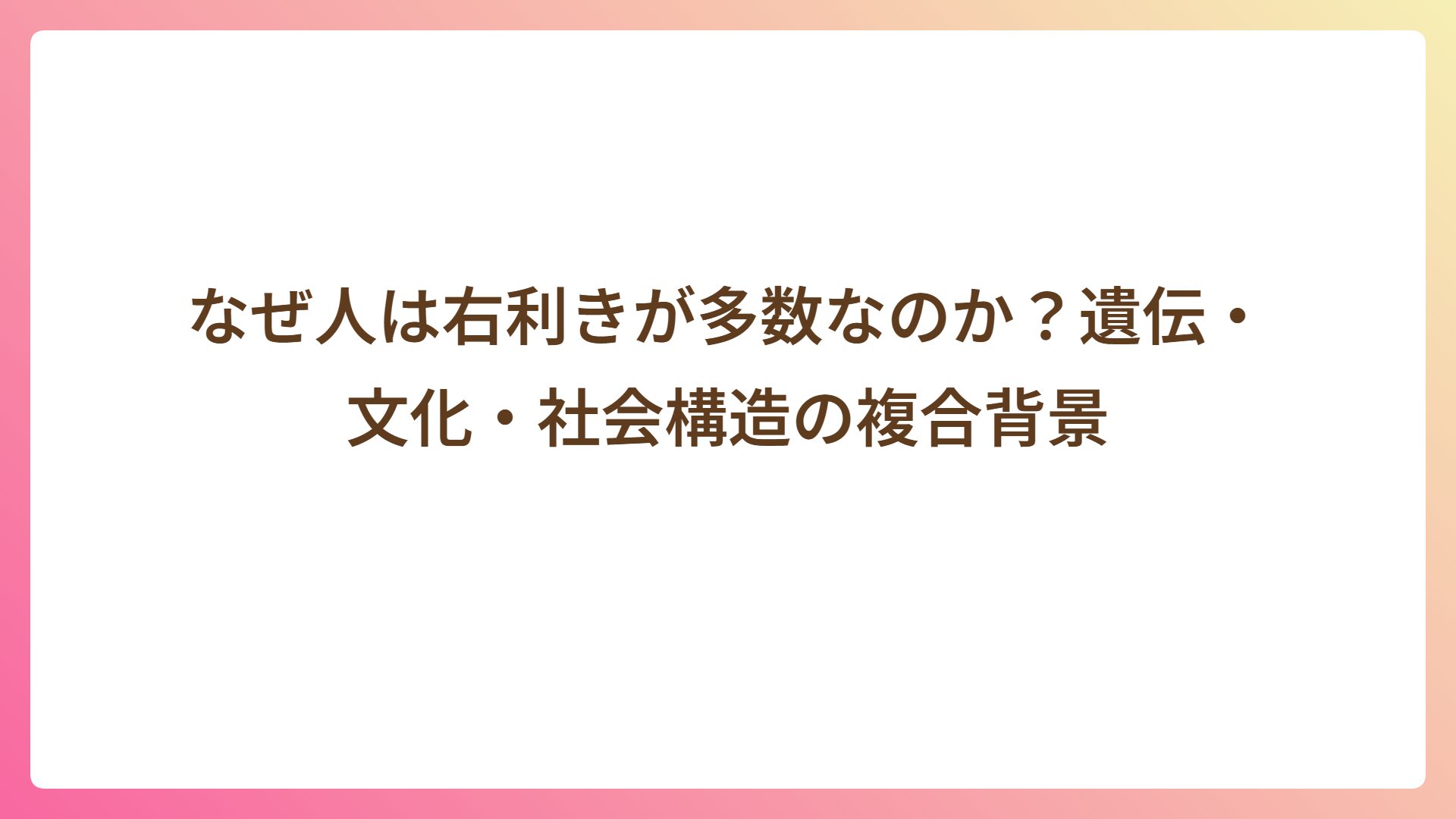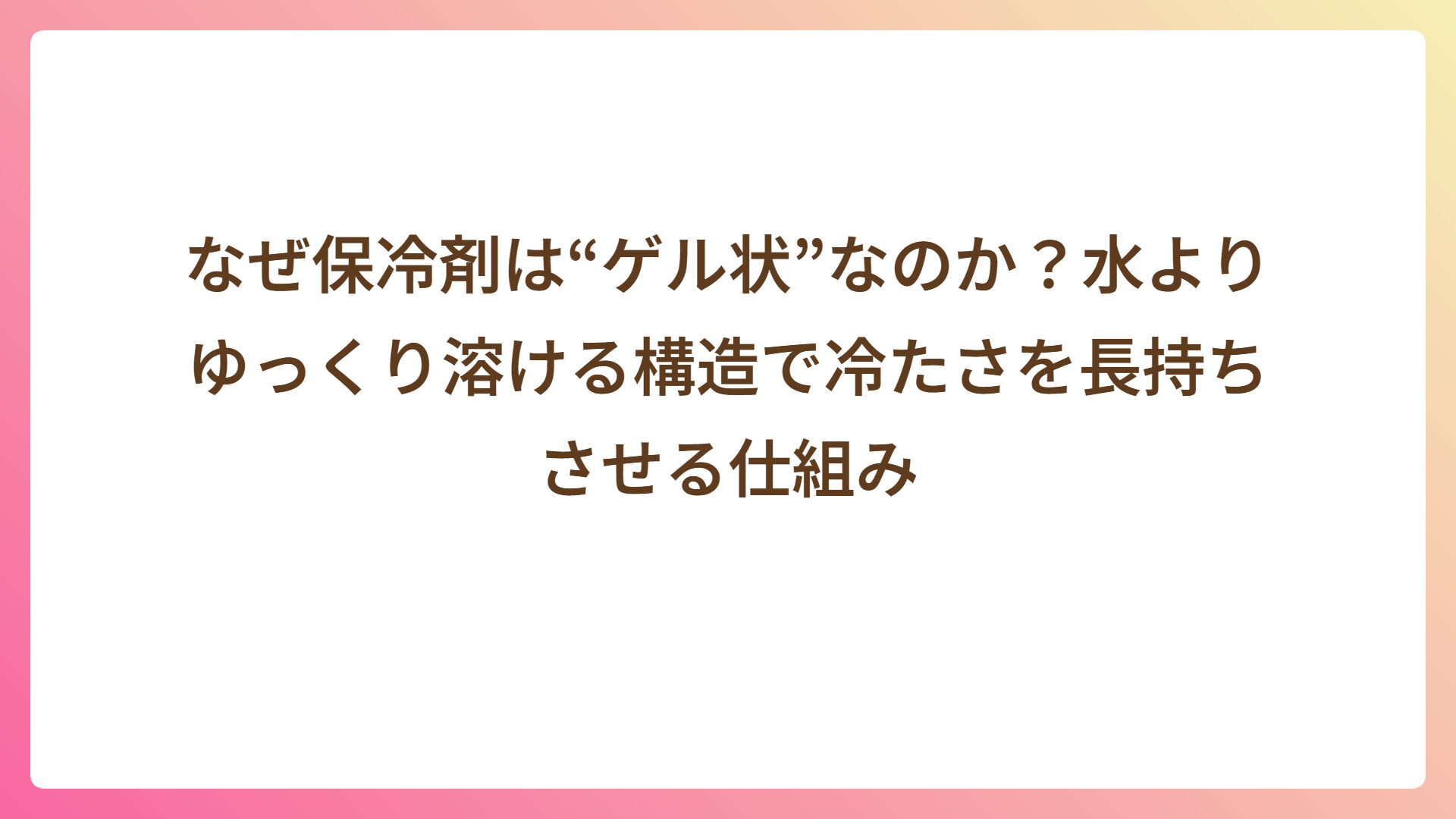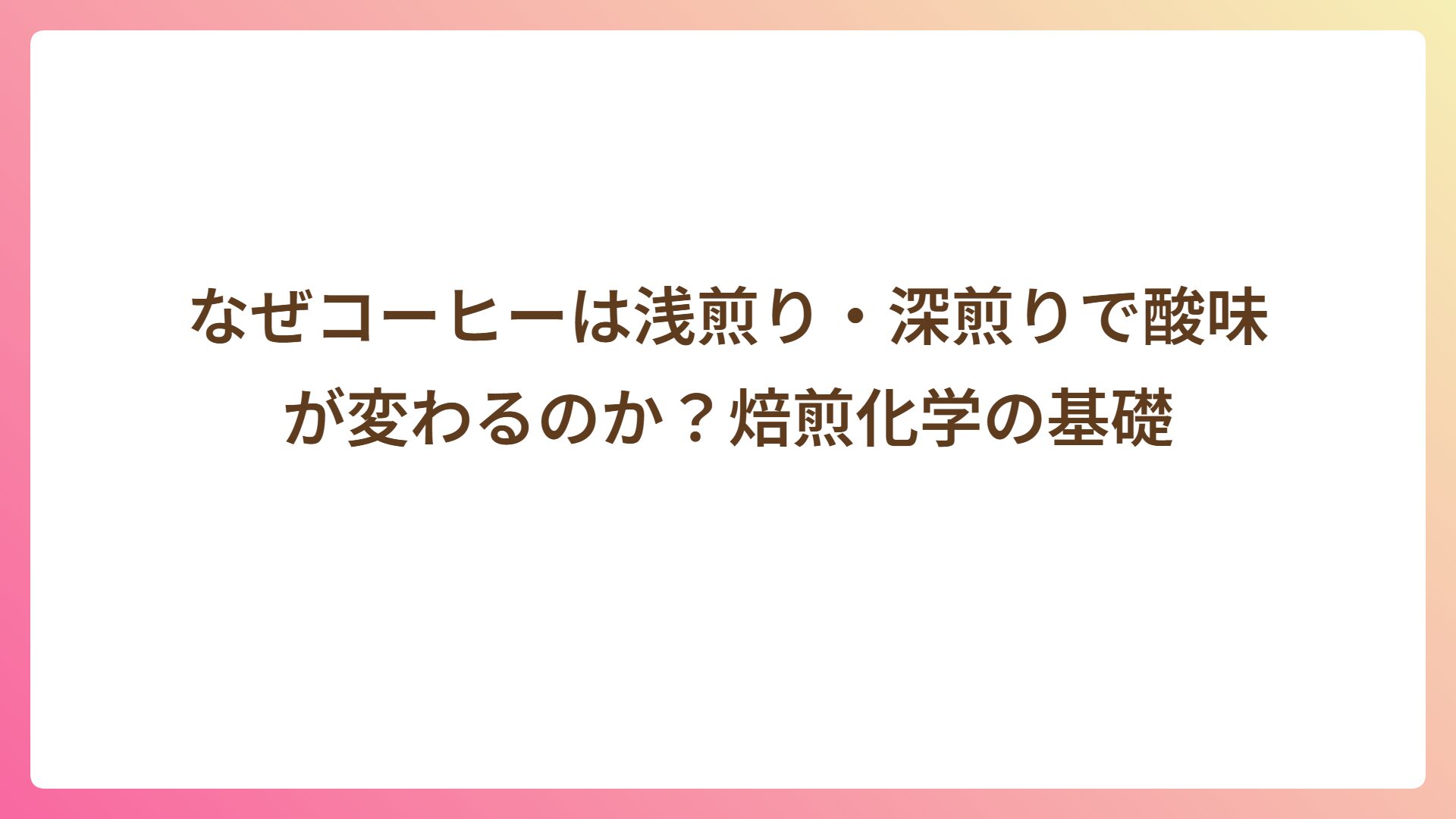なぜWi-Fiの電波は壁で弱くなるのか?周波数と減衰の科学的メカニズム
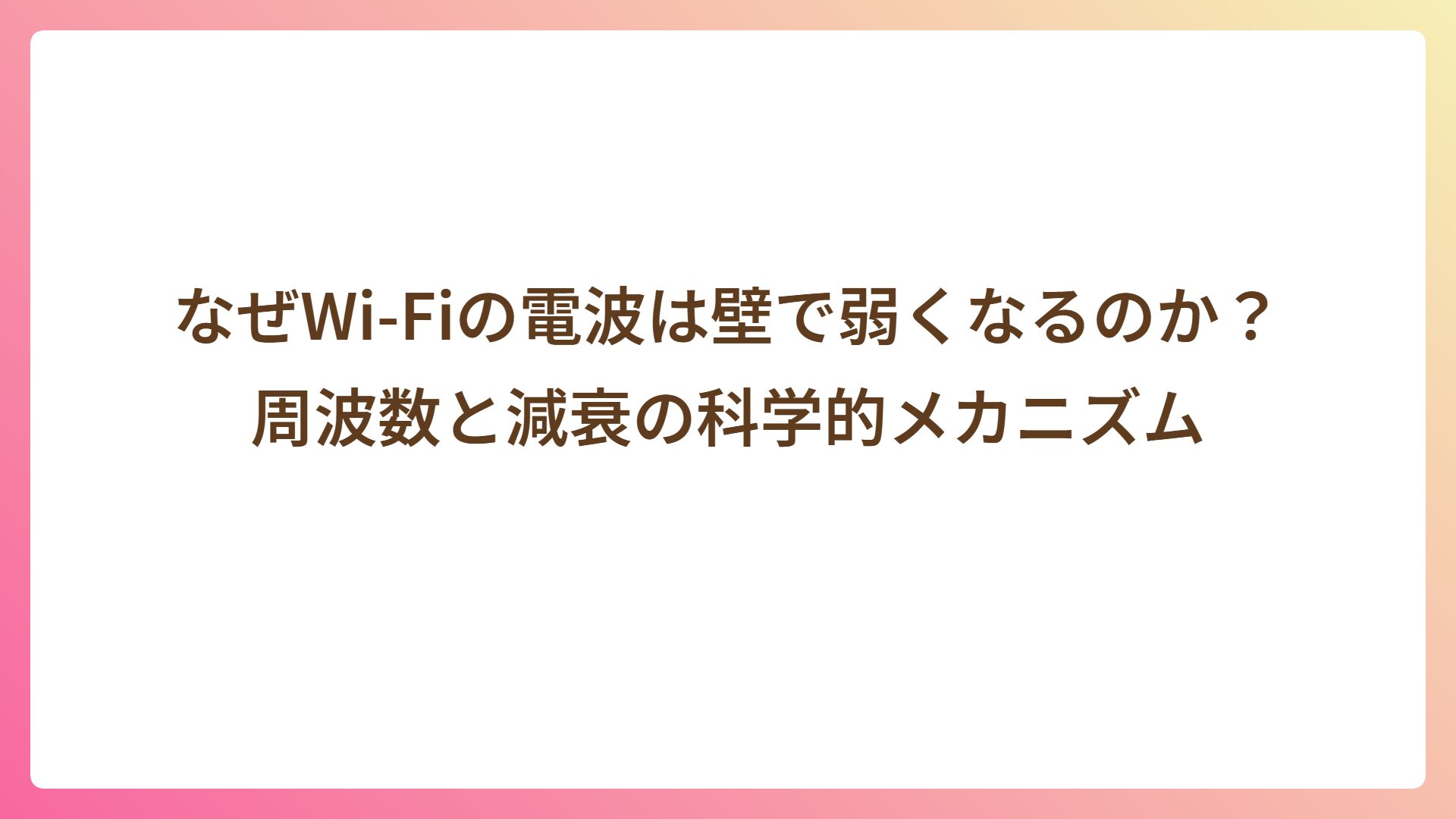
「隣の部屋に行くとWi-Fiが途切れる」「鉄筋の壁で電波が届かない」──そんな経験は誰しもあるでしょう。
無線LAN(Wi-Fi)は便利ですが、障害物に弱いという特徴があります。なぜ壁を挟むだけで、これほど電波が減衰してしまうのでしょうか?この記事では、周波数と減衰の物理的メカニズムからWi-Fiが壁で弱くなる理由を詳しく解説します。
Wi-Fi電波の正体:2.4GHzと5GHzの電磁波
まず前提として、Wi-Fiの電波は「電磁波」の一種です。
無線LANでは主に2.4GHz帯と5GHz帯という2種類の周波数が使われています。
- 2.4GHz帯:波長が長く、障害物を回り込みやすい
- 5GHz帯:通信速度は速いが、壁などで減衰しやすい
つまり、周波数が高い(=波長が短い)ほど直進性が強くなり、障害物を避けにくくなるのです。
このため、5GHzのWi-Fiは「速いけれど届きにくい」という性質を持っています。
壁で電波が弱くなる物理的な理由
Wi-Fi電波が壁で弱くなる主な原因は、吸収・反射・散乱の3つです。
- 吸収(Absorption)
壁の内部にある分子や水分が電波のエネルギーを吸収してしまいます。特にコンクリートやレンガは水分を多く含み、電波を通しにくい素材です。 - 反射(Reflection)
電波が金属や鉄筋などの表面に当たると、跳ね返ってしまいます。反射によって電波が届かない「影」になる領域が発生します。 - 散乱(Scattering)
壁の内部に不均一な構造(鉄骨・配線など)があると、電波がランダムに方向を変えます。その結果、強度が分散し、通信品質が低下します。
これらの要素が重なることで、壁を通過するたびに電波強度が大きく減衰するのです。
材質による電波減衰の違い
壁といっても、素材によって電波の通りやすさは大きく異なります。
代表的な建材の透過性を比較すると次のようになります。
| 壁の材質 | 電波の通りやすさ | 特徴 |
|---|---|---|
| 木材・石膏ボード | ◎ 通りやすい | 一戸建ての内壁など。吸収が少ない。 |
| コンクリート | △ やや通りにくい | 水分・密度が高く減衰が大きい。 |
| 鉄筋コンクリート | × 通りにくい | 鉄筋の反射でほぼ遮断される。 |
| 金属製の壁・ドア | ×× ほぼ通らない | 電磁波を反射して内部に届かない。 |
特に鉄筋コンクリート(RC構造)の建物では、Wi-Fiルーターの位置によって通信範囲が大きく変わります。
玄関近くにルーターを置くと、奥の部屋では電波がほぼ届かないケースも珍しくありません。
周波数による透過性の違い:2.4GHz vs 5GHz
Wi-Fiが2種類の周波数帯を使い分けているのは、速度と到達距離のトレードオフのためです。
| 周波数帯 | 波長 | 特徴 | 向いている環境 |
|---|---|---|---|
| 2.4GHz | 約12.5cm | 障害物に強く、遠くまで届く | 壁の多い家や広い部屋 |
| 5GHz | 約6cm | 高速通信だが減衰が大きい | ワンルームや見通しの良い空間 |
つまり、壁を越えて通信したい場合は2.4GHz帯を、速度重視なら5GHz帯を使うのが基本戦略です。
近年はメッシュWi-Fiなど複数ルーターで補完する仕組みも普及し、電波の死角を減らす工夫が進んでいます。
水分・人体も電波を弱める要因
Wi-Fi電波は水分を含むものに吸収されやすい性質を持っています。
人の体も約60%が水分で構成されているため、人が多い場所では電波が通りにくくなることがあります。
同様に、水槽・観葉植物・加湿器などもわずかに影響します。
「壁+人+家具」といった要素が重なることで、電波がさらに減衰し、通信が不安定になるケースも少なくありません。
まとめ:壁で弱くなるのは“物理法則どおり”
Wi-Fi電波が壁で弱くなるのは、
- 周波数が高く直進性が強いため回り込みにくい
- 壁の材質が電波を吸収・反射してしまう
- 水分や金属がエネルギーを奪う
といった物理的な減衰の仕組みによるものです。
つまり、「壁で電波が弱い」のは不具合ではなく、電磁波の性質上、当然の現象なのです。
Wi-Fiを安定させるには、壁の少ない場所にルーターを置くか、メッシュ中継機を活用するのが効果的です。