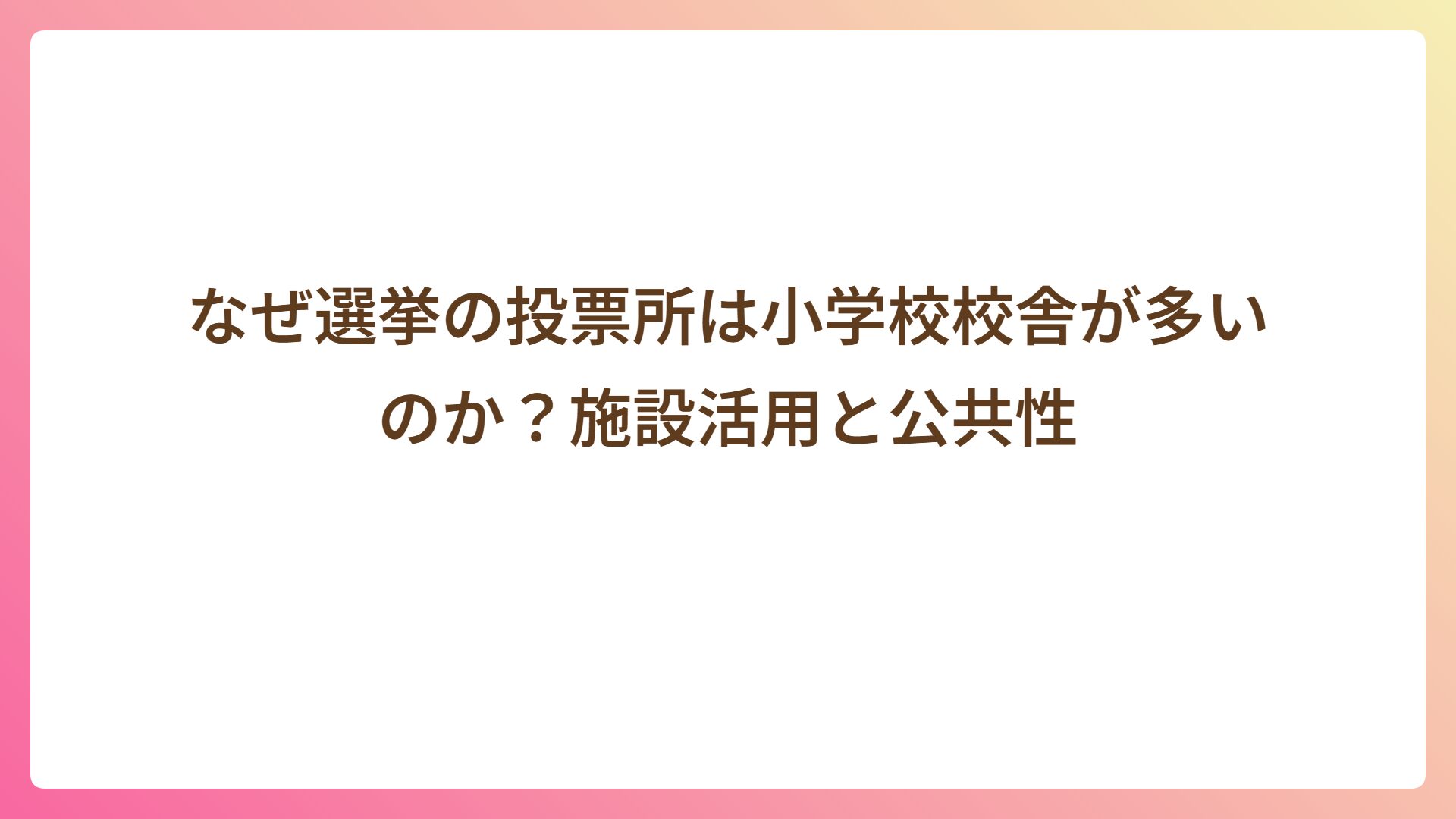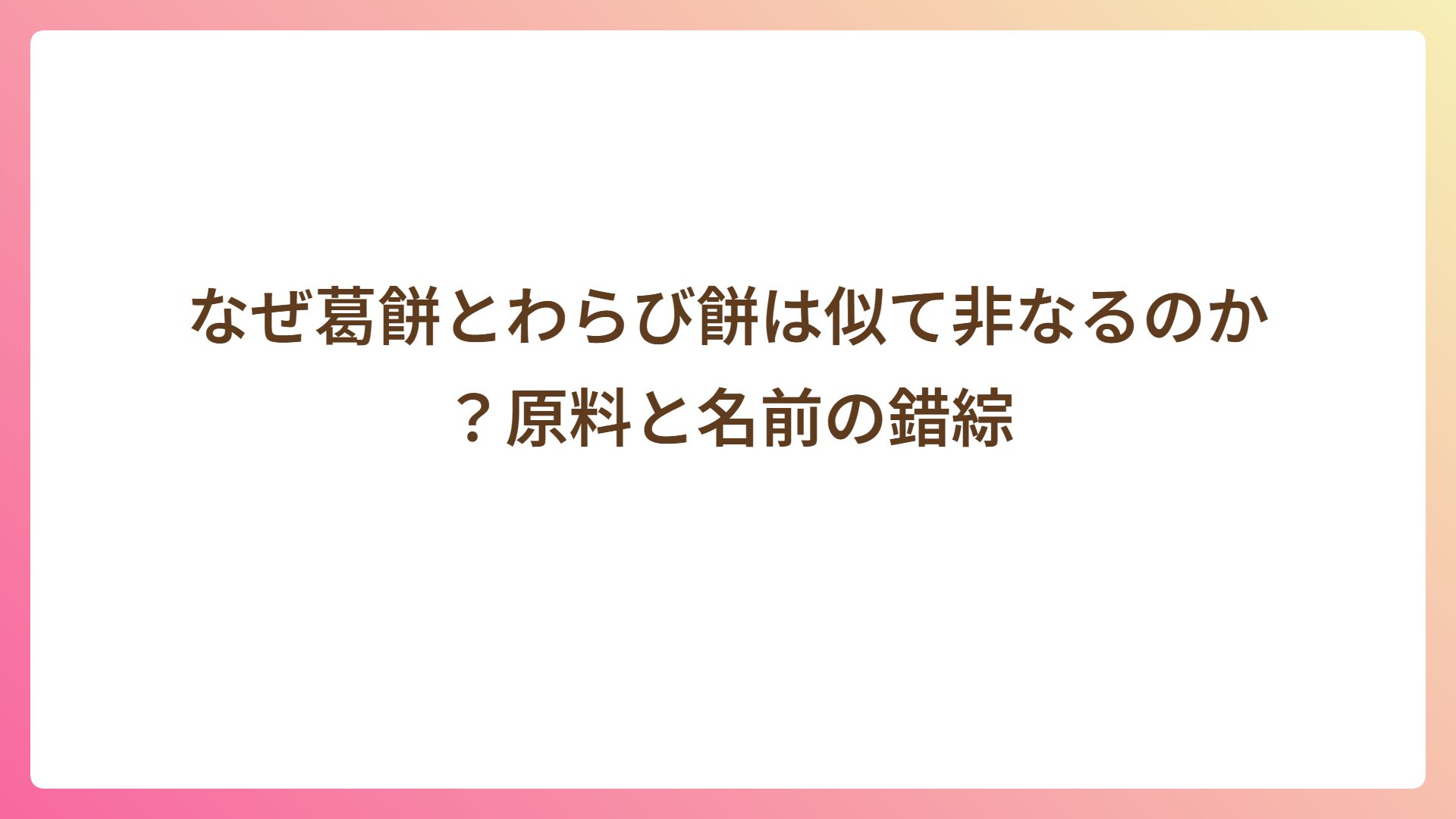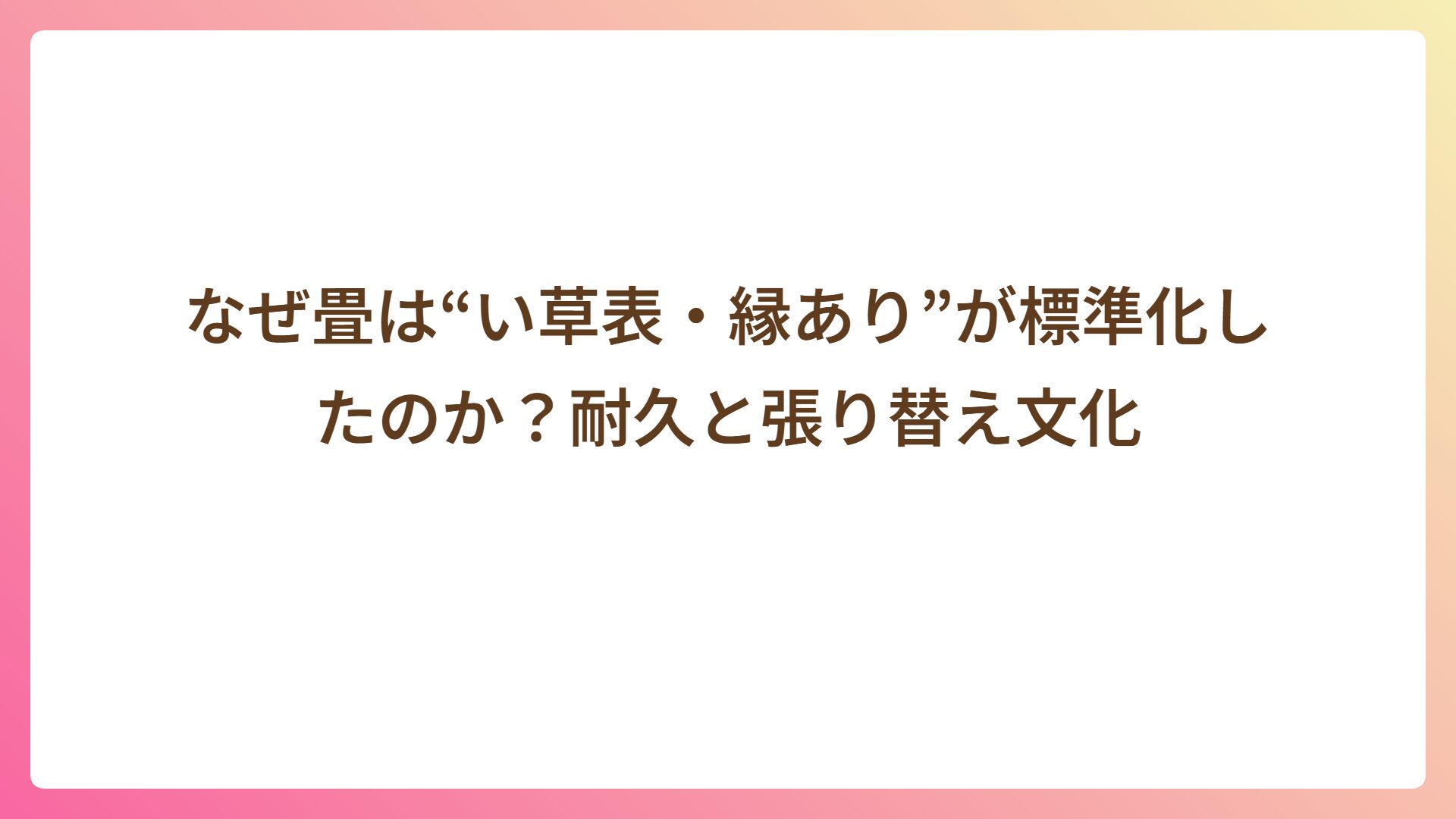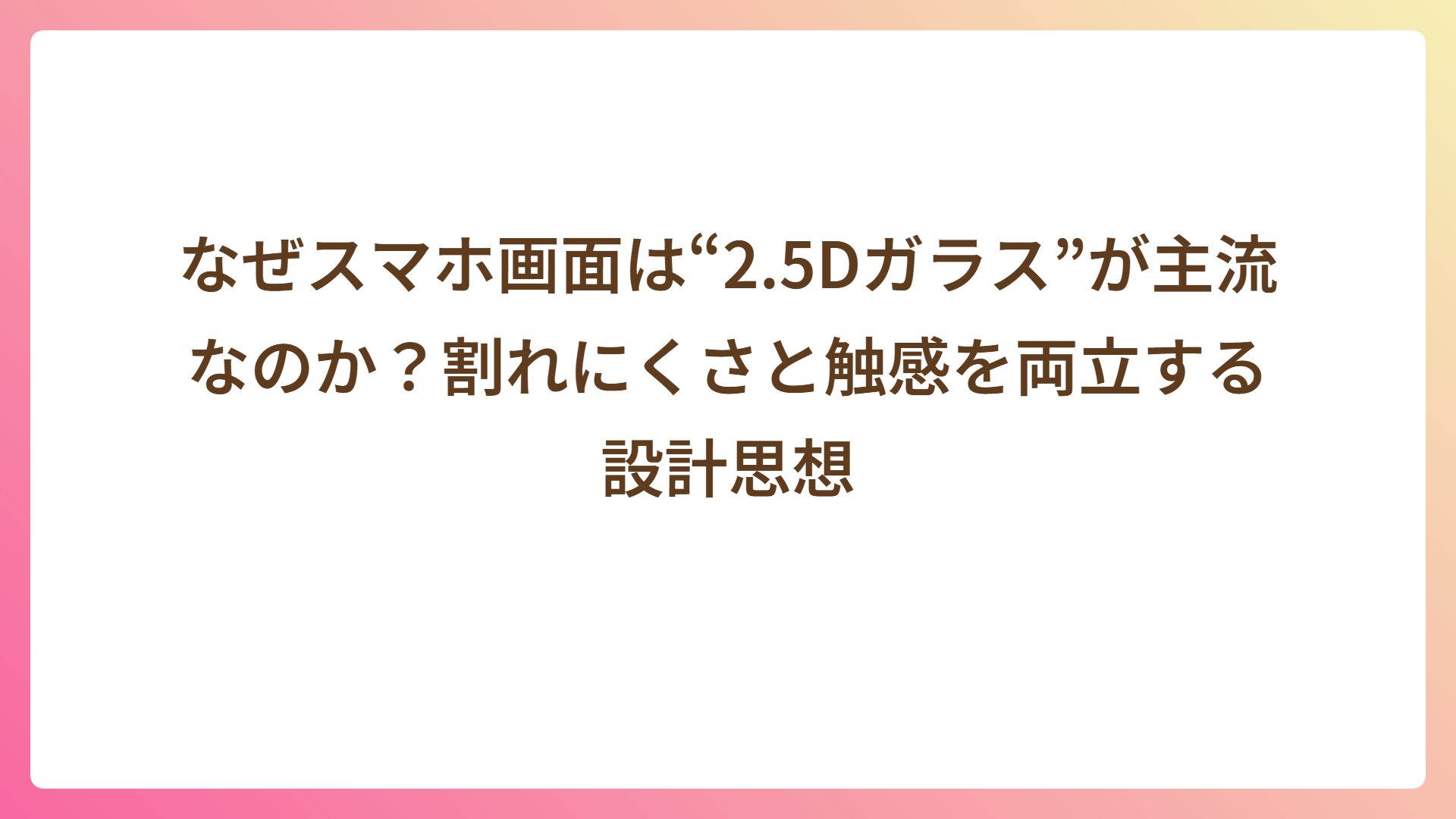なぜ紙幣は“顔の位置”が左右で違うのか?透かしと券面設計の理由
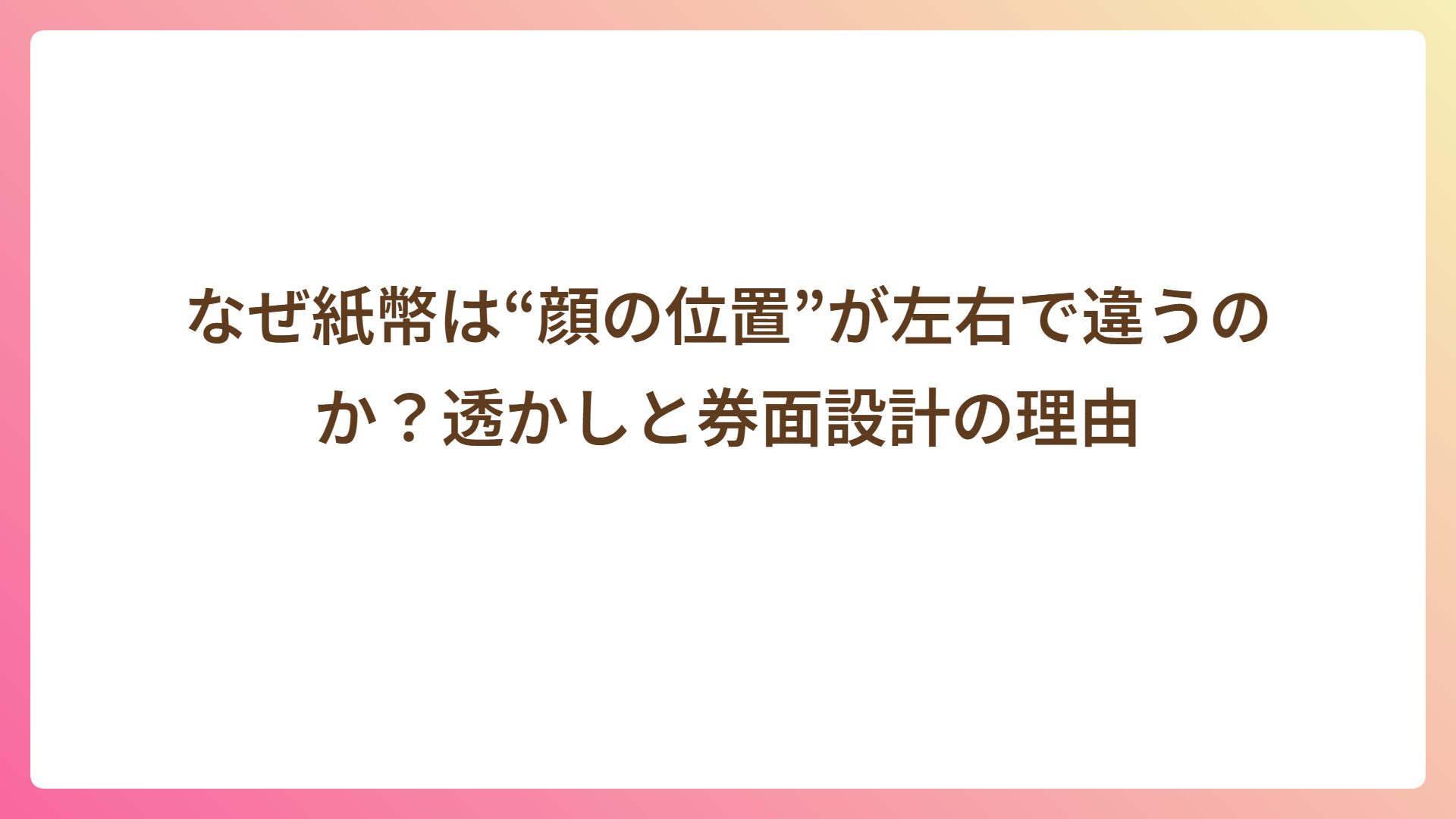
1万円札の福沢諭吉、5千円札の樋口一葉、千円札の野口英世――。
これらの肖像を見比べると、顔の位置が右寄りや左寄りと異なっていることに気づきます。
なぜ紙幣の顔は中央ではなく、あえて左右にずらされているのでしょうか?
実はこの配置には、偽造防止技術とデザイン設計上の深い理由が隠されています。
顔の位置がずれている最大の理由:透かしの配置
日本の紙幣で肖像が中央からずれている最大の理由は、透かし(すかし)との干渉を避けるためです。
紙幣には、光に透かすと見える「肖像透かし」が左側(または右側)に入っています。
この透かしは、肉眼でも確認できる高度な偽造防止技術の一つ。
印刷ではなく、紙そのものの繊維密度を変化させて描かれた立体模様であり、印刷工程とは別の「紙製造段階」で作り込まれています。
透かしの位置は、紙幣を折ったり汚したりしても確認しやすいように無地部分(余白)に設けられるため、
結果として肖像画を反対側に寄せる設計となっているのです。
偽造防止の観点:透かしと印刷肖像の“重なり防止”
透かしは、顔の輪郭や立体感を微妙な陰影で再現する精密な構造です。
印刷された肖像と重なってしまうと、線の模様や陰影が干渉し、
透かしが見えづらくなってしまいます。
そのため、
- 印刷された肖像と透かしは必ず反対側に配置
- 顔の位置を左右どちらかに寄せることで、透かし確認用の無地領域を確保
という設計ルールが採用されています。
実際、現行の日本銀行券ではすべて「透かし=余白側、印刷肖像=反対側」という構成です。
新紙幣(2024年発行)のデザインも同様
2024年発行の新紙幣(1万円:渋沢栄一、5千円:津田梅子、千円:北里柴三郎)でも、肖像の位置はそれぞれ異なります。
これはデザイン上の遊びではなく、
- 透かし位置(左側)
- ホログラム(右側)
- 凸版印刷やマイクロ文字などの配置バランス
といった複数の偽造防止要素を最適に配置するための結果です。
とくに新紙幣では、3Dホログラムが追加されたため、
肖像の位置もそれに合わせて微調整されています。
券面デザインのバランス:左右非対称が“見やすさ”を生む
紙幣デザインには、偽造防止だけでなく視認性と記号性も重視されます。
肖像を中央に配置すると、額面数字・署名・発行記号などの情報が重なり、視覚的に窮屈になります。
一方、肖像を左右どちらかに寄せることで、
- 額面数字が中央に大きく見える
- 余白に透かしや識別マークを配置できる
- 縦折り時にも肖像が隠れにくい
といった利点が得られます。
左右非対称のデザインは結果として美的バランスと機能性を両立させているのです。
海外紙幣との比較:透かし配置は共通ルール
実は、この「透かしと肖像の分離」は日本だけの特徴ではありません。
米ドル、ユーロ、ポンドなど多くの主要通貨でも、透かしは余白側・肖像は反対側という設計が採用されています。
これは国際的にも確立された偽造防止デザインの定石であり、
透かし・ホログラム・凹版印刷といった要素を左右に分けることで、
「どちらかが欠けても真偽判定できる」多層的な防御構造を実現しているのです。
まとめ:左右非対称は“安全とデザイン”の結果
紙幣の顔の位置が左右で異なるのは、
- 透かしを見やすくするための偽造防止設計
- 印刷と透かしの干渉を防ぐための構造的配慮
- 額面表示やホログラムとのバランス調整
- 美観と視認性を両立する券面デザイン
といった複数の目的が重なった結果です。
つまり、「左右非対称」は単なるデザイン上の遊びではなく、
安全性・機能性・審美性を両立した“計算された非対称”なのです。