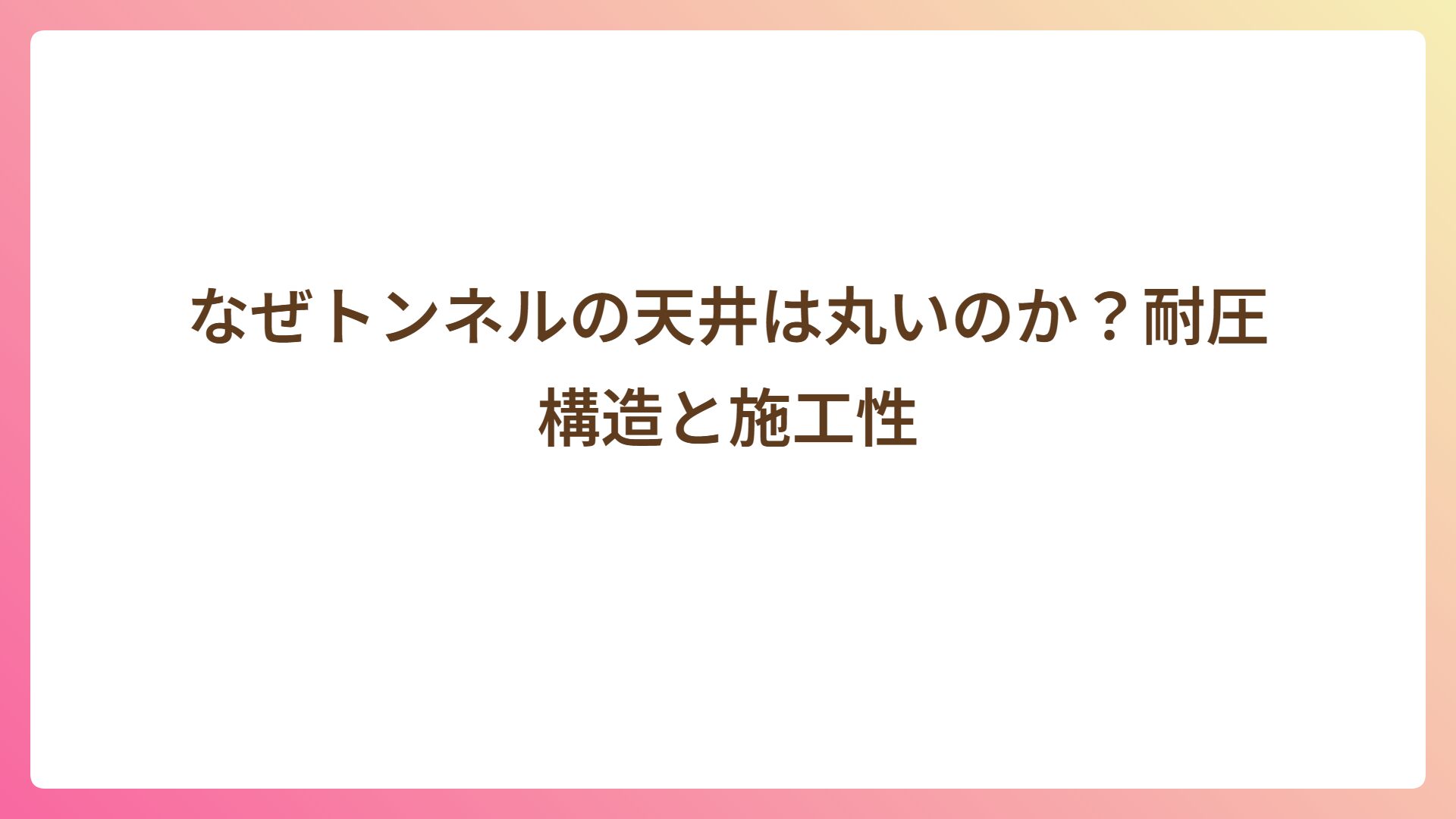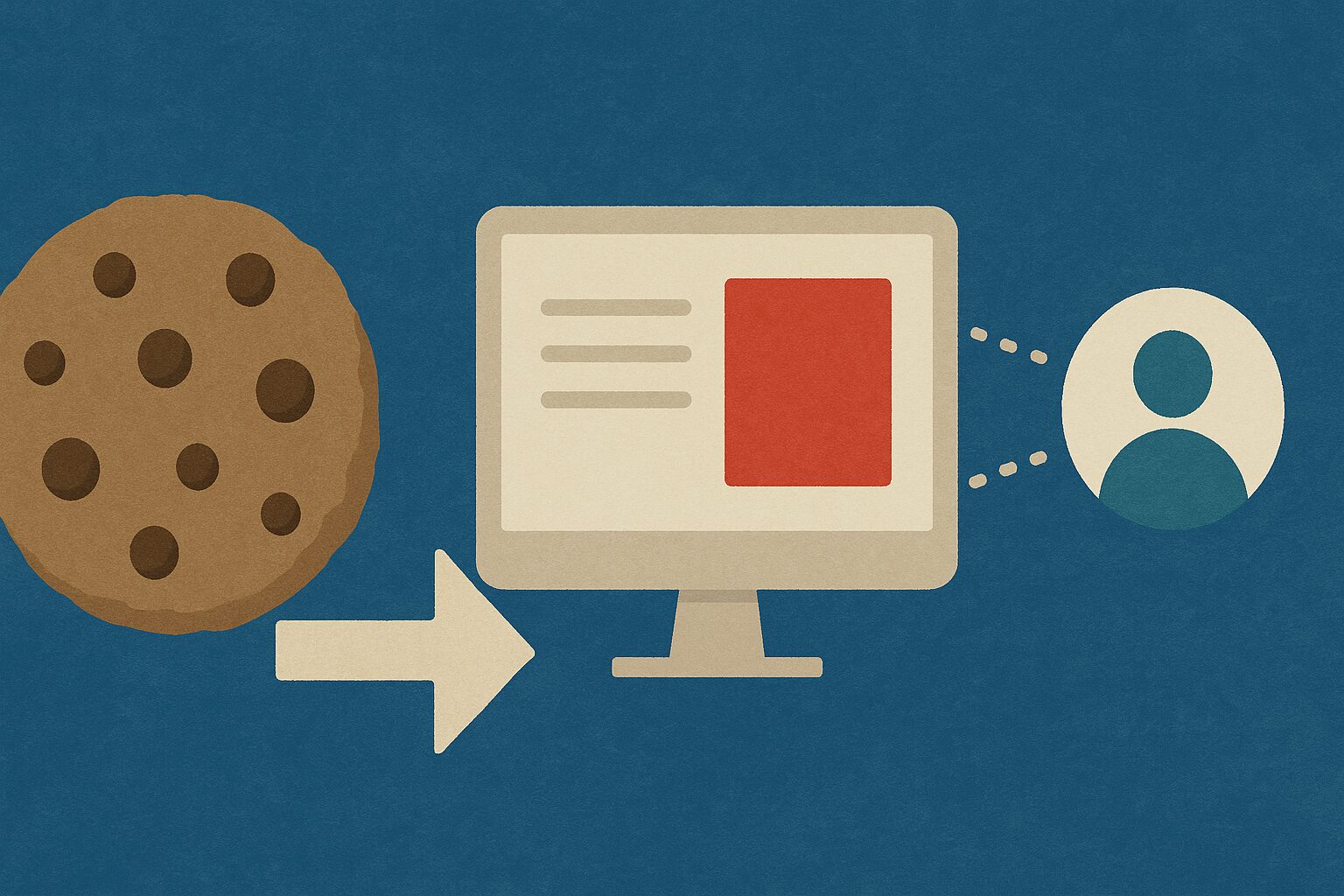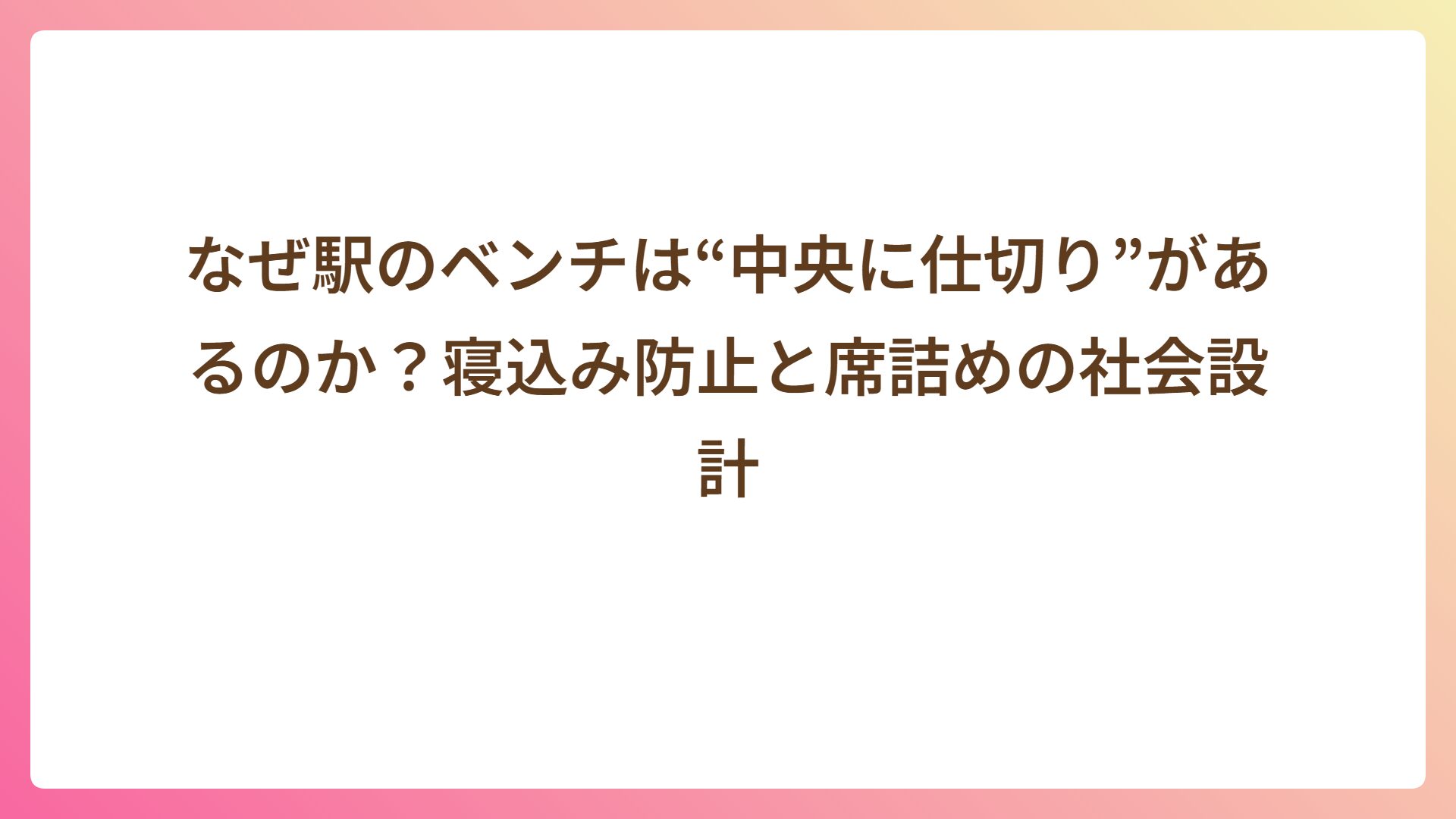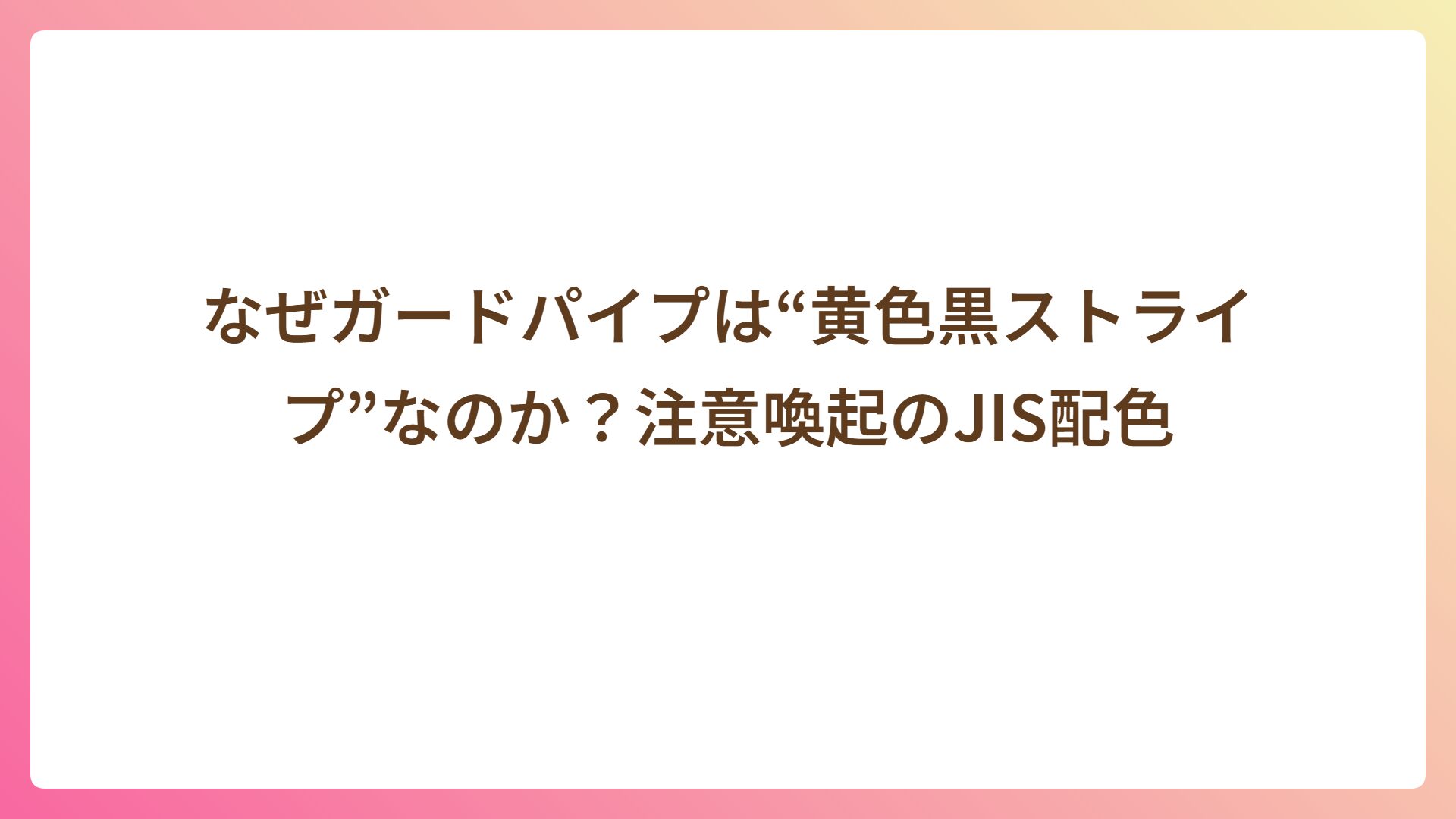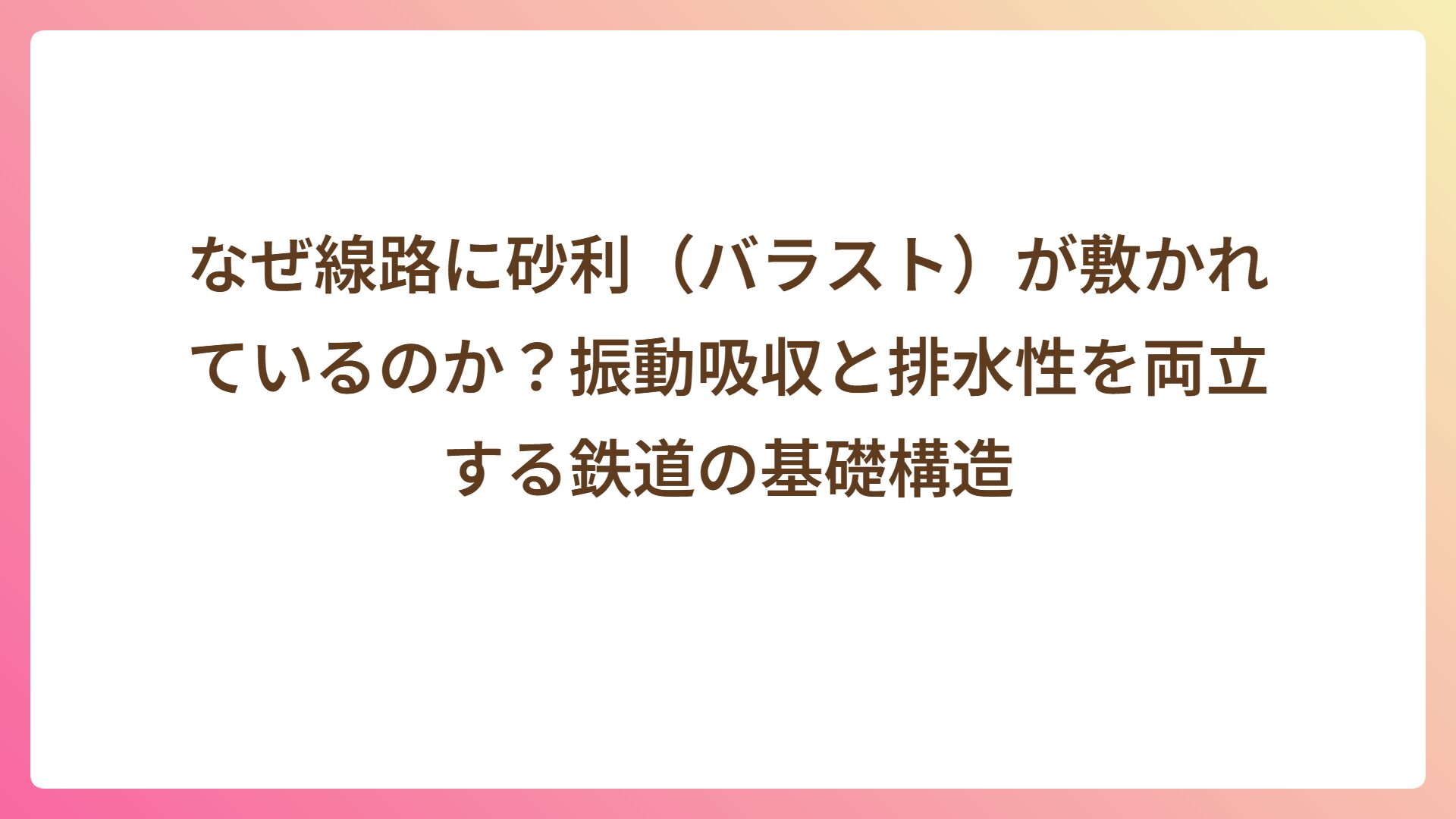なぜ自動水栓は“手を引くと水が止まる”のか?赤外線センサーと遅延設定の仕組み
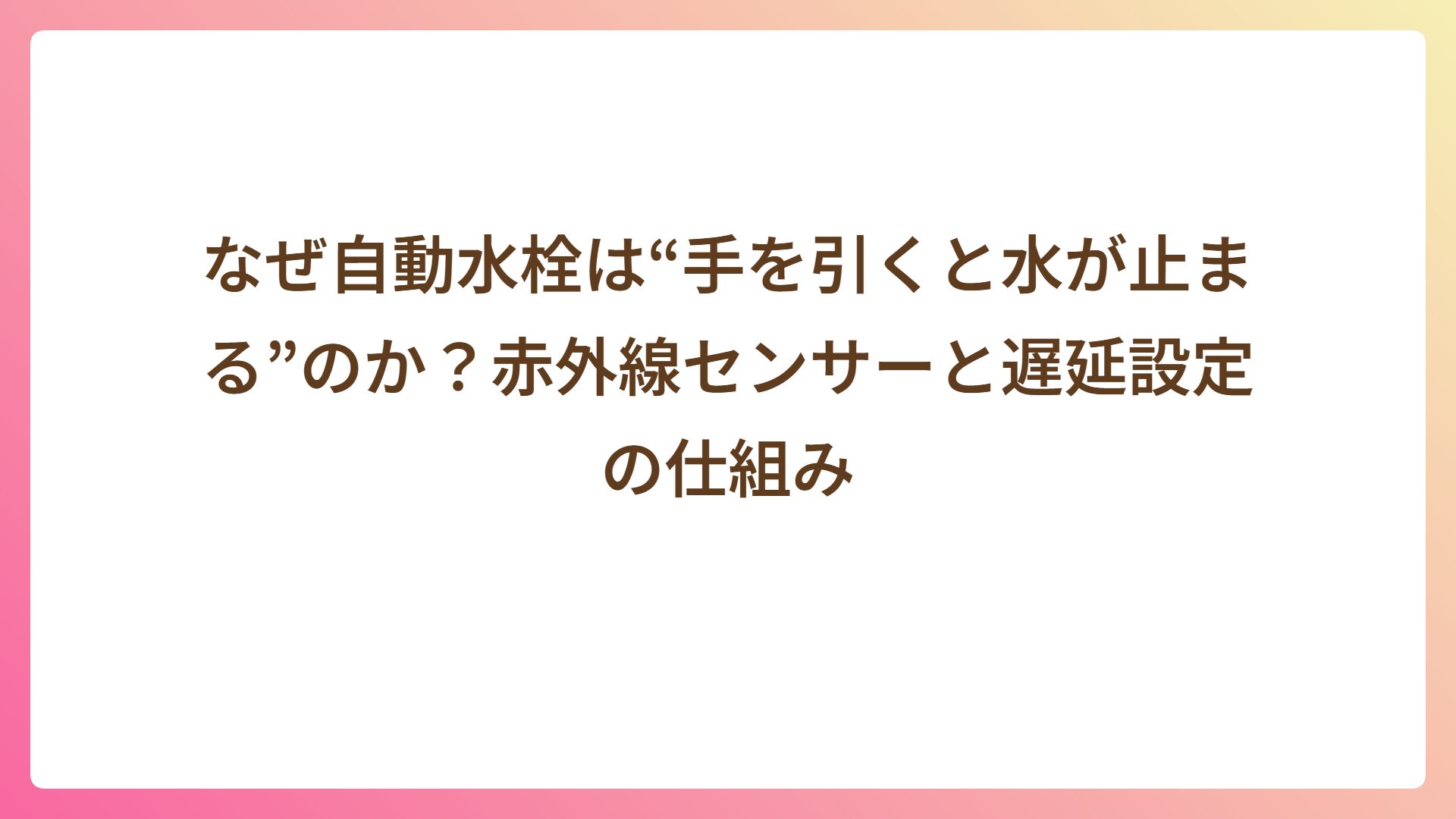
公共トイレやオフィスの洗面所でよく見かける「自動水栓」。
手をかざすと水が出て、引くと自然に止まりますが、よく見ると少しだけタイムラグがあります。
なぜ完全に手を引いた瞬間ではなく、“1〜2秒遅れて”水が止まるのでしょうか?
そこには、赤外線センサーの検知構造と使い勝手を考慮した遅延制御という技術的な理由があります。
自動水栓の基本構造:赤外線で“手の有無”を検知
自動水栓には、蛇口の根本または吐水口付近に赤外線センサーが内蔵されています。
センサーは常に赤外線を照射しており、手などの物体が近づくと光が反射して戻ってくる仕組みです。
- 手が近づく → 反射光を検知 → 電磁弁を開いて水を出す
- 手を引く → 反射光が途絶える → 電磁弁を閉じて水を止める
という単純な流れで制御されています。
この仕組みのおかげで、蛇口に触れずに手洗いができ、衛生的にも優れています。
“すぐ止まらない”のは誤検知を防ぐため
ではなぜ、手を引いた瞬間に水が止まらないのでしょうか?
これは、センサーが一時的な遮蔽や反射変化を「手を離した」と誤認しないようにするためです。
たとえば、
- 手を洗う途中で一瞬位置を変えた
- 水滴や泡がセンサー前を通った
- 周囲の人の服や光が反射した
といった状況で、センサーが敏感すぎると誤作動(ピタピタ水が止まる現象)が起きてしまいます。
そのため、実際の検知システムでは「反射が途切れてから〇秒後に停止」という遅延設定(ディレイ制御)が組み込まれているのです。
遅延設定の時間は“1〜2秒”が一般的
メーカーによって異なりますが、多くの自動水栓では「1〜2秒の停止遅延」が標準設定です。
これは、手を少し動かしても水が止まらないようにするユーザビリティ(使いやすさ)重視の時間です。
- 0秒(即停止)だと:手を動かすたびに水が止まり、使いにくい
- 3秒以上だと:手を引いたあとに無駄に水が出続ける
というトレードオフの中で、最も自然に感じる範囲が約1〜2秒とされています。
検知範囲の工夫:背景光や距離の補正
赤外線センサーは、反射の強さをもとに“手の有無”を判断しますが、
照明・周囲の壁の色・光沢のある洗面台などによって検知精度が変わります。
そのためメーカーは、
- 検知距離を20cm前後に固定(遠すぎる誤検知防止)
- 背景光のノイズ除去(蛍光灯のチラつきなどをキャンセル)
- 手の動きに対するヒステリシス制御(出・止めの閾値を分ける)
といった工夫を施し、安定した検知を実現しています。
これもまた、「手を引いてすぐ止まらない」理由の一部です。
電磁弁とセンサーの連動:機械的な遅延も存在
センサーが「手を離した」と判断しても、実際に水が止まるまでには機械的な反応時間があります。
電磁弁が閉じるまでに数百ミリ秒〜1秒ほどの遅れが生じるため、
この“物理的タイムラグ”と制御側の“意図的な遅延”が合わさって、
結果的に1〜2秒後に水が止まるように感じるのです。
まとめ:遅延は“便利さと安定動作”のための設計
自動水栓が手を引いた瞬間に水を止めないのは、
- 誤検知を防ぐためのソフトウェア的な遅延設定
- センサーの反射光変化を安定化させる制御設計
- 電磁弁動作による物理的なタイムラグ
という複数の要素によるものです。
つまり、あの“ワンテンポ遅れて止まる”動作は不具合ではなく、
快適さと安定性を両立させるための設計思想なのです。