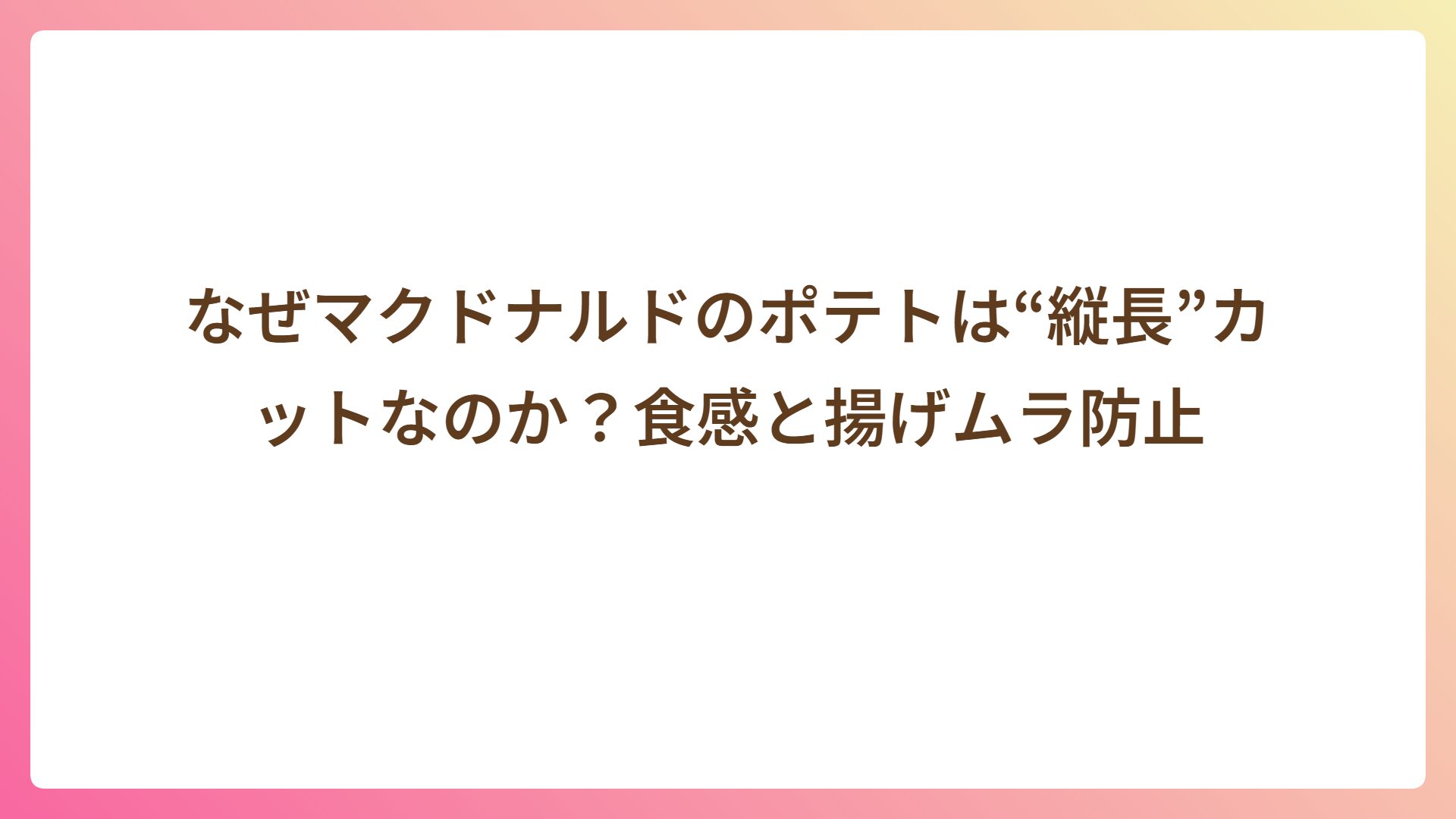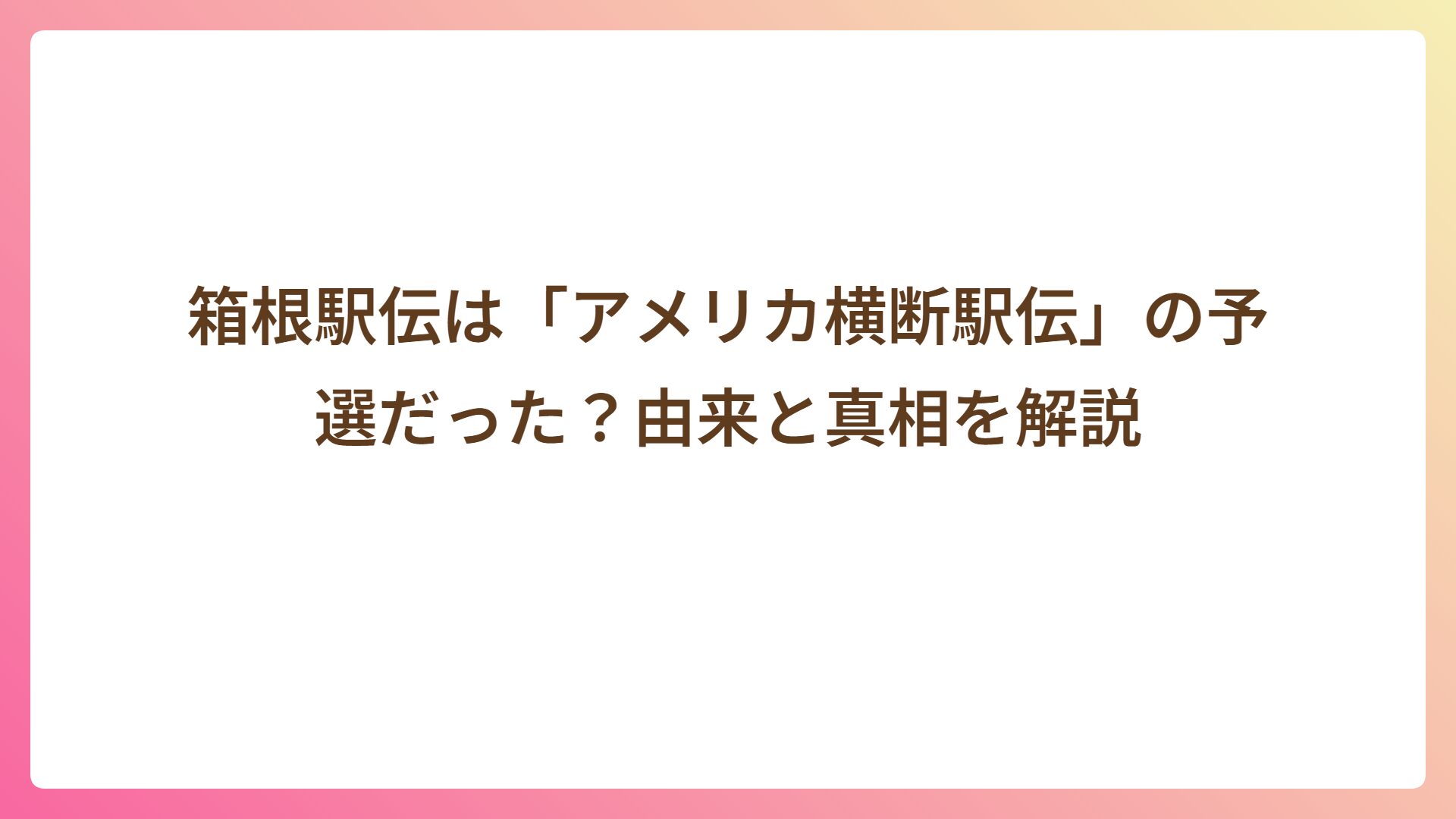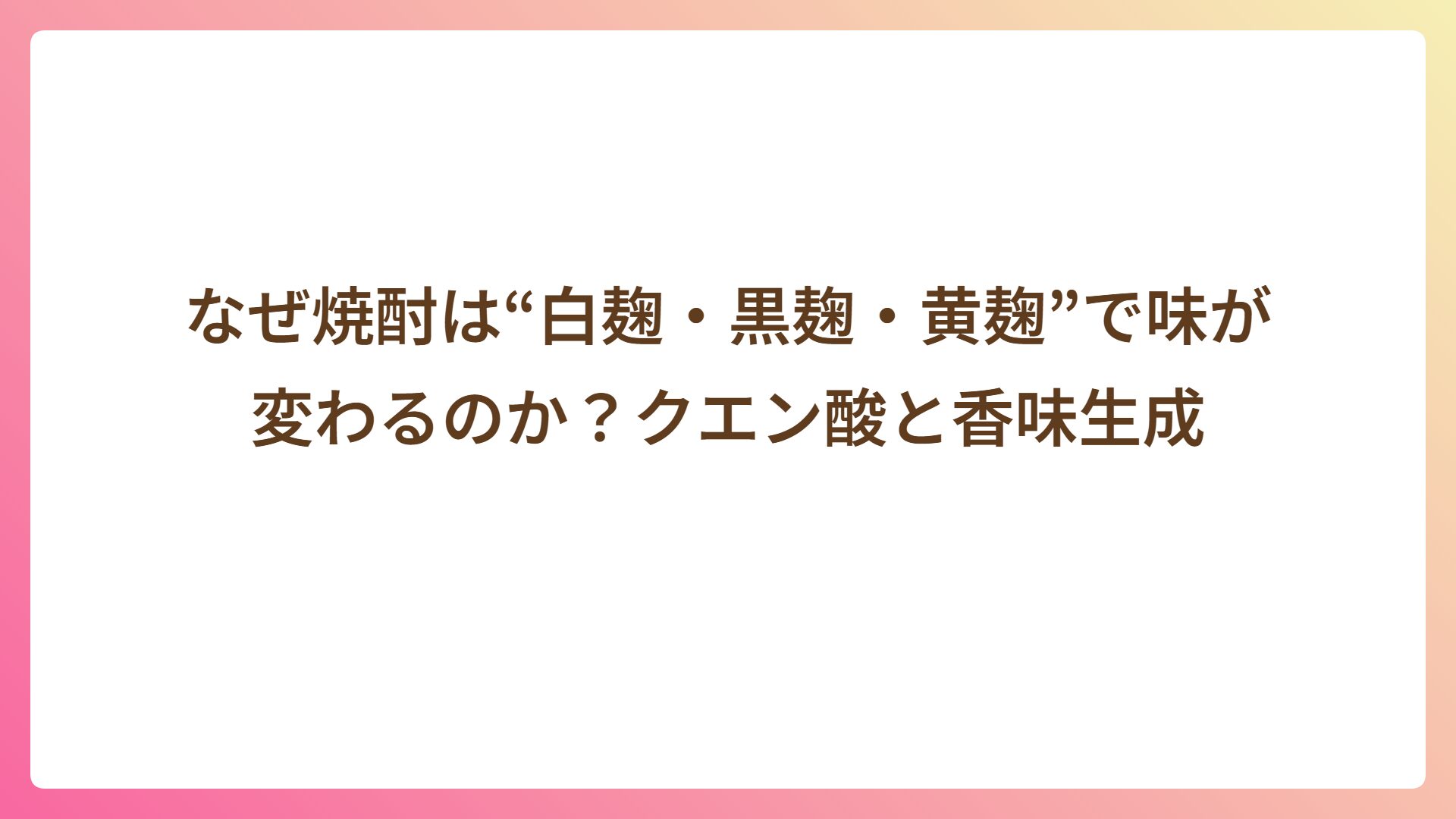なぜ空港の動く歩道は“長いのに遅い”のか?転倒リスクと搬送効率のバランス
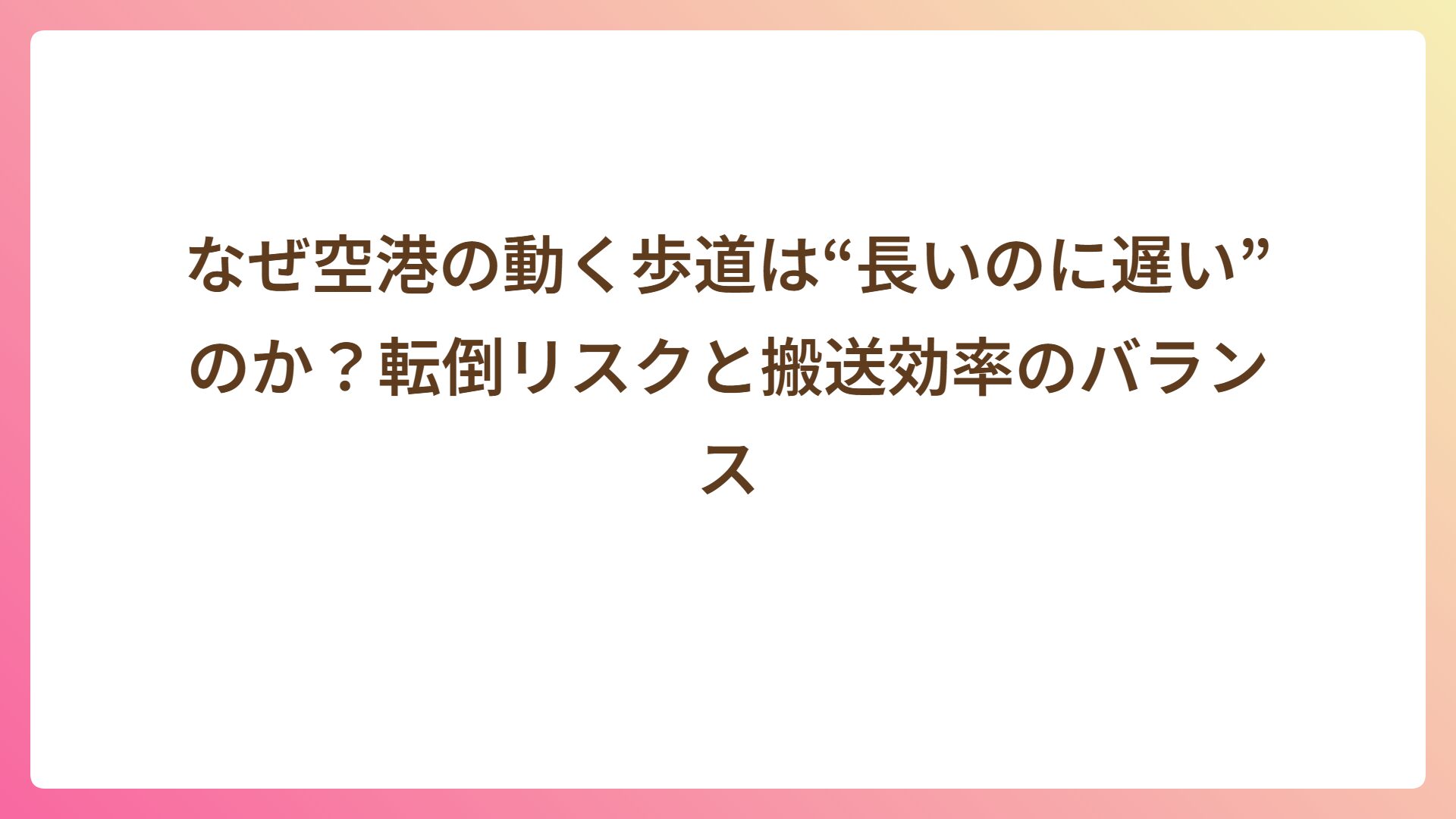
空港で見かける“動く歩道”。
長い通路を楽に移動できる便利な設備ですが、「意外と遅いな」と感じたことはありませんか?
同じ距離を歩くより少し早い程度で、急いでいる時には物足りなく感じるかもしれません。
しかしこの速度には明確な理由があります。
今回は、転倒リスク・人の動作特性・搬送効率という3つの観点から、なぜ空港の動く歩道は「長いのに遅い」のかを解説します。
動く歩道の速度は“安全基準”で制限されている
まず、動く歩道(正式名称:水平エスカレーター)は、国土交通省の「建築基準法施行令」および「JIS規格(日本産業規格)」によって速度上限が定められています。
- 一般利用者が使う歩道型:毎分約60〜90メートル(時速3.6〜5.4km)
- エスカレーター型(傾斜あり):毎分約45メートル(時速2.7km)程度
これは、高齢者・子ども・大きな荷物を持つ旅行者が安心して利用できるよう設定された値です。
少しでも速くすると、乗り降り時にバランスを崩して転倒する危険があるため、速度を上げることは法律上も難しいのです。
“長いのに遅い”と感じる理由:歩行速度との比較
一般的な人の歩行速度は、時速4〜5km程度。
つまり、動く歩道に立っているだけでは、普通に歩くのとほぼ同じスピードです。
しかし、動く歩道の上を歩けば、
- 自分の歩行速度(約5km/h)
- 歩道の移動速度(約4km/h)
が加算されて、合計で時速9km前後になります。
そのため、設計上は「歩きながら利用する人」と「立ち止まる人」の両方を想定し、
誰でも安全に乗れるスピードとして、少し“遅く感じる”速度が採用されているのです。
転倒リスクと反応時間の関係
速度を上げると、危険なのは「降りる瞬間」です。
動く歩道の終端では、床が静止状態に切り替わるため、
利用者は瞬時に足の速度を調整しなければなりません。
人間の反応時間は平均で約0.2〜0.3秒。
速度が速くなるほど、このわずかな時間差で足がもつれたり、荷物が前に倒れたりするリスクが高まります。
特に高齢者やスーツケースを引いている人は、
「速度差でつんのめる」事故が多発しており、
その安全対策として速度上限が低めに設定されています。
長距離でも“遅い”のは搬送効率を最適化しているから
空港の動く歩道は、単に人を運ぶだけでなく、利用人数の多さと連続稼働時間にも対応しなければなりません。
たとえば1本の歩道が1日中稼働し、数万人が利用することを考えると、
モーターの摩耗・振動・騒音を抑えるためにも、速度を上げすぎないほうが機械寿命を延ばせます。
また、空港では乗客がスーツケースやベビーカーを持って利用することが多いため、
「誰でも安全に乗れる速度」=「システムとして最も効率的な速度」でもあるのです。
海外の“高速動く歩道”はなぜ普及しないのか
一部の空港(例:パリ・シャルルドゴール空港、ロンドン・ヒースロー空港など)では、試験的に時速9〜12kmの“高速ムービングウォーク”が導入されたことがあります。
しかし、
- 乗り降り時に転倒事故が相次いだ
- スーツケースのタイヤが引っかかる
- 乗客の恐怖感が強い
などの理由で、ほとんどの施設で廃止または減速運用になりました。
つまり、理論上は速くできても、人間の安全限界がボトルネックになっているのです。
まとめ:遅さは“安全と快適さ”の最適解
空港の動く歩道が「長いのに遅い」と感じるのは、
- 転倒リスクを防ぐための法的速度制限
- 高齢者や荷物利用者を含む“誰でも使える”設計
- モーター耐久・搬送効率を考慮した運用設計
といった要素が組み合わさっているためです。
つまり、あの“ゆっくりした速度”は欠点ではなく、
「安全・効率・快適」を両立した、最も人に優しいスピードなのです。