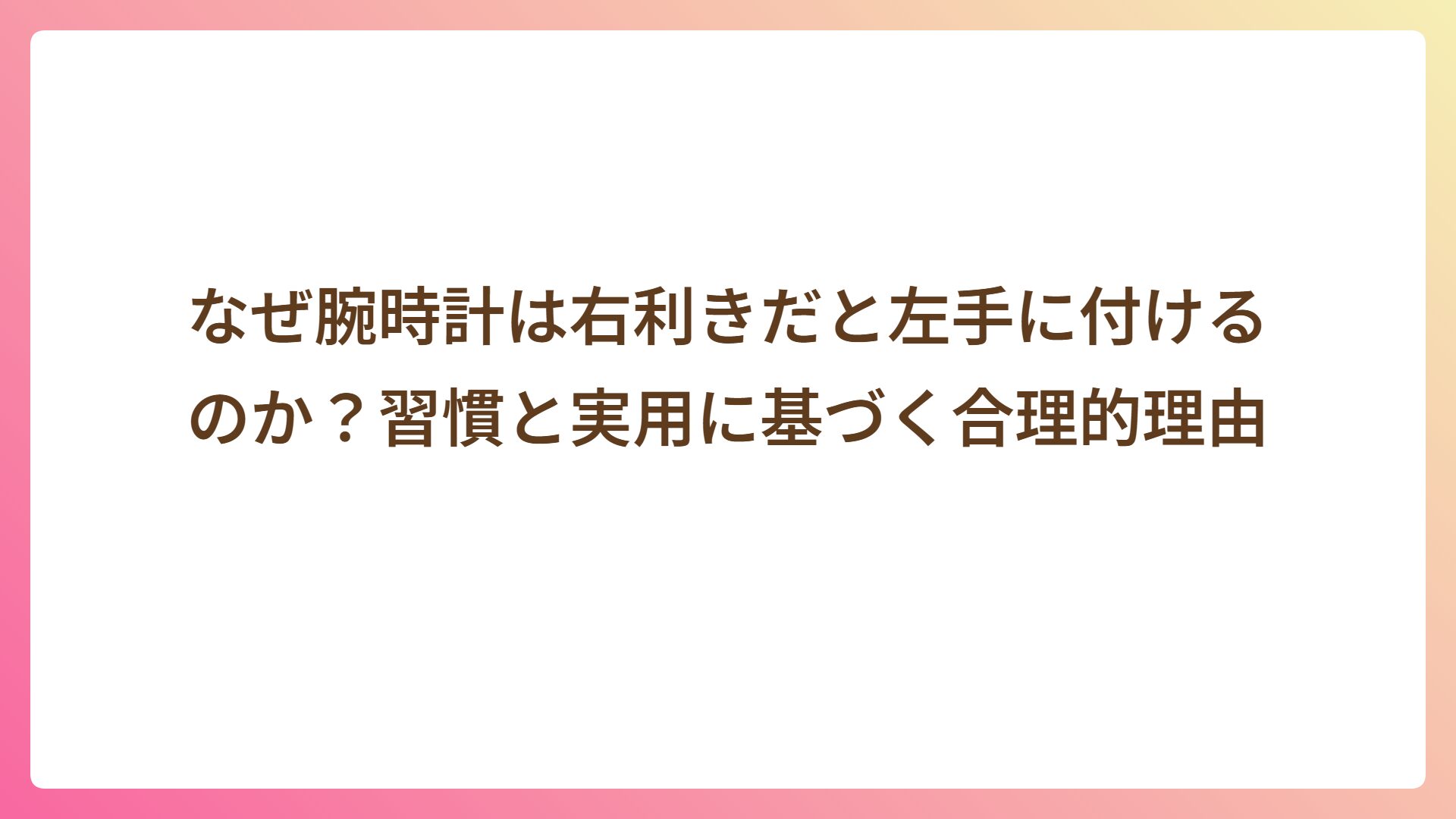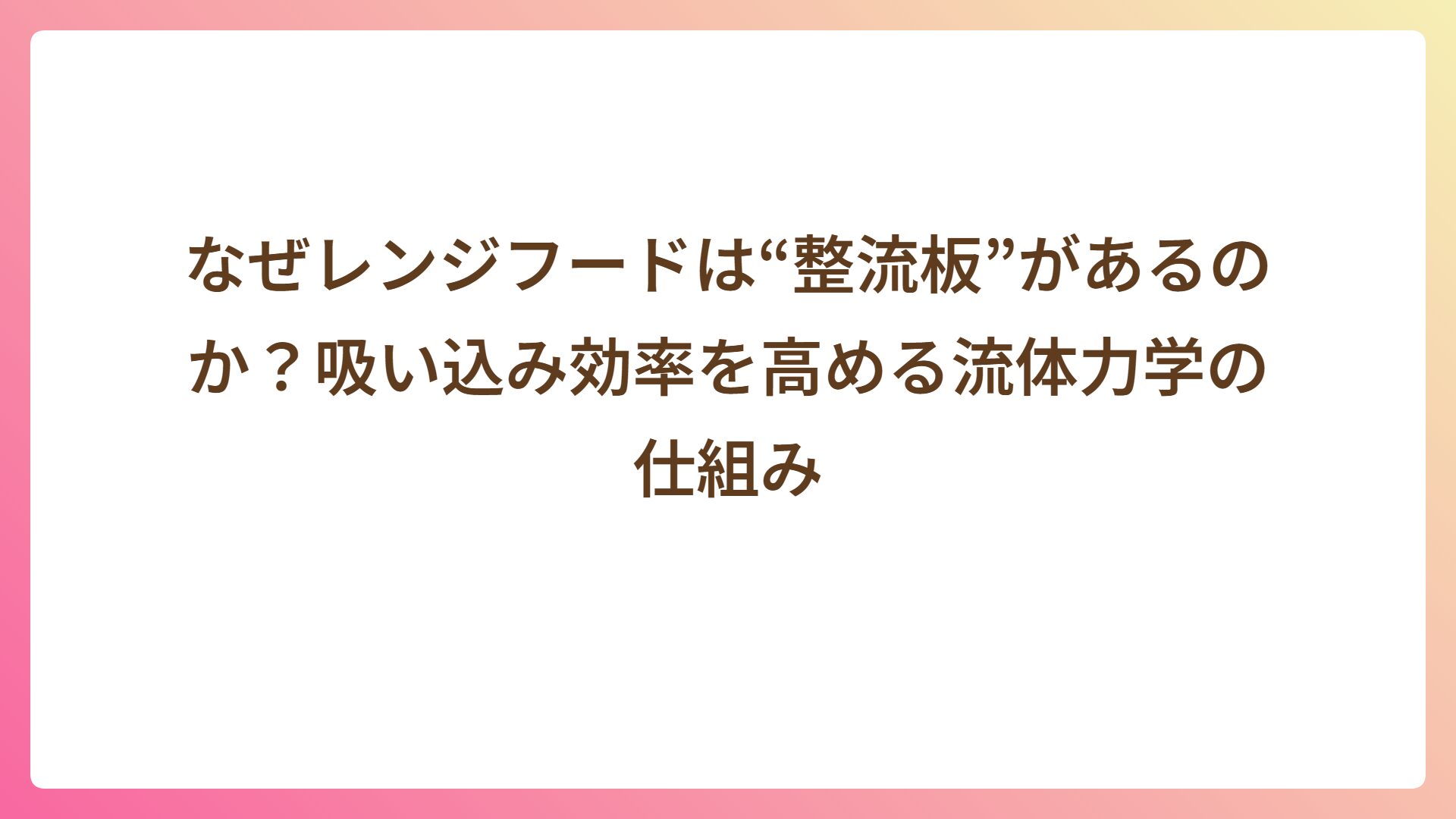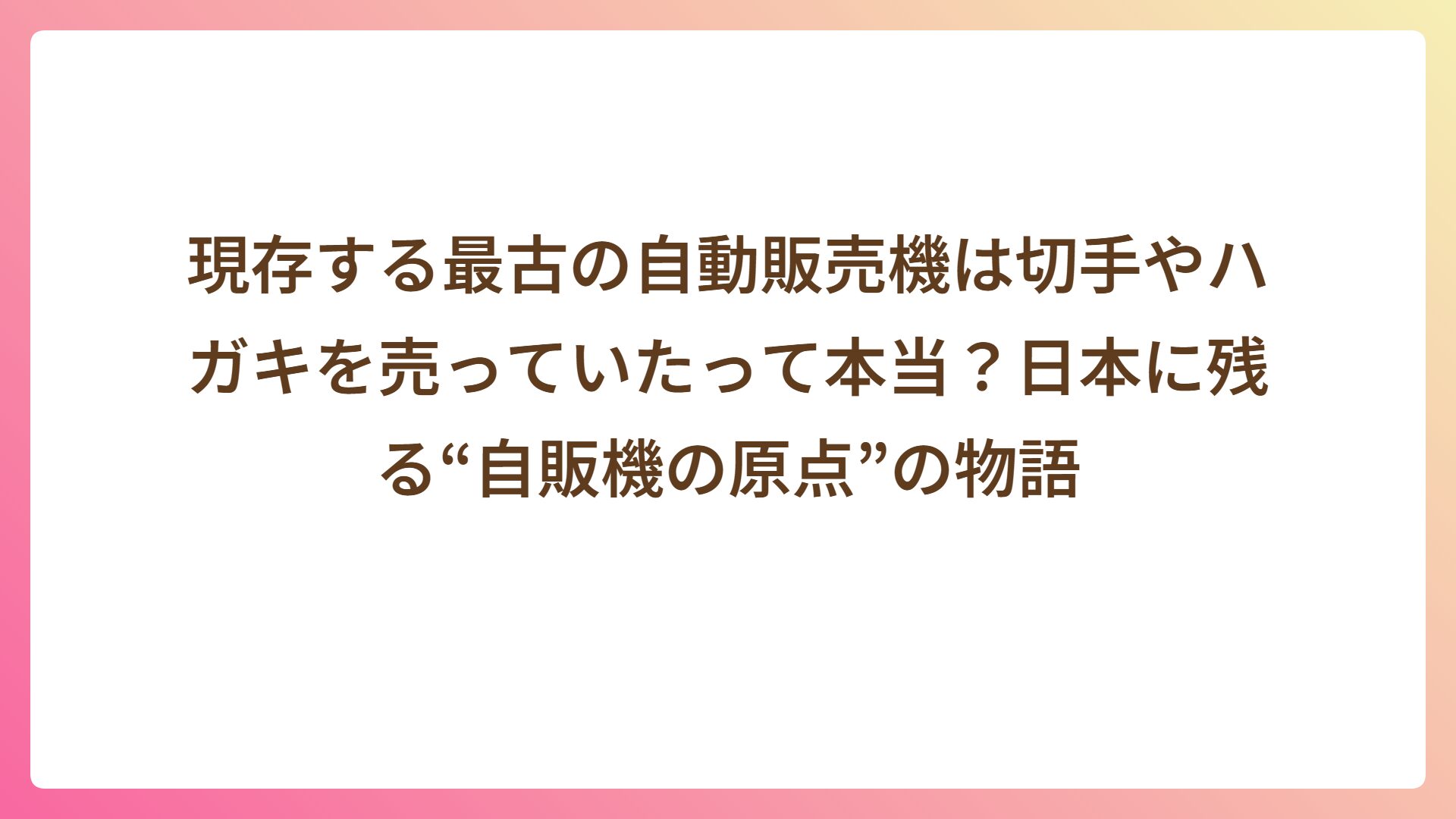なぜ硬貨にギザギザがあるのか?識別性と偽造防止のためのデザイン工学
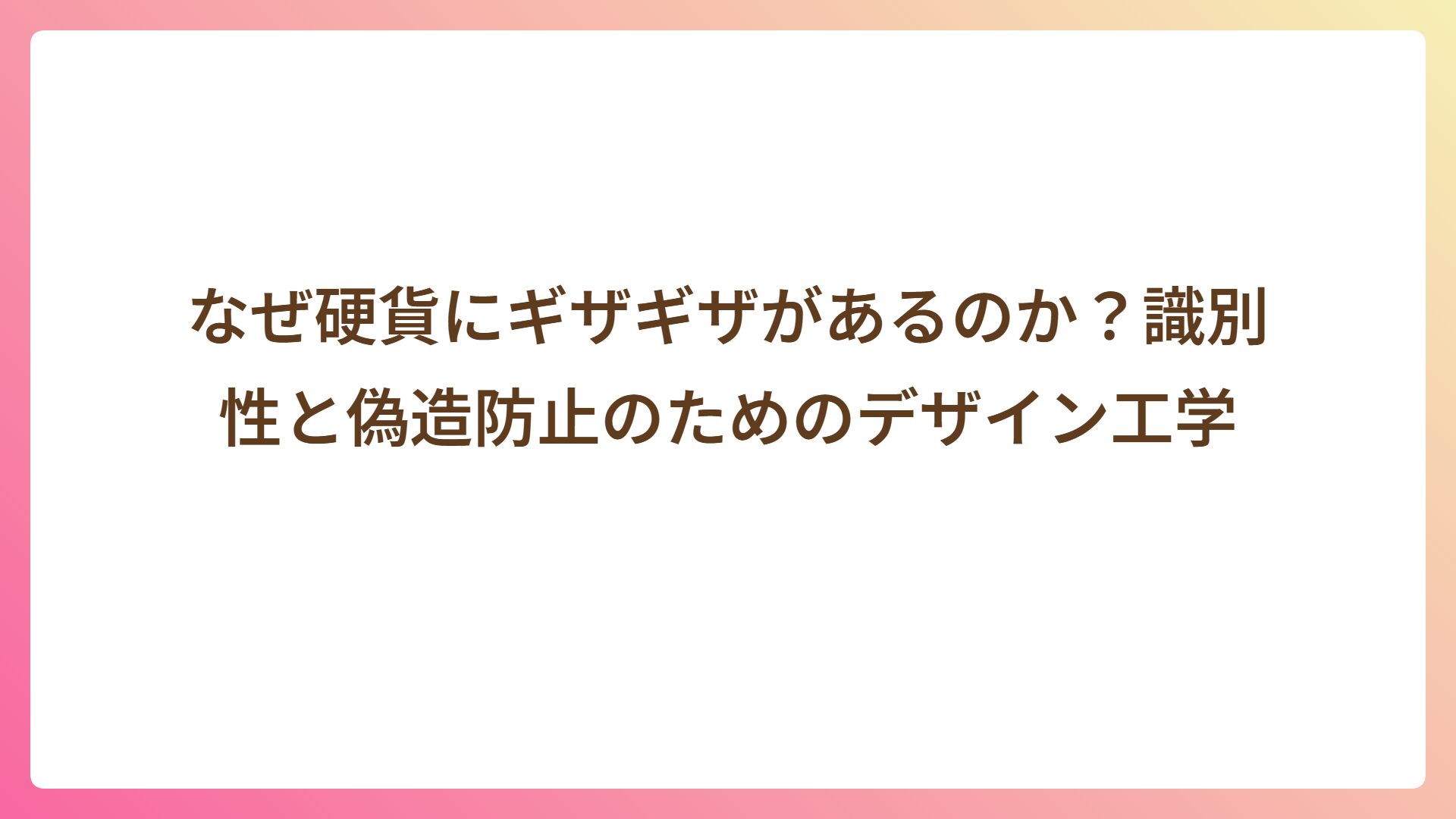
日本の硬貨を手に取ると、縁に細かいギザギザが刻まれているものがあります。
10円玉にはなく、100円玉や50円玉などにはありますよね。
実はこのギザギザ、デザインではなく、貨幣の安全性と実用性を高めるための重要な工夫なのです。
この記事では、硬貨にギザギザがある理由を、識別・防犯・製造技術の面から解説します。
理由①:硬貨を“触って識別”しやすくするため
ギザギザ(刻み)は、まず種類を触覚で見分けるために設けられています。
日本の硬貨には次のような違いがあります。
| 硬貨 | ギザあり | ギザなし | 穴あり |
|---|---|---|---|
| 1円 | × | ○ | × |
| 5円 | × | ○ | ○ |
| 10円 | × | ○ | × |
| 50円 | ○ | × | ○ |
| 100円 | ○ | × | × |
| 500円 | ○ | × | × |
これにより、目の不自由な人でも指先で種類を区別できます。
実際、日本の貨幣デザインはユニバーサルデザインの理念に基づき、
- 大きさ
- 重さ
- 厚み
- ギザの有無
を組み合わせて識別しやすく設計されています。
理由②:昔は“金や銀を削る偽造防止”のためだった
硬貨の縁にギザギザが生まれたのは、17〜18世紀のヨーロッパに遡ります。
当時の硬貨は金や銀などの貴金属製で、素材自体に価値がありました。
そこで一部の人が、
- 硬貨の縁を少し削って金属を抜き取る
- そのまま流通させる
という「削り取り詐欺(クリッピング)」を行っていました。
この対策として考案されたのが、縁に刻みを入れる「リーディング(reeding)」加工です。
もし縁を削るとギザが消えるため、すぐに不正が分かる仕組みでした。
つまりギザは、“切り取り防止の証拠”として生まれた偽造防止技術なのです。
理由③:現代でも“偽造検知”や“自販機識別”に役立つ
現在の硬貨は金属の価値ではなく貨幣価値(公定価値)で取引されていますが、
ギザは依然として重要な役割を果たしています。
自動販売機や両替機などでは、
- ギザの有無
- 縁の段差や反射の仕方
- 重量・磁性・直径
を複合的に検知して硬貨を識別します。
そのため、ギザがあると機械判定が正確になりやすいのです。
特に500円硬貨は高額なため、ギザや微細パターンが偽造防止の最前線となっています。
理由④:ギザの“数や深さ”も正確に管理されている
ギザは単なる装飾ではなく、1枚ごとに精密な規格があります。
たとえば:
- 100円硬貨 → 約118本
- 50円硬貨 → 約110本
- 500円硬貨 → 約120本
これらのギザはミント(造幣局)のプレス機で一気に刻まれ、
深さ・角度・本数が国ごとに厳格に管理されています。
つまり、ギザは国家レベルの精密なセキュリティデザインなのです。
理由⑤:10円玉だけ“あえてギザなし”なのは混同防止
10円玉がギザなしであるのは、100円玉と区別しやすくするためです。
もし両方にギザがあると、サイズや重さが近いため識別が難しくなります。
また、10円玉は銅色で視覚的にも差別化されており、
「ギザのない10円」という特徴が識別性をさらに高めています。
理由⑥:高額硬貨ほど“偽造対策が強い”
硬貨の価値が高くなるほど、偽造防止策も強化されています。
| 硬貨 | 主な偽造対策 |
|---|---|
| 10円以下 | 素材と寸法の差別化 |
| 50〜100円 | ギザ加工、穴あけ |
| 500円 | 二色構造・微細ギザ・レーザー刻印 |
特に500円硬貨は世界でもトップクラスの防偽性能を誇り、
ギザは他国製の模造コインを識別するための重要要素にもなっています。
理由⑦:ギザは“伝統と信頼の象徴”でもある
今日では、ギザには文化的・デザイン的な役割もあります。
- 日本の硬貨に共通する信頼の印
- 国の造幣技術の象徴
- 「公式の通貨」であることを示す意匠
として、ギザは単なる物理的対策を超えた伝統的シンボルとなっています。
まとめ:ギザギザは“安全と使いやすさ”を両立する設計
硬貨にギザギザがあるのは、
- 手触りで識別しやすくするため
- 昔は削り取り防止、今は偽造防止のため
- 自販機や機械で正確に識別するため
- 高額硬貨のセキュリティを強化するため
といった理由によるものです。
つまり、縁のギザギザは単なるデザインではなく、
「安全・利便・信頼」を兼ね備えた貨幣工学の結晶なのです。