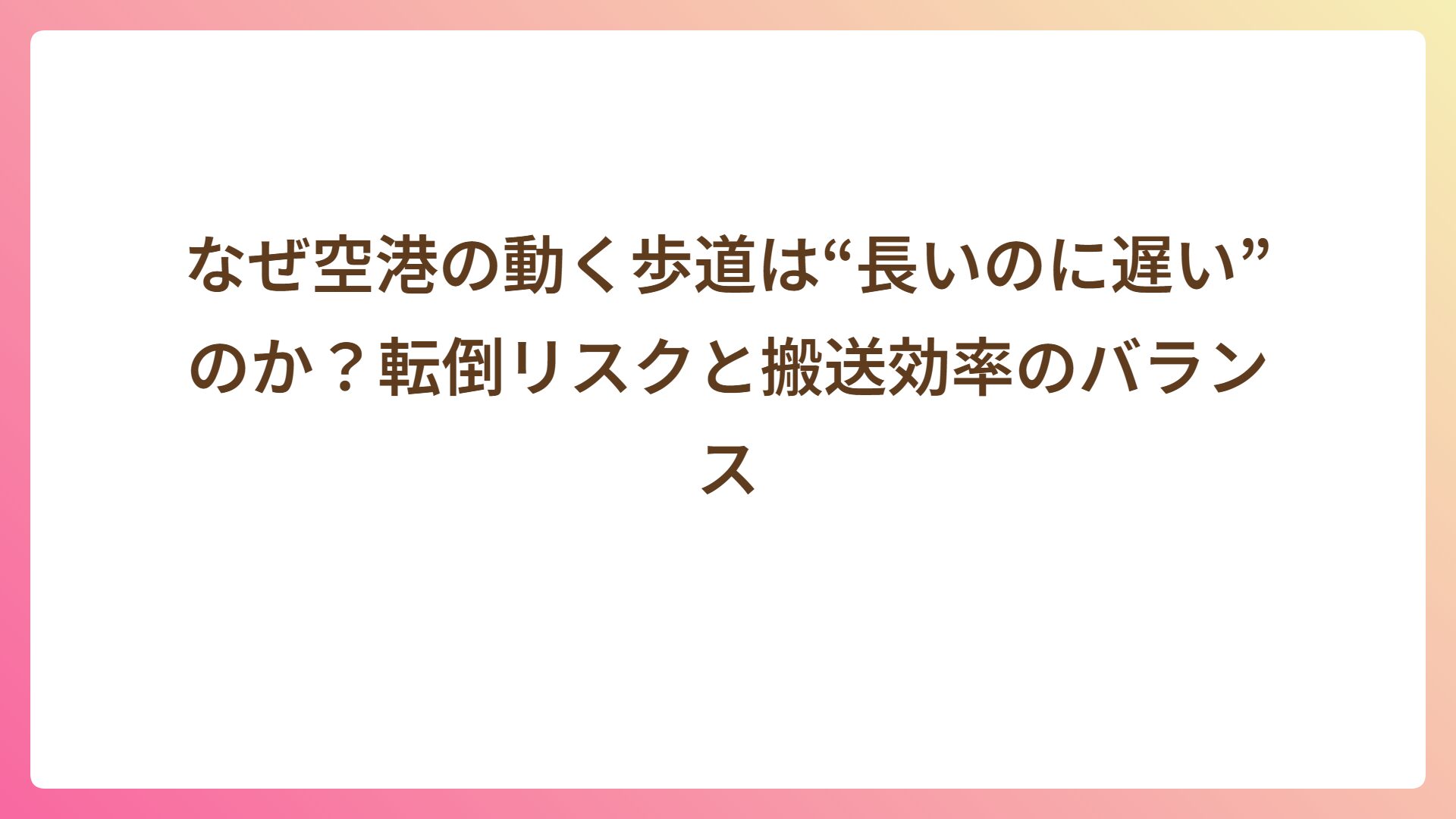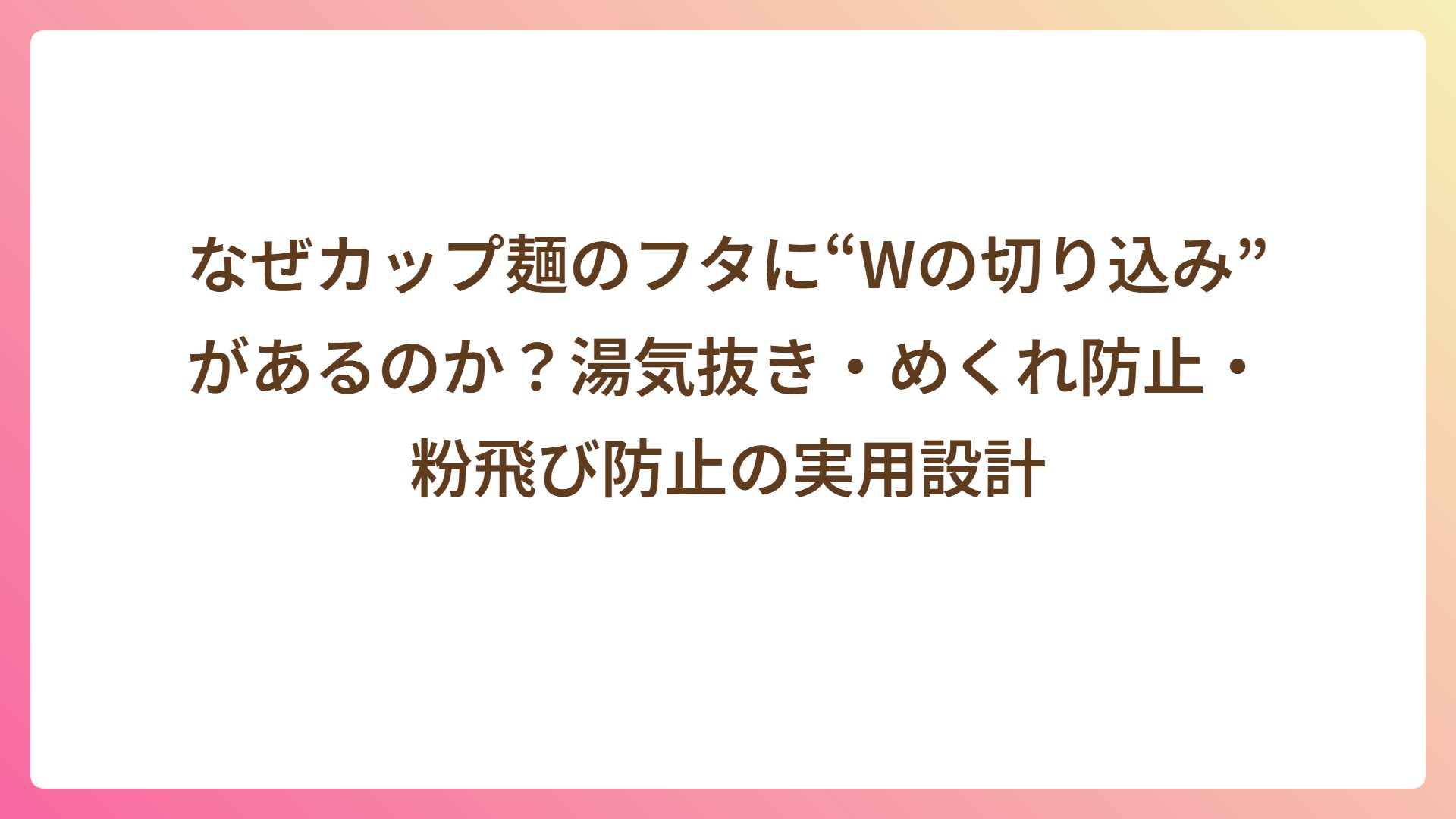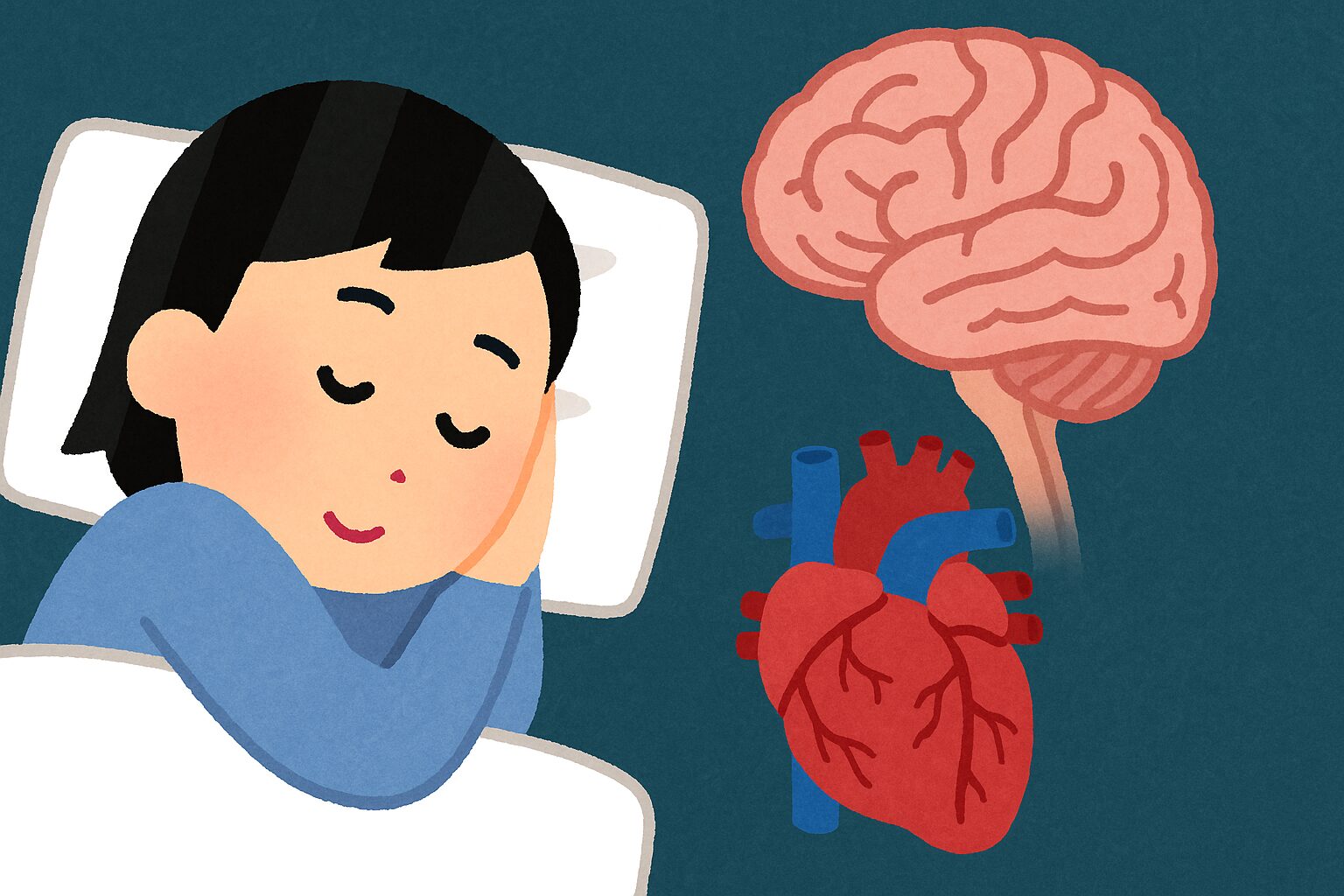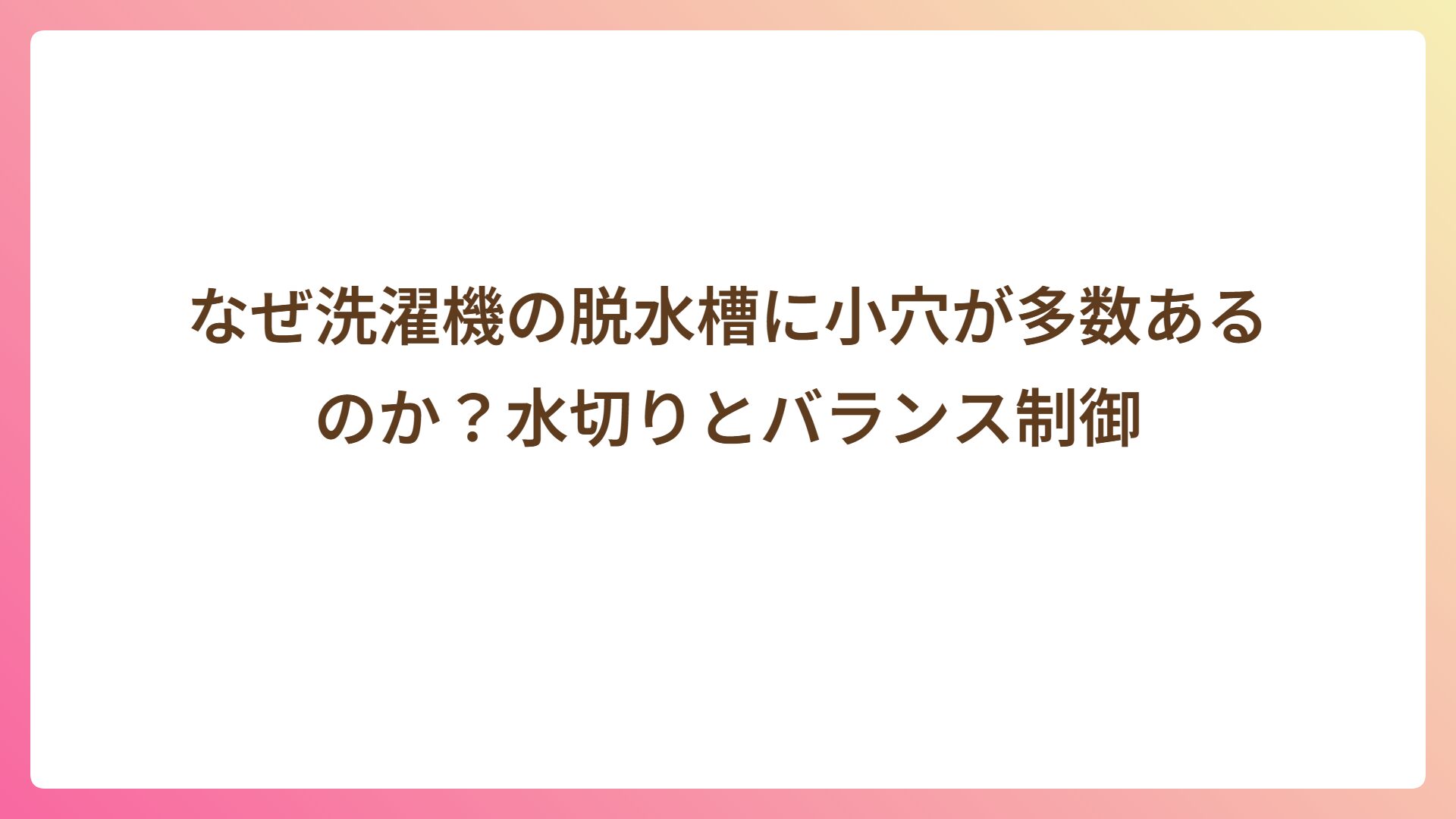なぜ鉄道は右側通行ではなく“左側通行”なのか?明治期の慣例と法整備の経緯
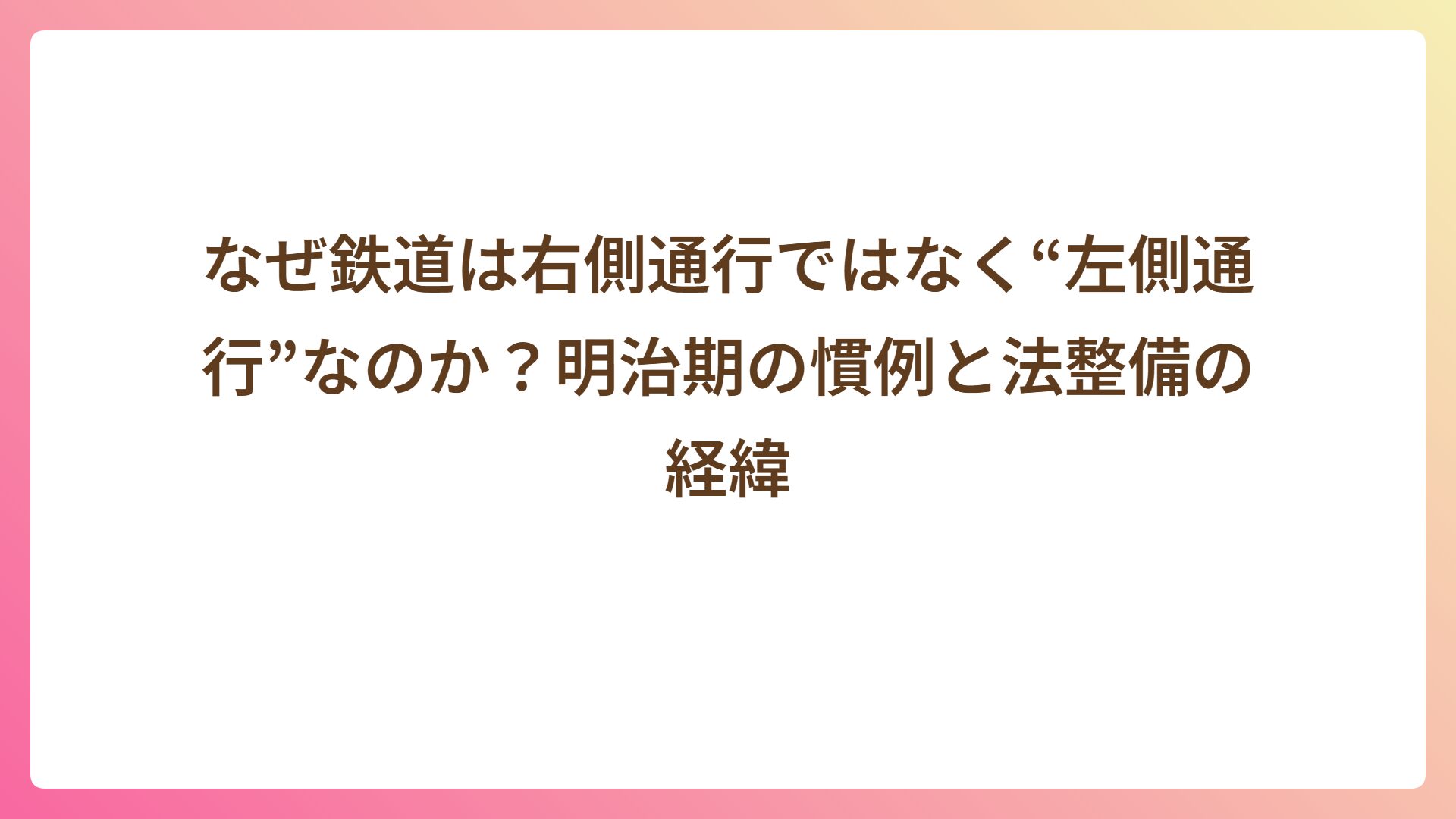
道路では車も鉄道も「左側通行」が基本の日本。
しかし、世界を見渡すと右側通行の国が多い中で、なぜ日本は鉄道まで左側通行になったのでしょうか?
その理由は、明治時代の鉄道導入期にまでさかのぼります。
この記事では、日本の鉄道が左側通行を採用した背景を、歴史・技術・法制度の視点から解説します。
理由①:最初の鉄道が“イギリス式”だったから
日本の鉄道は、1872年(明治5年)に新橋〜横浜間で開業しました。
この鉄道建設を主導したのが、鉄道先進国のイギリスです。
当時のイギリスでは、道路交通・鉄道ともに左側通行が基本でした。
そのため、イギリス人技術者が設計・施工・運転指導を行った日本でも、
- 駅のホーム配置
- 信号機の位置
- 分岐器(ポイント)の向き
などがすべて左側通行前提で作られました。
つまり、日本の鉄道が左側通行になったのは、最初に輸入した技術がイギリス式だったことが最大の理由です。
理由②:初期の“レール配置”が左側前提で定着した
鉄道の線路は、複線の場合「上り線・下り線」が決められています。
イギリス式では、
- 進行方向に向かって左側の線路を使う
- 駅のホームは主に線路の外側に設置する
というルールでした。
この構造がそのまま日本に持ち込まれた結果、
駅舎やホーム、信号システムも左側通行を前提に一体設計されました。
つまり、左側通行が“運転習慣”というよりも、設備設計上の構造ルールとして根付いたのです。
理由③:道路交通も同時期に“左側通行”で統一された
明治時代、日本では鉄道の普及と並行して道路交通も整備されていました。
1872年の鉄道開業から間もなく、1878年に東京府内規則で「左側通行」が明文化され、
後に全国へと広がっていきます。
こうして、
- 鉄道:イギリス式で左側通行
- 道路:警察法令で左側通行
と、両方の交通体系で“左側通行文化”が揃ってしまったのです。
結果として、鉄道も道路も「左側通行」が自然に受け入れられ、現在まで続いています。
理由④:車両設計・運転台の位置も左側に最適化された
鉄道車両の運転台(運転士席)は、基本的に左側にあります。
これは、すれ違う列車や信号を見やすくするためです。
左側通行の環境では、信号やホームが運転士の左手側にあるため、
- 信号確認が容易
- 停車位置の判断がしやすい
という運転上の利点があります。
そのため、車両設計そのものが左側通行前提になり、逆に右側に変えると支障が出てしまうのです。
理由⑤:右側通行の鉄道は“特殊事情”による例外
実は日本でも、右側通行の鉄道がまったくないわけではありません。
たとえば:
- 大阪環状線(JR西日本)の一部区間
- 京阪電鉄の複線トンネル区間
などでは、構造上の制約(勾配・トンネル・線路乗り入れの都合)で右側通行区間が存在します。
しかし、これらはごく一部にとどまり、全国的には左側通行が基本。
鉄道システム全体の整合性を保つため、原則は統一維持されています。
理由⑥:法制度でも“左側通行”が定められている
現在の鉄道に関する法令でも、左側通行が明文化されています。
たとえば、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(国土交通省)」には、
- 信号・保安設備の設置位置
- 列車運転の方向
などが左側通行を前提とした基準で設けられています。
こうした法制度上の根拠があるため、単なる慣習ではなく、法的にも左側通行がルールとして確立しています。
理由⑦:イギリス以外にも“左側通行”を採用する国が多い鉄道圏
実は、鉄道で左側通行を採用しているのは日本だけではありません。
イギリスの影響を受けた国々、例えば:
- オーストラリア
- インド
- 南アフリカ
なども、鉄道は左側通行です。
逆にフランスやドイツ、アメリカなどは右側通行が主流。
つまり、鉄道の通行方向は「どの国の技術を導入したか」で決まる」という歴史的背景があります。
まとめ:鉄道の左側通行は“歴史と制度が固めた標準”
鉄道が右側通行ではなく左側通行なのは、
- 明治期にイギリスの鉄道技術を導入したこと
- 設備設計・信号配置が左側通行前提で作られたこと
- 道路交通と整合した交通ルールが整備されたこと
- 法令でも左側通行が基準化されたこと
といった複合的な理由によります。
つまり、日本の鉄道が左側通行なのは偶然ではなく、
“最初の選択が今も続く、歴史と制度の必然”なのです。