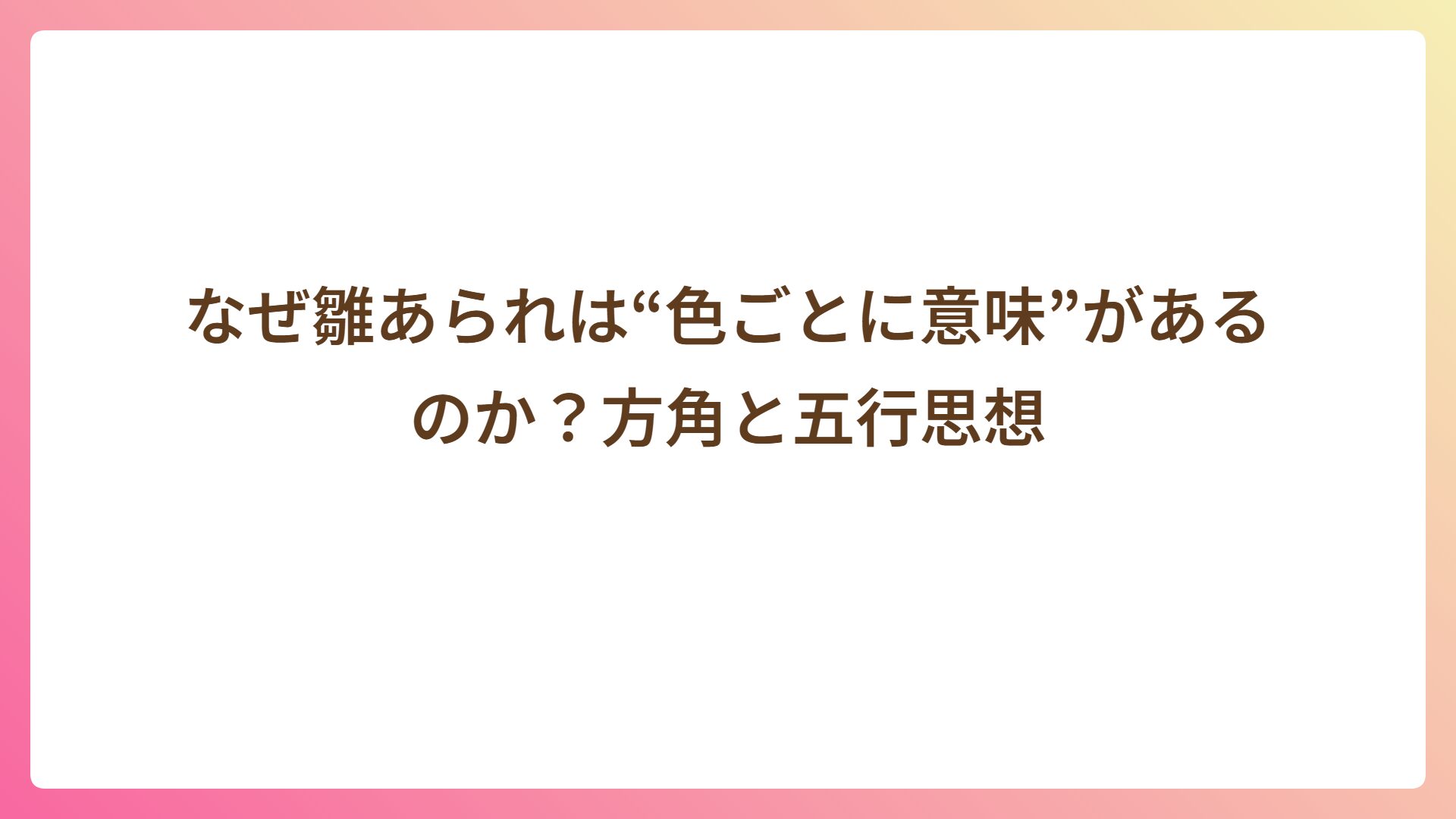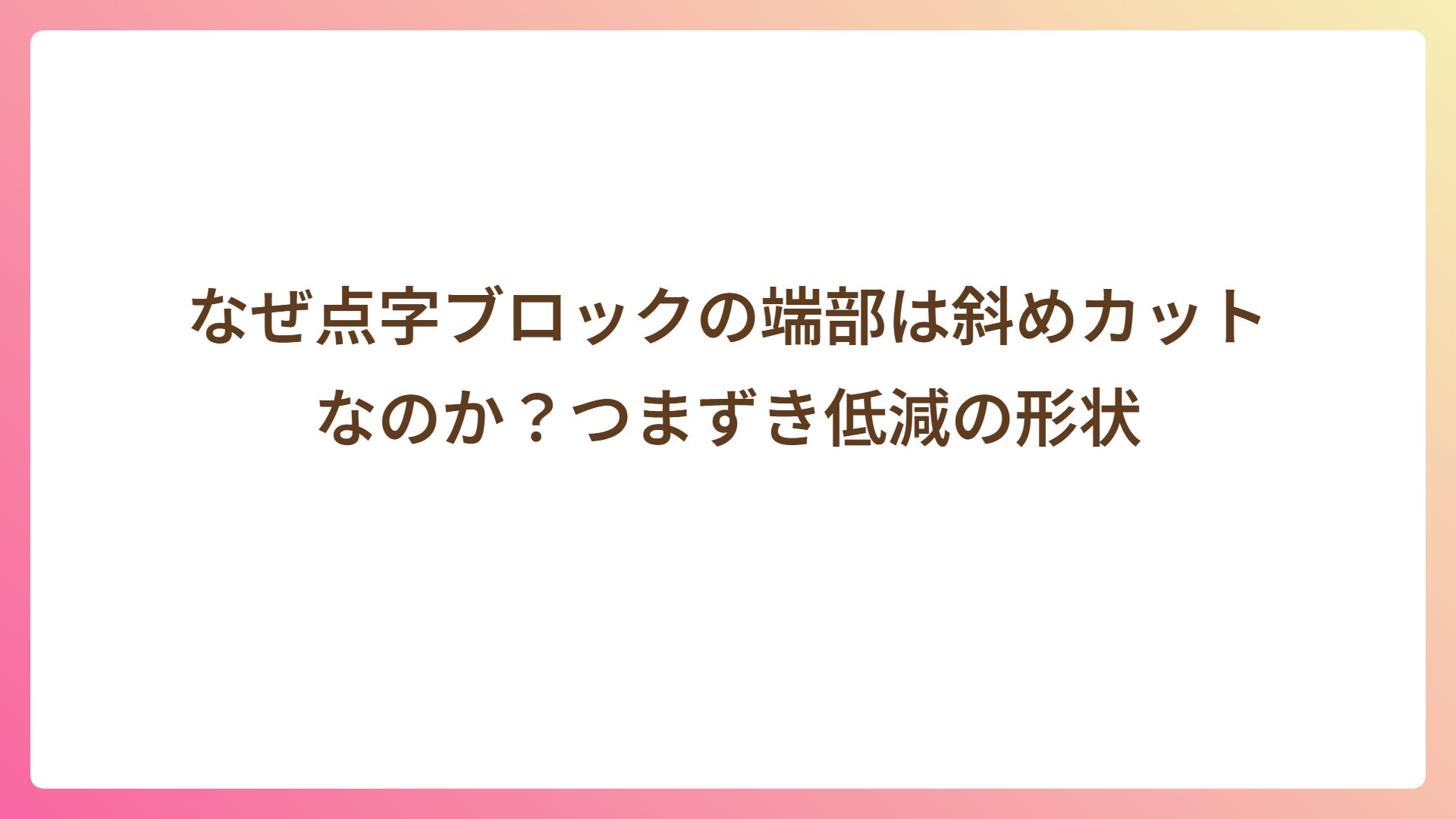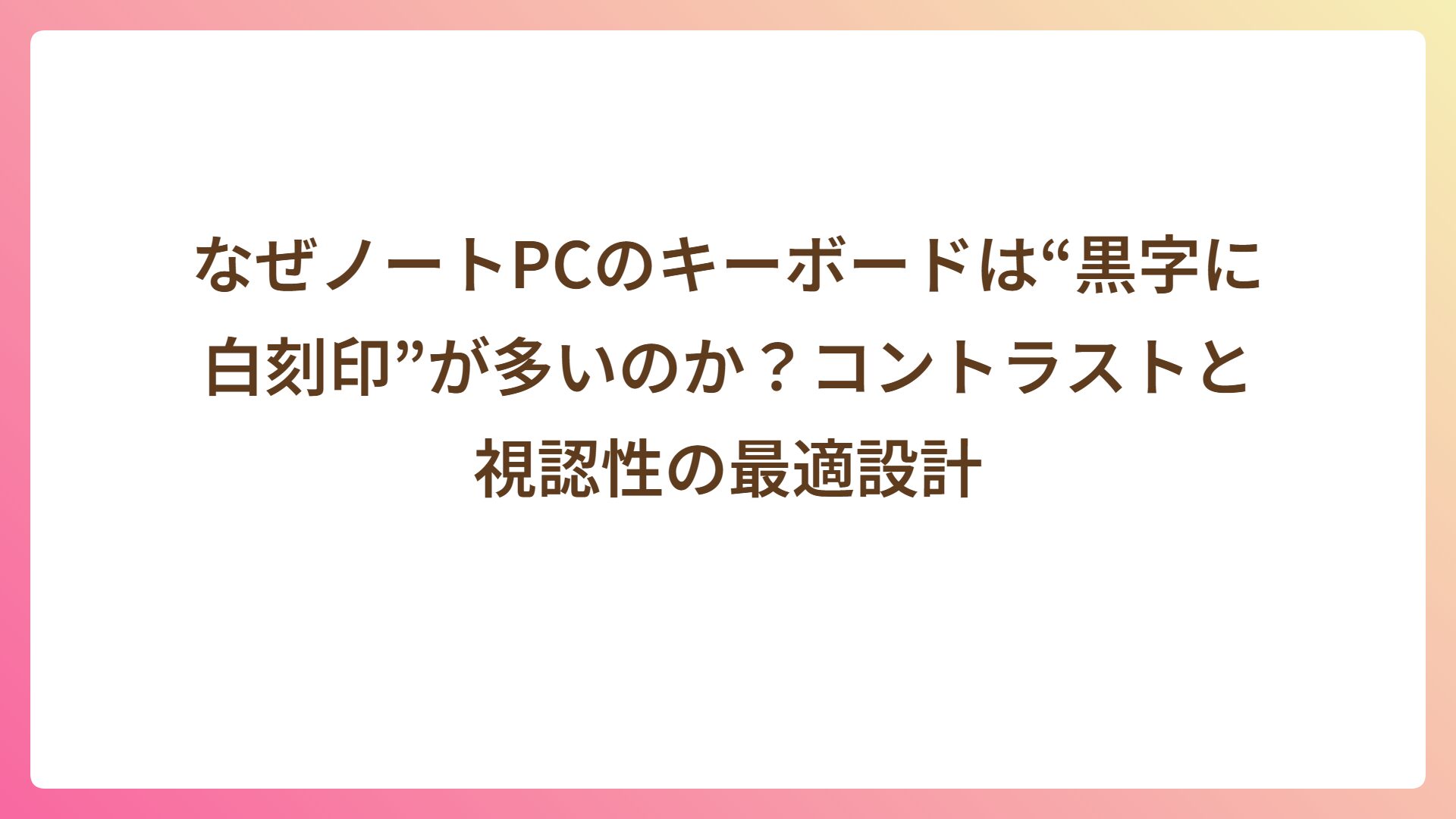なぜ横断歩道手前の路面に“ドット減速標示”があるのか?視覚的速度制御
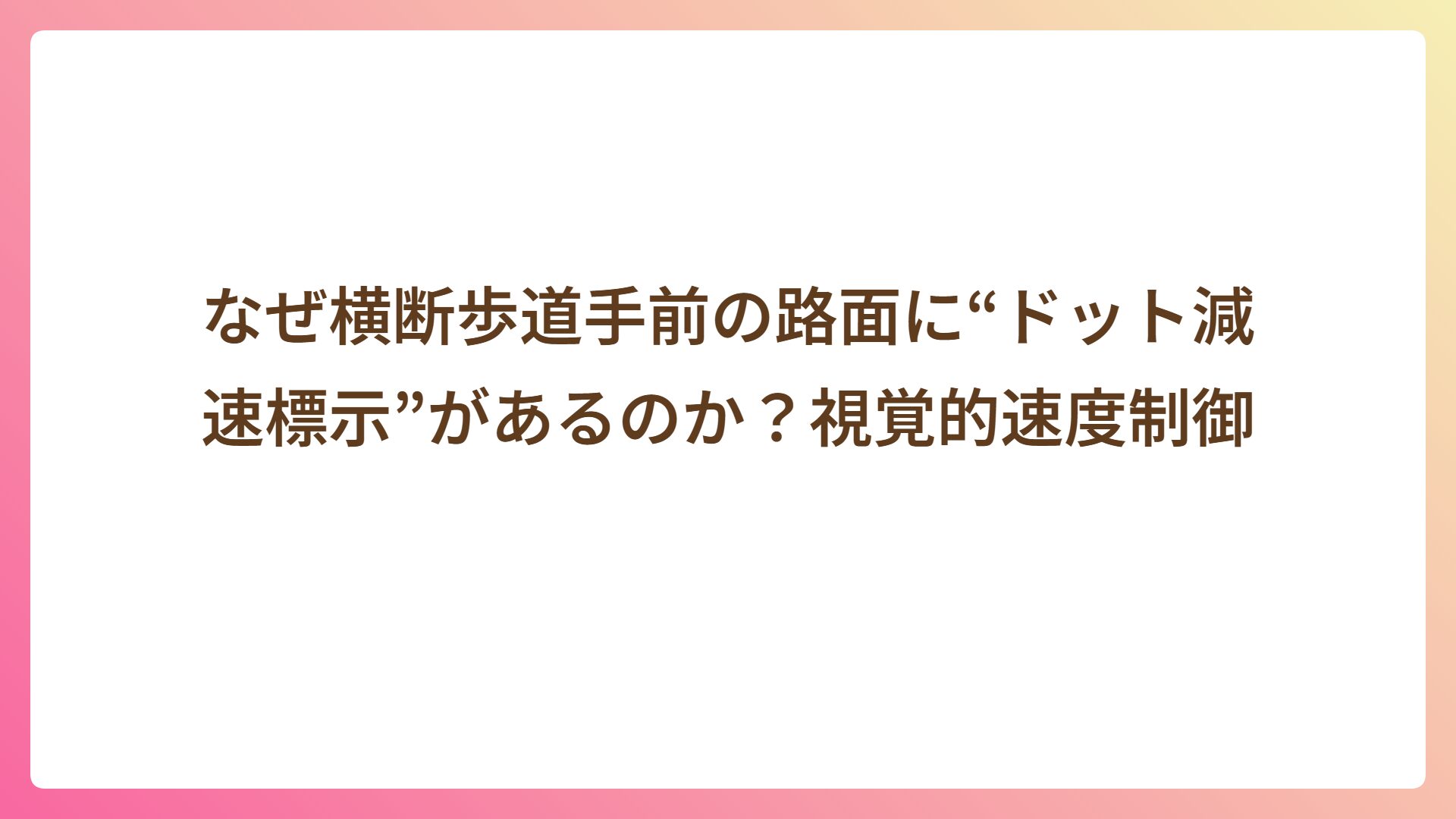
横断歩道の手前の路面に、白いドットや短い線が等間隔で描かれているのを見たことがあるでしょう。
一見ただの模様のようですが、実はあれはドライバーに**減速を促すための“錯覚設計”**です。
この「ドット減速標示」には、人間の視覚反応とスピード感覚のズレを巧みに利用した交通安全の仕掛けが隠されています。
ドット減速標示とは?
ドット減速標示とは、横断歩道や交差点の手前に設置される路面標示型の減速誘導サインです。
白い円や短線が等間隔に並び、前方へ進むにつれてその間隔が徐々に狭くなるように描かれています。
この配置がドライバーに「スピードが上がったように感じる錯覚」を起こさせ、無意識のうちにブレーキを踏ませるのです。
視覚錯覚を利用した“心理的ブレーキ”
人間は等間隔の模様を通過する際、その見え方の変化をスピード感の指標として感じ取ります。
間隔が狭まるにつれて模様が「流れる」ように見えるため、
「思っているよりスピードが出ている」と錯覚し、自然と減速行動が引き出されるのです。
この効果は「オプティカルリダクション(視覚的減速)」と呼ばれ、
物理的な段差や音によらず、心理的に速度をコントロールできる手法として注目されています。
実際の設計基準と効果
国土交通省の実験では、ドット減速標示を設置した区間では平均車速が時速5〜10km程度低下することが確認されています。
また、模様の形状や間隔は走行速度帯に応じて設計されており、
・30km/h以下の生活道路 → ドット径10〜15cm、間隔1〜2m
・50km/h前後の幹線道路 → ドット径20cm前後、間隔2〜3m
といった基準で調整されます。
ドットは耐摩耗性の高い熱可塑性樹脂で作られ、夜間でも視認できるよう反射ビーズを混ぜた塗料が使用されています。
振動や騒音を出さずに減速を促すメリット
従来の「減速帯(ハンプ)」や「ランブルストリップ」は、車体の振動や騒音を伴うため、住宅街では設置が難しいという課題がありました。
ドット減速標示は視覚的な効果のみでドライバーの行動を変えるため、静かで環境に優しい減速手段として採用が広がっています。
また、バイクや自転車でも安全に通過できるのも大きな利点です。
海外でも採用される“錯覚設計”
この手法は日本だけでなく、イギリスやオランダなどのヨーロッパ諸国でも導入されています。
特にスクールゾーンやトンネル出口など、「意識的なブレーキを促したい場所」で効果的に使われています。
国によっては白だけでなく黄色や青を使い、より強い注意喚起を狙うケースもあります。
まとめ
横断歩道手前の「ドット減速標示」は、模様の間隔を変化させてスピード感を錯覚させる“視覚的速度制御”の仕組みです。
ドライバーの心理に働きかけて、自然に減速を促す——それがこのデザインの狙い。
見た目は地味でも、交通安全を支える人間工学と心理学の融合技術なのです。