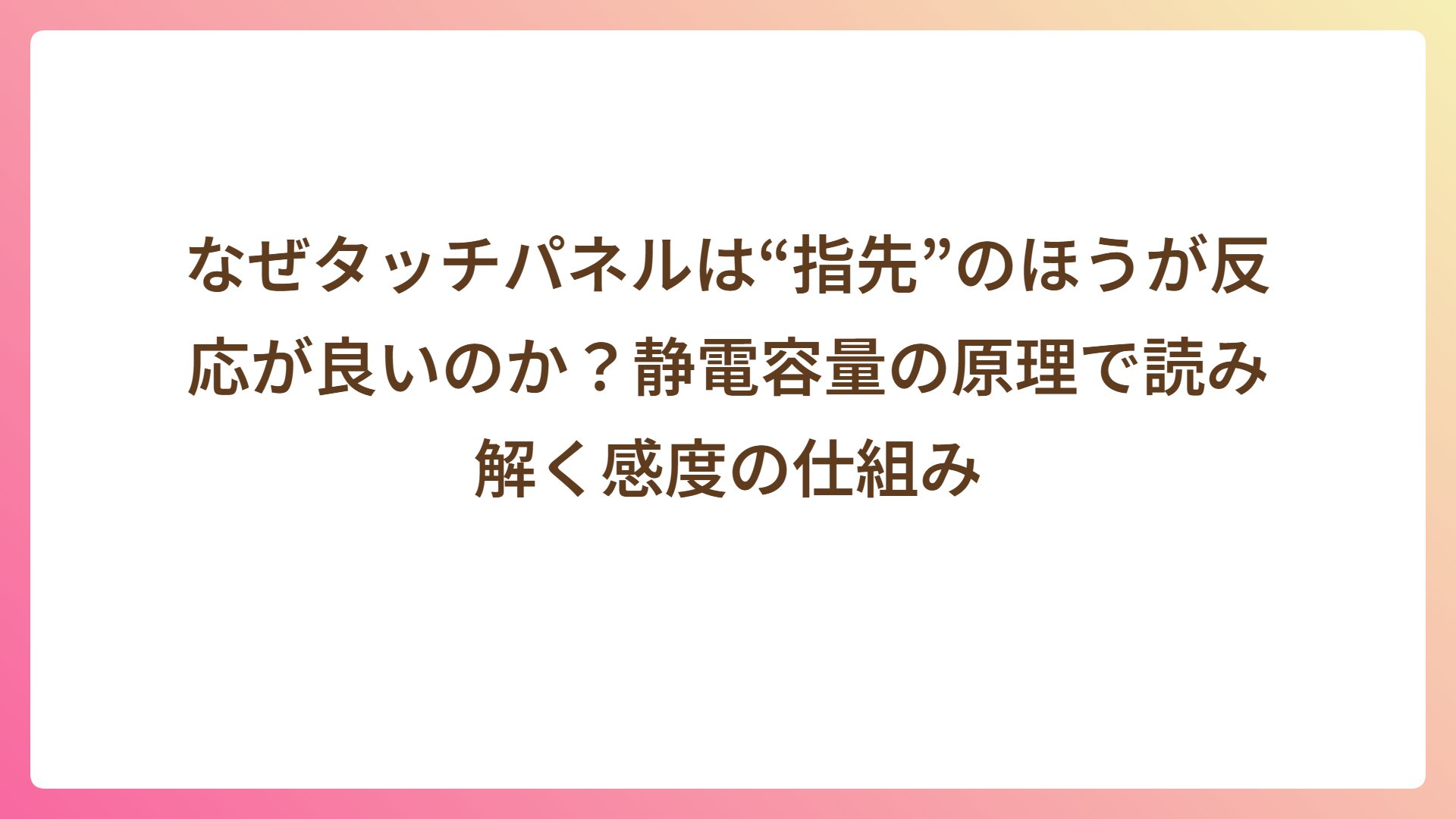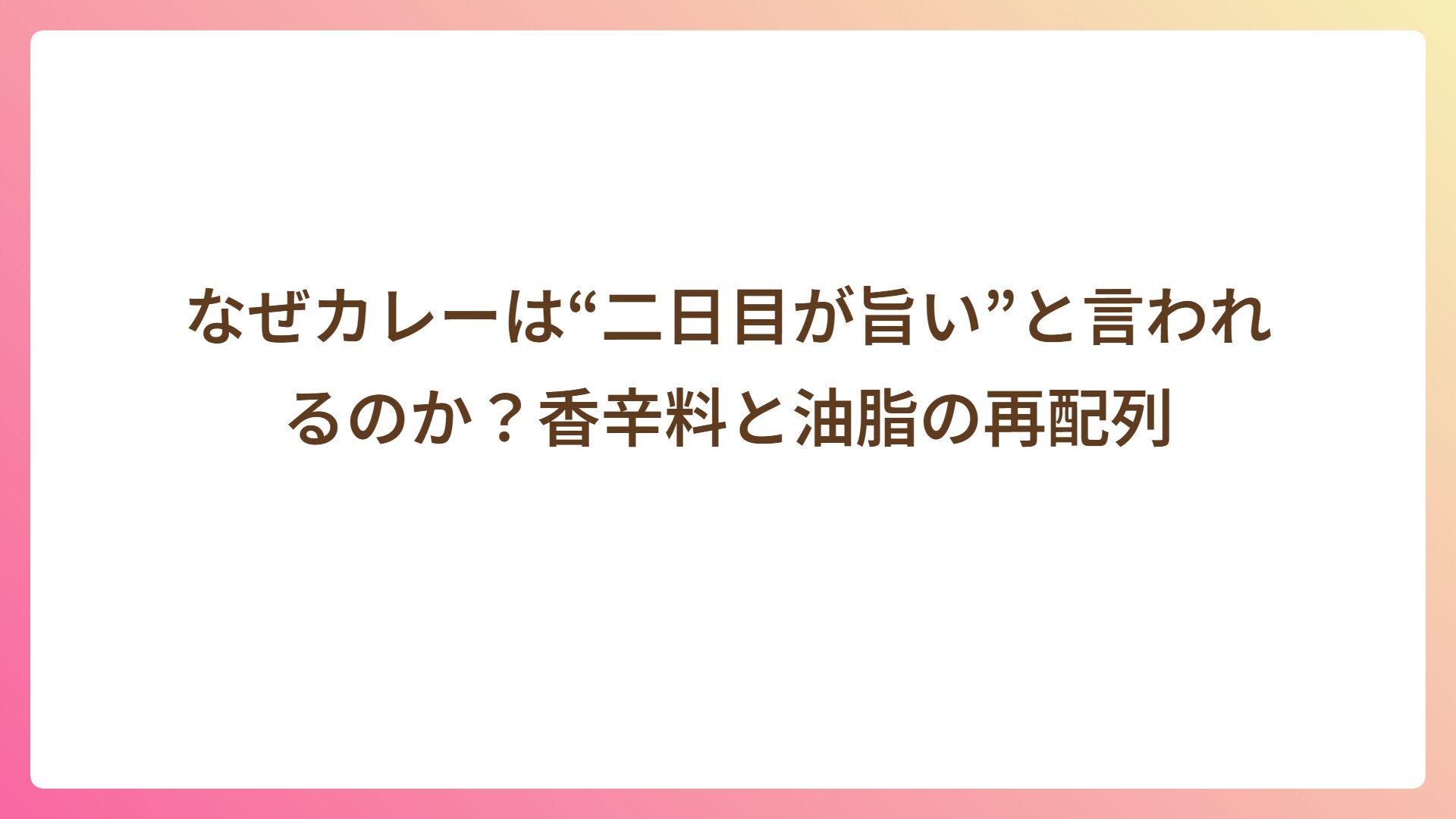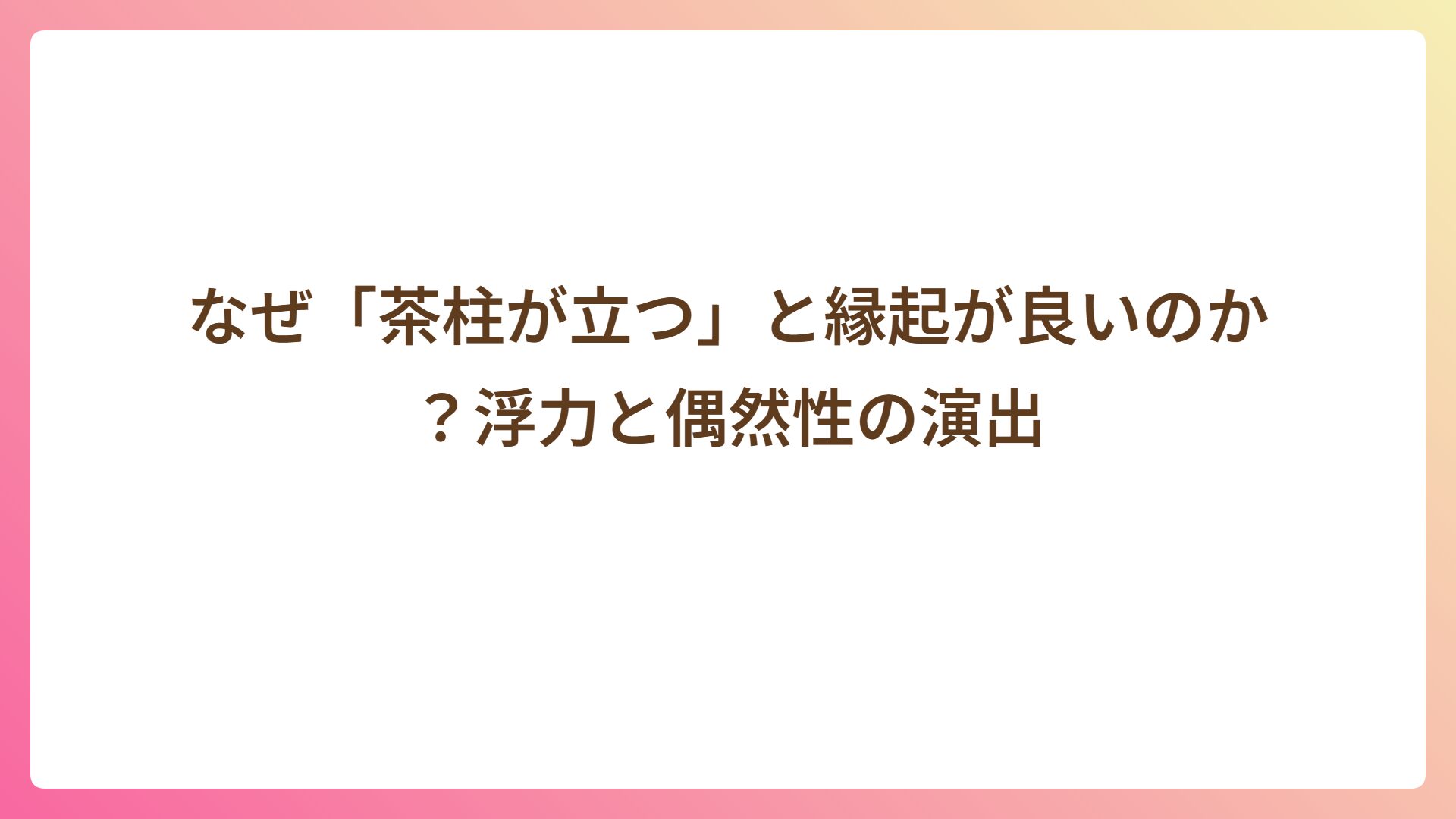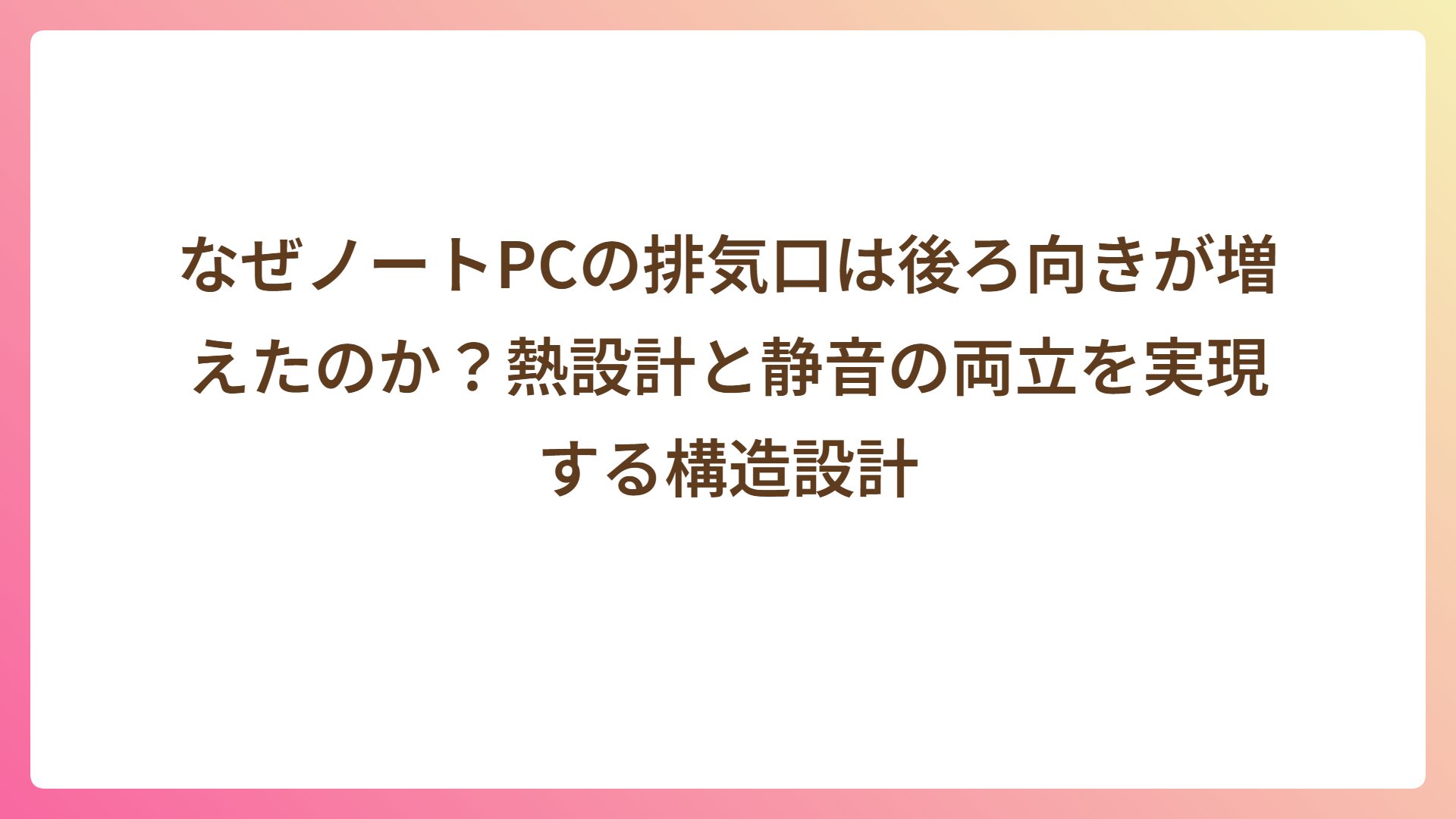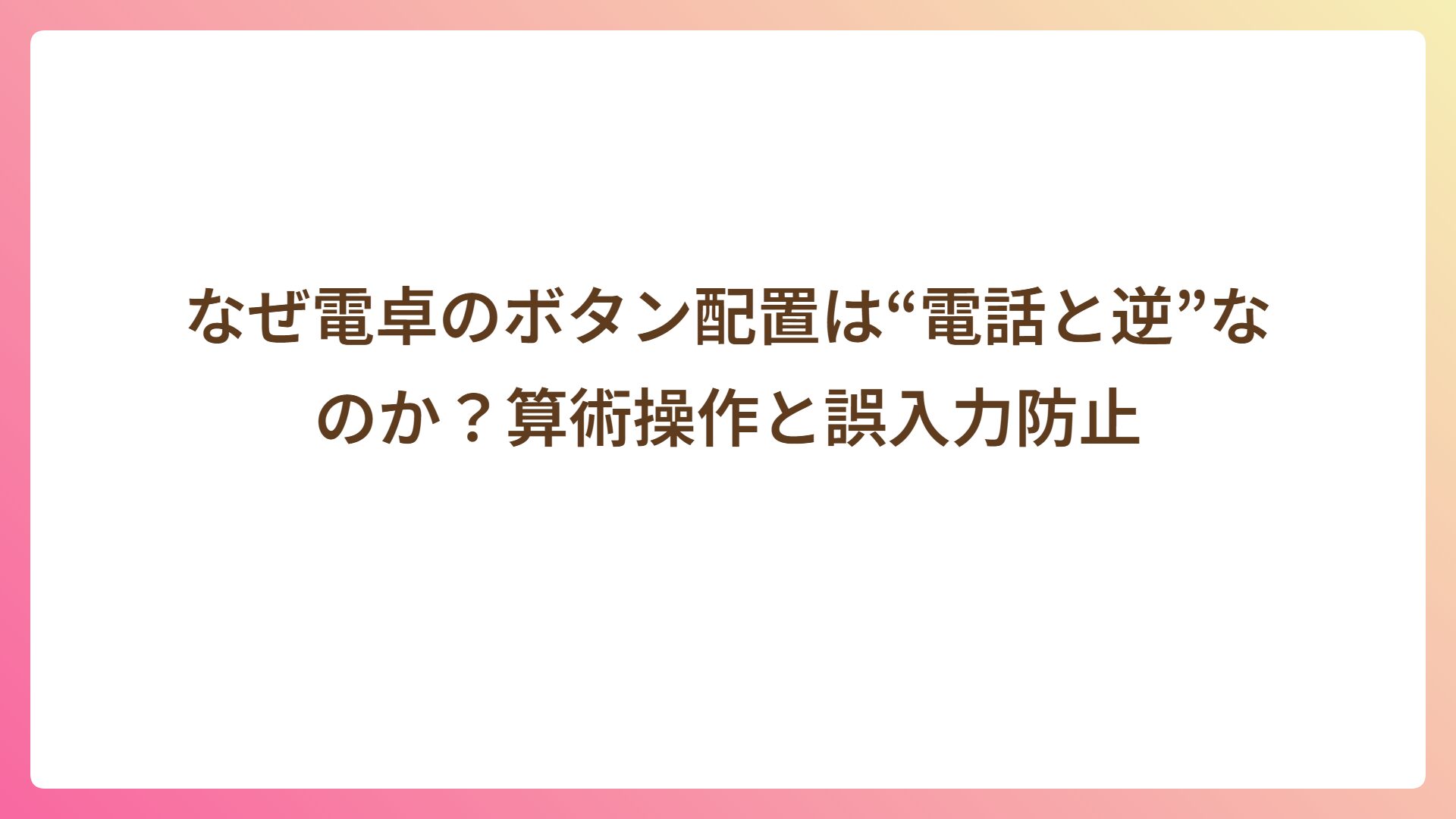なぜ缶コーヒーは“微糖表示”が細かいのか?糖類基準と表示ルール
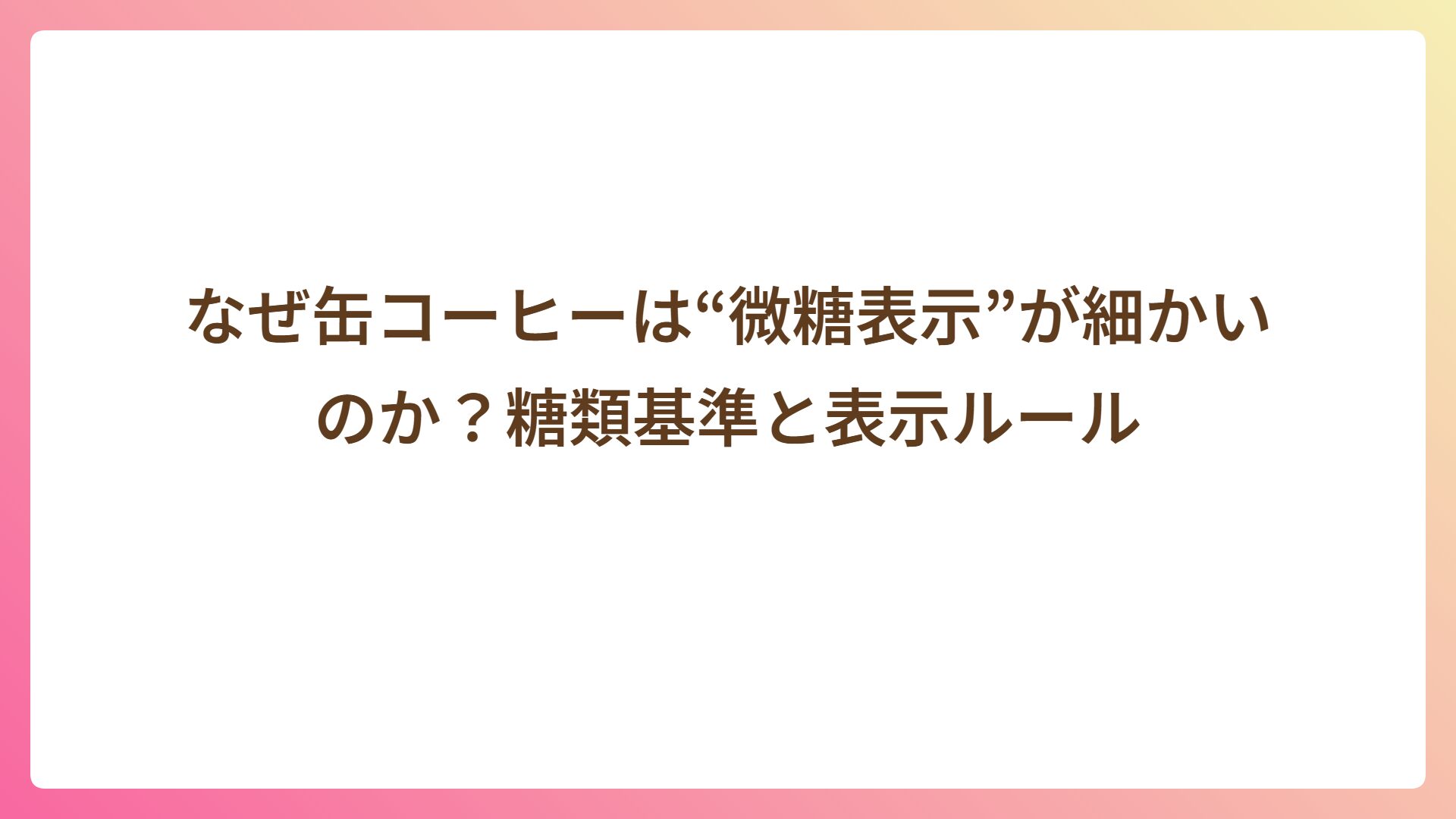
缶コーヒーを選ぶとき、「微糖」「低糖」「甘さひかえめ」など似たような表記が並んでいて、どれが本当に甘くないのか迷うことがあります。
なぜここまで細かく分類されているのでしょうか?
実はこの“微糖表示”には、法律で定められた糖類基準と自主ルールの両方が関係しているのです。
「微糖」は法律で定められた正式な区分ではない
まず押さえておきたいのは、「微糖」や「低糖」という言葉自体は法律上の正式な栄養表示区分ではないということです。
厚生労働省や消費者庁の「栄養成分表示制度」では、糖類について以下のような明確な定義があります。
- 糖類ゼロ(無糖):100mlあたり糖類0.5g未満
- 低糖:100mlあたり糖類2.5g以下
一方、「微糖」や「甘さひかえめ」は法的な定義ではなく、
業界団体(日本缶詰びん詰レトルト食品協会)などが自主基準として設けた用語です。
そのため、メーカーごとに若干の差がありますが、一般的には100mlあたり糖類1g前後が「微糖」として扱われています。
なぜ“微糖”が細かく分けられているのか
缶コーヒーは嗜好品であり、「甘さの感じ方」には個人差が大きい商品です。
そのためメーカーは、味覚の印象を正確に伝えるために糖類量を段階的に区分しています。
例えば、
- 「微糖」:糖類0.8〜1.2g/100ml前後
- 「低糖」:2g前後
- 「甘さひかえめ」:2.5〜3g前後
といったように、ほんの数グラムの違いが“味の印象”を左右するのです。
特にブラック派の人が「ほんの少し甘いのが欲しい」と思ったときに選ぶのが「微糖」であり、
メーカー側もこの微妙なゾーンを狙って幅広い層を取り込むマーケティング戦略をとっています。
糖類と炭水化物の表示の違い
缶コーヒーの成分表示を見ると、「炭水化物」「糖類」の2つが書かれている場合があります。
ここで注意すべきは、炭水化物=糖類+食物繊維などの総称であり、
糖類だけを減らしても炭水化物の値が変わらないこともあるという点です。
つまり「糖類オフ」や「微糖」と書かれていても、
でんぷんやオリゴ糖など他の炭水化物が含まれていれば、カロリー的にはそれほど変わらない場合もあるのです。
消費者庁のガイドラインによる制約
「微糖」などの表記を使う際には、誤認防止のためのルールも存在します。
消費者庁の食品表示基準では、実際の糖類含有量に基づいた根拠資料を提出できることが求められています。
つまり、「微糖」と表示するからには、
・他社や通常品より糖類が少ない
・100mlあたりの糖類量が明確に低い
ことをデータで示さなければならないのです。
このため、メーカー各社は製品開発段階で糖度測定(Brix値)や官能評価を行い、
「どこまで甘さを抑えたら“微糖”と感じられるか」を科学的に検証しています。
甘味料の種類も“微糖感”を左右する
糖類を減らすだけでは味が物足りなくなるため、人工甘味料や天然甘味料(アセスルファムK、ステビアなど)を併用して、
砂糖の半分以下の量でも“甘く感じる”味設計が行われています。
このバランス調整によって、糖類表示上は低くても口当たりの甘さを保てるのです。
まとめ
缶コーヒーの“微糖表示”が細かく分かれているのは、
法律で定められた糖類基準と、業界独自の自主ルールを両立させるためです。
おいしさと健康志向の両立を図る中で、「ゼロでも甘すぎず、甘くなさすぎない」絶妙な中間地帯を狙ったのが“微糖”。
そのわずかな数値差の裏には、味覚・表示・規格の三点を精密に調整する技術と戦略が息づいているのです。