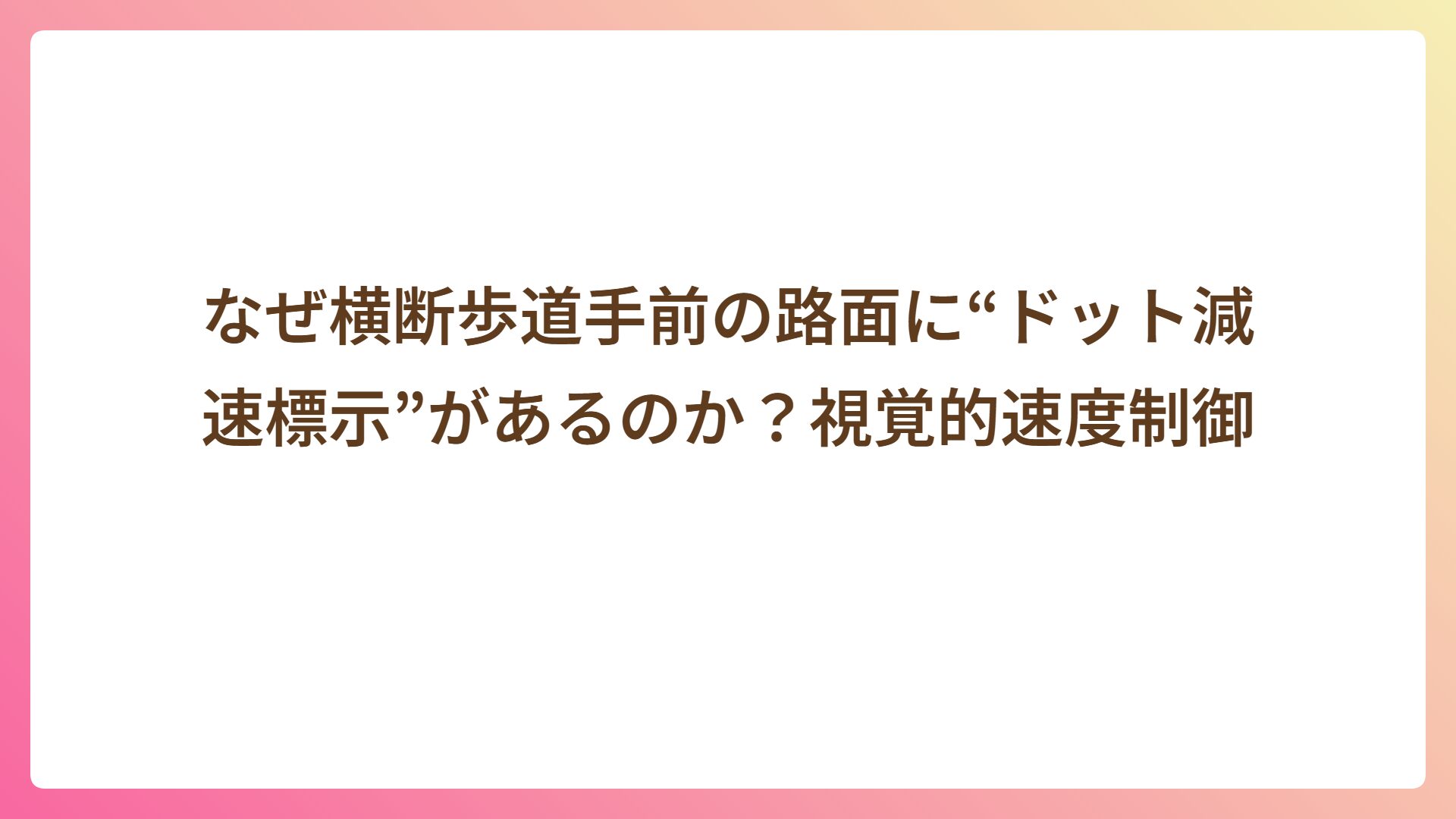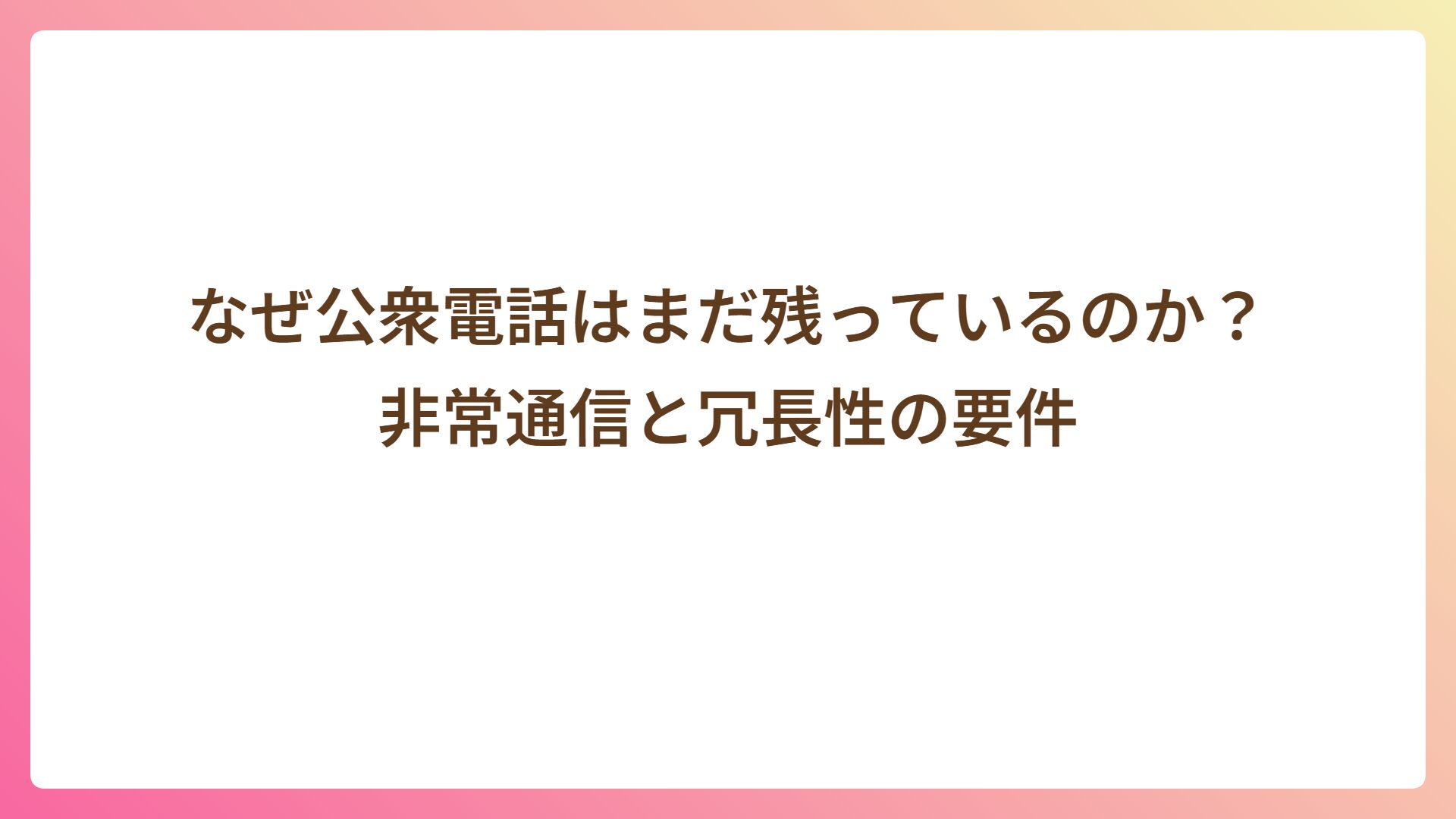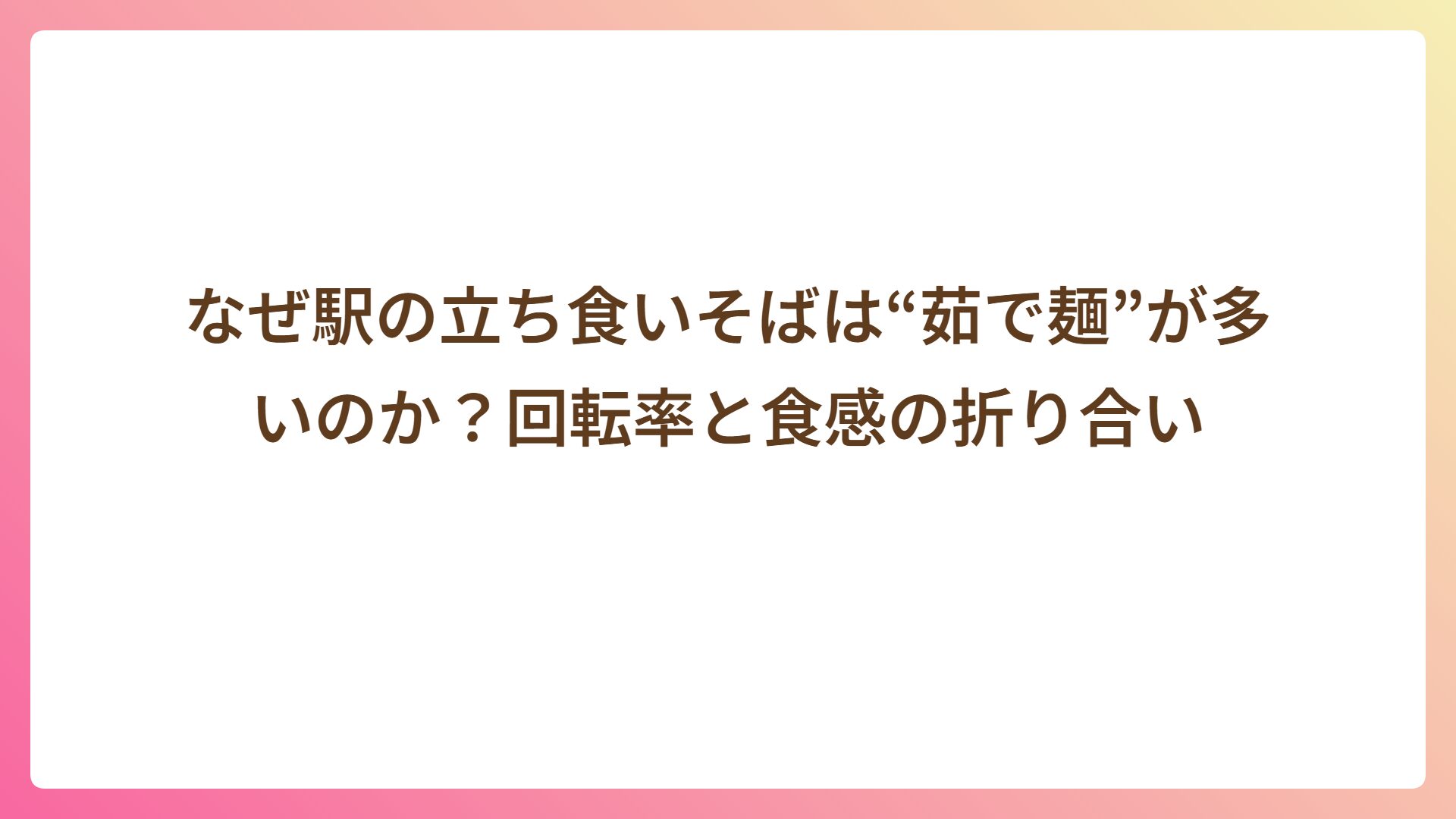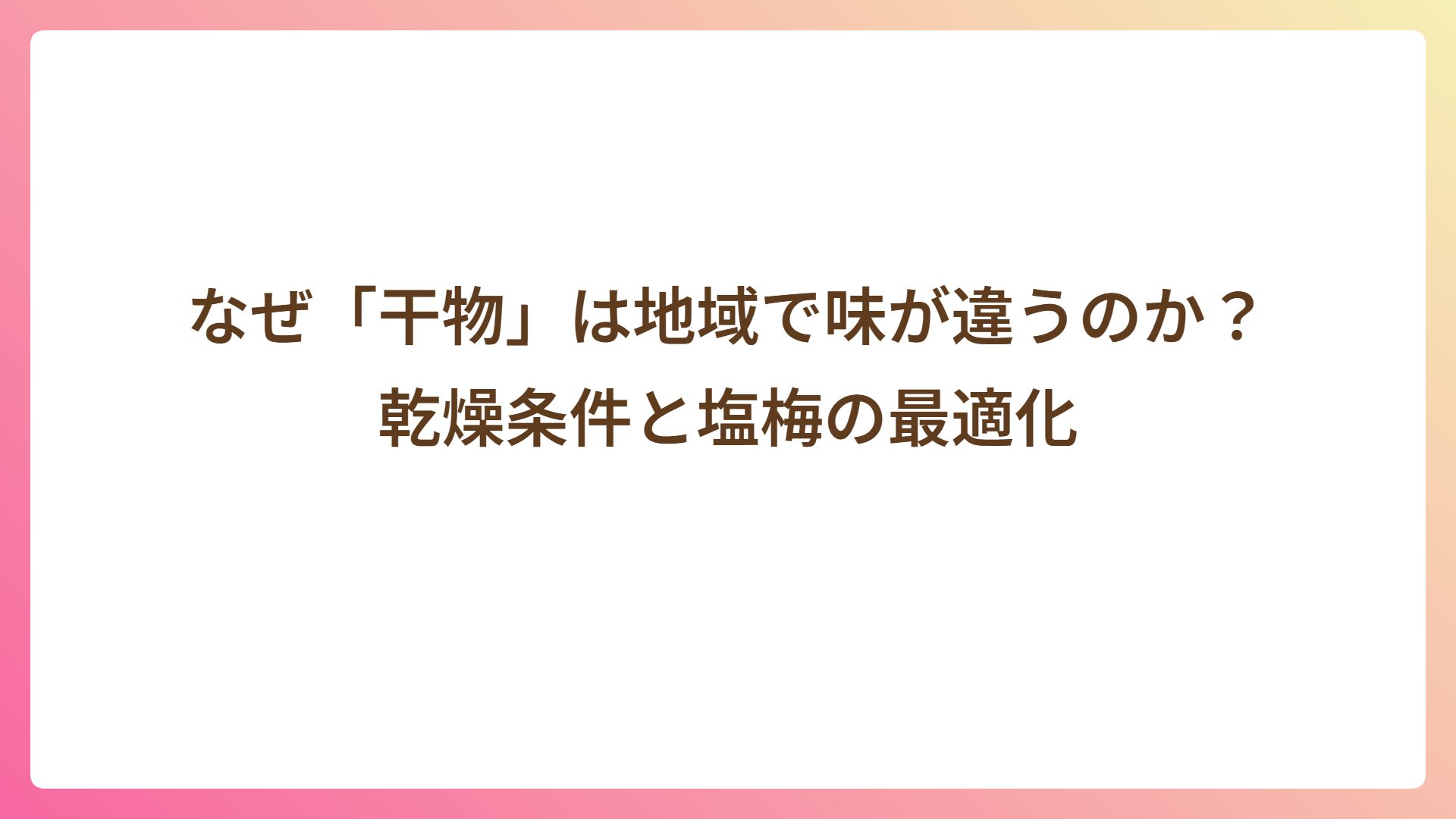なぜ電車の優先席は「吊り広告」が少ないのか?視界と注意喚起のデザイン
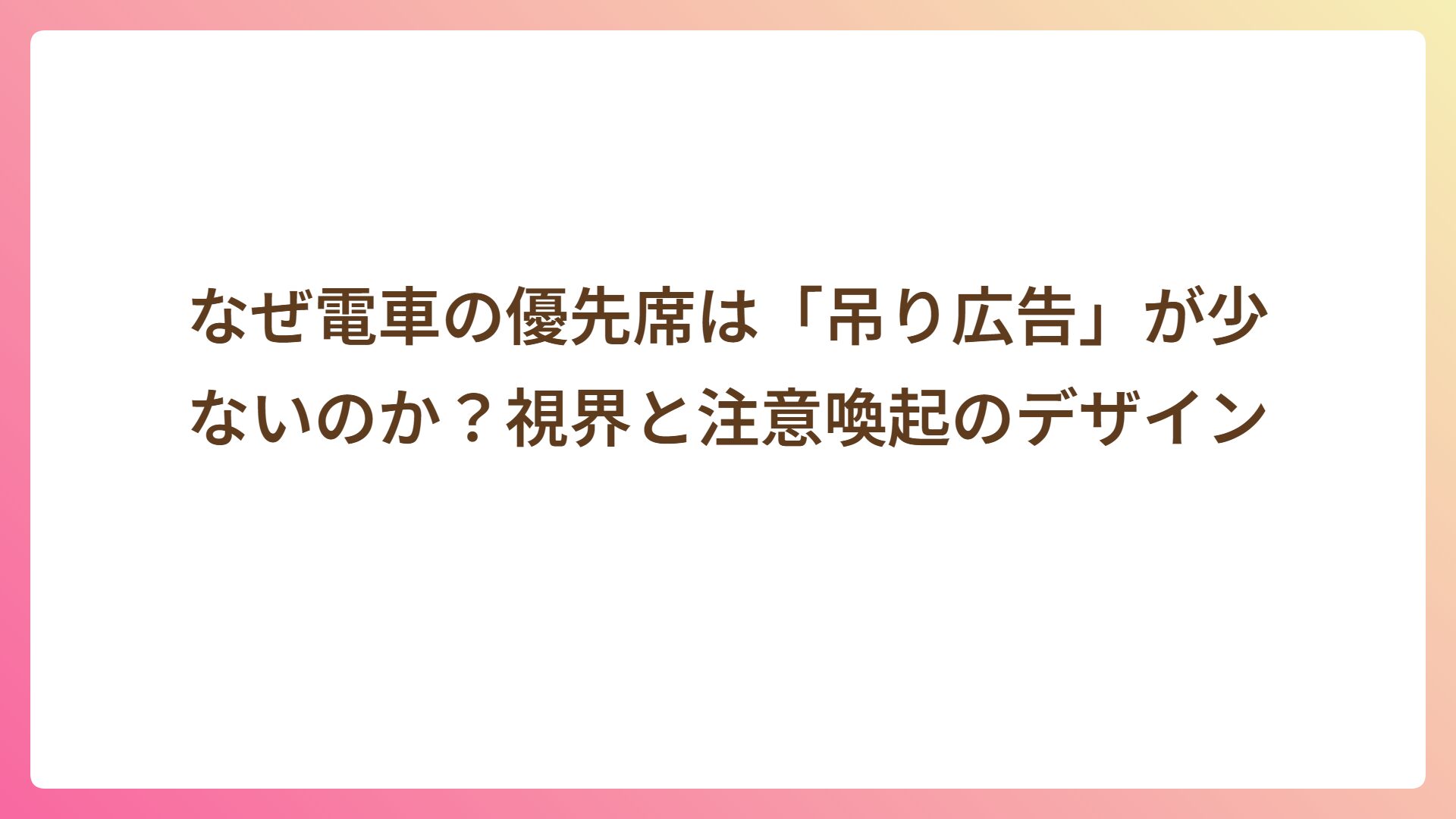
電車に乗ってふと見上げると、優先席の上だけ吊り広告が少ない、あるいはまったくないことに気づくことがあります。
座席の構造も同じなのに、なぜここだけ違うのでしょうか?
それは、高齢者・障害者・妊婦など、配慮が必要な利用者の視界と安全を守るためのデザインだからです。
優先席付近は“視界を広く保つ”設計
吊り広告が少ない最大の理由は、立っている人の視界を確保するためです。
優先席付近には、杖を持った人、バランスを取りづらい人、または補助者と一緒に立つ人など、
周囲の状況を常に確認したい利用者が多く集まります。
吊り広告があると視線を遮りやすく、
・座席の空きが見えにくい
・降車時にドア位置が把握しづらい
・周囲の人との距離感がつかみにくい
といった支障が生じることがあります。
そのため、鉄道会社では優先席付近を**広告よりも安全性を優先した“開放エリア”**として扱っているのです。
注意喚起サインを“目立たせる”目的も
優先席の真上には、必ずといっていいほど「優先席マーク」や「スマートフォン電源OFF推奨」などの掲示があります。
吊り広告を設けると、これらのサインが隠れてしまうため、
掲示物を見やすく保つ目的でも吊り広告を減らす設計がされています。
特に、目線の高さに配置される「優先席案内ステッカー」や「吊り下げピクトグラム」は、
遠くからでも認識できるようにするため、周囲をあえて“空ける”ことがデザイン上のルールになっています。
揺れや接触のリスクを減らす
優先席の上は、立っている乗客が比較的多く集まる場所でもあります。
吊り広告があると、つり革や広告の角に頭や手がぶつかる危険が生じやすくなります。
特に杖を持つ人や体のバランスをとるのが難しい人にとっては、
視界を遮るだけでなく不意の接触リスクを高める要因となるのです。
こうした理由から、JR東日本や大手私鉄では
「優先席上部は吊り広告を設けない」または「軽量短冊タイプのみ可」など、
社内規定として明文化している例もあります。
落ち着いた“空間デザイン”としての役割
広告を減らすことは、心理的にも大きな効果をもたらします。
優先席付近は、体調のすぐれない人や妊婦など、静かで落ち着いた空間を必要とする利用者が座る場所です。
そのため、色味の強い広告や点滅照明を避け、視覚刺激を抑えた穏やかなゾーン設計が好まれています。
近年の新型車両では、優先席エリアだけ照明を少し落としたり、
吊り広告を減らして「落ち着き」「配慮」を演出するユニバーサルデザイン的アプローチも採用されています。
鉄道広告業の視点から見た合理性
広告面積を減らすことは一見マイナスのようですが、
鉄道会社にとっても「苦情や事故リスクの低減」という大きなメリットがあります。
特に優先席付近は視線が集中しやすく、トラブルが発生した際に企業イメージへ影響が及ぶため、
広告よりも安全設計を優先する方が合理的と判断されているのです。
また、近年ではデジタルサイネージの導入が進み、
優先席以外のエリアで高効率に広告を表示できる仕組みが整ったことも、この配置に拍車をかけています。
まとめ
電車の優先席に吊り広告が少ないのは、
視界の確保・注意喚起・心理的安心感を重視した空間設計だからです。
単なる“広告スペースの省略”ではなく、
利用者の安全と快適さを第一に考えた、公共交通デザインの最適解なのです。