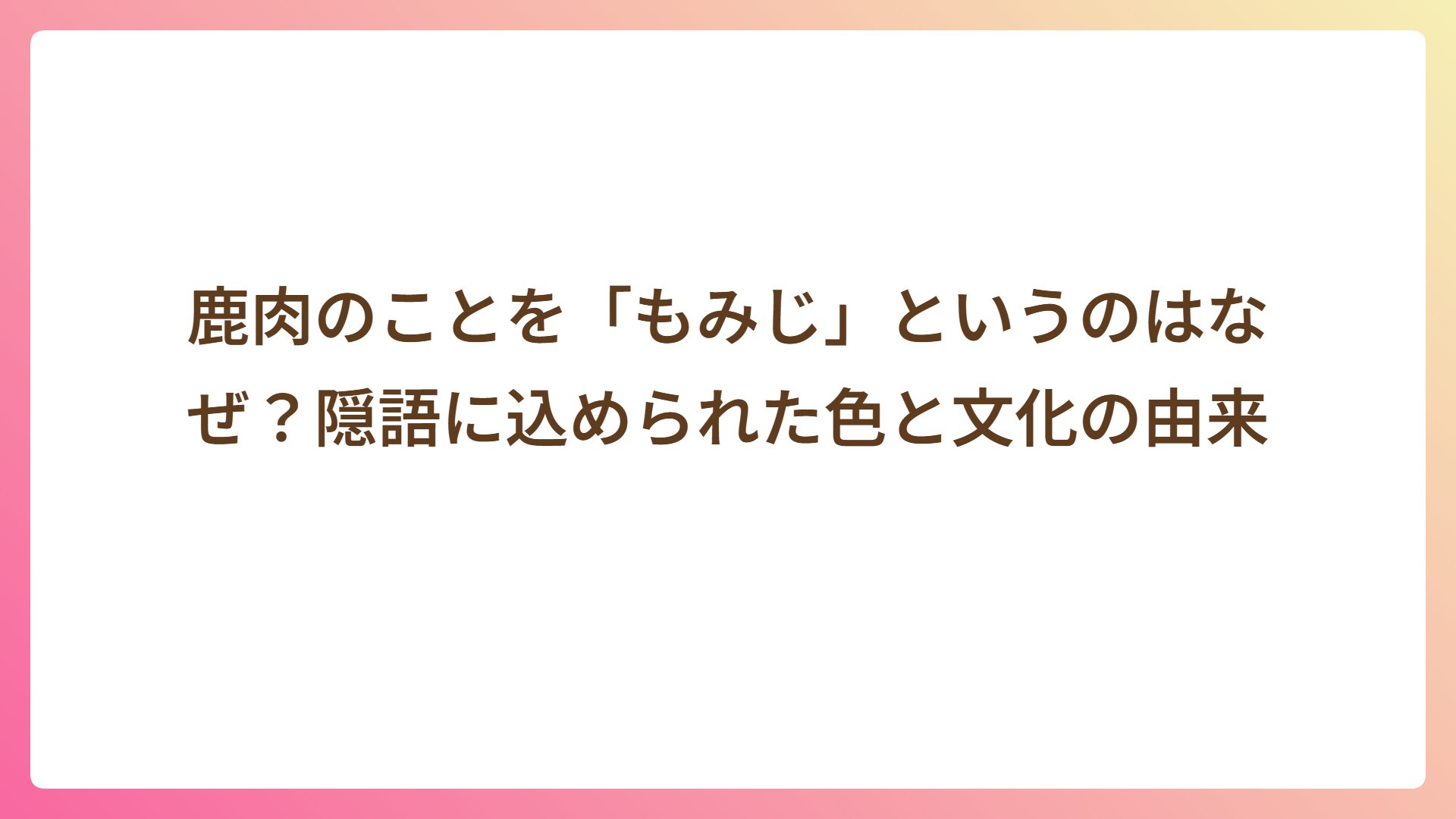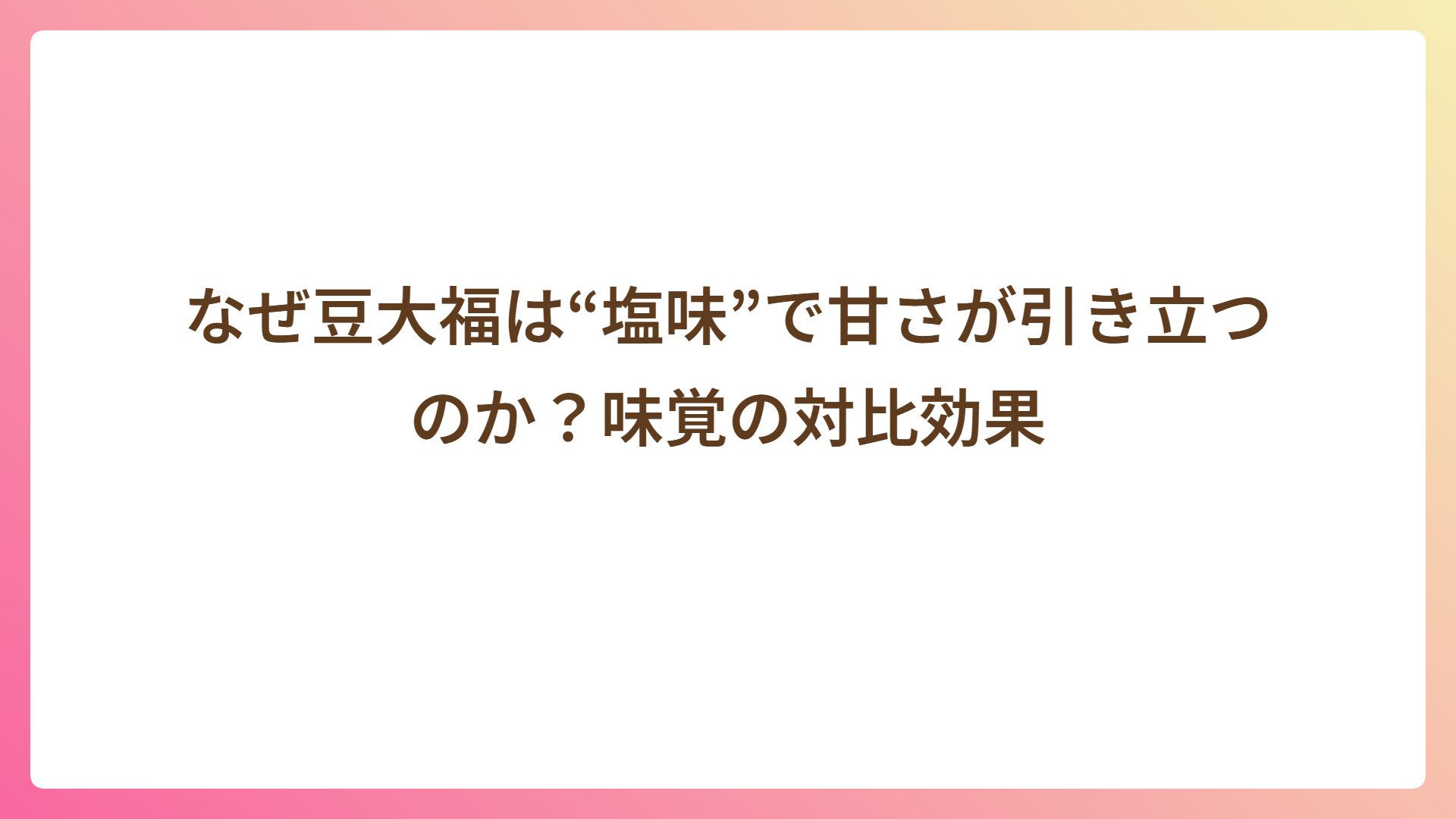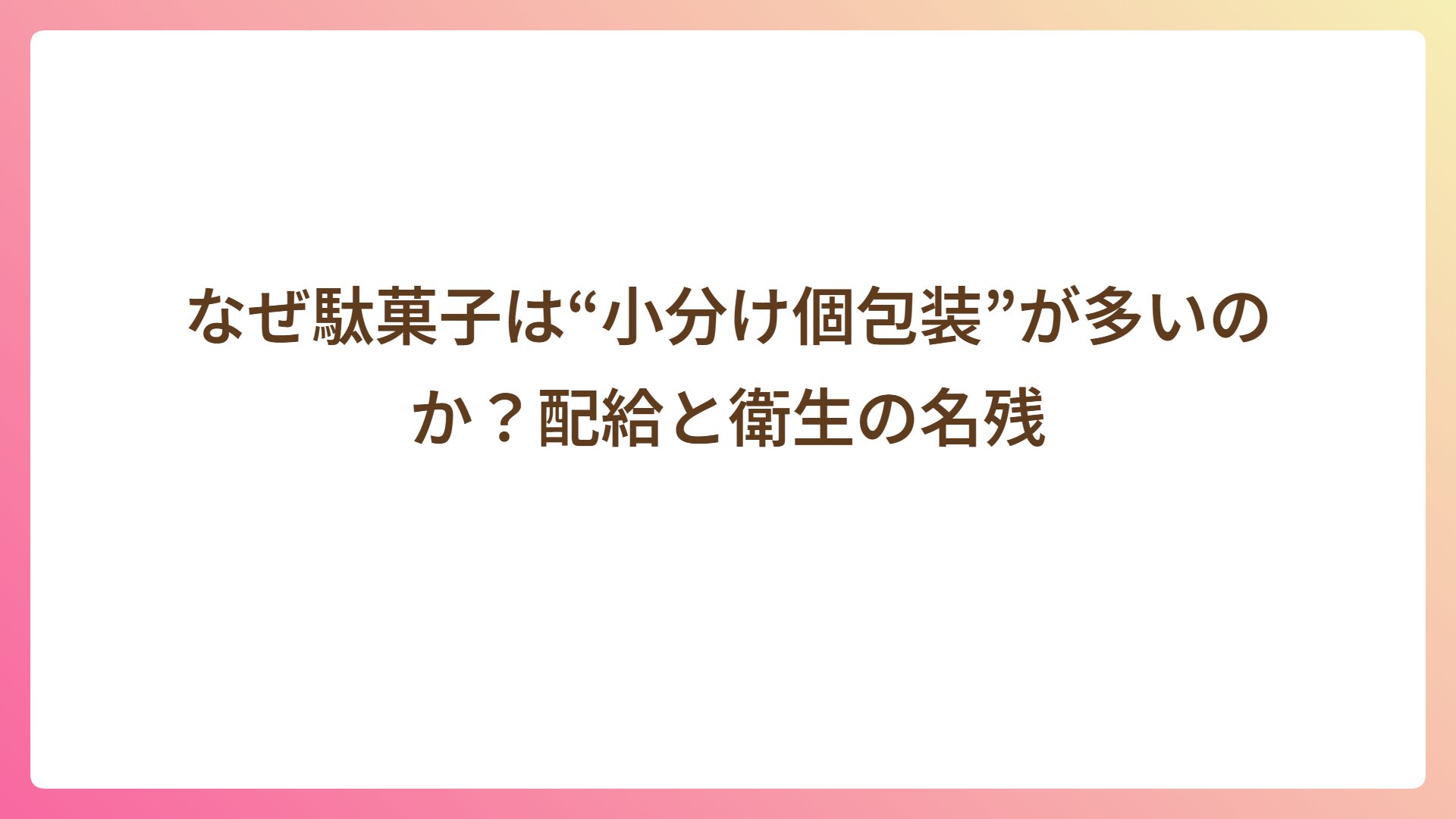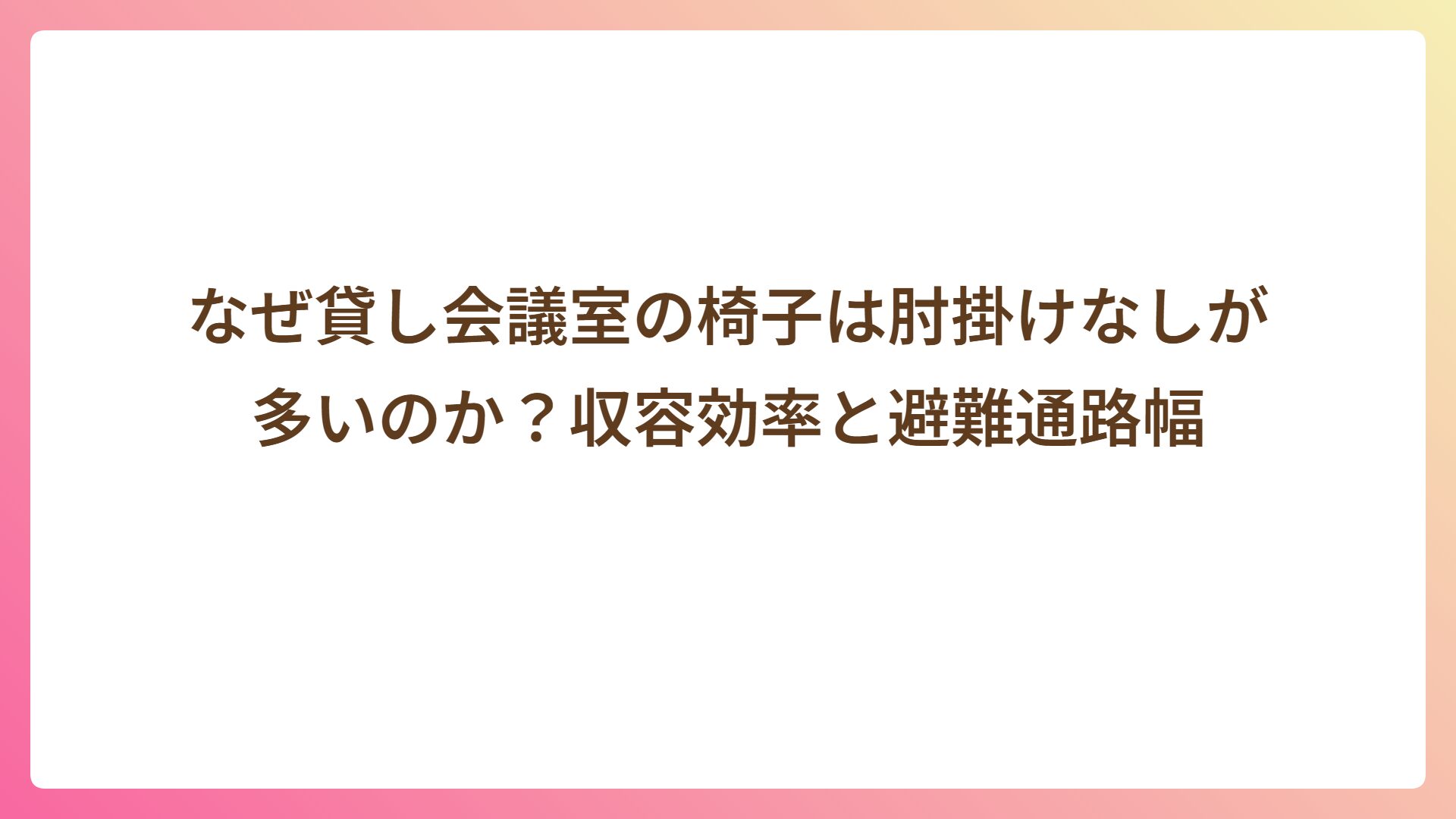なぜ食洗機対応と非対応の食器があるのか?樹脂の耐熱と塗装の密着
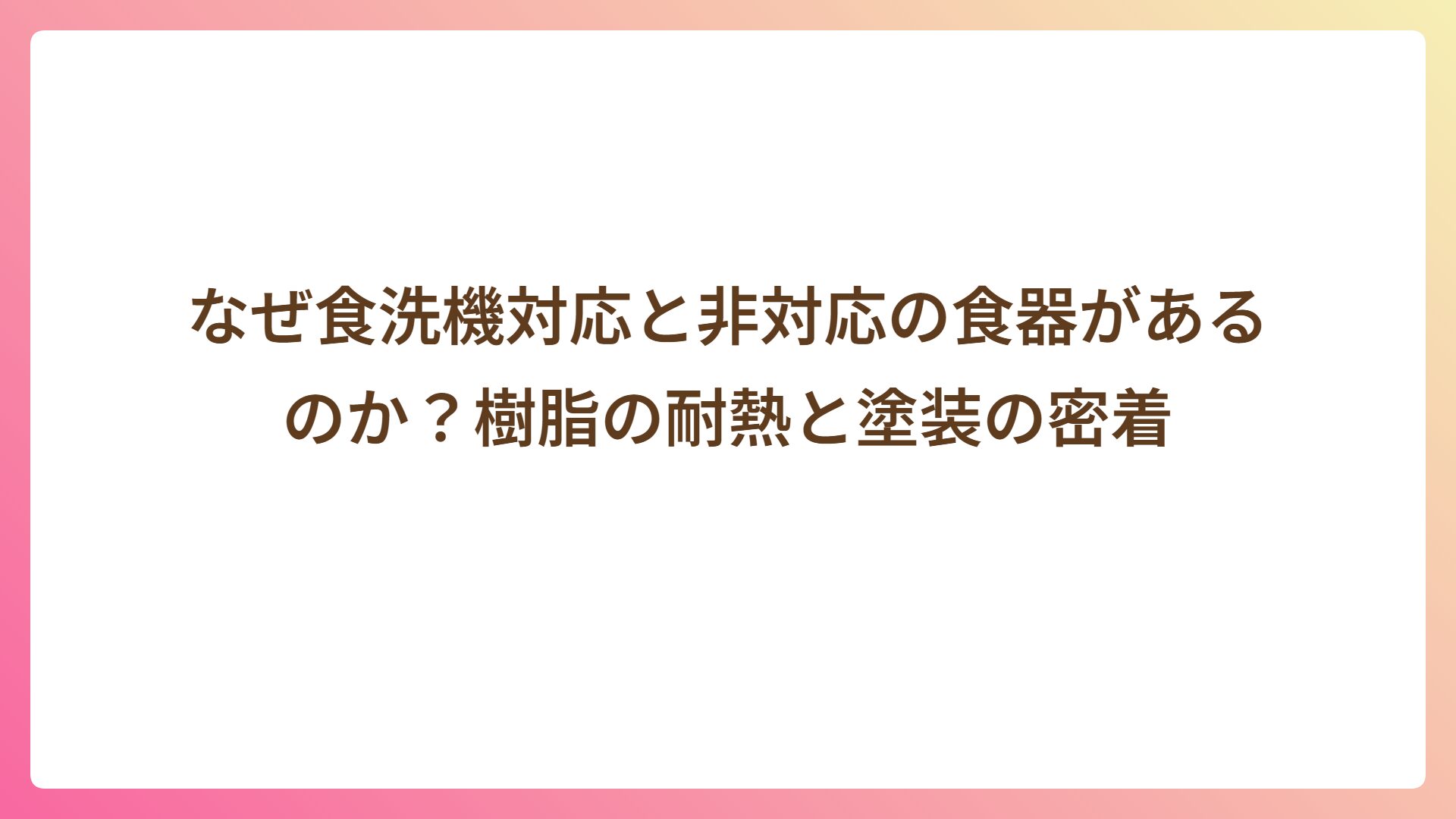
「この食器は食洗機非対応」と書かれていると、つい何が違うの?と思ってしまいますよね。
見た目は同じでも、実は素材の耐熱温度や表面処理の構造に大きな差があります。
なぜ同じお皿でも、食洗機にかけられるものとそうでないものがあるのでしょうか?
食洗機の内部は“意外と過酷”
家庭用の食洗機は、内部温度が70〜80℃前後に達します。
高温の洗浄水と強い水流、そして洗剤中のアルカリ成分が、
食器に熱・圧力・化学的刺激を繰り返し与えます。
つまり、食洗機は単なる「お湯洗い」ではなく、
素材の耐久性を試す高温・高圧・高アルカリの環境なのです。
この条件に耐えられるかどうかが、「対応・非対応」を分ける最大の基準になります。
樹脂(プラスチック)は“耐熱温度”で分かれる
プラスチック製の食器では、
素材の耐熱温度が食洗機対応かどうかを決定づけます。
代表的な素材の耐熱温度は以下の通りです。
- ポリプロピレン(PP):約120℃ → 対応しやすい
- メラミン樹脂:約100℃ → ギリギリ対応
- ポリスチレン(PS):約70℃ → 非対応が多い
食洗機内の温度や洗剤成分によって、
耐熱温度ギリギリの素材は変形・白化・ひび割れが起きることがあります。
そのため、同じプラスチックでも成形方法や厚み、添加剤によって対応可否が変わるのです。
陶磁器でも“釉薬や塗装”がポイント
陶磁器は基本的に高温焼成されているため、
素材自体は食洗機に十分耐えられる強度を持っています。
しかし、問題になるのは表面の釉薬(ゆうやく)や塗装層です。
特に、
- 金・銀・プラチナの装飾(転写)
- 手描きの上絵付け
- マット釉や貫入(ひび模様)仕上げ
などは、アルカリ性洗剤や高温水流で剥がれ・変色・曇りが起きやすくなります。
そのため、メーカーは「非対応」と明記し、
長期使用での美観維持を優先しているのです。
木製や漆器は“含水膨張”に弱い
木や漆器は、内部に微細な空隙(くうげき)を持つ天然素材。
熱や水分を吸収すると膨張し、乾燥時に収縮するため、
繰り返すうちに歪み・割れ・塗膜の剥離が起こります。
また、漆塗りやウレタンコートは高温の洗浄水で柔らかくなり、
ベタつきや艶落ちの原因にもなります。
そのため、これらはほとんどが非対応です。
ガラスや金属は“急変温と衝撃”が課題
ガラスやステンレスなどの無機素材は熱には強いですが、
- 急激な温度変化(熱衝撃)
- 水流による衝突
により、割れや欠けが発生することがあります。
特に強化ガラスは丈夫に見えても、
小さな欠けから一気に割れる「テンパリング破壊」を起こすことがあり、
安全性を考慮して「非対応」とされることもあります。
“食洗機対応”は実は“耐久テスト済み”の証
「食洗機対応」と表示できる製品は、
メーカーが高温・洗剤・水圧の耐久試験をクリアしたものに限られます。
つまり、「対応」と書かれているのは単なる宣伝ではなく、
実際に長時間使用しても変形・色落ちしないことが確認された証拠なのです。
逆に「非対応」と書かれているものを無理に入れると、
1回では問題なくても数十回の使用で劣化が進み、
結果的に寿命を大きく縮めてしまう可能性があります。
まとめ
食洗機対応・非対応の違いは、
素材の耐熱性・塗装の密着力・構造の安定性によって決まります。
プラスチックは耐熱温度、陶磁器は釉薬、木製品は水分膨張——。
それぞれの素材特性に合わせた判断が必要です。
つまり、「対応・非対応」という表示は、見た目の違いではなく“科学的な耐久基準”の違いなのです。