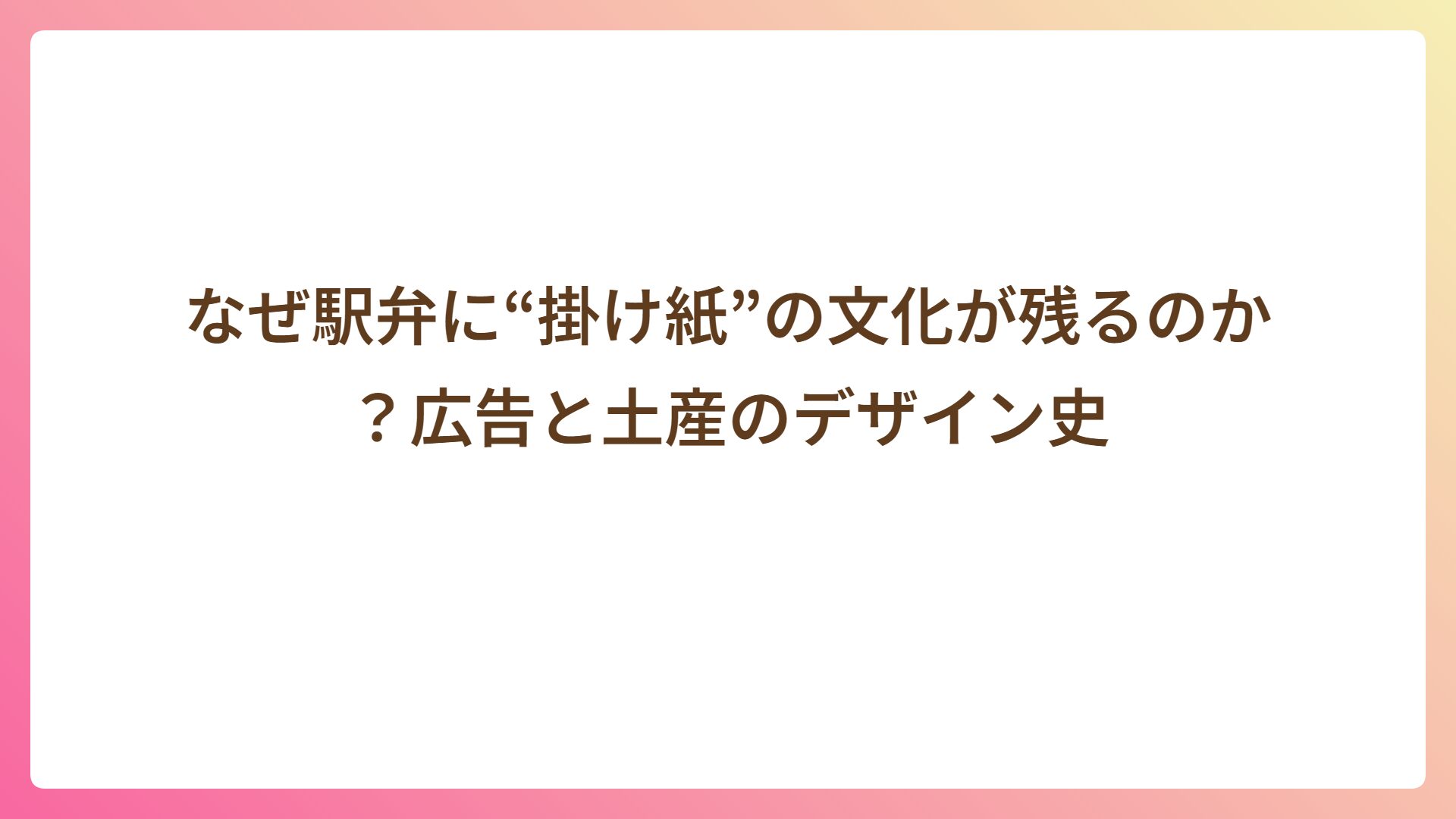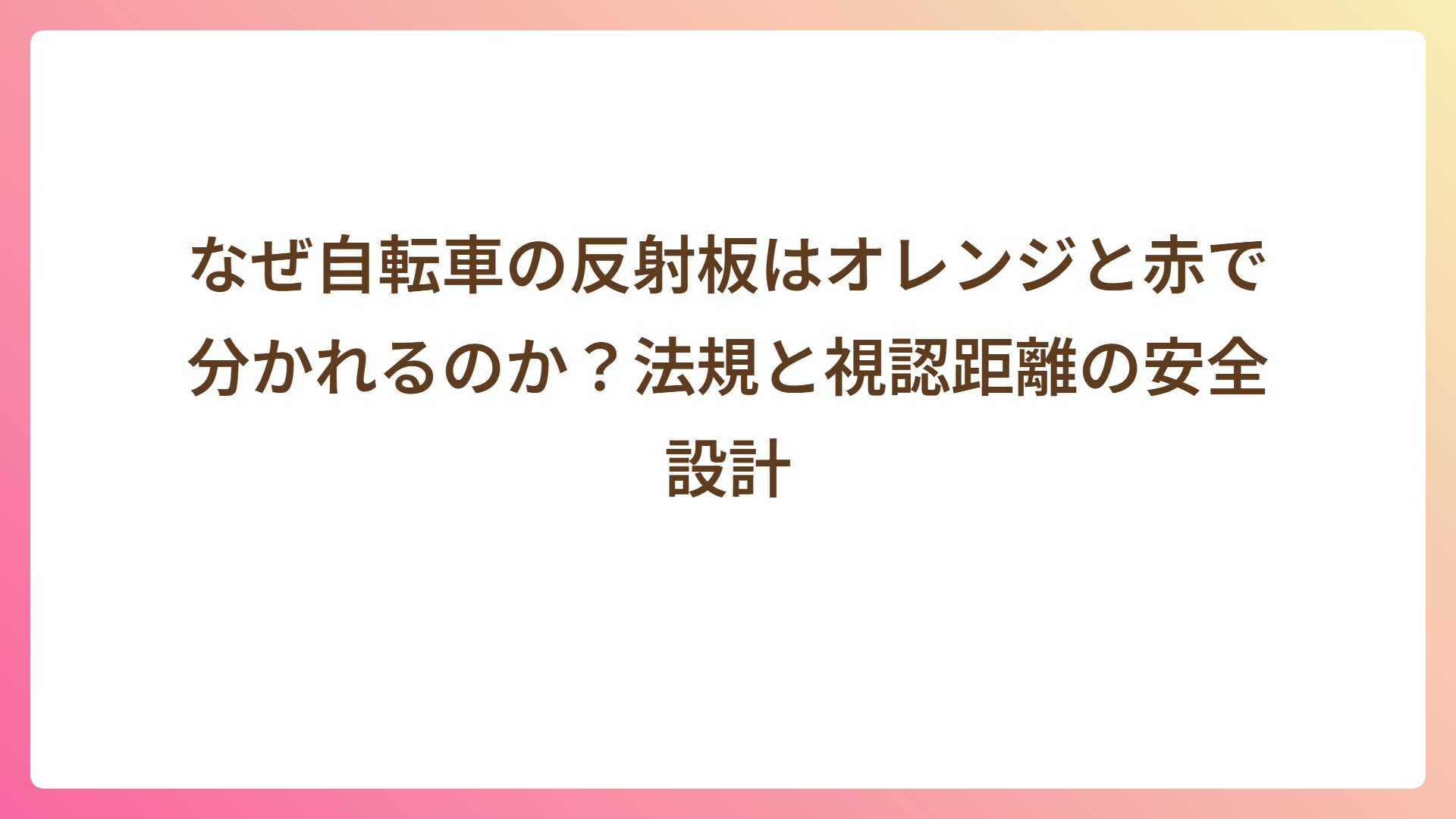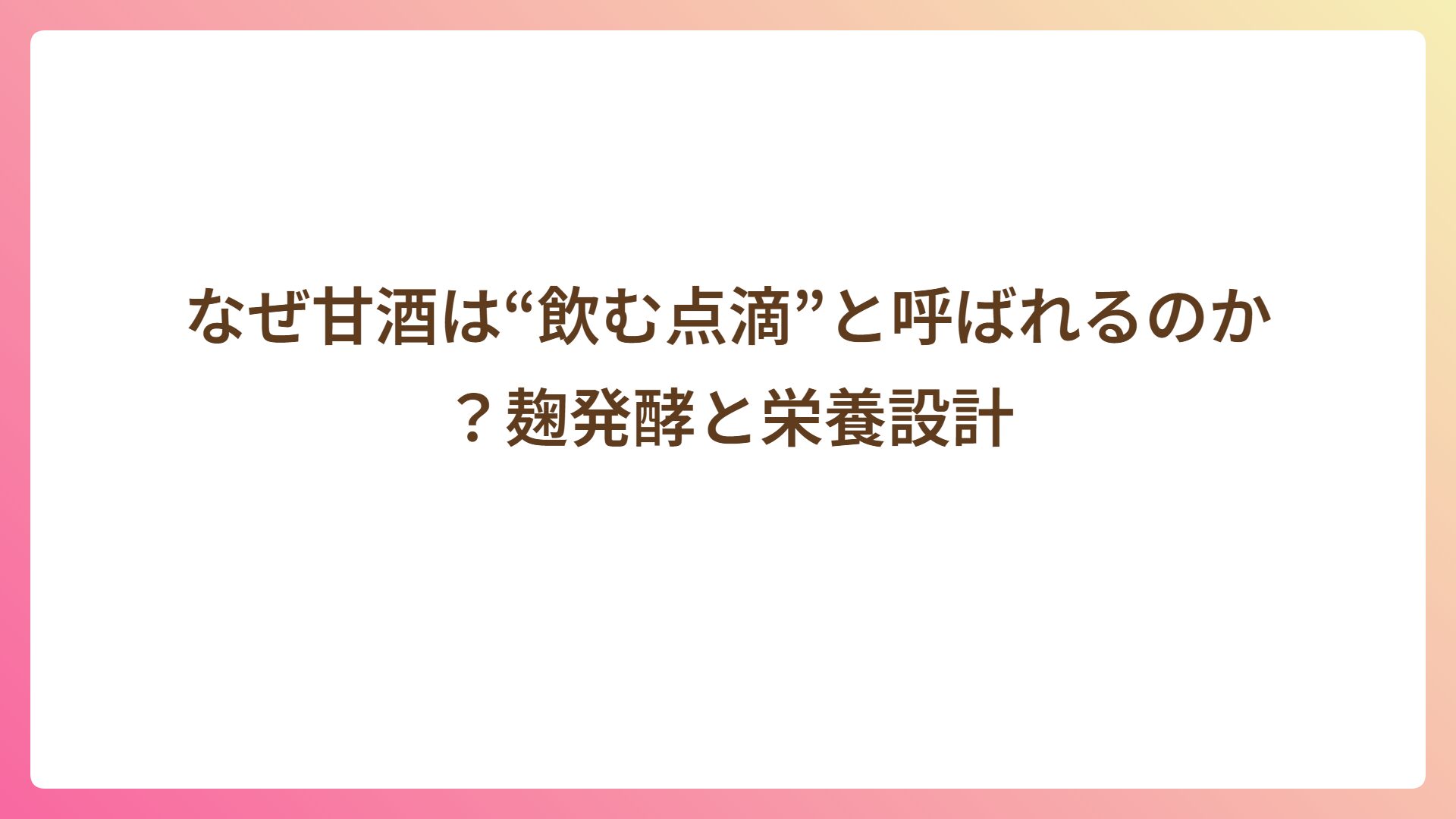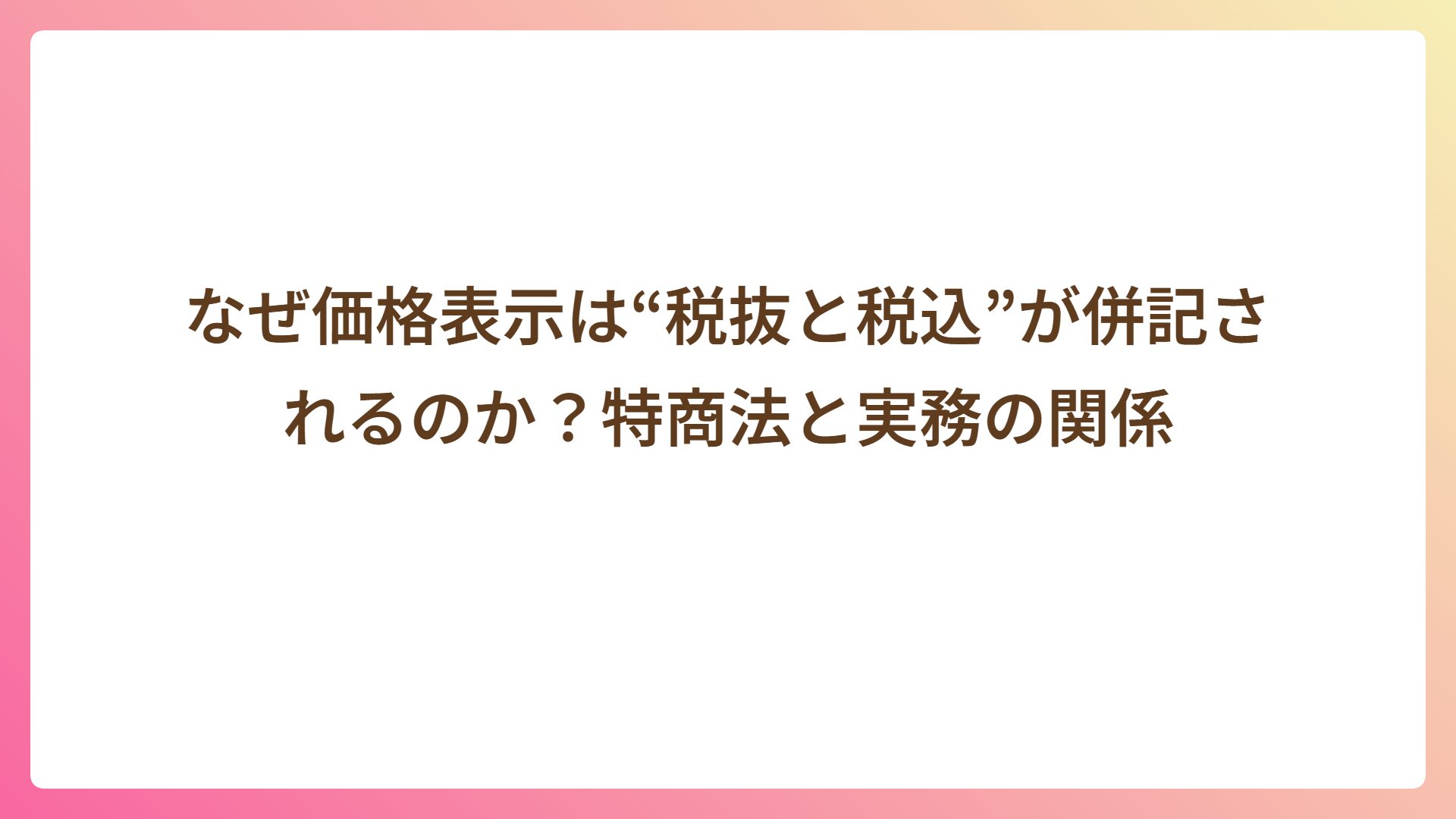なぜ封筒ののりしろは三角形なのか?接着面積とずれ止め
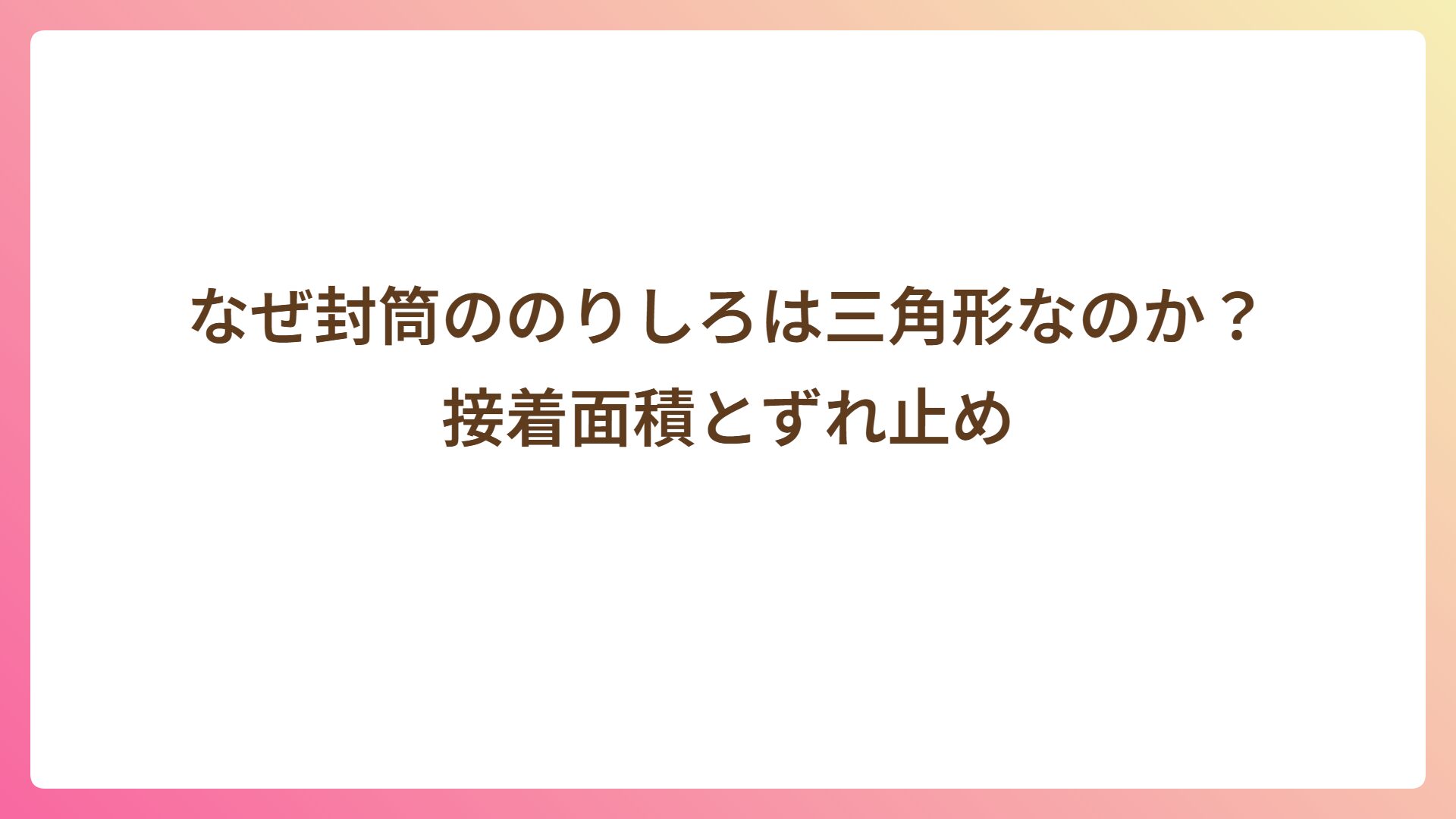
封筒を開いてよく見ると、裏側ののりしろが三角形にカットされています。
単純にデザインのためではなく、実はこの形には接着・量産・整列の観点から理にかなった理由があります。
今回は、封筒の三角形のりしろに隠された工学的な設計意図を解説します。
三角形は“のりムラ”を防ぐ最適形
封筒ののりしろは、接着剤を塗布して貼り合わせる部分です。
もしのりしろが四角形のままだと、
重なりの端にのりが溜まりすぎてはみ出したり、ムラができたりします。
一方、三角形にすることで、
端にいくほど接着面積が自然に小さくなり、
のりが均一に薄く伸びやすい構造になります。
つまり、のりの厚みを自動的に制御できる“形状設計”なのです。
接着面積を確保しつつ“軽量化”
封筒の形状設計では、「封を閉じる強度」と「紙の重なりによる厚み」のバランスが重要です。
三角形のりしろは、
- 基部(中央)では広く接着して強度を確保
- 端に行くほど狭くして余分な紙を減らす
という効率的な接着設計になっています。
これにより、強度を落とさずに用紙の使用量と重量を削減でき、
郵送コストや紙資源の節約にもつながります。
“ズレ止め”のための角度設計
三角形にカットする最大の実用的理由は、
封筒を組み立てるときに紙がずれにくくなることです。
四角いのりしろだと、貼り合わせ時に平行面が多く、
わずかなズレで全体の形が歪みやすくなります。
しかし三角形は、接点が中央に集中する構造のため、
貼る際に自然と位置が定まり、ずれを最小限に抑えられるのです。
工場の自動封筒製造ラインでも、
三角形の方が位置合わせがスムーズで生産効率が高いという利点があります。
封筒を開閉しやすくする“段差回避”効果
のりしろが三角形だと、折り返したときの重なりが段階的になります。
これにより、裏フラップを閉じたときに段差や厚みの集中を防ぎ、
開閉部分がきれいに収まります。
特に大量の封筒を重ねるときに、
のりしろが四角いと重なり部分が厚くなり、束が傾いたり反ったりしてしまうことがあります。
三角形はこの問題を避けるための構造的な合理化でもあるのです。
乾燥・圧着工程にも有利
封筒は製造後にのりを塗布し、
乾燥→折り→圧着という工程を経ます。
三角形形状は、空気が抜けやすく乾燥が早いという利点もあります。
のりが均一に薄く塗布されるため、
圧着ムラや気泡の発生を防ぎ、仕上がりが平滑になります。
このため、郵便封筒・長形・洋形などあらゆる形式で採用されているのです。
海外封筒との比較
海外の封筒では、裏のりしろが直線や波形など多様ですが、
日本では定型郵便に求められる寸法精度と機械封入適性のため、
三角形のりしろが標準化されています。
特に日本の封筒は、
自動封入機で紙の端を基準にセットする方式を採用しており、
三角形の方が紙詰まりを起こしにくく、
封緘作業の信頼性が高いのです。
まとめ
封筒ののりしろが三角形なのは、
のりムラを防ぎ、ずれを抑え、軽量で精密に貼れる形だからです。
見た目の単純な“切り欠き”のようでいて、
そこには接着工学・量産効率・郵送品質をすべて満たす設計思想が込められています。
日常の封筒の裏には、数ミリ単位で最適化された紙の工学が息づいているのです。