電子レンジはどうやって温めてる?マイクロ波・水分子・摩擦熱のしくみを解説!
mixtrivia_com
MixTrivia
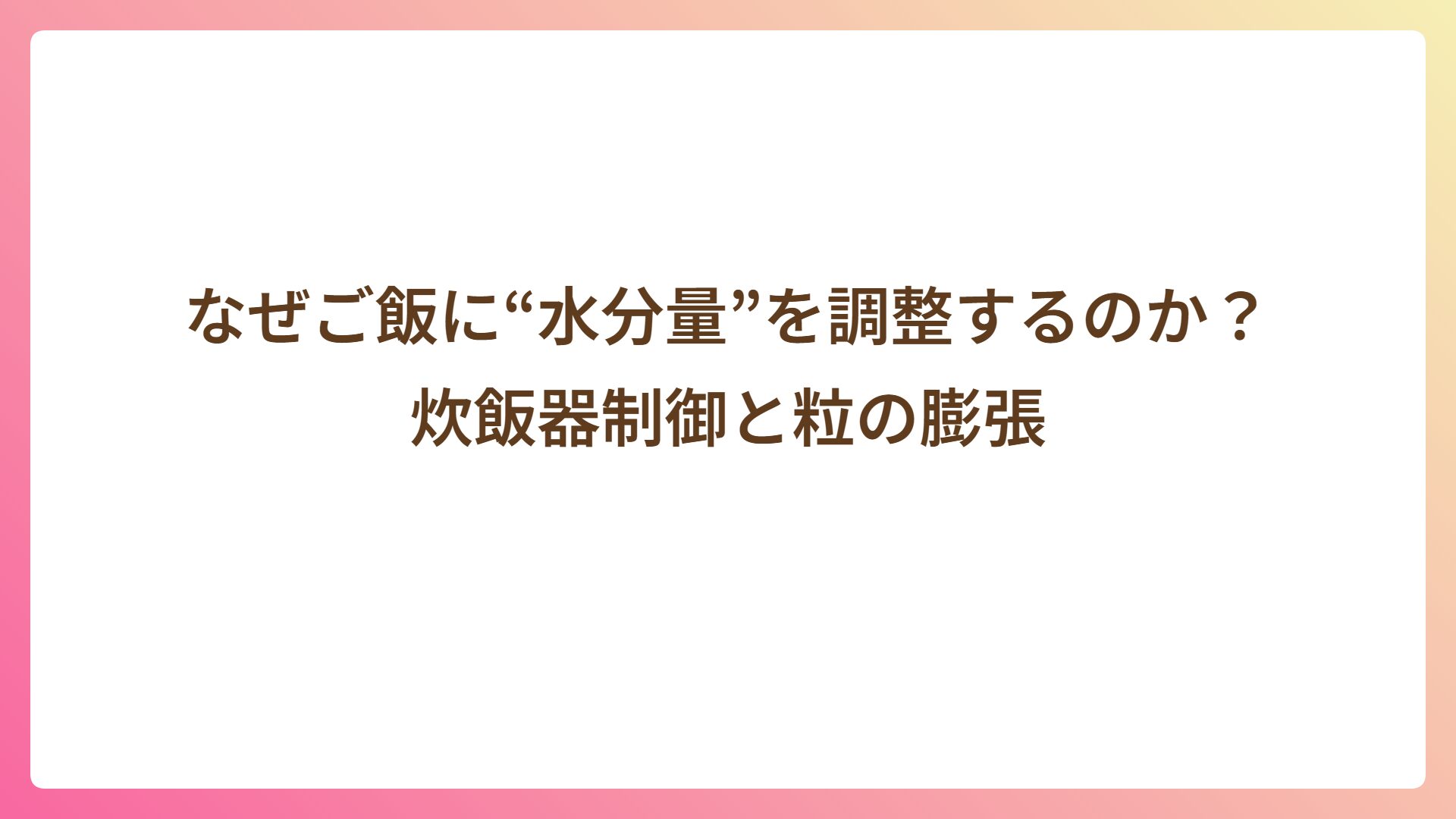
「ご飯を炊くときは水加減が命」とよく言われます。
ほんの数十ミリの違いで、炊きあがりの食感や香りが変わるほど、水分量は繊細な要素です。
ではなぜ、ご飯を炊くときに水の量を調整する必要があるのでしょうか?
生の米には硬いデンプン粒が詰まっており、水と熱を加えることでこれが柔らかく変化します。
この現象を糊化(こか)と呼び、米が「ご飯」へと変わる最も重要な過程です。
糊化には、米粒の内部まで水が均等に浸透していることが不可欠です。
水が少なすぎると中心部が加熱されても硬いまま残り、逆に多すぎると表面だけが崩れてべちゃついた食感になります。
つまり、適正な水分量はデンプンの変化を均一に進めるための鍵なのです。
炊飯器は内部の温度上昇をセンサーで検知し、「沸騰したら炊き上げ」「水がなくなったら保温」といった制御を行っています。
水の量が多ければ加熱時間が長くなり、少なければ早く炊き上がります。
つまり炊飯器は、水分量を基準に加熱プロセスを制御しているのです。
想定より水が少ないと温度が早く上がりすぎ、内部が十分に蒸らされないまま終わってしまうこともあります。
同じ計量カップを使っても、米の状態によって吸水率は変化します。
新米は水分を多く含むため少なめに、古米は乾燥しているため多めにするのが基本です。
また、冬場は米が冷えて吸水が遅いため、やや長めに浸水させると炊きムラを防げます。
このように、水分量の調整は米の状態に合わせて炊飯器の制御を最適化する行為でもあるのです。
ご飯の水分量を調整するのは、
米の糊化を均一に進め、炊飯器の温度制御を正しく働かせるためです。
水の多い少ないは、ただの好みではなく「熱とデンプンの科学」。
一粒一粒がふっくら立つご飯の裏には、精密な水と熱のバランス設計が隠されているのです。