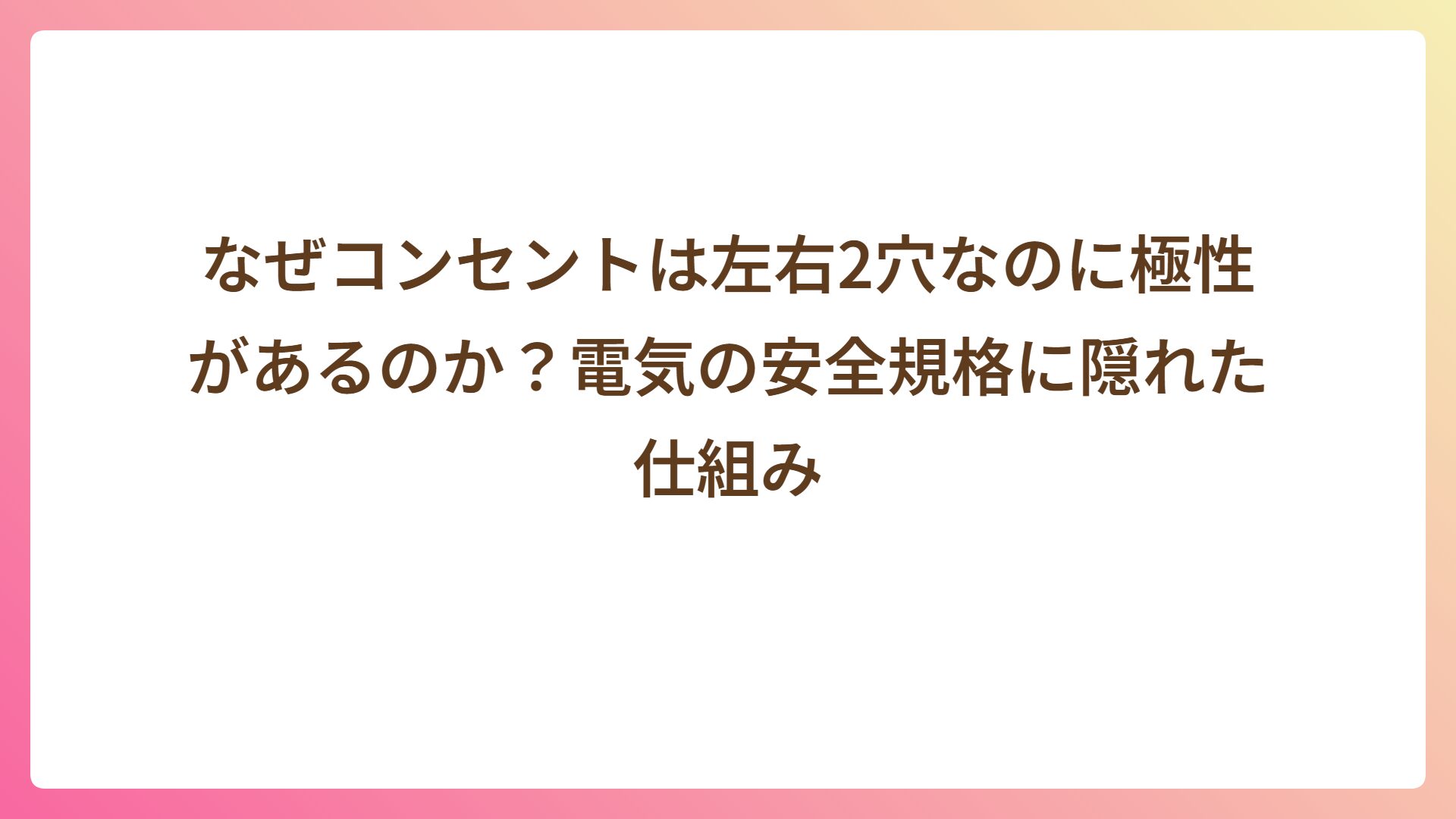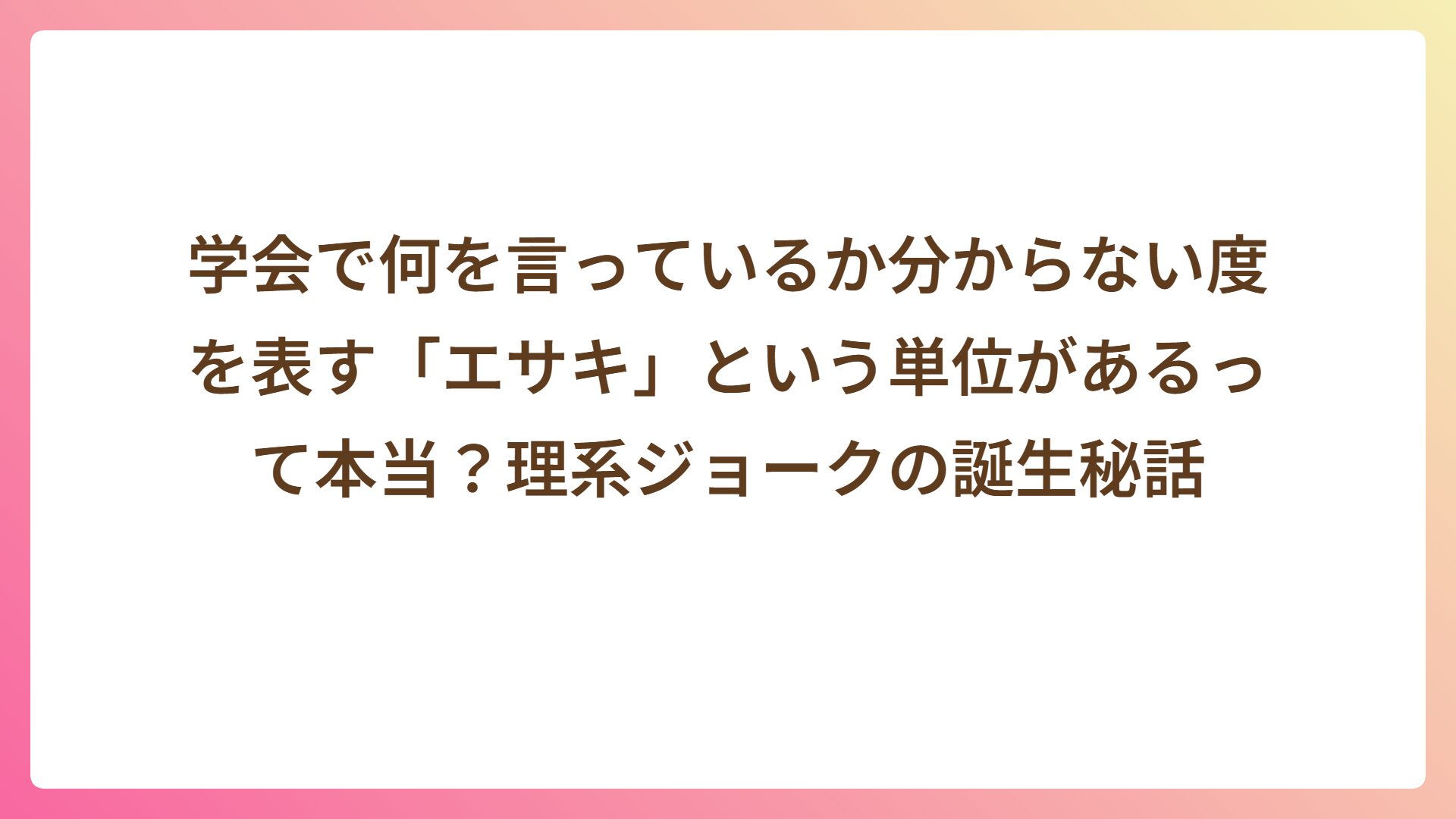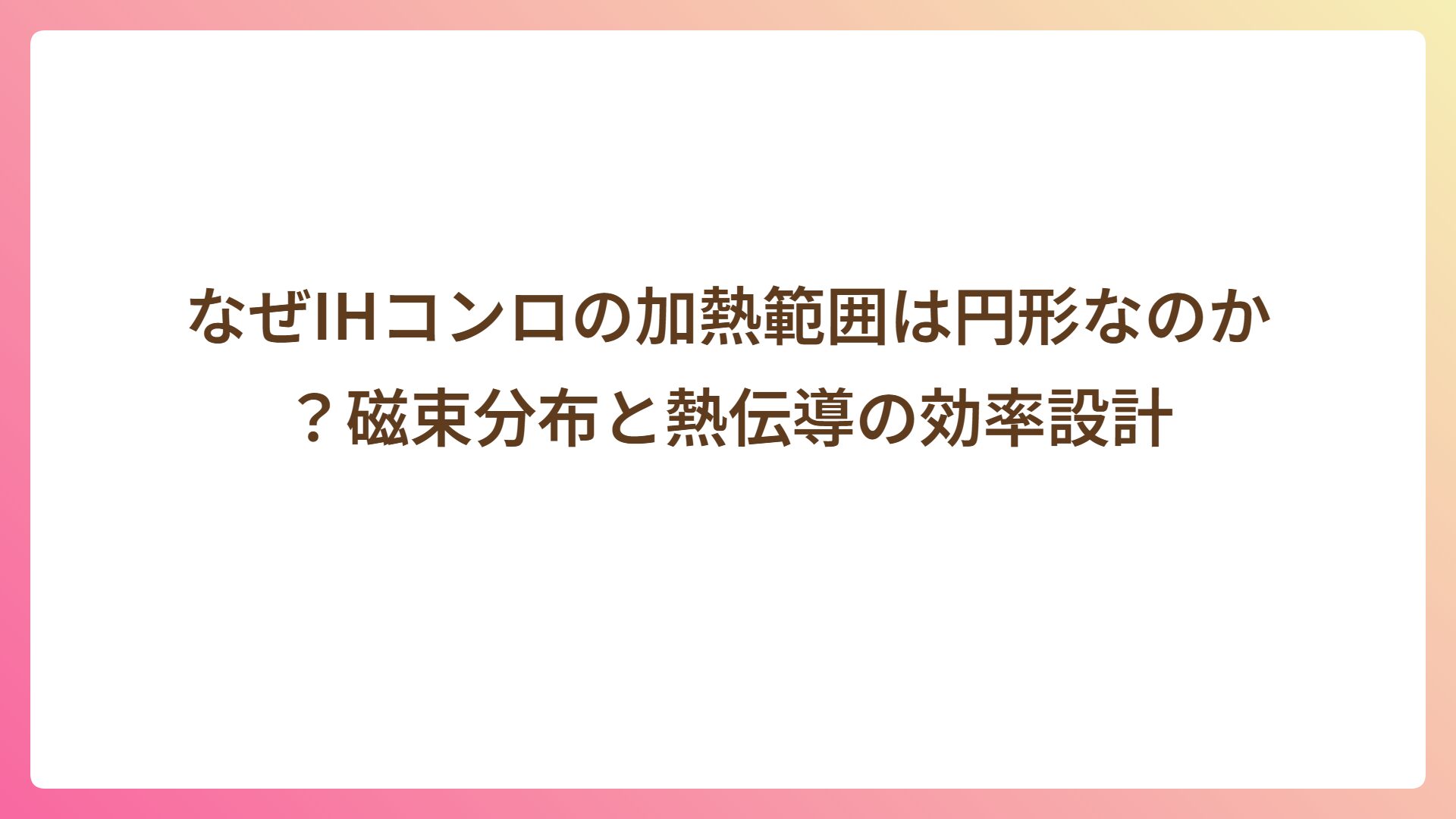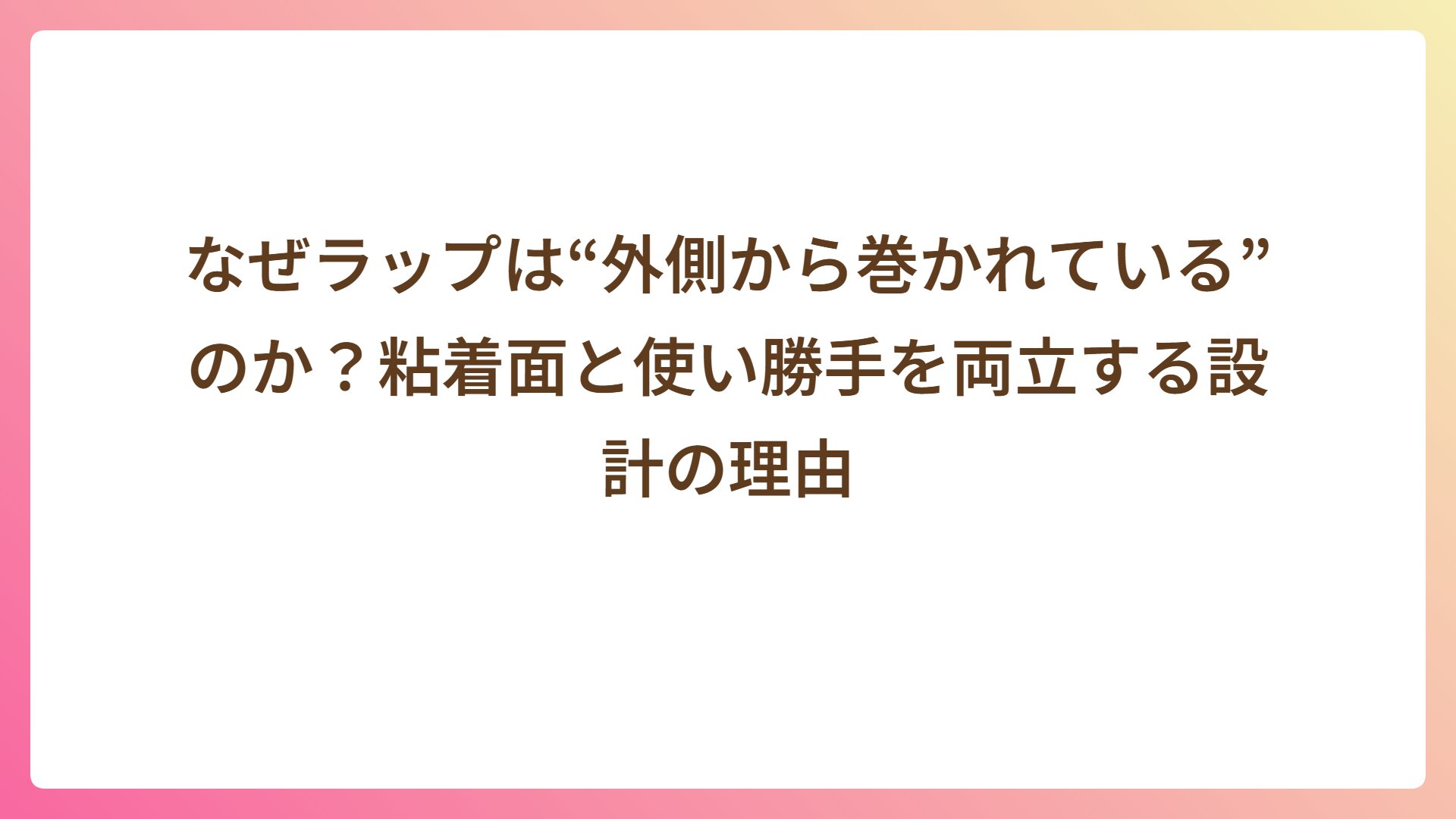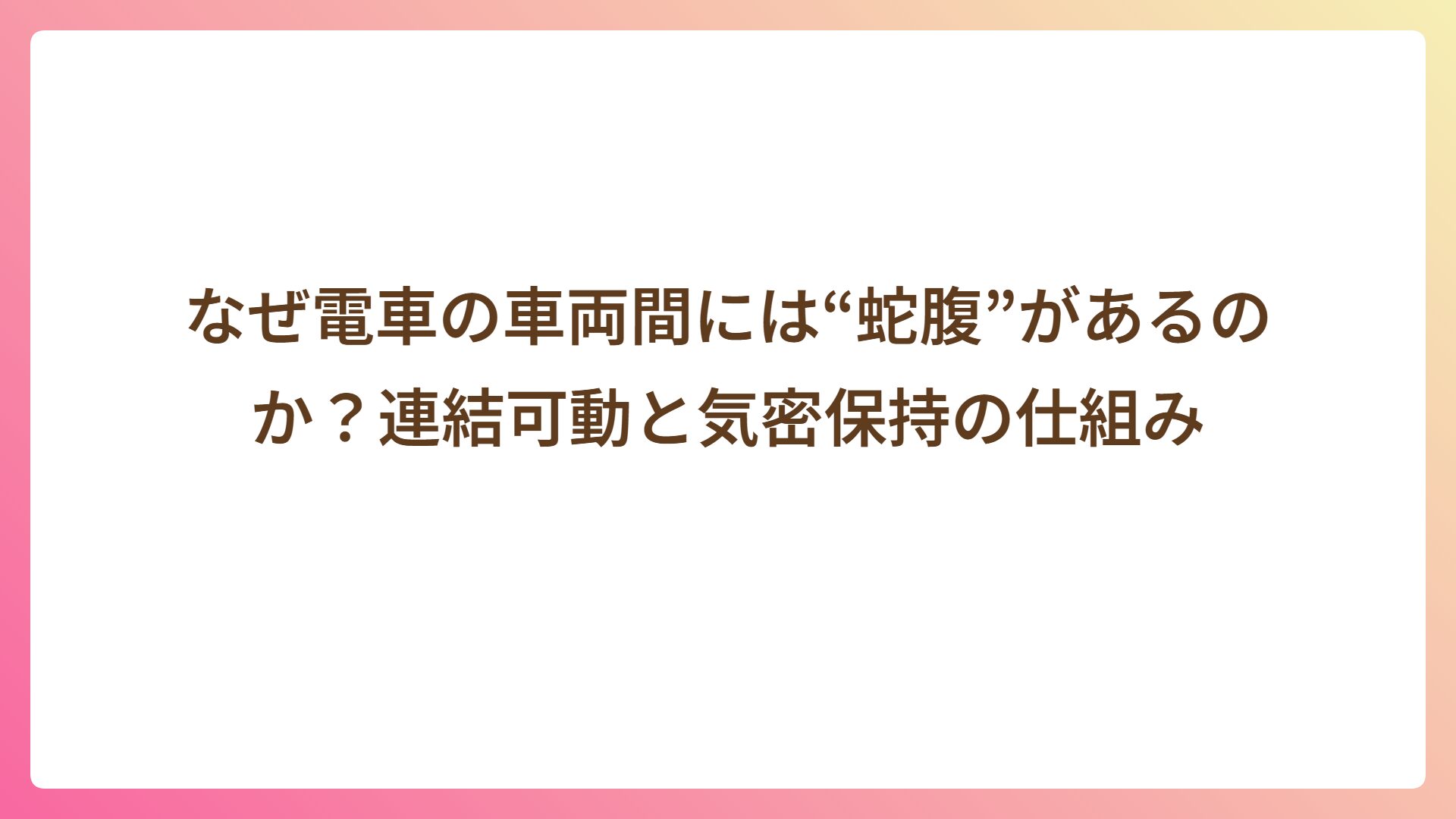なぜ選挙の投票所は小学校校舎が多いのか?施設活用と公共性
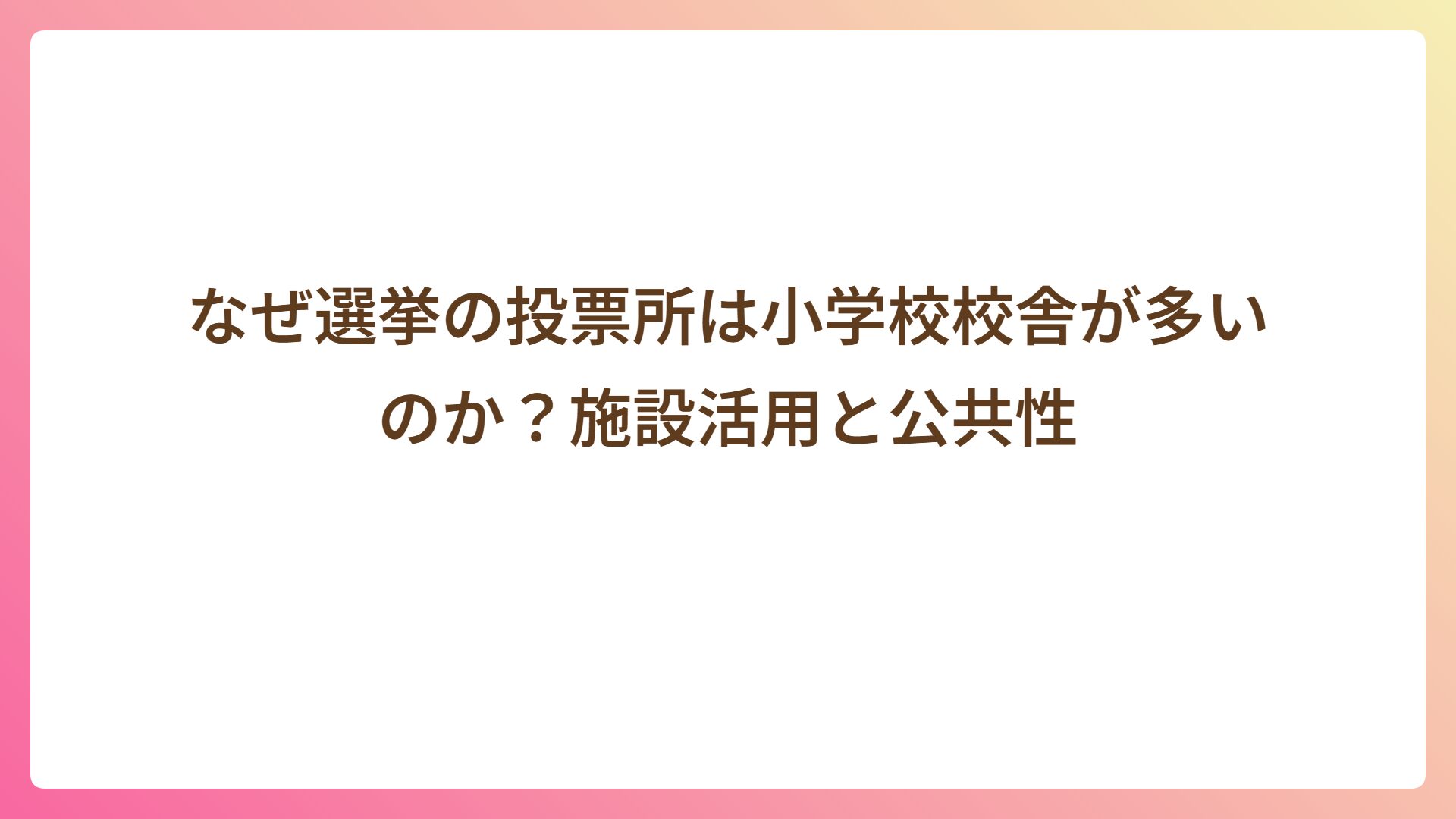
選挙の日、投票所として案内されるのはたいてい近くの小学校。
なぜ公民館や役所ではなく、小学校が多いのでしょうか?
それは「誰でも行きやすく、安全に運営できる」場所としての条件を最も満たしているからです。
地域の中心にあり、誰でも行きやすい立地
小学校は、学区という形で地域ごとに分けられており、ほとんどの住民が徒歩圏内にある公共施設です。
道路やバス路線からもアクセスしやすく、高齢者や車いす利用者でも無理なく行けるよう設計されています。
行政側にとっても、住民票の区域(投票区)と学校区が重なりやすいため、地域単位で投票所を割り当てやすいという利点があります。
広い体育館があり、多人数の出入りに対応できる
選挙当日は多くの有権者が一斉に訪れます。
そのため、受付・投票記入台・投票箱を並べても十分なスペースが確保できることが重要です。
小学校には大きな体育館や講堂があり、雨天時でもスムーズに投票を行える環境が整っています。
また、体育館の出入口は複数あり、一方通行の動線を確保しやすいため、混雑やトラブルを防ぎやすいという点も評価されています。
公共施設としての「中立性」
選挙では、公平性が最も重視されます。
特定の団体や企業の施設を使用すると、政治的中立性に疑念を持たれるおそれがありますが、
小学校は自治体が運営する教育施設であり、完全な公共の場。
誰のものでもない「地域の共有空間」であるため、投票所として利用しても政治的偏りが生じません。
設備・人員・安全面で運営しやすい
学校には電気、水道、トイレ、非常口などの基本インフラが整っており、災害時避難所としての基準も満たしています。
また、教職員や自治体職員が常駐しているため、開票所の設営やトラブル対応にも迅速に対応できます。
加えて、防犯カメラや照明設備が整っていることから、夜間開票時の安全性も確保しやすいというメリットがあります。
まとめ
投票所に小学校が多いのは、
地域性・公共性・安全性・設備の充実という条件をすべて満たすためです。
身近で誰もが安心して訪れられる場所——。
小学校は、まさに「民主主義の入り口」として最もふさわしい公共空間なのです。