なぜ自動ドアのセンサーは“腰の高さ”で反応しやすいのか?検知範囲の最適化
mixtrivia_com
MixTrivia
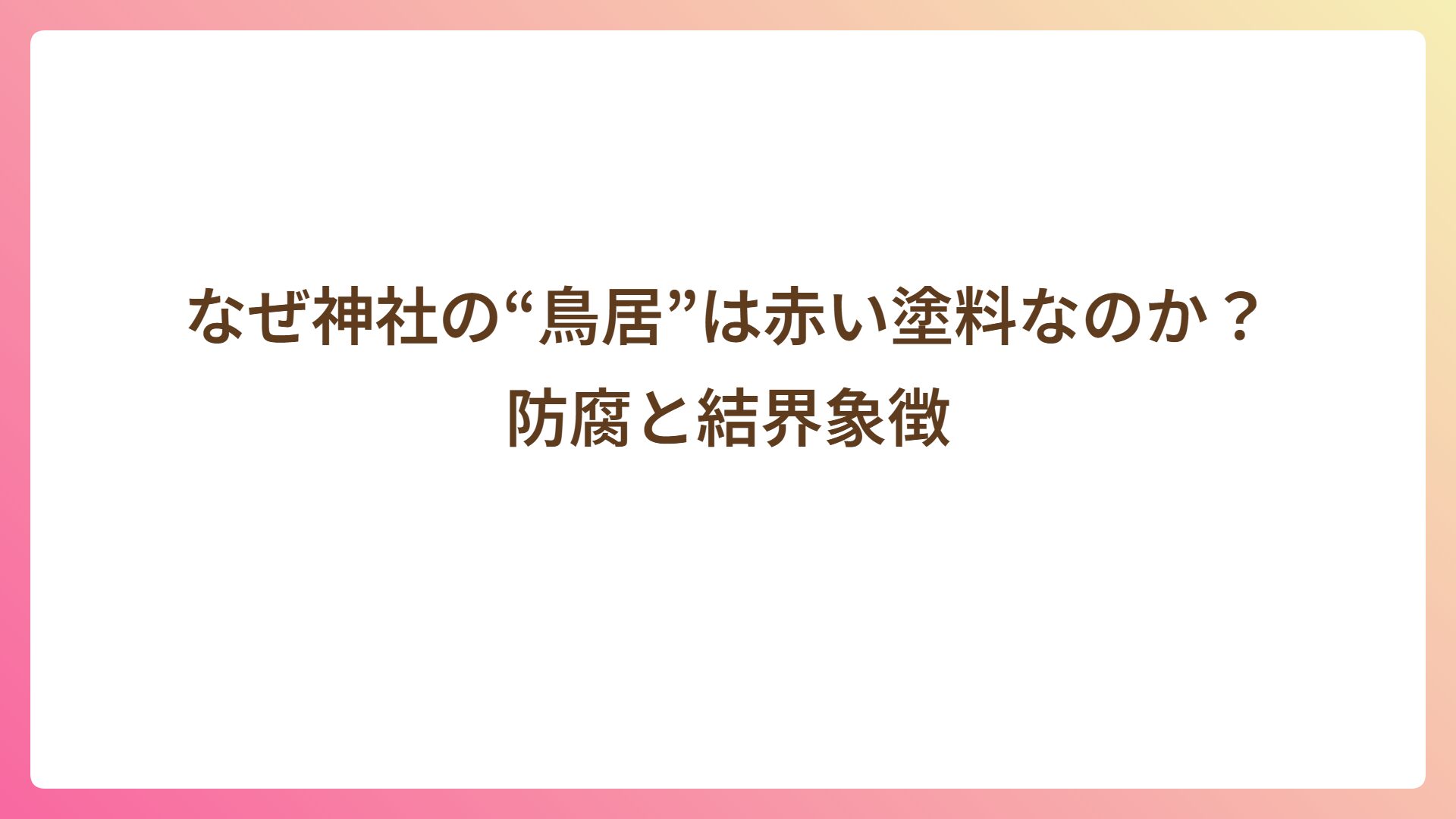
神社に行くと、まず目に入るのが赤い鳥居。
どの神社でも同じように見えるこの色には、単なる装飾を超えた深い理由があります。
実は、朱色には実用性と信仰性の両方が込められているのです。
鳥居の赤は、「朱(しゅ)」と呼ばれる酸化水銀を含む顔料で塗られています。
古くから朱には防腐・防虫・防カビ効果があることが知られ、木造建築の保護に用いられてきました。
雨や湿気にさらされる鳥居は、放っておくとすぐに腐ってしまいます。
そこで朱を塗ることで、耐久性を高め、長く神域の入口を保つことができたのです。
現代では水銀を含まない樹脂系の朱塗料が使われていますが、「朱=保護の色」という伝統は今も受け継がれています。
日本では古来より、赤は生命・太陽・火を象徴する色であり、同時に魔除けの色とされてきました。
病や災厄を遠ざける色として、社殿や橋、鳥居などに多く用いられています。
鳥居は、俗界と神域を分ける“結界”の役割を持ちます。
その境界を強調するために、視覚的に最も目立ち、神聖さを感じさせる赤が選ばれたのです。
つまり、朱色の鳥居は「ここから先は神の領域」というサインでもあります。
すべての神社の鳥居が赤いわけではありません。
伊勢神宮のように、無垢の檜材を使い塗装しない「白木造り」の鳥居もあります。
これは「自然そのものを神聖視する」という神道の古い形式を保ったもので、
朱塗りは後に全国へ広がった実用・象徴の融合スタイルといえます。
神社の鳥居が赤いのは、
木を守る防腐技術と、神域を守る結界の象徴という二つの意味を持つからです。
朱色は、美しさと実用を兼ね備えた“信仰の色”。
それは、時代を超えて神と人を隔てる“見えない境界線”を示しているのです。