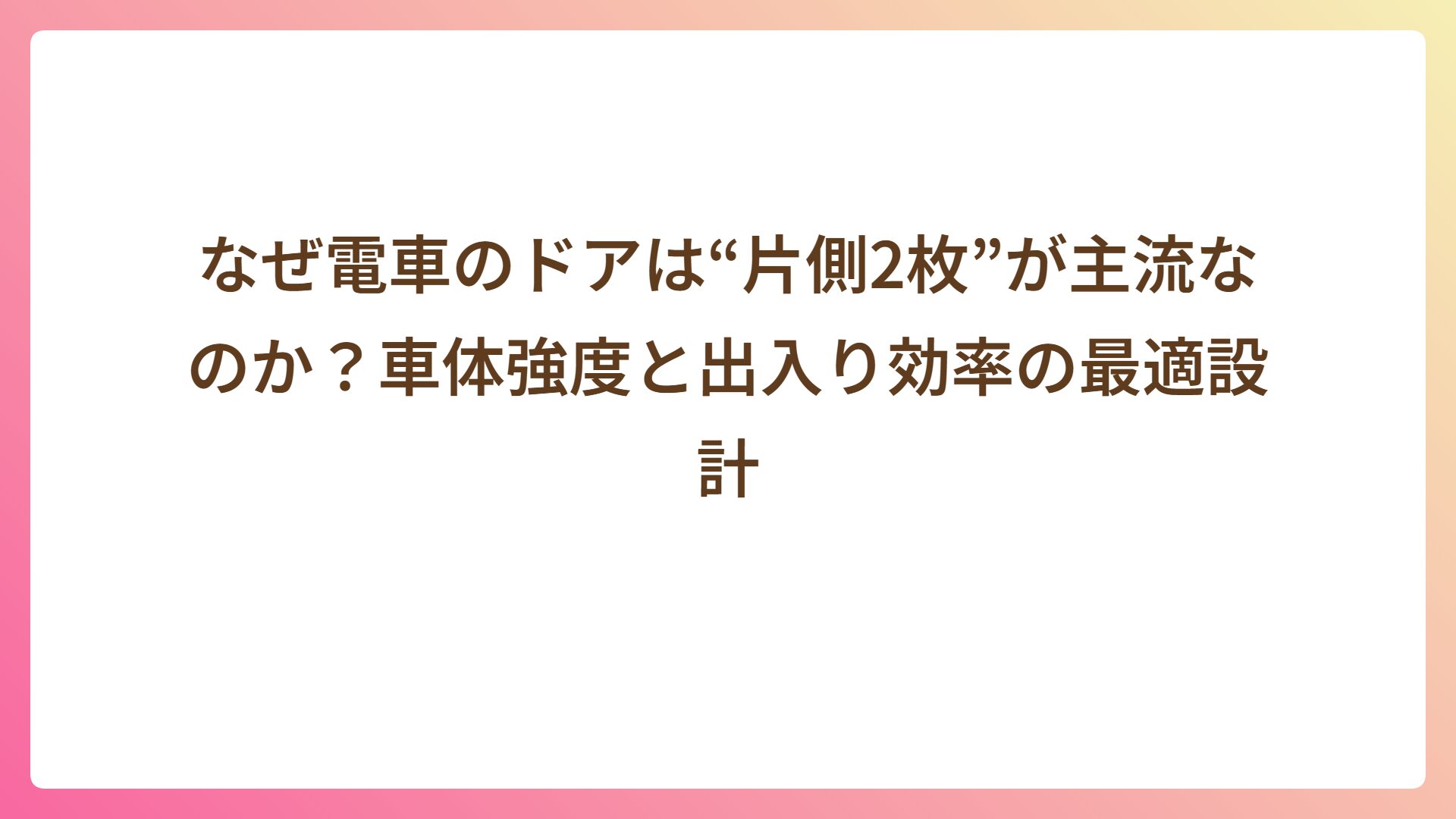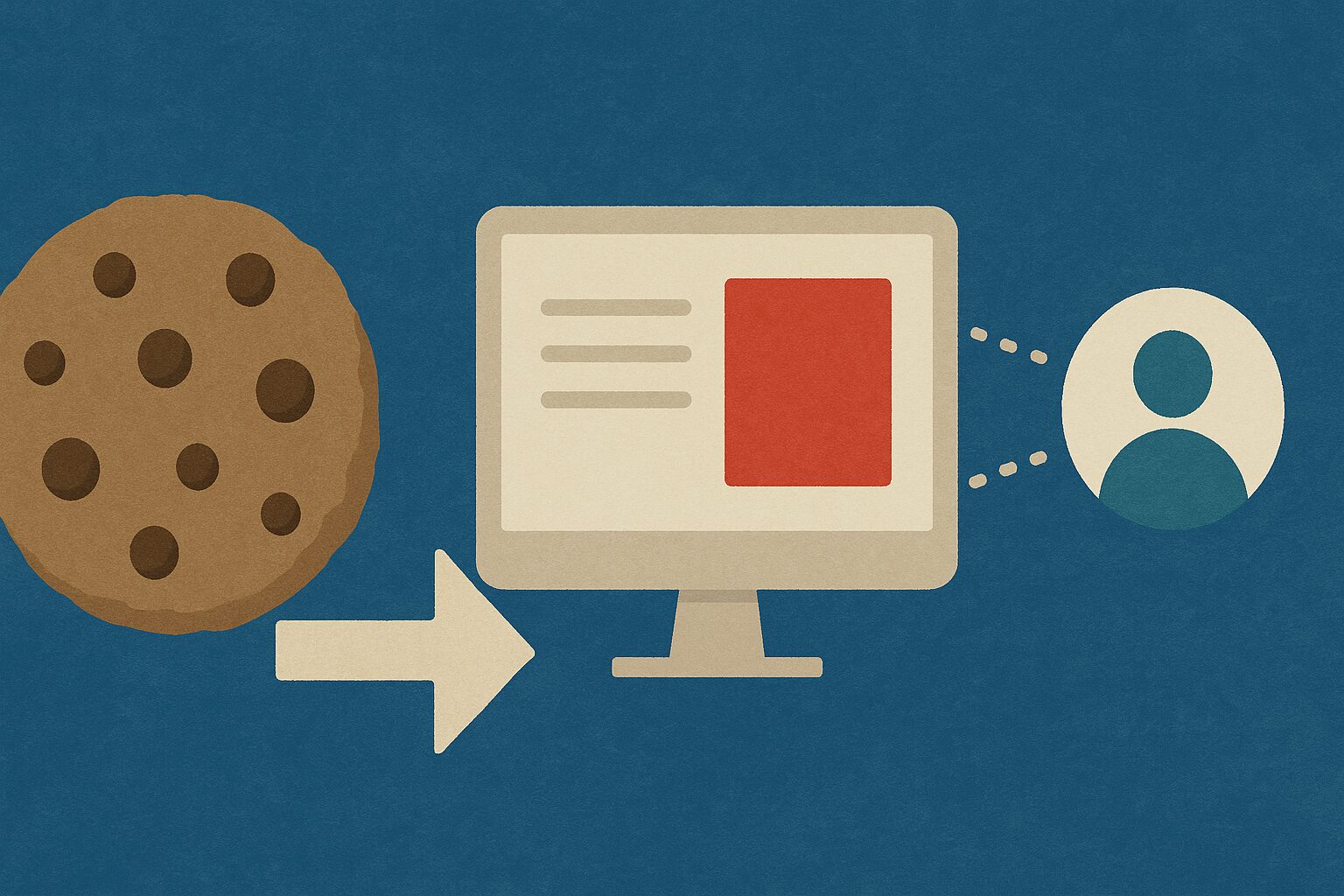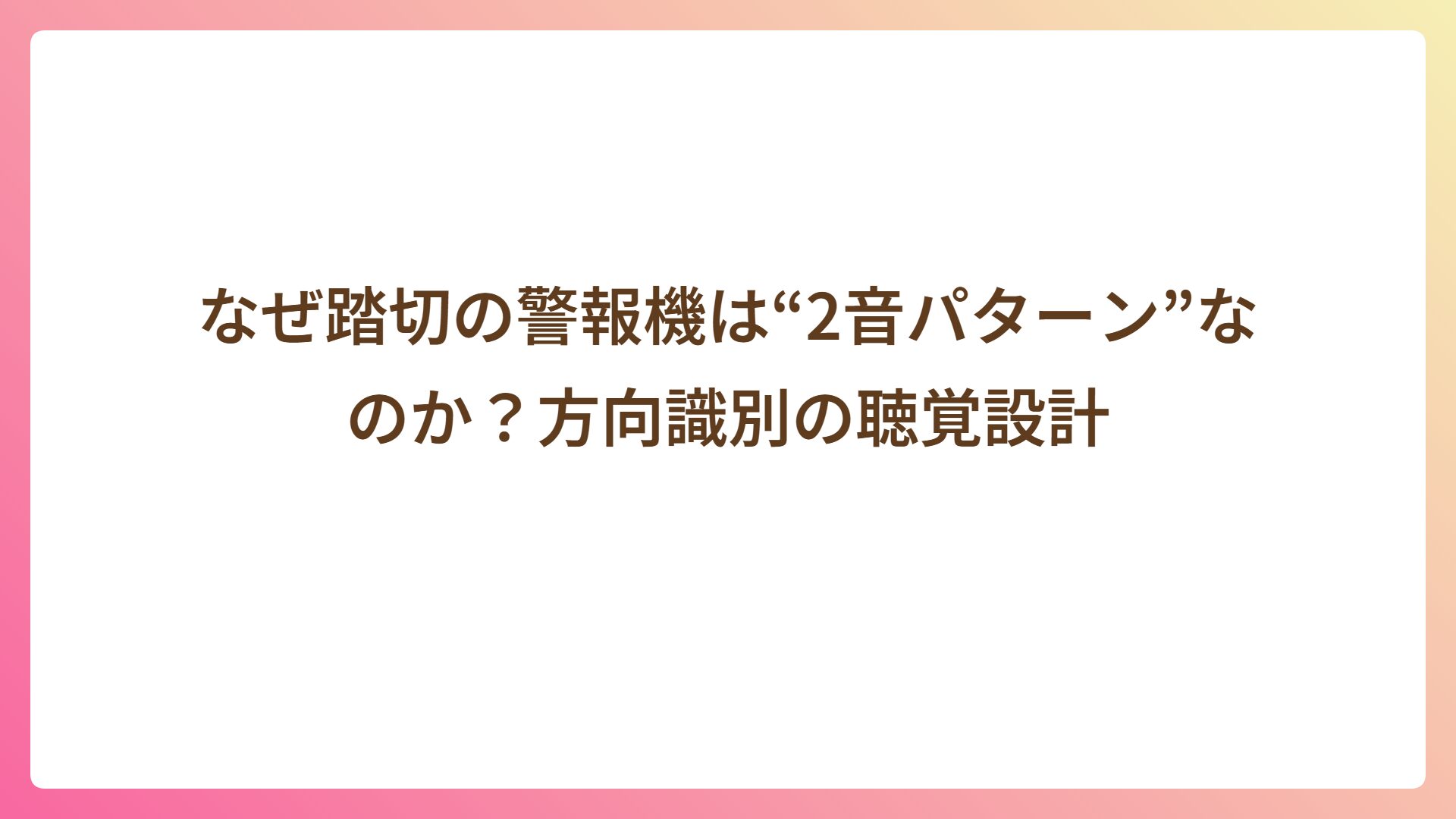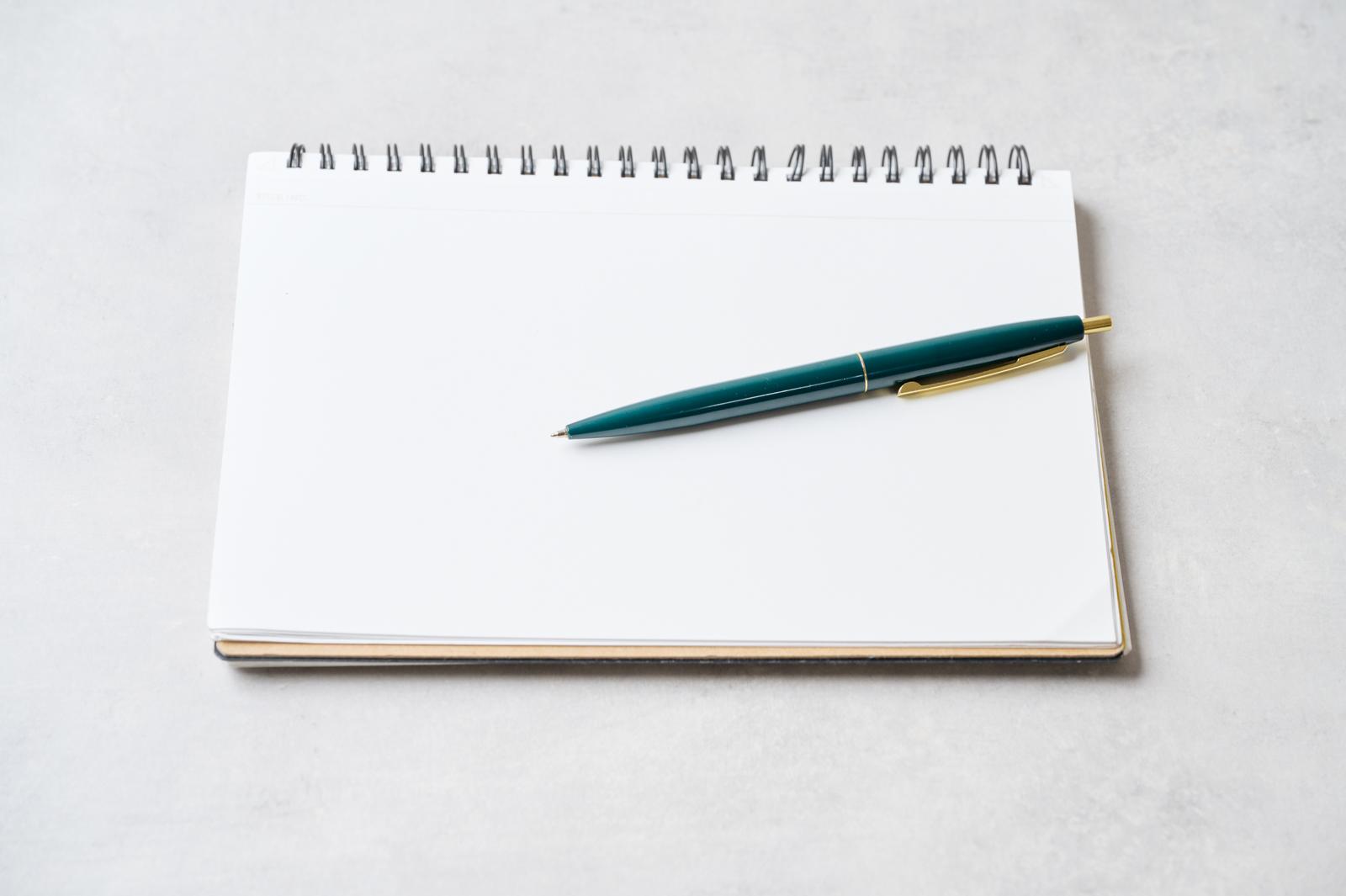なぜ提灯に“赤白”の縞模様が使われるのか?祝祭色と視認性
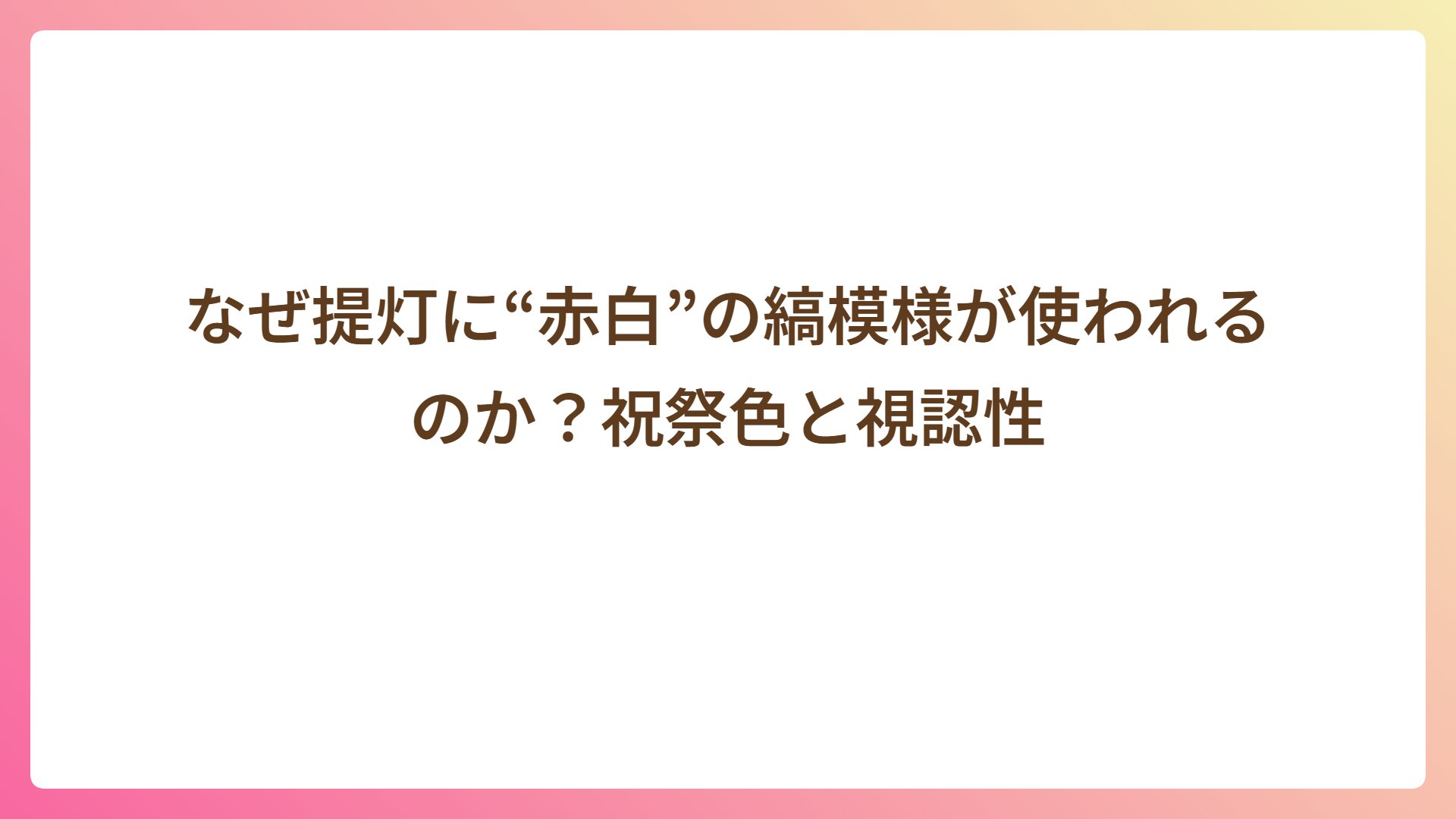
夏祭りや神社の境内、商店街のイベントなどでよく見かける赤白の提灯。
並んで吊るされると、一気にお祭りの雰囲気が高まります。
なぜ提灯には「赤と白」という縞模様が多いのでしょうか?
そこには、古くから受け継がれてきた日本独自の色の意味と実用的な理由が隠されています。
「赤白」は日本の伝統的な祝いの配色
日本では古来より、赤と白は“祝い事”や“清め”を表す色として使われてきました。
紅白まんじゅう、紅白幕、紅白の水引など、あらゆる慶事で登場する定番の組み合わせです。
この由来は、赤=魔除け・生命力、白=純潔・神聖を象徴する色の意味にあります。
つまり、赤白の組み合わせは「清められた生命の象徴」であり、神事や祭礼の場で縁起の良い配色として定着したのです。
提灯が担う「祝祭のサイン」としての役割
提灯はもともと夜間の照明具でしたが、祭りや行事では「祝祭空間を示す標識」の役割を果たします。
赤白の縞模様は、昼間でも目立つコントラストがあり、遠くからでも一目で「ここで行事がある」と認識できます。
夜になると、内部の灯りに透けて柔らかな赤白の光が浮かび上がり、非日常的な雰囲気を演出します。
つまり、赤白の提灯は視覚的にも心理的にも“祭りのスイッチ”を入れる存在なのです。
江戸時代に定着した祝祭デザイン
赤白提灯が広まったのは江戸時代。
寺社の縁日や芝居小屋、商人の祭礼などで使われるようになり、次第に「祭り=赤白提灯」という図式が定着しました。
庶民の間では、提灯の明かりを灯すこと自体が“吉兆”とされ、
特に赤白のものは「悪を払って福を呼ぶ光」として親しまれてきました。
目立ちやすく安全性にも優れる配色
赤と白の組み合わせは、明暗の差が大きく、薄暗い環境でも識別しやすいのが特徴です。
そのため、夜のイベントや人混みの中でも視認性が高く、安全面でも優れたデザインです。
視覚的にもリズミカルで明るい印象を与えるため、現代でも商店街や催事の装飾に多く採用されています。
まとめ
提灯に赤白の縞模様が使われるのは、
「祝い」と「清め」を象徴する日本の伝統色であり、視認性にも優れた実用的なデザインだからです。
赤白の灯りが連なる光景は、
古くから人々が“日常と非日常を分ける境界”として灯してきた、祝祭のシンボルそのものなのです。