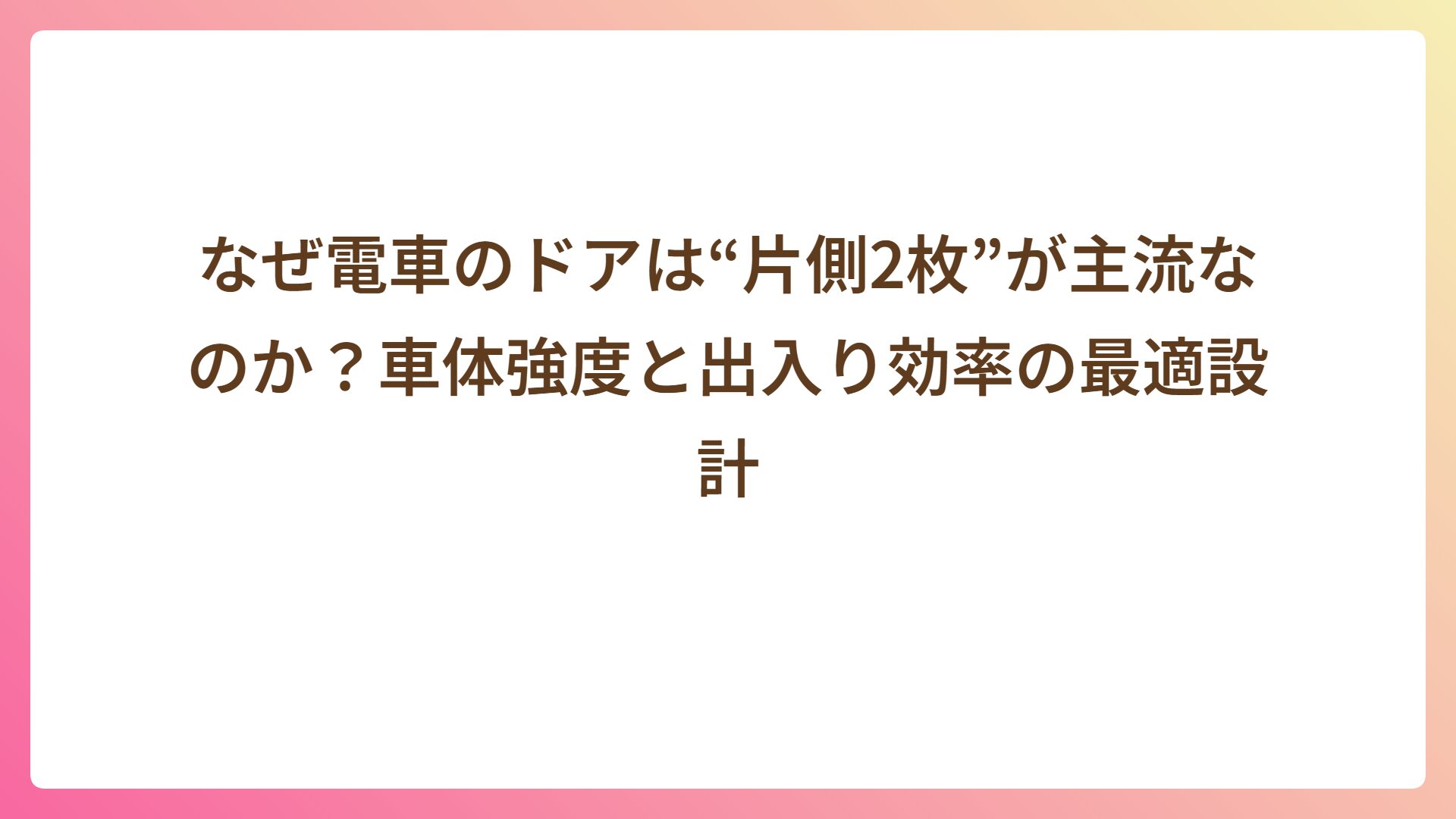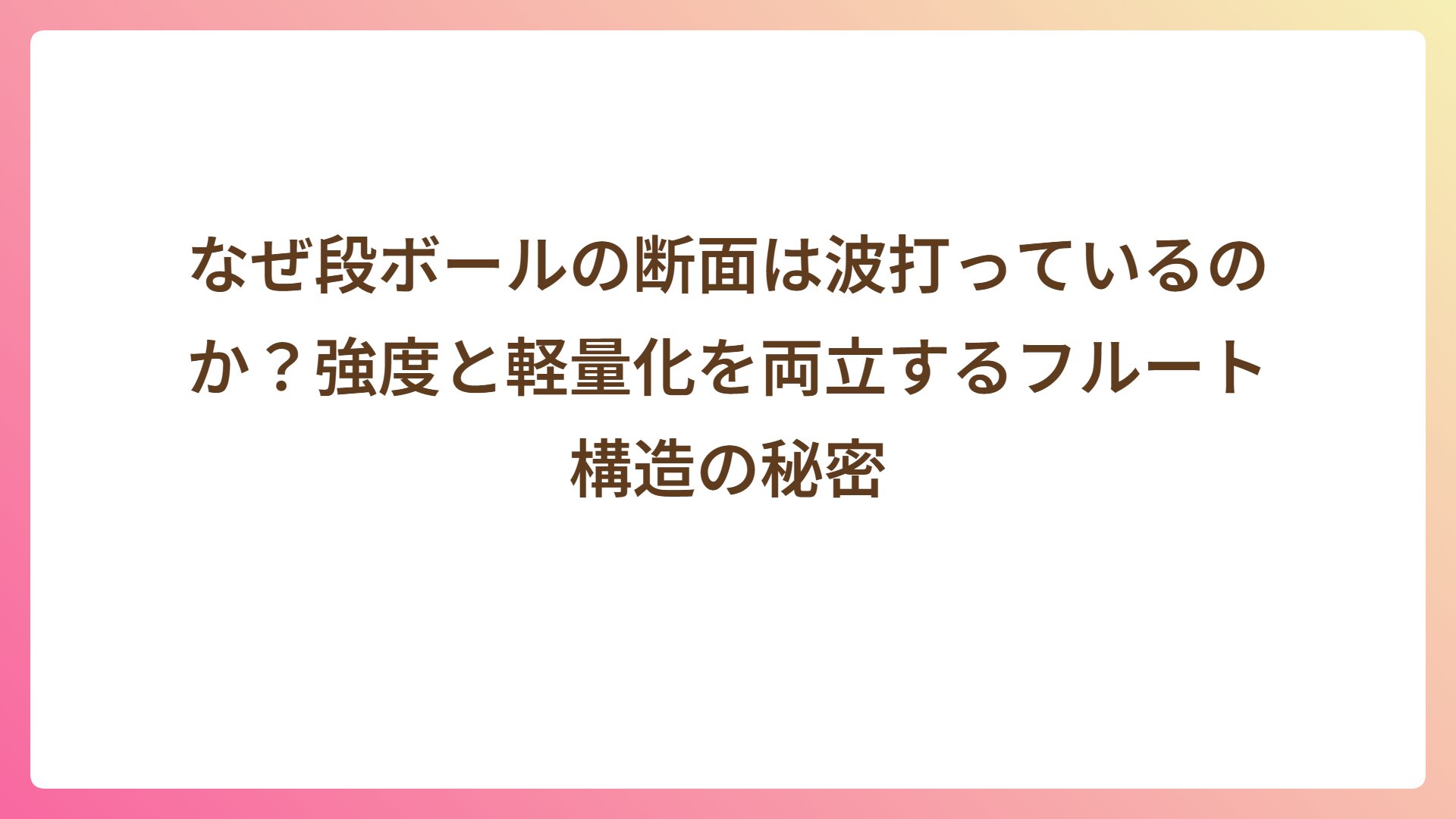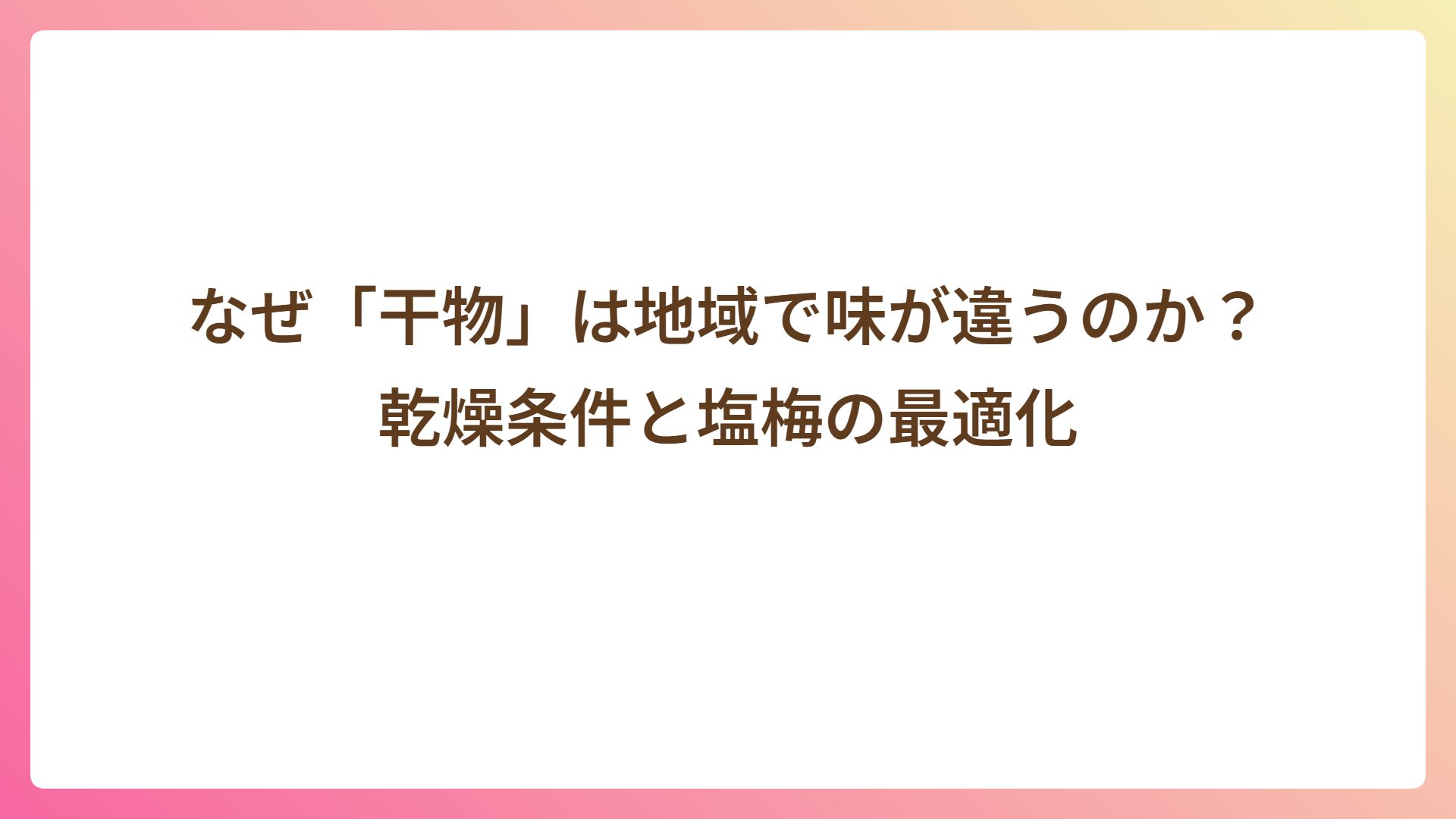なぜ羽子板は朱色が多いのか?魔除けと視認性
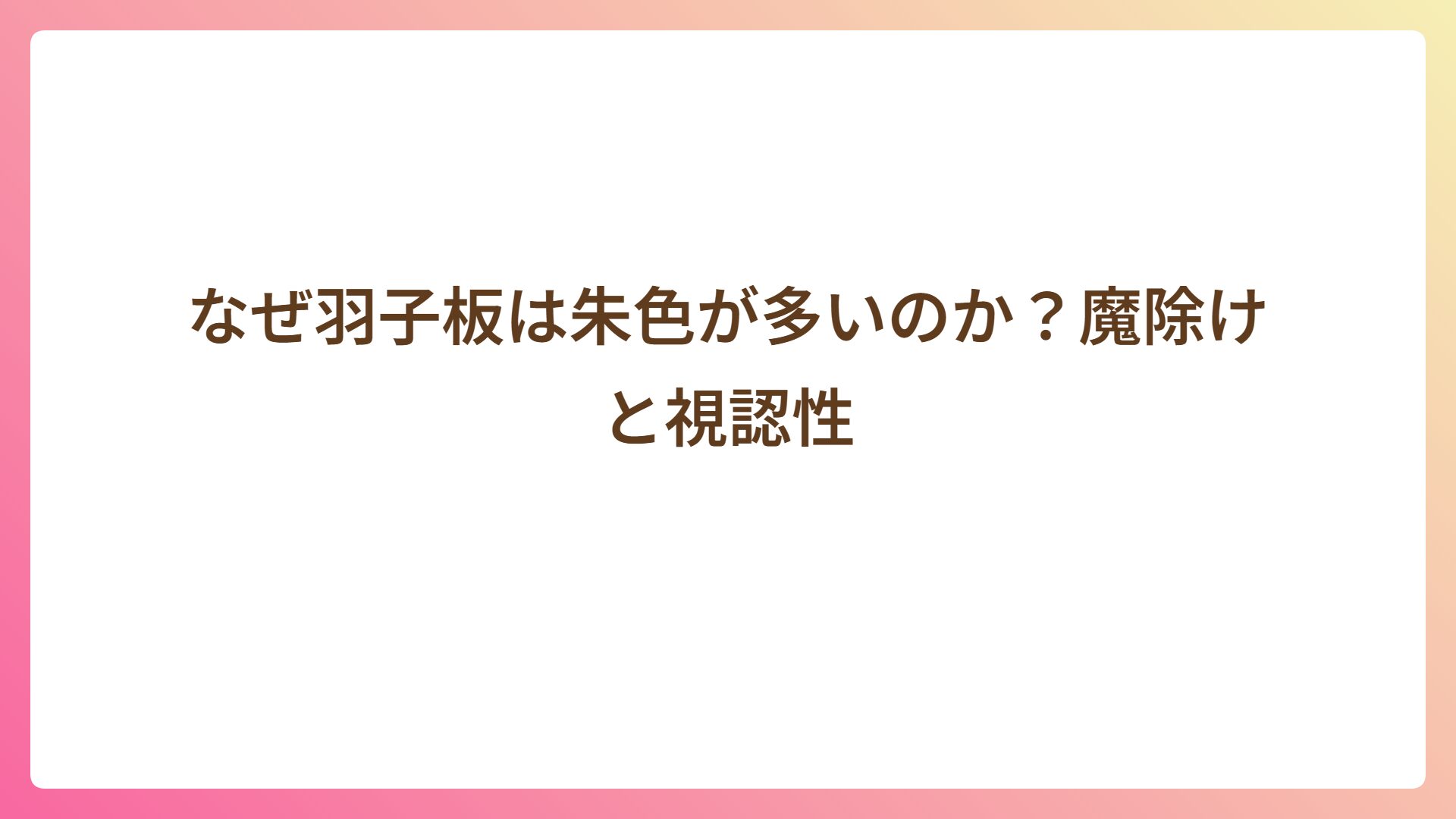
正月の飾りや羽根つき遊びでおなじみの羽子板。
よく見ると、板や絵柄、飾り紐などに鮮やかな朱色が多く使われています。
なぜ羽子板は、他の玩具よりも朱色が強く印象づけられるのでしょうか?
そこには、古くから続く「魔除けの信仰」と、遊びとしての実用性が関係しているのです。
朱色は「邪を払う」神聖な色
朱色は古来より、魔除け・厄除け・生命力の象徴とされてきました。
これは、太陽や血の色を連想させることから、「命の力を宿す色」として重んじられてきたためです。
神社の鳥居や祭具にも朱が多く用いられているのは同じ理由です。
羽子板ももともと、邪気や病気をはね返す護符としての意味を持っていました。
平安時代には「羽根つき」は女児の健やかな成長を願う行事で、
板の朱色は「病魔をはねのける」「悪運を遠ざける」色として定着していったのです。
遊びの中で「見やすい」実用色でもある
羽根つきは屋外で行うことが多く、羽根(黒い球付き)を打ち合うためには、
板の動きが相手からもはっきり見えなければなりません。
その点、朱色は背景の空や雪景色の中でも最も目立つ色で、
動きが追いやすく、タイミングを取りやすいという実用的な利点があります。
つまり朱色は、魔除けの象徴でありながら、ゲームとしても合理的な色だったのです。
江戸時代の装飾文化で“縁起色”として定着
江戸時代になると、羽子板は正月飾りや贈答品としての役割を持ち始めます。
特に「初正月」に女の子へ贈る羽子板には、病除けと長寿の願いが込められ、
朱・金・黒を基調にした豪華な意匠が流行しました。
中でも朱色は、家の中に飾っても華やかで縁起の良い色として親しまれ、
以降「羽子板=朱色」という印象が文化的に定着していったのです。
まとめ
羽子板に朱色が多いのは、
魔除けの象徴と、視認性に優れた実用色であるためです。
朱は“はねのける”力を宿す色。
邪気を払い、子どもの健康を願うその祈りが、今も正月の羽子板に込められているのです。