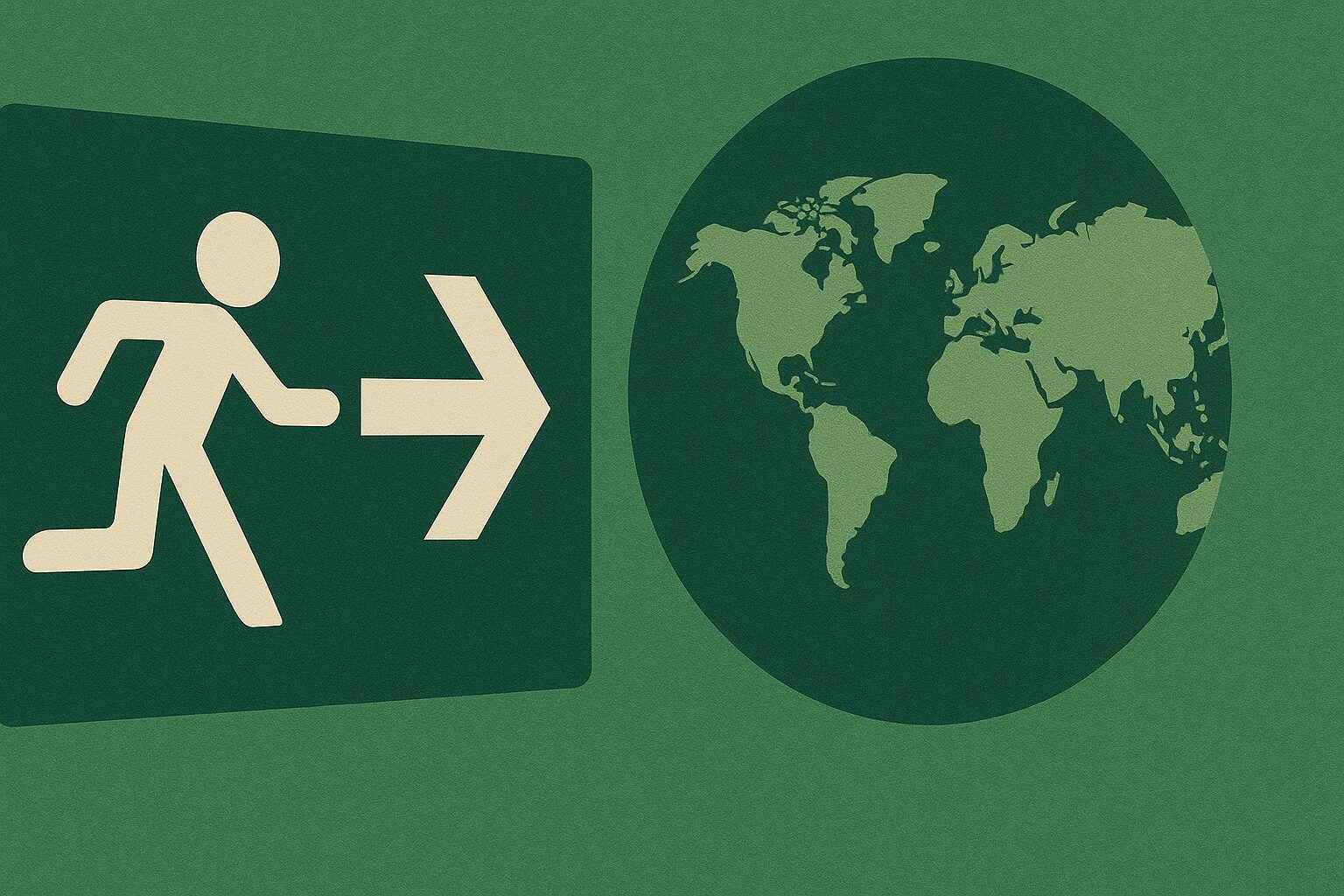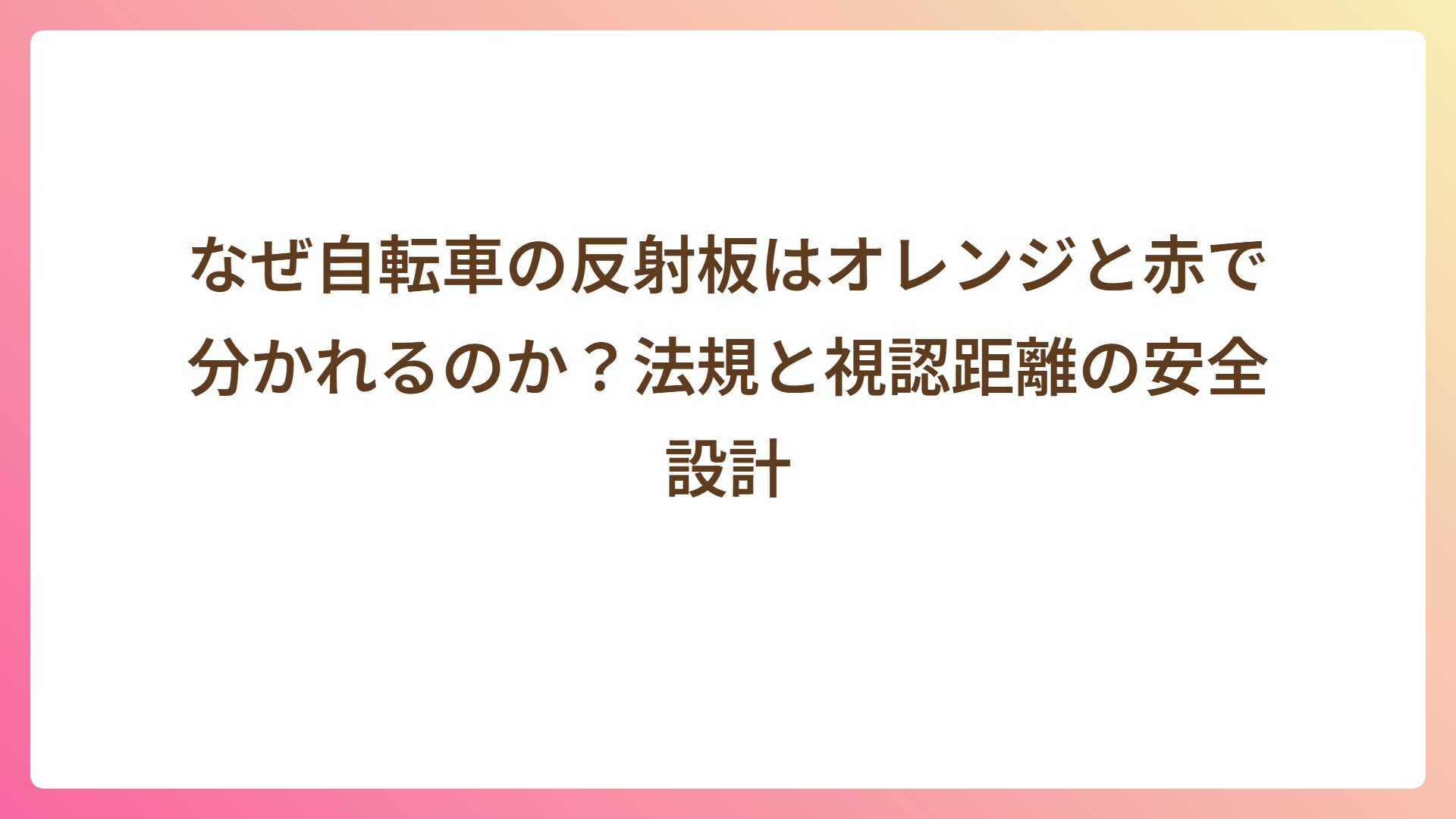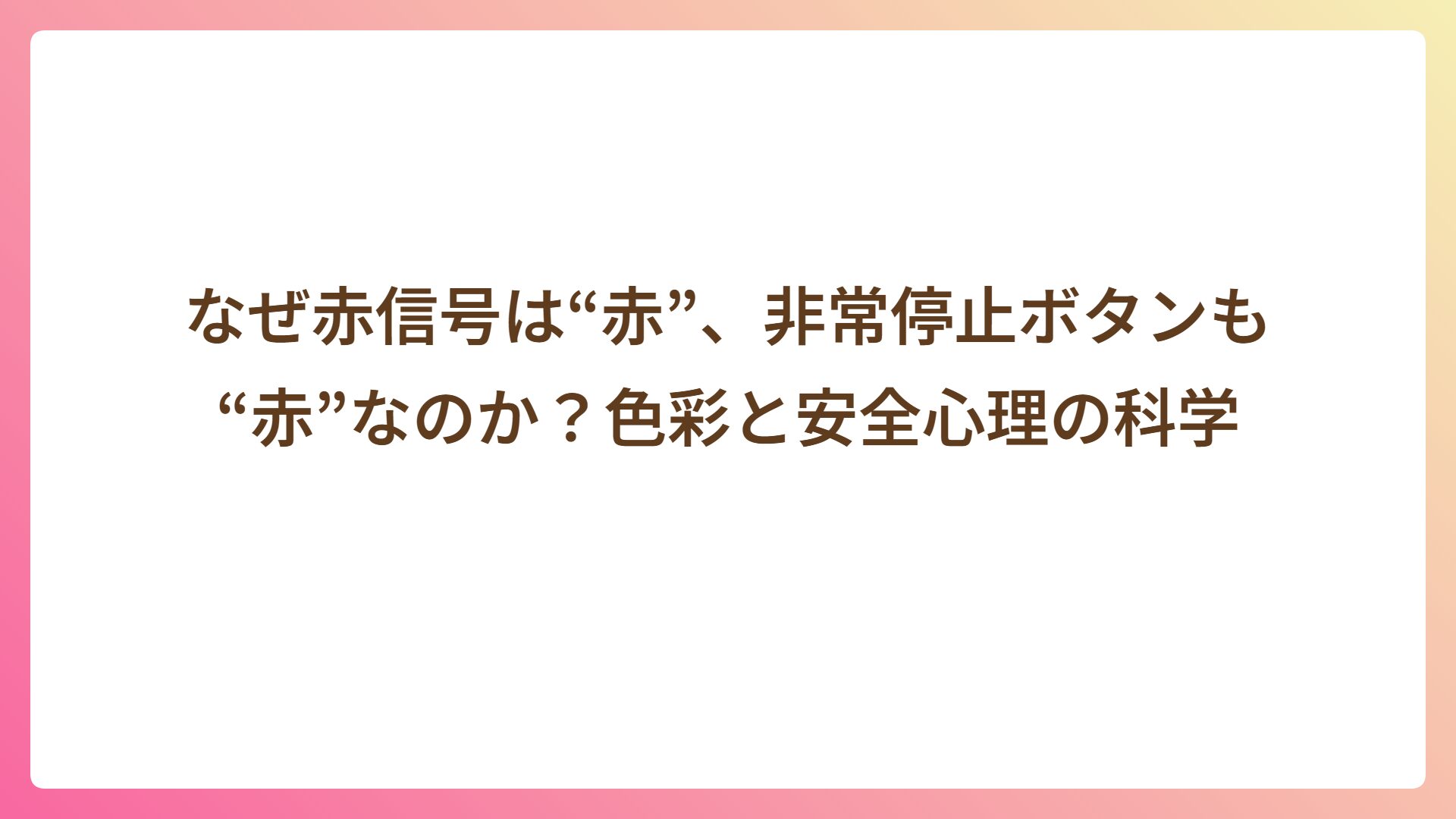なぜ裁判所の証人席は高めに設置されているのか?証言の可視化と緊張感
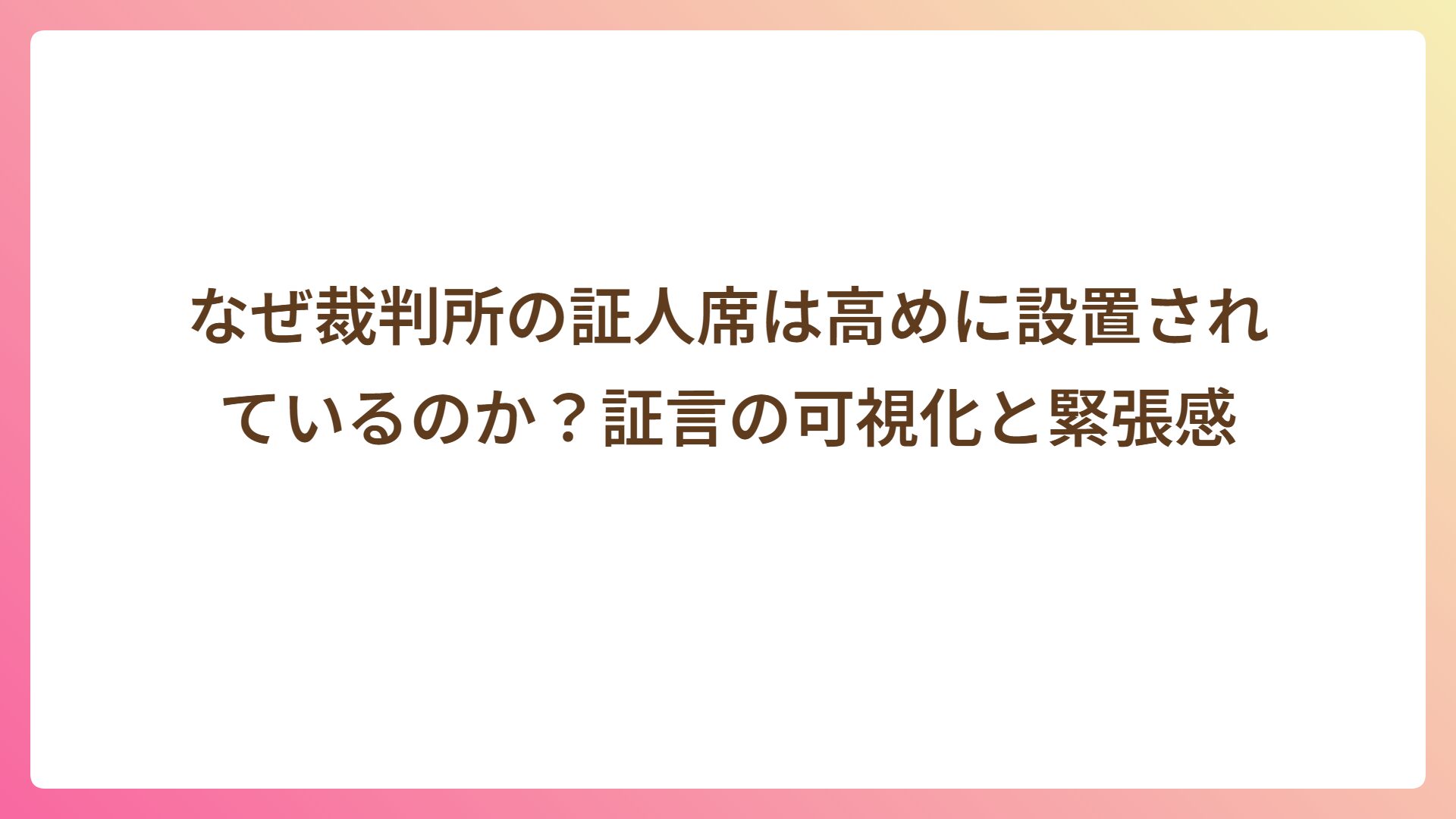
テレビやニュース映像で見る裁判所の法廷。
証人が立つ「証人席」は、裁判官席より低く、弁護人席や被告席よりやや高い位置にあります。
なぜこのように、わずかな段差を設けて設計されているのでしょうか?
それは、発言の可視性と心理的緊張の演出という2つの目的から来ています。
裁判官・陪審員・傍聴人から“見えやすくする”ため
証人の発言は、裁判の行方を左右する重要な要素です。
そのため、法廷では証人の表情や視線、声のトーンまでがしっかり見えるように設計されています。
証人席を床より少し高くすることで、
裁判官席・陪審員席・傍聴席のどの位置からでも顔が視認でき、声が通りやすい構造になります。
特に大型の法廷では、発言者が低い位置にいるとマイクに頼らざるを得ず、
非言語的な情報(表情・態度)が伝わりにくくなるため、
高さの調整=証言の信頼性を確保する設計でもあるのです。
発言に「責任」と「緊張感」を持たせる心理効果
証人席をわずかに高くすることには、心理的な意味もあります。
一段上がった場所で多くの人の視線を浴びると、人は自然に姿勢を正し、発言に慎重になります。
これは、「宣誓した言葉に責任を持たせる」ための空間的演出です。
逆に被告席や弁護席は少し低く設けられており、
証人が証言する際に「注目されている立場」であることを明確に示しています。
この“緊張設計”が、証言の真実性を高める抑止力にもなっているのです。
発声・音響の面でも合理的
法廷では声の反響を最小限に抑え、明瞭に聞き取れる音響設計が求められます。
証人席をやや高く設けることで、声が天井方向に抜けすぎず、
裁判官席に向けて自然に届く反射角が得られます。
この高さは見た目だけでなく、音響的にも最適化された寸法なのです。
世界的にも共通する「可視性の原則」
証人席を高くする慣習は日本だけでなく、欧米の裁判所でも共通しています。
どの国でも「証言は公開のもとで行われるべき」という原則があり、
そのためには全員から見える位置に立たせることが不可欠なのです。
つまり、証人席の高さは法の公平性を視覚的に表現する構造でもあります。
まとめ
裁判所の証人席が高めに設けられているのは、
発言者を見やすくする可視化設計と、証言に重みを与える心理設計の両立によるものです。
そのわずかな段差は、単なる建築構造ではなく、
「法の場における真実性と緊張感」を支えるための空間的メッセージなのです。