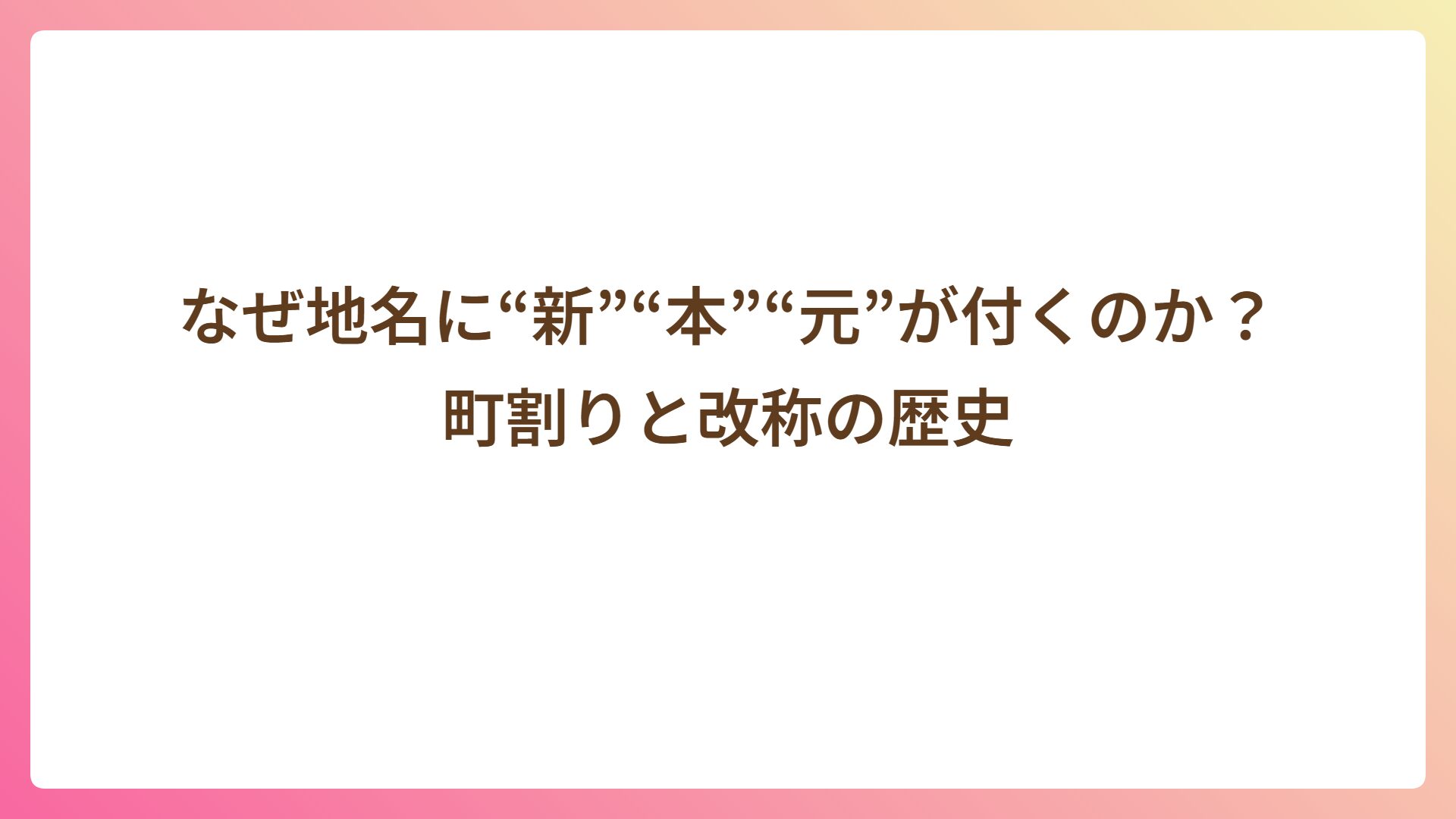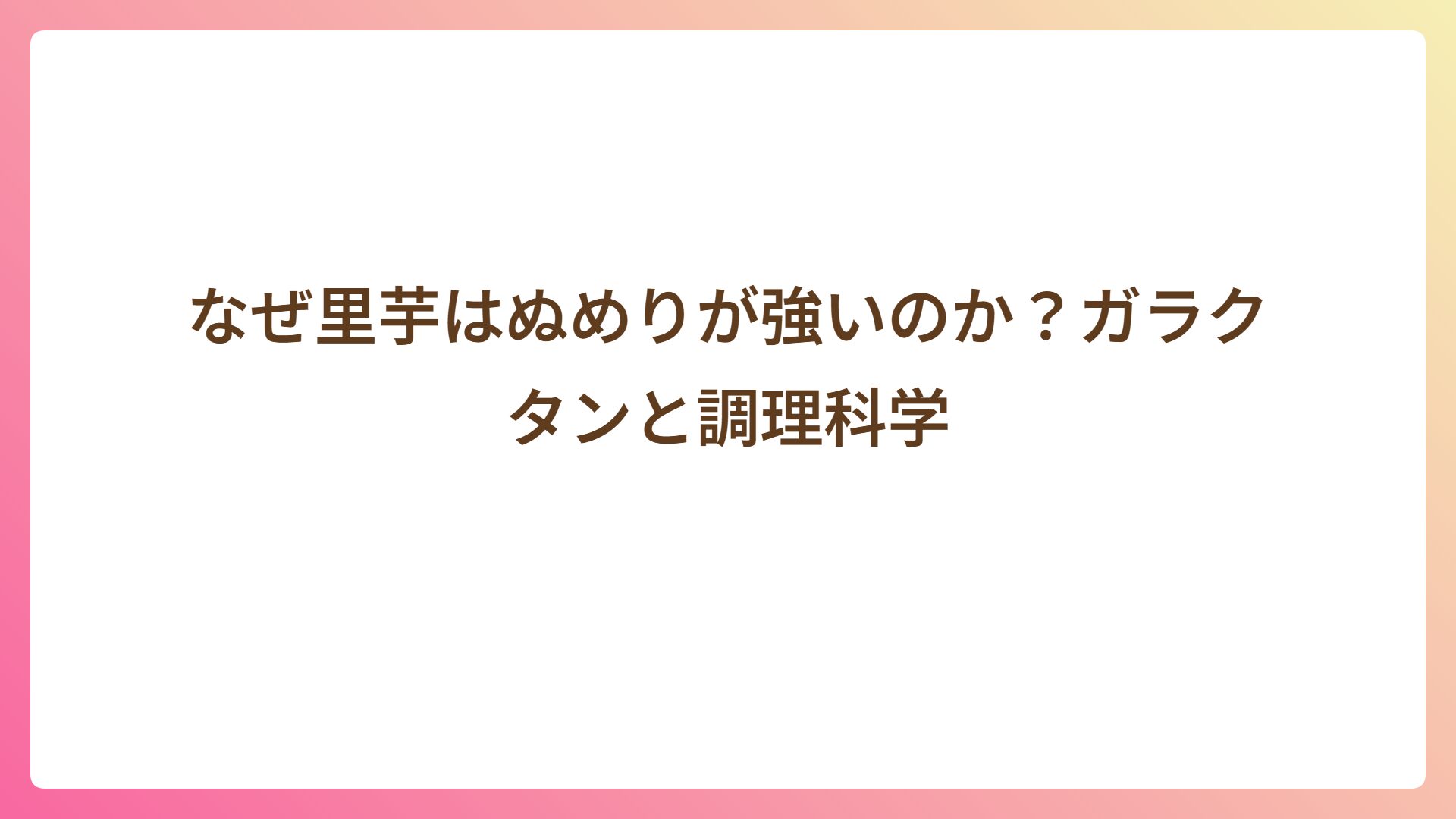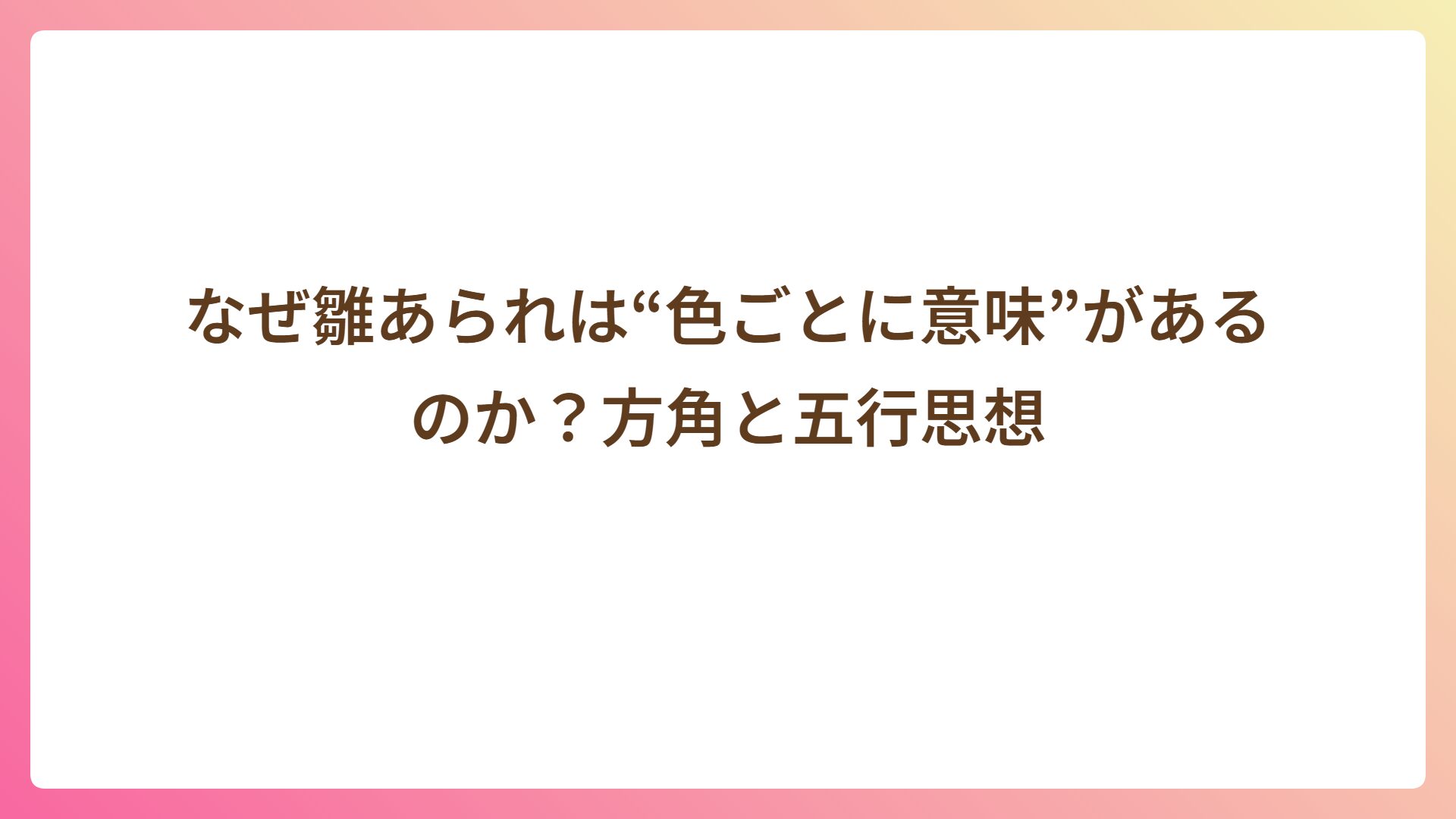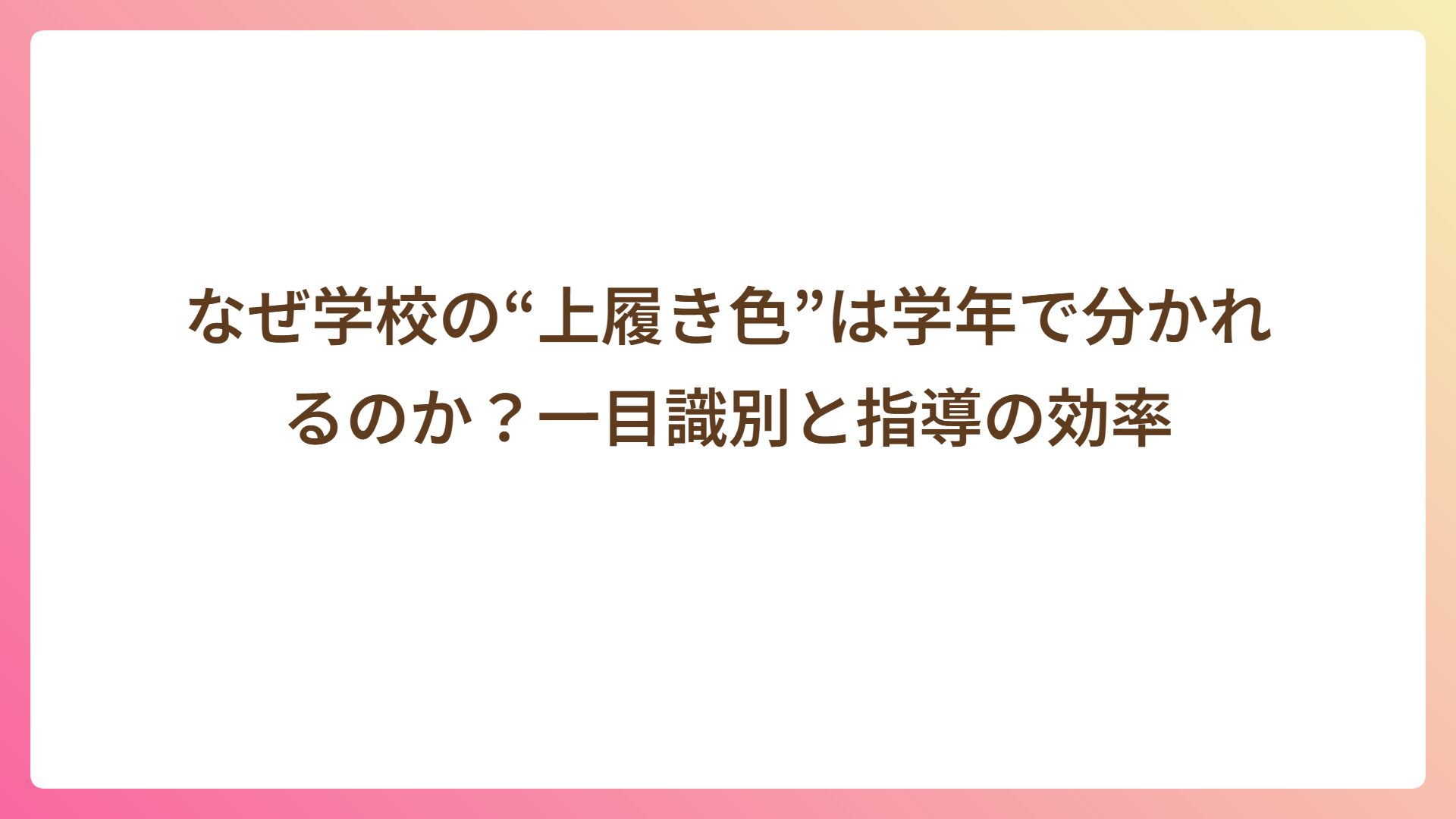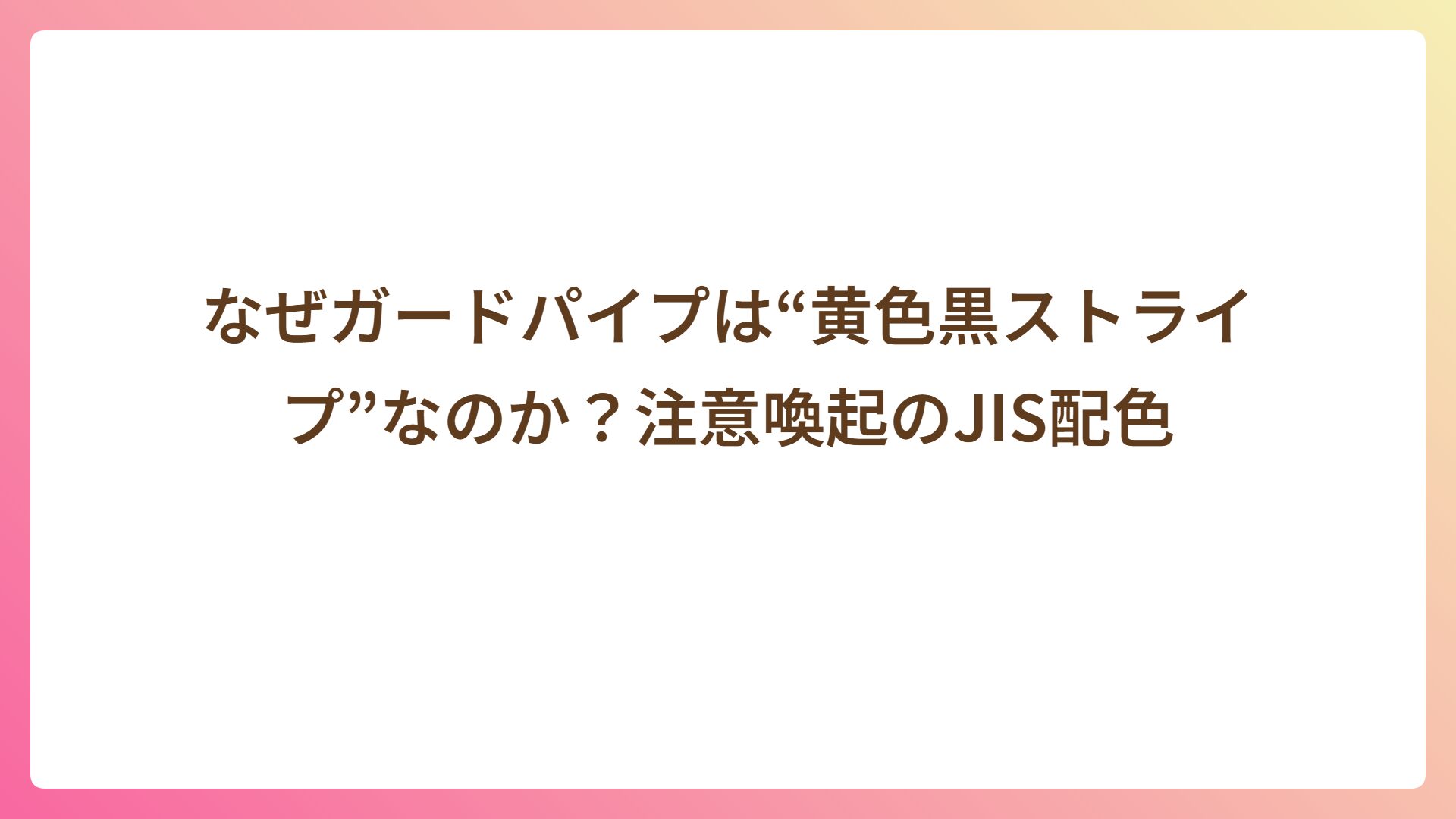なぜ鶏肉は“唐揚げ”で国民食になったのか?油の普及と学校給食
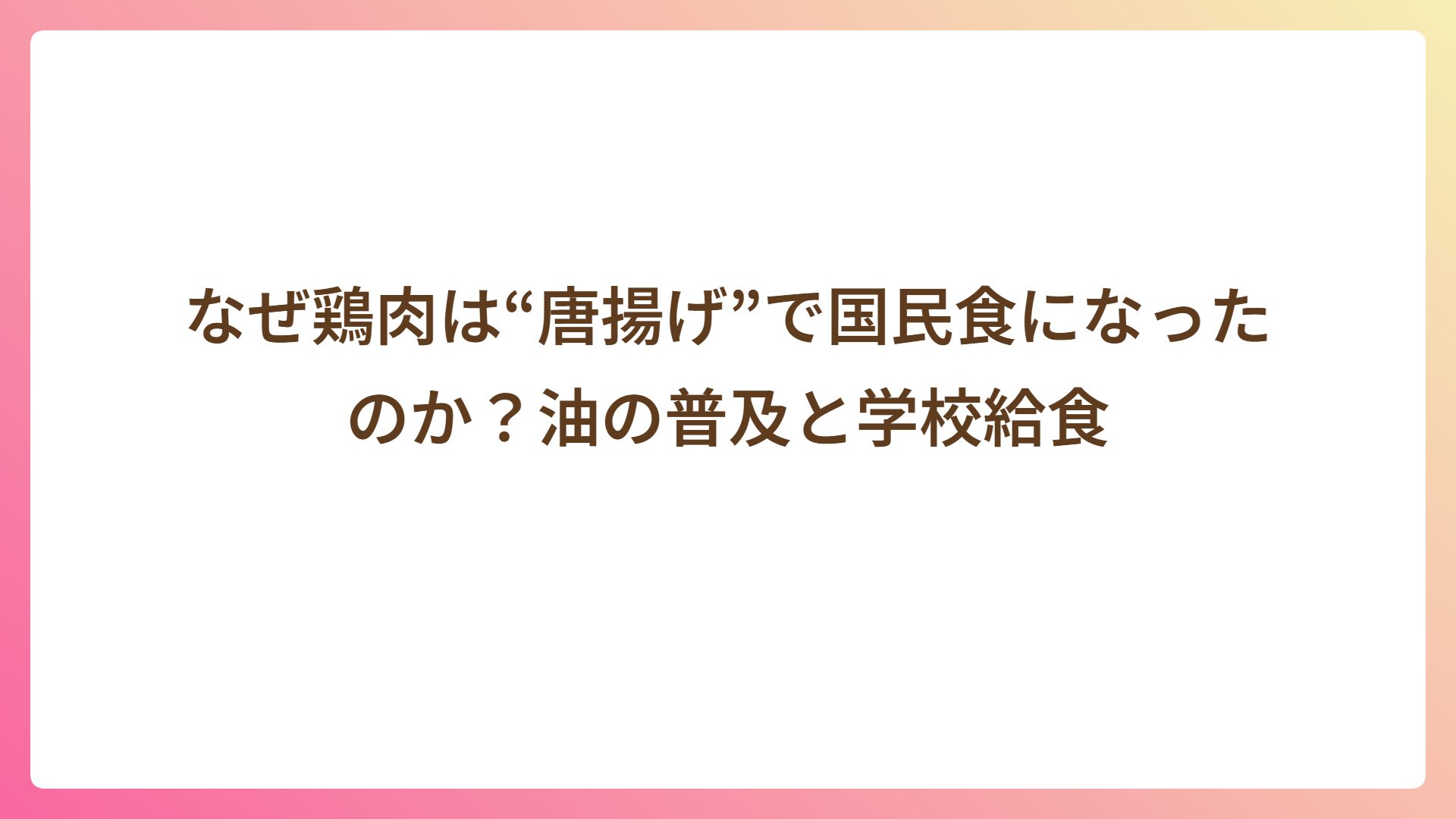
お弁当にも、夕飯にも、居酒屋にも。
いまや日本人の誰もが親しむ「鶏の唐揚げ」。
しかし、この料理がここまで国民的な存在になったのは、決して偶然ではありません。
その裏には、戦後の油脂産業の発展と学校給食による食文化の広まりがありました。
唐揚げのルーツは「精進揚げ」ではなく「南蛮文化」
唐揚げの名は、中国料理の「炸(チャー)」や「唐菜」から来ていますが、
日本での唐揚げは、実は洋風・中華の要素を取り入れた日本独自の料理です。
江戸時代にも「唐揚げ」と呼ばれる料理は存在しましたが、
それは魚や豆腐を油で軽く揚げる程度のもの。
現在のような衣を付けて鶏肉を油で揚げるスタイルが確立したのは、
昭和初期〜戦後にかけてのことです。
鶏肉が一般家庭に広まったのは戦後から
戦前の日本では、鶏肉は「晴れの日の食材」でした。
日常的に食べられるのは、卵を産まなくなった廃鶏か、行事用の鶏鍋くらい。
しかし、戦後になるとGHQの栄養改善政策や養鶏技術の進歩によって、
ブロイラー(肉用鶏)の大量生産が始まります。
1950年代には、国産鶏肉の流通量が飛躍的に増え、
安価で入手しやすい動物性たんぱく源として家庭の食卓に定着しました。
この「鶏肉の大衆化」が、唐揚げ普及の大前提となります。
食用油の工業化が“揚げ物時代”をつくった
戦前までの家庭では、油は高級品。
ごま油や菜種油を少量ずつ使うのが一般的で、
“油で揚げる”料理は特別なものでした。
ところが戦後、大豆・菜種油の精製技術と輸入拡大により、
安価で透明度の高いサラダ油が大量生産されるようになります。
これにより、家庭でも気軽に油をたっぷり使えるようになり、
コロッケ・天ぷら・唐揚げといった“揚げ物黄金期”が到来しました。
とくに鶏の唐揚げは、
油との相性が良く、調味も簡単、食べ応えもある。
まさに「新時代の家庭料理」として受け入れられたのです。
学校給食が“唐揚げ世代”を生んだ
1954年に学校給食法が制定され、全国の小中学校で給食が始まります。
当初はパンとミルクが中心でしたが、
栄養バランスを考慮して動物性たんぱく質として鶏肉料理が多く採用されました。
その中でも唐揚げは、
- 調理が大量生産に向く
- 子どもが食べやすく残りにくい
- 冷めてもおいしい
という理由から、給食のスター料理に。
1970年代の子どもたちにとって、唐揚げは「みんなが好きな味」の代名詞となり、
その世代が大人になる頃には、
唐揚げはすでに国民的ソウルフードになっていたのです。
コンビニと弁当文化が後押しした“常食化”
1980年代以降、コンビニやスーパーの惣菜コーナーが急増すると、
唐揚げは「持ち歩けるおかず」として再評価されました。
調理しなくても買える・冷めてもおいしい・子どもも大人も好き——
この三拍子が揃った唐揚げは、
お弁当・晩酌・イベント・駅弁と、あらゆる食シーンに対応できる万能選手へ。
「唐揚げ専門店」や「からあげグランプリ」が登場するのも、
この“常食化”の延長線上にあります。
まとめ
鶏の唐揚げが国民食になったのは、
食用油の普及・鶏肉の大量生産・学校給食による世代浸透という三つの要因が重なったからです。
唐揚げは単なる家庭料理ではなく、
戦後日本が築いた「安く・うまく・みんなが食べられる」食文化の象徴。
その一口には、技術革新と時代の空気が香ばしく詰まっているのです。