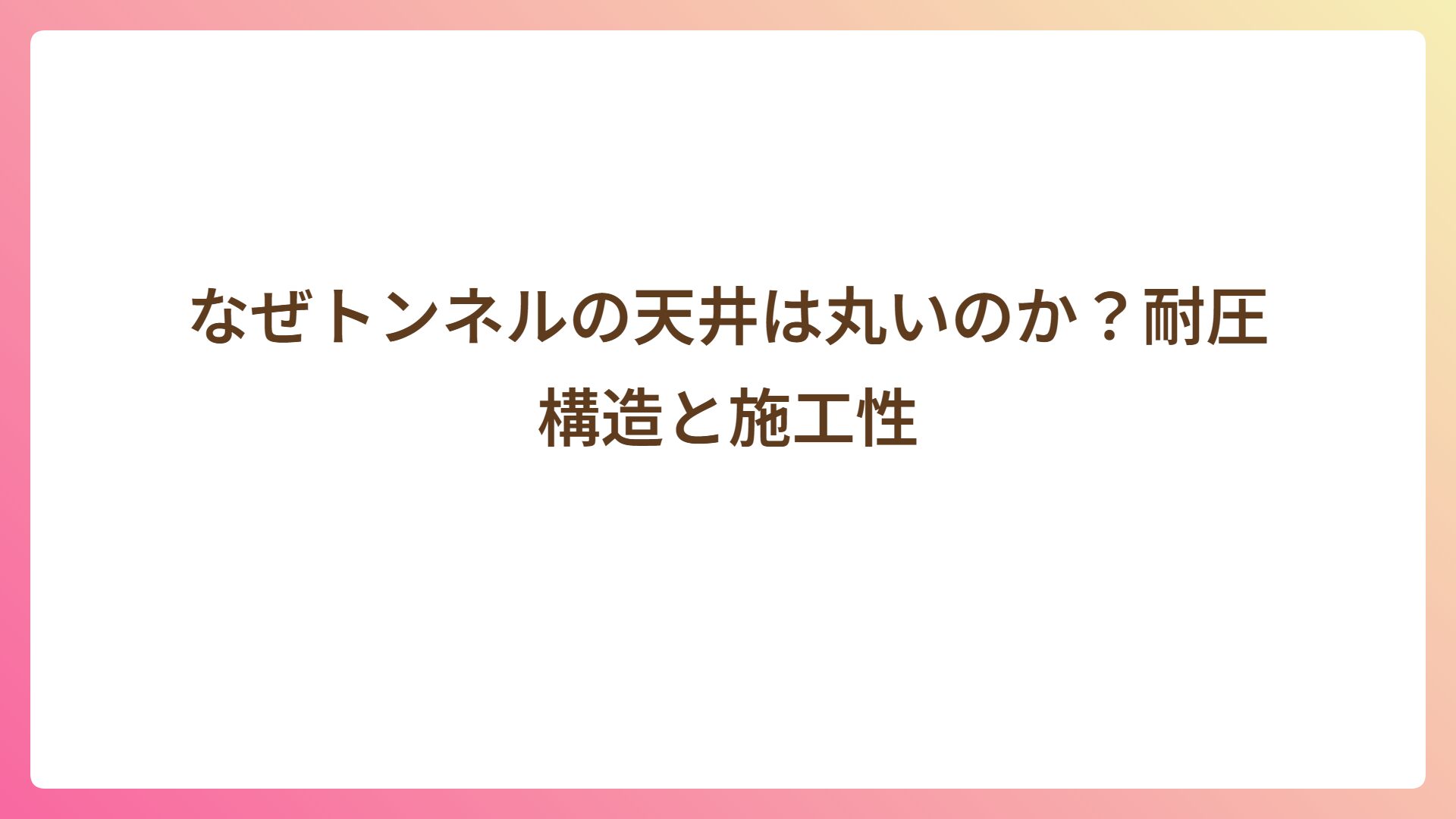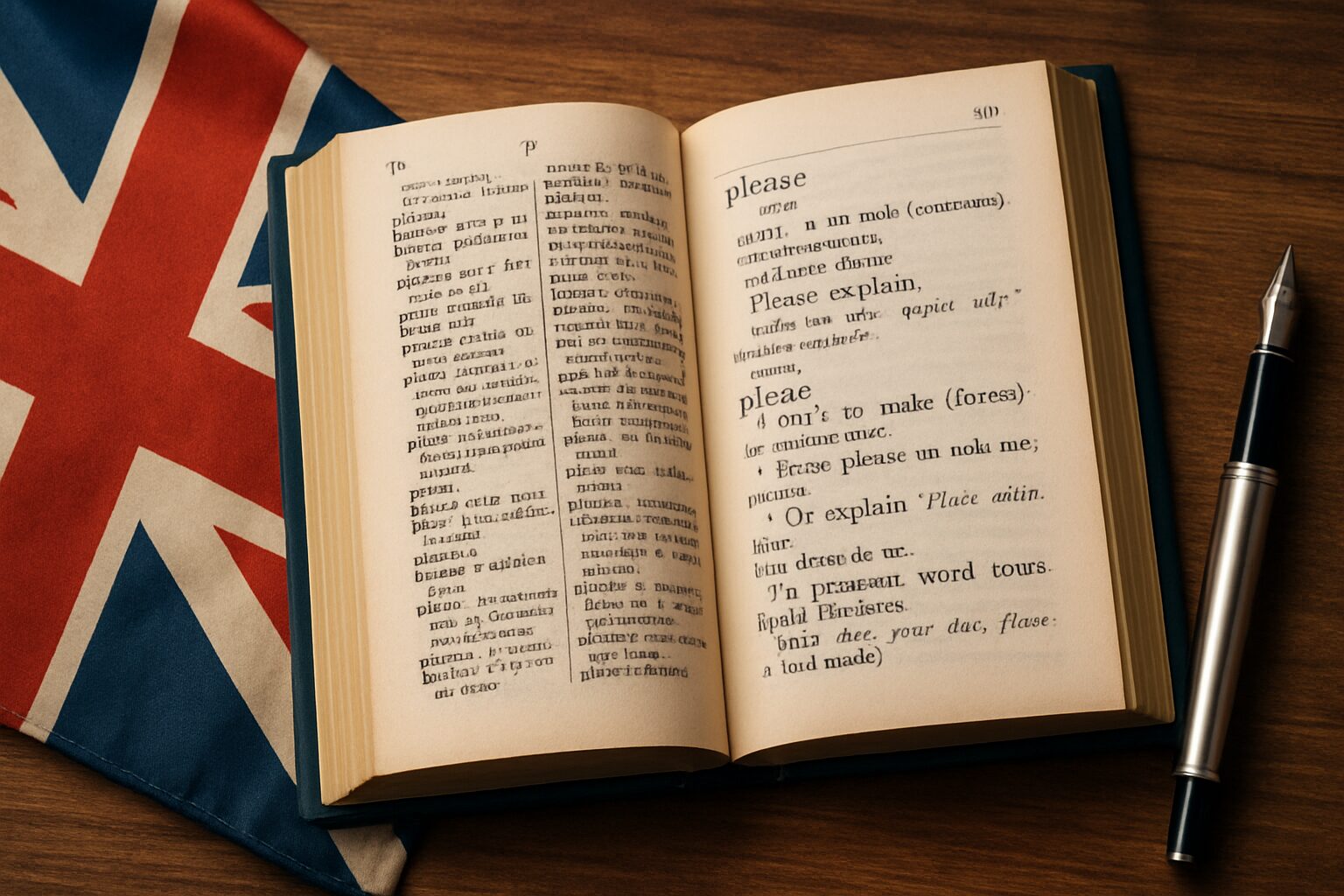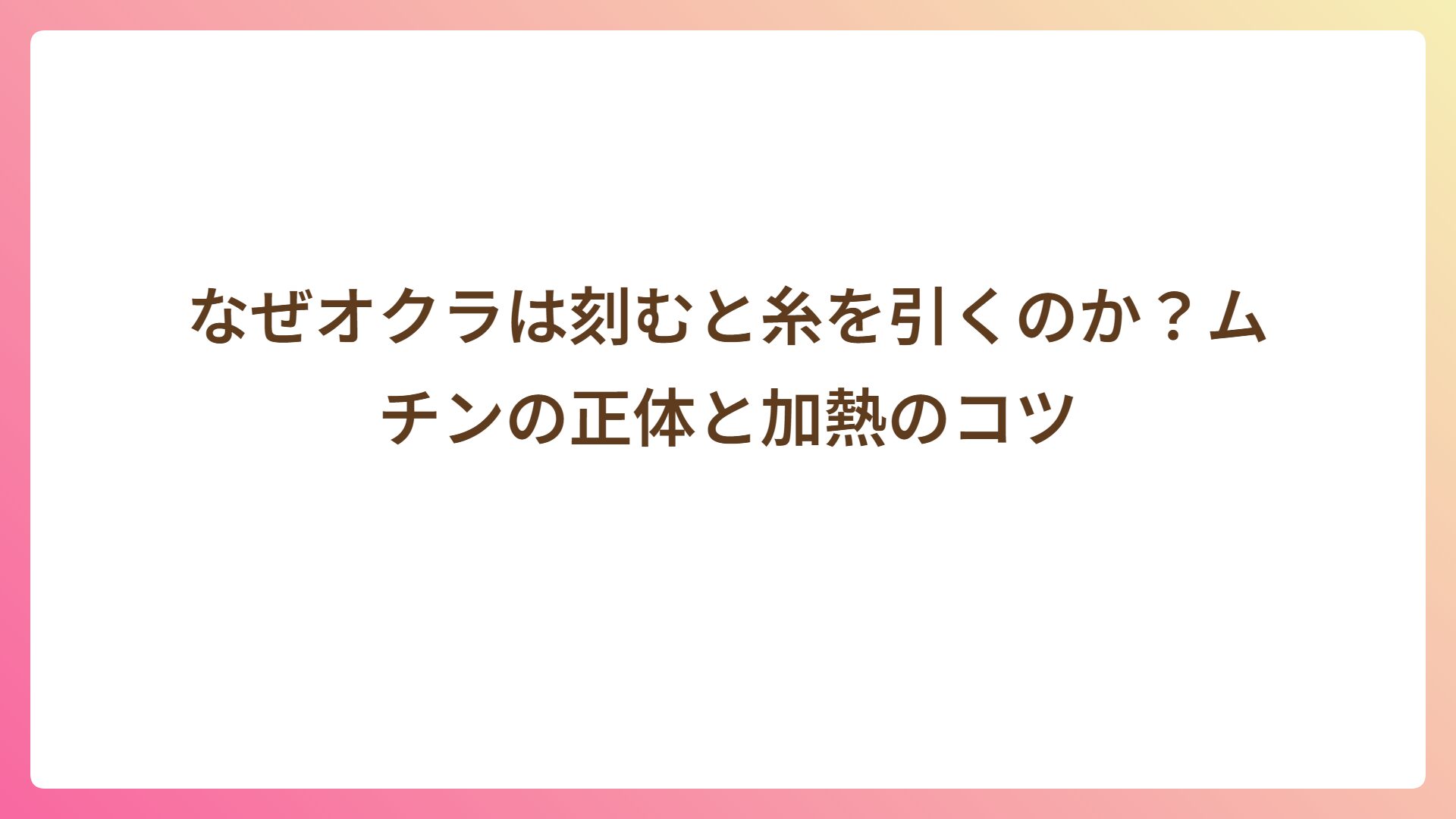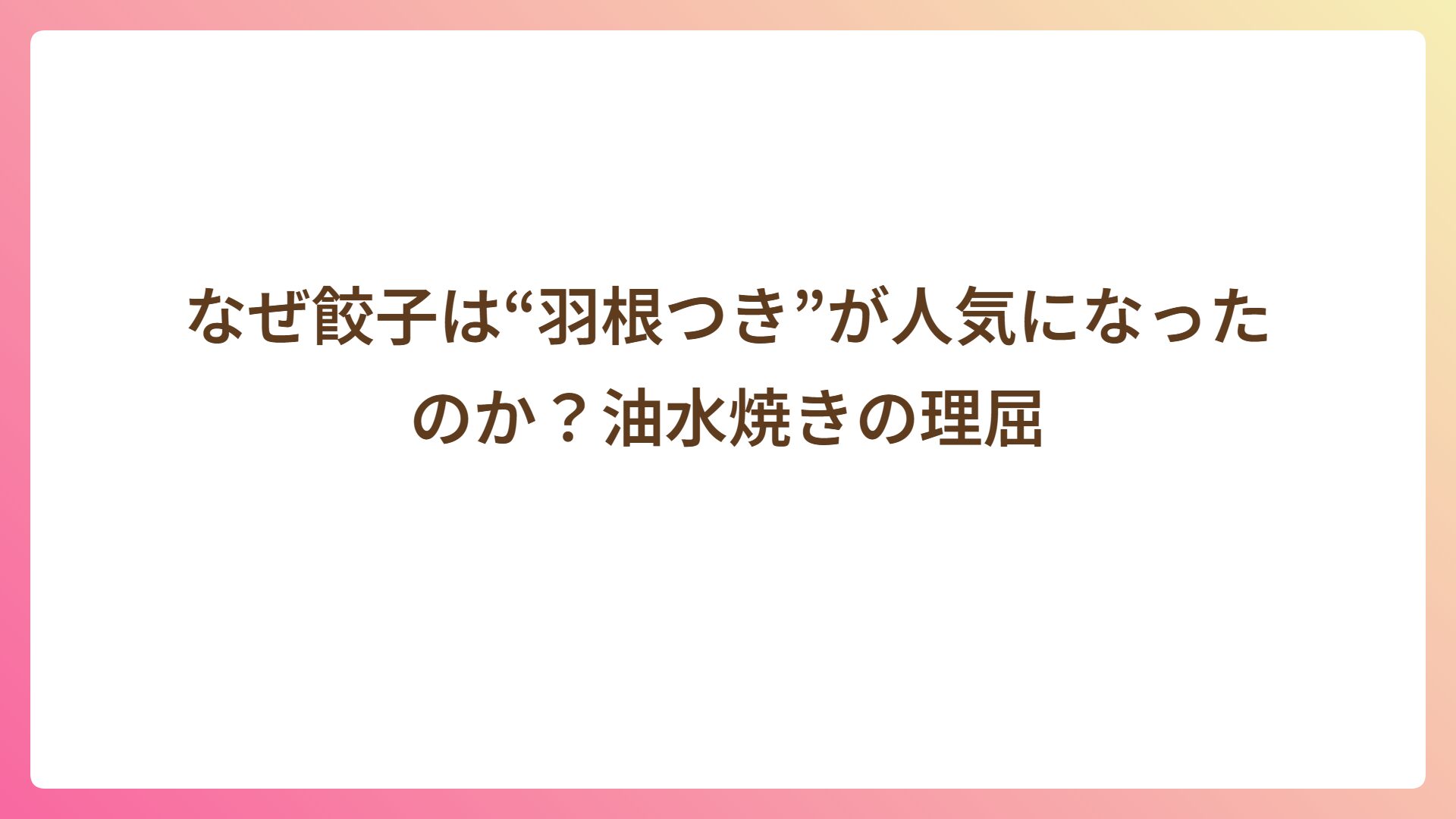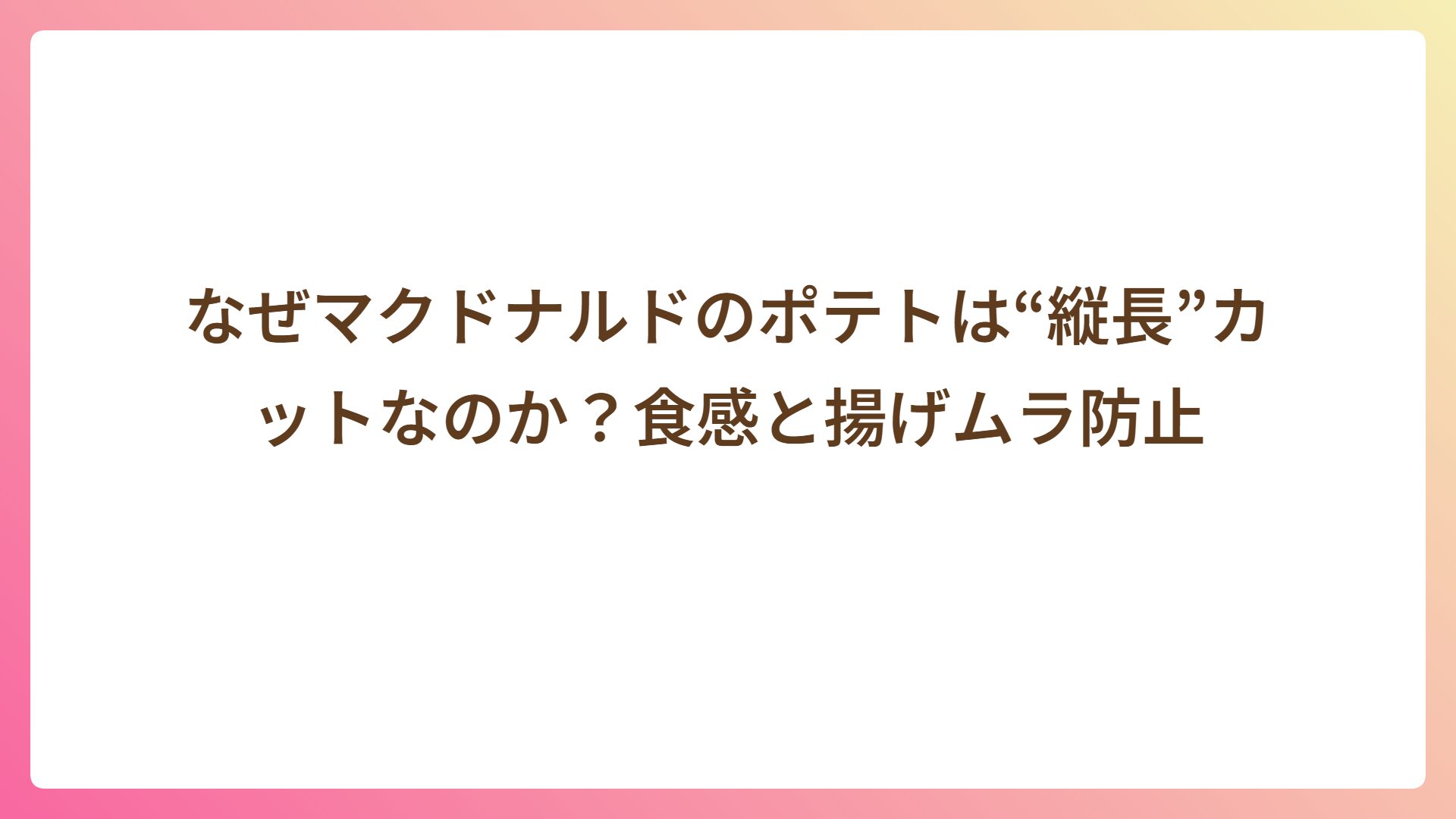なぜ鏡餅は“重ねる”のか?円と歳の象徴
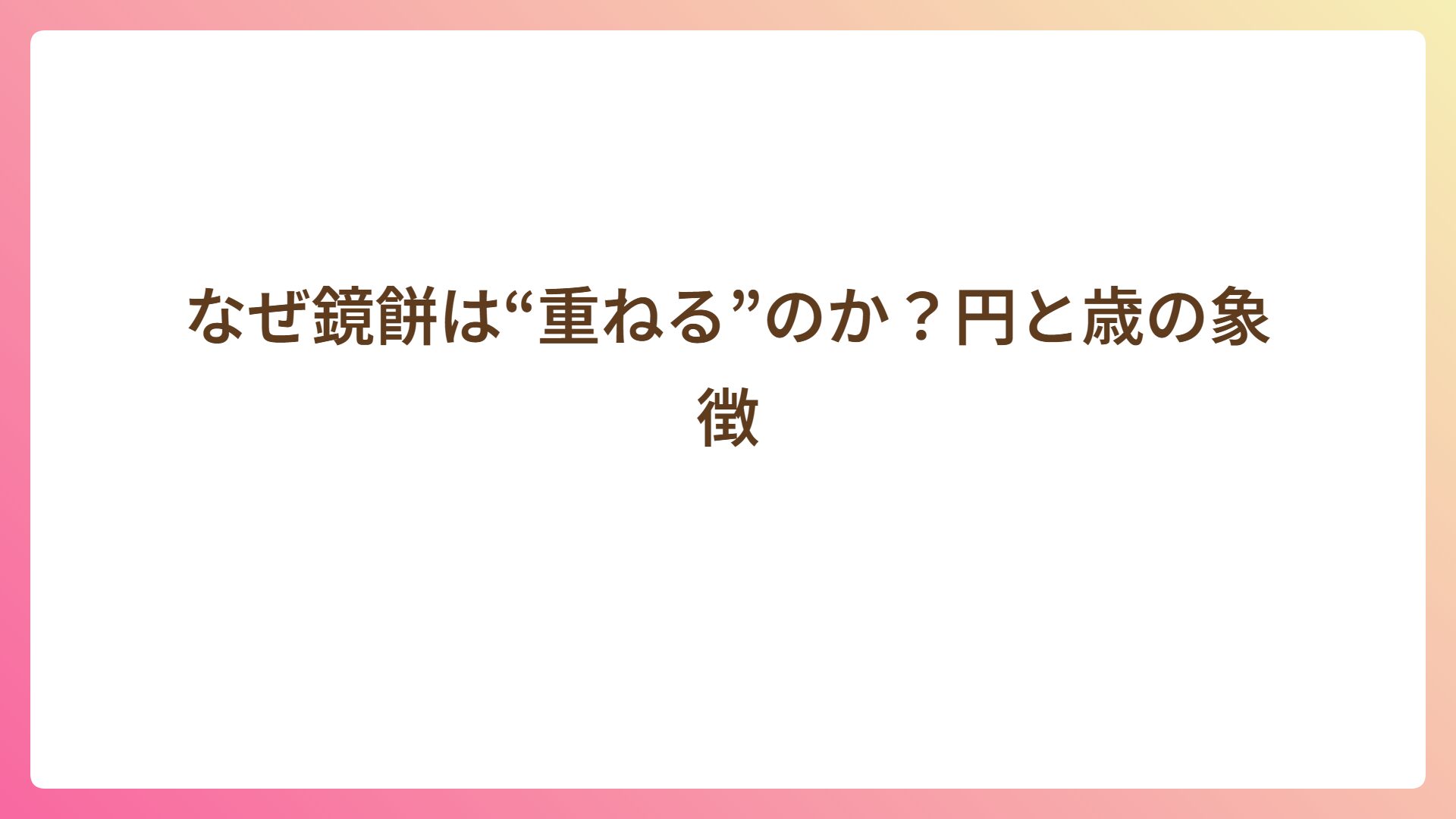
お正月に飾られる鏡餅。
上下二段の丸い餅が重ねられ、その上に橙(だいだい)をのせる姿は、
日本の新年を象徴する伝統的な光景です。
しかし、なぜ鏡餅は“重ねる”形をしているのでしょうか?
その答えは、円形に込められた調和の願いと、歳月を重ねるという人生観にあります。
鏡餅は“年神の依代(よりしろ)”
鏡餅は、正月にやってくる年神(としがみ)さまをお迎えするための供え物です。
年神は新しい一年の「命」と「稲の実り」をもたらす神とされ、
その宿る場所として餅が飾られます。
日本では古くから、餅は「稲魂(いなだま)」の象徴。
米を搗いて作る丸餅は、生命力と豊穣のエネルギーを凝縮した食物と考えられていました。
鏡餅とは、つまり年神が降臨し、宿る神聖な“鏡”のような存在なのです。
“重ねる”のは歳月と円満の象徴
鏡餅を二段に重ねる理由は、
「歳月を重ねる」=「長寿と繁栄」を意味するからです。
上段と下段には諸説ありますが、代表的な解釈は以下の通りです:
- 下段:過去(旧年)
- 上段:未来(新年)
- 重ねることで:時をつなぎ、円満に年を越す
つまり、二段の餅は「昨年の感謝と新年の祈り」を重ね合わせる形。
年神さまを迎え、過去と未来がつながる象徴的な構造なのです。
また、丸い形にも意味があります。
円(まる)は「和」や「縁」に通じ、人の心が円満におさまることを願う形。
この“丸の重なり”こそ、鏡餅の最も美しい縁起といえます。
“鏡”という名前の由来
「鏡餅」という名は、古代の青銅鏡に似た形に由来します。
鏡は神事において、神の依代(よりしろ)として用いられる神聖な道具。
伊勢神宮の「八咫鏡(やたのかがみ)」をはじめ、
鏡は真実を映す心の象徴でもありました。
つまり鏡餅は、
神を映す鏡のように人の心と神の心を通わせる媒介として名付けられたのです。
橙をのせるのは“代々続く”の願い
鏡餅の頂に置かれる橙(だいだい)は、
「代々(だいだい)家が続くように」という言葉遊びから、
家系繁栄の象徴とされています。
また、橙は冬でも実が落ちず、翌年も枝に残ることから、
「家運が途切れない」「命が受け継がれる」縁起物として親しまれました。
重ねた鏡餅の上に橙をのせる構造は、
まさに命の継承と繁栄を三層で表す造形なのです。
神への供えから“食べる儀式”へ
正月が明けると、「鏡開き」で鏡餅を割って食べます。
これは神に供えた力の宿る餅をいただき、
一年の無病息災を祈る行為。
餅を「切る」と言わず「開く」と呼ぶのは、
刃物を避け、神との縁を“断たない”ため。
ここにも、円満に始まり円満に終えるという考えが貫かれています。
まとめ
鏡餅を重ねるのは、
過去と未来をつなぐ歳の象徴であり、
円形に込められた調和と長寿の願いの表れです。
- 二段=歳月の重なり・円満
- 丸形=和と縁の象徴
- 橙=家運の継続
鏡餅とは、単なる正月飾りではなく、
「時と命を重ねる」という日本人の祈りの形なのです。