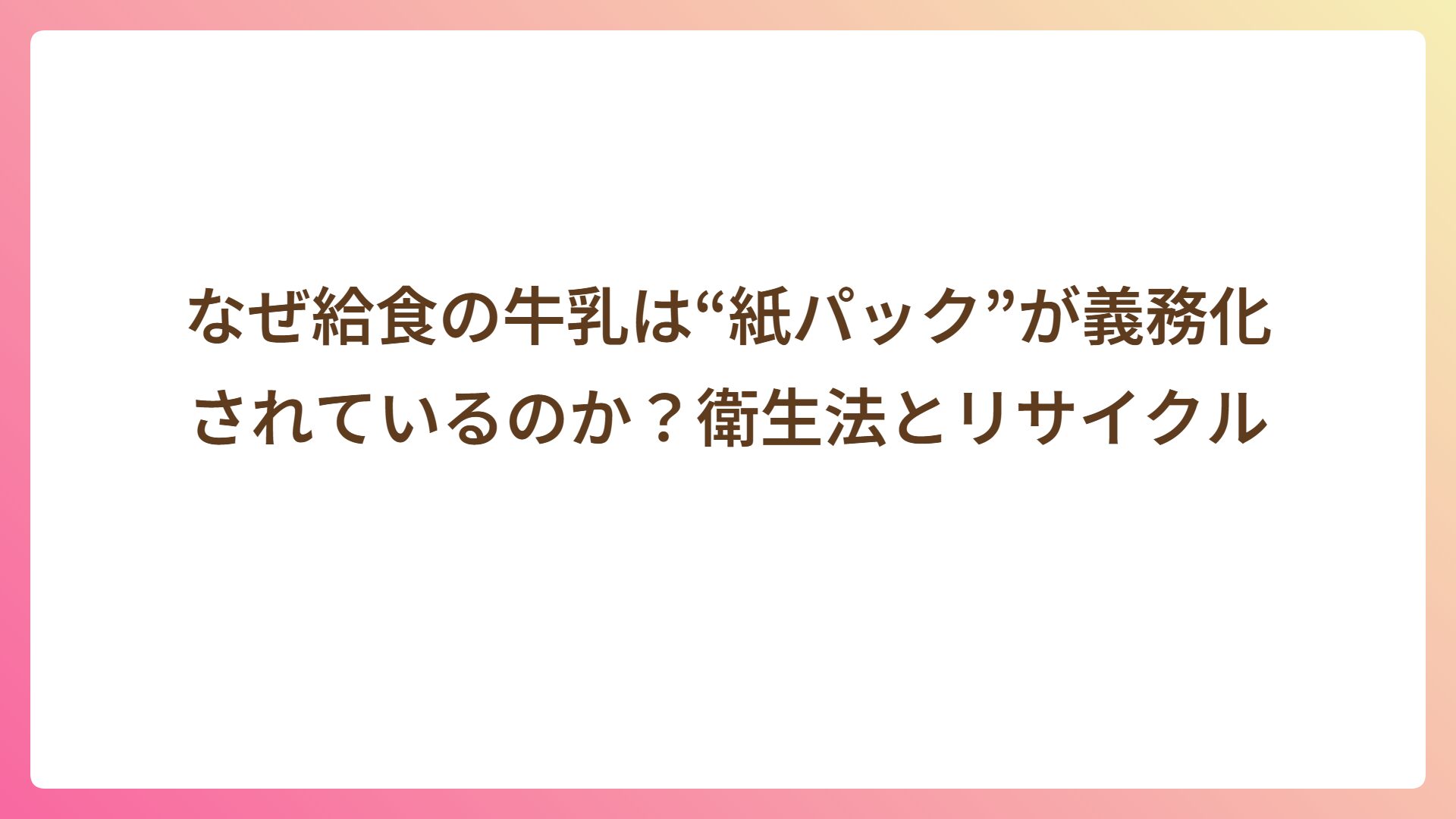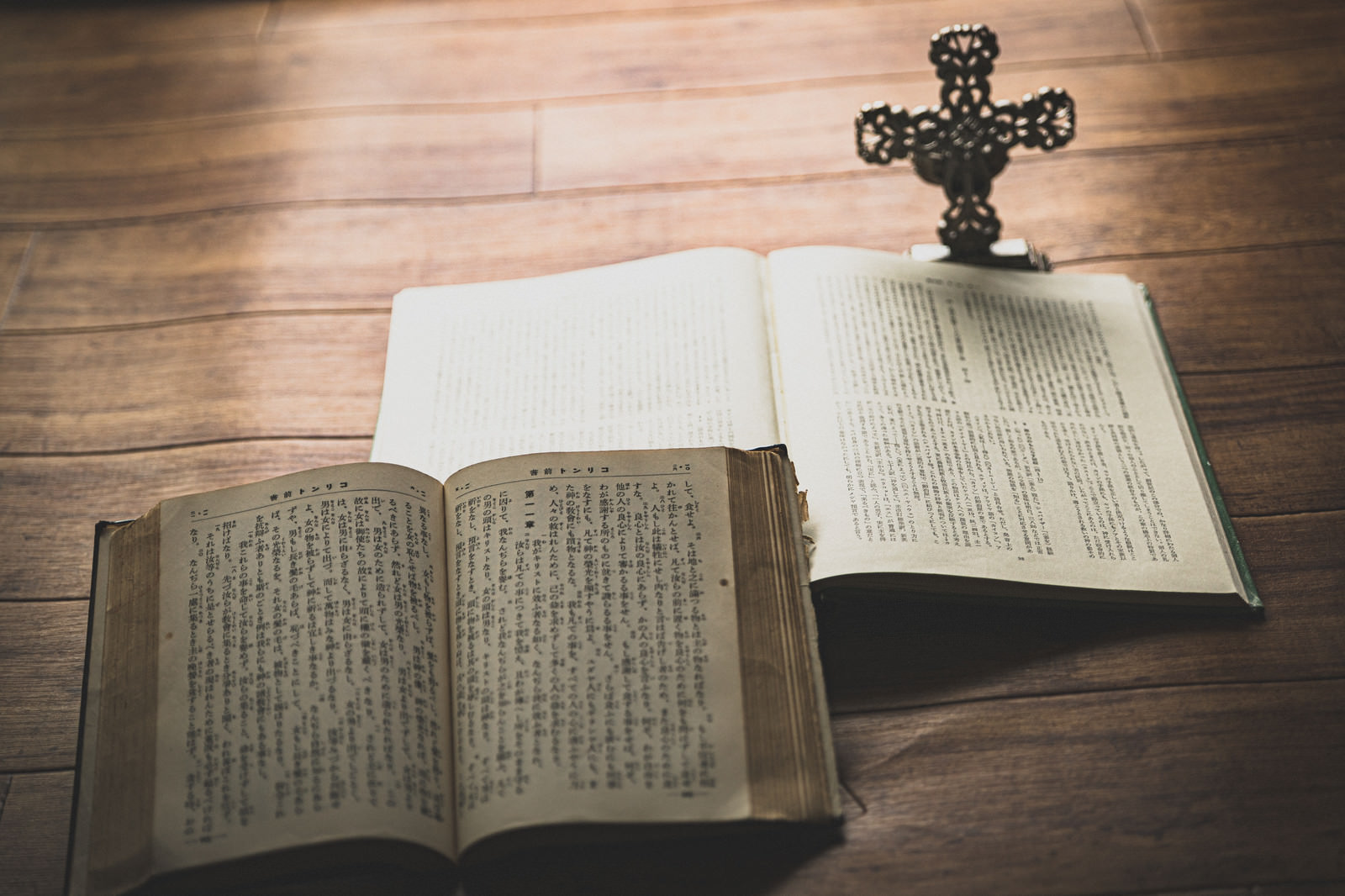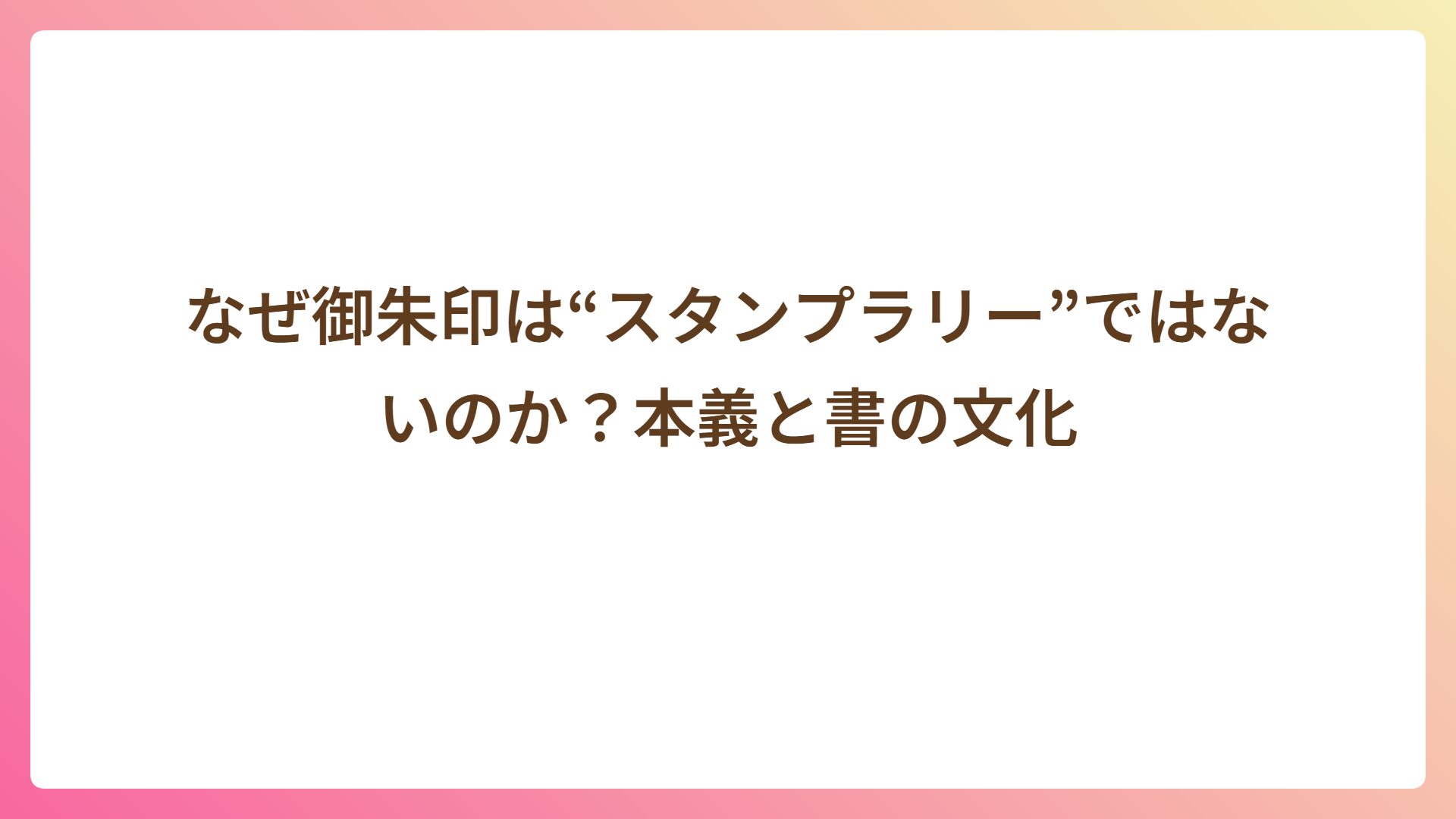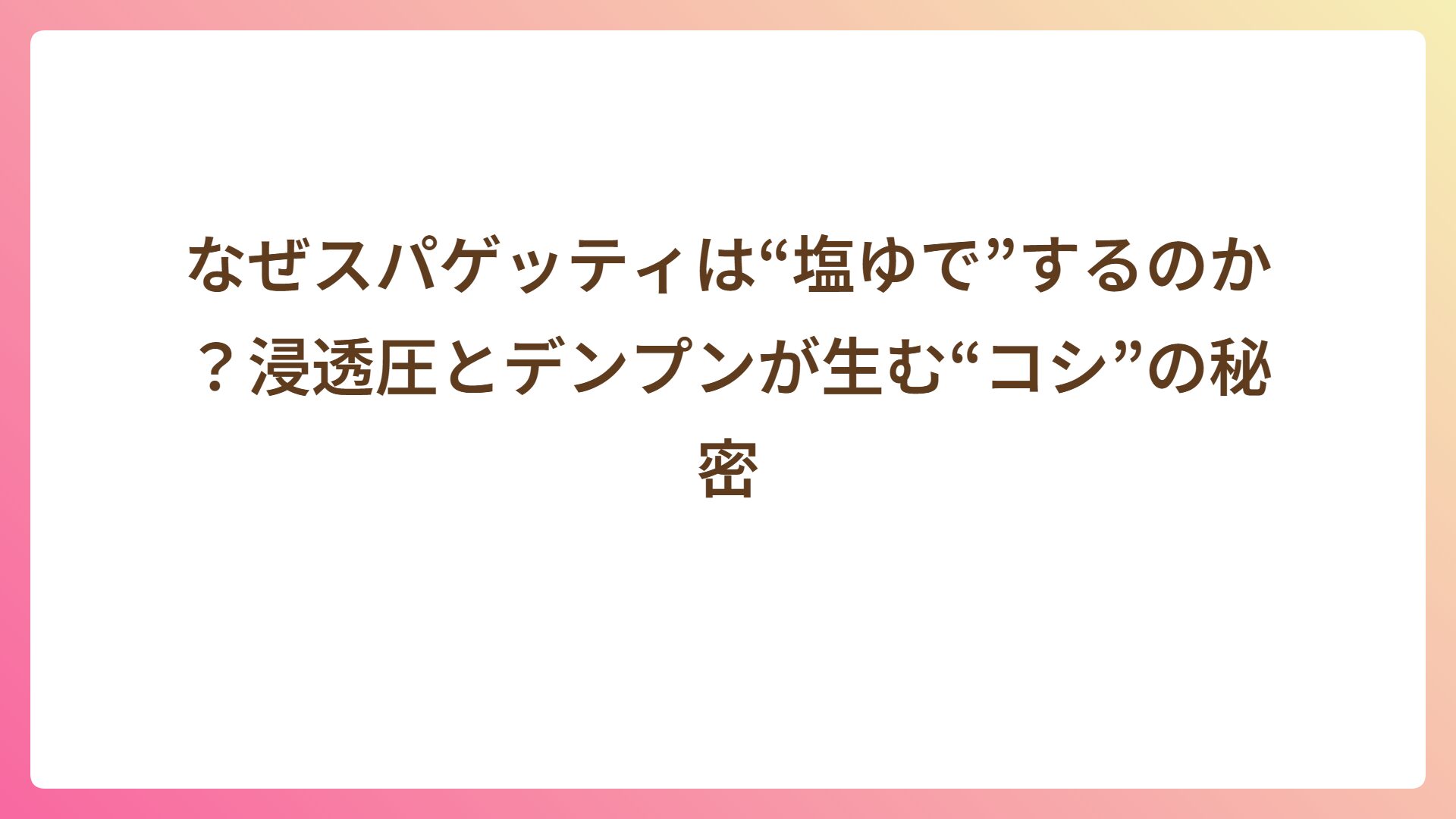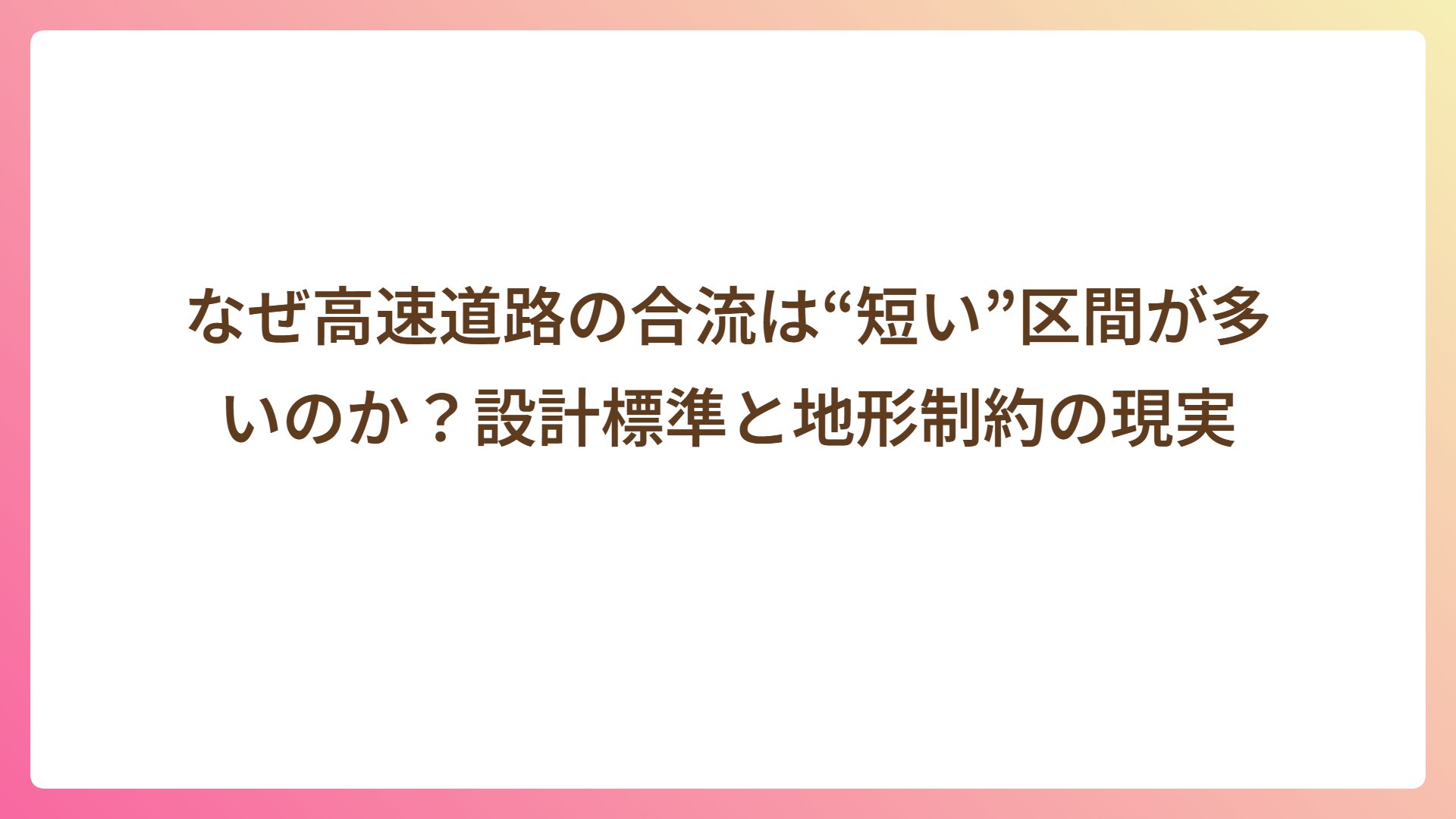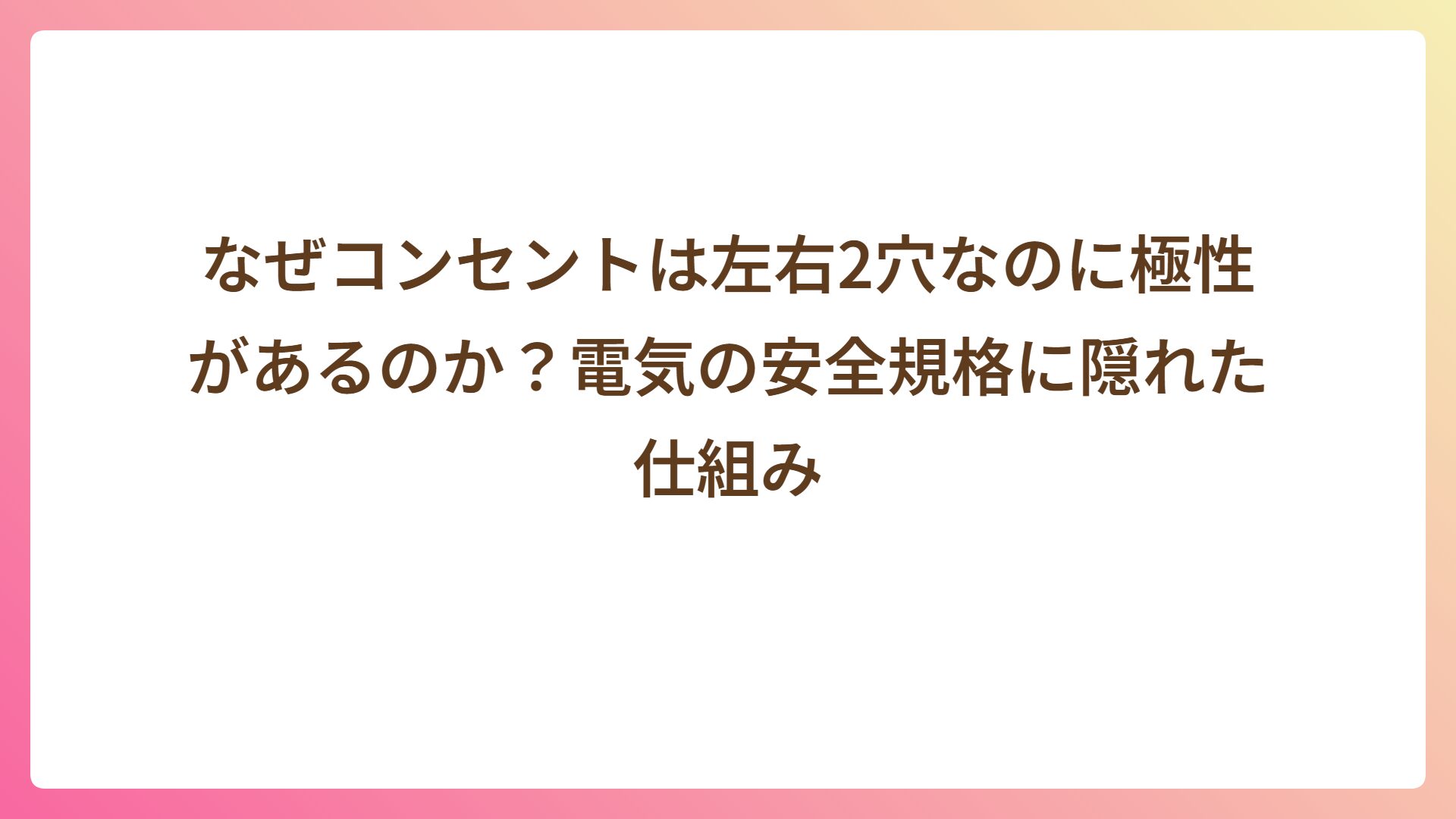なぜ日本では“氷砂糖”が家庭酒の定番なのか?溶解速度と抽出管理
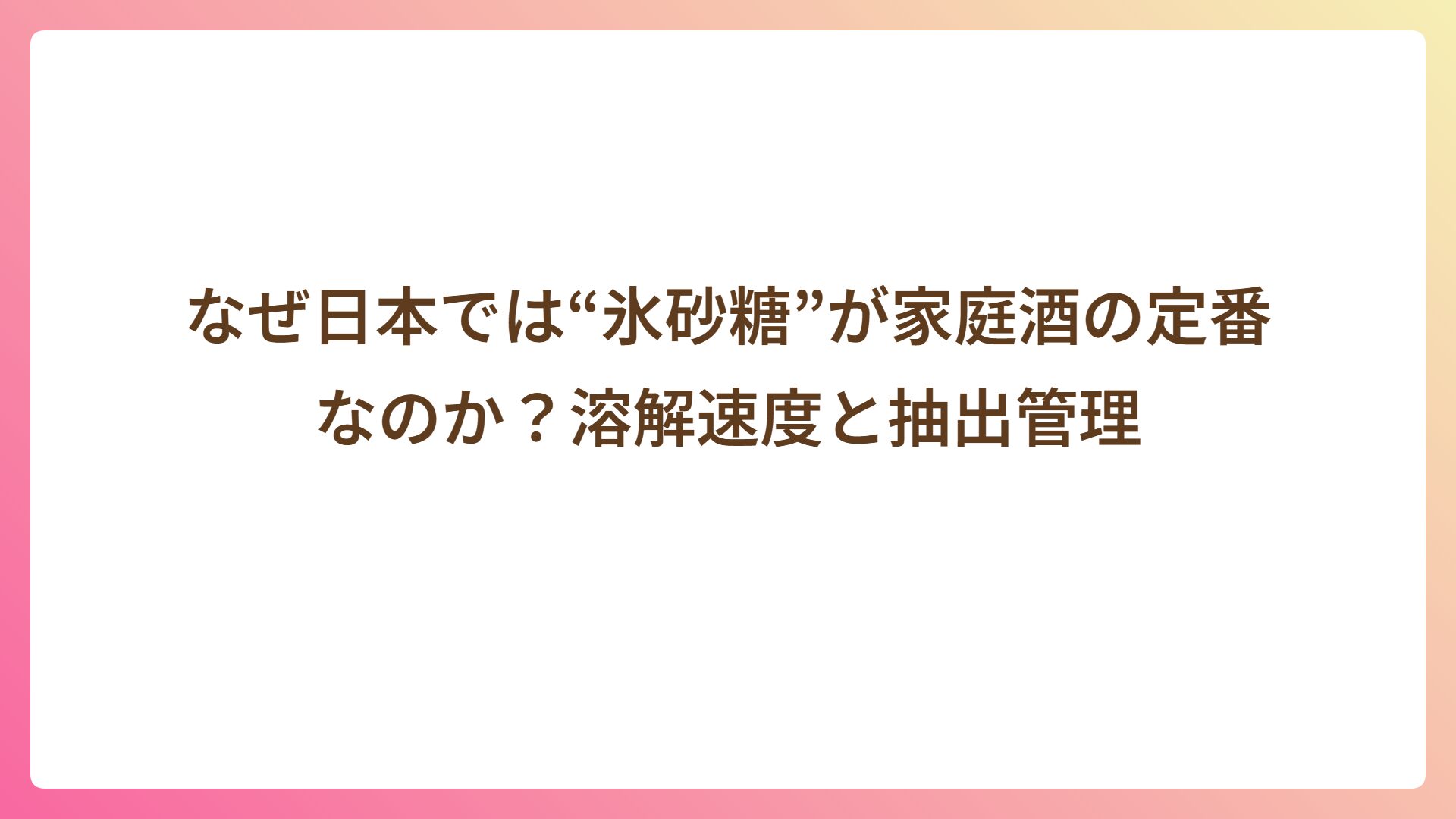
日本の家庭で果実酒を漬けるとき、砂糖といえばほとんどの場合「氷砂糖」が選ばれます。
同じ砂糖でもグラニュー糖や黒糖ではだめなのか――。
その答えは、氷砂糖の溶け方の遅さと、抽出をコントロールする働きにあります。
氷砂糖は“ゆっくり溶ける砂糖”
氷砂糖は、グラニュー糖を水に溶かしてから再結晶させたもので、
一粒が大きく透明な結晶構造をしています。
このため表面積が小さく、アルコールや水に溶ける速度が非常に遅いのが特徴です。
この「ゆっくり溶ける」という性質が、果実酒づくりでは大きな利点になります。
急に砂糖が溶けてしまうと、液中の糖度が一気に上がり、
果実の水分や香り成分がアルコールにうまく移らなくなることがあります。
氷砂糖を使うことで、数週間〜数か月にわたって穏やかに抽出が進むのです。
溶解速度が“抽出のペースメーカー”になる
果実酒では、アルコールが果実から香りや酸味成分を引き出す一方、
糖分がその速度を緩衝材のように調整しています。
糖分が少ないと抽出が急激に進み、青臭さや渋みが出やすく、
逆に多すぎると果実からの成分移行が止まってしまいます。
氷砂糖のゆっくりした溶解は、アルコール濃度と糖濃度のバランスを一定に保ち、
“果実がほどよく開く時間”を与える仕組みとして働くのです。
果実の形を崩さない“穏やかな浸透圧変化”
梅やさくらんぼなどの果実を漬けるとき、糖が急に溶け出すと
液の浸透圧が急上昇し、果肉がしぼんでしまいます。
氷砂糖なら糖の溶け出しがゆるやかなため、果実の細胞が少しずつ水分を放出し、
果肉を保ちながら香りや酸を均等に抽出できます。
これにより、仕上がりが濁りにくく、果実の風味を長く保つことができるのです。
雑味を出さない“純度の高さ”
氷砂糖は高純度のショ糖結晶で、不純物やミネラル分がほとんど含まれていません。
そのため発酵や変色を引き起こす要因が少なく、
長期保存にも向く“安定した糖源”として信頼されています。
黒糖や三温糖は風味が強く、香りに個性を出したいときには有効ですが、
果実本来の香りを生かす梅酒や果実酒では、氷砂糖の無臭で澄んだ甘さが理想的なのです。
家庭酒文化で定着した“安心の目安”
氷砂糖が家庭酒の定番となった背景には、科学的な理由だけでなく文化的な経緯もあります。
昭和期に梅酒づくりが家庭の年中行事として広まった際、
扱いやすく失敗しにくい砂糖として推奨されたのが氷砂糖でした。
見た目にも清潔感があり、量を量りやすく、
アルコールに長く漬けても味が変化しにくいことから、
「果実1kgに氷砂糖1kg」という黄金比が定着したのです。
まとめ:氷砂糖は“時間を味方にする砂糖”
家庭酒に氷砂糖が選ばれる理由は、甘さのためだけではありません。
- ゆっくり溶けて抽出をコントロールする
- 果肉を傷めず、香りを長持ちさせる
- 不純物が少なく、長期保存に強い
- 失敗しにくく、安定した味を生む
つまり、氷砂糖は果実とアルコールの“対話をゆっくり進める”ための調整役なのです。
時間をかけて自然に甘みが馴染むその過程こそが、家庭酒の深い味わいを育てているのです。