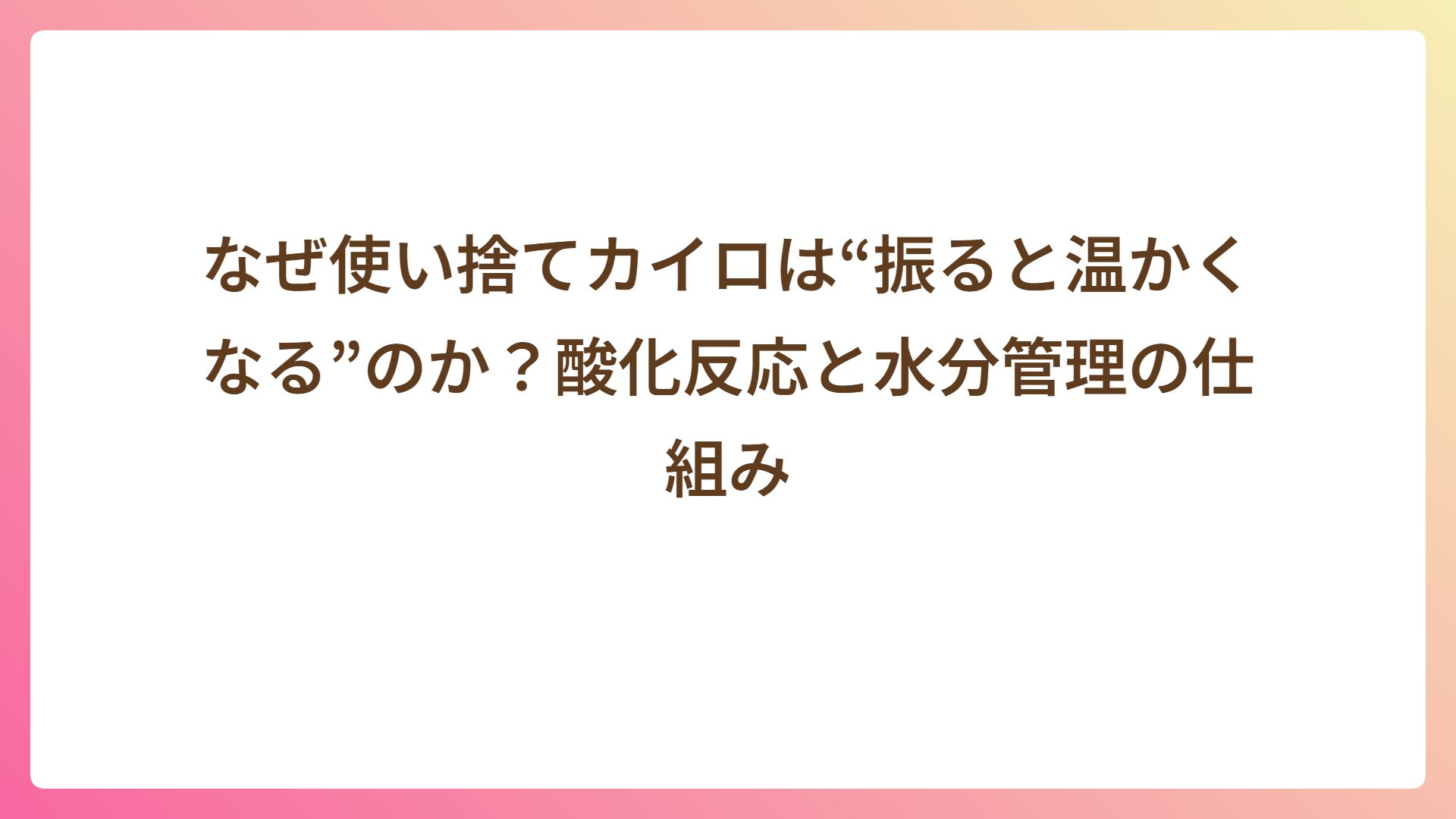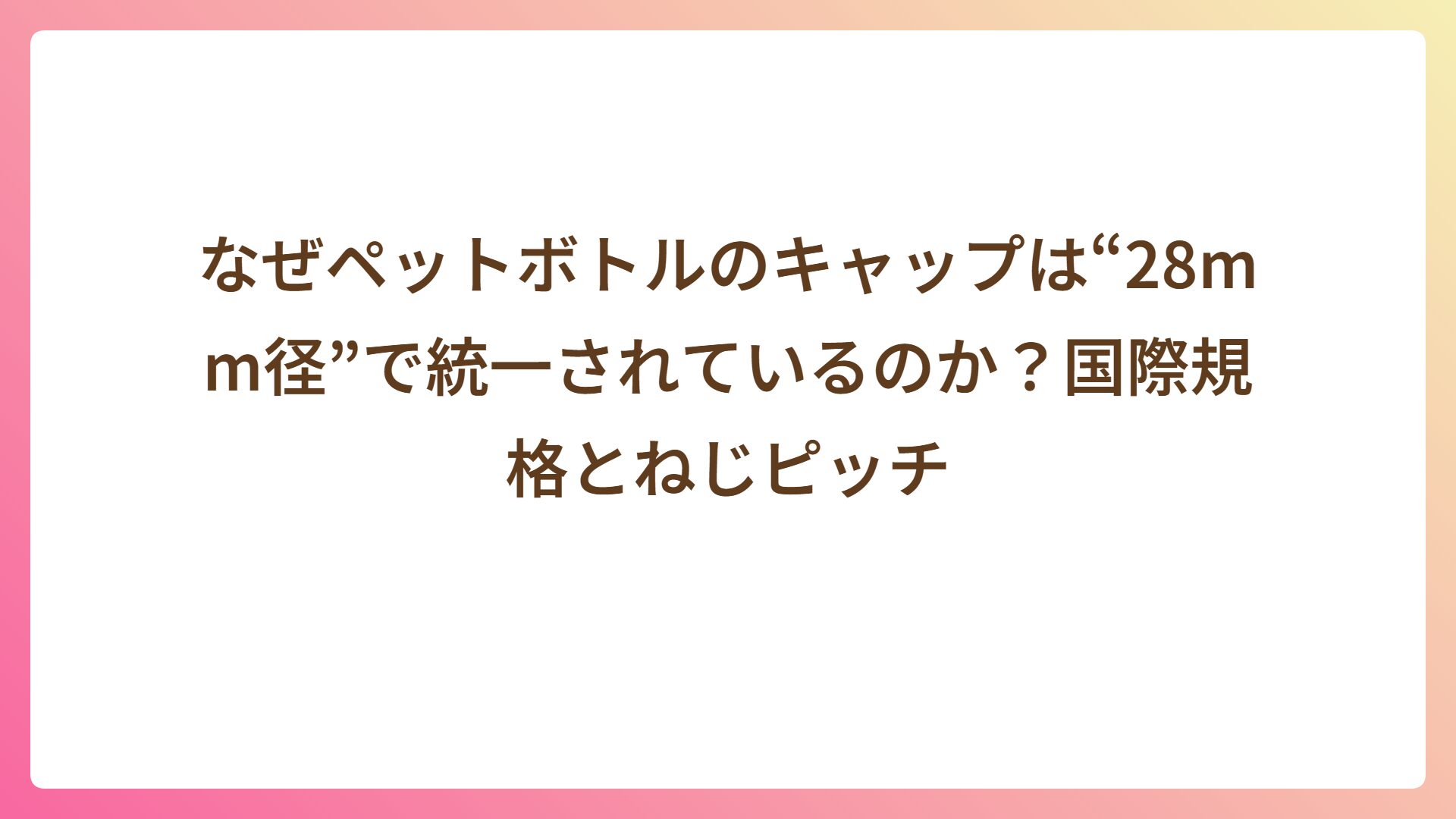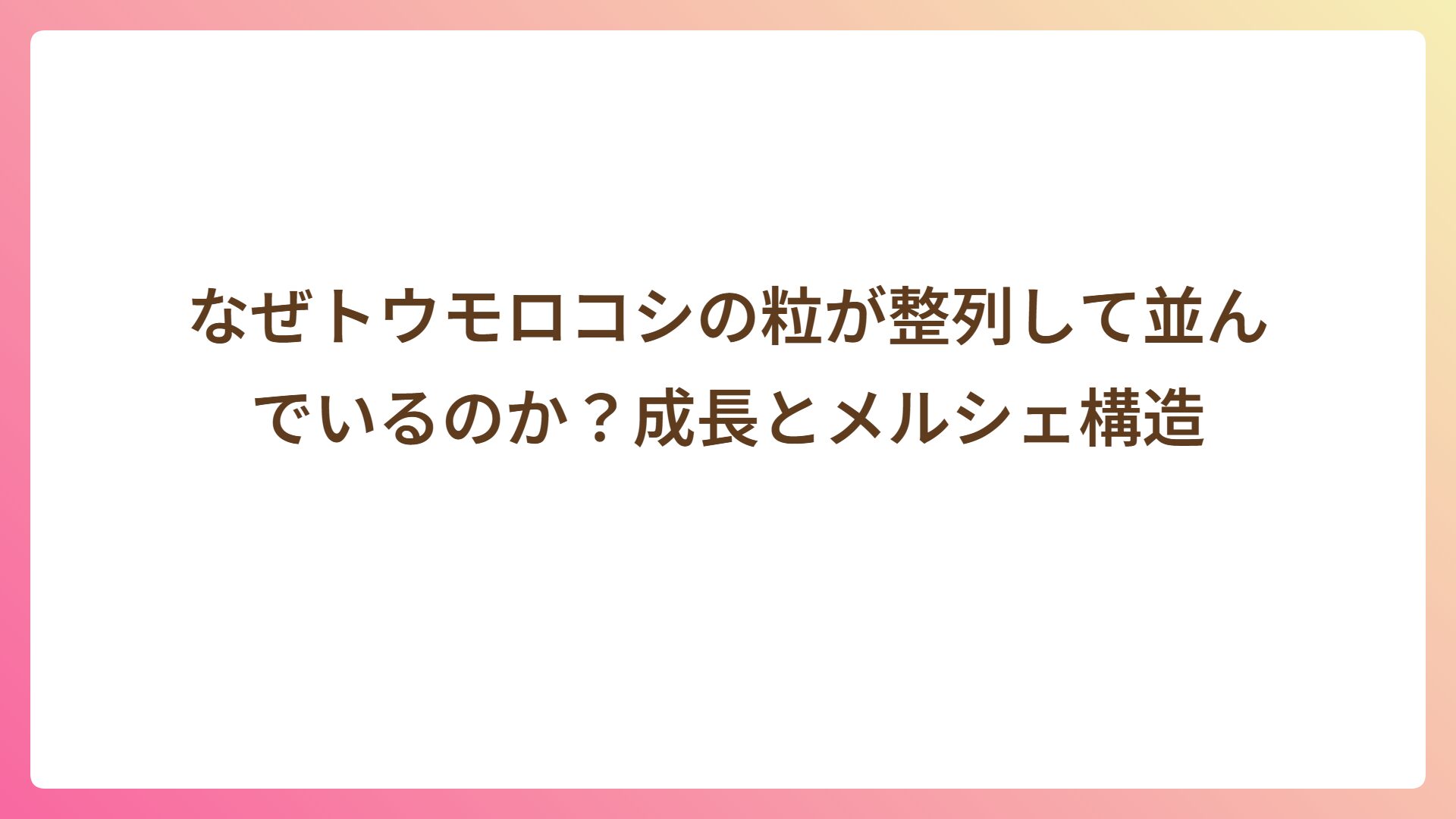なぜ座布団は“五枚重ね”が礼装とされたのか?落語と格式
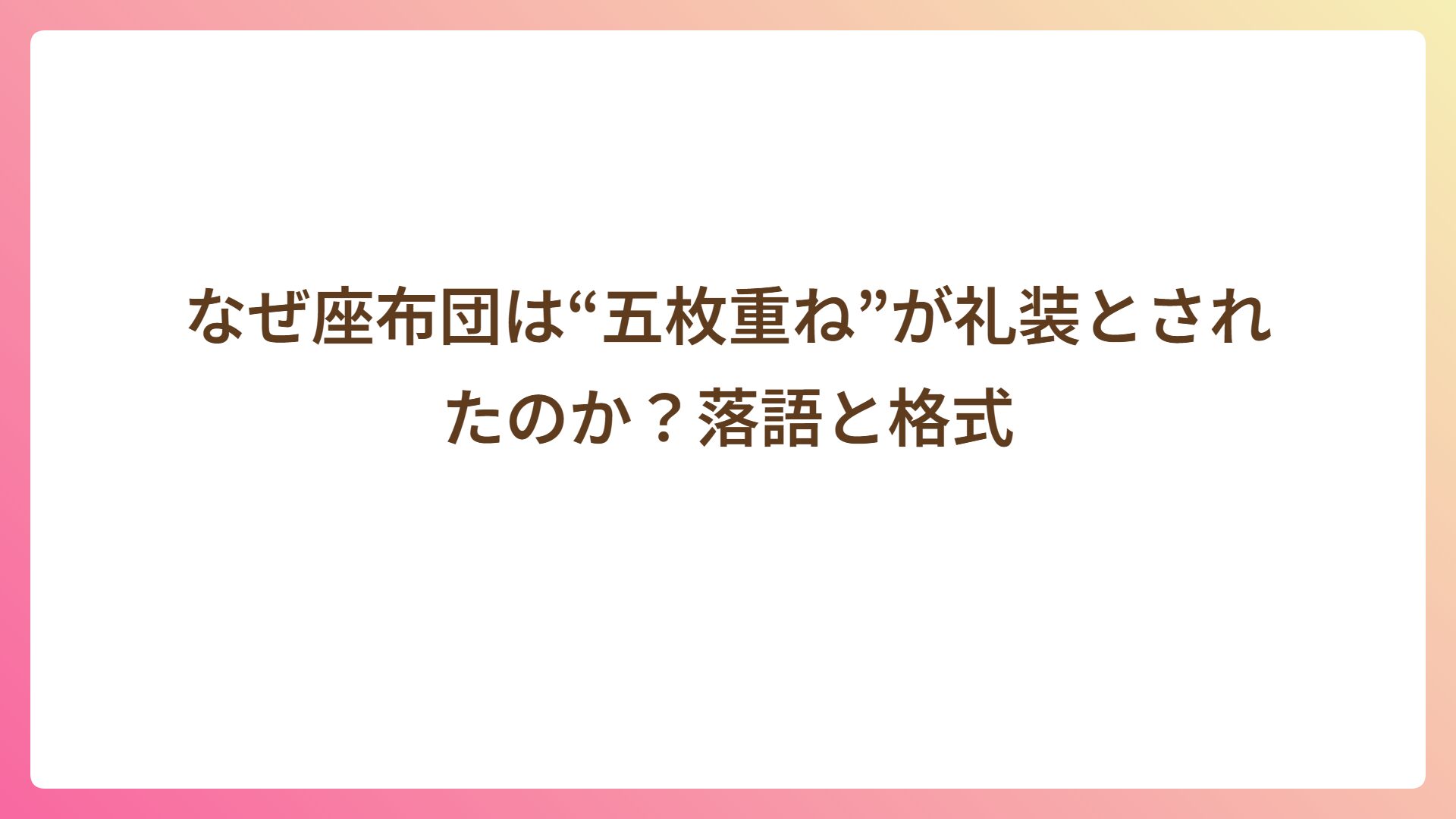
落語の高座や格式ある和室で、座布団が何枚も重ねられている光景を見たことがあるでしょう。
特に「五枚重ね」は“最上級の礼装”とされます。
ではなぜ、五枚という枚数が特別な意味を持つようになったのでしょうか。
座布団はもともと“身分を示す道具”だった
座布団が一般に使われるようになったのは江戸時代中期のこと。
それ以前の日本では、上座の人だけが畳の上に敷物を許される特権を持っていました。
最初は僧侶や貴族が使う「茵(しとね)」と呼ばれる座具で、
権威や位を象徴する“座の印”でもあったのです。
つまり、座布団は単なるクッションではなく、
「座る人の格式」を目で示すための道具として発展してきました。
「五枚重ね」は最高礼装の象徴
座布団を重ねる枚数は、時代とともに「敬意の段階」を表すようになります。
客人や上位者に対して座布団を重ねることは、
その人の格や敬意の度合いを視覚的に示す行為でした。
正式な礼法では、
- 一枚:日常・普段使い
- 三枚:儀礼的な場での丁寧な設え
- 五枚:最上位者をもてなす際の最高礼装
とされ、「五枚重ね」はまさに最上級の敬意の形を意味します。
公家や大名、宗教儀式の上座など、限られた人物のみが許された座でした。
落語の世界における「五枚の象徴」
この格式の名残を受け継いでいるのが、落語の高座です。
落語家が座布団を一枚だけ敷いて演じるのは、「たった一人で高い格式の場に挑む」という象徴でもあります。
一方、テレビ番組『笑点』では、座布団を加算・減算する形式が採用されています。
五枚重ねになると「名誉」や「満点」といった扱いを受けるのも、
もともと“五枚=最高の礼”という伝統的な意味合いを反映しているのです。
五という数字が持つ“安定と中心”
五枚という数には、単なる慣例以上の象徴的意味もあります。
古来、日本では「五」は中心や調和を示す数とされてきました。
五行(木・火・土・金・水)、五徳、五体、五感など、
すべてが「均衡の取れた完全な状態」を表します。
座布団五枚という重ね方は、
“礼の完成形”“敬意の頂点”を示す数としても選ばれたのです。
現代に残る「重ねの美学」
現在では、家庭で五枚も座布団を重ねる場面はほとんどありませんが、
冠婚葬祭や茶の湯の場では、「座布団を重ねる=敬意を積み重ねる」意味が今も生きています。
また、和室のしつらえにおいても、
座布団を丁寧に重ねて置くことは場を清め、客を迎える準備が整った合図とされます。
この“重ねる美意識”が、日本の礼法や空間文化の根底を支えているのです。
まとめ:座布団五枚は“敬意の頂点”
座布団の五枚重ねが礼装とされた背景には、次のような理由があります。
- 上位者をもてなすための格式ある座具だった
- 五枚は礼法上の最高位を示す
- 「五」は調和・完成を象徴する数
- 落語や儀式の世界でその象徴性が受け継がれた
つまり、座布団五枚は単なる数の問題ではなく、
「敬意を積み重ねる」という日本的礼法の象徴なのです。
落語家が一枚の座布団に込める覚悟も、
この伝統の延長線上にあるといえるでしょう。