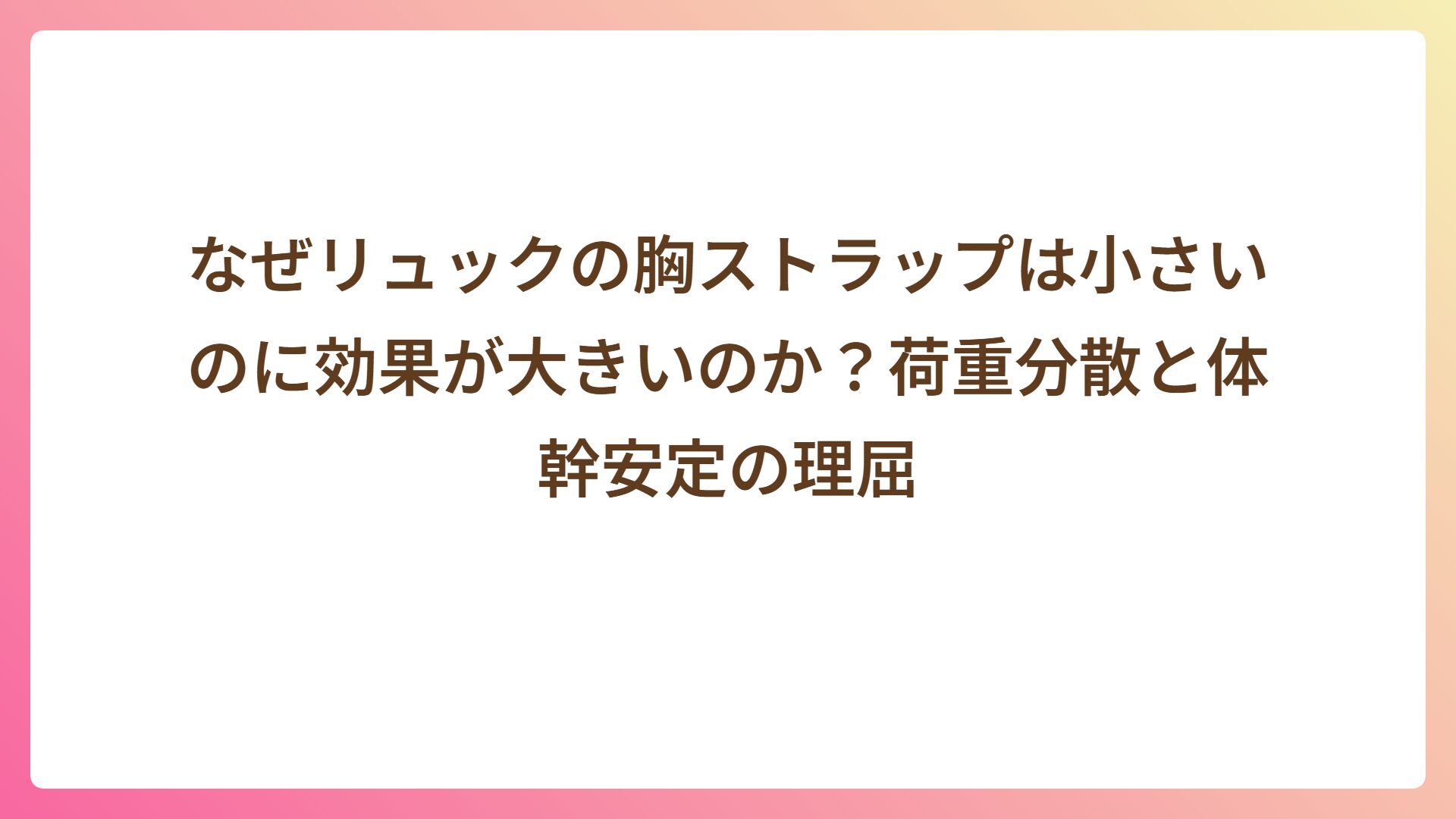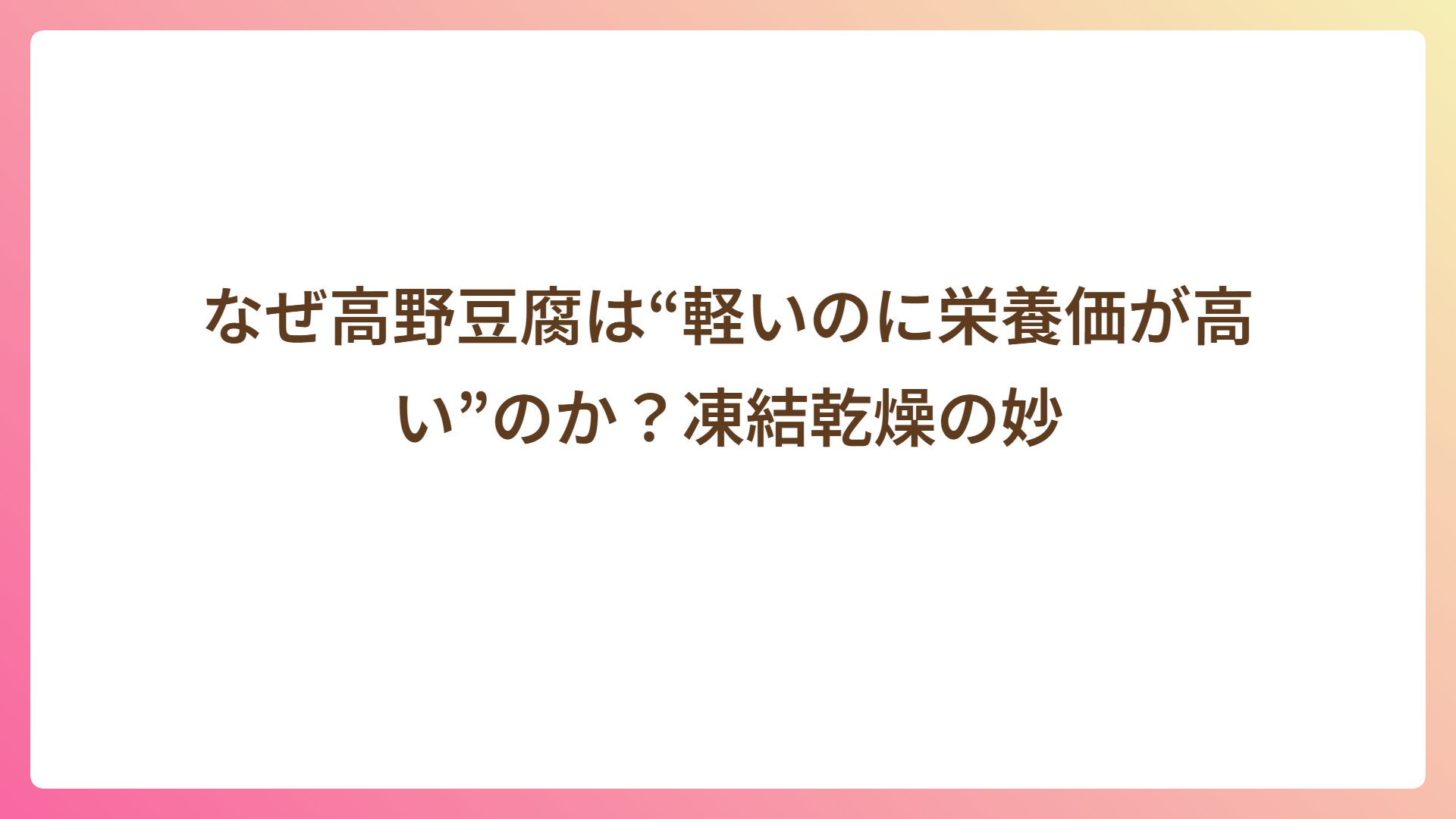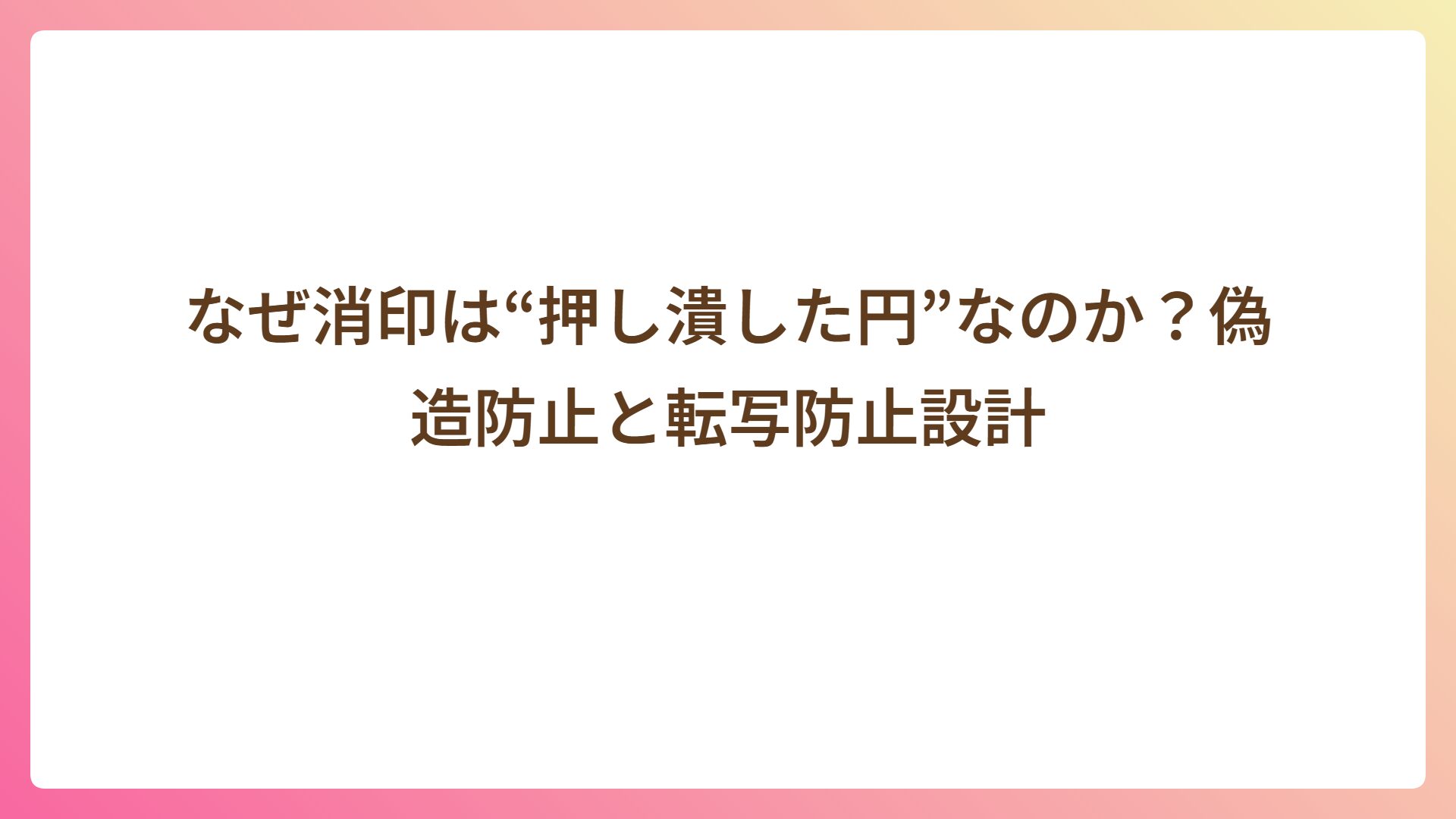なぜストローは“白と赤”のツートンが多いのか?識別性と製造コスト
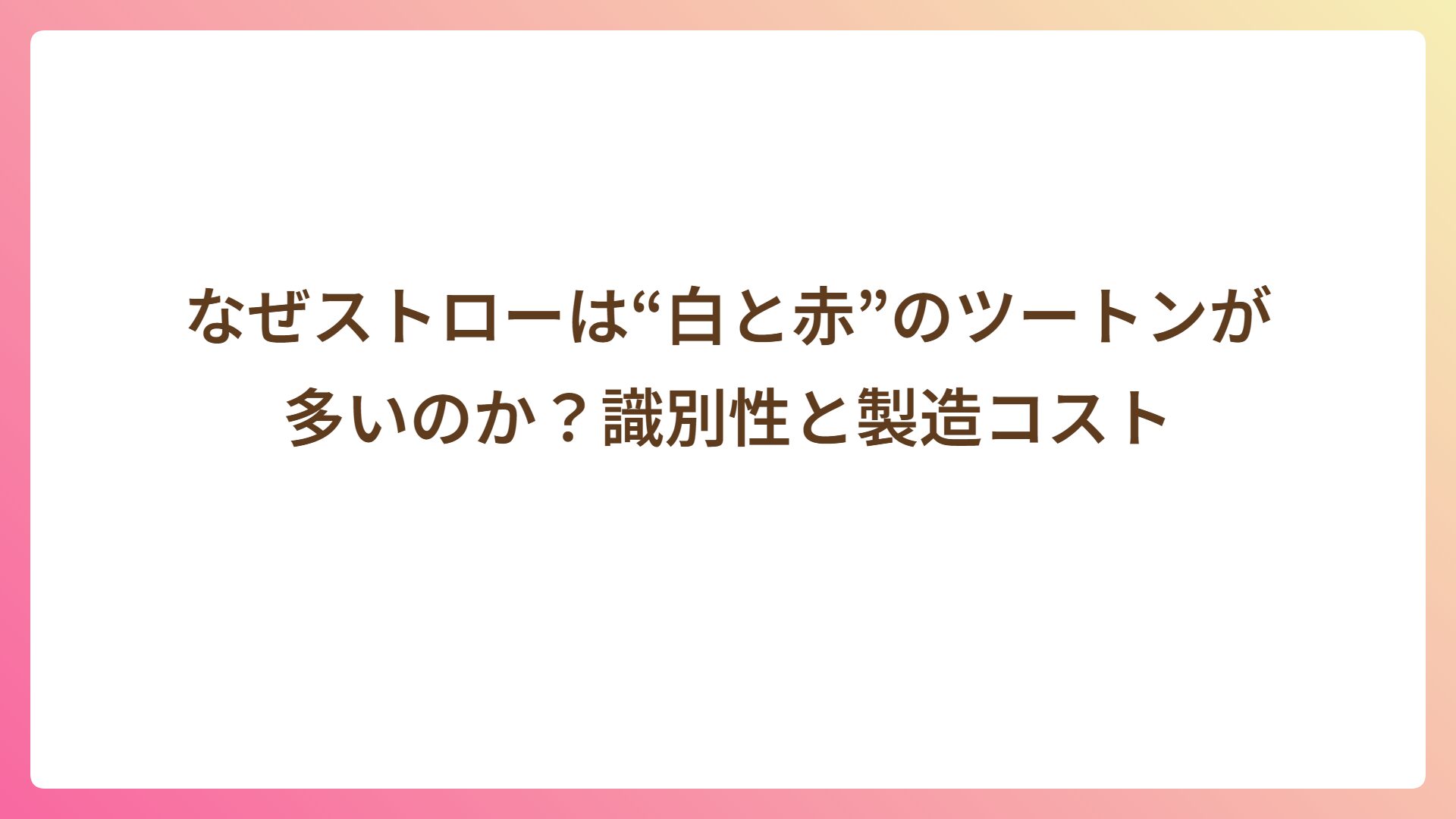
ファストフード店やコンビニのドリンクについてくるストロー。
よく見ると、白地に赤い縦線――このツートンデザインが圧倒的に多いことに気づきます。
なぜ単色ではなく、この配色が世界的に定番になったのでしょうか。
それは、見た目の清潔感と製造コストの合理性を両立した結果なのです。
元祖は“透明ストロー”から始まった
ストローの歴史をさかのぼると、19世紀の紙製ストローが原型。
その後、1950年代に登場したプラスチック製ストローが大量生産の時代を築きました。
当初は透明なストローが主流でしたが、
飲料の色が透けて見た目が不衛生に見えるという欠点がありました。
特に、使い捨て文化が定着し始めた頃は、
「清潔そうに見えること」が消費者の安心感を左右していた時代。
そこで、内部が見えにくく、汚れや液体の残りを隠せる白いストローが主流となっていきました。
“赤ライン”は識別と清潔のサイン
白一色のストローは清潔ですが、単調すぎて識別性に欠けるという問題がありました。
複数人で同じドリンクを頼んだとき、誰のものかわからなくなる。
また、製造工程での検品でも、色味がないと汚れや変形を見つけづらい。
そこで導入されたのが、赤いラインを1〜2本入れるデザインです。
赤は明度・彩度ともに高く、白地に映える色として最適。
これにより、
- 誰のストローか見分けやすい
- 不良品の検知が容易になる
- 清潔感を損なわずに“安心感”を与える
といった視覚的なメリットが得られるようになりました。
“赤と白”は最も安価で安定した配色
ではなぜ、青や緑ではなく「赤」が主流になったのでしょうか。
その理由は、製造コストと材料の安定性にあります。
ストローの色づけには、プラスチック用の着色マスターバッチ(顔料粒子)が使われます。
赤系の顔料は少量でも発色が良く、少ないインク量で視認性が高いため経済的。
さらに、食品衛生基準に適合する顔料の中では、
赤と白が最も入手しやすく、かつ色ブレが起こりにくいという利点もありました。
つまり、赤いラインは「安全・安定・低コスト」の三拍子が揃った実用最適色だったのです。
ストライプの“量産ライン”にも都合がよかった
ストローは、押し出し成形機でプラスチックチューブを延ばしながら作ります。
このとき、着色樹脂を細い糸状に流し込みながら成形すると、
自動的に縦ストライプ模様をつけることができます。
つまり、赤いラインは装飾ではなく、
生産ライン上で自然に付けられる構造的なデザインだったのです。
新たな印刷工程を増やさずに済むため、
加工コストをかけずに“デザインされた製品”として成立しました。
視認性+心理効果で“飲み物が美味しく見える”
赤は食欲を刺激する色としても知られています。
食品パッケージやロゴで赤が多用されるのと同じく、
ストローに赤を入れることで飲み物がより鮮やかでおいしそうに見える効果があります。
特に乳白色のストローに赤が加わると、
飲料とのコントラストが強調され、
「冷たくて新鮮」「清潔で爽やか」という印象を与えるのです。
現在は“環境対応素材”でも引き継がれるデザイン
紙ストローやPLA(生分解性プラスチック)など、
近年は環境配慮型素材への転換が進んでいます。
それでも、多くの製品が“赤と白”のストライプを踏襲しているのは、
この色がすでに「ストローらしさ」の象徴になっているからです。
つまり、素材が変わっても見た目の安心感と識別性を守るため、
赤白ストライプの意匠は現代でも受け継がれているのです。
まとめ:赤白ストローは“機能と印象の最適解”
ストローが白と赤のツートンである理由を整理すると、次の通りです。
- 透明より衛生的に見える白地が好まれた
- 赤ラインで識別性と検品性を高めた
- 赤顔料が安価で発色が良く、量産に適していた
- 製造ラインで自然にストライプを付けられた
- 清潔・美味しそうという心理効果を持つ
つまり、赤白ストローは見た目の心地よさと工業効率が一致したデザインなのです。
一見単純な2色には、衛生・コスト・心理・生産性のすべてを最適化した
“無意識のプロダクトデザイン”の知恵が隠されているのです。