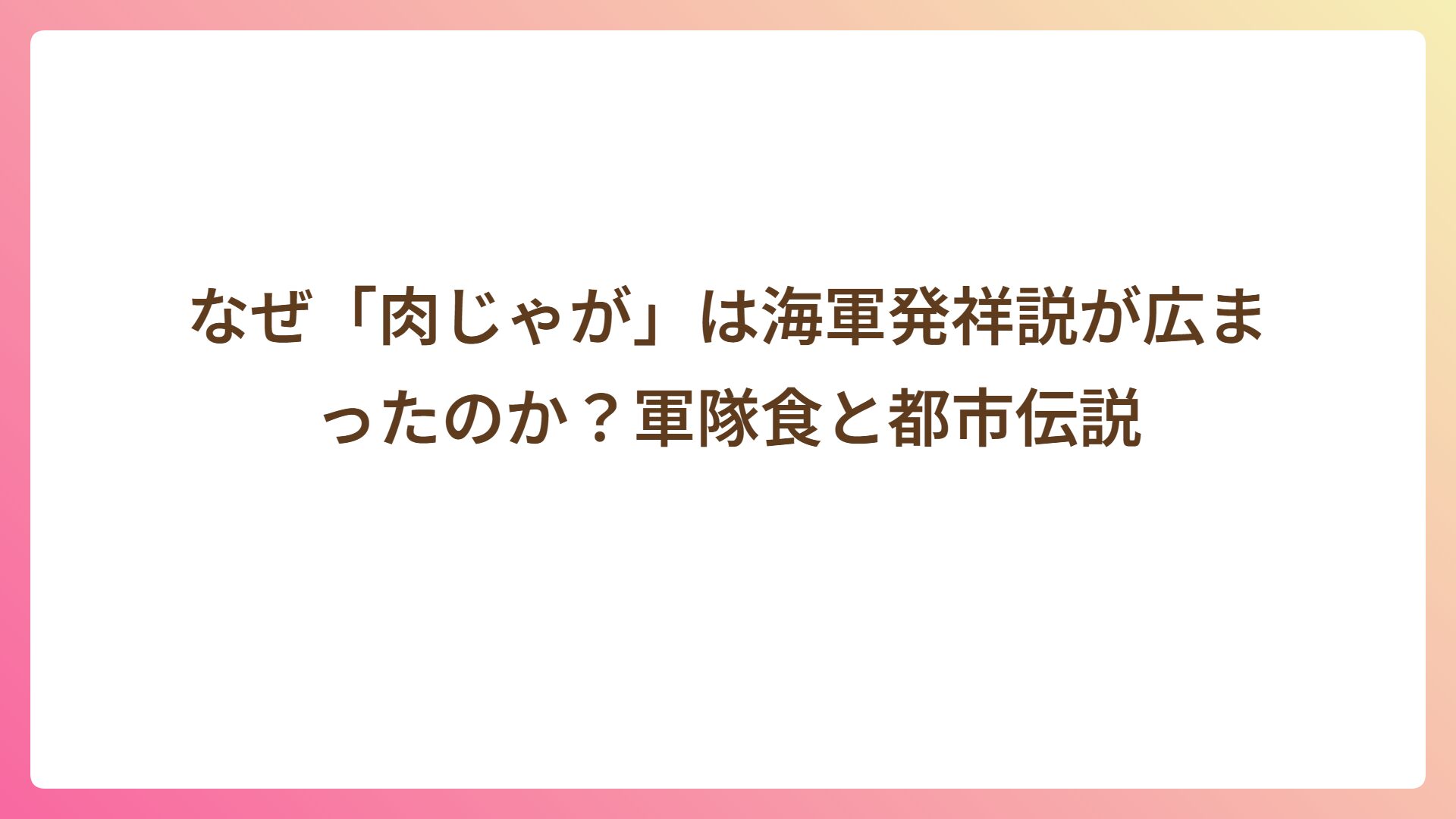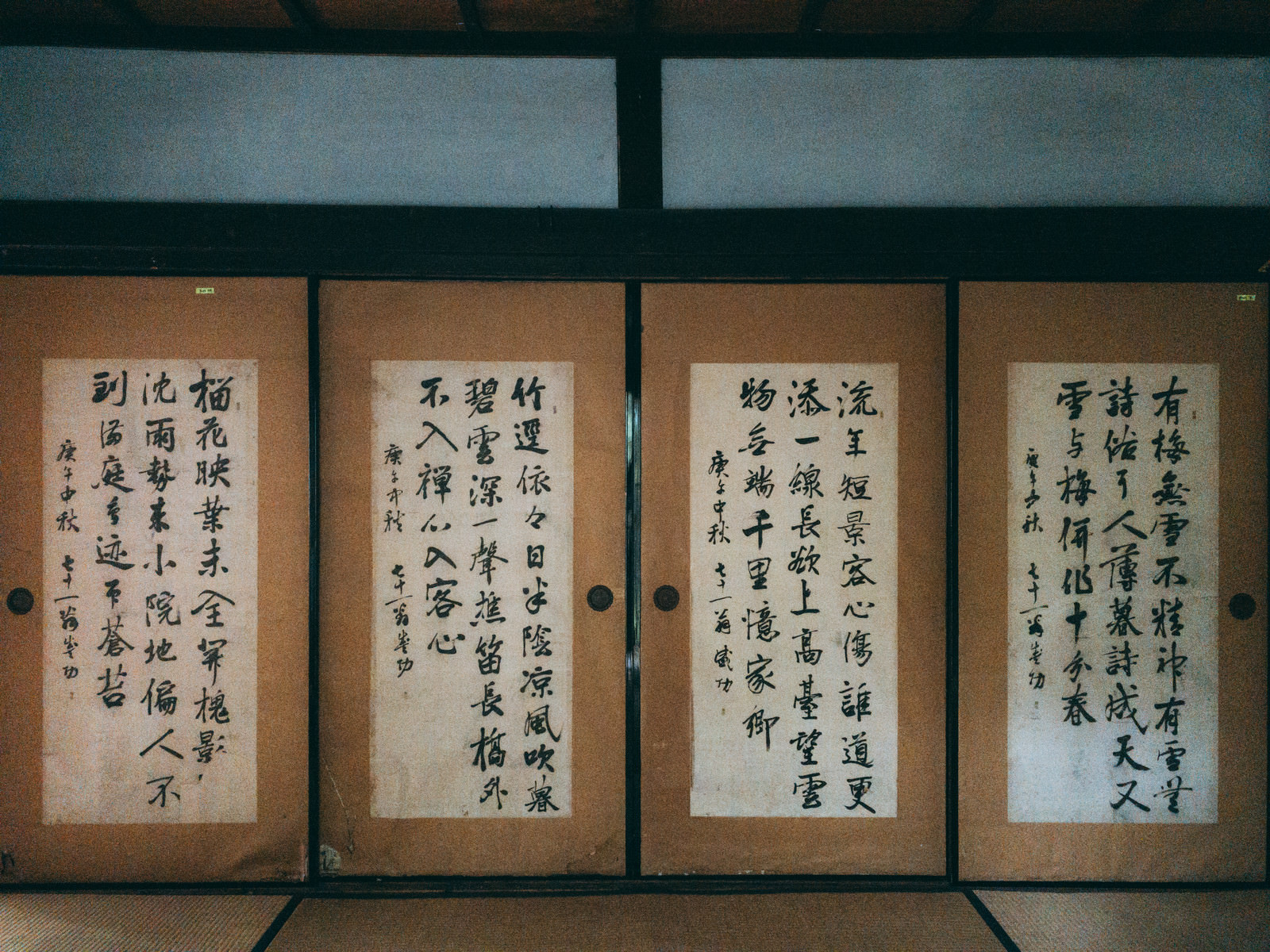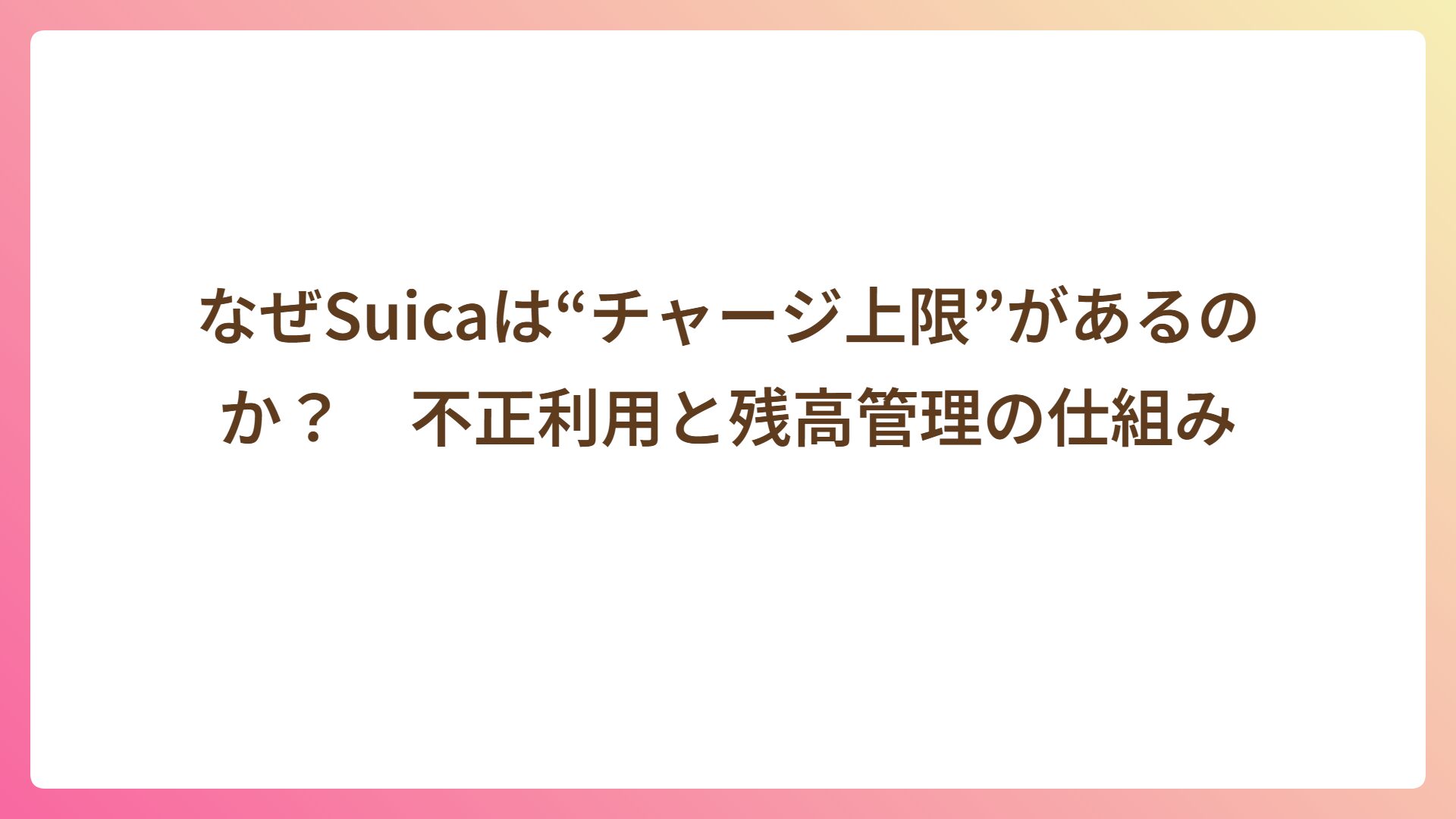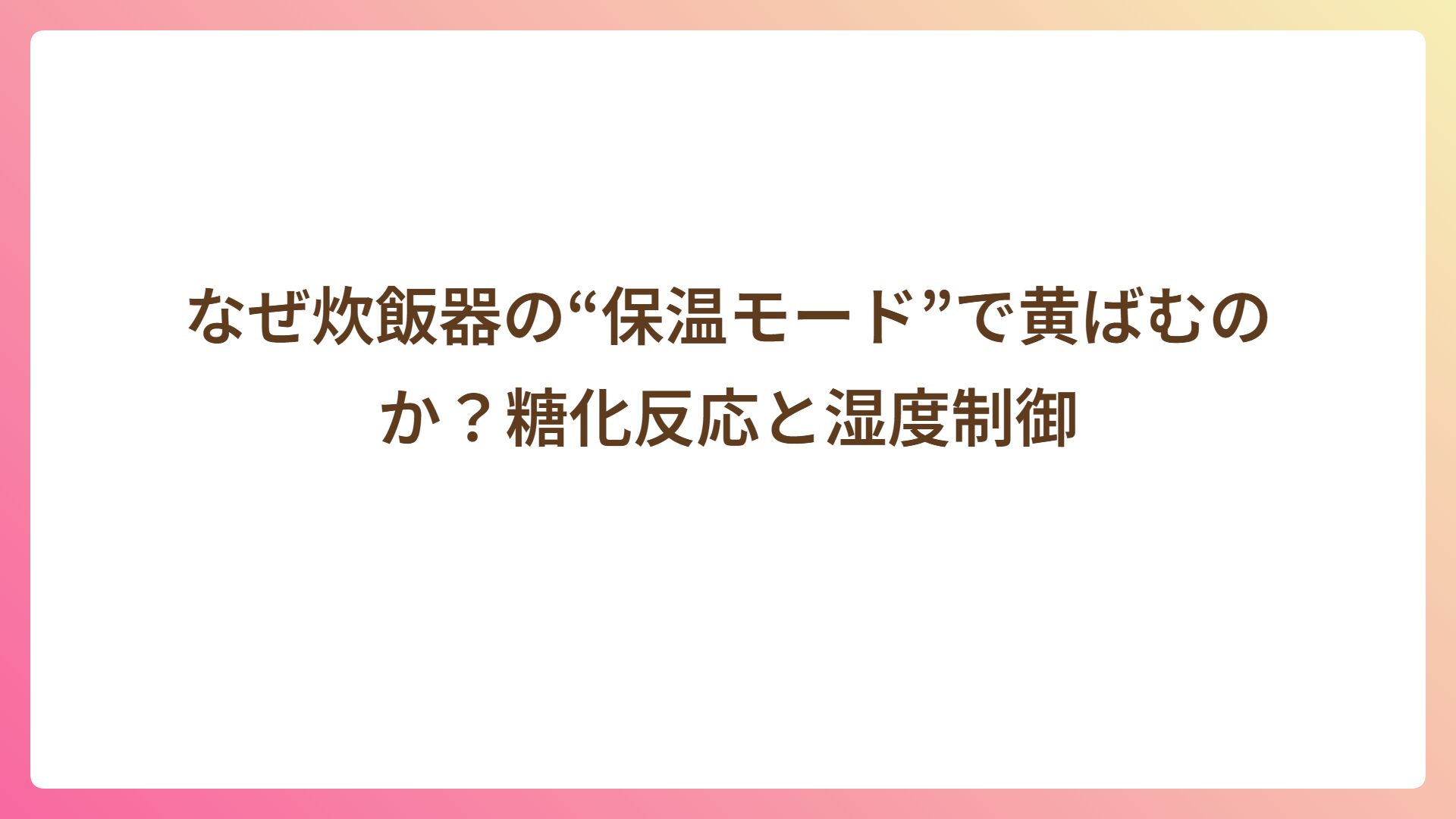紙のサイズにA判とB判がある理由とは?2種類に分かれた歴史を解説

ノートや書類、コピー用紙など、日常的に使う紙には「A判」と「B判」の2種類があります。
「そもそも紙のサイズなんて統一すればよくない?」と疑問に思ったことがある方も多いのではないでしょうか。
今回は、このA判とB判という2系統の紙サイズがなぜ存在するのか、その背景を解説します。
昔の日本の紙の規格
まずA判・B判が導入される以前、日本には多くの独自規格がありました。
- 四六判(しろくばん)
- 菊判(きくばん)
- 三五判(さんごばん)
- 新四六判
- 菊半截(きくはんせつ)
書籍には四六判、雑誌には菊判がよく使われていましたが、サイズが出版社によって微妙に異なるなど、統一感に欠けていたのが課題でした。
そのため、昭和初期に「紙の規格を統一しよう」という動きが強まりました。
A判の採用はドイツ由来
紙のサイズを標準化するにあたり、日本は海外の規格に注目します。
当時のアメリカやイギリスでは「原紙のサイズだけ決めて、それを分割する」という方式を採用。一方ドイツでは「原紙と、それを半分ずつにしたすべてのサイズ」を規格化するという、より細かい方式を使っていました。
このドイツ式は、A0を原点とし、縦横比が常に√2(約1.414)になるよう設計されていて、どのサイズを半分にしても同じ形を保てるのが特徴です。
さらに、このA5サイズが当時の雑誌で使われていた「菊判」に近かったため、日本ではドイツ式のA判規格をそのまま採用しました。
B判は日本で生まれた独自規格
一方、A判では四六判(書籍サイズ)にうまく対応できなかったため、もうひとつの規格が必要になりました。
そこで、A判の縦横比はそのままに、面積を1.5倍に拡大した新しい規格を設け、それを分割していく方式を考案。
これにより、四六判に近いサイズ感の紙を作ることが可能になり、これが日本独自の「B判」として定着していったのです。
つまり、A判はドイツ由来、B判は日本生まれ、という明確なルーツがあるのです。
おわりに
紙のサイズがA判とB判の2種類に分かれている理由には、それぞれ歴史的な背景があります。
ただの面倒な仕様に見えても、その裏には合理的な理由と経緯があることがわかると、ちょっとした“面白さ”を感じられますよね。
今後、紙を選ぶときには「A判とB判、どっちが適してるかな?」と背景を意識してみるのも楽しいかもしれません。