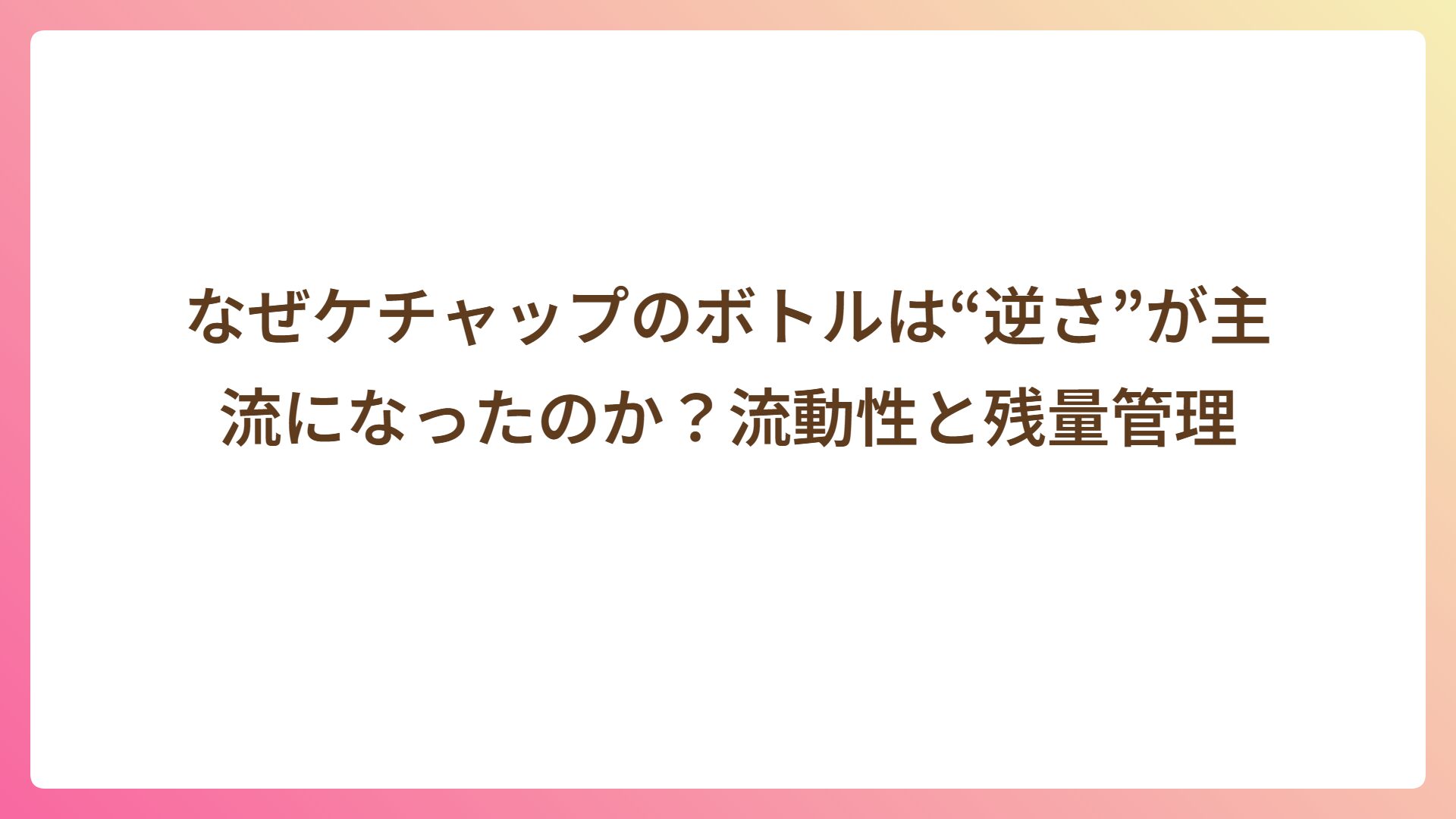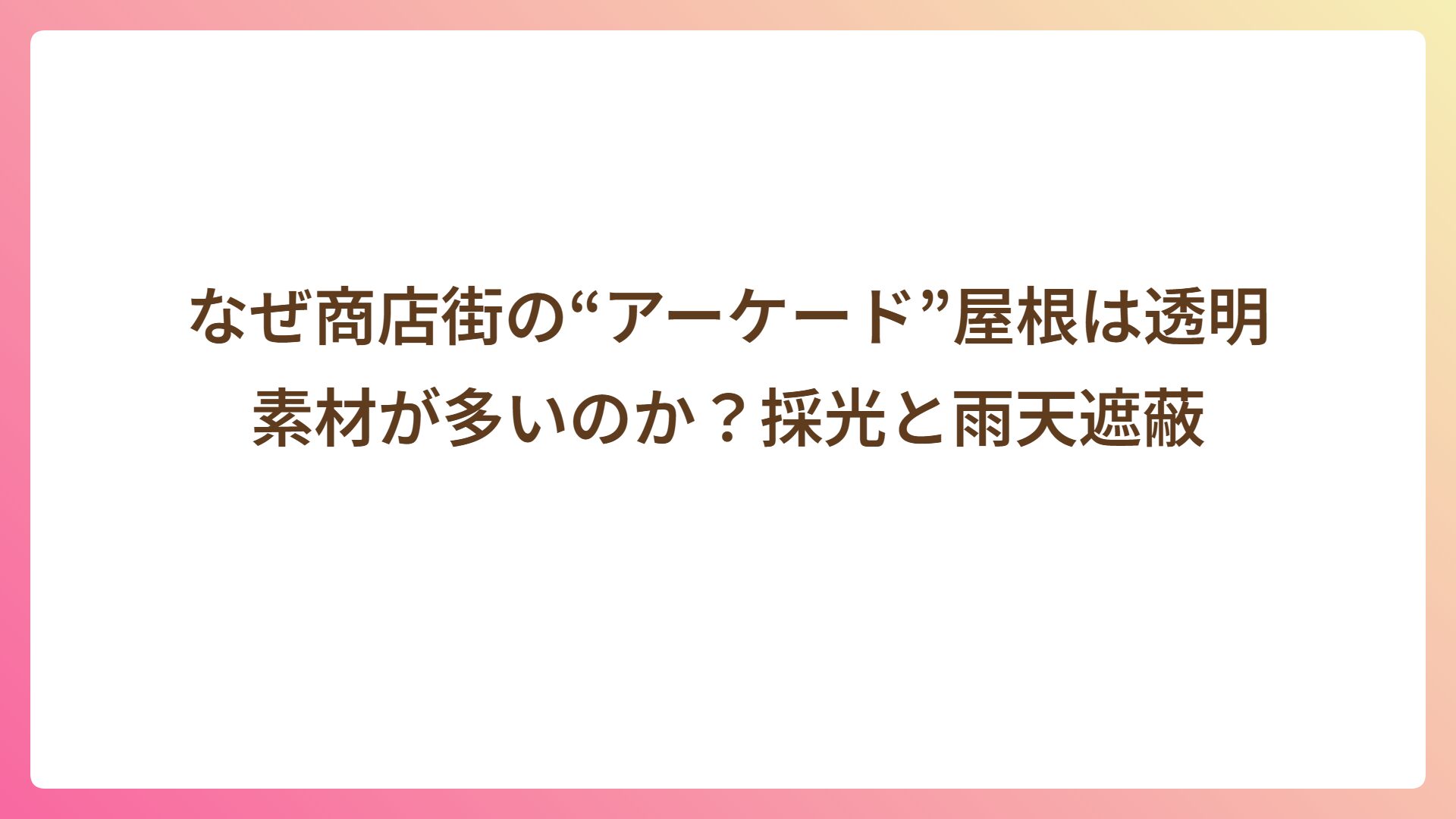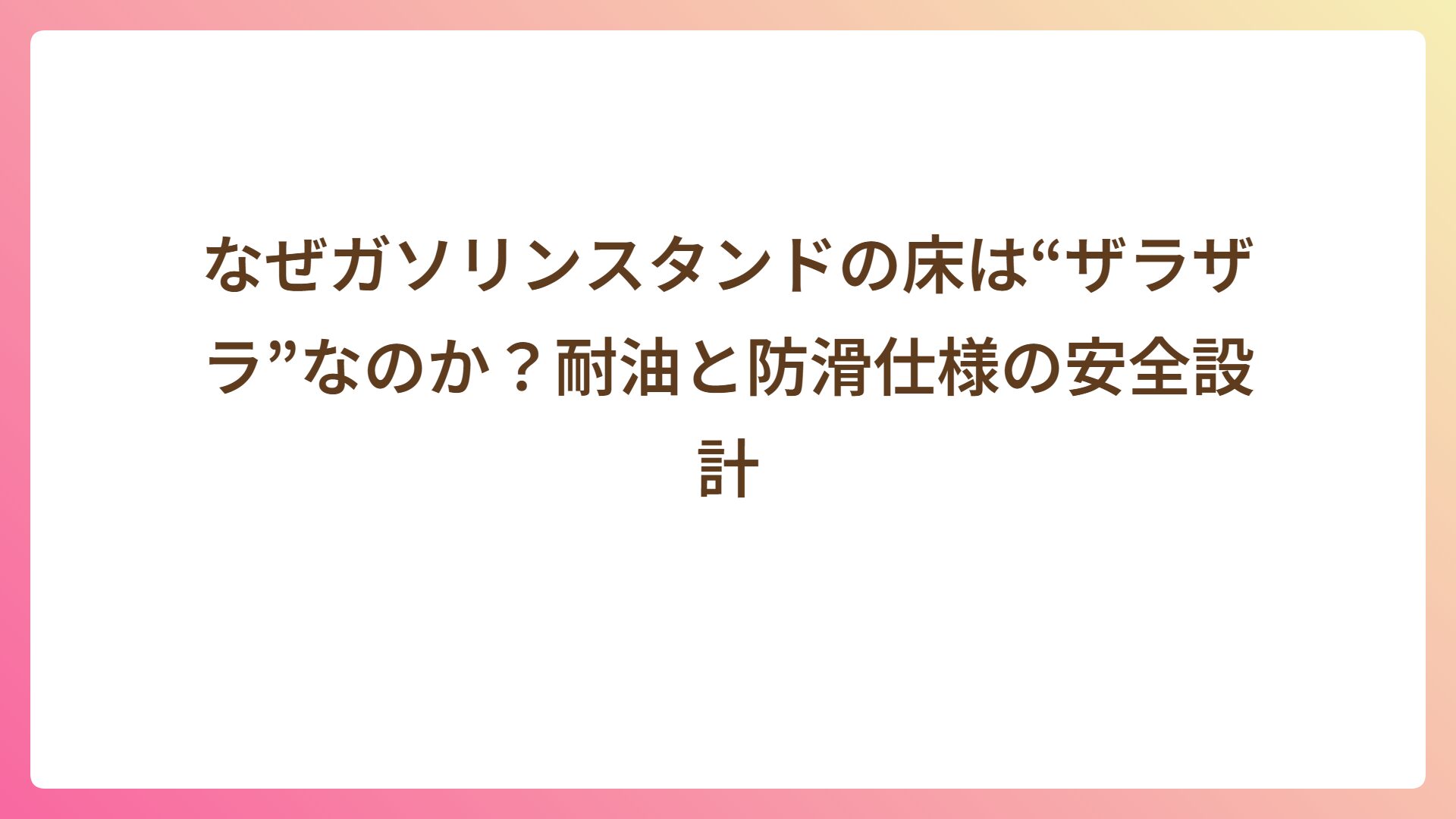なぜ人はあくびをするのか?眠気だけじゃない“脳冷却”の役割を解説

授業中、会議中、退屈なわけでもないのに――思わず出てしまう「あくび」。
誰にでも起こるこの生理現象、実はまだ完全には解明されていません。
しかし最近の研究では、「あくびには脳を冷却する働きがある」という説が注目されています。
この記事では、あくびの仕組みや脳冷却仮説、そして“うつるあくび”の心理的理由まで、科学的にわかりやすく解説します。
あくびとは? ― 体が自然に行う「調整動作」
あくびは、無意識に大きく口を開けて深呼吸する生理反応です。
その際、
- 大量の酸素を取り込み
- 二酸化炭素を排出し
- 顎や顔の筋肉を一気に動かす
という一連の動作が起こります。
かつては「脳に酸素を送るため」と説明されてきましたが、
現在ではそれだけでは説明がつかないとされ、体温や脳の働きの調整機能が注目されています。
「眠いときに出る」は半分正解
確かに、眠気や退屈時にあくびが出やすいのは事実です。
これは、眠くなると脳の覚醒レベルが下がり、温度が上昇するため。
あくびをすることで、血流や呼吸が活発になり、脳がリフレッシュされるのです。
つまり、眠気によるあくびは「眠気のサイン」ではなく、眠気に抗うための反応ともいえます。
有力説①:脳を冷やす「脳冷却仮説」
近年、最も有力とされているのが脳冷却仮説(brain cooling hypothesis)です。
これは、「あくびは脳を適温に保つための自然な冷却システム」だという考えです。
その仕組みはこうです👇
- あくびをすると大量の空気が口や鼻を通過
- 血流が増加し、顔や頭部の温度が下がる
- 冷えた血液が脳に送られ、脳の温度をリセット
実際、研究では「あくびの直前に脳の温度が上がり、直後に下がる」ことが確認されています。
つまり、あくびは“脳を冷却して集中力を回復させる行為”なのです。
有力説②:覚醒状態を保つための“再起動”
別の説として、あくびは脳を一時的に刺激し、覚醒レベルを上げるリセット動作だという見方もあります。
眠気や退屈、酸素不足などで脳が低活動状態になると、あくびによって一時的に血流が増加し、脳が再活性化されます。
つまりあくびは、「眠くなったときの再起動ボタン」のような役割を果たしているのです。
「うつるあくび」は共感能力の証拠?
誰かがあくびをすると、自分までつられてしまう――これを伝染性あくびと呼びます。
これは人間だけでなく、チンパンジーやイヌなどの社会的動物にも見られる現象です。
心理学的には、伝染性あくびは共感能力(エンパシー)と関係しているとされます。
脳内の「ミラーニューロン」が他人の動作を無意識に模倣することで、あくびが“感染”するのです。
つまり、あくびがうつるのは、相手に共感している証拠でもあります。
あくびは人間だけの現象ではない
実は、あくびは人間だけでなく、200種類以上の動物にも見られます。
たとえば――
- 鳥類:眠る前にあくびのような口の開閉を行う
- サル:社会的緊張をほぐすサインとしてあくびを使う
- イヌやネコ:ストレスを感じたときに「あくび」で気持ちを落ち着かせる
このことから、あくびは「情動を整えるための普遍的な生理反応」とも考えられています。
まとめ:あくびは“脳と心のリセット動作”
あくびは退屈や眠気だけでなく、
- 脳の温度を下げる(脳冷却仮説)
- 集中力を回復させる
- 共感やストレス調整の役割を持つ
といった多面的な意味を持つ生理現象です。
つまり、あくびは「眠いから出る」のではなく、「脳を守るために出る」――人間の体がもつ自然の知恵なのです。