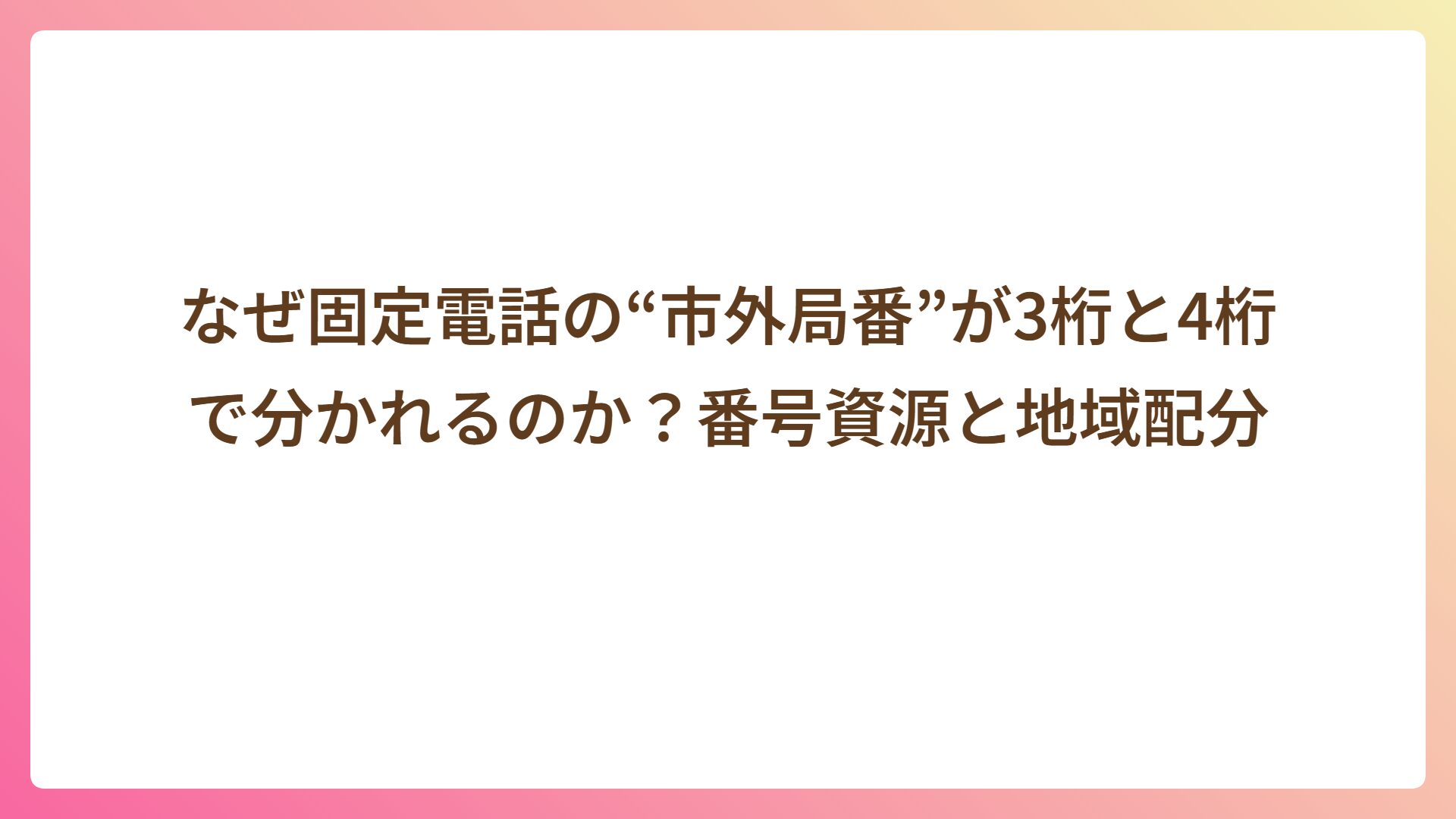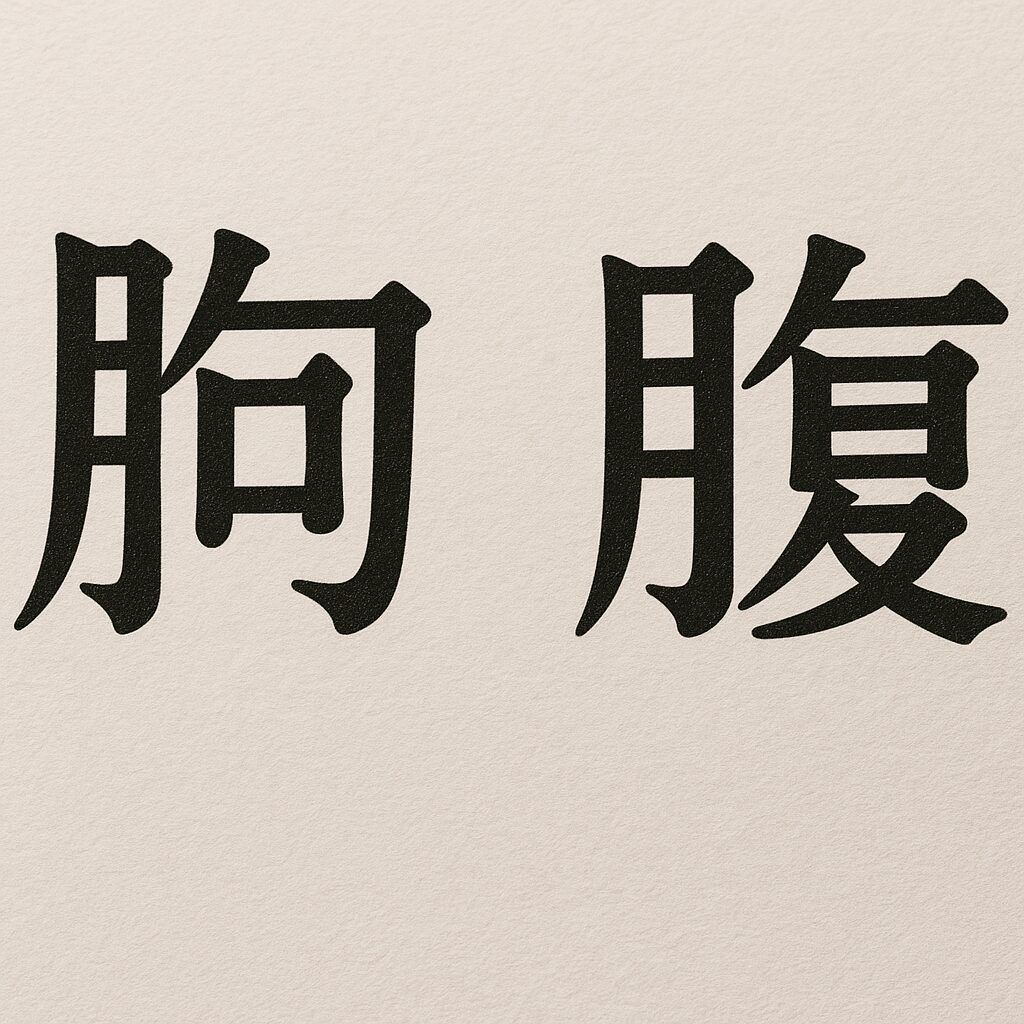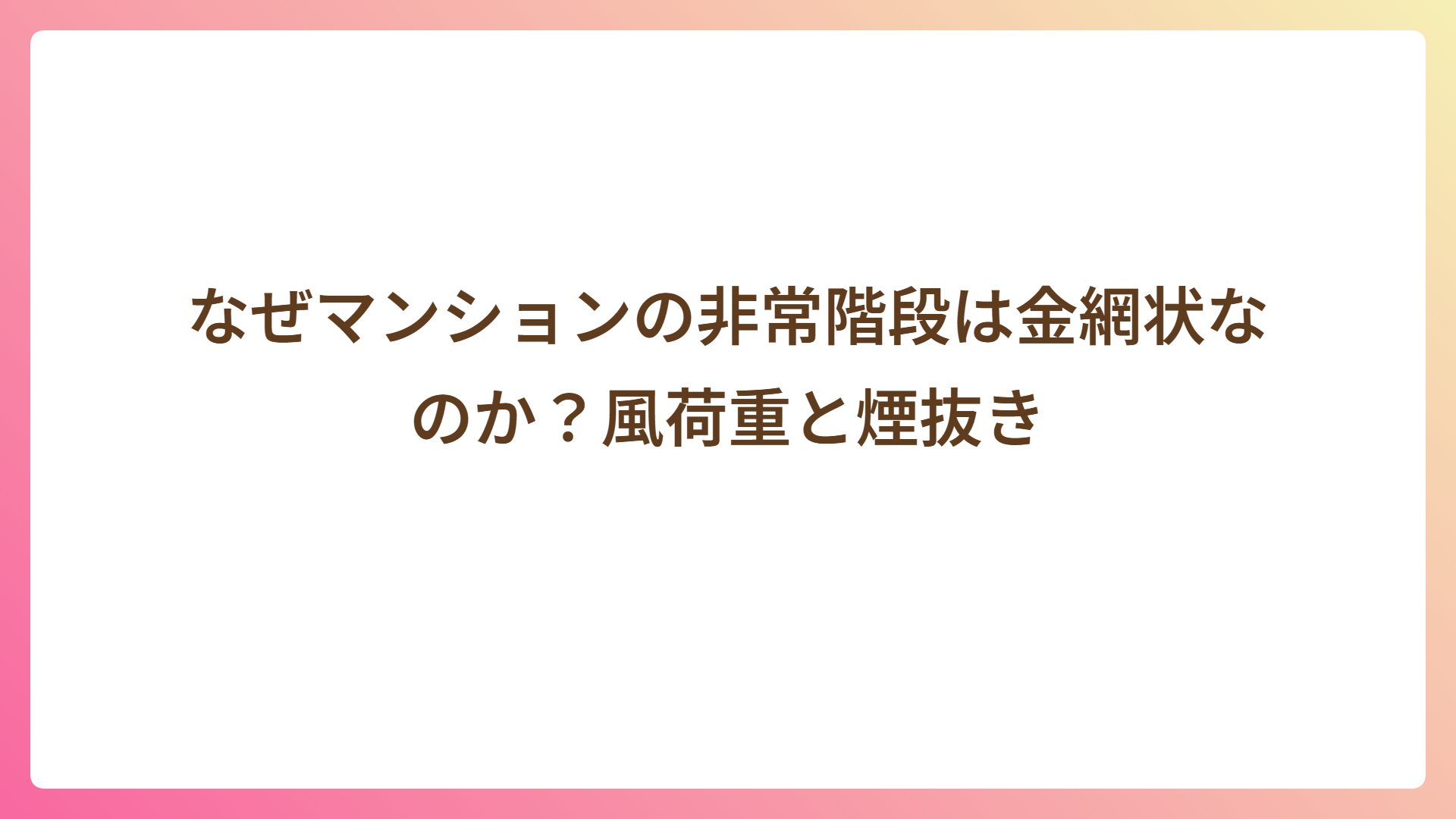なぜバナナは緑色の状態で輸入されるのか?追熟と鮮度保持の仕組み
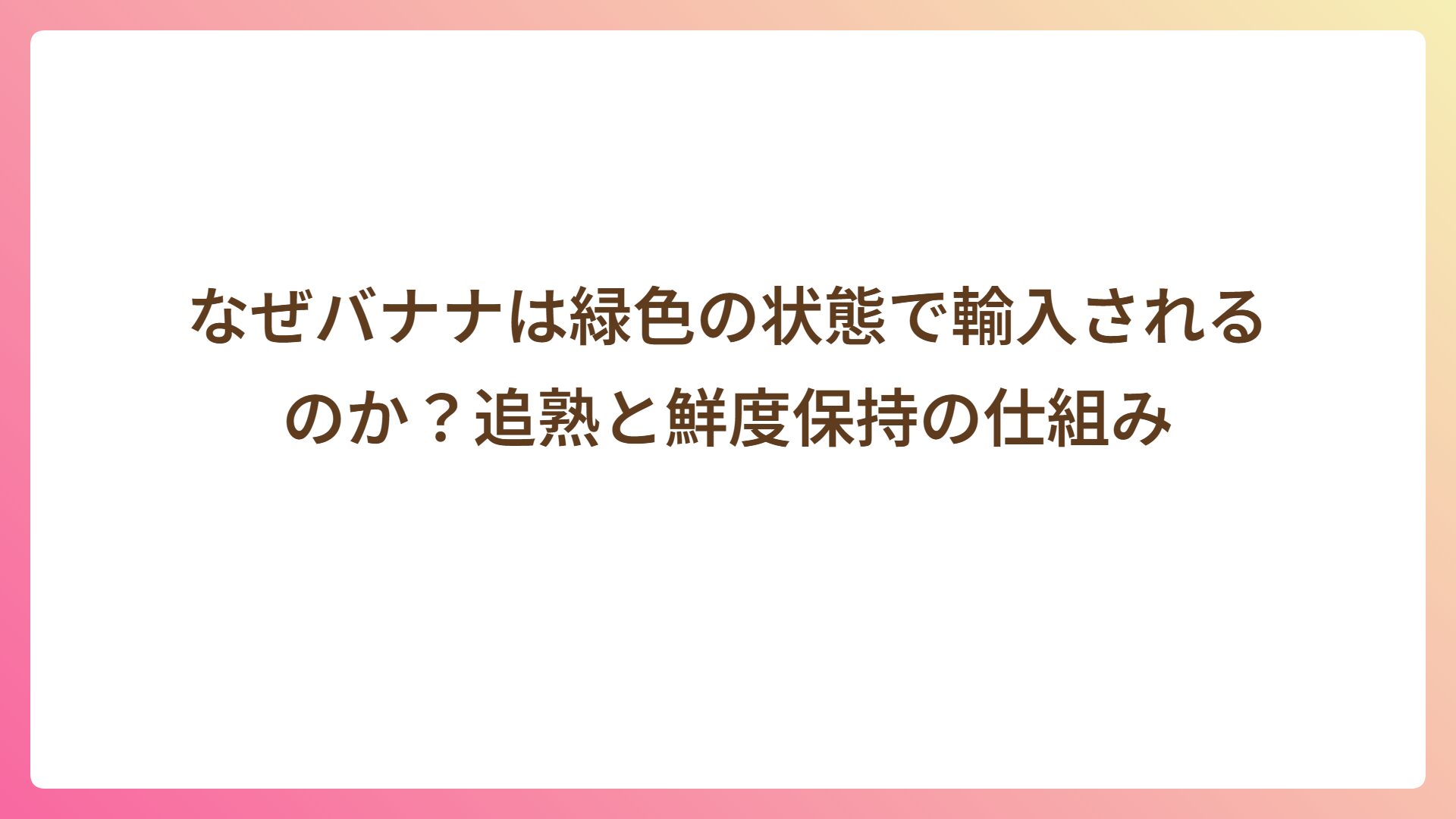
スーパーに並ぶバナナはきれいな黄色をしていますが、
実はその多くが日本に届く時点では緑色の未熟な状態です。
なぜ、完熟した黄色のバナナをそのまま輸入しないのでしょうか?
そこには、果実の生理と流通技術を両立させた「追熟」システムが関係しています。
バナナは“追熟型果実”だから
バナナは収穫後も呼吸を続ける追熟型果実です。
成熟を促す植物ホルモン「エチレン」を自ら放出し、
でんぷんを糖に変えて甘みを増していきます。
しかし、黄色く熟した状態では呼吸活動が急速に進み、
数日で黒く変色してしまいます。
そのため、生産地(主にフィリピンやエクアドルなど)では、
あえて緑色のうちに収穫・出荷するのが基本となっています。
低温輸送で“熟成を一時停止”
収穫された青いバナナは、すぐに13〜14℃程度の定温コンテナに積まれます。
この温度帯ではエチレンの働きがほぼ止まり、
呼吸速度も低下するため、熟成を一時的に凍結した状態になります。
輸送中に気温が上がってしまうと、
「船の中で黄色くなる(早熟)」現象が起きてしまうため、
温度管理は非常に厳密に行われています。
日本到着後に“人工追熟”を行う
港に到着した緑のバナナは、すぐに「追熟室」と呼ばれる専用施設へ。
ここで人工的にエチレンガスを吹き込み、
温度(約18〜20℃)と湿度を一定に保ちながら一斉に熟成を進めます。
この工程により、数日で均一な黄色になり、
スーパーに並ぶ頃にはちょうど食べ頃の状態になります。
つまり、黄色いバナナは「日本で熟したバナナ」なのです。
輸送ダメージと腐敗を防ぐため
完熟した黄色のバナナは果皮が柔らかく、
衝撃に弱いため輸送中の擦れや圧力で黒く傷むリスクがあります。
緑色の段階なら果肉が締まっており、
長距離輸送でも形を保ちやすい。
このため、品質を守るためにも未熟輸送が最適なのです。
追熟管理で“出荷タイミング”を自由に
青いまま輸入すれば、
日本側で「追熟を始める時期」を自由に調整できます。
需要や天候、出荷スケジュールに合わせて追熟をコントロールできるため、
販売計画と在庫管理の自由度が高いのです。
これは、果実を「生もの」ではなく「管理可能な製品」として扱うための
流通戦略上の工夫でもあります。
まとめ
バナナが緑色のまま輸入されるのは、
追熟を制御して鮮度と品質を保つためです。
低温で熟成を止め、日本で一斉に追熟させることで、
最もおいしい状態を狙って出荷できる。
私たちが毎日食べている黄色いバナナは、
実は輸送と科学のタイミング管理によって完成した果実なのです。