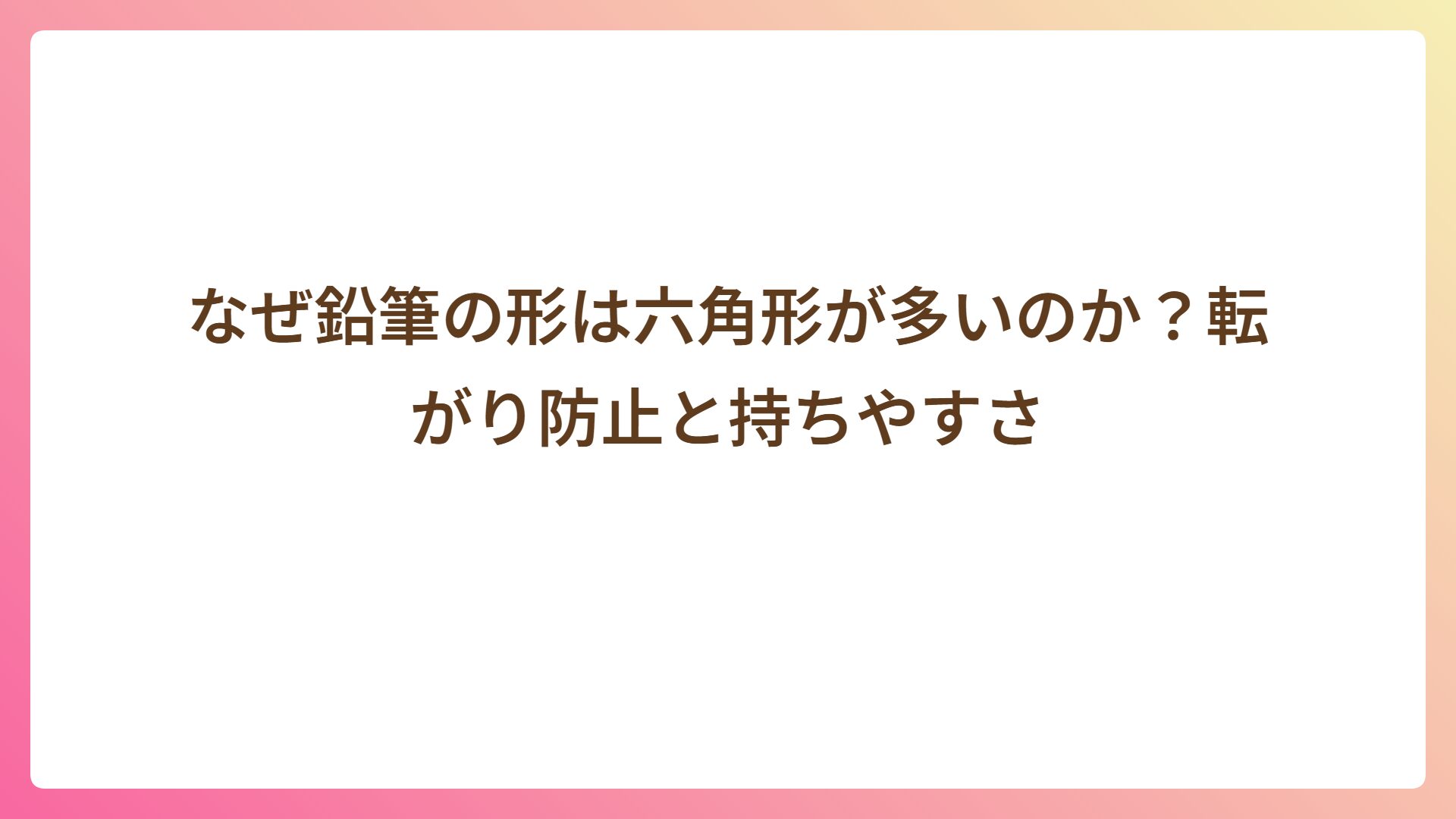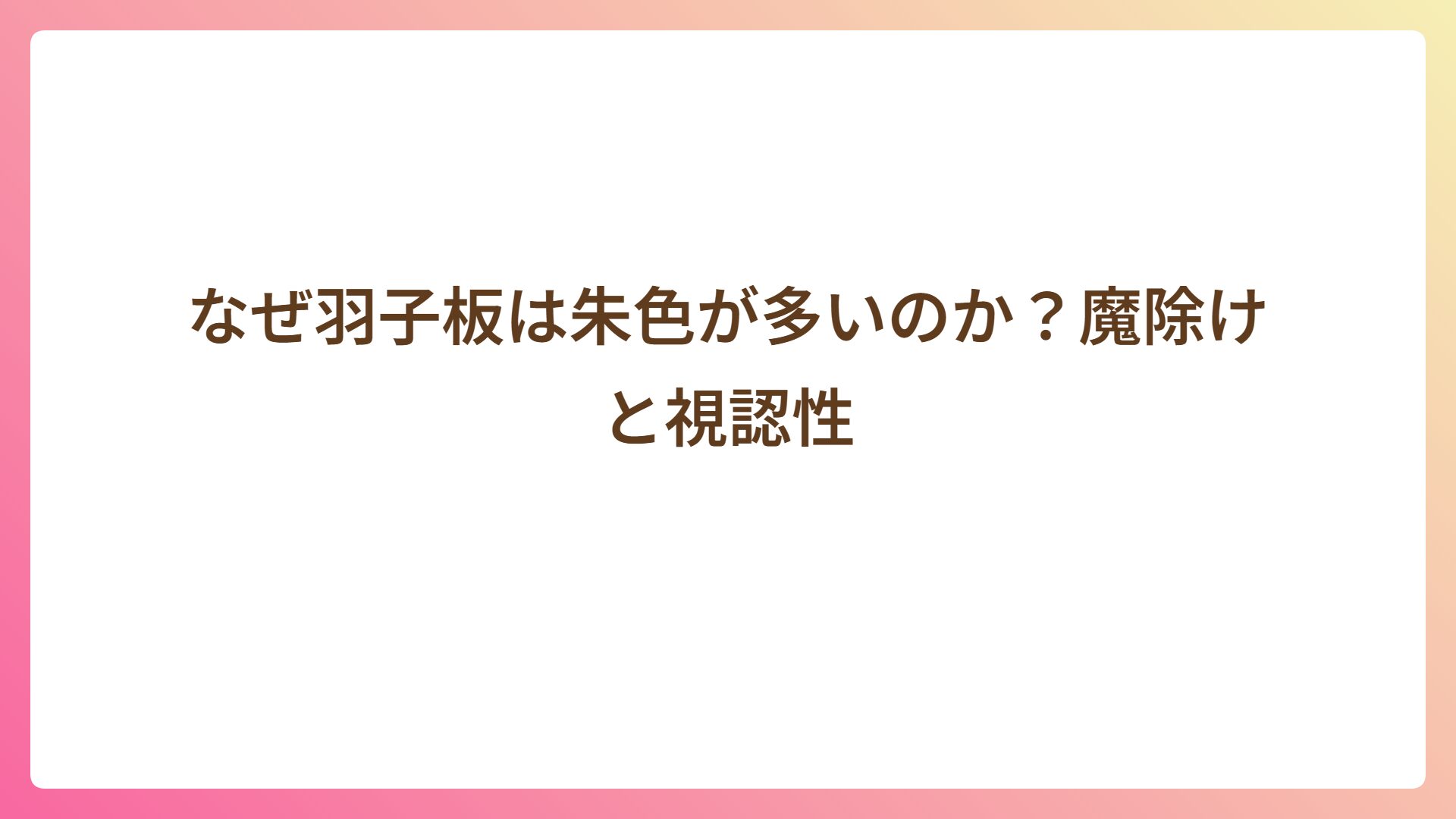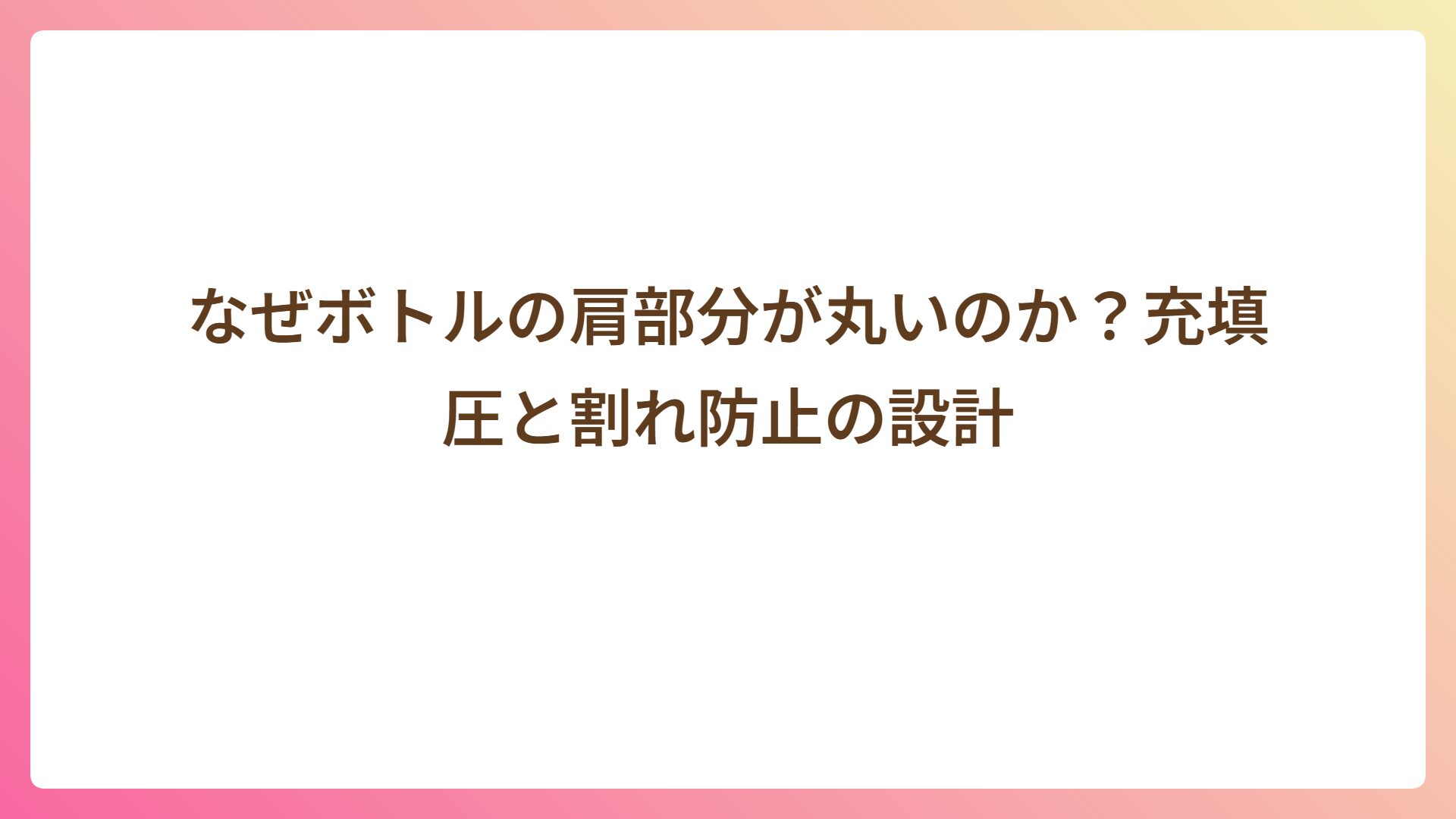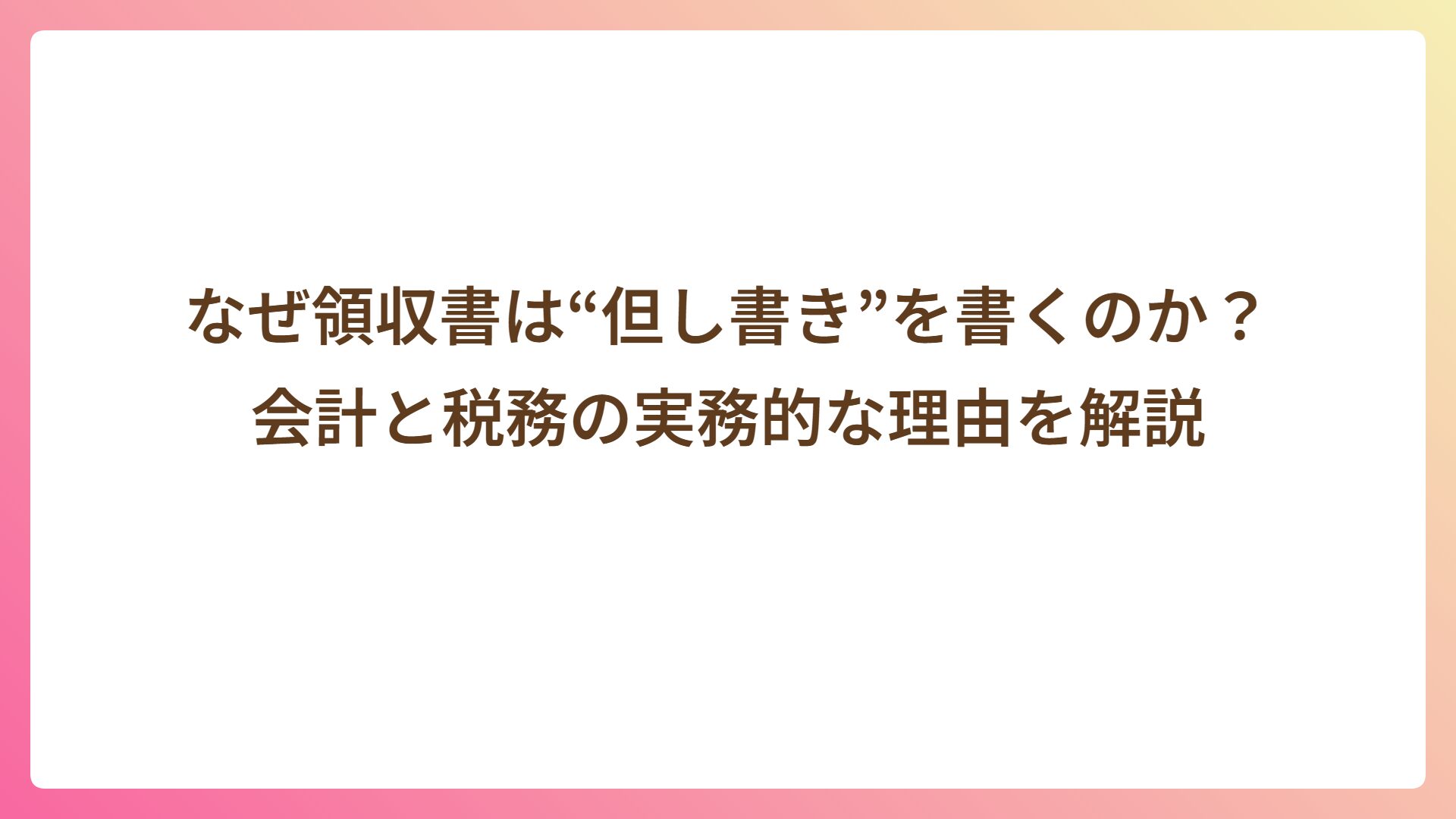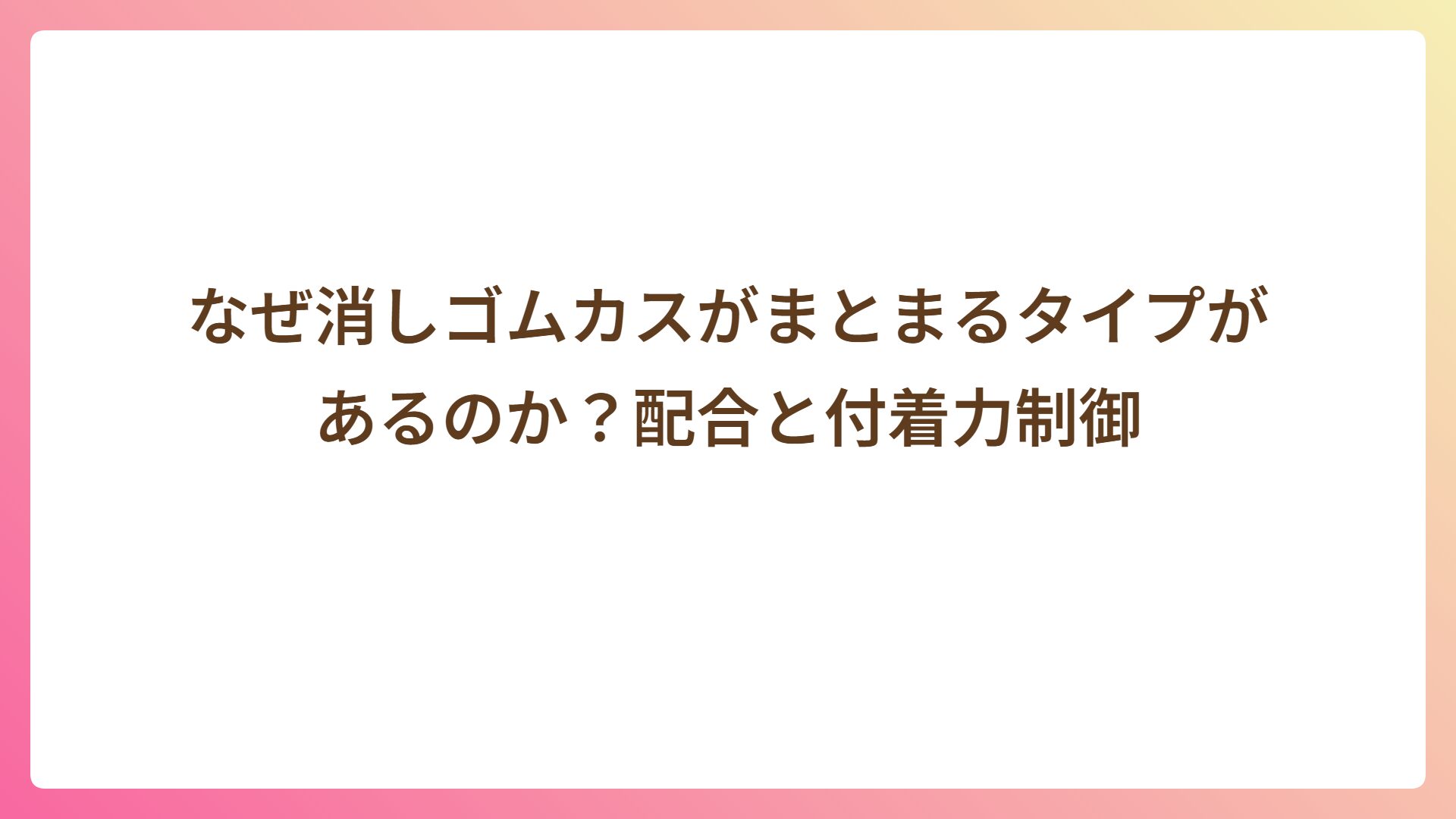なぜ美術館は“低色温度ライト”を使うのか?退色リスクと演色性
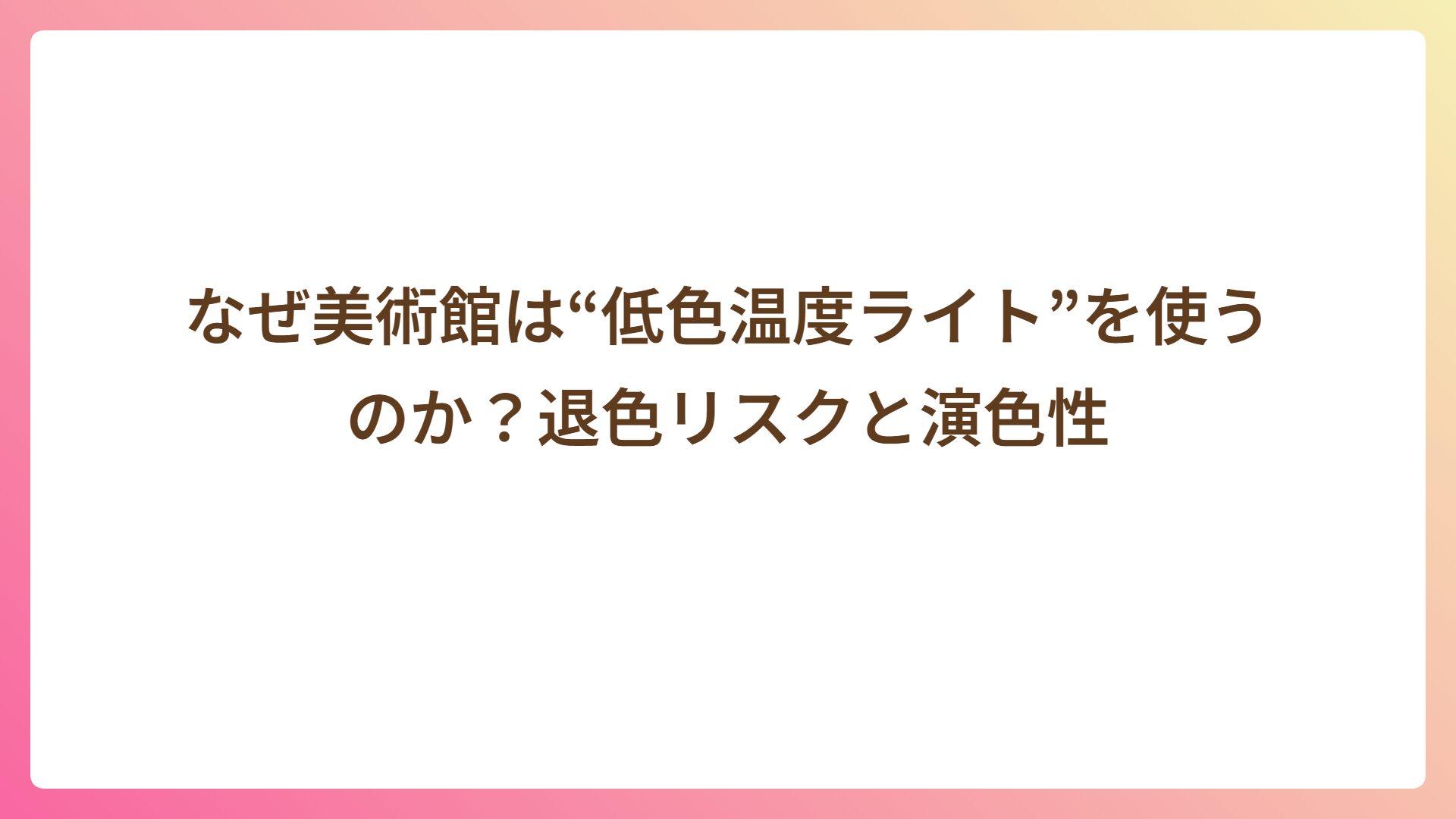
美術館の展示室は、家庭の照明よりも少し黄みを帯びた柔らかい光で照らされています。
なぜあえて白く明るい照明を避けているのでしょうか?
実は、美術館の照明は作品を守りながら本来の色を忠実に見せるために、綿密に計算された“低色温度ライト”で設計されているのです。
低色温度ライトとは?
照明の「色温度」とは、光の色味を数値で示したもの。
単位はケルビン(K)で表され、数値が高いほど青白く、低いほど黄みを帯びた光になります。
一般的なオフィス照明は約5000K(昼白色)ですが、美術館では2700〜3500K程度の低色温度ライトが主流です。
この暖かみのある光は、作品に落ち着いた雰囲気を与えつつ、紫外線・青色光を抑える効果を持っています。
青色光が“退色”を引き起こす
絵画や染織品などの展示物は、光によって化学的な劣化(フォトデグラデーション)を受けます。
特に波長の短い青色光や紫外線はエネルギーが強く、顔料・染料・紙の分子構造を破壊して退色を引き起こします。
そのため、美術館ではこれらの波長を含みにくい低色温度=赤寄りの光を選ぶことで、
作品への光ダメージを最小限に抑えているのです。
さらに、LED照明の中でも「美術館用」として設計されたタイプは、
青色LEDにフィルターをかけたり、独自のチップ構成で紫外線をほぼゼロに近づけるなどの工夫が施されています。
退色防止と“見た目の忠実さ”の両立
光を弱くすれば退色は防げますが、その分作品が暗く見えてしまいます。
美術館照明ではこのジレンマを解決するために、演色性(CRI:Color Rendering Index)という指標が重視されます。
演色性とは、光源が物の色をどれだけ自然に再現できるかを表す値で、
美術館ではCRI 95以上という非常に高い基準が求められます。
低色温度ライトは青成分を減らしつつも、赤・緑・黄などの色域をバランスよく再現できるように調整されており、
観覧者が「本来の色味」として自然に感じられるよう設計されています。
照明角度と反射のコントロール
低色温度ライトは、光の当て方にも工夫があります。
直接光ではなく、壁や天井に反射させた間接照明を用いることで、
光量を均一にし、絵具の艶やキャンバスの凹凸に生じる反射を抑えています。
これにより、観覧者がどの角度から見ても色の深みや質感が安定して見えるのです。
展示物ごとに異なる照度管理
美術館では、作品の素材ごとに「照度(ルクス)」も厳密に管理されています。
たとえば、
・油絵:150〜200ルクス程度
・水彩・紙作品:50ルクス以下
・古文書・染織品:30ルクス以下
といったように、素材の光耐性に応じて細かく制御されます。
低色温度ライトは、この低照度環境でも色が沈まずに見えるという特性を持つため、
展示照明として非常に適しているのです。
まとめ
美術館で低色温度ライトが使われるのは、退色リスクを抑えながら作品本来の色を美しく再現するためです。
青色光を減らすことで劣化を防ぎ、高演色設計によって自然な見え方を維持する。
その柔らかな光は、単なる演出ではなく、美と保存を両立させるための科学的な照明設計なのです。