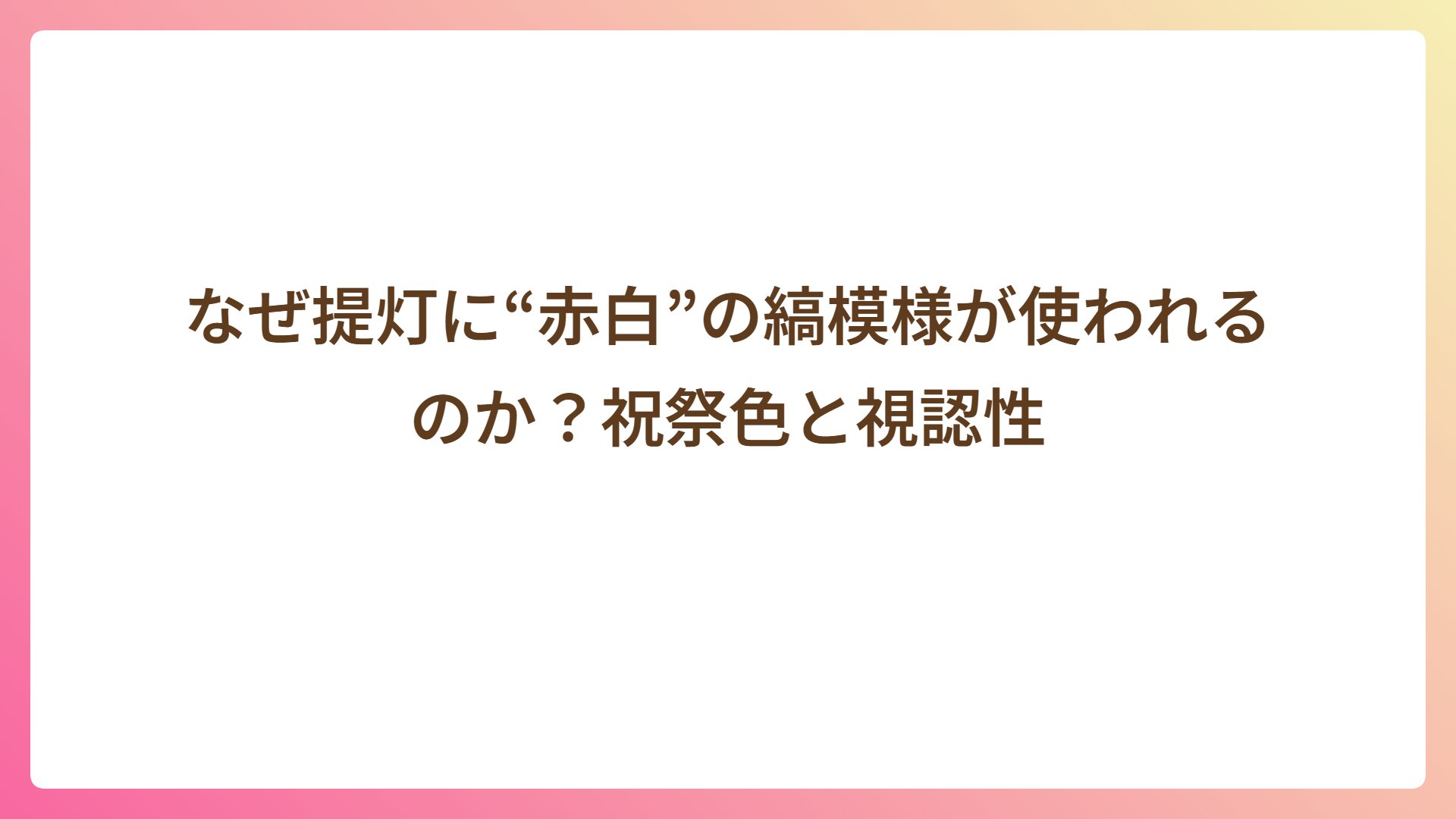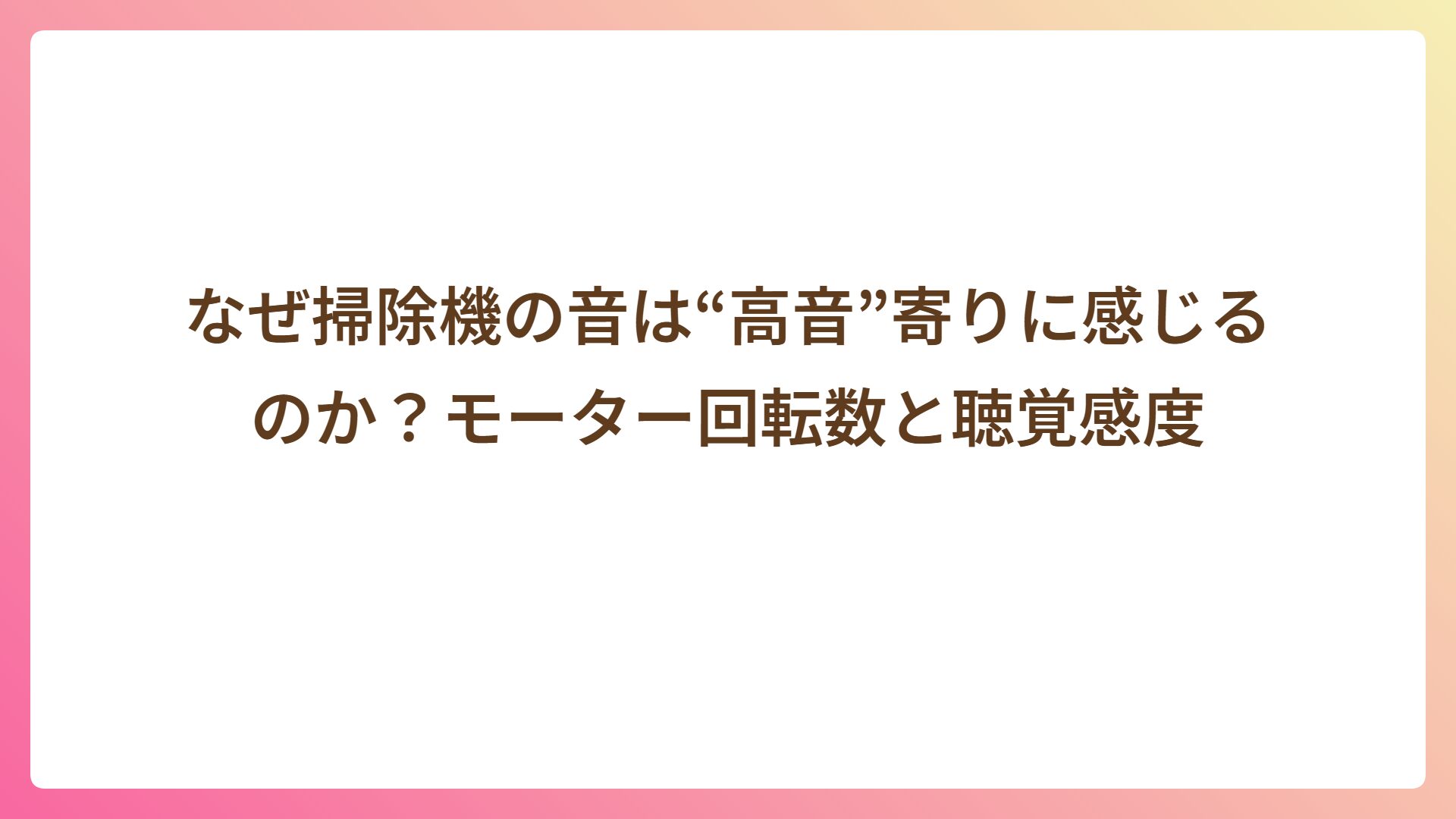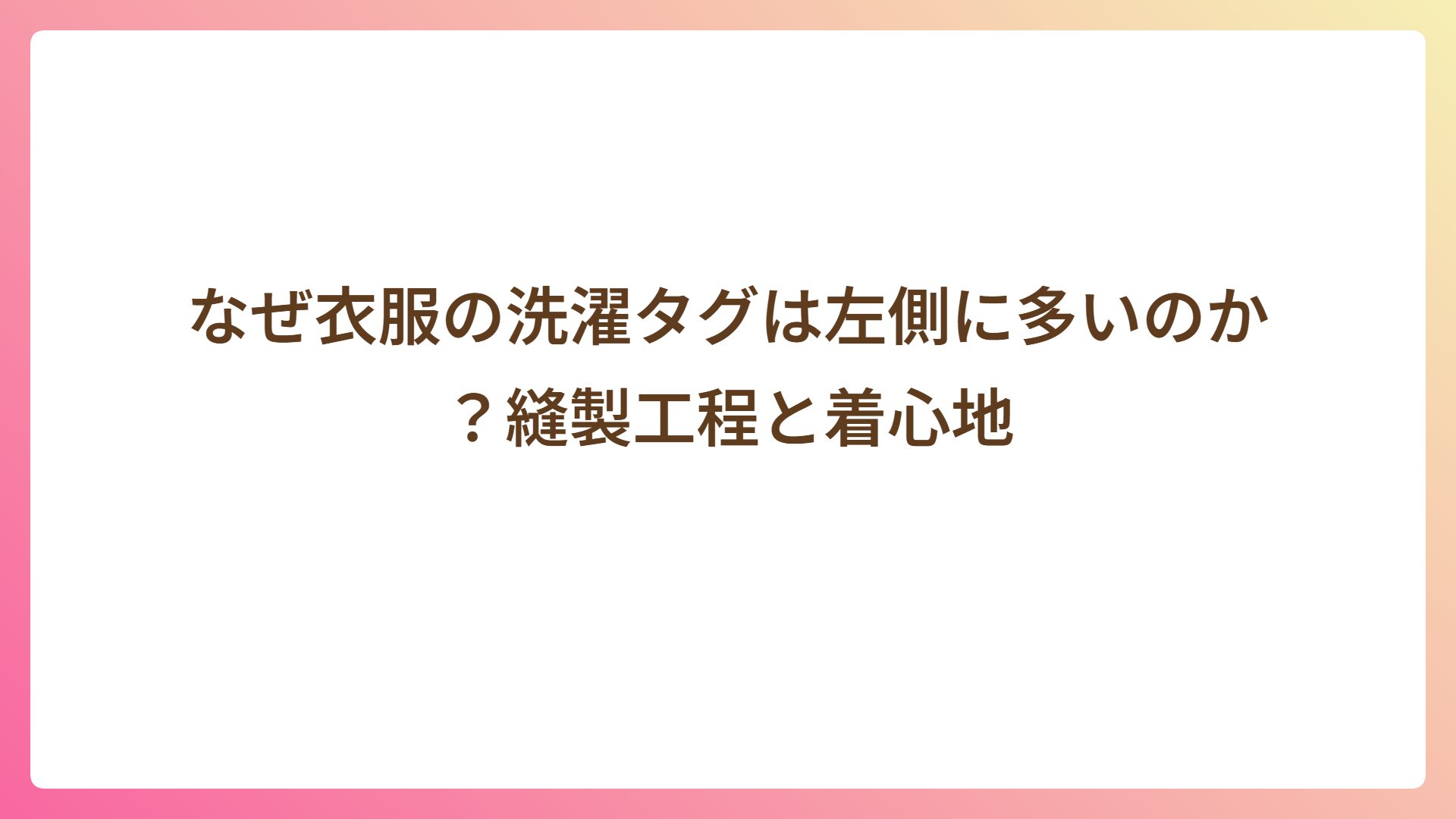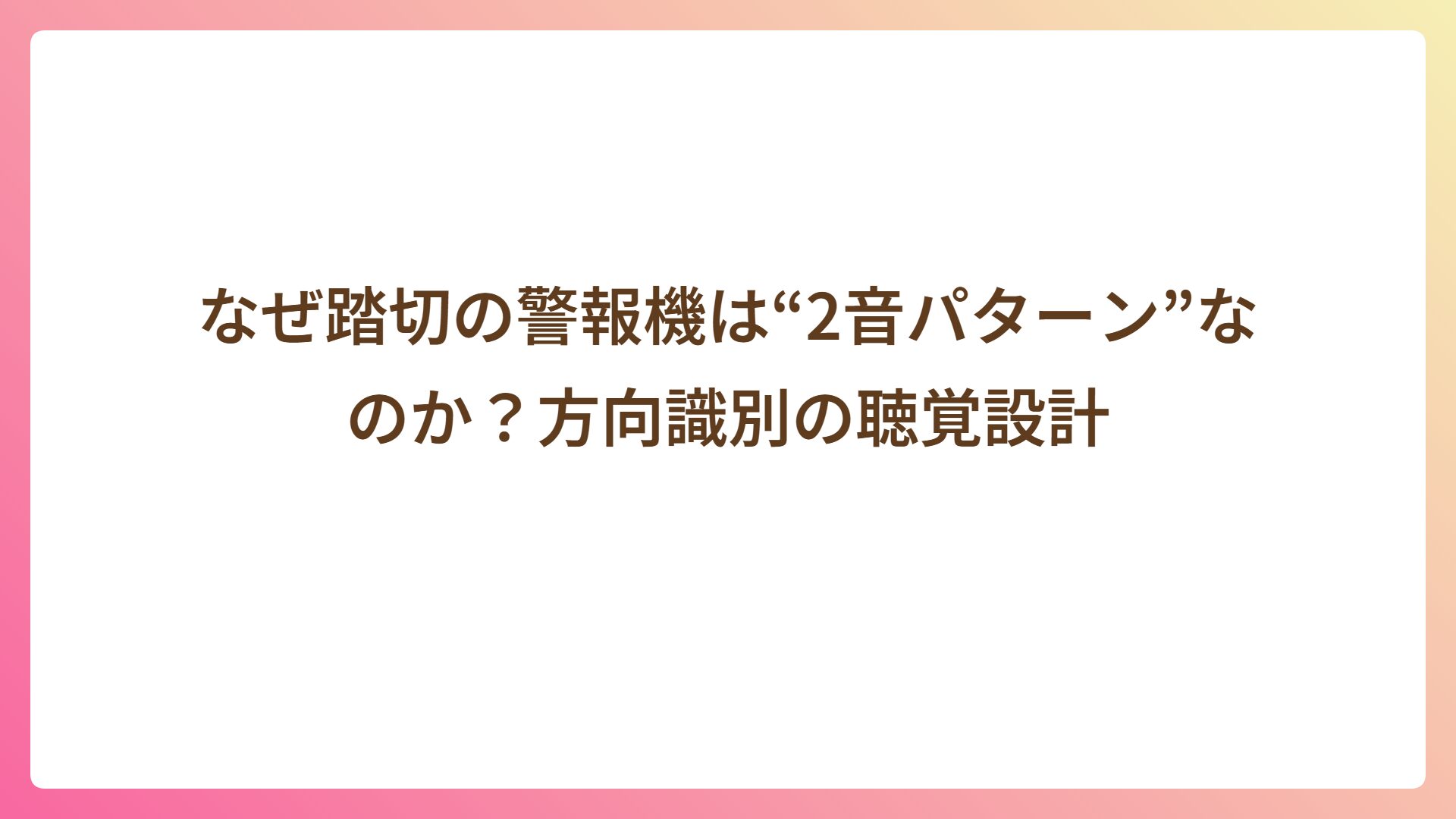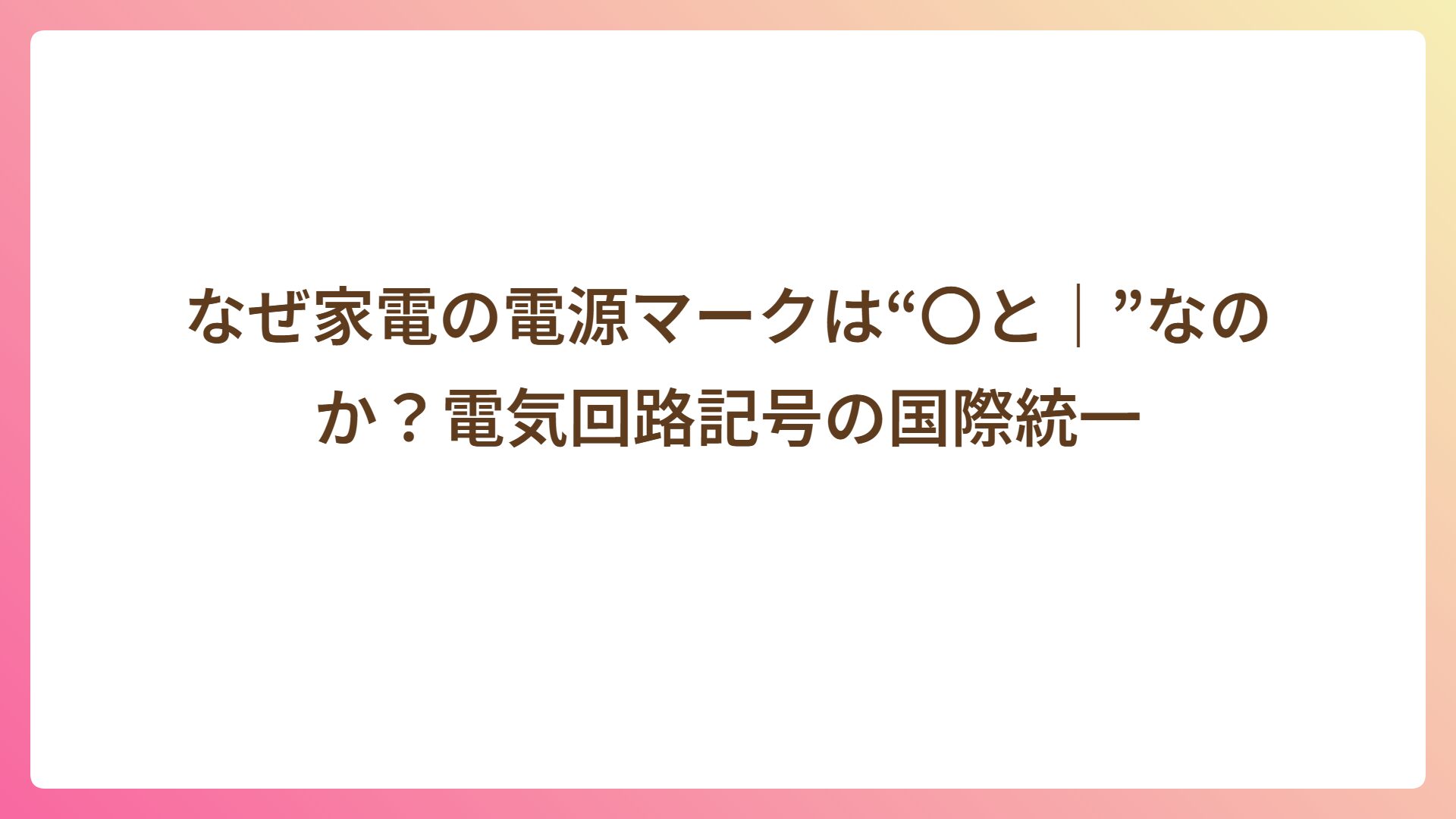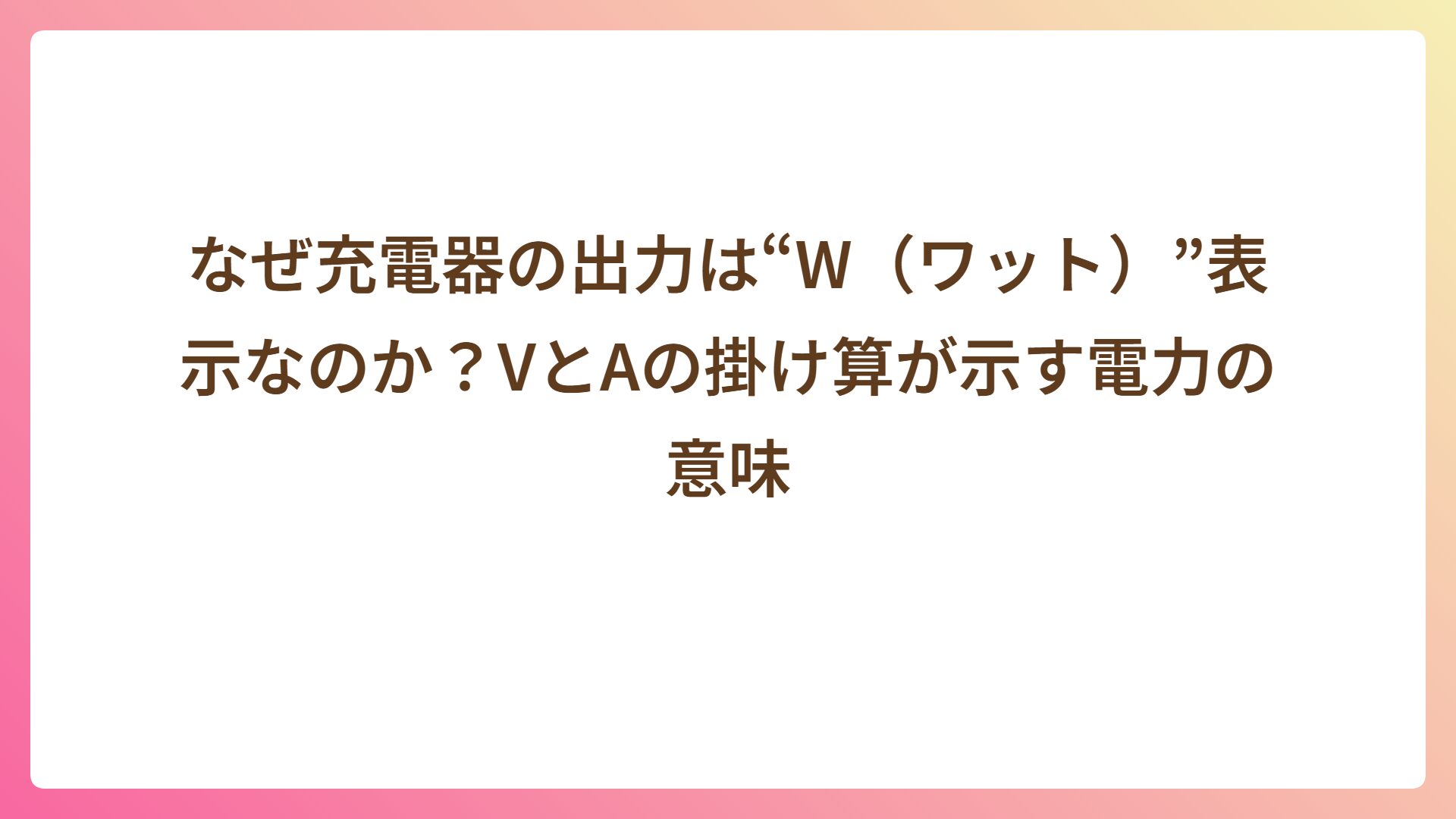なぜバス停の時刻表は“縦書き/横書き”が混在するのか?可読性と掲示面積の最適化
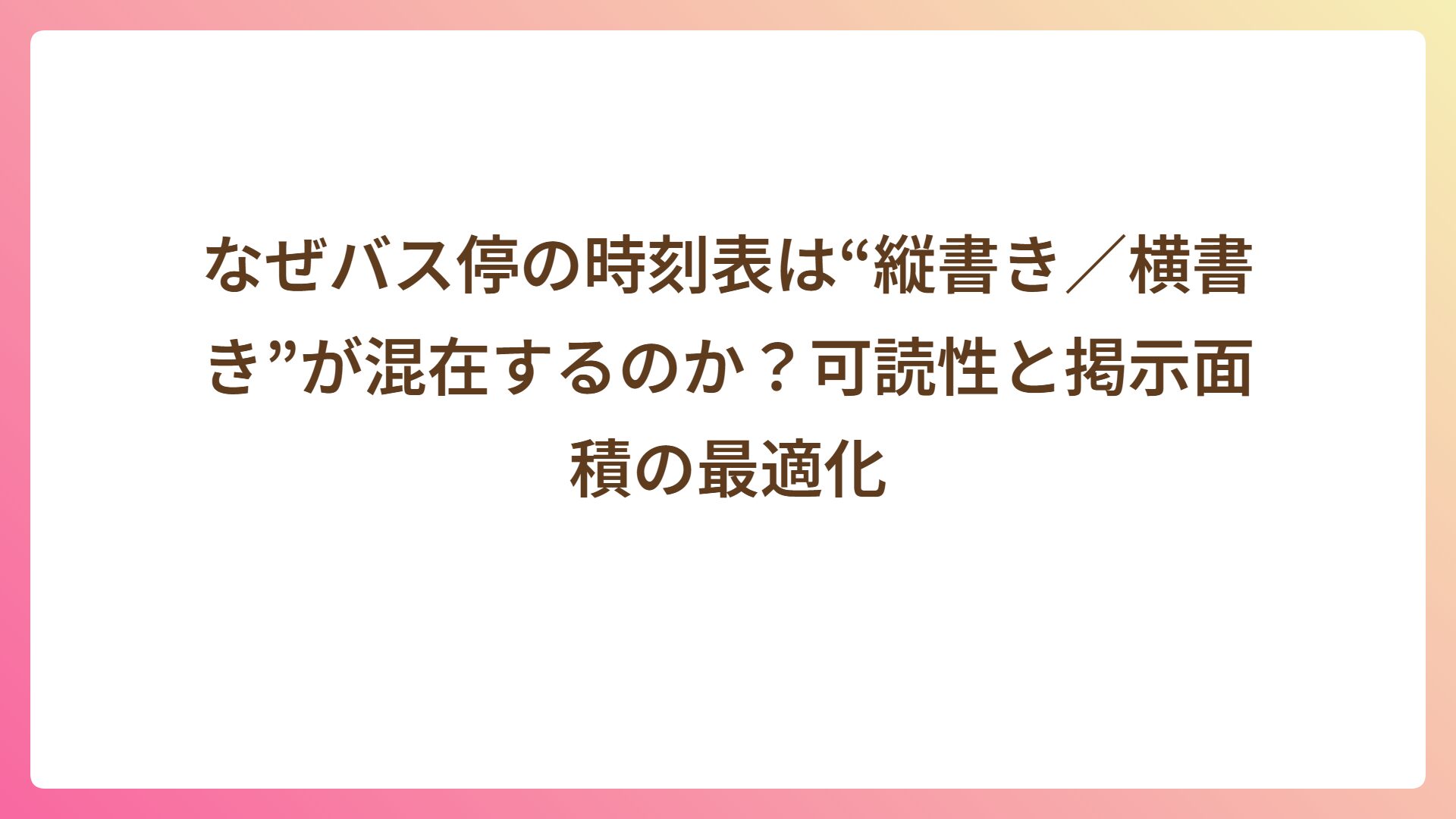
バス停の時刻表をよく見ると、縦書きのものと横書きのものが混在しています。
同じ会社でも停留所によって形式が違ったり、数字が縦に並ぶ表と横に流れる表があったりと、意外と統一されていません。
これはデザイン上の自由ではなく、「見やすさ」と「掲示効率」を両立するための設計上の工夫なのです。
この記事では、バス停時刻表が縦書き・横書きで分かれる理由を、可読性・スペース・利用環境の観点から解説します。
理由①:掲示面積を最大限活用するため
バス停の掲示板は、狭いスペースに複数の情報(行き先、路線図、注意書きなど)を載せる必要があります。
縦書きと横書きを使い分けることで、限られた掲示面積を効率よく使えるのです。
たとえば、
- 時刻の本数が少ない地方路線では、時刻を縦に並べたほうが省スペース
- 本数の多い都市路線では、横に流す方が一目で比較しやすい
つまり、時刻表の密度(本数×時間帯)によって、最適な書き方が変わります。
理由②:数字が“縦でも読める”日本語文化
日本語は縦書きにも横書きにも対応できる珍しい言語です。
そのため、数字が多い時刻表でも「縦並び」でも違和感がありません。
たとえば、
7:10 7:40 8:10 8:40
という横並びの情報を、
7時10分
7時40分
8時10分
のように縦に積んでも読解に支障がないのは、日本語ならではの利点。
この柔軟性を生かして、掲示スペースや利用環境に合わせて書式を切り替えることが可能になっています。
理由③:利用者の立ち位置・視線方向に合わせている
バス停の形状によっては、利用者が近距離で縦に読むか、離れた位置から横に追うかが異なります。
- 近距離で読む(狭い歩道・屋根下など) → 目線移動が小さい「縦書き」が有利
- 遠目から全体を把握(大型停留所やターミナル) → 横方向に展開する「横書き」が有利
特に都市部の複数路線停留所では、横書きで一覧性を重視するケースが多く、
郊外では縦書きで見上げながら読むスタイルが主流です。
理由④:印刷テンプレート・運行管理システムの違い
時刻表のフォーマットは、各バス会社の運行管理システムで自動生成されます。
システムによっては、
- 古いタイプ:縦書き(印刷用紙に合わせた設計)
- 新型システム:横書き(デジタル掲示対応)
といった差が残っており、導入時期の違いが混在の一因になっています。
また、紙掲示とデジタル案内板を併用している事業者では、
紙は縦書き、モニター表示は横書きという媒体別最適化が行われていることもあります。
理由⑤:バスの運行本数と時間帯配置に合わせた視覚設計
本数が少ない路線では「時間を縦に並べる」ことで時系列が自然に読めます。
一方、本数が多い路線では、
7時台・8時台・9時台
のように横方向で時間帯ごとにまとめるほうが見やすくなります。
つまり、
- 縦書き:1時間あたり数本の低頻度路線
- 横書き:1時間に10本以上の高頻度路線
といった運行パターンに応じて見やすい配置が変わるのです。
理由⑥:車道側からの視認性を考慮
一部のバス停では、乗客だけでなく運転士が時刻を確認できるよう設計されています。
この場合、車道側からの視線方向を考慮して、
- 車道に対して垂直に掲示 → 縦書きが自然
- 車道に対して平行に掲示 → 横書きが自然
というように、設置角度と文字方向の整合性を取るケースもあります。
理由⑦:利用者層(高齢者・観光客)への配慮
高齢者は、数字が縦に並ぶ方が「次の便までの時間」が感覚的に把握しやすい傾向があります。
一方、外国人観光客や若年層は、英数字の横書き表示に慣れています。
そのため、
- 地方路線 → 縦書き(日本語主体・年配利用者中心)
- 都市部・空港路線 → 横書き(多言語併記・視覚的レイアウト重視)
というように、利用者層に合わせたフォーマット最適化が行われているのです。
まとめ:縦横の違いは“美観”ではなく“設計思想”
バス停の時刻表が縦書き・横書きで混在しているのは、
- 掲示スペースを最大限に使うため
- 路線の本数や構成に合わせた見やすさのため
- 設置環境(距離・角度・光)に合わせた可読性設計のため
- 利用者層や運用システムの違いによるため
という、実務的かつ人間工学的な理由によるものです。
つまり、「統一されていない」のではなく、
それぞれの場所に最適化されているのが現実。
縦書きも横書きも、利用者が“最短で読み取れる”ことを第一に考えた結果なのです。