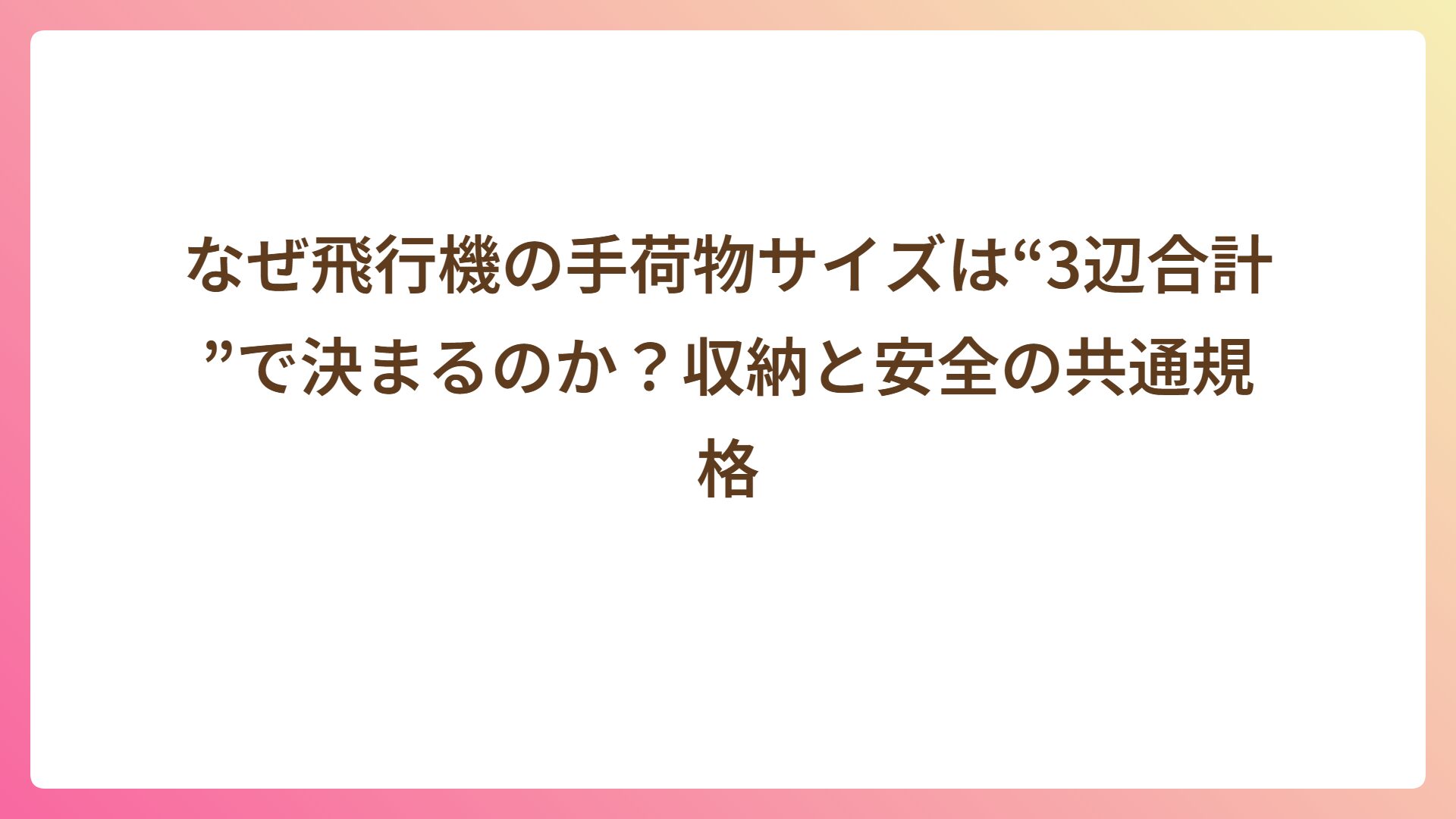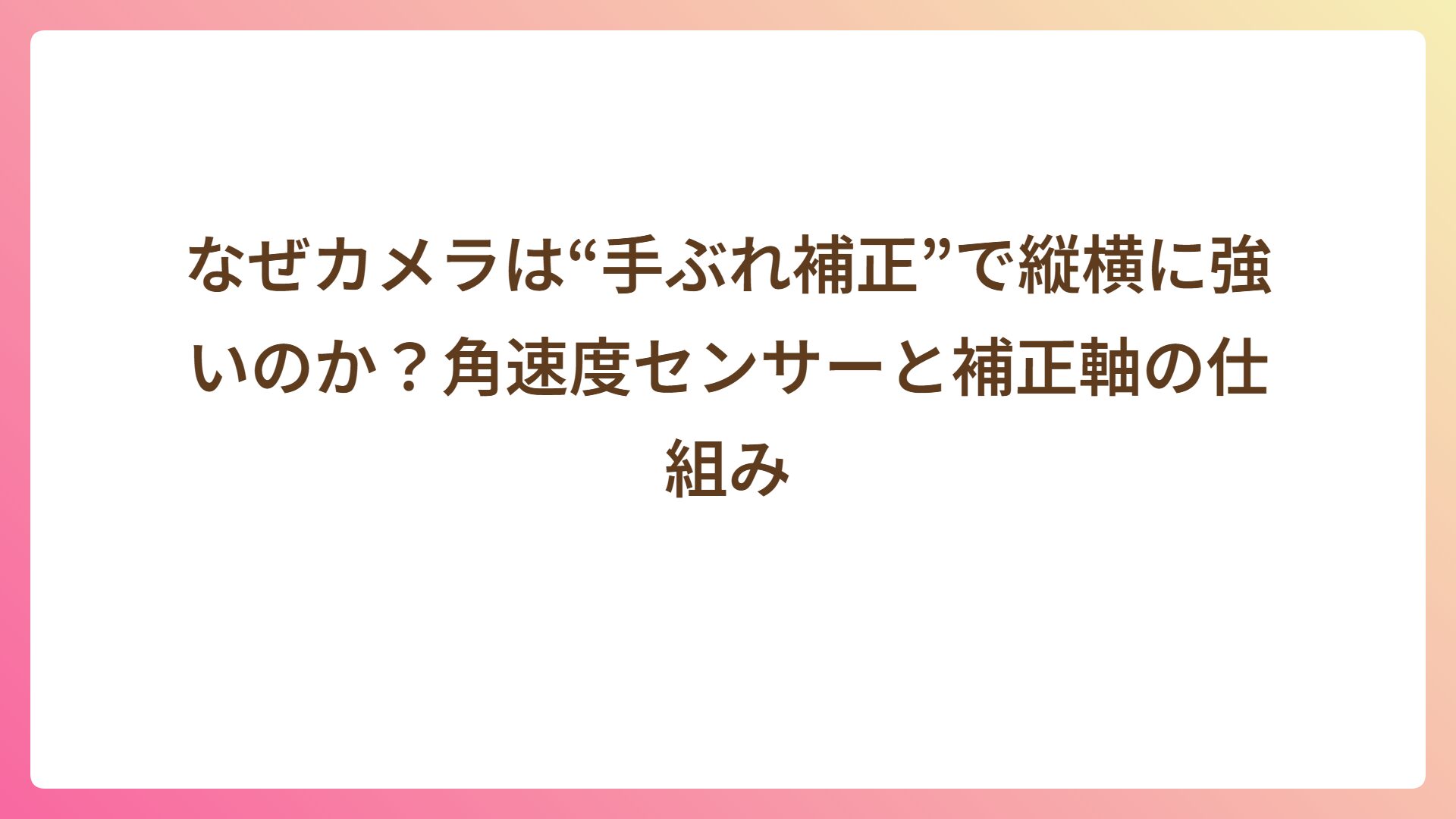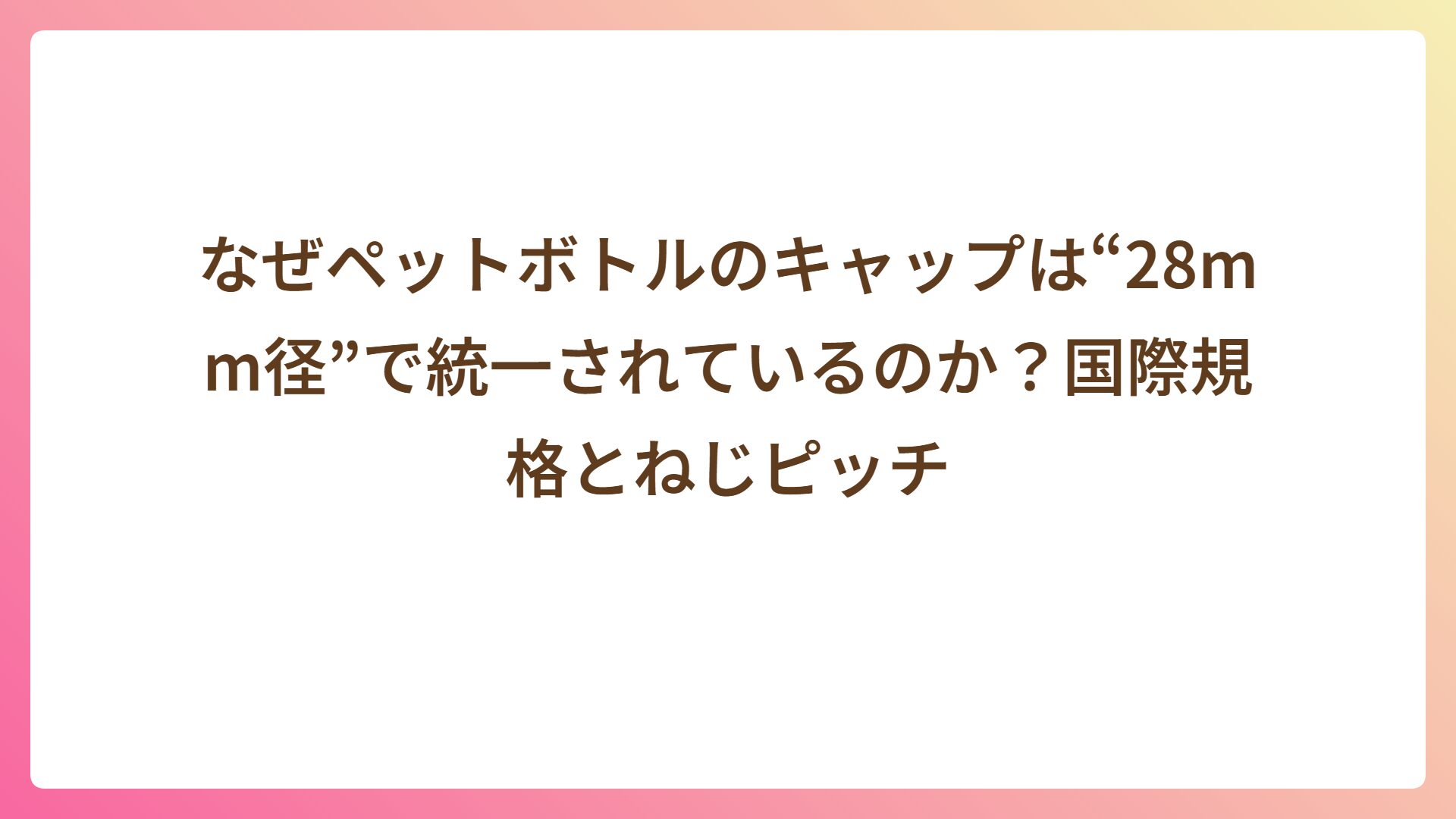なぜ路線バスの座席は硬めなのに長距離にも使われるのか?耐久と姿勢保持

路線バスに乗ると、「ちょっと座面が硬いな」と感じたことはありませんか?
同じバスでも観光バスはふかふかの座席なのに、なぜ路線バスはあえて硬めに作られているのでしょうか。
実はこの“硬さ”には、耐久性・姿勢保持・安全性といった複数の目的が込められているのです。
硬めの座席は「耐久性」を優先した設計
路線バスの座席は、1日に何百人もの乗客が入れ替わり立ち替わり座る“公共設備”です。
そのため、柔らかいウレタンや布張りではすぐにへたりや破損が発生してしまいます。
硬めの発泡ウレタンや樹脂シートを採用することで、
10年以上使用しても形が崩れにくい耐久性を確保しているのです。
また、布張りでは汚れやにおいが残りやすいため、
清掃しやすいビニールレザー素材(PVC)が多く使われています。
硬く感じるのは、この素材特有の張りと反発力によるものです。
長時間座っても“疲れにくい硬さ”
意外かもしれませんが、人間の体は柔らかすぎる座面に沈み込むと、
腰や太ももの筋肉が緊張し、逆に疲労がたまりやすくなることが知られています。
路線バスの座席は、短時間の乗降を繰り返しても姿勢が崩れにくいよう、
骨盤をしっかり支える硬さに調整されています。
つまり、路線バスの座席は“柔らかい=快適”ではなく、
“硬め=姿勢が保てる”という実用的な快適性を重視しているのです。
安全性の観点:急ブレーキ時の姿勢保持
都市部では停車や発進が頻繁に行われ、
乗客が体を揺らすリスクも高くなります。
硬めの座席は、沈み込みが少ないため腰がしっかり固定され、体が前に流れにくい構造になっています。
また、路線バスは立ち客が多いため、
「座っている人が急ブレーキで前につんのめられないようにする」ための硬質設計でもあります。
柔らかすぎる座席だと、衝撃時に沈んで反動で体が浮きやすくなるため、
安全性の観点からも硬めが適しているのです。
軽量化と燃費への配慮
柔らかいシートクッションを厚くすれば快適にはなりますが、
その分座席重量が増加します。
路線バスは1台あたり20~30席あり、1席あたり数百グラムでも、
合計すると数十キログラムの差になります。
軽量化は燃費にも直結するため、
メーカーは“必要最小限のクッション厚”で軽さと剛性の両立を図っているのです。
長距離運行にも使われる理由
地方路線や高速乗合バスなどでは、同じ車両が短距離・長距離の両方に使われることがあります。
この場合も、座面形状と背もたれ角度で快適性を確保しています。
たとえば背もたれをやや後傾(約100度)にし、
クッション内部の硬度を段階的に変えることで、
硬めながらも体圧を分散させる構造になっているのです。
さらに、硬めの素材は通気性が良く、
長時間座ってもムレにくいため、夏季運行にも向いているという実用上の利点もあります。
まとめ
路線バスの座席が硬めなのは、
耐久性・姿勢保持・安全性・軽量化といった複数の要素を両立させるためです。
多くの人が毎日使う公共の椅子として、
“柔らかい快適さ”よりも“疲れにくく壊れにくい硬さ”が選ばれているのです。
その一見無骨な座り心地の裏には、長期使用と安全運行を支える設計思想が息づいているのです。