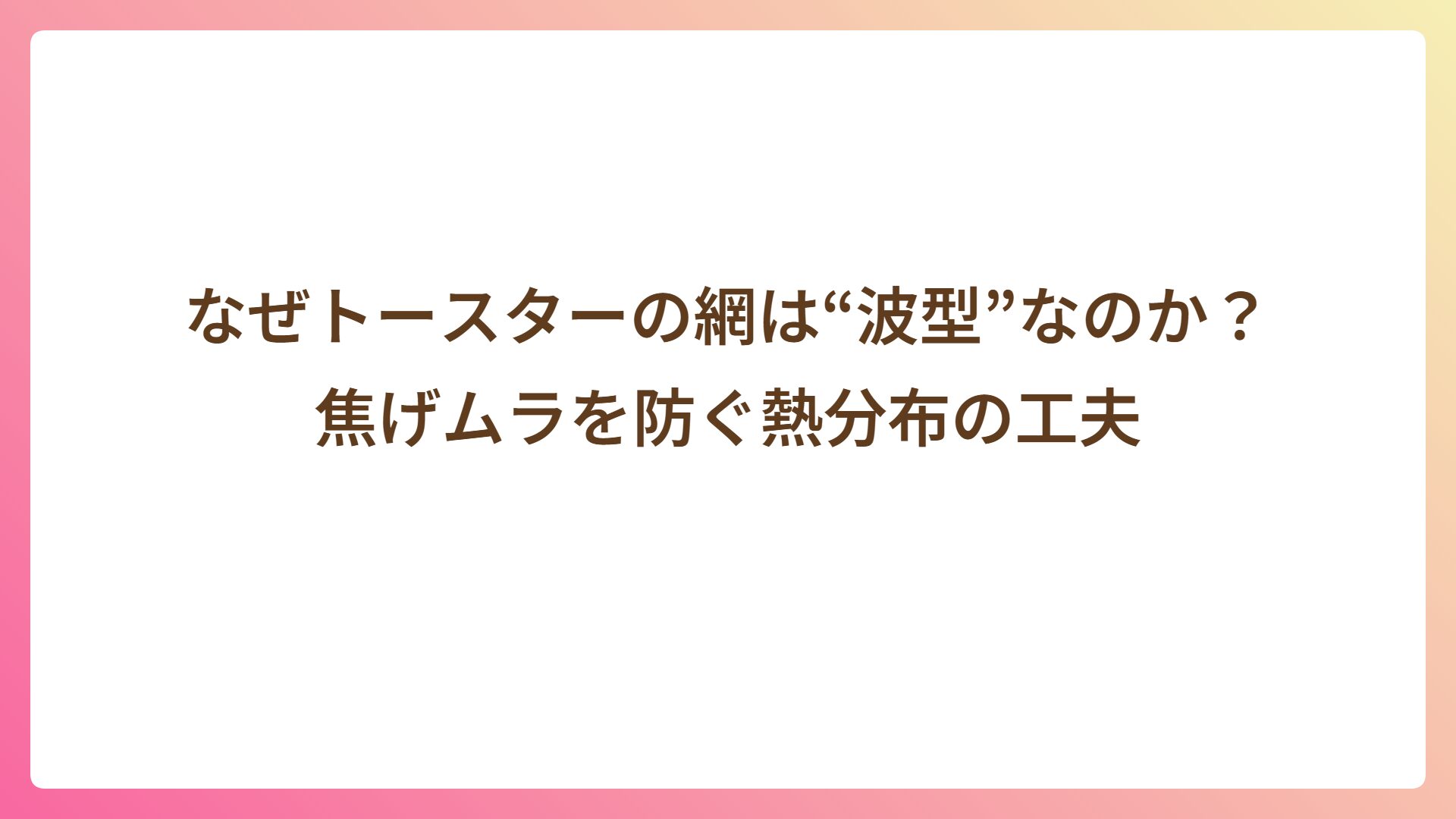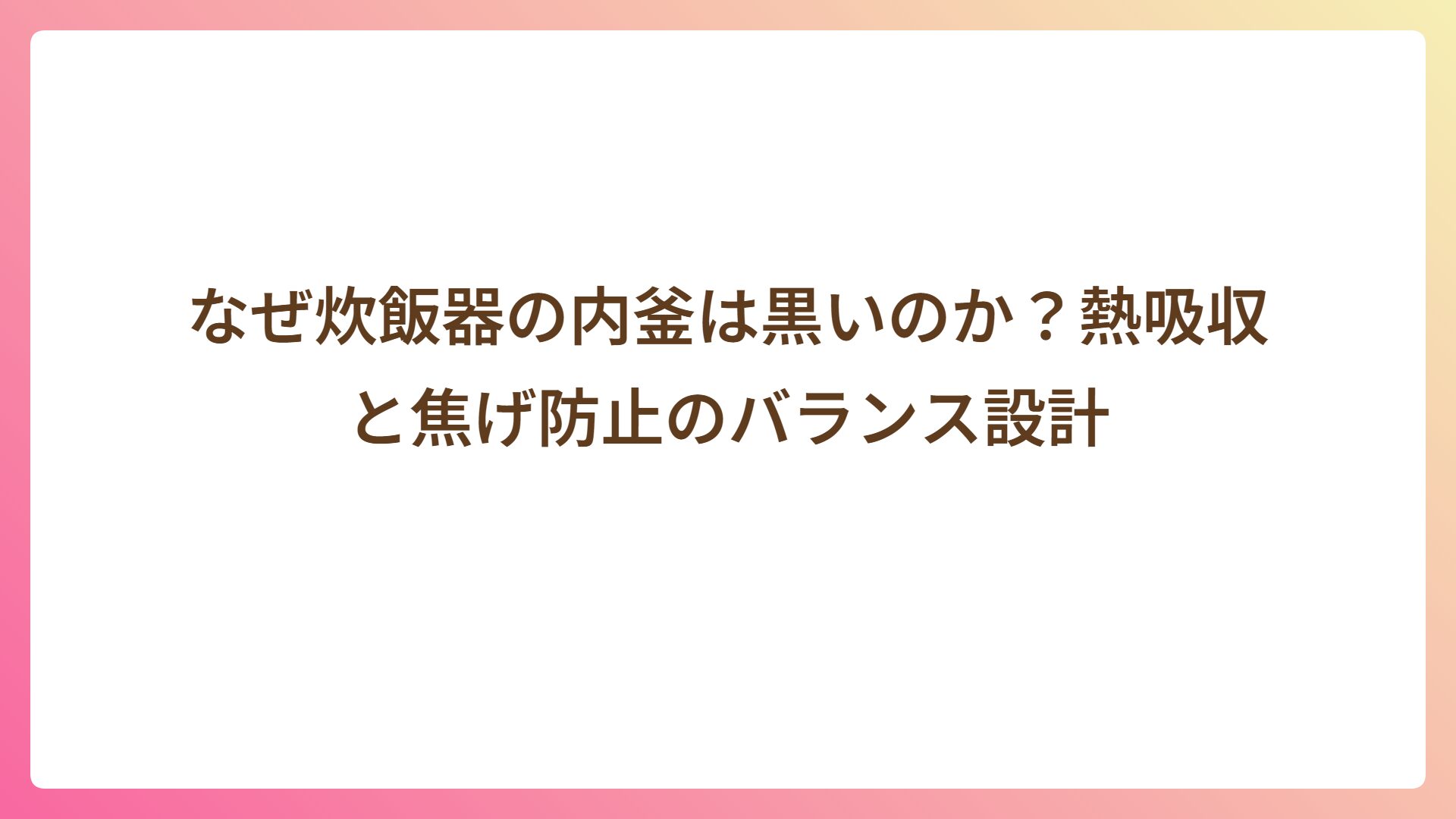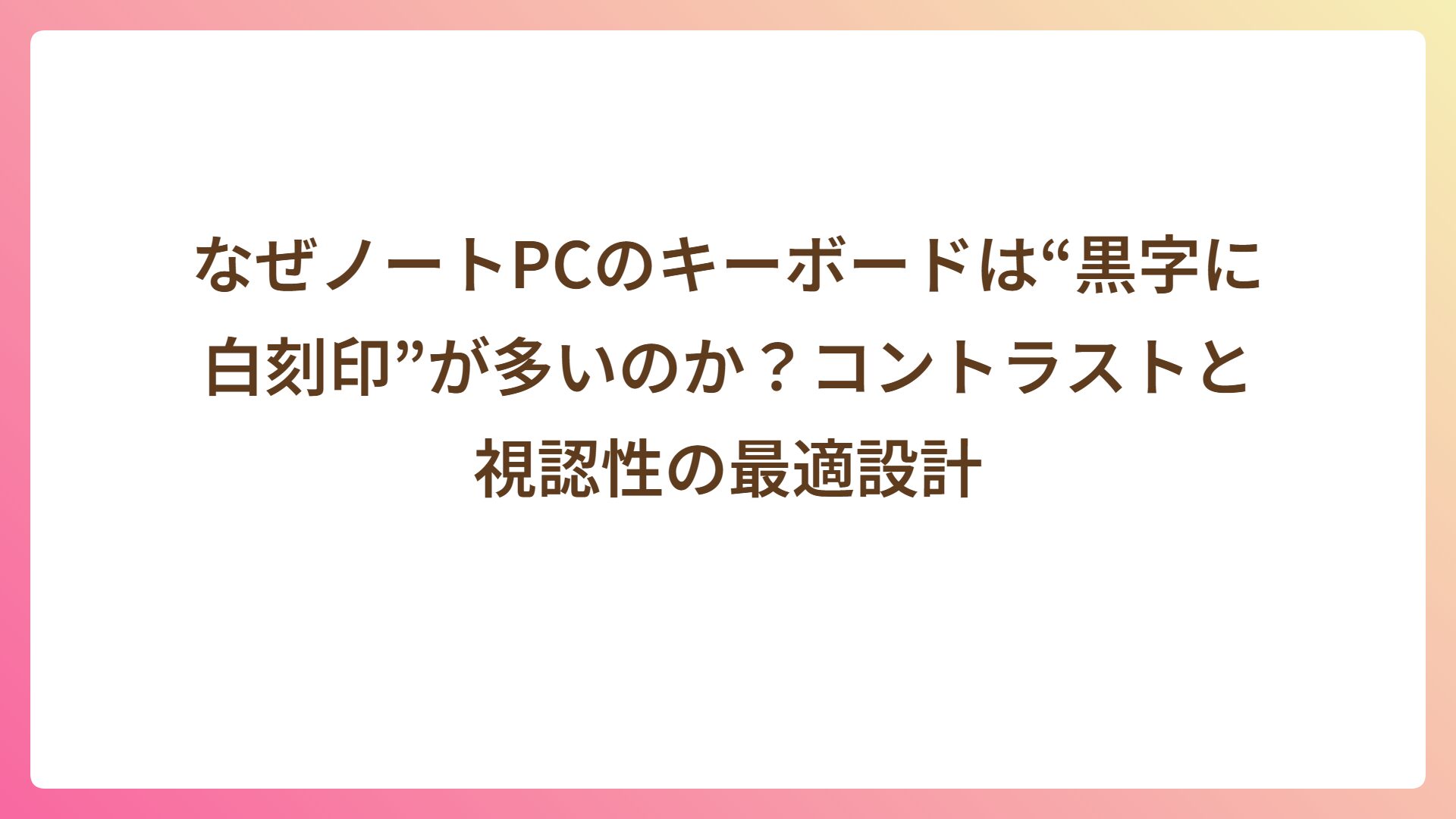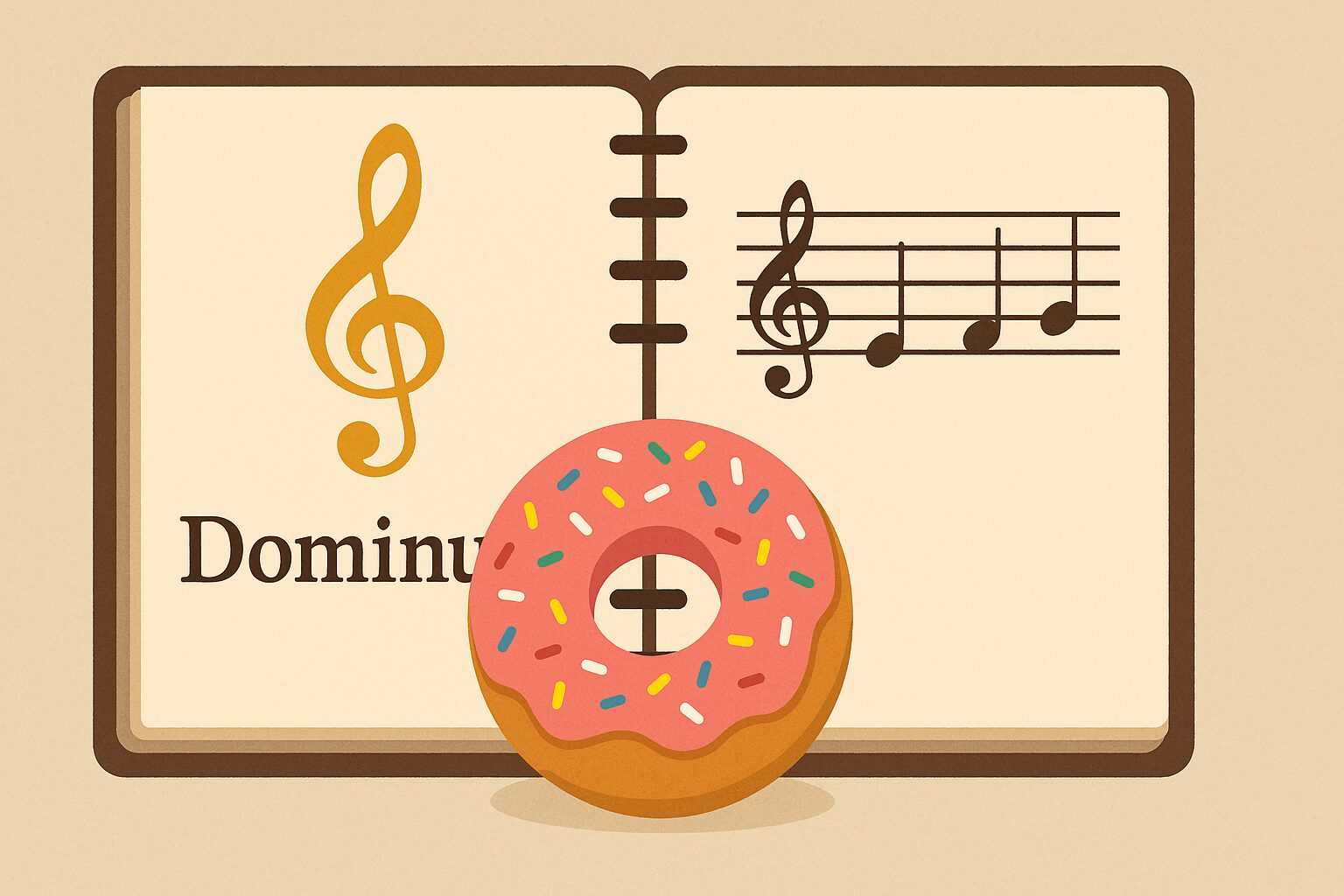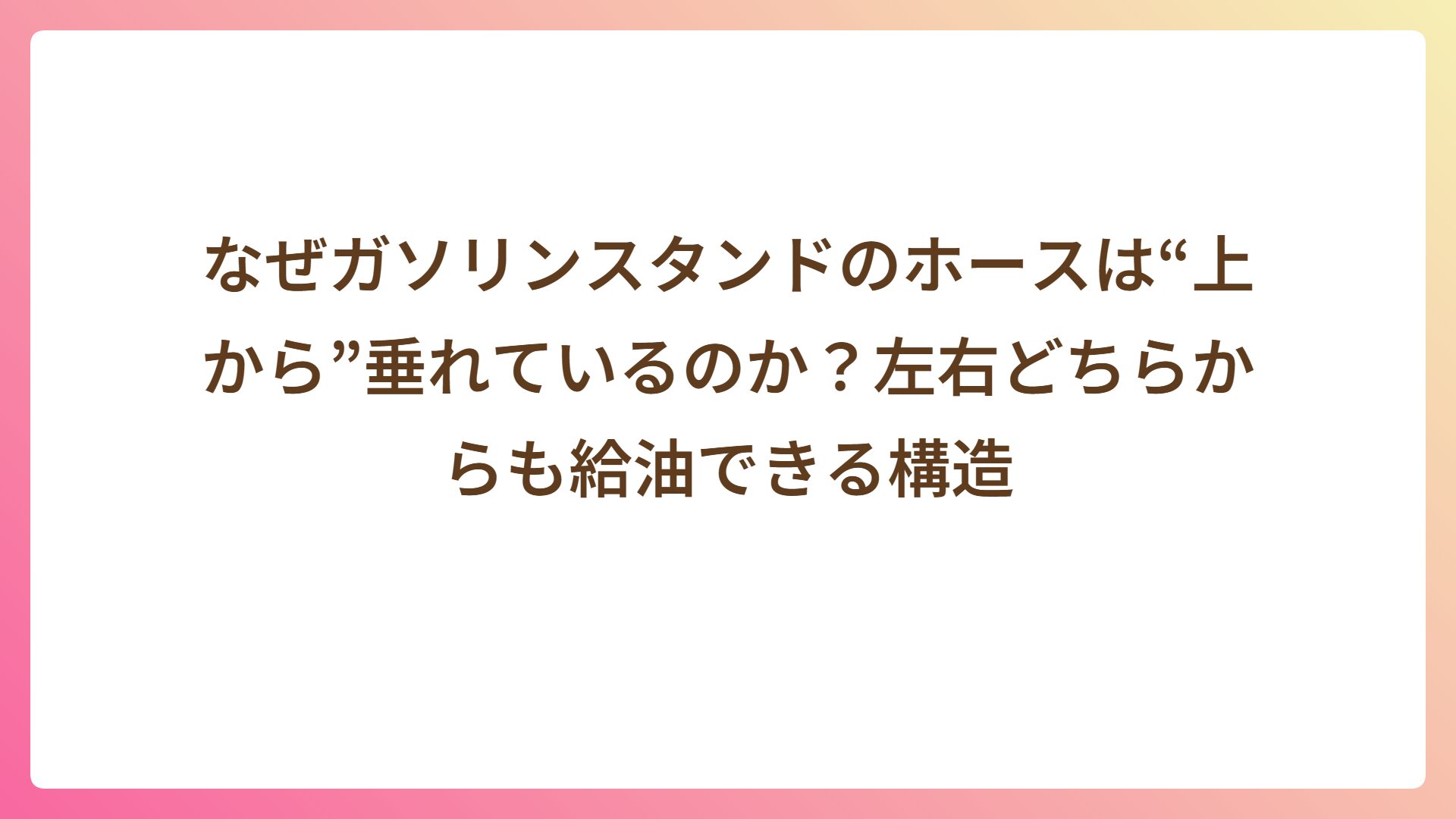「25℃」の“C”はなに?なぜ読まない?温度表記の意味とセルシウス度の由来を解説
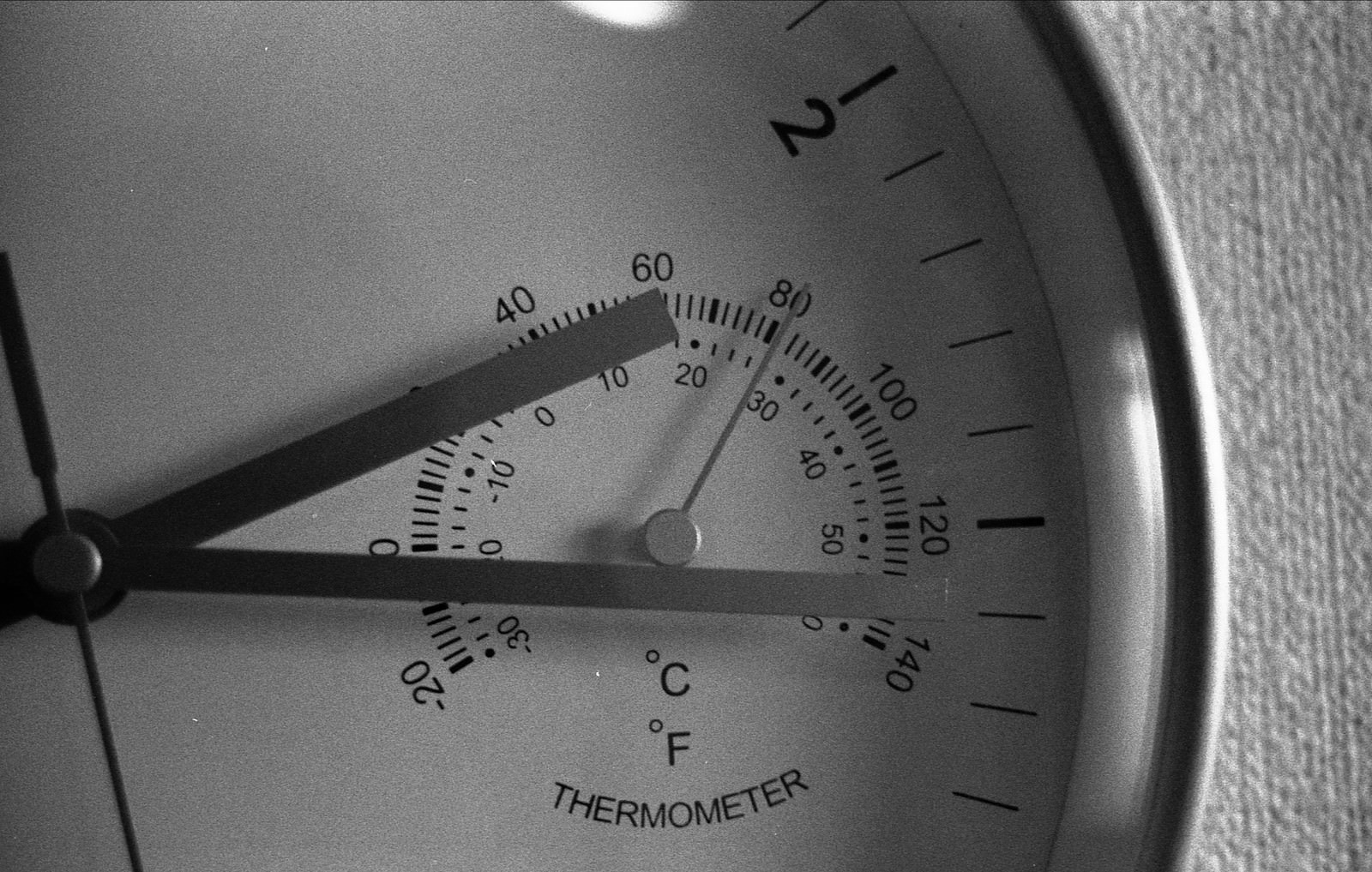
みなさんは「25℃」という表記を見たとき、どう読んでいますか?
多くの人が「にじゅうごど」と読むと思いますが、同じように「25°」も「25度」と読みますよね。
では、「℃」の最後についている “C” にはどんな意味があるのでしょうか?
また、「度(ど)」「°(度の記号)」「℃(摂氏記号)」にはどんな違いがあるのでしょうか?
「C」はセルシウスという人物の頭文字
「℃」の“C”は、温度の単位である セルシウス度(Celsius) を表しています。
セルシウス度は、日本では「摂氏」とも呼ばれ、私たちが普段使っている温度表記の単位です。
この単位を考案したのは、スウェーデンの天文学者 アンデルス・セルシウス(Anders Celsius)。
彼の名前に由来して「C」の文字が使われています。
つまり「℃」とは、「度数」+「セルシウス」の意味を持つ記号なのです。
Cは「単位名」を明示するためにある
「℃」の“C”は、温度がセルシウス度で示されていることを明確に伝えるための記号でもあります。
実は、温度の単位には他にもいろいろあります。
- ℉(華氏:Fahrenheit)
- K(絶対温度:ケルビン)
- °Ré(レオミュール度) など
これらと区別するために、「摂氏(セルシウス)」の温度であることを示す“C”がつけられているのです。
なお、K(ケルビン)には°の記号はつけず、単位記号「K」のみで表記されるという違いもあります。
なぜ「C」は読まないの?
「25℃」を読むとき、私たちはたいてい「25度」としか言いません。
“セルシウス”という単位名は 音声として省略されるのが一般的だからです。
たとえば「25kg(キログラム)」を「25キロ」と略して読むように、「25℃」も「度」だけで通じるようになっています。
ただし、理科の授業や学術的な場面では、「25度セルシウス」と正確に読むこともあります。
実は「度」だけでは不十分なことも
日本では「気温=摂氏(℃)」という前提があるため、“C”をあえて口に出す機会は少ないかもしれません。
しかし、国や文脈が違えば話は別です。たとえばアメリカなどでは気温を 華氏(℉) で表すのが一般的なので、「25度」が摂氏か華氏かで まったく違う温度になります。
だからこそ、「C」はただの飾りではなく、重要な区別の手がかりでもあるのです。
温度表記には意味が詰まっている
「25℃」という何気ない表記の中にも、単位の歴史と国際的な基準が詰まっています。
Cはセルシウスの名に由来し、さまざまな温度単位との混同を避けるために欠かせない存在です。
そして、普段私たちが読まないのは、慣用的に省略されているだけのこと。
海外旅行や理科の学びの中で、温度表記の違いに触れたときには、ぜひこの「C」の意味を思い出してみてください。