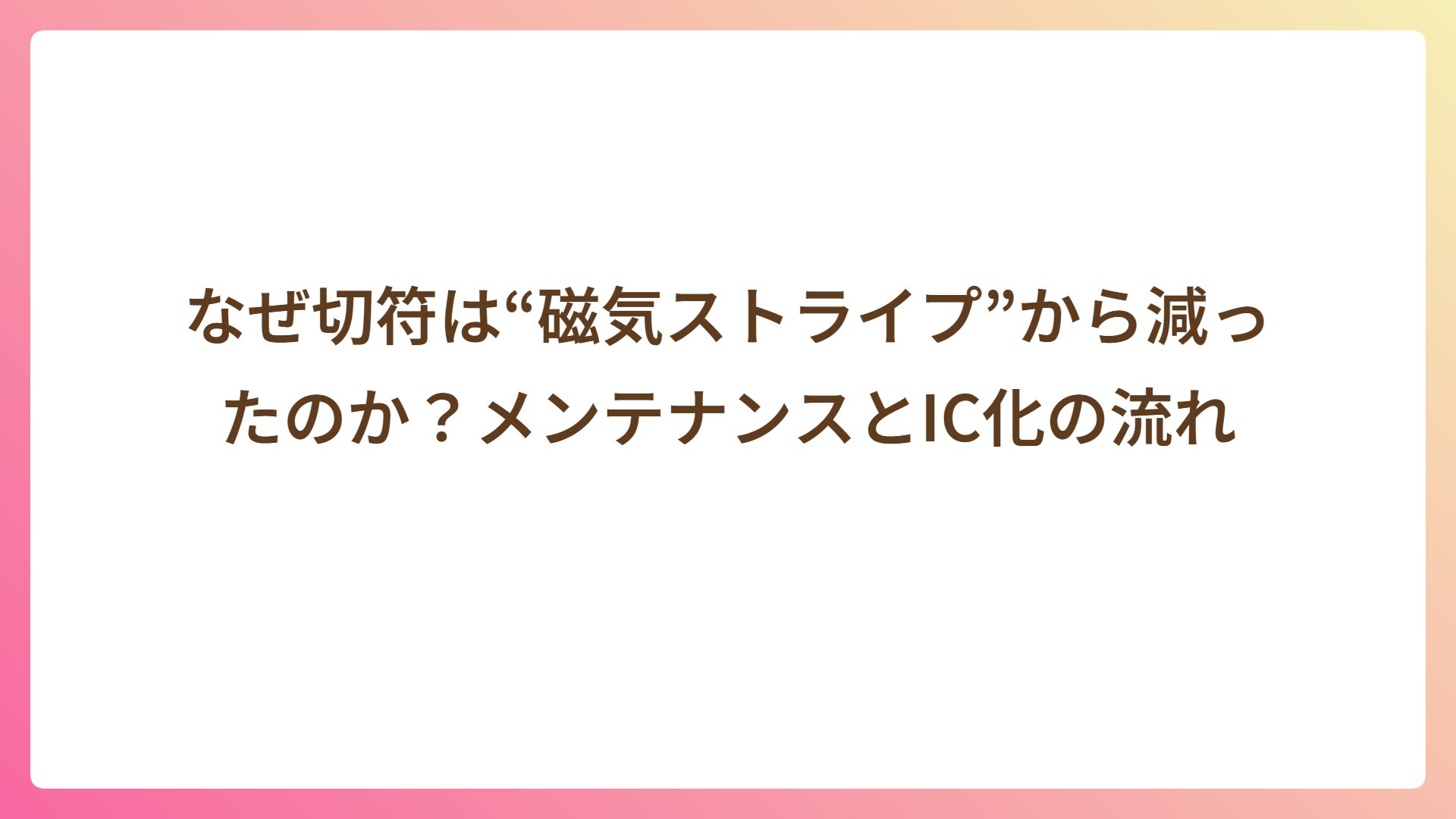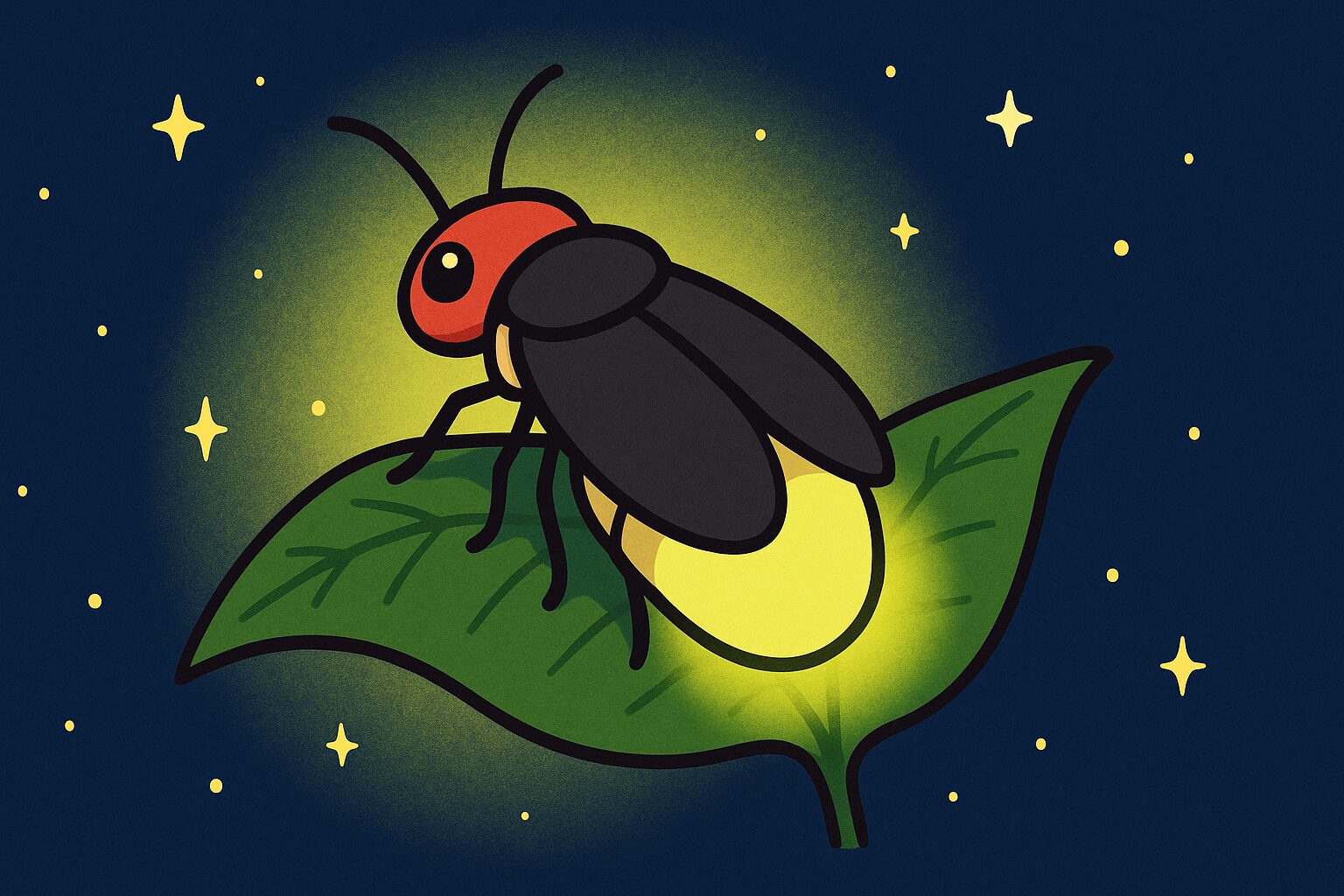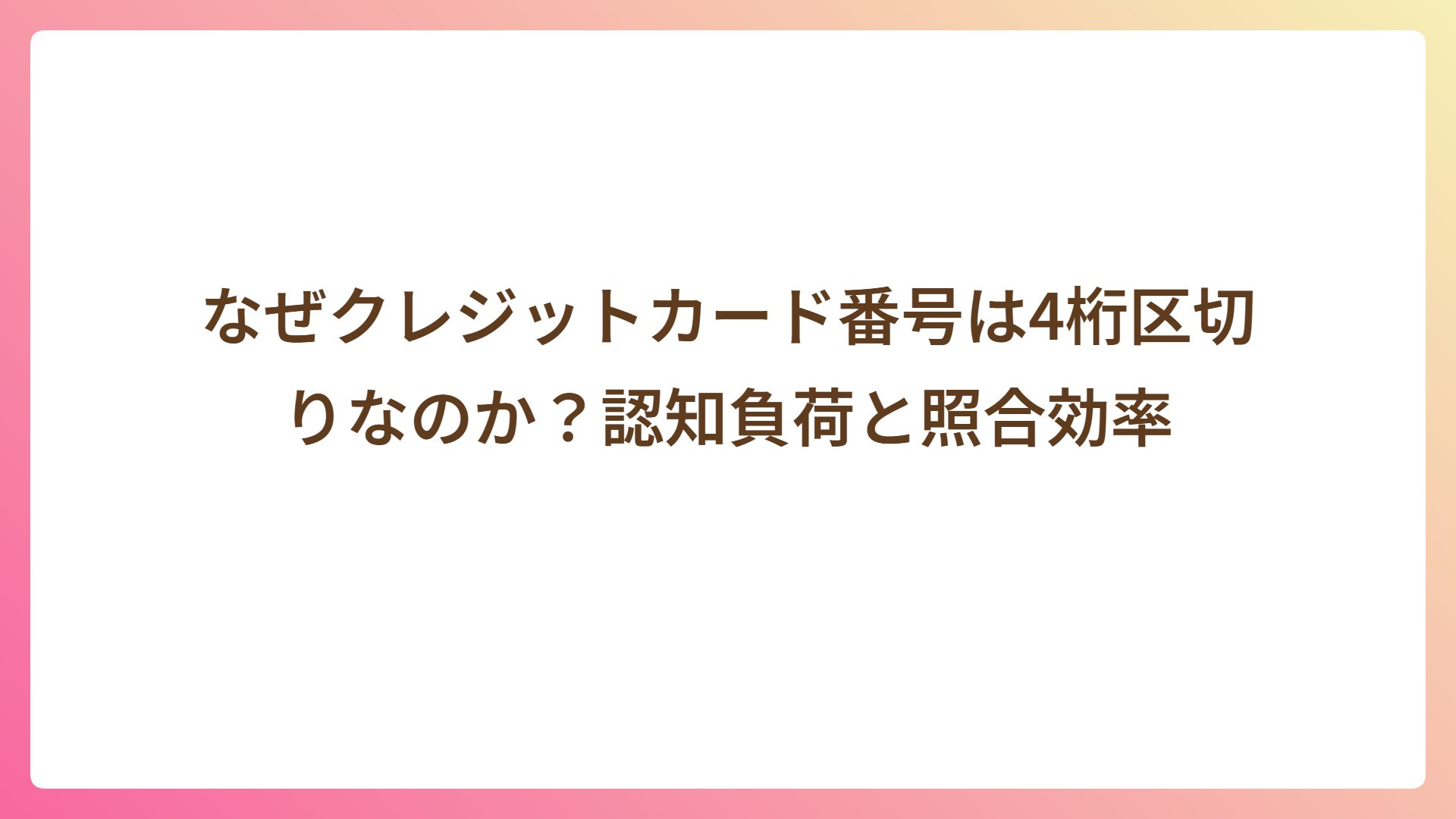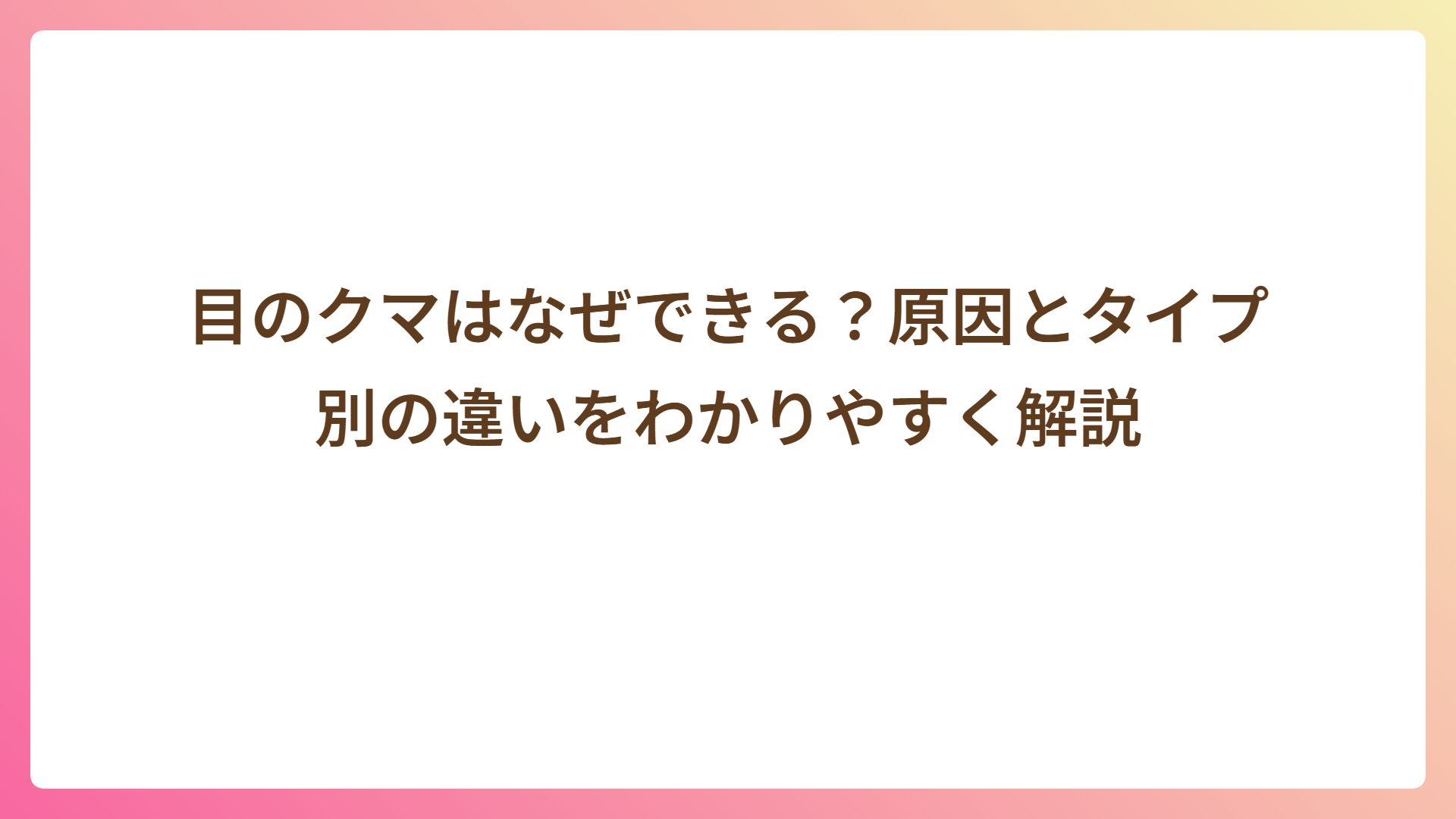なぜ道路のセンターラインは“黄色/白”で使い分けるのか?追越可否を示す交通ルール
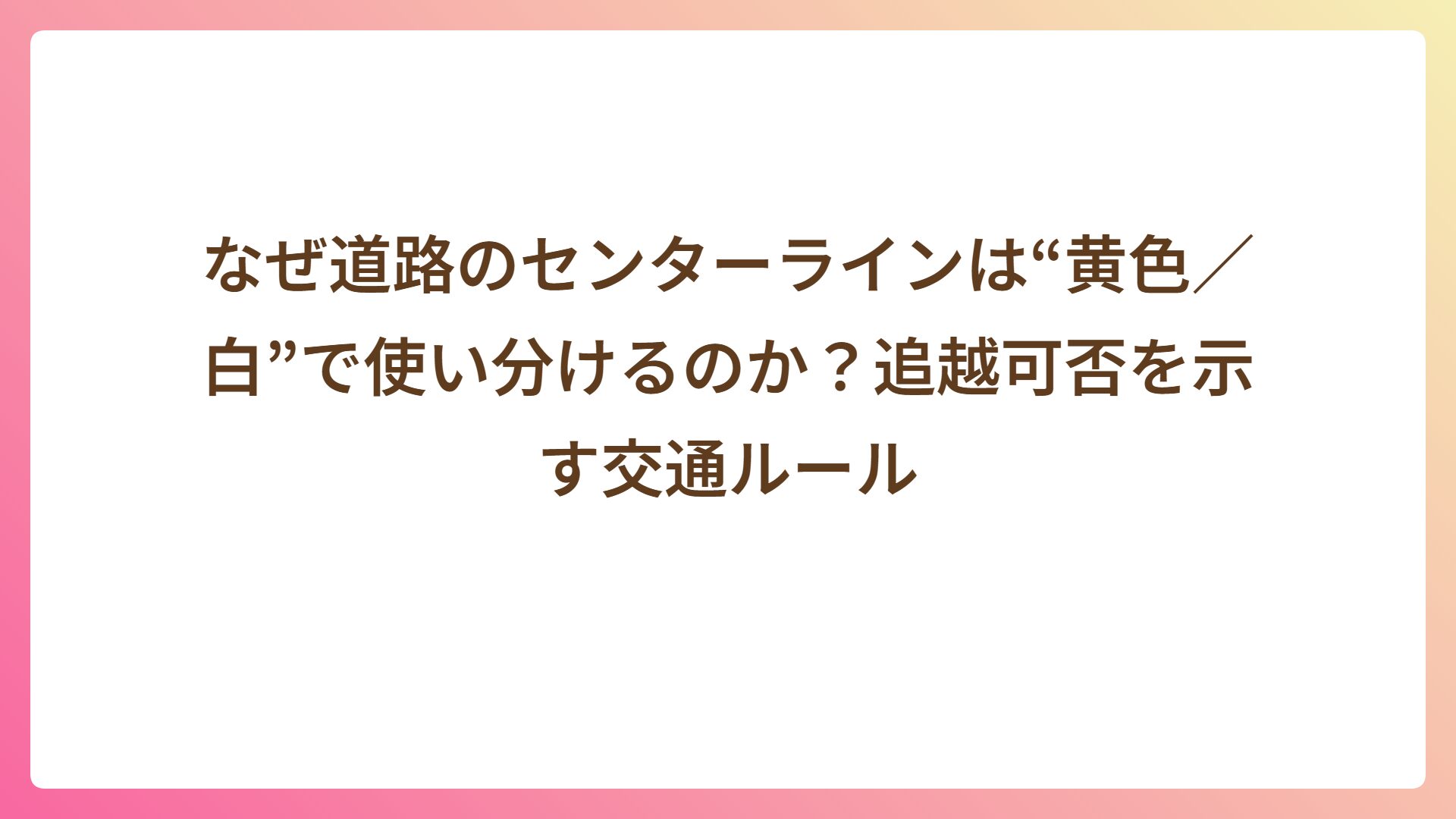
道路を走っていると、センターラインが白線の道と黄色線の道があることに気づきます。
どちらも「中央線」ですが、実は色の違いには明確な意味と法律上の効力があります。
この区別を知らないと、うっかり違反になることも。
この記事では、センターラインが黄色と白で使い分けられている理由を、追越ルールと交通安全設計の観点から詳しく解説します。
センターラインは「道路交通法で定められた交通区分線」
センターライン(中央線)は、道路交通法第18条および道路標示令によって定義されており、
車両の通行区分を示す標示です。
基本の考え方は次のとおり:
- 白線:通行区分のみを示す(越えてもよい場合あり)
- 黄色線:通行区分+追越禁止を示す(越えるのは禁止)
つまり、色の違いは「線を越えていいかどうか」の違いなのです。
白のセンターライン:対向車線の区分のみ(越えてOK)
白いセンターラインは、道路の中央を示すだけの線です。
法律上は「車両通行区分線」に分類され、次のような場所で使われます。
主な使用場所
- 交通量が少ない一般道
- 十分な見通しがある直線道路
- 幅員が広く、安全に追越できる区間
特徴
- 対向車がいないタイミングで、追越しや右折で越えることが可能
- ただし、安全確認と右側通行規制に従う必要あり
つまり白線は、安全条件を満たす場合に限り“越えてもよい線”です。
黄色のセンターライン:追越し禁止・進入禁止の警告線
一方、黄色のセンターラインは「追越しのために対向車線へ出てはいけない」ことを示す標示です。
正式名称は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(標示番号101)」で、
道路交通法第17条に基づく強い法的効力を持ちます。
主な使用場所
- カーブ・坂道・トンネルなど見通しが悪い区間
- 対向車との衝突リスクが高い場所
- 交通量の多い幹線道路
禁止される行為
- 黄色線を越えて追越し・右折・転回すること
(※右折専用レーンなど例外を除く)
つまり黄色線は「危険だから越えてはいけない線」。
安全確認ではなく、法的に“物理的な境界”として扱う線なのです。
片側だけ黄色/もう片側が白いセンターラインの意味
ときどき見かける、「片側が黄色・もう片側が白」のセンターライン。
これは片側だけが追越禁止区間であることを意味します。
例
- 黄色側:追越し禁止
- 白側:追越し可
つまり、見通しの良い下り坂側(白線)は越えてOK、
見通しの悪い上り坂側(黄色線)は越えてNG、
というように、道路条件に応じて一方通行的に設定されています。
破線と実線の組み合わせにも意味がある
センターラインは「色」だけでなく「線の形」でもルールが異なります。
| 表示タイプ | 意味 |
|---|---|
| 白の破線 | 追越し・車線変更OK |
| 白の実線 | 原則として車線変更NG(区分線) |
| 黄色の実線 | 対向車線への越え禁止(追越し禁止) |
| 黄色+白の複合線 | 一方方向のみ追越し禁止 |
このように、色と線種の組み合わせで交通ルールを細かく伝えているのです。
なぜ黄色が「禁止」なのか?──視認性と国際基準の理由
黄色が採用されているのは、単に目立つからではなく、国際的な安全色の規格に基づいています。
- 黄色は「警告」「注意」を示す色(ISO安全色)
- 白線に比べて夜間や雨天でも視認しやすい
- 反射材を使うことでライト照射時に強く浮かび上がる
つまり黄色線は、危険を強調するための“視覚的な警告信号”なのです。
センターラインの維持コストと塗り分けの工夫
センターラインは数年ごとに塗り直されますが、
黄色線は反射材や高耐久塗料を使用するためコストが高めです。
そのため、必要な場所だけに限定して使われています。
また、積雪地域では雪で線が見えにくくなるため、
キャッツアイ(反射ポール)やカラー舗装で補助表示を行う場合もあります。
まとめ:黄色線は“注意喚起”ではなく“法的なストップサイン”
道路のセンターラインが黄色と白で分かれているのは、
- 白線:通行区分のみ(越えてもOK)
- 黄色線:追越禁止・越えてはいけない
- 複合線:一方向のみ禁止
という明確なルールに基づくものです。
つまり、黄色線は単なる「注意線」ではなく、
交通事故を防ぐための“法的な境界線”なのです。
見通しや地形条件に合わせて色分けされており、
道路設計の現場では、安全データに基づいた設計意図がしっかり存在します。