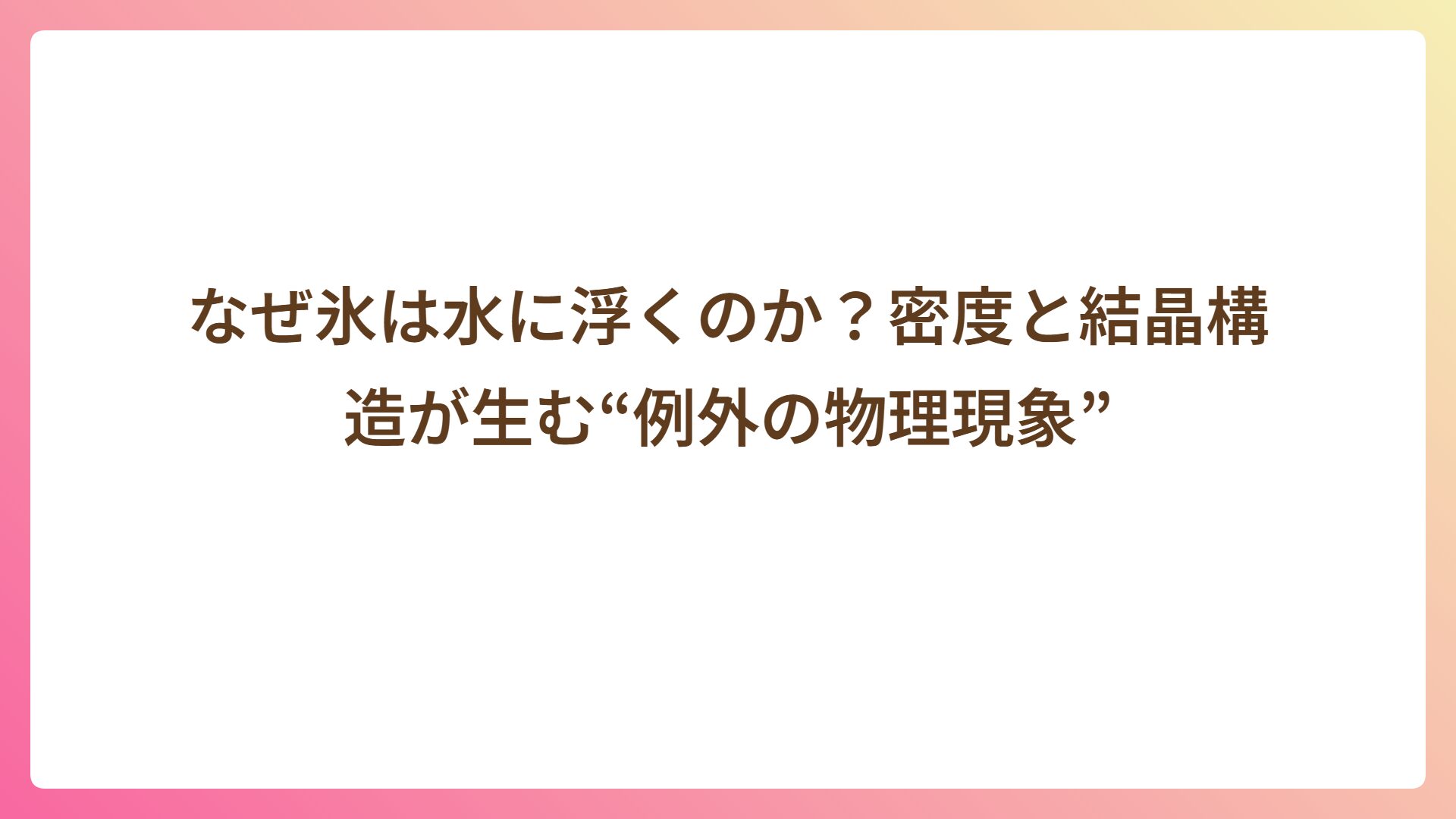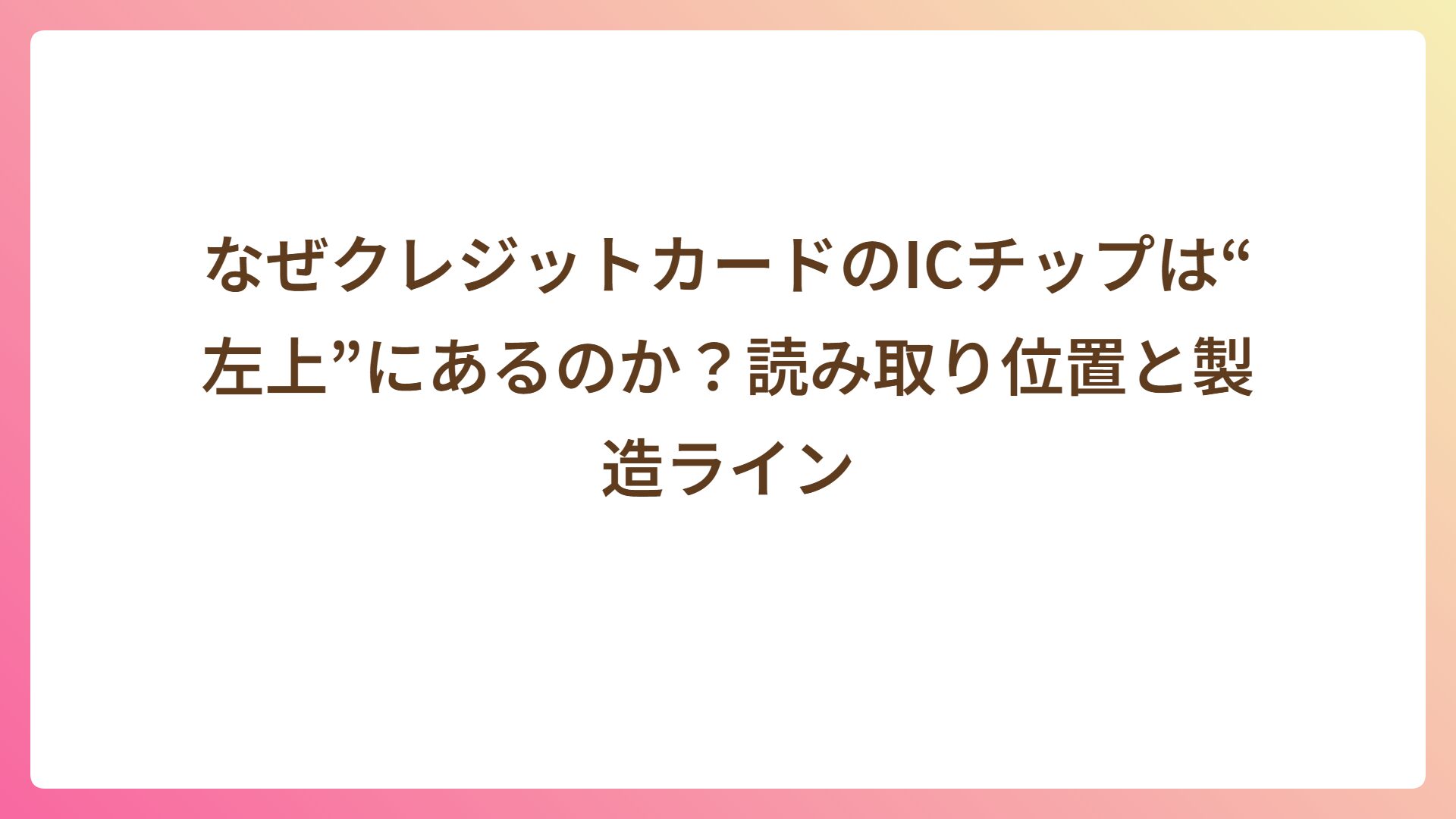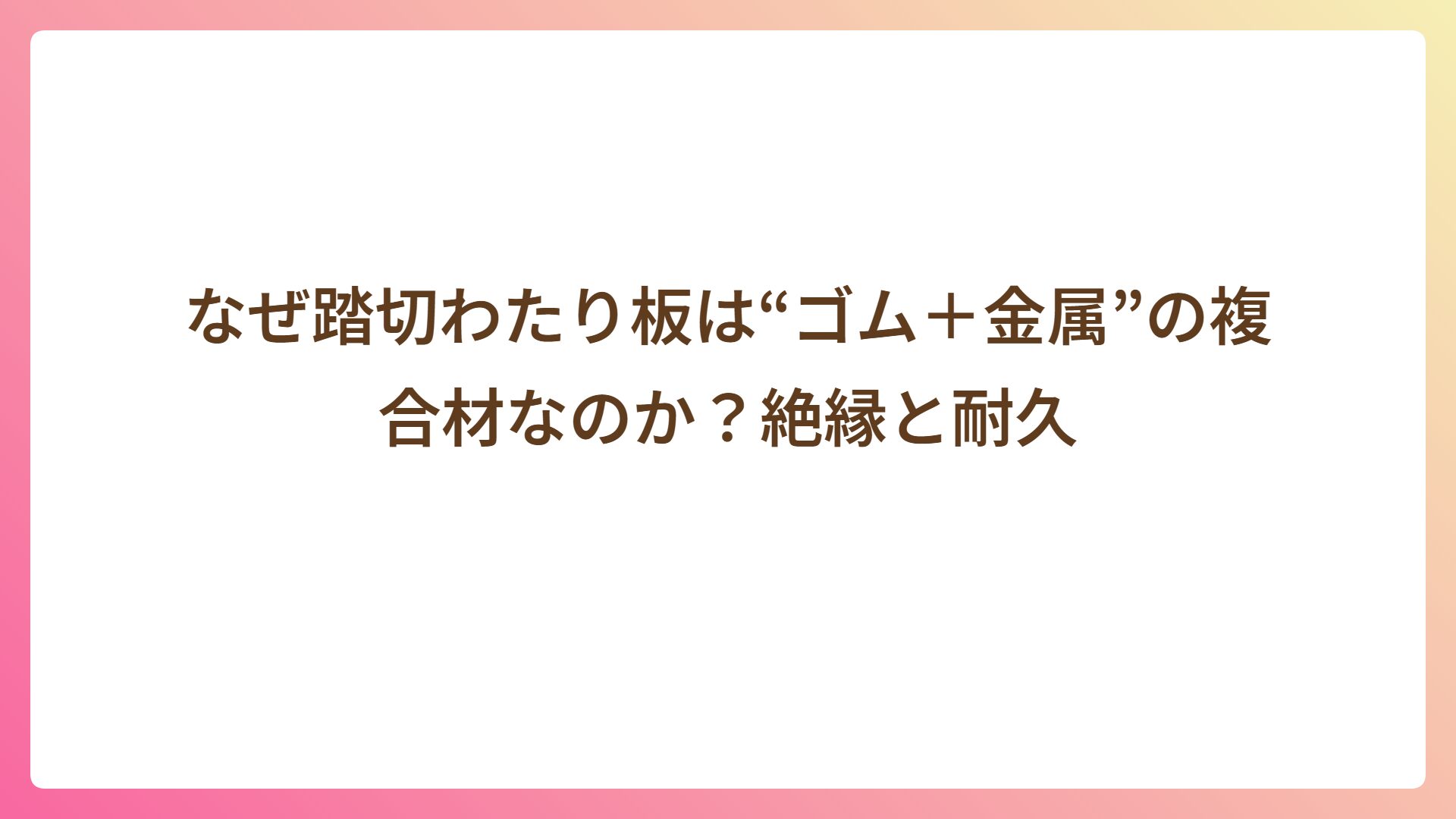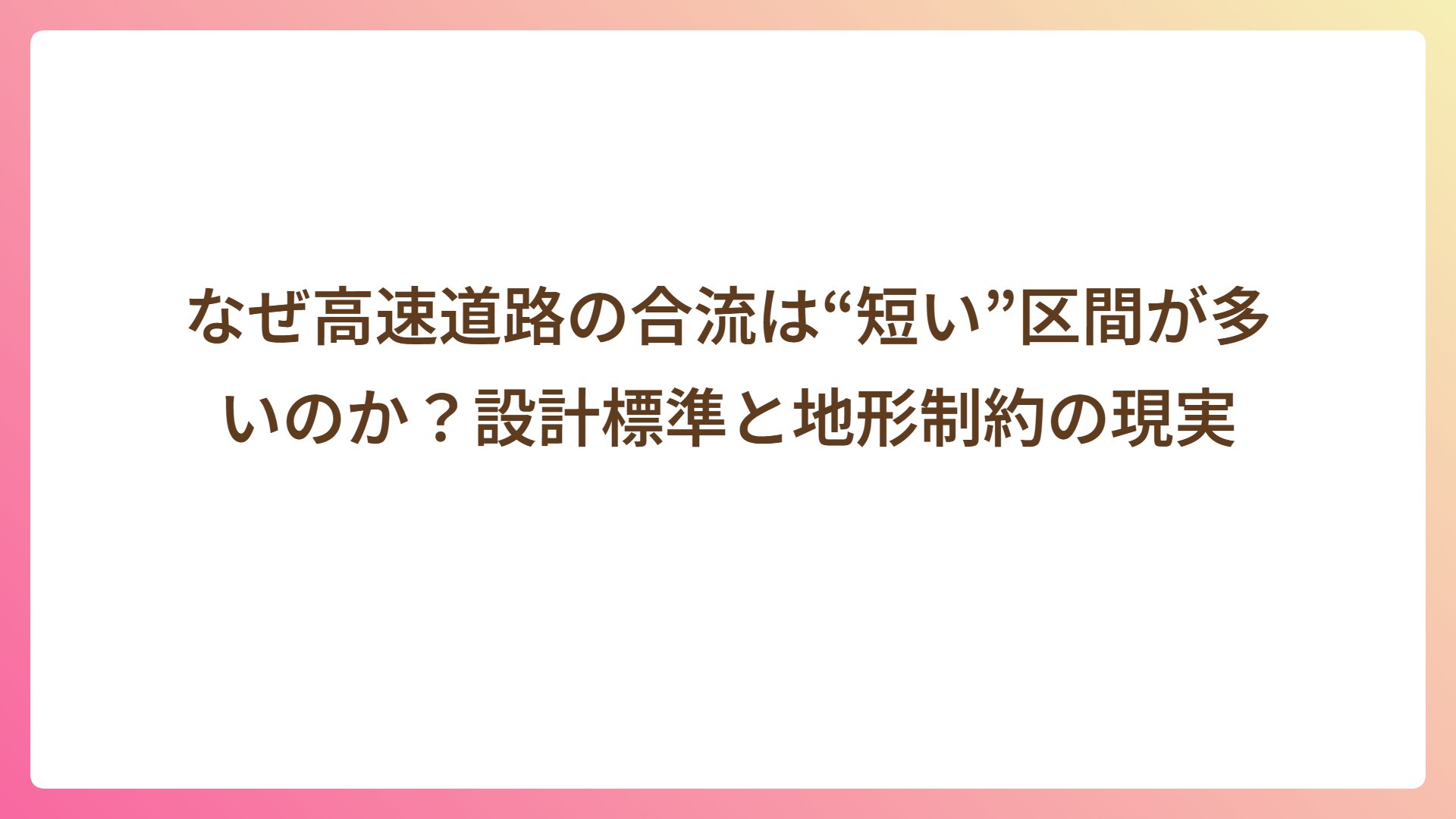なぜ団子は“三色”が定番化したのか?季節と配色の民俗学
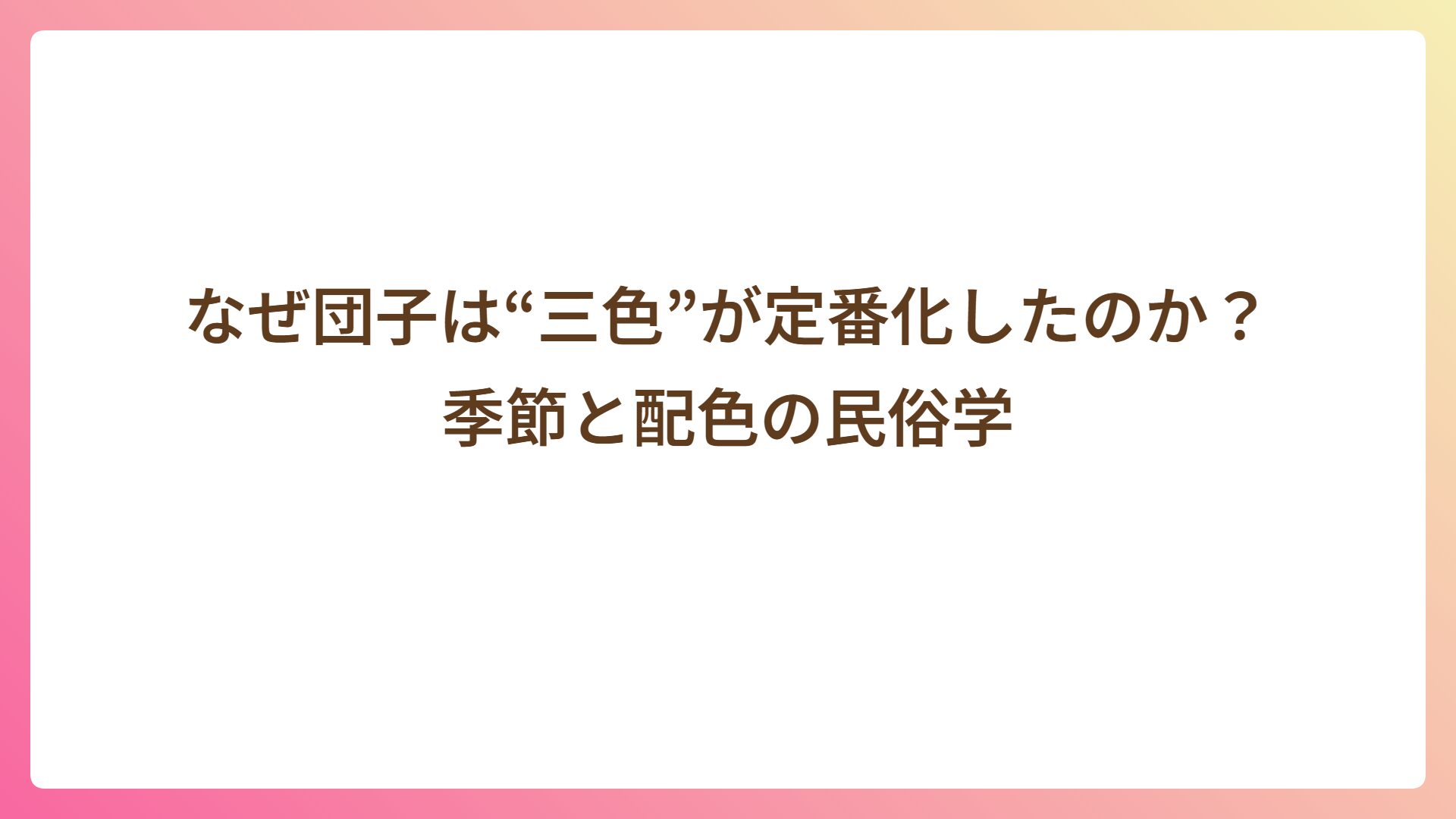
花見や行楽シーズンになると必ず目にする「三色団子」。
赤(桃色)・白・緑の三つの色が並ぶ姿は、見た目にも華やかで日本の春を象徴するお菓子です。
しかし、なぜ“三色”が当たり前になったのでしょうか?
その背景には、季節の象徴色と古来の色彩思想が隠れています。
三色団子のルーツは「花見団子」
三色団子の原型は、江戸時代に広まった「花見団子」といわれています。
当時の江戸では、上野や隅田川などで桜の花見が一大行事となり、
屋台では手軽に食べられる串団子が人気を集めました。
桜の花を模した赤(桃色)・白・緑の色づかいは、
春の景色そのものを表現するもの。
桜=赤、残雪=白、新芽=緑というように、
自然の移ろいを三色で象徴した和の色彩表現だったのです。
赤・白・緑 ― 日本人が好む“縁起の三原色”
三色団子の色には、それぞれ意味があります。
- 赤(桃色):生命力・魔除け。桜や桃の花に通じる春の色
- 白:清浄・純粋。冬の雪を思わせる潔白の象徴
- 緑:成長・再生。新芽や若草を表す生命の象徴
この三色は、古くから神事や祝儀の場でも使われてきた縁起の配色です。
鏡餅の紅白や柏餅の緑の葉などにも共通するように、
日本人は自然とともに「色」で季節と生命の循環を感じ取ってきたのです。
陰陽五行と三色のバランス
中国の陰陽五行思想では、
赤=陽・火、白=陰・金、緑=木を象徴し、
この三色を組み合わせることで天地自然の調和を表すとされました。
団子の三色は、この思想を日本流に取り入れたものともいわれます。
つまり、三色団子は単なる彩りではなく、
“自然と調和した幸福”を願う配色なのです。
“四季”ではなく“春”に特化した理由
三色団子が春に定着した理由は、
「桜=日本の象徴」「団子=手軽な花見食」の結びつきにあります。
実は「秋は四文屋(しもんや)」「春は団子屋」と呼ばれたほど、
江戸では季節によって人気の屋台が変化していました。
春は桜の名所で団子を売るのが最も繁盛し、
その際に季節感を出すために春色の三色団子が考案されたのです。
こうして、三色団子=花見=春というイメージが全国に広がりました。
「三色団子に四季の意味を込めた説」も
一方で、近年では「三色団子は四季を象徴する」とする説もあります。
- 桃色:春の花
- 白:冬の雪
- 緑:夏の草
そして「秋がない」=「(飽き)ない」団子、として縁起を担ぐ語呂合わせも有名です。
これは後世の俗説ですが、縁起物としての定着を後押ししました。
現代にも生きる“見て楽しむ和菓子の色”
三色団子は、食べる前にまず「見る」ことを楽しむ和菓子。
鮮やかな配色は、花見の席だけでなく、
日常の中で季節を感じる小さな風景を提供してくれます。
特に現代では、季節感を視覚で伝える文化が再評価され、
三色団子は「日本の色感覚を象徴するお菓子」として愛され続けています。
まとめ
団子が三色になったのは、
春の自然を象徴する色彩表現と、縁起・思想・美意識の融合によるものです。
赤=春の息吹、白=冬の余韻、緑=命の芽吹き。
この三色には、
“自然とともに生きる日本人の感性”が今も息づいているのです。