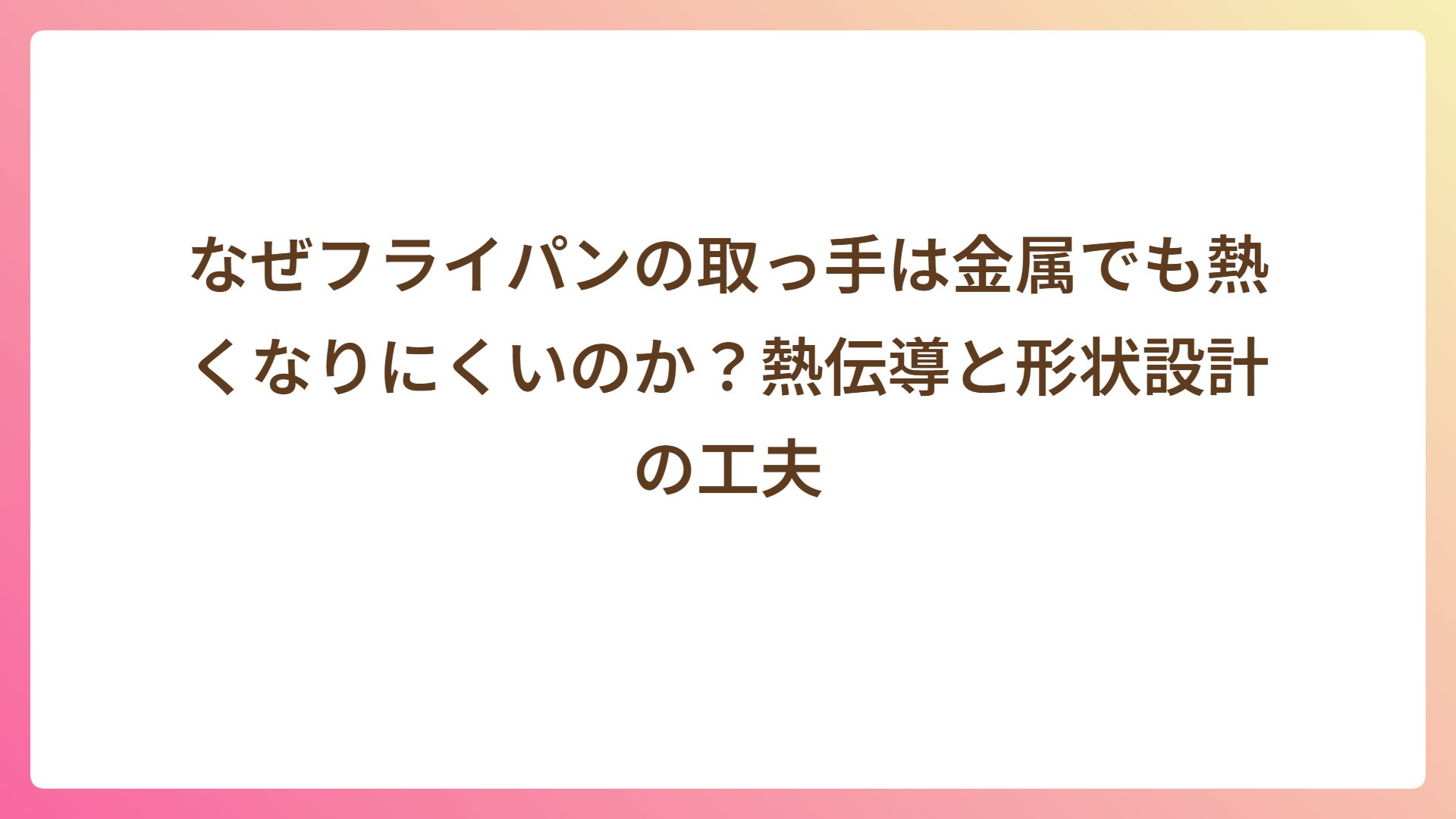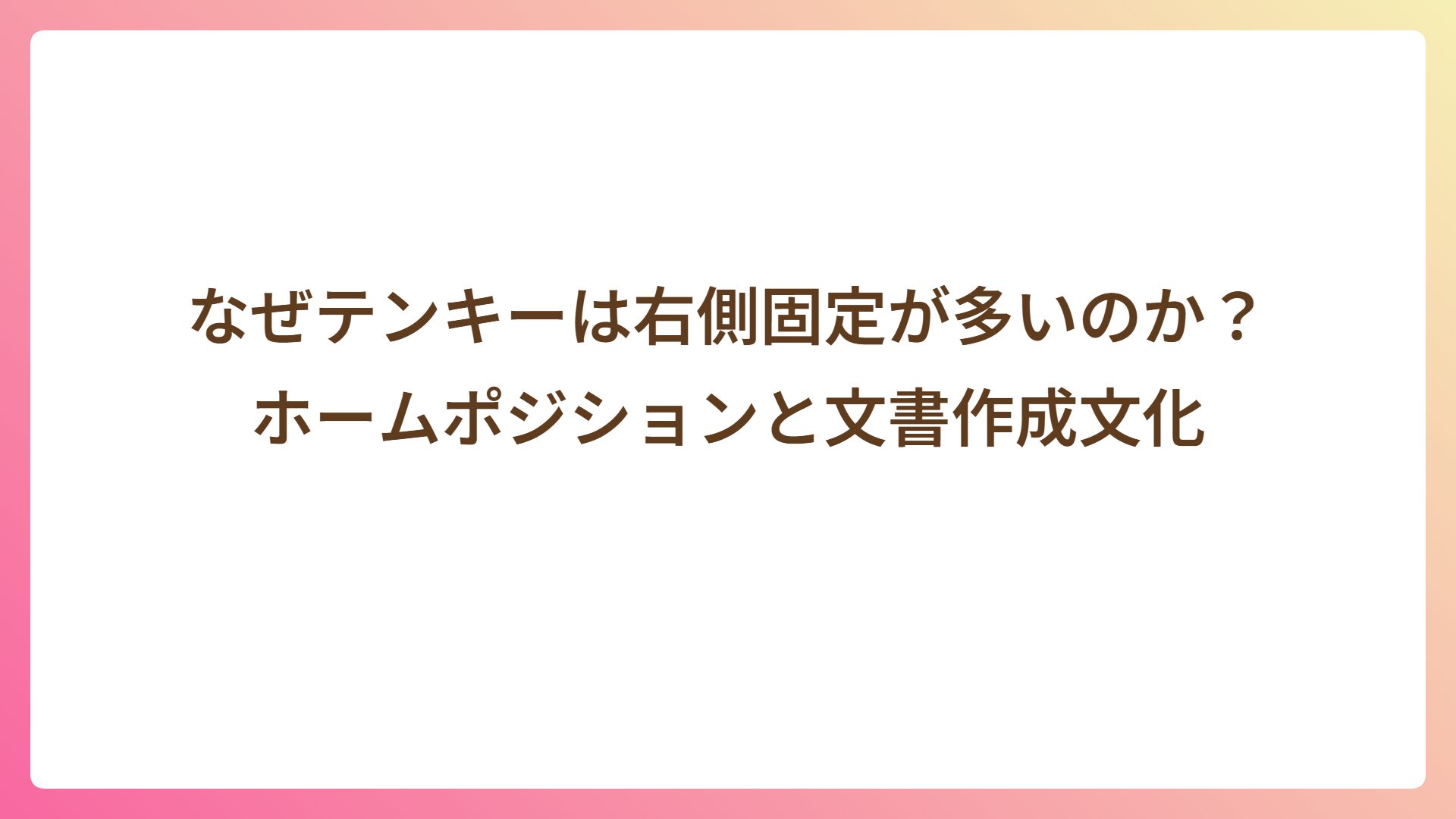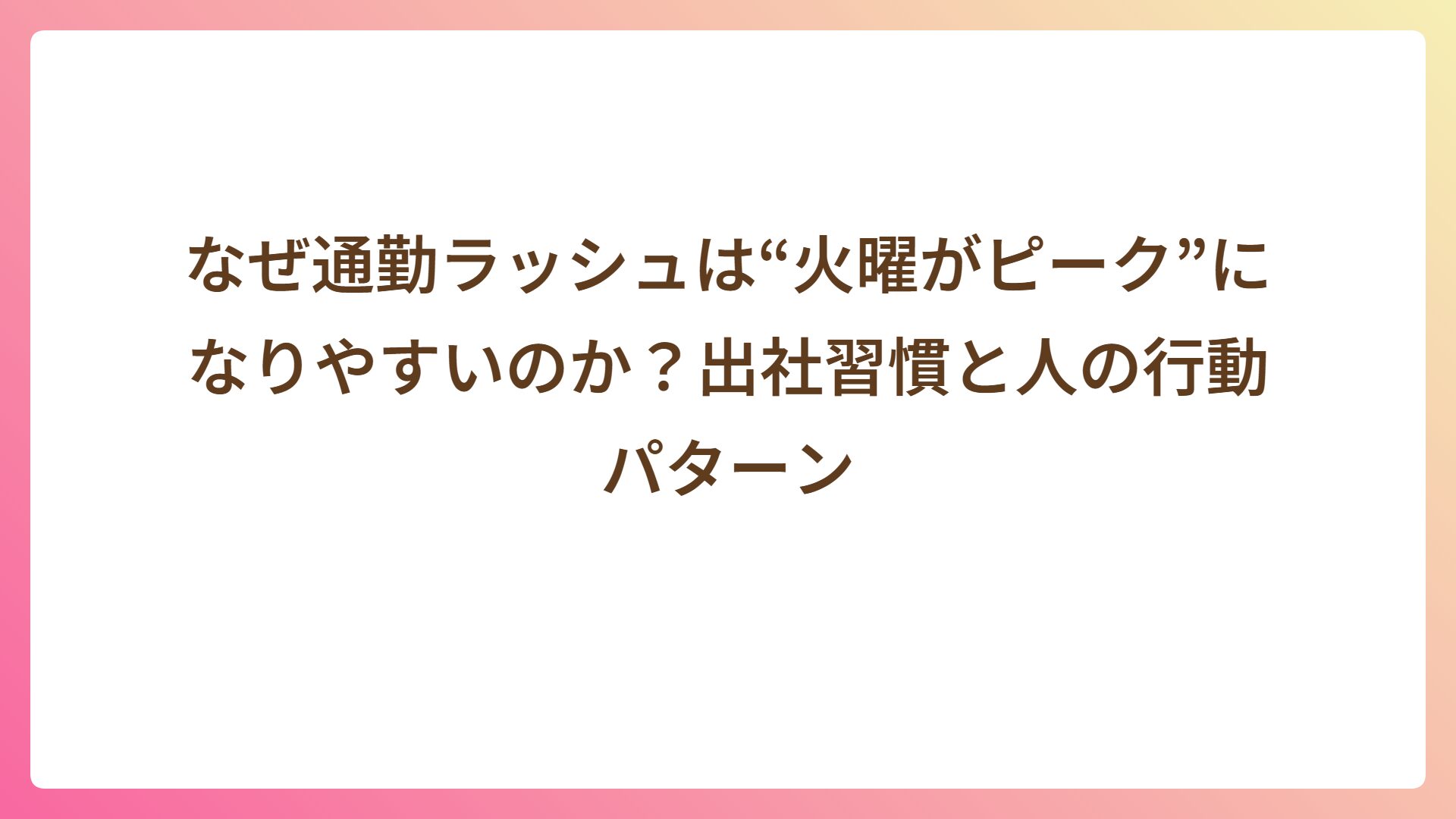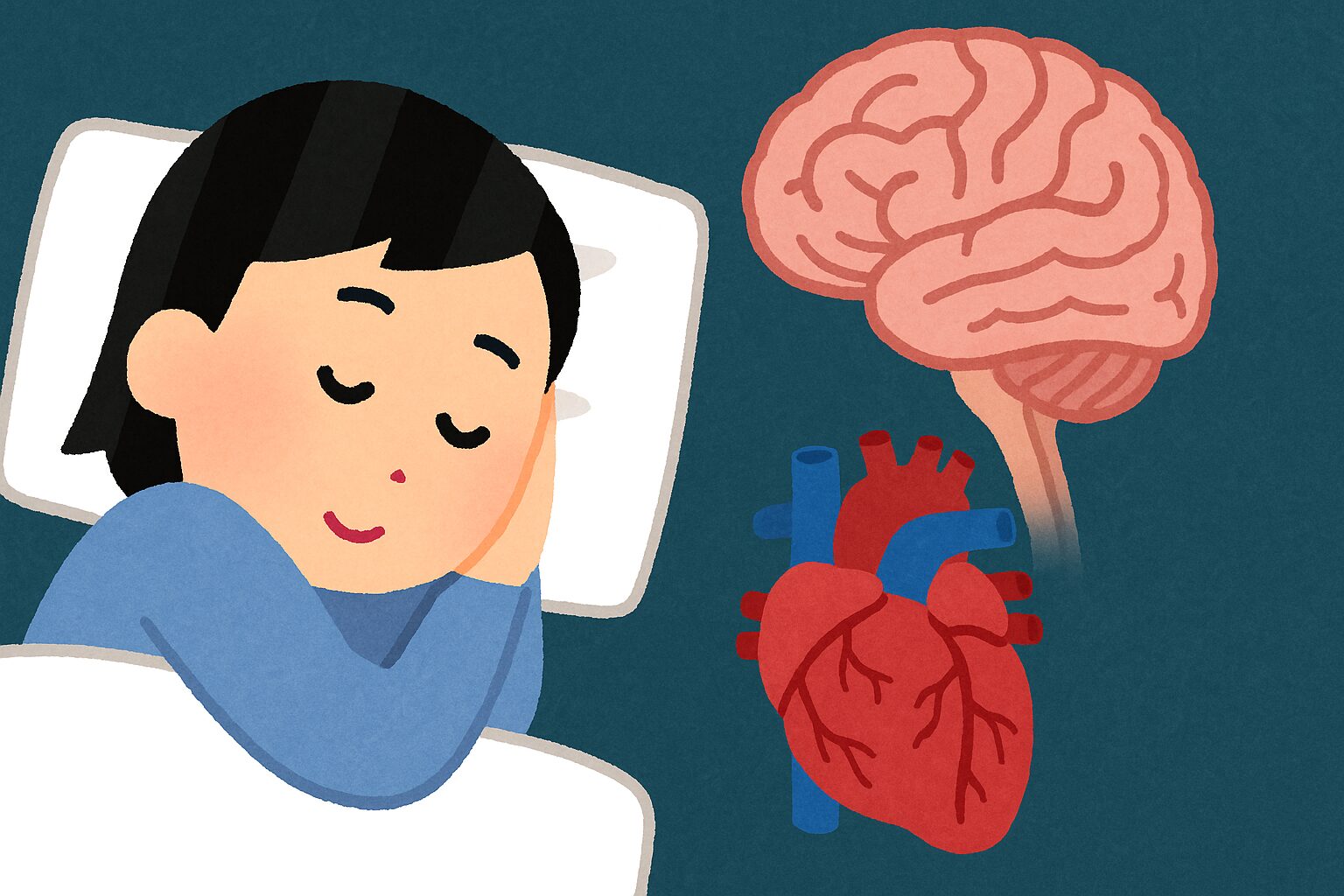なぜ電車の車両間には“蛇腹”があるのか?連結可動と気密保持の仕組み
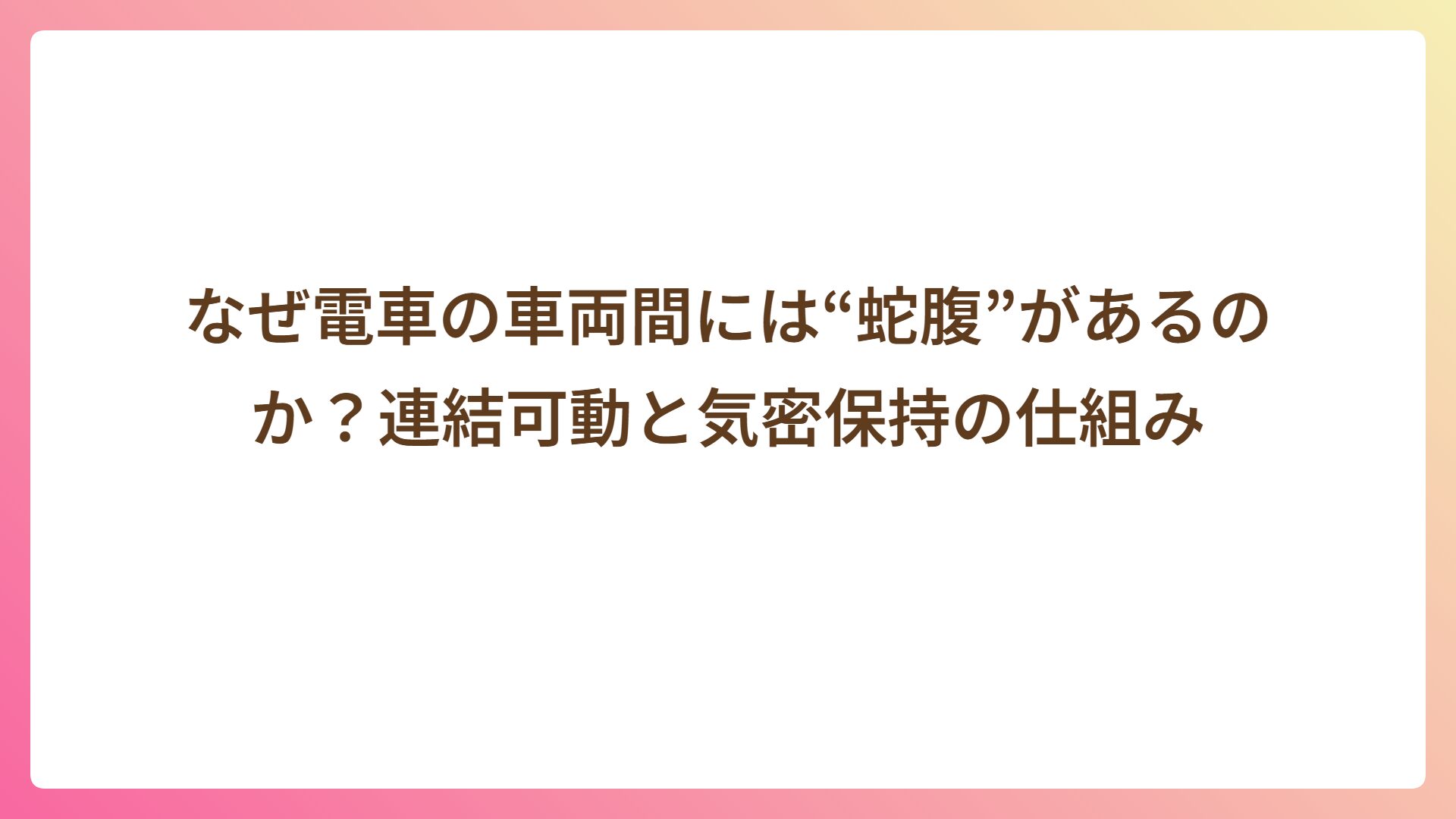
電車の車両と車両の間には、アコーディオンのように伸び縮みする蛇腹(じゃばら)が設けられています。
普段は気にせず通り抜けていますが、なぜわざわざこのような構造になっているのでしょうか?
実は蛇腹は、電車がカーブを曲がるための可動性と、車内の気密・防音性を維持するための重要な部品なのです。
この記事では、電車の車両間に蛇腹がある理由を、構造・安全・快適性の観点から解説します。
理由①:車両同士が“自由に動けるようにする”ため
電車は直線だけでなく、カーブや勾配を通過します。
しかし、車両は金属製で硬いため、連結部分にはある程度の可動性が必要です。
実際、電車の車両は連結器(自動連結器)でつながれており、
- 前後方向にわずかに伸縮
- 左右方向に首を振る
といった動きを許容しています。
このとき、車両間を覆う蛇腹は、
- その動きに合わせて柔軟に伸び縮み
- すき間をふさぐ役割
を果たしており、車体の動きと空間の密閉性を両立しているのです。
理由②:車両間の“隙間風・騒音”を防ぐため
蛇腹のもう一つの大きな役割は、車内の気密性・静粛性の確保です。
蛇腹がない状態だと、
- 外気が入り込み、冷暖房効率が悪化
- 風切り音や軌道音が車内に侵入
- 車両間を通過する際に風圧が発生
といった不快要因が発生します。
蛇腹で連結部を覆うことで、
- 気圧差や風を遮断
- 騒音を軽減
- 安定した温度環境を維持
という快適な車内空間を実現しているのです。
理由③:“連結部を通れるようにする”ための通路保護
蛇腹は、車両間を乗客が安全に移動できるようにする通路カバーでもあります。
もし蛇腹がなければ、
車両間は金属のジョイントと隙間だらけで、
- 足元が不安定
- 転落や挟まれ事故の危険
があります。
蛇腹とその内側の床板(渡り板)によって、
- 足元のすき間をなくし、安定して歩ける
- 風雨や車外の騒音を遮断できる
- 緊急時にも安全に通行可能
という安全通路の確保が行われています。
理由④:トンネル内の“気圧変動”に対応するため
新幹線や地下鉄などでは、トンネルを高速で通過する際に急激な気圧変化が起きます。
もし車両間が完全に密閉されていなければ、
- 空気が車両間を通って“風の通り道”になる
- 「ドンッ」という気圧ショック音が発生
といった現象が起きてしまいます。
蛇腹によって連結部を覆うことで、
- 気圧差の伝わりを緩和
- 車両全体を一体的な気密空間として保つ
ことができ、耳への圧力負担を軽減する効果もあるのです。
理由⑤:可動部を“外部環境から守る”カバーとして
連結器や空気ホース、ケーブル類など、車両間には多くの重要機器が通っています。
蛇腹はこれらを雨・雪・砂埃などから保護する外装カバーの役割も果たしています。
とくに高速運転では、
- 車両下部に巻き上げられる粉塵
- 雨天時の水しぶき
が激しく衝突するため、蛇腹がそれらを防ぐことで、機器の劣化を防止しています。
理由⑥:素材は“耐久性と柔軟性”のバランス設計
蛇腹は単なるゴムではなく、
- 耐候性ゴム
- 合成樹脂
- 金属フレーム入り布(布入りゴム)
などを複合した多層構造になっています。
この構造により、
- 長期間伸縮しても破れにくい
- 夏冬の温度差でも劣化しにくい
- 防音・防水性能を維持
といった高耐久で柔軟な特性を発揮しています。
理由⑦:新幹線などでは“二重蛇腹構造”で気密性を強化
高速走行する新幹線や特急列車では、
車両間の気圧や騒音をさらに抑えるために、
二重構造の蛇腹(内外二重カバー)が採用されています。
- 外側:防風・防水・気圧対策
- 内側:防音・温度保持・通行安全
これにより、高速走行中でも静かで快適な車内を維持できるようになっています。
まとめ:蛇腹は“安全・快適・密閉”を守る可動カバー
電車の車両間に蛇腹があるのは、
- 車両の動きに合わせて伸縮し、隙間をふさぐため
- 風・騒音・気圧差を遮断するため
- 乗客が安全に通行できる通路を作るため
- 雨や埃から連結部を保護するため
といった安全性と快適性を両立する構造設計のためです。
つまり、あのアコーディオンのような蛇腹は、
電車を“つなぎながら密閉する”ための精密な工学部品なのです。