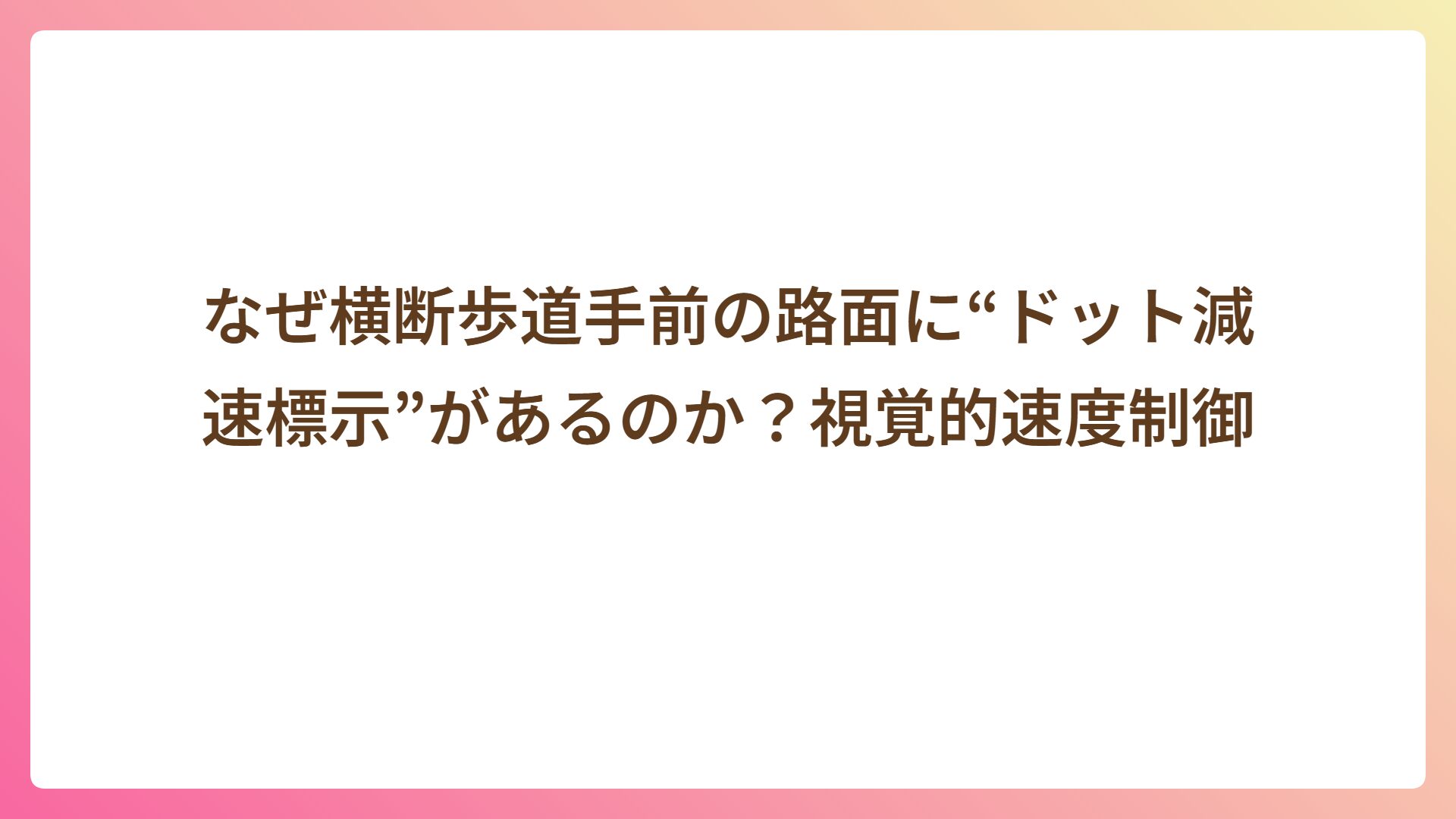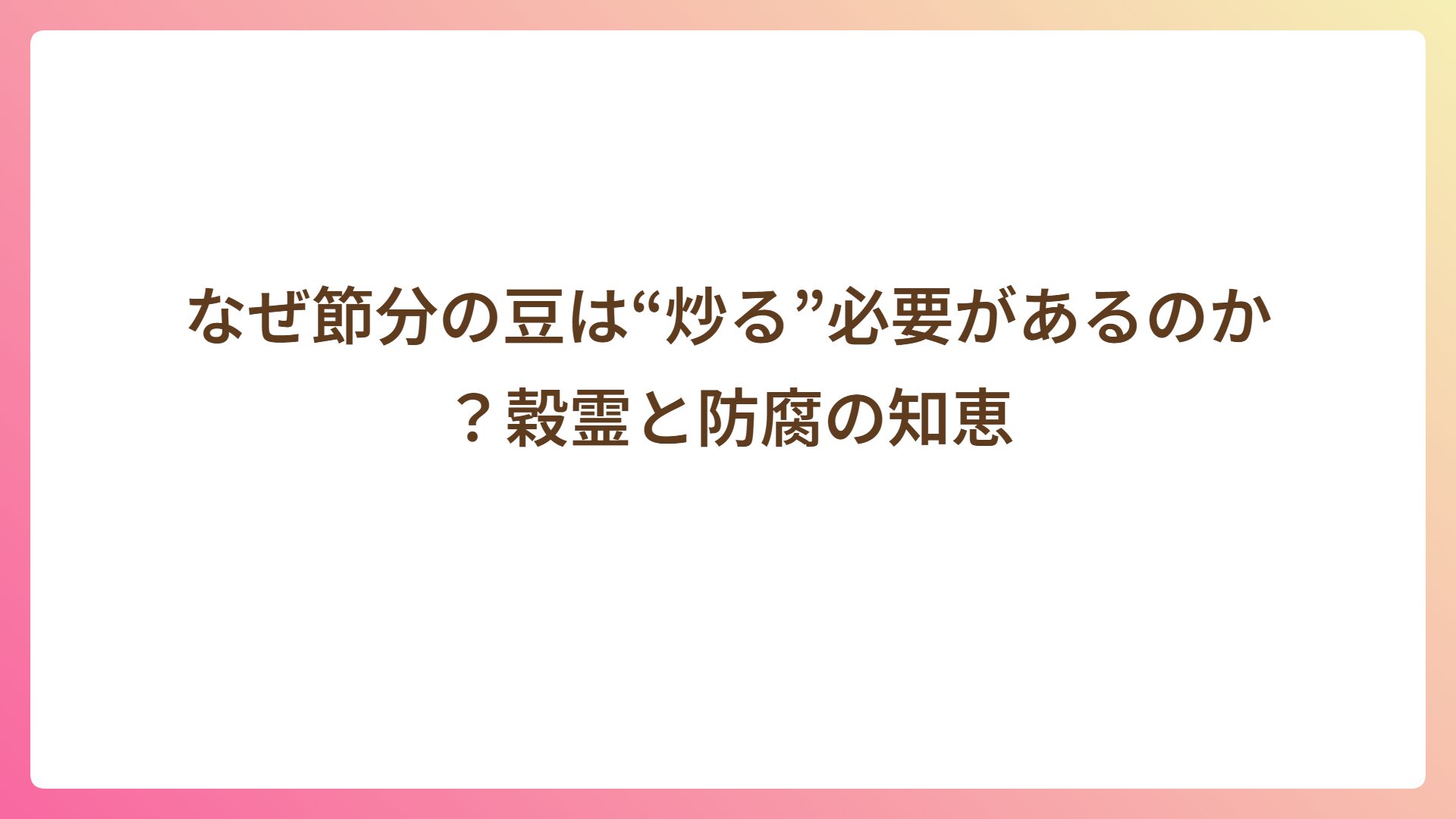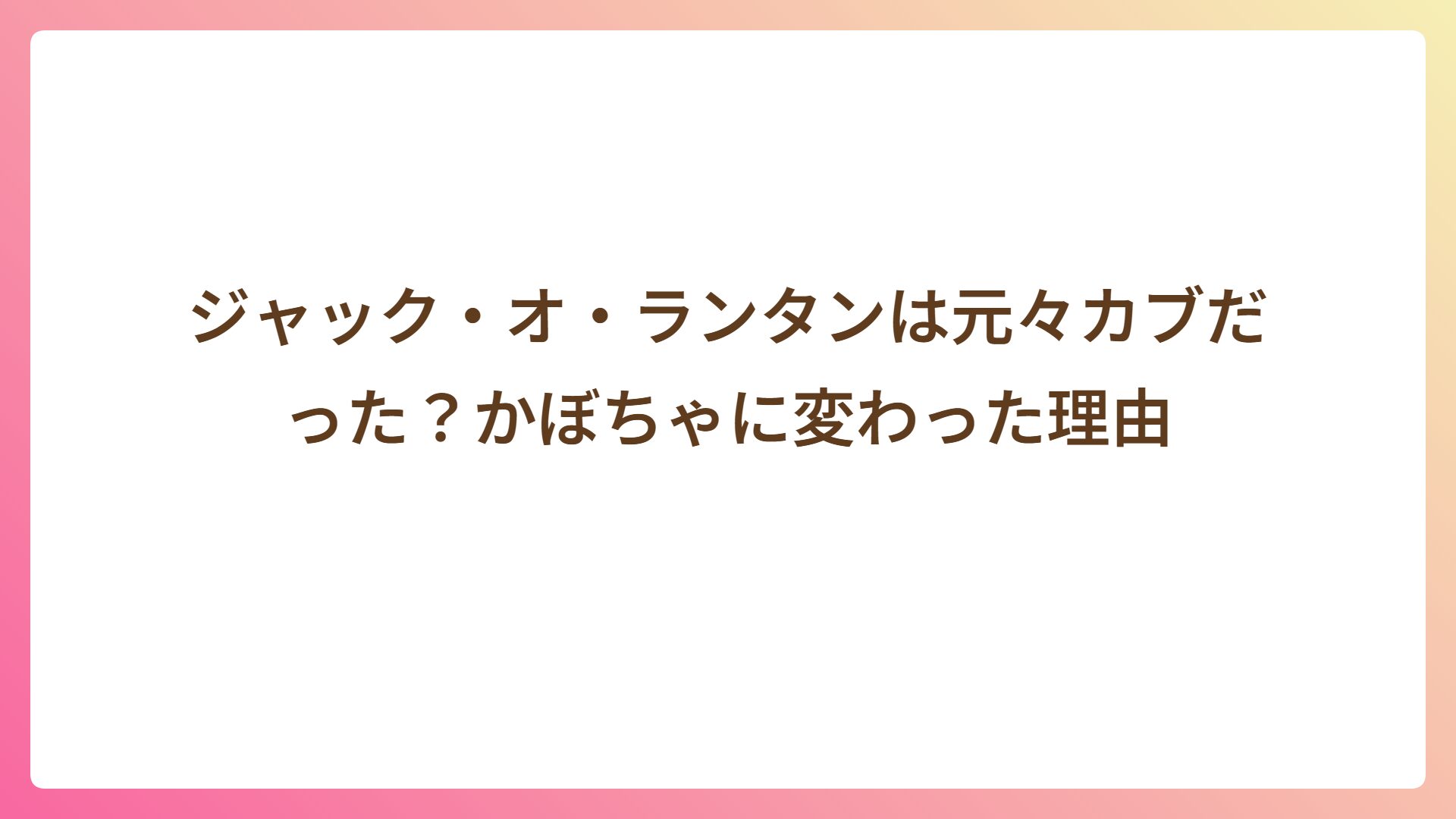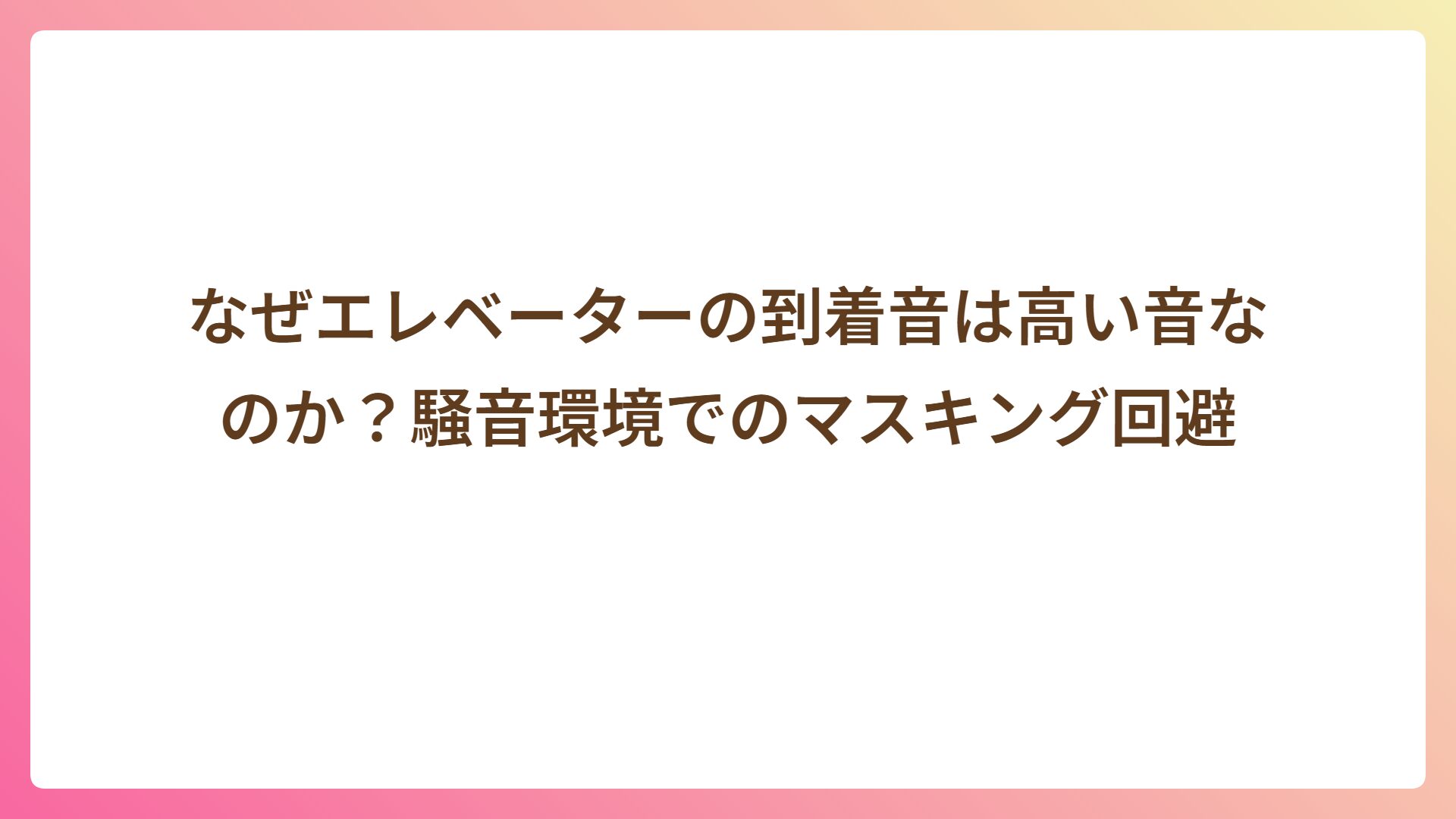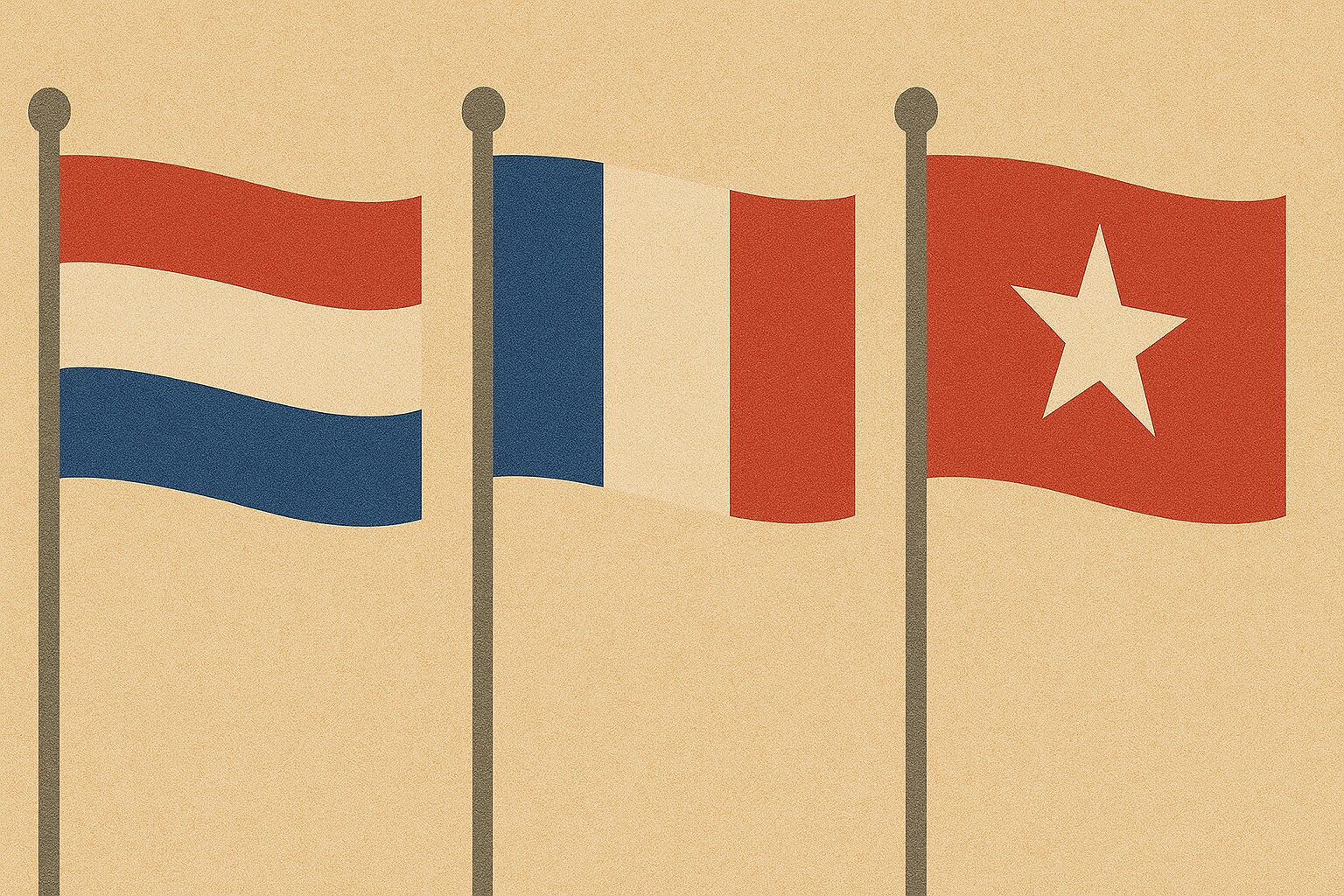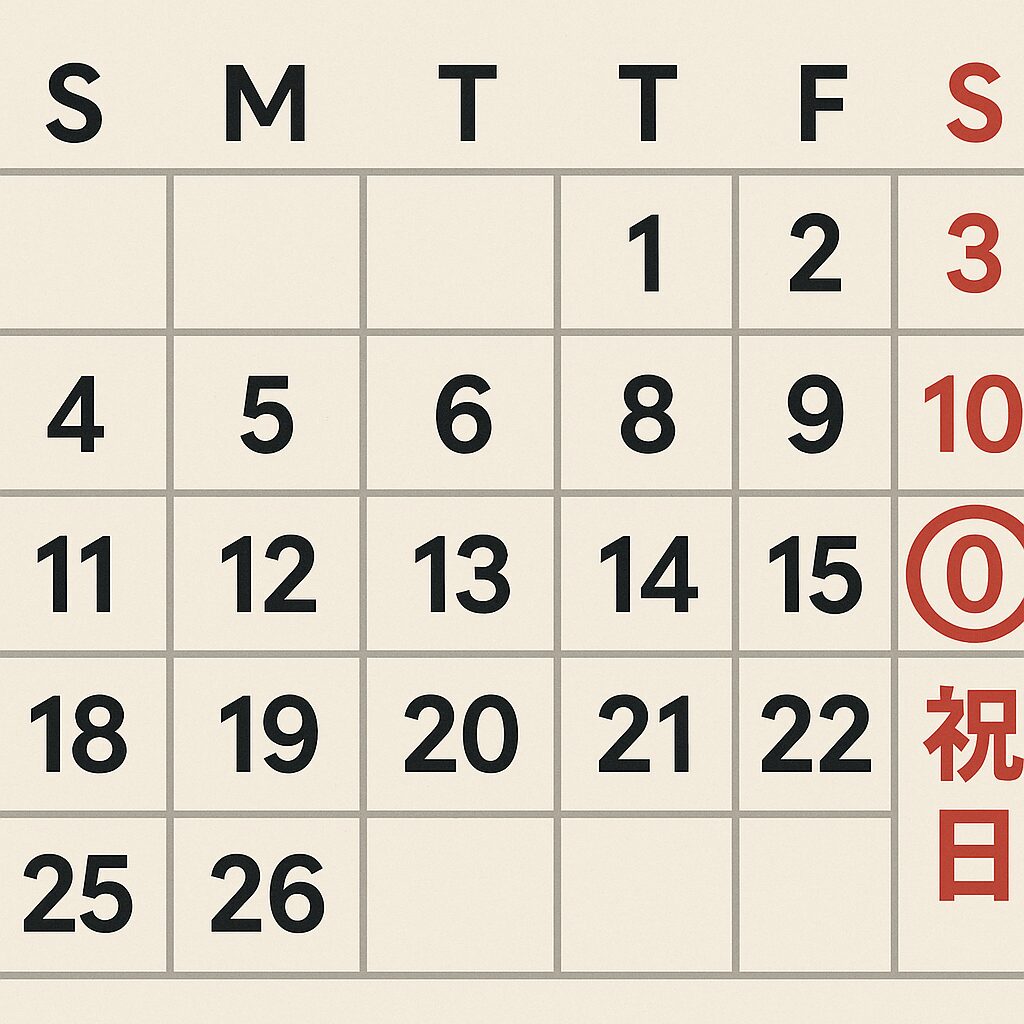なぜ土用の丑に鰻を食べるのか?キャッチコピーと養生文化
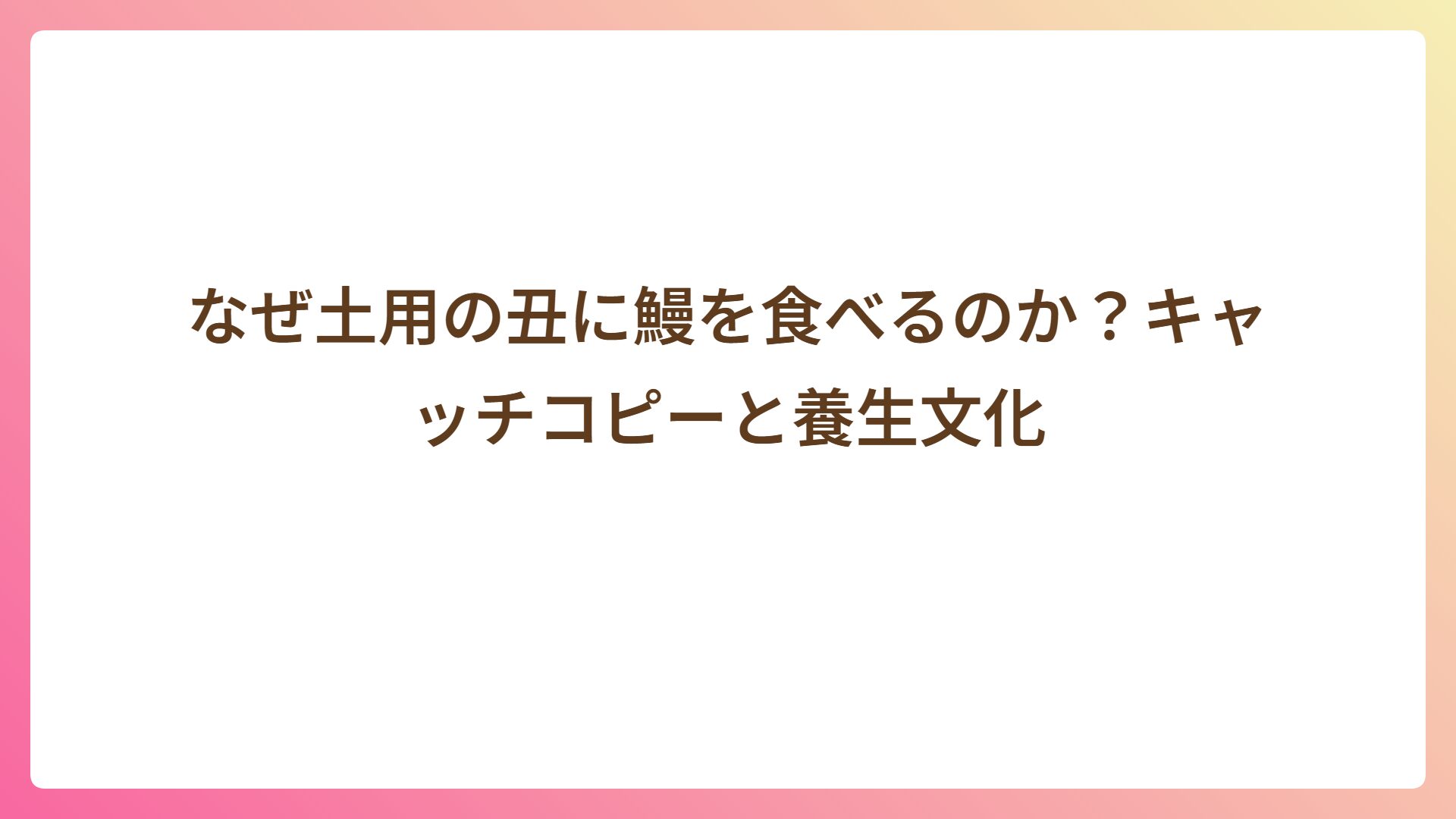
「土用の丑の日には鰻を食べよう」——。
夏の風物詩としてすっかり定着していますが、
なぜこの日に鰻を食べるようになったのでしょうか?
実は、江戸時代のマーケティングと古代の養生文化が結びついた結果なのです。
“土用”とは季節の変わり目を意味する
まず、「土用」とは「立春・立夏・立秋・立冬」の前の約18日間を指す言葉です。
古代中国の五行思想(木・火・土・金・水)に基づき、
季節の切り替えには「土」が中心になると考えられたため、
この期間を「土用」と呼びました。
つまり、土用は一年に4回あり、
私たちが思い浮かべる“夏の土用の丑の日”は、
そのうち立秋前の最も暑い時期を指しています。
この厳しい季節に食欲を失わないよう、
体を養う食事をとる風習が生まれました。
それがのちに「鰻」に結びついていくのです。
“丑の日”と“う”のつく食べ物
「丑の日」とは、十二支の丑(うし)にあたる日のこと。
昔は日付にも十二支が割り当てられており、
この日に“う”のつく食べ物を食べると夏負けしないという俗信がありました。
うどん、梅干し、瓜(うり)などがその代表で、
その一つが「うなぎ」だったのです。
つまり、“う”の語呂合わせと夏バテ防止の発想が結びついたのが出発点でした。
平賀源内が仕掛けた“キャッチコピー戦略”
江戸時代中期、夏に鰻が売れず困っていた鰻屋が、
博学者・平賀源内に相談したのが転機でした。
源内は「本日、土用の丑の日」と書いた看板を掲げ、
「丑の日に“う”のつく食べ物を食べると縁起が良い」という俗信を利用。
これが評判を呼び、鰻屋は大繁盛。
この仕掛けが口コミで広まり、
「夏の土用=鰻を食べる日」という習慣が庶民の間に定着したとされています。
つまり、土用の鰻の起源は、
江戸のキャッチコピー戦略による販促キャンペーンだったのです。
鰻は“夏の滋養強壮食”でもあった
もっとも、ただの宣伝で終わらなかったのは、
鰻が実際に栄養価の高いスタミナ食だったからです。
鰻にはビタミンA・B群・D・Eが豊富に含まれ、
脂質も多く、疲労回復や食欲増進に効果的。
当時の庶民は肉を日常的に食べなかったため、
鰻はまさに“夏バテ防止のご馳走”でした。
また、江戸の食文化では「陰陽のバランス」を重んじ、
暑さ(陽)に対して脂ののった鰻(陰)を食べることで体調を整える、
という東洋的な養生思想にも合致していたのです。
“食べる風習”が“文化”に変わるまで
平賀源内の宣伝以降、
「鰻=土用のスタミナ源」というイメージは次第に定着し、
明治期には新聞広告や商標にも使われるようになりました。
やがて昭和に入り、電気冷蔵の普及とともに鰻が通年食べられるようになると、
夏だけの特別感がむしろ“伝統”として強調され、
「土用の丑=鰻」という食文化の象徴へと昇華していったのです。
まとめ
土用の丑に鰻を食べるのは、
平賀源内による宣伝が、養生思想と時代の健康意識に結びついた結果です。
- 「丑の日に“う”のつく食べ物」=語呂合わせの縁起
- 鰻=夏バテ防止・栄養満点の滋養食
- 広告コピーが食文化へと昇華
つまり、鰻の風習は単なる商売の工夫にとどまらず、
健康と季節を大切にする日本人の“養生の知恵”が形になったものなのです。