なぜ焼酎は“白麹・黒麹・黄麹”で味が変わるのか?クエン酸と香味生成
mixtrivia_com
おもしろサッカーデータ
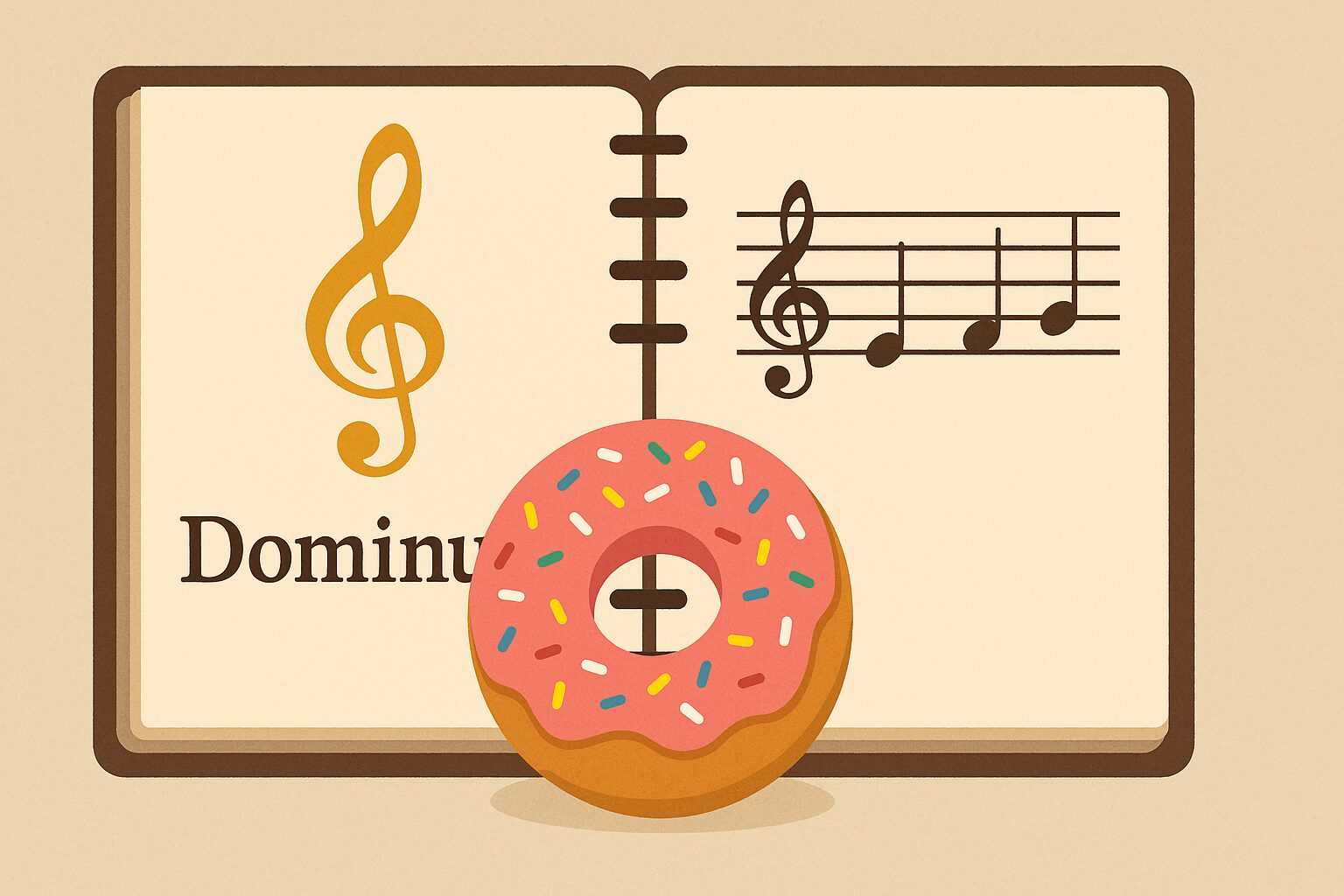
『ドレミの歌』でおなじみの「ドはドーナツのド」。しかし実際には、音名の「ド」はドーナツとは関係がありません。本当の由来をたどると、1000年前のヨーロッパにまでさかのぼることができます。
世界で最も広く使われる階名「ドレミファソラシド」はイタリア語です。
たとえば「ハ長調」の「ハ」は、この日本語式の階名から来ています。
「ドレミ」の起源は、11世紀の修道士グイード・ダレッツォが編み出した学習法にあります。彼は聖歌『聖ヨハネの賛歌』の歌詞から、それぞれの音の出だしの音節を取り出しました。
このようにして音の高さを覚えるための「音階」が生まれたのです。
もともと「ド」は「Ut」と呼ばれていました。しかし発音しづらいため、ラテン語で「主」を意味する **Dominus(ドミヌス)**の頭文字を取り、現在の「Do(ド)」が定着しました。
また「シ」は当初存在せず、しばらくは6音(ド〜ラ)だけの「ヘクサコルド」で音楽が作られていました。やがて聖歌の最後「Sancte Iohannes(聖ヨハネ)」の頭文字から「Si」が加えられ、今の7音体系となりました。
「ドはドーナツのド」というのはあくまで歌の中の覚え方であり、実際の由来はDominusのド。
由来を知れば、「ドレミファソラシド」がただの音の並びではなく、1000年以上の歴史を持つ仕組みであることがわかります。友達が歌っていたら、ぜひ雑学として教えてあげましょう。