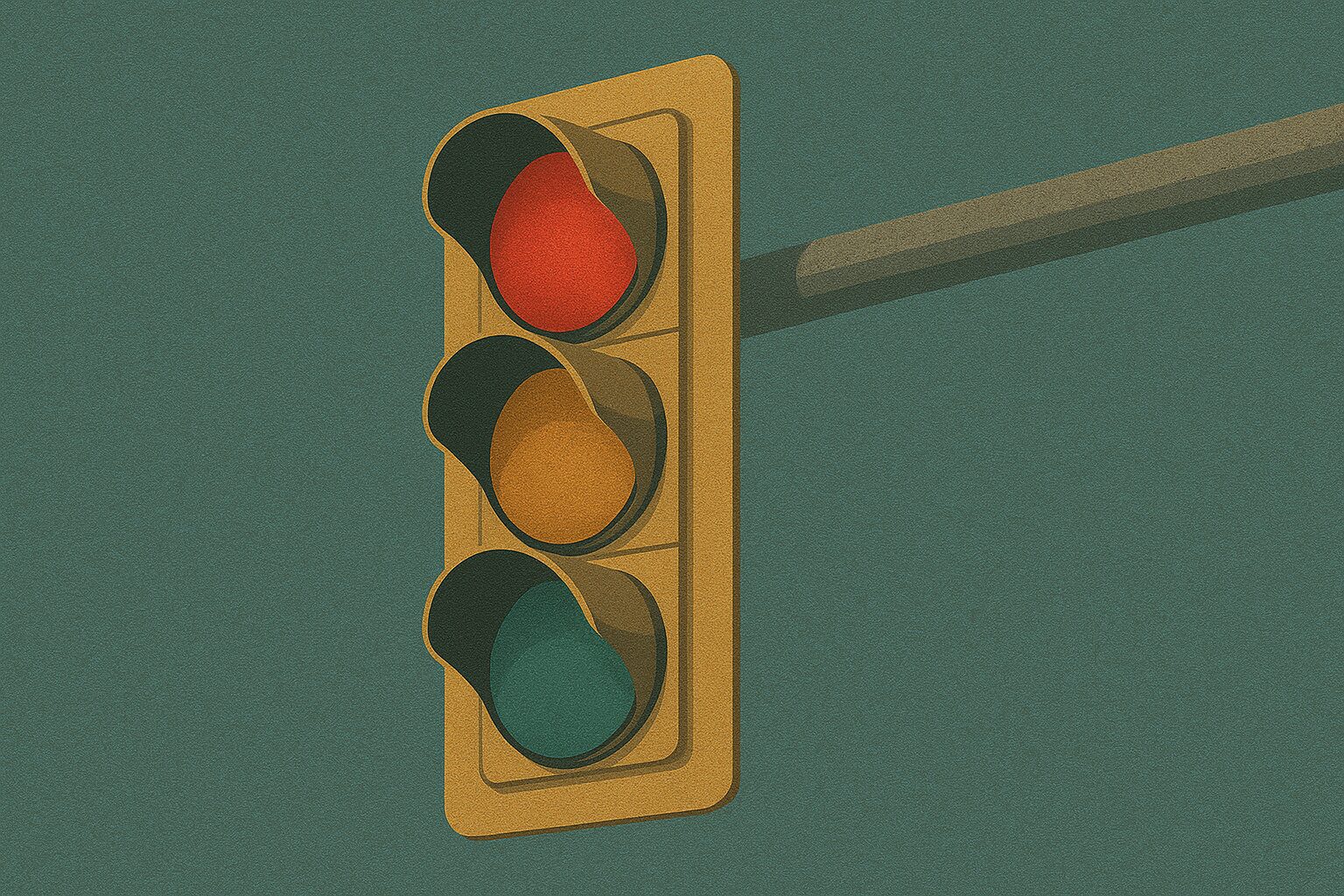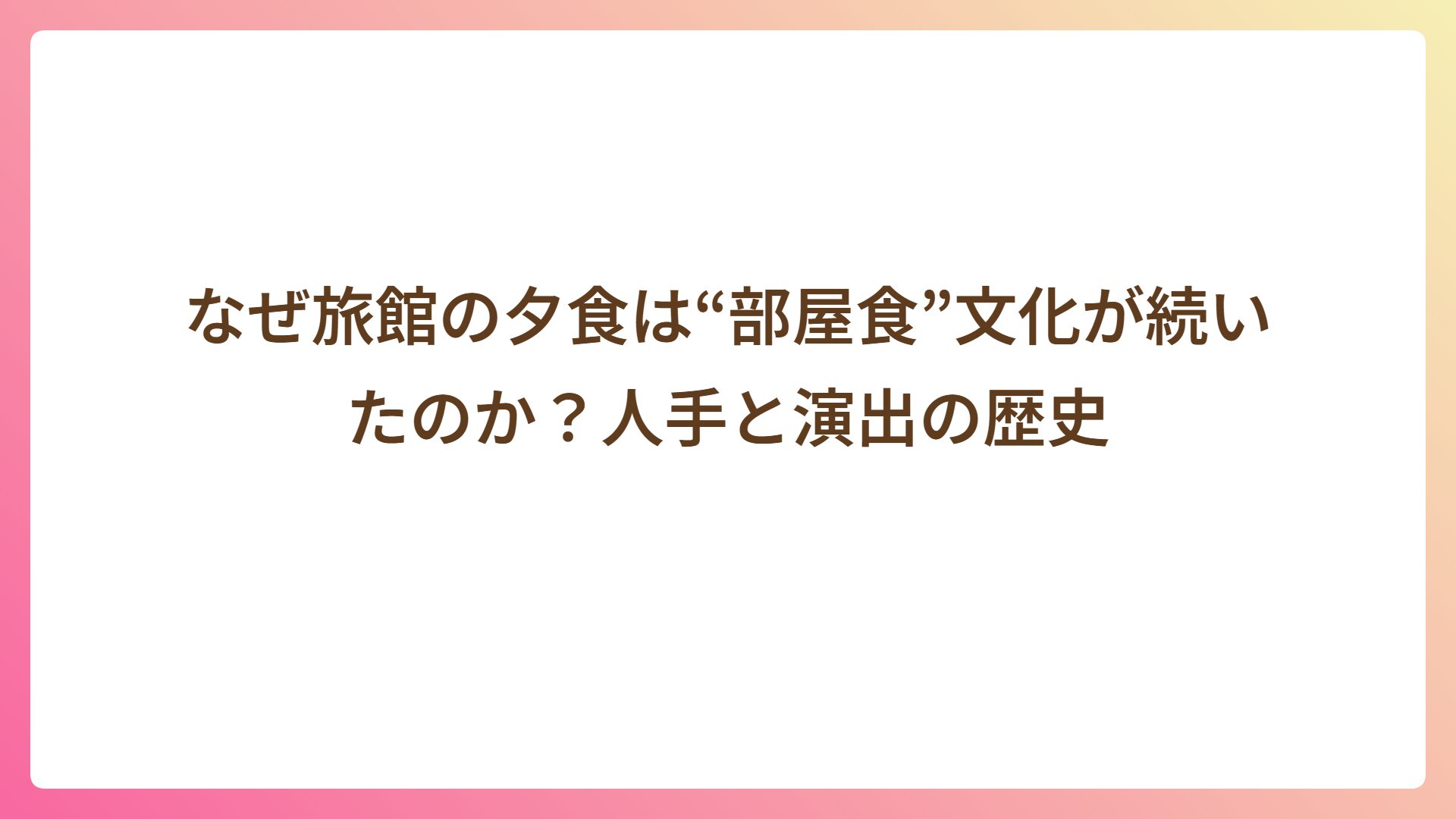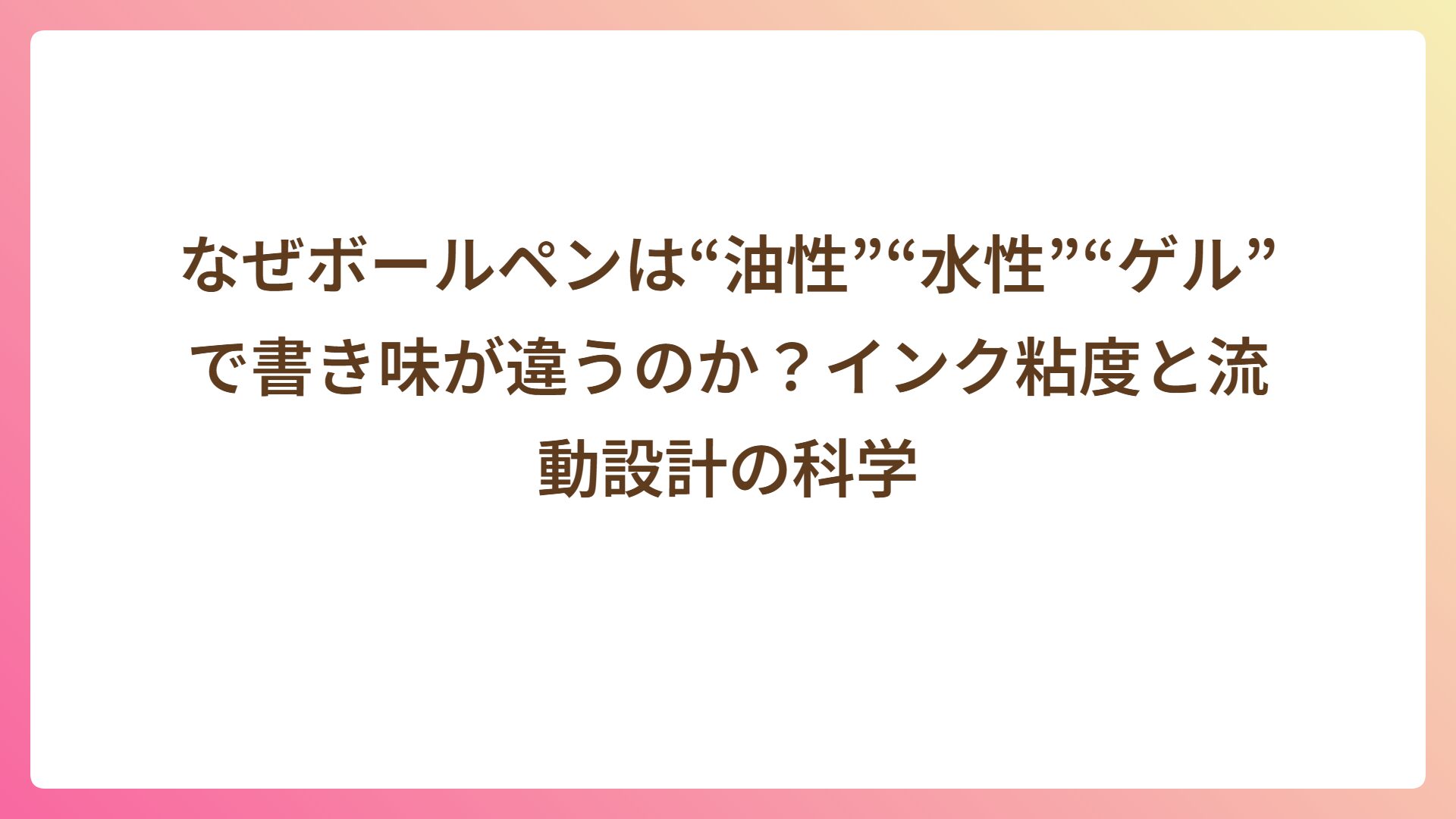なぜイヤホンは右側だけケーブル長が違った時代があったのか?首回りと摩擦音
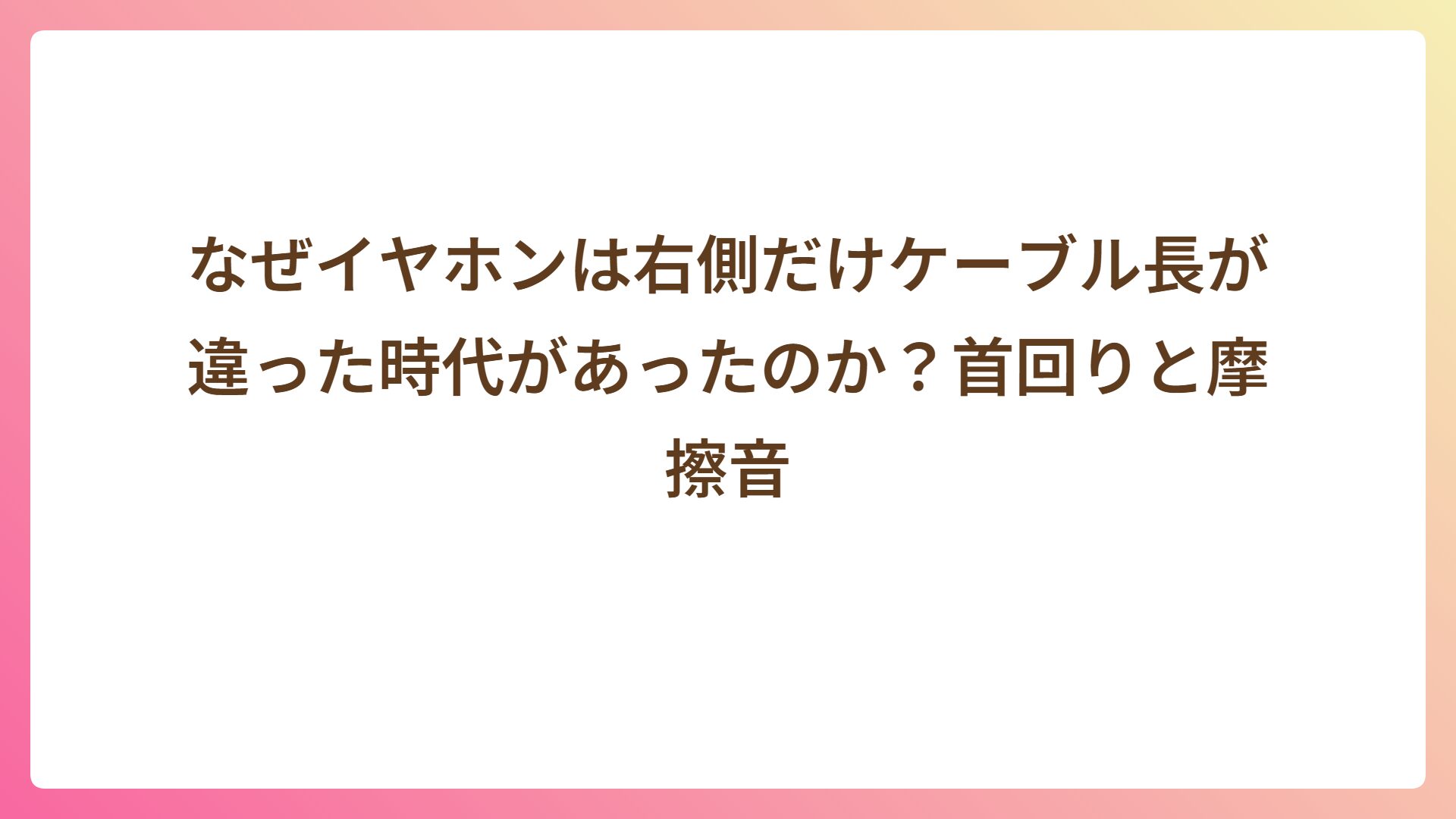
2000年代前半のイヤホンを思い出すと、右側のコードが長く、左側が短い「アシンメトリー(Y字)」型が多く見られました。
現在では左右が同じ長さの「U字」型が主流ですが、なぜ昔のイヤホンはわざわざ右側だけ長く作られていたのでしょうか?
首の後ろを回す「ネックホルダー方式」だった
右側のケーブルが長い設計は、首の後ろを回して装着するためのものでした。
当時はポータブルCDプレーヤーやMDプレーヤーを胸ポケットやバッグに入れて使う人が多く、ケーブルが前方に垂れると邪魔になりやすかったのです。
そこで、左の短いケーブルを耳にかけ、右の長いケーブルを首の後ろから回すことで、ケーブルが身体に触れにくく、動作中も安定するよう工夫されていました。
これが、いわゆる「片出し風デザイン(J字型)」と呼ばれる時代の主流構造です。
ケーブル同士の摩擦音(タッチノイズ)を防ぐ
イヤホンのケーブルは服や肌に擦れると、「ガサガサ」というタッチノイズが発生します。
左右のケーブルが胸元で擦れると特に耳障りになりやすいため、右側を長くして左右が重ならないようにすることで、この摩擦音を低減できました。
また、首の後ろにケーブルを通すことで、歩行時や通勤時の揺れによるノイズも軽減され、外出向けイヤホンとして最適な構造だったのです。
リモコン付きイヤホンやスマホ普及で構造が変化
スマートフォンが登場すると、リモコン付きマイクを備えたイヤホンが一般化しました。
このとき、マイクを操作しやすいように左右対称のU字構造が求められ、右だけ長い設計は徐々に姿を消しました。
さらにBluetoothイヤホンの普及により、ケーブルそのものが不要になったことで、「右長」デザインは完全に過去のものとなりました。
まとめ
イヤホンの右ケーブルが長かったのは、
首の後ろを通すための安定構造と、摩擦音を減らすための工夫によるものでした。
便利さと快適さを両立させるための設計だった「右長スタイル」。
今では見かけなくなりましたが、音楽プレーヤー全盛期の時代を象徴する、合理的なデザインの名残だったのです。