なぜ「○藤」という名字は多いのか?藤原氏との意外なつながり
mixtrivia_com
MixTrivia
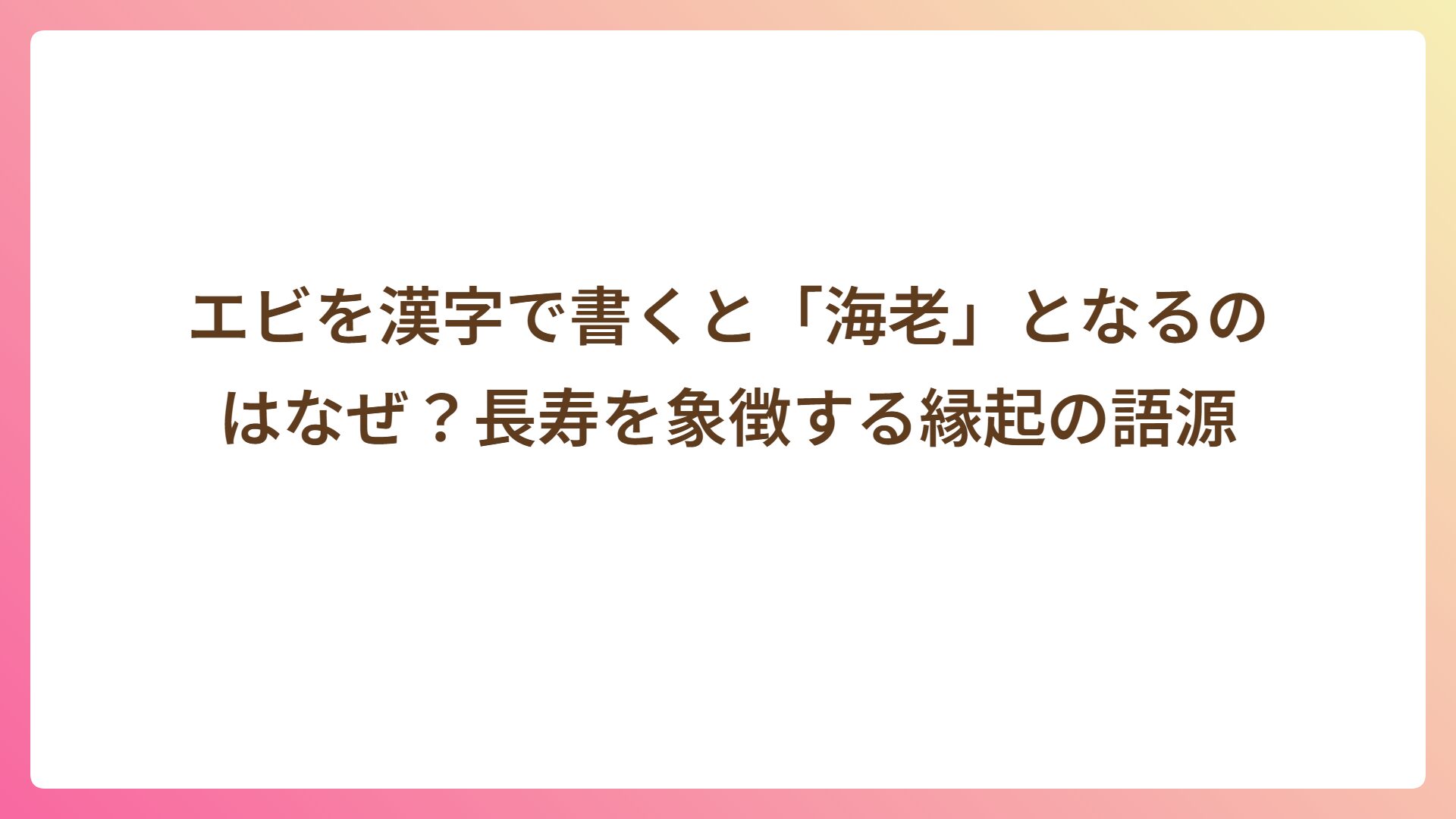
寿司ネタや年末年始の料理などでおなじみのエビ。漢字では「海老」と書きますが、実はこの表記は中国由来の正確な漢字ではなく、日本で生まれた当て字です。なぜ“海の老い”という少し不思議な字があてられたのでしょうか。
エビを「海老」と書く理由の第一は、その姿のたとえにあります。
エビは体を丸め、長いヒゲを持つことから、まるで腰の曲がったお年寄りのように見えることから「老(おい)」の字が使われました。
そして海に生息しているため、そこに「海」を加えて「海老」となったのです。
つまり、「海にいる老人のような姿の生き物」という見た目の比喩から生まれた表記です。
日本では古くから、長寿を象徴する生き物としてエビが親しまれてきました。
おせち料理にエビが入っているのも、「腰が曲がるまで長生きできるように」という願いを込めてのことです。
このような縁起の良い意味づけから、「老」という字が敬意と祝意の象徴として定着しました。
つまり「海老」という漢字には、単に形の比喩だけでなく、長寿祈願の文化的背景も含まれているのです。
もともと中国ではエビを「蝦」と書き、日本語でも古くはこの字が使われていました。
しかし日本では、「海老」の方が意味が分かりやすく、縁起が良いとされたため、一般的に広まっていきました。
その結果、現在では「蝦」は学術名や外来語表記(例:小蝦=エビの幼生)などで残り、「海老」は日常語・食文化の文脈で使われるようになっています。
エビを「海老」と書くのは、見た目の特徴と縁起を合わせた日本独自の当て字です。
海に住み、腰の曲がった姿が長寿を連想させる――そんなポジティブな願いが込められた言葉。
単なる生物名ではなく、幸福や長寿を象徴する文化的なシンボルとして定着したのが、「海老」という漢字なのです。