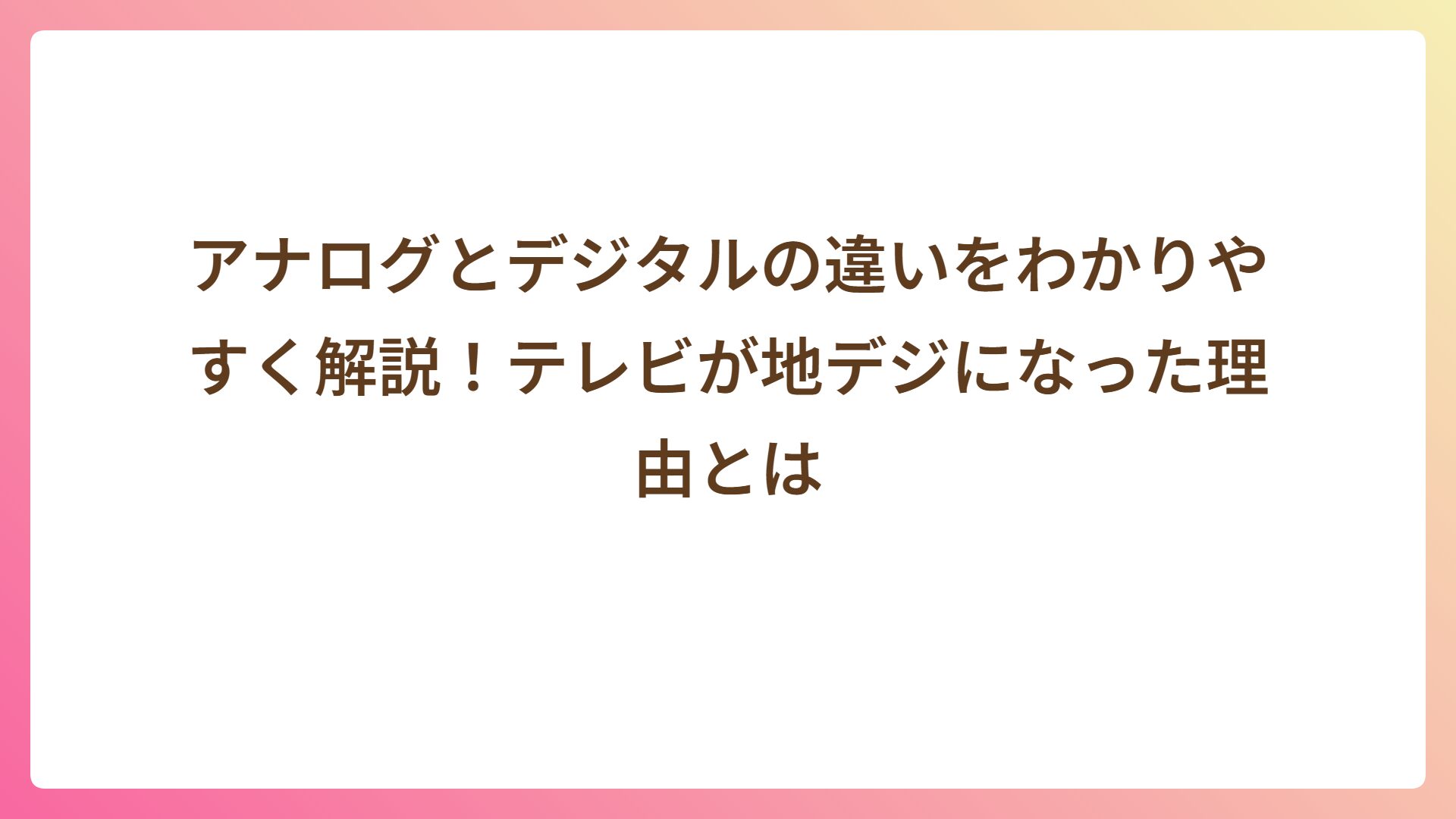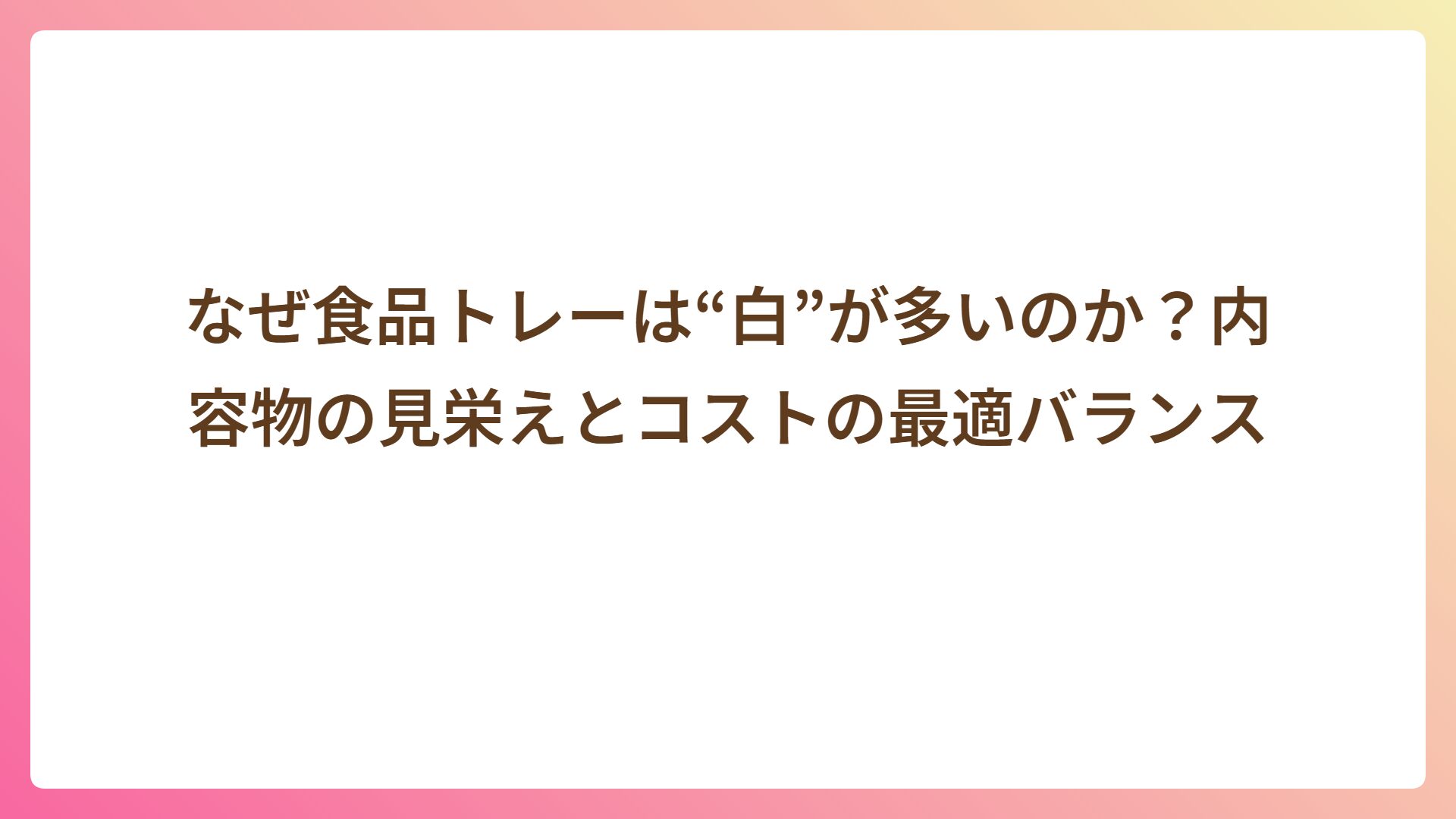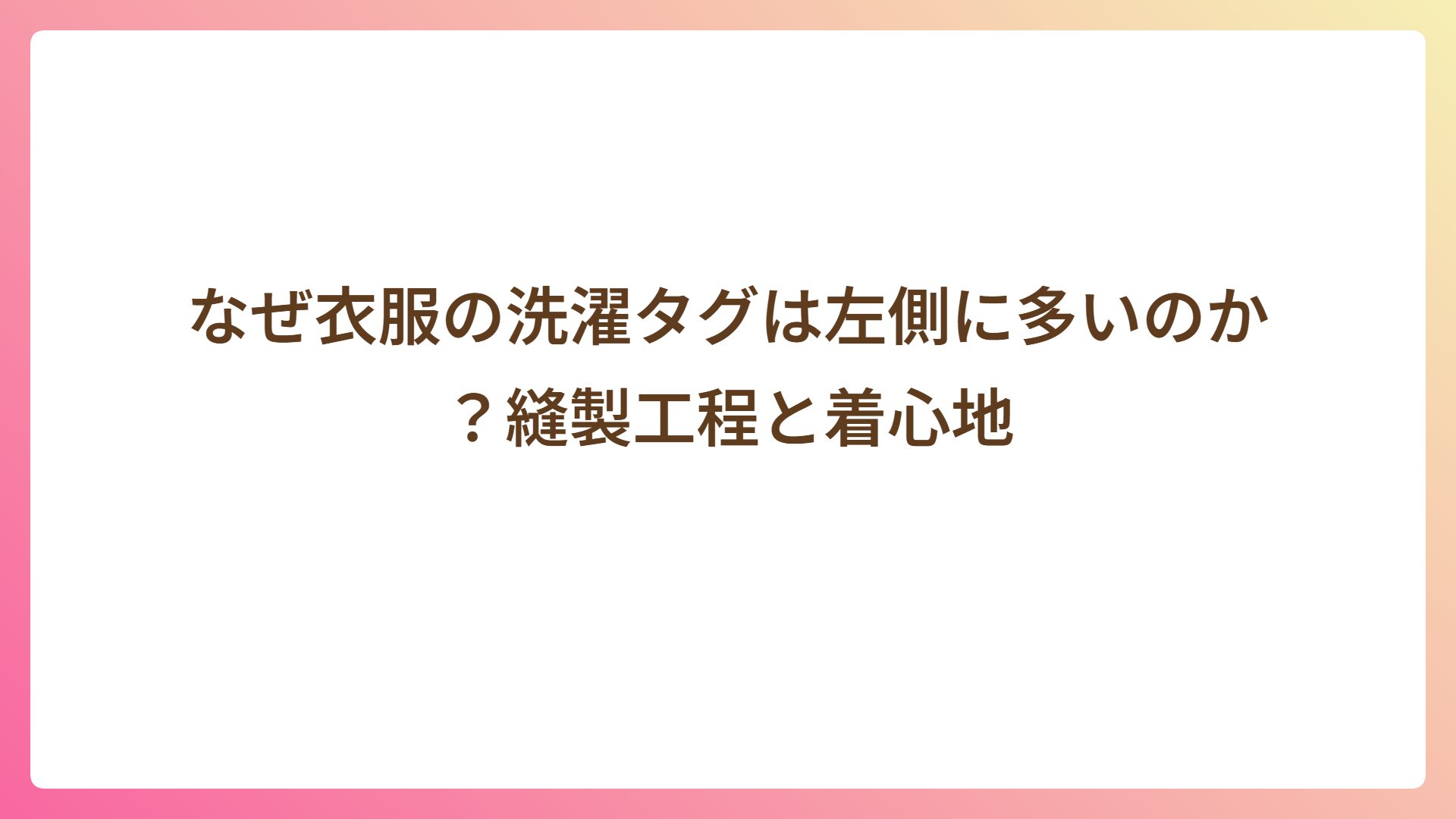なぜ駅ホームの端部は“ゴムボード”が増えたのか?滑りと段差緩和
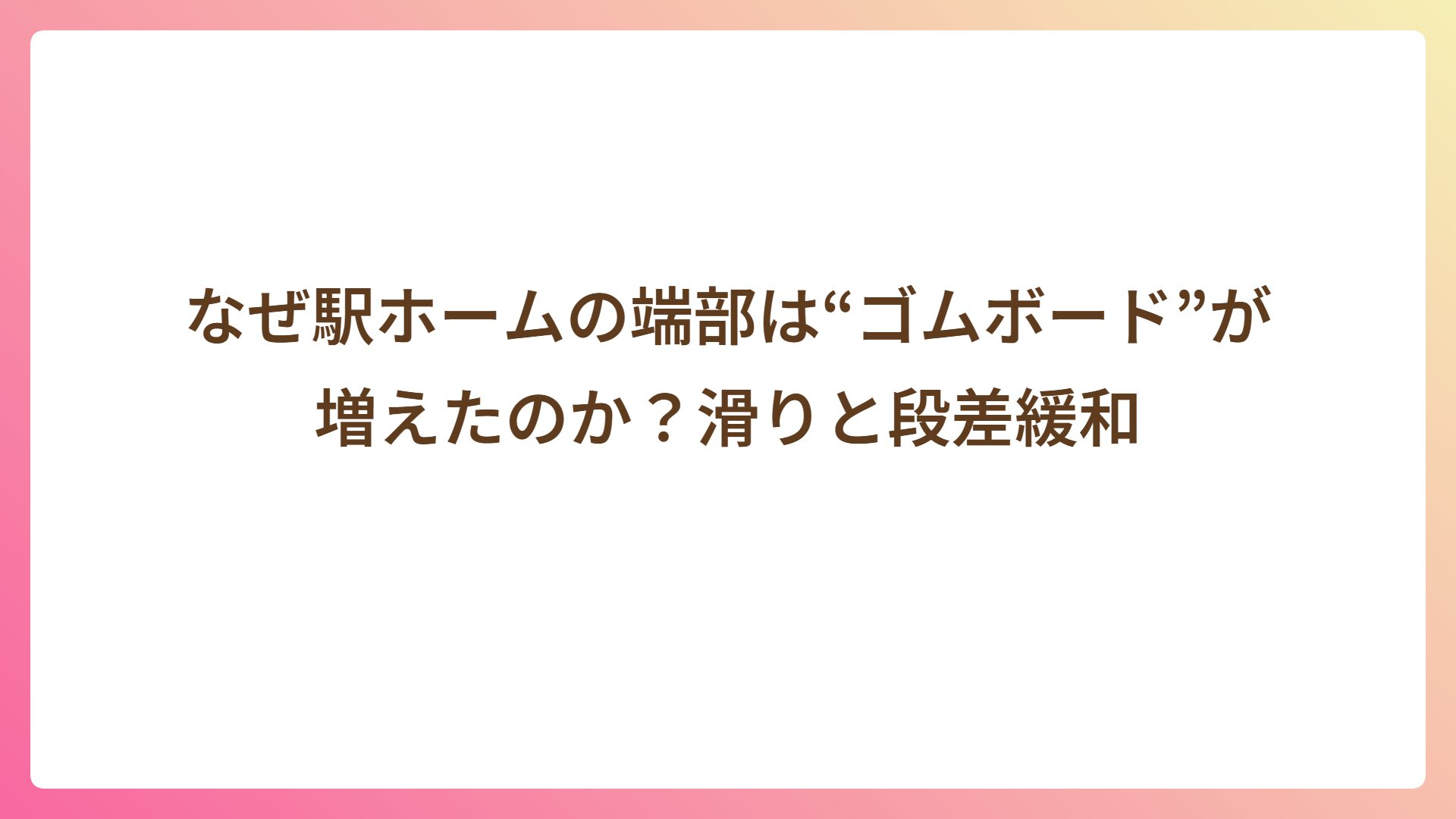
近年、駅のホームの端をよく見ると、コンクリートではなく黒っぽいゴム状の板が敷かれている場所が増えています。
一見、滑りやすそうにも見えますが、実はこれは安全性を高めるための最新素材。
ホームの端部にゴムボードが採用されているのは、滑り防止・段差緩和・メンテナンス性をすべて両立するための設計なのです。
ゴムボードとは?
ホーム端部のゴムボードは、正式には「合成ゴム系ホームエッジボード」と呼ばれる部材です。
主にEPDM(エチレンプロピレンゴム)や再生ゴム+樹脂複合材でできており、
弾力と耐候性に優れ、雨や紫外線にさらされても劣化しにくいのが特徴です。
これまでホームの端はコンクリート製ブロックが一般的でしたが、
最近では安全性の向上や施工性の改善を目的に、ゴム系素材への置き換えが進んでいます。
滑りを防ぐための“摩擦設計”
見た目はツルツルしていても、実際には表面に細かな凹凸パターン(ノンスリップ加工)が施されています。
ゴムは水を弾きやすく、さらに凹凸が水膜を分散させるため、雨天時でも滑りにくい摩擦特性を保ちます。
また、通勤ラッシュなどで多くの人が足を踏み出すエリアでも、靴底とのグリップ力を一定に保てるよう設計されています。
特に、白杖や車いすなどの接触時にも滑りを防ぐため、JIS規格では滑り抵抗係数(C.S.R.)の基準値が定められ、
ゴムボードはこれを十分に満たすように作られています。
段差を緩和し、つまずきを防ぐ
コンクリート製のホームブロックでは、端部と線路側との間に数センチの段差が生じやすく、
足先が引っかかって転倒する危険がありました。
ゴムボードは弾性を活かしてホームと線路側の継ぎ目を緩やかに傾斜させ、
乗客が誤って踏み出した際の衝撃を吸収します。
また、車いすやベビーカーの進入時にもスムーズに通過できるよう、
縁の形状が丸みを帯びた設計になっていることが多いです。
設置とメンテナンスが容易
従来のコンクリートブロックは重く、交換にはクレーンなどの大型機械が必要でした。
一方、ゴムボードは軽量で、人力でも施工・交換が可能。
経年劣化しても部分的に取り替えられるため、メンテナンスコストを大幅に削減できます。
さらに、裏面には空気層を設けたハニカム構造を採用することで、
軽量化と衝撃吸収の両立を実現しています。
安全基準とバリアフリー化への対応
国土交通省が定める「鉄道駅バリアフリー化ガイドライン」では、
視覚障害者誘導ブロックやホームドアとの干渉を避けながら、
転落防止と歩行安全を高めるホーム端部構造の導入が推奨されています。
その流れの中で、ゴムボードは視覚障害者誘導ブロックとの一体施工が可能であり、
新設・改修どちらの駅でも柔軟に導入できる素材として採用が広がっています。
環境面でもメリットがある
最近では、使用済みタイヤや工場端材を再利用したリサイクルゴムボードも増えています。
廃棄物を減らしつつ安全性を高められるため、環境配慮型インフラ材としても注目されています。
まとめ
駅ホームの端部にゴムボードが使われるのは、
滑り防止・段差緩和・施工性・環境性能をすべて満たすためです。
コンクリートに代わる新素材として、
利用者の安全と快適さを支える“黒い縁の一枚”には、人と交通の接点を守る設計思想が込められているのです。