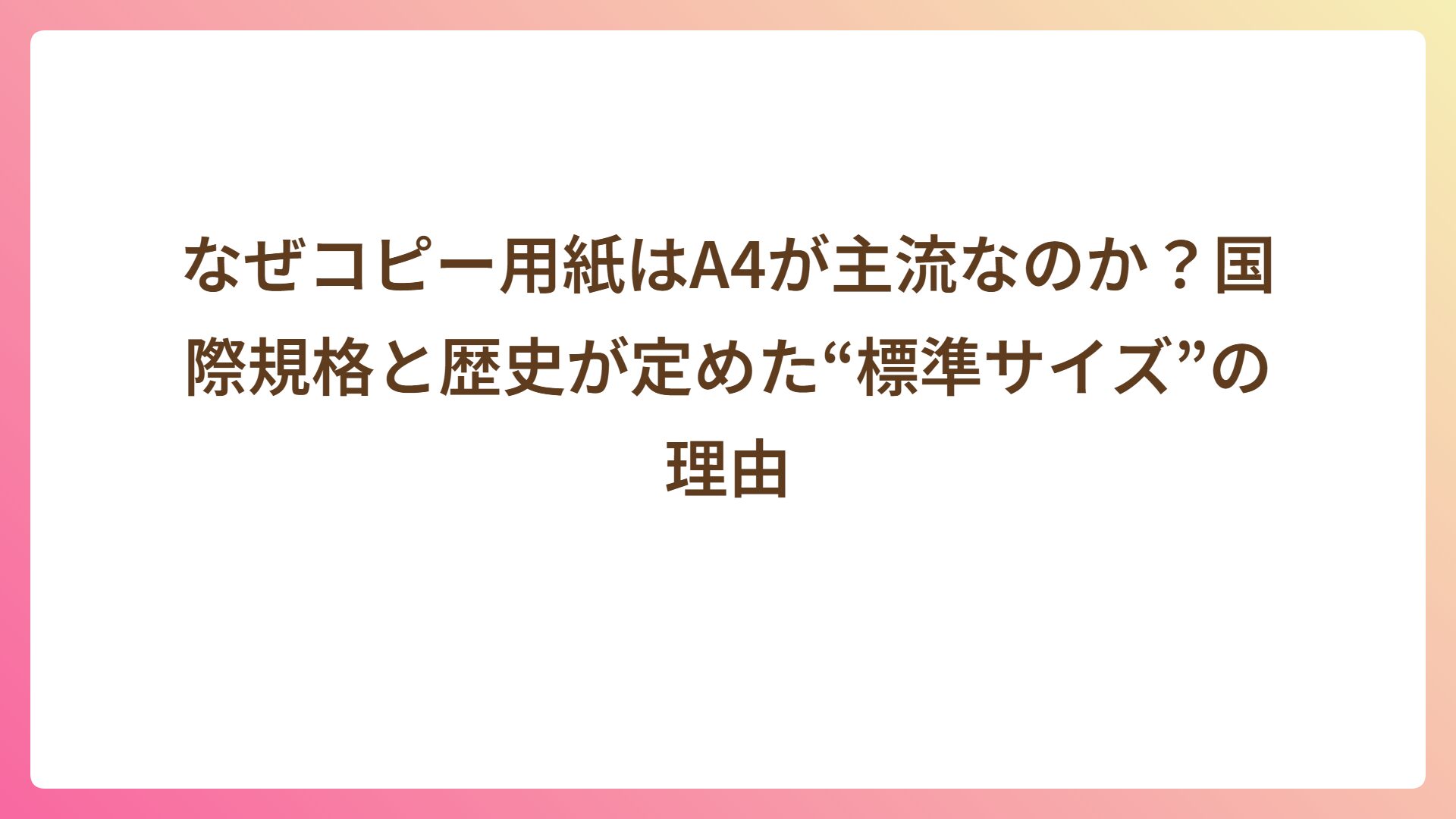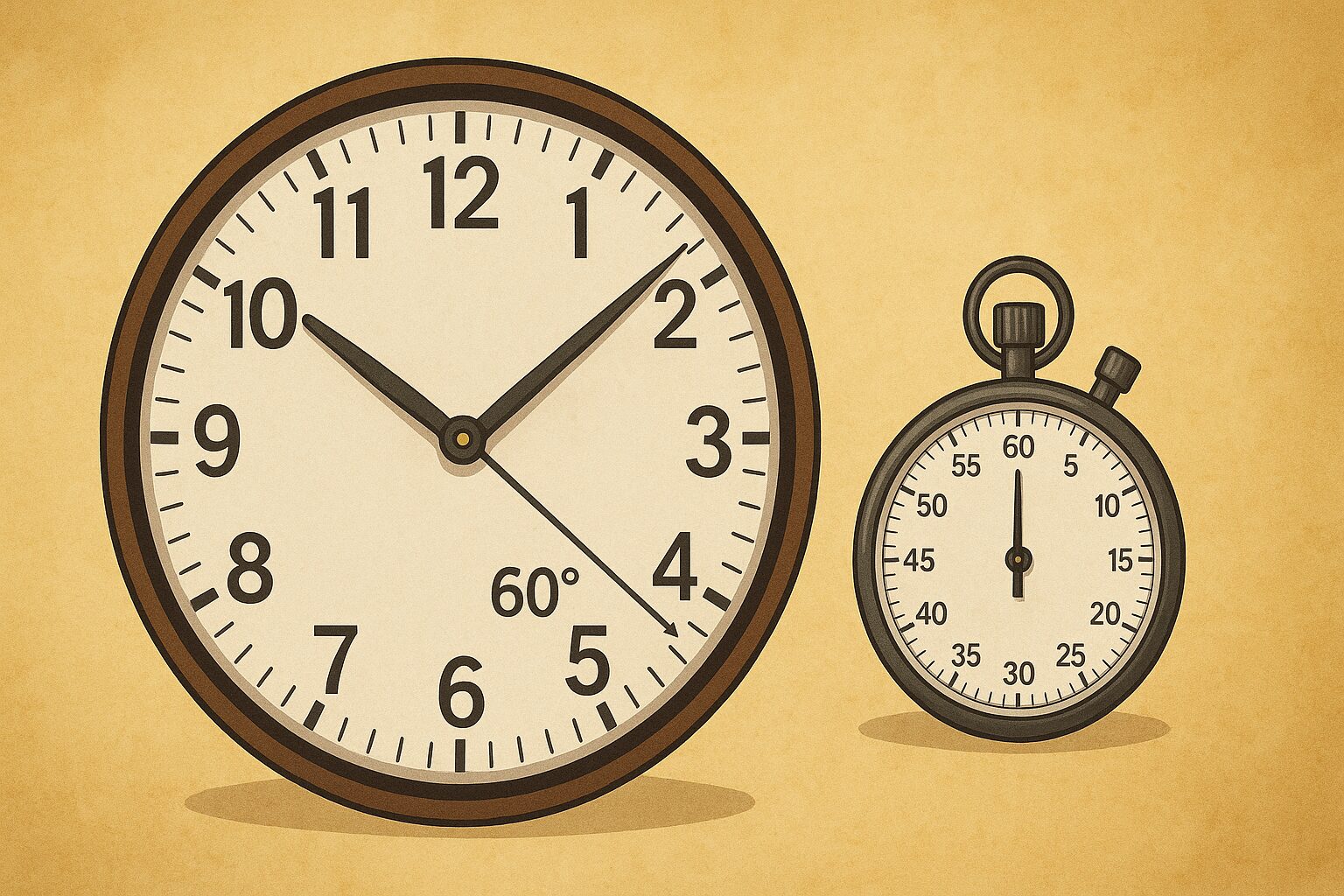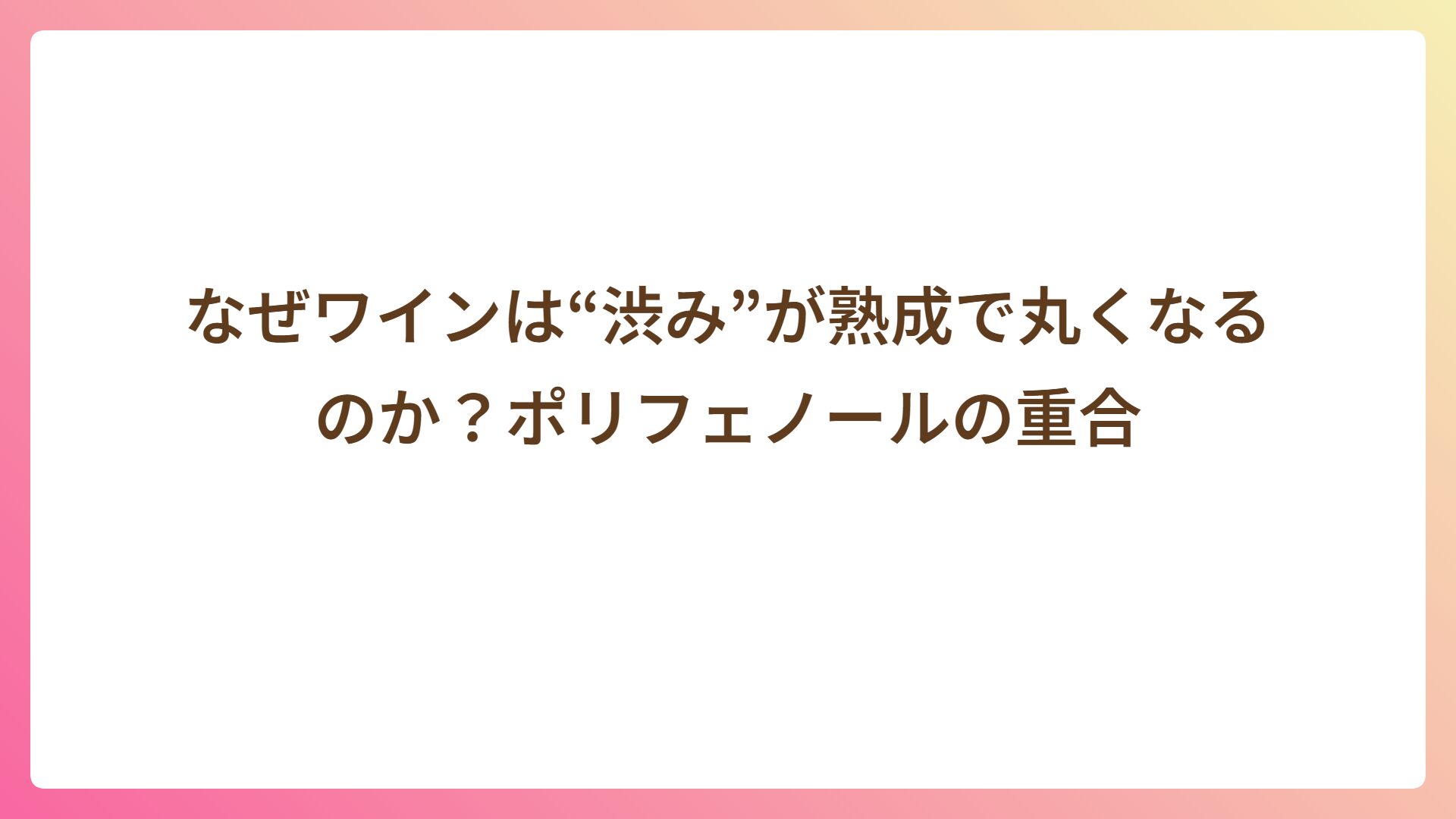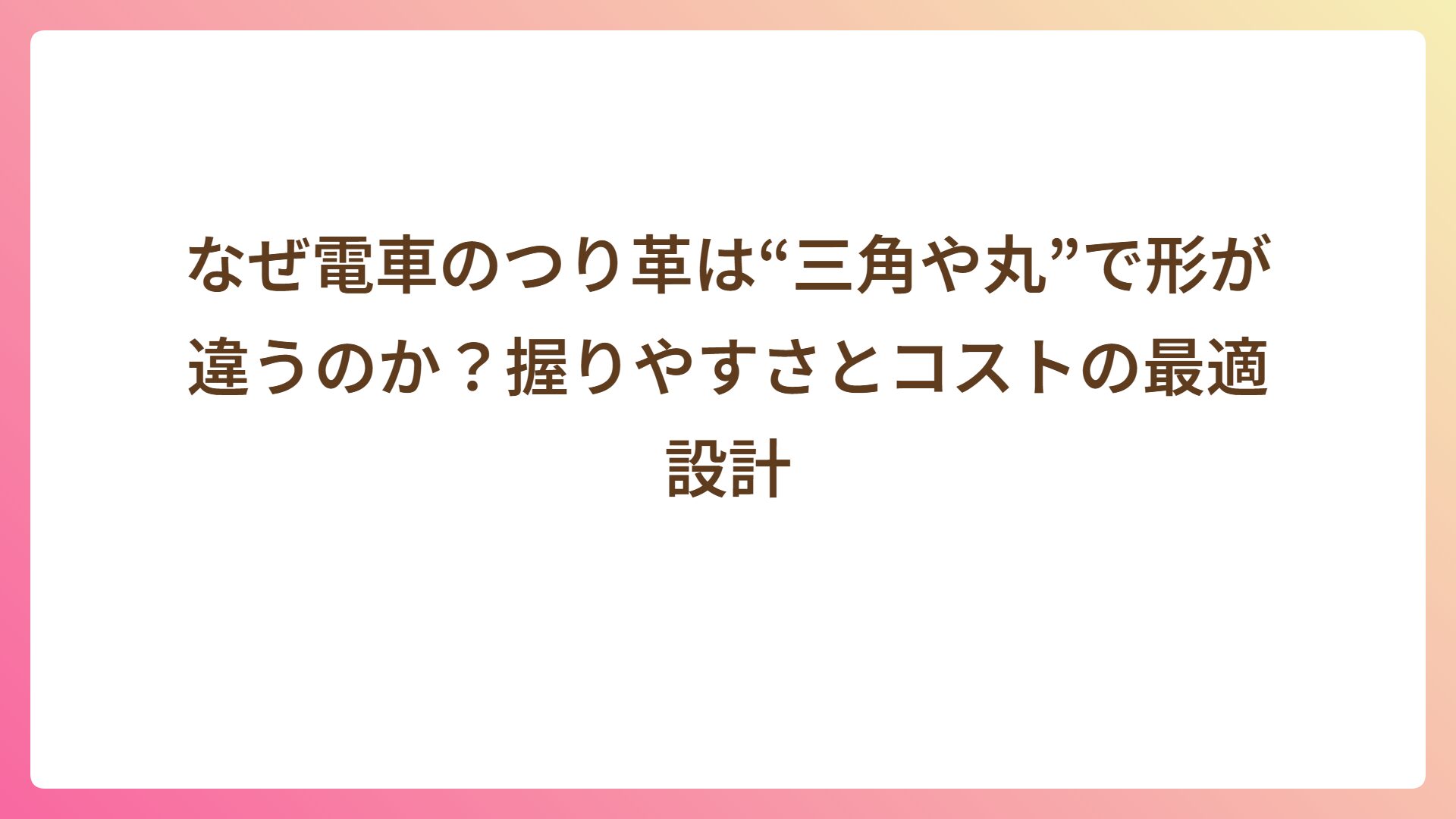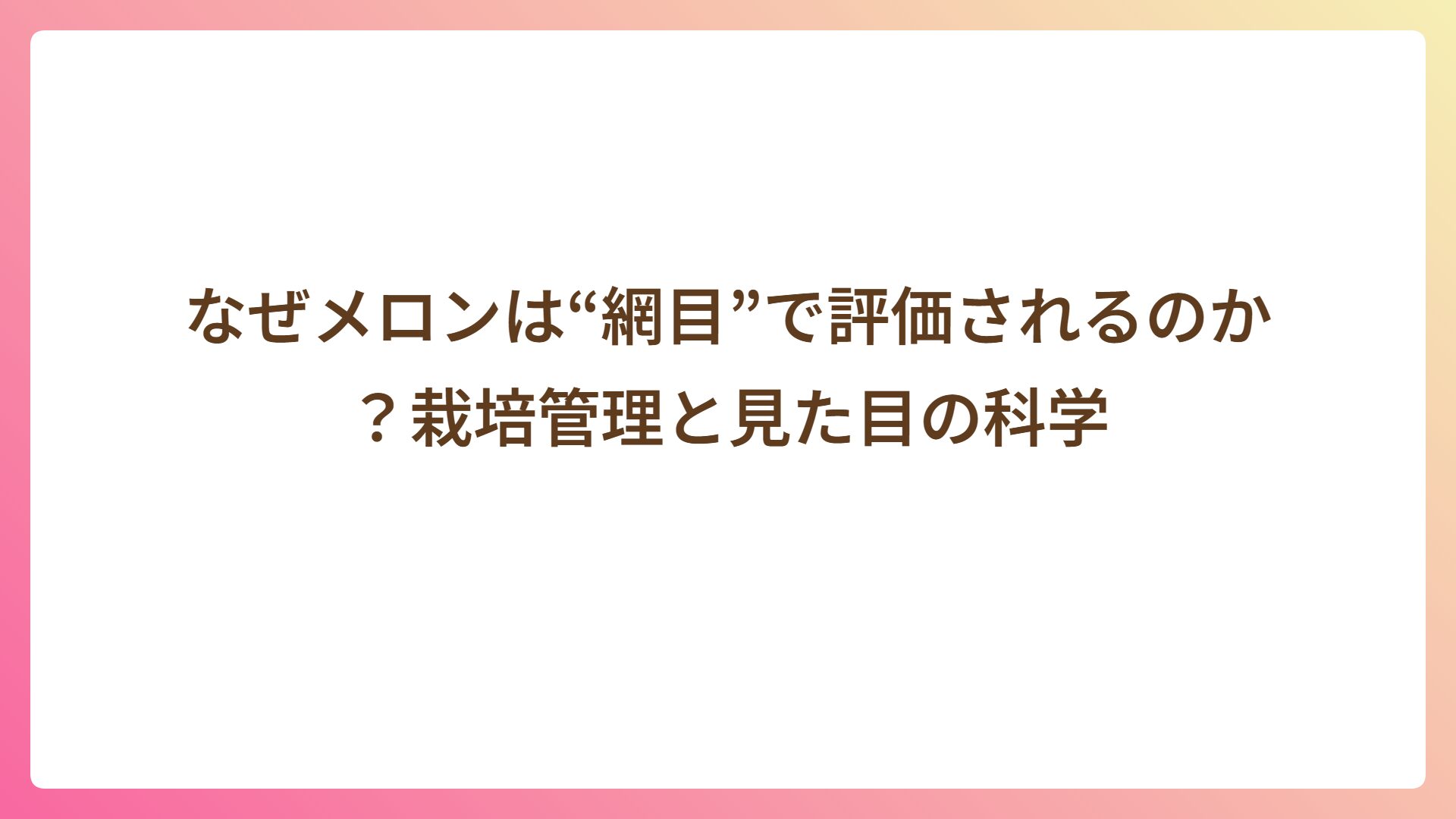なぜエレベーターに鏡が付いているのか?安全性・混雑緩和・ユニバーサルデザインの理由
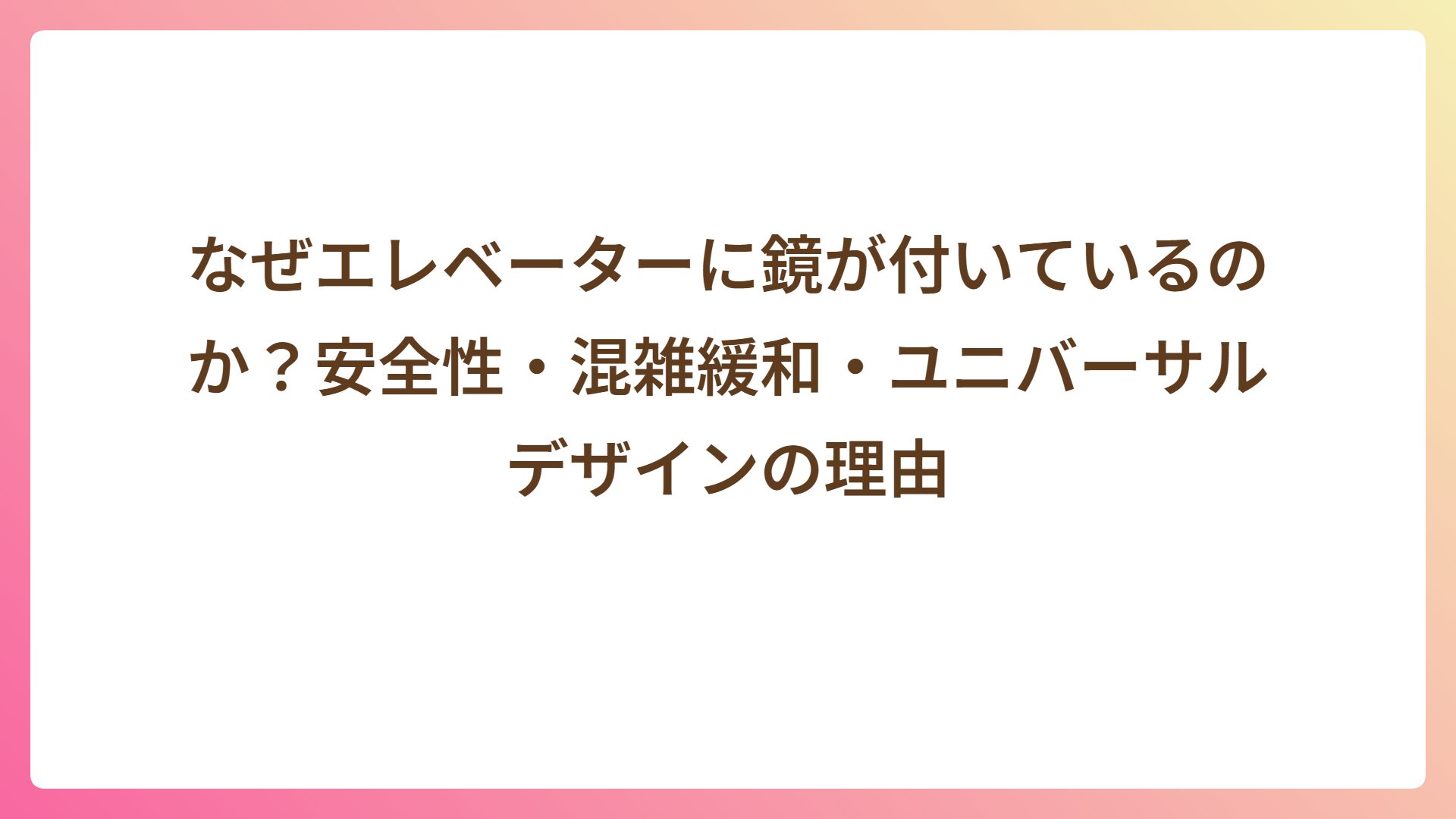
商業施設やオフィスビルのエレベーターに乗ると、後方の壁や側面に鏡が設置されていることに気づきます。
見た目を広く見せるためだけでなく、実はそこには安全・快適・誰でも使いやすい空間を実現するための工夫が隠されています。
この記事では、エレベーターに鏡が付いている理由を、3つの観点(安全・混雑・ユニバーサル設計)から解説します。
理由①:後方確認による“安全性の確保”
エレベーターの鏡はまず、安全確認のために設けられています。
特に大型施設では、後ろを向かずに降り口の状況を確認できるようにすることが目的です。
- 後方に人がいないか
- 扉が開いた瞬間に衝突しないか
- 荷物やベビーカーの位置を把握できるか
など、鏡によって視界が広がることで事故防止につながります。
車いす利用者の場合も、後ろを振り向かずに出口方向を確認して安全に後退できるため、
鏡は「後方視界補助装置」としての役割を果たしているのです。
理由②:車いす利用者への“ユニバーサルデザイン”
エレベーターの鏡が一般化した最大の理由は、
車いす利用者が後ろ向きで降りられるようにするためです。
エレベーターの構造上、狭い空間で車いすを方向転換するのは難しく、
出入口と反対側に鏡を設置することで、
- 後方を見ながら安全にバックできる
- 扉の開閉を確認しやすい
- 同乗者の位置も分かりやすい
といったユニバーサルデザイン上の配慮が可能になります。
この設置基準は、
日本工業規格(JIS A 4301「エレベーターの構造基準」)にも明記されており、
「車いす使用者が後方確認できる鏡の設置が望ましい」とされています。
理由③:空間を“広く見せる”心理的効果
鏡は空間を広く感じさせる心理的な効果もあります。
エレベーターのような密閉された空間では、狭さや圧迫感を感じやすくなりますが、
鏡によって視覚的な奥行きが生まれ、開放感・安心感を演出できます。
特に高層ビルや商業施設では、
「閉所恐怖を軽減する」「乗客の緊張を和らげる」目的で鏡が活用されているのです。
理由④:混雑時の“譲り合い・整列”を促す
鏡があることで、乗客は自分や他人の位置を確認しやすくなり、
自然と譲り合い・整列が促されます。
- 混雑時に奥へ詰めやすくなる
- 降りる人が先に出やすい位置を把握できる
- 他人との距離感を保ちやすい
といったスムーズな動線設計にもつながっています。
実際、駅や商業施設の改修で「鏡を増やすだけで混雑が軽減した」例も報告されています。
理由⑤:防犯・監視の補助にも役立つ
鏡は、防犯カメラと併用することで死角を減らす効果もあります。
狭いエレベーター内では、人の影になって映らない範囲ができやすいため、
鏡を設けて視界を補うことで、防犯映像の死角を補完します。
また、利用者自身も鏡越しに周囲を確認できるため、
不審者対策としての心理的な安心感にもつながっています。
鏡が設置されないタイプもある
ただし、すべてのエレベーターに鏡が付いているわけではありません。
たとえば、
- 超高層ビルの展望用(景観を重視)
- 狭小マンションや住宅用(スペース制限)
などでは、省略されることもあります。
一方で、公共施設・商業施設・病院などでは、
バリアフリー法の観点から鏡の設置が推奨されています。
まとめ:鏡は“見た目”ではなく“安心のための装置”
エレベーターに鏡が付いているのは、
- 後方確認による安全確保
- 車いす利用者への配慮(ユニバーサルデザイン)
- 圧迫感の軽減と心理的快適さ
- 混雑時の整列促進
- 防犯補助
という多面的な機能性の結果です。
つまり、鏡は“装飾”ではなく“安心と安全のための仕組み”。
私たちが何気なく見ているその鏡には、誰もが使いやすい社会を目指すデザイン思想が映し出されているのです。