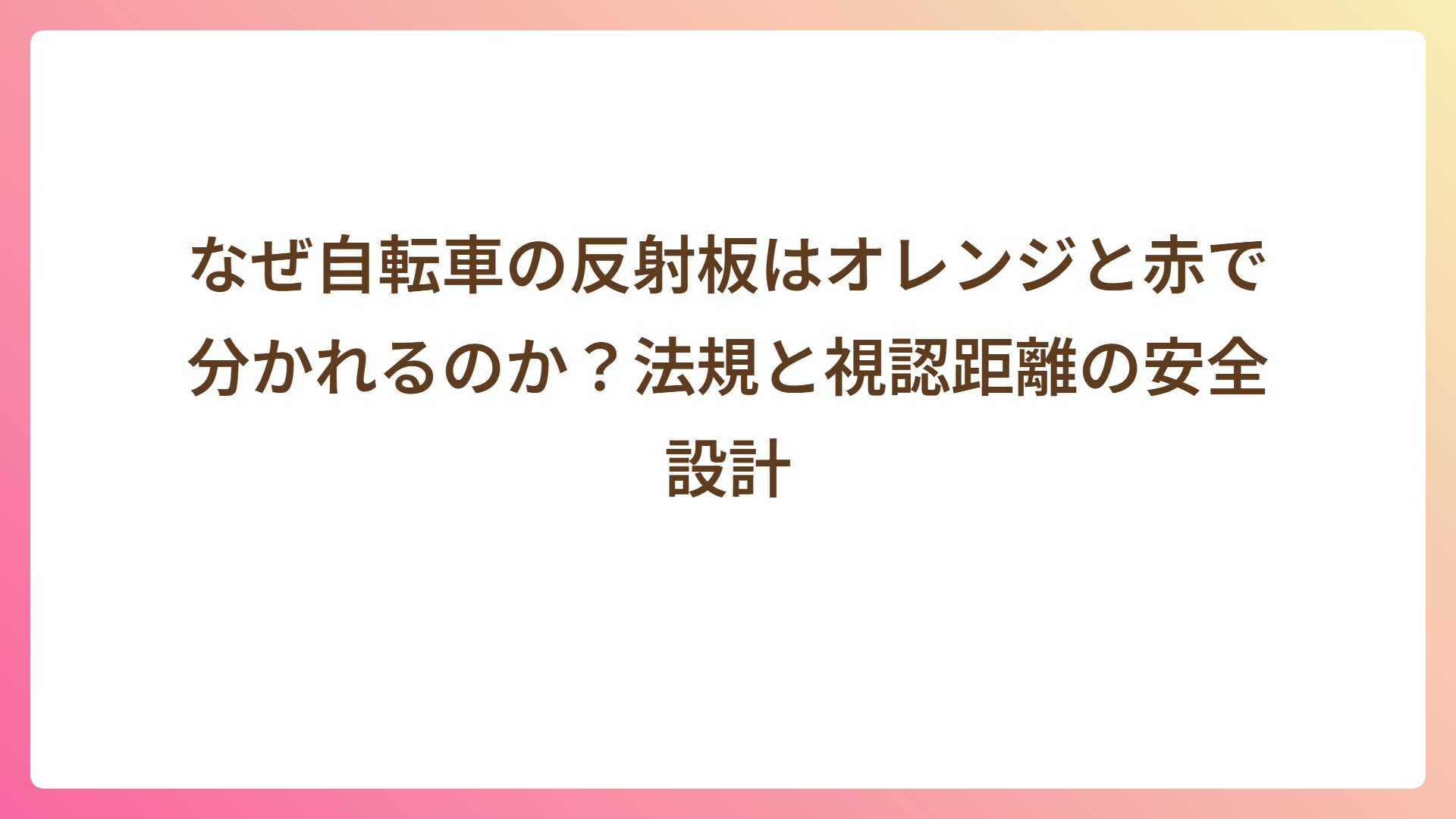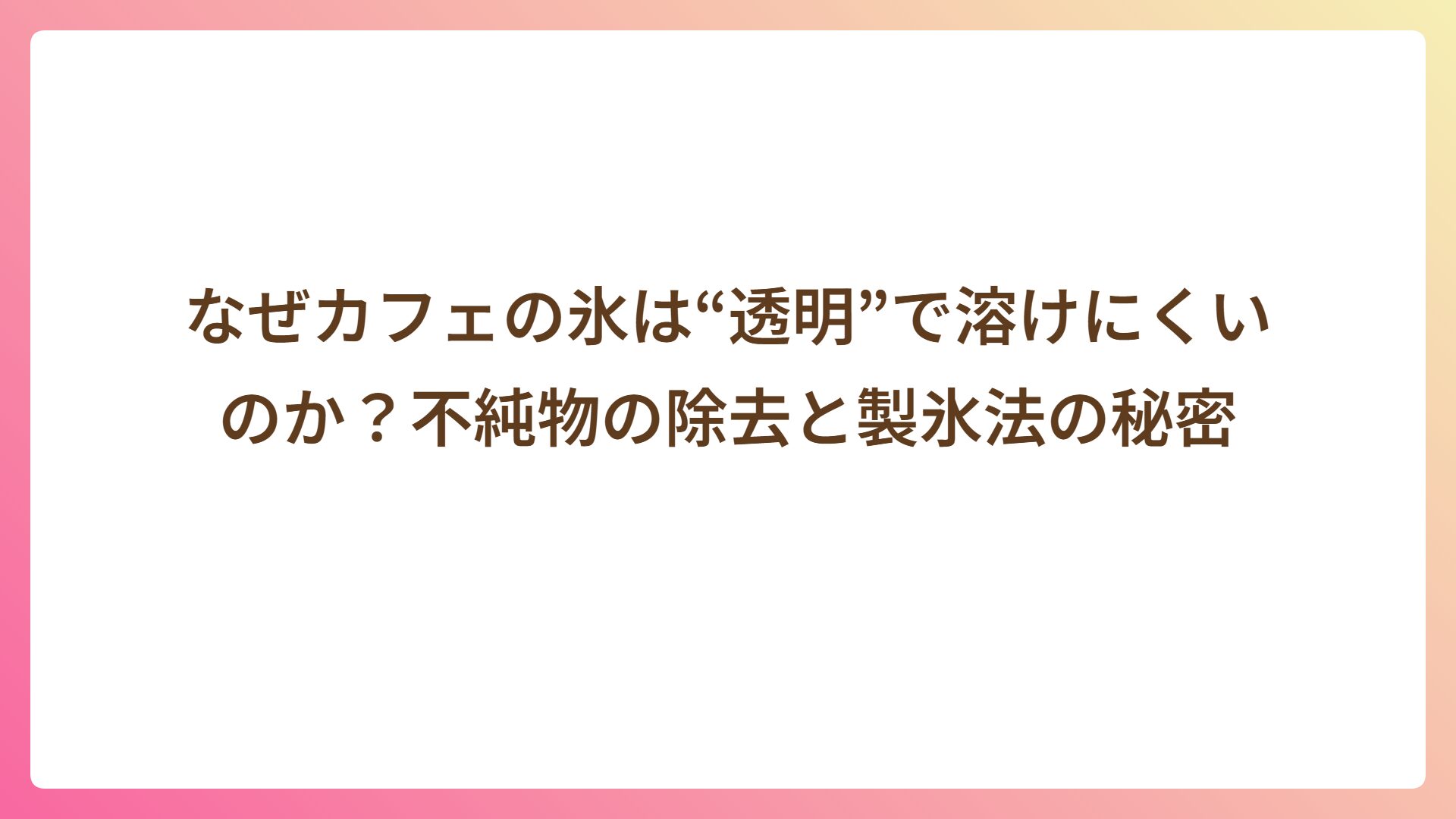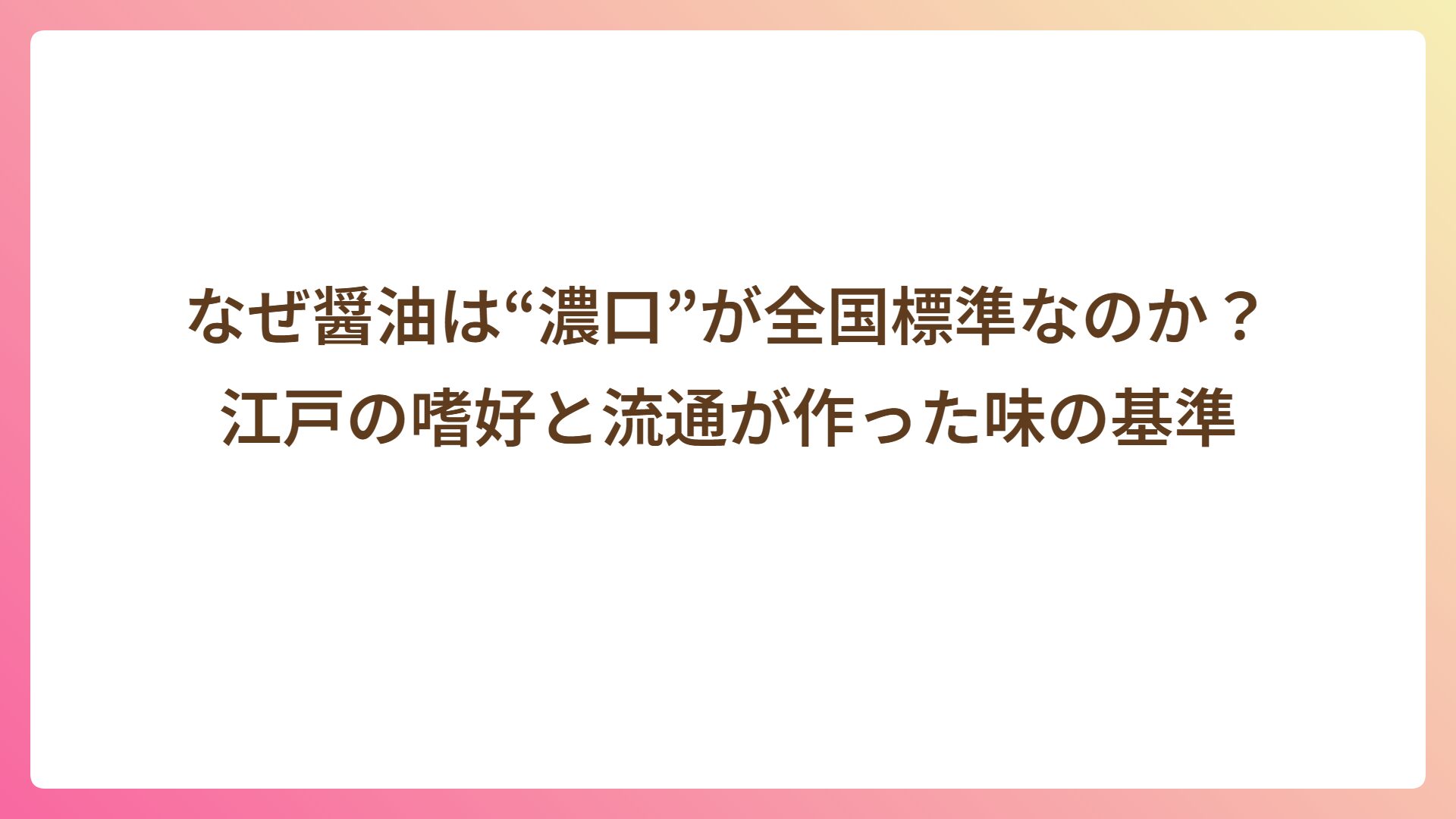なぜエレベーターの到着音は高い音なのか?騒音環境でのマスキング回避
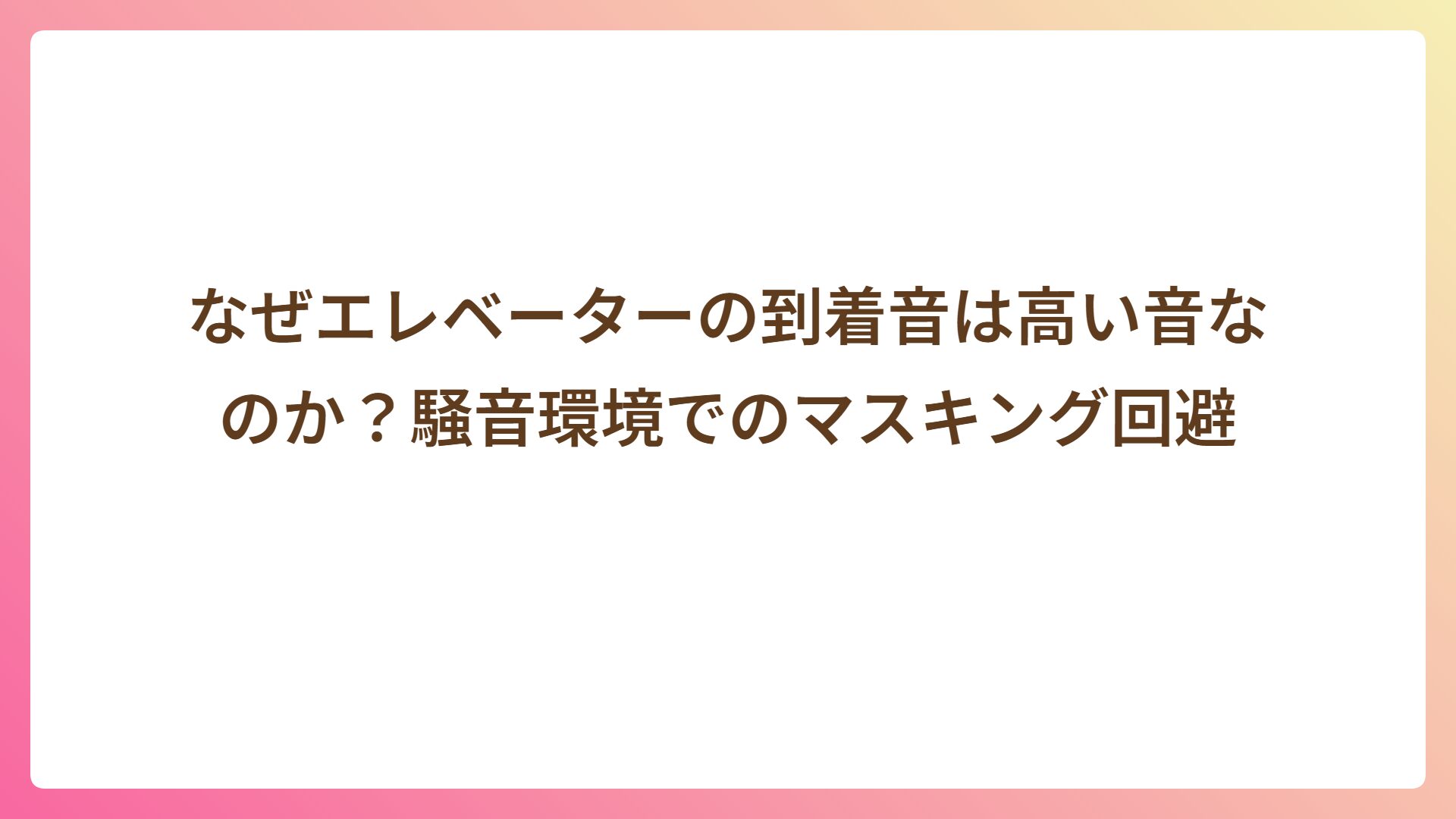
駅やオフィスビルなどで、「ピン」「ポーン」というエレベーターの到着音を耳にすることがあります。
なぜこの音は低音ではなく、やや高めのトーンで設定されているのでしょうか?
それは、日常環境にあふれる騒音の中でも確実に聞き取れる“聴覚設計”が関係しているのです。
高音は“騒音マスキング”を受けにくい
人の耳が最も敏感に反応する周波数は約2,000〜4,000Hz付近です。
この帯域は、人の声の母音成分や子音のピークと重なるため、
私たちは本能的にその音域の変化を素早く察知できます。
一方で、駅や商業施設の環境音は、
人の話し声・空調音・足音・電車の走行音など、
中低音域(200〜1,500Hz)に集中しています。
そのため、エレベーターの到着音を高音側(2,000Hz以上)に設計すると、
周囲のノイズにマスク(覆い隠され)されにくく、
遠くからでも明瞭に聞き分けられるのです。
聴覚の“方向感”を利用した設計
高い音は波長が短く、反射や回折が少ないため、
音源の方向を正確に把握しやすいという特徴があります。
これにより、人は「どのエレベーターが来たか」を直感的に判断できます。
複数台のエレベーターが並ぶビルでは、
高音の短いチャイムによって特定の位置から発せられる音を明確に感じ取れるため、
視覚的に探す時間を短縮できるのです。
“高音=明るい印象”という心理的効果
音の高さは、人の感情にも影響を与えます。
一般的に、低音は重厚・威圧的な印象を与え、
高音は軽快・明るく・親しみやすい印象を生みます。
エレベーターの「ポーン」という高めのチャイムは、
単なる注意喚起ではなく、乗客に安心感を与える目的も持っています。
特に商業施設やホテルでは、明るく清潔な空間演出の一部としても設計されているのです。
バリアフリー対応としての“周波数分離”
視覚障がい者にとって、エレベーターの到着音は重要な情報源です。
高音のチャイムは、周囲の低音域ノイズ(エスカレーターや空調)から
明確に分離できる聴覚サインとして機能します。
さらに、上行・下行を区別するために、
- 上行:高い音(例:ピン)
- 下行:低い音(例:ポン)
という周波数差による方向認知も取り入れられています。
これはJIS(日本産業規格)やISOのバリアフリー設計にも準拠しています。
音量ではなく“周波数”で聞かせる
単に音を大きくすれば聞こえるわけではありません。
騒音の多い場所で大音量を出すと、
周囲に不快感を与えたり、残響で聞き取りにくくなることがあります。
そのため、エレベーターの到着音は、
必要最小限の音量でも確実に届くように“音色設計”がされています。
つまり、「聞こえる音」ではなく「通る音」として設計されているのです。
施設ごとに最適化された音設計
近年のビルでは、施設の用途に合わせて到着音のトーンを調整しています。
- 病院や図書館:控えめな高音(静音設計)
- 駅や空港:やや鋭い高音(騒音環境対応)
- ホテルやオフィス:柔らかい電子チャイム音
このように、環境ごとの音響マスキング特性を分析したうえで、
最も聞き取りやすく、かつ不快にならない心理音響設計が行われているのです。
まとめ
エレベーターの到着音が高いのは、
騒音に埋もれにくく、方向がわかりやすく、心理的にも安心できる音だからです。
人の聴覚が最も敏感な周波数帯を狙い、
音量ではなく“音質”で注意を引く――。
このわずか一音に、バリアフリー・心理音響・環境設計のすべてが詰まっているのです。